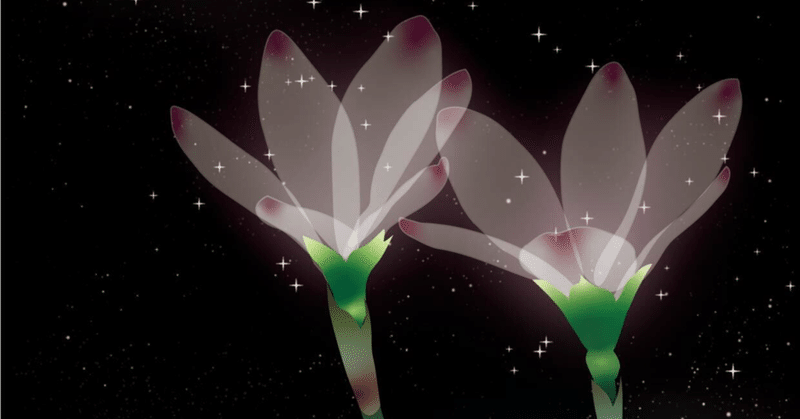
連載SF小説『少年トマと氷の惑星』Ⅸ.再生(最終話)
Ⅸ.再生
まだトマが暖炉の側ですやすやと眠っている中、旅立つカイムを見送るためにティエラは小屋の外に出てきた。
「お前さんの魂は、連れてかなくていいんだな?」
「ええ。可愛いトマがいるもの。命が尽きるまで、あの子といるわ」
ティエラは、カイムに向かってにっこりと微笑んだ。
「そうかい。俺がここからいなくなれば、トマの『鍵』も外れて、すぐに大人になるだろう。きっと、これからも延々とお前さんに質問するだろうから、色々教えてやってくれ」
「ふふ、そうね。楽しみだわ。でも、本当にトマにお別れを言わなくていいの? 目が覚めたら、あの子、きっと寂しがるわ」
「いいさ。大人になれば、俺のことなんてすぐに忘れちまうよ」
カイムは大きな両翼を広げると、氷の大地を蹴って飛び立った。
カイムが翼を何度か羽ばたかせると、その姿はすぐに小さくなって、夜空に溶けて消えてしまう。
ティエラは、カイムが消えた方向へいつまでも手を振っていた。
*
その日、何百年もの間眠っていた太陽に、黒いカラスが帰ってきたのを見た男がいた。
「黒い鳥が太陽に帰ってきた! 太陽が赤々と燃えだしたぞ!」
男は、そう叫び、周りの人に走り伝えたという。
太陽は轟々と燃え盛り、煌々とした光を取り戻した。
その光は、あの惑星の闇夜を一気に振り払い、今、澄み切った青空に燦然と輝いている。
トマが目を覚ますと、窓から差し込む強烈な白い光に目が眩み、思わずカイムの名前を呼んだ。
しかし、トマの元に駆けて来たのは、頬を紅潮させたティエラであった。
「トマ! 朝よ! 朝が帰って来たんだわ!」
ティエラに手を引かれ、目を細めたまま小屋の外に出ると、トマは身体中に暖かい光を感じた。暖炉で燃える炎とは違う、柔らかくじんわりと肌に染み渡る光だ。
だんだんと明るい光に慣れ、少しずつ目を開けてみると、今までの星降る漆黒の夜空はすっかり消え失せ、どこまでも高く突き抜ける爽快な青空が広がっている。
「明るくって、眩しいよ! 空がどこまでも青いよ! これが……、これが朝なんだね!」
トマは、思い切り腕を伸ばして、輝く空を仰ぎ見た。
太陽の光を浴びた瞬間から、トマの身体は成長の準備を始めている。
止まっていたトマの背を、体重を、筋肉を、どこまで伸ばしてやろうかと細胞たちが意気込んでいるようだ。
心臓は大きく鼓動を打ち、手や足の末端まで血液を行き渡らせると、トマの毛髪や爪をほんの少しだけ伸ばして、古くなった細胞を頭皮や肌にうっすらと蓄積させた。
「ティエラ、ティエラ! あの歌を歌って! 太陽の下でこの惑星に聴かせてあげて!」
トマにせがまれたティエラは、青空の下で伸び伸びと美声を響かせる。
シュウの残した歌は、懺悔の歌であり、植物たちの再生を願う歌であるが、ティエラは、どこか遠くにいると信じるシュウの無事と、これから大人になっていくトマが健やかに育っていけることを心から願い、祈りを歌に込めた。
やがて、数百年の間、氷で覆われていた沈黙の惑星が、海の青さと緑の溢れる美しい姿を取り戻していく様子を、太陽からもはっきりと確認することができた。
その後、二度と太陽からカラスが飛び立つことはなく、あの惑星が朝を忘れることもなくなったという──。
美しい青き惑星は、夜になれば数多の星が降り注ぎ、朝になれば山脈の陰から眩しい太陽が顔を出す。
トマは毎日、朝日と共に目を覚ますと、広大な緑の大地を進み、新しい発見を探しに出かけた。
森で初めて見る植物を見つけると、ティエラに字を教えてもらいながら、紙に植物の絵と手紙を書く。
『きょう はじめての だいはっけんだよ。 あさがきて73にちめ。 とま』
いつかカイムと祖父に読んでもらえる日を信じ、トマは今日も命を燃やしている。
(了)
🌟
最後までご覧いただきまして、ありがとうございます☺️
ゆうなってさんのリクエストから生まれた物語、「少年トマと氷の惑星」を楽しんでいただけたでしょうか。
全ての謎はまだ明らかになっていませんが、シュウや不老不死のキーとなる『鍵』のお話しは、また別の機会に。
心がざわめく出来事の多いこの頃ですが、想像やワクワクはきっと心を燃やしてくれます。
これからも、(超マイペースではありますが)創作を楽しんでいきたいです🍀
《Special Thanks🌼》
リクエスト:ゆうなってさん
ヘッダーイラスト:Tamaそらイメージさん
🌟第一話は、こちらから↓
いつも応援ありがとうございます🌸 いただいたサポートは、今後の活動に役立てていきます。 現在の目標は、「小説を冊子にしてネット上で小説を読む機会の少ない方々に知ってもらう機会を作る!」ということです。 ☆アイコンイラストは、秋月林檎さんの作品です。
