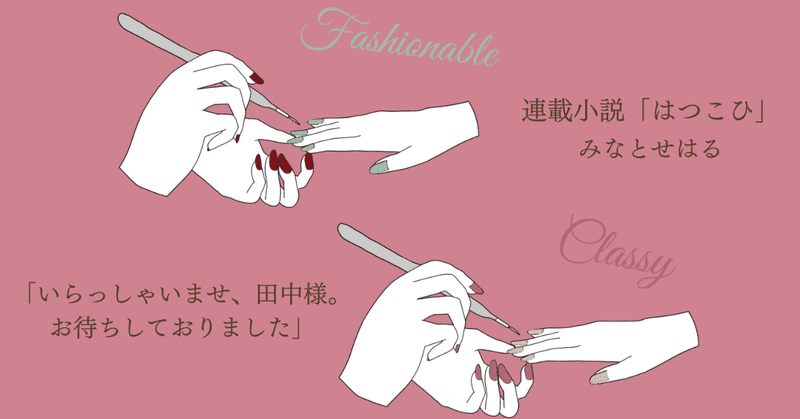
【連載小説】はつこひ 十六話
店の扉が開き、「チリン、チリン」とベルが鳴る。
「いらっしゃいませ」
「蝶子さん、こんにちは。カイヤの右腕のメンテナンスはもう済んでいるかしら」
あれから三日が経ち、田中様とカイヤさんが一緒に店にやって来た。
「田中様、お待ちしておりました。ちょうど昨日、トリートメントを終えたところなのですよ。さあ、カイヤさん。どうぞこちらの椅子にお掛けになってくださいね」
「その前に見て。これ、いいでしょう」
カイヤさんはカウンターの中にいた私の目の前まで来ると、コートを脱いでから新しい黄色のノースリーブワンピースを見せてくれた。一つ歳を重ねた彼女がターンをすると、ひらひらとした裾がなだらかな円を描く。
「とても素敵ですね。カイヤさんによくお似合いです」
「ありがとう。お気に入りなの」
そう言いながらカイヤさんが椅子に座ると、ガラステーブルの上に置いた右手は中指と薬指を同時に跳ねさせていた。その姿を後ろの待合室から見守る田中様も、目を三日月の形にして微笑まれている。
「カイヤさん、初めてのマニキュアはいかがでしたか。途中で色が落ちてしまったり、どこかが欠けてしまったりしませんでしたか?」
「大丈夫よ。昨日ね、お友達に青色のネイルを見せたらとても羨ましがっていたの。今度はお友達を連れてきてもいい?」
「もちろんですわ。カイヤさんのお友達でしたら大歓迎です。そうそう、お手入れした方の腕の爪もぜひ見てくださいね。今お持ちします」
一度カウンターの奥に戻ると、戸棚の中からトリートメント・メンテナンスを終えたばかりのカイヤさんの右腕を取り出す。カイヤさんの肌に指跡を残さぬよう、三巾ほどある生絹の生地で丁寧に包み、できる限り優しく二本の腕で支えながら運んだ。
「お待たせいたしました。こちらがお預かりしていたカイヤさんの右腕です」
カウンターに戻ると、ガラステーブルの上で生地を広げる。数種の天然ハーブを調合した特製オイルで手入れをした肌は、以前よりも艶気を増して新品の合成タンパク質の肌にも負けない滑らかさだ。指先に施した青色のグラデーションもますます輝いて、カイヤさんは「わあ」と感嘆の声をあげた。
「お気に召していただけましたか?」
「もちろんよ! 早くその腕に交換したいわ!」
カイヤさんが装着していたレプリカの腕を自分で外し始めたので、オリジナルの腕を布に乗せたまま持ち上げて彼女に差し出す。カイヤさんは新しい腕を胴体に垂直にセットすると、「カチッ」と音をさせて一度でうまくはめ込んだ。少し経つと、それまで白みを帯びていた右腕が温度を持ち始め、ほんのりとピンク色に染まっていく。
「いかがですか?」
「うん。うん! すっごくいい感じ。ありがとう、蝶子さん」
カイヤさんは私の手を取ると、田中様にそっくりな笑みを浮かべて礼を言った。
「カイヤさんの手は、とても温かいですね。それに、生まれたての赤ちゃんみたいにふわふわした肌です」
彼女の小さな右手をそっと包み込むと、そのまま引き留めてしまいたくなる。けれど、それはいけない。飯村さんのために借りる右腕は、一人一度までと決めている。
「私の手は温かくて、赤ちゃんみたいに柔らかいのね。そんなこと言ってもらったの、初めて」
カイヤさんはそう呟くと、自分の手をまじまじと見つめた。
「初めてなのですか?」
「だって、そういうの、分からないもの」
「……この間いらした時、カイヤさんは私の手が以前よりもカサカサしているとおっしゃいました。温度や柔らかさも、それに似た感覚ではありませんか?」
「瞳を通して見れば、温度も湿度も『数値』ですぐに分かるわ。ちょうどこの間、水分量が少ない時には『カサカサ』という言葉を使うと学校で習ったところだったの。でも、温かいとか冷たいとか、柔らかいとか硬いとか、そういうのは知らないわ」
「そういうのは知らないわ」
カイヤさんの言葉が頭の中で反芻する──。
『君の手は柔らかいんだねえ。それに、温かい』
彼と初めて会ったあの雨の日、確かにそう聞いた。
『蝶子ちゃんは柔らかくて、温かい。『愛してる』って、こういうことをいうんだね』
あの年のクリスマス・イブ、確かに彼はそう言った。
田中様もカイヤさんも最新型のアンドロイドだ。五十音順につけられる身体名前は、「あ行」に近いほど旧型で、飯村さんが彼女たちに分からないものを感じられるはずがない。
それなのに、なぜ飯村さんにはそれが分かったのだろう。
「蝶子さん。蝶子さん、大丈夫? 顔色が悪いわよ」
はっと気がつくと、田中様がカウンターまでやって来て、心配そうな顔をこちらに向けていた。
私の前に座っているカイヤさんは、目を見開いたままでいると思えば、急にまばたきを繰り返し、口角を上げたかと思えば、次の瞬間には頬を膨らませ、忙しなく表情を変化させている。こんな時にどんな表情をするのが正解なのか、主記憶装置にアクセスをして懸命に探しているのだ。
ああ、こんなに小さな女の子を戸惑わせてしまうなんて。彼女の知らなくて良いことまで、人間の私が教える必要はないというのに。
「田中様、カイヤさん、ご心配をお掛けして申し訳ありません。人間というのは時々、感傷というものに浸ってしまっていけませんね。でも、もう大丈夫ですわ」
笑みを作って答えると、二人はやっと目を細めて口角を上げた。
「それじゃあ、蝶子さん。丁寧なお仕事をしてくれて、ありがとう。また私のネイルもお願いしにくるわね」
「蝶子さん、ありがとう。さようなら」
田中様とカイヤさんを店の外まで見送ると、クリスマス・イルミネーションに彩られた商店街の一本道がきらきらと輝いている。
目を閉じれば、遠くの方で電車が走る音が聞こえた。裏にある木造住宅街も、賑やかな表通りから切り離されたように今年もしんと静まり返っている。
昔も今も、この街は何も変わらない。
私の周りの世界だけが何度も同じ景色を繰り返し、いつまでも回り続けているようだった。
(つづく)
(2475文字)
第一話は、こちらから↓
いつも応援ありがとうございます🌸 いただいたサポートは、今後の活動に役立てていきます。 現在の目標は、「小説を冊子にしてネット上で小説を読む機会の少ない方々に知ってもらう機会を作る!」ということです。 ☆アイコンイラストは、秋月林檎さんの作品です。
