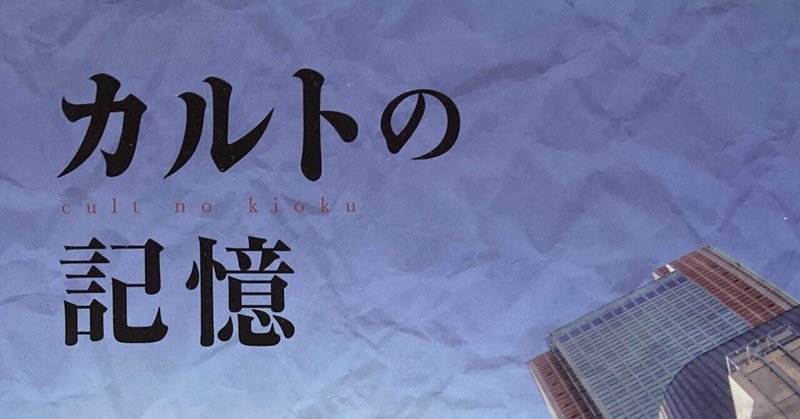
#006第五章 三軒茶屋
#カルト #統一協会 #入信 #脱会 #体験手記 #やま
#山下ユキヒサ
ボクの20代の数年間はカルトの記憶でした。
「カルトの記憶」は、
ボクの統一協会入信から脱会までの体験手記です。
*
ボクはこの世界で生きる意味を与えられ、
仲間たちと共に毎日夜中まで活動に明け暮れました。
そこには、説明の要らないような青春のきらめきも確かにありました。
そして、もう一つ確かなことは、
落ちても落ちたことに気づかないような、
マインド・コントロールという〈落とし穴〉に、
ボクらはしっかりとはまり込んでいたのです。
カルトの記憶/目次
プロローグ
第一章 ブンブン
第二章 アジト
第三章 学生たち
第四章 チャーチの人々
★★★第五章 三軒茶屋
第六章 特急ロマンスカー
第七章 出口
エピローグ
主要参考文献
【第 五 章 三 軒 茶 屋 】
年が明け、八二年を迎えた。
所属していた東京第三地区・目黒支部は、地区本部である世田谷協会に吸収合併されることになった。目黒から世田谷への移転で、生活環境は一変した。
われわれ目黒協会の信徒二十名が世田谷協会のメンバーに加わる。世田谷には大学生を主力メンバーとし、献身者や社会人を含めると三十名以上のメンバーが在籍していた。第三地区は合併することで一挙に大所帯となった。
活動拠点は世田谷区三軒茶屋。
世田谷通りと玉川通り(R246)が交差する、三軒茶屋交差点周辺である。その中心的活動とは伝道活動ということになる。
〈三軒茶屋〉という地名の由来は、江戸時代の中頃、丁度この玉川通りと世田谷通りの分岐点に三軒の休み茶屋があったという。
やっぱり、そのままね。ちなみに三軒の茶屋とは、角屋、田中屋、信楽屋だという。
地下には東急田園都市線三軒茶屋駅がある。
また交差点から目と鼻の先には、東急世田谷線の三軒茶屋駅がある。朝夕にはこの二つの駅を利用する人々で通りは溢れる。
入教してからの僕は、新人トレーニングのロードをひた走ることになる。ちょうど合併した時期に地区内部で三日間の修練会がスタートし、それが終了するとさらに次の訓練が準備されていた。
合併によって世田谷で初顔合わせした他の新人メンバー七名と共に、目黒区柿の木坂で訓練を受けることになった。訓練場所は木造二階建ての古い一軒家。
ここは昭和の三十年代後半に建てられたのだという。ここで訓練生は寝泊まりし、ここから学生は大学に、社会人は仕事に出た。
通称〈四〇トレ〉と呼ばれる四〇日間のトレーニングだ。それぞれ帰ってから講義を受けるのだ。寝食を共にするこの空間で、僕らは打ち解け合い、絆を深めていった。
この家の玄関前には、人の背丈より少し高い梅の木が植えてあった。春を告げるこの花がつぼみをふくらませ花開くまで、トレーニングは続いた。
僕らの信仰のつぼみも、この場所でゆっくりと膨らんでいった。
このトレーニングで生まれて初めて〈断食〉なるものを体験した。四十時間断食だった。四十時間では五回分の食事を抜くことになる。期間中水だけは飲めるが他の飲食は一切禁止である。
この断食も無事終えた。しかし、断食の本当の試練は、それが終了したときから始まるのだということが実際やってみて分かった。それはどういうことかと言うと、断食中の胃は小さくなっている。
そこにいきなり普通食を流し込めば体に負担がかかる。だから少なくとも断食に要した同じ長さを掛けて、除々に戻していくのだ。断食中は食事をしないということが大前提だから我慢している。
しかし断食が終了して禁食が解除されると、今まで押さえつけていた食欲が爆発し、食べたくて食べたくて我慢が出来なくなるのだ。
そしてついつい食べ過ぎては苦しくなり、後悔することになる。
初期の大先輩たちも断食をした。そんな先輩たちの断食にまつわる武勇伝をスタッフから聞いた。昔は断食の正しい知識など知らないまま行った。そして、伝説になるような出来事が数々起こる。
今は幹部クラスになっているある男性が、一週間断食をやり遂げた。その後でスタミナをつけるぞとばかり、トンカツ屋に駆け込んだのだ。運ばれてきたカツにむしゃぶりつき、ご飯をかき込み、味噌汁で流し込んだ。結果は胃痙攣を起こし、救急車で運ばれたという。
四〇時間という、五回の食事を抜いただけの断食だったが、明けの最初の食事はとても感動的なものだった。
主食はお粥と重湯の中間ぐらいのもの。副食は海苔の佃煮に梅干し。やっとかたちの残る米粒をスプーンですくい口に運ぶと、体にじんわりと染み込んでいく。
一口一口を大切にゆっくりと時間を掛けて味わった。まるで離乳食のような食事だったが、頬擦りしたくなるほど愛しく豊かな味わいだった。食べものに対して愛しいなどと感じたことなどなかった。
今までいかに無造作に食べ物を口に運び、食欲を満たしていたことか。このことは僕に〈食べる〉という行為を根本から考えさせる体験となった。
水行もやった。それも真冬の水行だ。風呂オケですくうと一気に水をかぶった。古い木造の風呂場で、すき間風が半端ない。
〈心臓麻痺〉という言葉を強く意識しながら歯を食いしばった。
この四十トレが終了すると、今度は〈二一日間実践トレーニング〉へと続いた。トレーニング場所も柿の木坂を離れ、活動拠点である三軒茶屋へと戻った。
トレーニング期間はあっというまに数ヶ月が過ぎていた。
毎日が教義で溢れた。組織内の考え方に僕らは身も心もどんどん染めあげられていった。そしていよいよ実践メンバーとして巣立つための総仕上げとして、最後の実践トレーニングが用意されていた。
その頃になると、毎夜行われる実践メンバーだけの〈反省会〉にも参加が許されるようになる。そんなある日、いつもなら二十二時過ぎから始まるその反省会も、今日は責任者たちの会議があるとかで、いつもより早い時間に始めるという連絡を受けていた。
講義が終わりマンションを出ると、新人の仲間七名と〈三茶〉の舗道を歩いていた。
「今日の全体集合、何時からだっけ…」うろ覚えだった僕はみんなに確認した。
「エート、今日は、二十時から…」仲間の一人が答える。
「じゃもう、時間がないね。夕食早く食べに行かなきゃ…」
僕の言葉が切掛けとなり、薄暮れの街をみんなは駆け出した。それからすぐのことだった。仲間の一人が舗道の隅に何かを見つけ皆に声かけた。それは二つ折りの黒い革の財布だった。
僕らは自然に小さな輪になり、落とし主を特定するために財布を開き手がかりを探した。財布の中身は一万円札が三枚、他に各種クレジットカードが十枚近くあった。落とした人は今頃困っているだろうね、仲間の一人が呟いた。そうだね、と僕らもうなずいていた。
最寄りの交番に届けようとすぐに話がまとまる。しかし、時間に余裕のないこともあり、いざ誰が届けるかという段になるとみんなは黙ってしまった。
拾得物を交番に届けること。それは少し厄介な仕事だ。それに財布の中身はちょっとしたものだったから尚更だった。そのとき新人メンバーの最年長で、唯一の社会人二十九才の吉崎さんが、「いいよ、僕が行ってくるよ…」と引き受けてくれた。
普段から温厚で兄貴のように慕われている吉崎さんは、このあたりの行動が違う。僕にとっては誇れる霊の兄貴だ。
「さっすが、オトナだねー」「社会人はやっぱちがうねー」「パパさん、よろしくねー」ほっとした僕らは、口々に声を掛けた。
〈パパさん〉とは彼に対する仲間内の愛称だった。吉崎さんは実年齢より三つ四つ上に見えた。もちろん独身なのだが、家庭持ちで幼い子供がいてもおかしくないような落ち着きがあった。
口数は少ないが、いつも静かなほほ笑みを絶やさない頼れる兄貴だった。
僕らは少し茶化しながら、彼の申し出をオーバーに持ち上げた。吉崎さんは僕らの声に笑顔で応え、満更でもなさそうに片手を上げた。
二十時。
反省会が始まった。
吉崎さんは先の一件を済ませ、滑り込むようにしてなんとか間に合った。
この時間はまず一日の報告から始まる。いつもなら支部長が報告を受けるのだが、留守の支部長に代ってこの日は佐竹さんの担当だった。佐竹さんは我々新人の教育担当講師だった。
講義内容は理論的で理知的。だが身振り手振りの全身を使い、表情豊かに語った。ユーモアにも富んでいた。ただ、話に熱が帯びてくると徐々に声が大きくなり、身振り手振りがさらに加速すると、黒板をばんばん叩いた。
新人代表の吉崎さんが研修の報告に続いて、さっき拾得した財布の件を付け加えた。
「…ということで皆で話し合い、私が交番に届けまし…」言い終らないうちに佐竹さんが噛みついた。
「えっ、交番に届けた? 何やってんの。どうして協会に持ってきて献金しないの?
その人だってそんな金は二、三回飲みに行けばすぐに使っちゃう金なんだよ。そのお金は献金することによって、その人の救いの(蕩減)条件になるんじゃないか」
今まで講義では訊いた事のないような激しく責めるような口調だった。威圧するような言葉に圧倒された。僕らは押し黙るしかなかった。
この部屋の空気は、一瞬のうちに凍結された。そして、だれも何も言わなかった。
良かれと思ってした社会的行為。それは小学生でも知っている親切な行為のはずだった。
われわれ新人には協会へ献金するなどという発想は、誰も持ち合わせていなかった。
(えっ…あれは間違っていた? 拾ったお金は統一協会に献金しなくちゃいけない? エッ、ちょっと待ってくれよ。それってまずいんじゃないの…。それって、人の金を盗むことになるんじゃないの…。
そりゃ、ネコババだよ。そんなのあり…。エッ、そうなの。ここのみんなはそのこと了解している? みんなが黙っているということは…そういうことなの?
そうか、そうか…僕らの方が甘かったという…そういうことなんだ。そこまでしなくてはいけない世界なんだ、ここは…)
止まった思考が先に進まないまま、自分の行き場のない思いは、ぐるぐると空回りするばかりだった。
そんな僕の戸惑いなどお構いなく、何もなかったかのように話題は次に移っていた。しばらくすると誰かの報告に、和やかな笑い声さえ生まれていた。さっきまでの険しく張り詰めた空気が嘘のようだ。耳元の音量が急に絞られるように、仲間たちの声が遠くになった。同じ部屋にいる先輩たちが、どうしようもなく遠い存在に思えた。
ネコババという行為を、神の救いとして聖化する。落とし主のお金をネコババすることが、その人の救いにさえなるという思考。組織にしてみれば、それは〈聖なる行為〉なのだ。
身につけてきた社会性や倫理観が揺さぶられていた。今まで常識だと思っていた現実の世界が、新しい価値観に呑み込まれようとしている。
神の国の実現。それはこの地上に文鮮明教祖を頂点とする天国を建設することだという。教祖の言葉は絶対で、その命令は何よりも最優先される。それは信徒の生活や人権よりも、社会のルールよりも法律よりもである。
カルト・グループは、自分たちのみが真実、進歩、絶対のモデルを体現していると前提している。だから自分たちの教えに合わない現実はすべてあやしいもので、否定すべきものだとなってしまう。外部の社会に非寛容であり、外部から包囲、弾圧、迫害されているとの感覚を好んで育てることもある
僕らはたとえ風呂に入れない日があったとしても、こんな影響力のシャワーを浴びない日はなかった。
自分たちだけが常に正しいのだという〈独善〉と、だからこそ徹底した〈排他的〉態度で外部からの情報を遮断する。そこには自分たち組織の都合だけを最優先する〈幼児性〉がそこかしこに顔を出す。
外部から問題性を指摘されれば、それは宗教的迫害だと騒ぎ立て、取り合わない。なにを問題視されてるのか考えもしない。
こんな集団が〈カルト〉かと問われれば、それはそうだと答えるしかない。僕らはそんな〈カルトのシャワー〉を、知らず知らずのうちに毎日浴びていた。
だが、そのときそんなことには全く気付かずに、生活していた。
*
さらに数ヶ月が過ぎた。
昼間は経済活動や伝道に励み、夜は大学に行った。
最初の経済活動は〈珍味〉の訪問販売。チャーチではこんな商品を扱っていた。珍味はいわば販売の入門編だ。ラフなスタイルで〈イカ、カニ、ツナ、コンブ〉を加工した、要するに〈酒のつまみ〉を売り歩くのだ。
バッグに数十袋も詰め込み、ワゴン車に乗って指定区域を一軒一軒売り歩いた。一袋二千五百円のブツだ。
一軒でも多く回るため、少しでも売り上げを伸ばすため、一軒終わると次の家へ走っていくことが立派な行為とされていた。だがそんなことをいつもしていたわけではない。
数十袋の物(商品)を入れたバッグはぎしぎしと肩に喰い込み、走ろうとする意欲を萎えさせた。
売り込むためにはちょっとした仕掛けがあり、それはセールストークの中にあった。
「北海道の稚内(わっかない)から来ました。今、キャンペーンで回らせていただいています」。
そんなのは大嘘だった。「北海道の稚内から来た…」という言葉はきっと魅力的に響くのだ。
北海道の何か珍しいもの、何か美味しそうなものをもって来た、と思わせるのだろう。そのひと声で警戒心が随分薄くなるのを感じた。
北海道にはまだ行ったことがなかった。それが〈ワッカナイ〉から来た売り子の兄ちゃんに成り済ますのだ。
統一協会員であることを隠し、偽り、終わる一日。
統一協会の教えを真理だと信じて協会員になったはずの自分が、メンバーになった途端その名を隠す。
そればかりか教えを口にすることもなく、酒のつまみを売り歩くような毎日。
信じていることを隠したり、偽ったりすることが求められる活動。それが経済活動だった。それから珍味販売は一ヶ月ほどで終了した。正直ホッとした。珍味販売は心底嫌いだったからだ。しかし、次の販売が準備されていた。
次は〈印鑑販売〉だという。
*
「港区に新しくお店ができましたので、ただいまキャンペーンで回らせて頂いています。ボナール商会と申します」
ほんの一週間前まで、「北海道の稚内から来ました…」というトークだったのが、「港区のボナール商会と申します」になった。
珍味から印鑑へと販売商品が変わった。組織としては、とりあえず一通りの活動を体験させようという目論見だったのだろう。商品は〈酒のつまみ〉から〈開運の印鑑〉になった。
扱う商品が変わると販売の方法も態度も服装も、そしてもちろんセールストークも切替った。
珍味は調子よく軽妙に立ち回らないと売れない。しかし、印鑑は落ち着いた語り口と態度で接客しなければ、信用されない。
五日前の夜のミーティングのことだ。
指導役の先輩が販売方法を伝授する。
「相手は〈ボナール商会〉と言われてもいったい何なのか? どんな商品を扱っているのかわからないでしょ? そう、そこがミソなんです。相手は戸惑いますからね…一方的にトークしないで相手にも話させる、そんな間を作って下さい。
そして、相手が、何ですかそれ、なんて尋ねてきたら、それはお客さんになってくれるチャンスです。そこで初めて『姓名判断や手相、印相鑑定をしていますが、ただ今キャンペーン中で無料で観させて頂いています』とトークして下さい。
「笑った」「なるほどねー」など体験をされましたら お気持ちで、サポートお願いします。 記事の充実資金のほか、世界の子供たち支援に充てさせていただきます。

