
2020年、Mi-Project/まつど暮らしの保健室の取り組み
地域の中の拠り所として、世代や生活背景の違う人と人が、同じ時間や空間を共有する。その中で育まれる一人の感情や関係性を大切にしてこその、まつど暮らしの保健室。
改めて大切にしたいと思えるこのコンセプトに気づくことができたのが、2020年であったように思う。
(ちょうど1年ぶりのnoteになってしまいました・・・)
対話のフラッグを手がかりに
コロナ禍という状況に、私たちがまず取り組んだことは、コンセプトの再検討だった。
その中で、まつど暮らしの保健室運営指針(ミープロモデル)を作成した。
(未だ更新中で、みなさんへ公開するタイミングを伺ってます・・・)
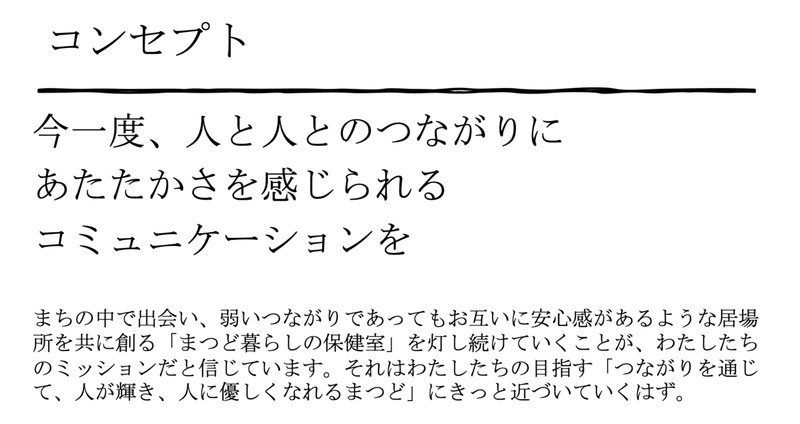
これは、新型コロナウィルス感染症の”感染拡大状況”を表す数値を参考に、開室形式や感染対策をレベル別に設けた指針である。
だが指針といってもまだまだ不確定な状況。この指針に基づけばOKでない。
あくまでこの指針を元に、方針を対話で検討することを一番の目的にしたいと考えた。
いわば対話のフラッグ的存在がミープロモデルだった。

このミープロモデルを手がかりに、
まつど暮らしの保健室を市内3ヶ所で開室してきた各地の居場所/コミュニティカフェ運営者と、
開室の形式をその都度その都度話しあいながら、まつど暮らしの保健室を開室してきた。
その中で各地共通していたのが、
これまでまつど暮らしの保健室に足を運んできて下さった地域住民と私たちとの繋がりは途切れたりしないんだよ
と感じてもらえることだった。



講座もイベントも、チラシを作っての広報も例年より注力せず、まつど暮らしの保健室を始めて3年間で出会った方々との関係性を紡ぐことに、私たちの存在意義を見出したような気がする。
ーーーーーーーーーーーーーーー
お便りには、あたたかさを添えて
まつど暮らしの保健室を開室できなかった状況も多くあった。
その中で取り組んだのが、「保健室便り」の発行。
「オンライン」を拒絶してしまうような方へ、会報や回覧板、誰かから渡ることを想定した、お便り。
こだわったのが、私たちの顔を想像してもらうこと、そして手書きイラストで文字量は極力少なくすること。
そうすることで、あたたかさをいつもよりも感じられるのではないかと。
なんて人の手による時間のかかる作業にみえるが、これがまた愛情を注ぎやすくなる。

かわいい・・・
元々漫画家志望だった作業療法士のメンバーによるデザイン。
内容はメンバーの持ち寄り。
新型コロナウィルス感染症に関するタイムリーな情報(コロナマスクの付き合い方や熱中症対策など)、フレイル(筋トレや口腔ケア)関連などのメンバーの得意を活かした内容。
そして、マスクの付き合い方に関しては、ママや子ども向け地域密着の広報誌にも寄稿させていただいた。
もっともっと届けるべきメディアだと自信を持って言えるので、年明けからはもっとメンバーの個性が出る記事を随時発信していく予定だ。
ーーーーーーーーーーーーーーー
「まちに出て会話する」を創る
場所ありきのまつど暮らしの保健室が新たに取り組んだのが、
【OHANA Project】
これは松戸市常盤平地域包括支援センターと共同で、まちの景観として馴染みのある花壇や畑を、地域住民の皆さんと作り上げることで、
「まちの彩りをケア」しにまちへ出るきっかけと、その場で居合わせた人と会話するきっかけをつくることを目指した。
「まちの彩りをケアする」とは、人からケア(気にかけてもらう)してもらうことの多い高齢者や日常生活になんらかのハンデがあるような人でも、
お花に水をあげたり、草むしりをしたり、虫を取ったり、成長を楽しんだりと、彩りになる花や野菜を見守ることで、嫌な気分や塞ぎ込んでしまう気持ちを少しでも忘れることができるのではないかという発想である。
まちの彩りをケアしてくれた方々は、まさに制度の狭間でいるような地域住民(例えば記憶がなかなか持続しない人)にも参加していただいたり、必要な資源を提供してもらったり一緒に作ってもらったり。
そして収穫した野菜を販売した。購入してくれた方の中には、成長を見守ってくれた人もいた。





一見、馴染んでいて見落としてしまうようなまちの景観でも、人と人とのつながりを創るストーリーが生まれた。
そして健康相談や講座などで専門職や地域住民が出会うのではなく、まちに足が遠のいてしまっている人をまちに呼び、自然に誰かや何かをケアする循環が起こるような仕掛けにもなったように感じる。
この取り組みを含め、広報まつど9月15日号市民活動特集にも取り上げていただいた。

ーーーーーーーーーーーーーーーー
土を、また耕す。
総じて、2020年の取り組みをふりかえると、
結局自分たちの居場所や出会いを守りたかったんだなと気付かされる。
誰かを支援する。誰かのために何かを提供する。そういった関係性もあるだろうが、
私たち自身もメンバー同士や地域の方々と今までのように繋がっているためにできることにチャレンジしたのだと思う。
だからこそ、
地域住民にとっての繋がりや場、必要とされていることに向き合う必要がある。
ーーー
今年は、メンバー間で時間をかけて一人ひとりの思いや言葉を表現してきました。
これからを見据え、私たちだからできること、すべきことにひたむきに。
今一度未来を考えることから2021年をスタートさせていきます。

(文責:松村)
これまでの活動が整理できておらず、ごめんなさい。Facebook中心に気まぐれに投稿してます。Mi-Projectの活動に興味あるという方は、info@mi-project-matsudo.comまで気軽にご連絡ください!
