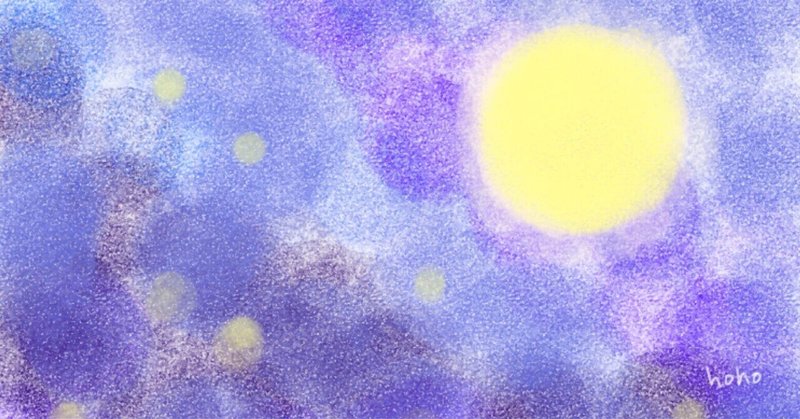
不倫沼①
ここから書くことは半分本当で、半分フィクションです。誰の参考にもならないし、見る人によってはただ不快なだけかもしれないが、自分自身同じ過ちを繰り返さないためにも備忘録として書いておくものです。悪しからず。
Fと出会ったのは私が転職してすぐのことだった。
男という男に失望し、男に期待せず、これから自分の将来について考えていこうとしている時だった。
Fに対しては、初めて会った時からなんとなく惹かれるものがあった。
最初はそれほど意識していなかったのだが、喋る機会が増えるほどに、自分の意思とは裏腹に、言いようもなく親しい感情が湧いてくるのだった。
Fは同じ部署で、4つ年下だった。背が高く、眼鏡をかけていて、笑うと眼鏡の奥の目が無くなるくらい、人懐こい笑顔が何とも言えず魅力だった。
同じく結婚はしているが子どもはおらず、課の集まりや飲み会に決まって顔を出していた。
あまり積極的に話すタイプではなかったが、ある時から目が良く合うようになった。
あるいは私が見ていたからかもしれない。
彼と目が合うと、私は自分の中心に何かが突き抜けるような感覚を覚えた。
これは本当に不思議なことだったが、忘れていた何かを思い出させてくれるような感じがした。
言葉を選ばずに言うなら、昔から、「そうなることを知っていたような」感覚だった。
気づけば私は仕事中でも彼のことが気になって仕方なくなっていた。
いつも淡々と、黙々と仕事をしているF。恥ずかしがり屋で、私が書類を手渡すときにもそばへ行くと照れたように目を逸らした。
それが何とも言えず可愛らしく、私はわざとからかって顔を覗き込んだりした。
Fとの距離は急激に縮まったのは、ある飲み会の後だった。
ある夏の日、課の飲み会の帰り道、方向が一緒になった私たちは、話をしながら歩いているうちに、どちらからともなく見つめ合い、抱き合った。
長い時間誰も通らない夜道で抱きしめ合って、自然とキスをした。
それはとても自然な感覚で、その時も強く、「この人にやっと会えた」と思った。
「墓場まで持っていかなくちゃね」
と、Fは言った。
私も、このことは誰にも言ってはいけないのだと強く思った。
ただ、月明かりだけが、私たちのことを知っているかのように明るく照らしていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
