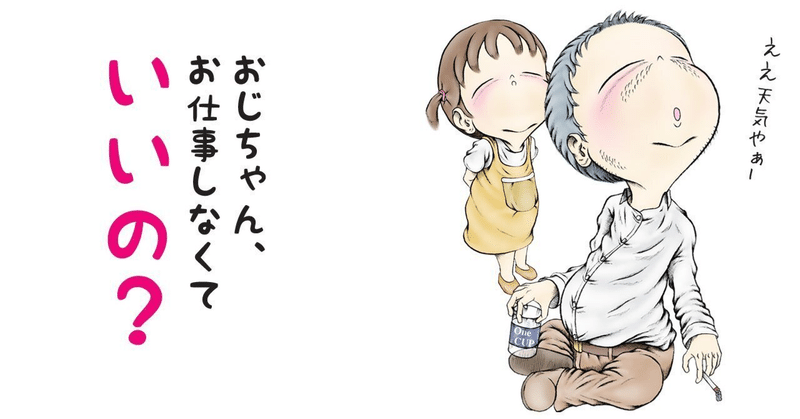
【失業手当】ハローワークでサクッと『求職活動』の徳を積む方法
失業手当の建前
『失業手当』とは、何とも人をモヤモヤした気持ちにさせる制度だ。
毎月の給料から安くもない保険料を何十年も払い続けたのだから、その対価として失業時には『失業保険』を正々堂々と受け取っていいはずであるが、制度の実態はどうもそうはなっていないようだ。
そもそも、制度の名称も『雇用保険』なのであって、『失業保険』ではないから、失業したからといって、自動的にお金が銀行口座に振り込まれるわけでは決してない。
『失業手当』は、正式には『雇用保険』の失業等給付制度に含まれる『求職者給付の基本手当』のことを指す言葉であることからもわかるように、『求職者』=『失業の状態ですぐに働ける人』に対してのみ給付される手当なのだ。
失業の状態ですぐに働ける方とは
離職し、「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態」にある方をいいます。
したがって、就労している人は元より、学生や家事、介護、自営準備に専念する人、あるいは次の就職が決まっていたり、逆にまるで求職する気がなかったり、病気の人などは手当を受給できない制度上の立て付けとなっている。
これから、『失業手当』を受け取るために『ハローワーク』に出かけようと思っている人は、上記の建前を十分に頭に叩き込んだ上で訪れた方が、スムーズに事が運ぶものと思われる。
これにそぐわない行為や言動、申告をおこなうと、いろいろトラブルの原因になりかねない。
むろん言うまでもなく、虚偽の申告はNGである。
虚偽申告して不正受給した場合の罰則はとても厳しく、『倍返し』どころか『3倍返し』になるようである(汗)。
※不正をした場合、受給した金額の3倍の金額を返還
お役所の世界では、建前が何よりも大切なのだ(笑)。
いくら貰えるのか?
では、『失業手当』はいくら貰えるのだろうか?
金額は、平均給与額の動向などに基づき毎年8月に改訂されているようなので、詳細はその時点で『ハローワーク』に確認して欲しいが、参考までに、執筆時点(2024.5)でのデータを載せておく。

ざっくり言うと、失業前の賃金日額と年齢で給付率が決まり、さらに上限額と下限額が定められている。
50代で退職するなどで賃金日額が高い属性の方は、現役時に手にしていた金額とのギャップが大きいだろうから、あまり過度の期待はしない方がいい。
それでも、無収入の身となった者に取っては、4週毎に振り込まれる『失業手当』は、金銭的にはもちろんのこと、精神的にも大変にありがたいお金であることに変わりはない。
何日間支給されるかも、各人の属性によって異なってくる。

まず、自己都合なのか、或いは会社都合の退職なのかで分けられる。さらに、保険の加入期間と年齢が加味されて決定される。
繰り返し何度も受給する人が増えたら保険制度自体が成り立たなくなってしまうのは自明の理なので、加入期間によって支給日数に差をつけるのは理解できる。しかし、求職する間の生活費を支給するという『雇用保険』の制度趣旨からして、自己都合退職者を冷遇することに、何らかの合理的な理由があるようには思えない。
会社の業績が傾いて止む無く解雇された人は善で、自己都合で辞めた人は悪なのだろうか?
自己都合退職の場合は、さらに支給開始までに3か月の待機期間という一種のペナルティが課せられている。これではまるで、「転職は悪で、同じ会社で定年まで働くことが美徳である」と国が推奨しているようなものではないか?
日本に、まっとうな転職市場が育たない原因の1つには、こういった制度的な問題も潜んでいるように思える。
それでも自分の場合は150日、ありがたくいただいた。
ハローワークの手続き
『ハローワーク』の手続きの流れは図のとおりだ。

このなかで、『失業手当』を受給するうえで重要なのが、28日毎に訪れる『失業の認定』と、それに必要な『求職活動』の実績だ。
『失業の認定』は、『認定日』と呼ばれる予め指定された日に、『ハローワーク』を訪れ、受給条件を満たしていることを申告し認定印をもらう必要がある。もし認定されなければ、『失業手当』は支給されないのだ。
『認定日』は原則、変更が不可能だ。求職活動をしているのだから、いつでも来れる筈だという役所のロジックだと思われるが、こういう高圧的なところも、モヤモヤが蓄積されていく原因の1つだ。
ところで、『認定日』は28日毎に巡ってくるため、毎回、同じ曜日になる。この曜日は、最初に『ハローワーク』を訪れた曜日で決まるので、通院などの都合がある方は、最初に『ハローワーク』を訪れる曜日を気にしておいた方がいいかもしれない。
あと、曜日で言うと、祭日は月曜日のケースが多いが、『ハローワーク』も休みとなるため、その場合は前後の金曜日か火曜日を『認定日』に指定されることになる。その日はいつもの倍の人数が『ハローワーク』に押し寄せるため、すごく混みがちだ。都市部に所在する『ハローワーク』で、春などの繁忙期にあたる場合は、その辺も考慮した方が得策だ。
しかし、こういった類の話は後からわかる話で、気づいた時はもう遅かったりするのが世の常である(笑)。
求職活動の実績作り
さて、『ハローワーク』に通い始めて一番頭を悩ませるのが、『求職活動』の実績作りであろう。
『失業の認定』毎に、2回の『求職活動』の実績が必要とされている。言い換えると、4週に2回ずつ『求職活動』という名の徳を積む必要がある。
徳なくして、お金は手に入らないのだ(笑)。
『ハローワーク』の求人情報は、今どきはわざわざ『ハローワーク』を訪れなくとも、PCやスマホのアプリで検索・閲覧することができる。しかし、単に求人票を閲覧するだけの行為は『求職活動』の実績としては、認定されない。
ここでも、お役所の基準があり、『求職活動』の実績として認められる例としては、下記があげられている。

この中で、手っ取り早い方法として自分が採用したのが、『職業相談』と『オンラインセミナー』だ。
『ハローワーク』に出向き『失業の認定』を受ける
同日に『ハローワーク』で『職業相談』を受ける
自宅で『オンラインセミナー』を受講する
『ハローワーク』で次回の『失業の認定』を受ける
以降、繰り返し
この方法であれば、『ハローワーク』に出向くのが、『認定日』だけで済むことになる。
自分にとっては、この方法が一番簡単に『求職活動』という名の徳を積む方法であったので、紹介する。
職業相談の実際
4週に1度は必ず『失業の認定』のために『ハローワーク』を訪れる必要があるため、その足で『職業相談』を受けて、徳を1回積むのが効率的である。
自分の通っていた『ハローワーク』では、『失業の認定』とは別のコーナーに、『職業相談』のコーナーが並んでいて、受付で番号札を貰い呼ばれるまで順番を待つシステムであった。
自分が並んだのは、一般の『職業相談』コーナーであるが、保育・看護・介護コーナーや建設・警備コーナー、高齢者コーナー、若年者コーナー、職業訓練コーナーなどの『職業相談』が種類別に設けられていた。
最近の市役所などでは、人件費圧縮の目的で非正規雇用の職員が大量に存在するらしいが、『ハローワーク』もその例外ではなく、『失業の認定』の根幹業務を正規雇用の職員でこなし、『職業相談』業務などには非正規雇用職員を多く回しているように見受けられた。
実際、70代くらいのシルバー雇用と思しき相談員がお相手の場合も多かった。
初めて利用する方は、『職業相談』とは何を相談したらいいのだろうか?と悩むかもしれない。
もちろん、条件に合う求人票を探してもらい面接の段取りまで付けてもらうことも可能だし、履歴書の書き方や、面接の受け方の相談なども可能だ。
しかし、『ハローワーク』の求人票は家でも確認できるし、自分の場合はじっくり腰を落ち着けて将来の可能性を検討する方針であったため、大勢の相談者を捌かなければならない職員の方の貴重な時間を浪費しても申し訳ないので、ごく短時間で終わらせていた。
職員「今日は何か相談ありますか?」
自分「特にありません」
職員「活動報告ということですね。また何かあったら相談してください」
『職業相談』の印
自分「ありがとうございました」
で、終わる場合もあったし、
自分「セミナーのパンフレットはありますか?」
職員、ごそごそ探して「こちらですね」
自分「ありがとうございます。内容確認してみます」
『職業相談』の印
のパターンもあった。時間にして1~2分程度だった。
オンラインセミナーを活用する
セミナーは一度だけ『ハローワーク』で開催されているものに参加したことがあるが、長いし内容もつまらなかったし家からも遠かったので、以降は全て『オンラインセミナー』に切り替えた。
世の中には民間事業者の主催するセミナーもあるようだが、ネット情報等によると、登録した途端に昼夜構わず担当者から鬼電が入るとの噂もあり、煩わしそうだったので敬遠した。
自分が利用したのは、東京都が都民の雇用・就業を支援するために設置した『東京しごとセンター多摩』主催の『オンライン就職支援セミナー』だ。
事前に登録・予約が必要であるが、配信期間中の好きな時間に家のPCやスマホで受講できるのでたいへん便利だ。終わった後に、ごく簡単なアンケートはあるがテストはない。
受講証明書も発行されないので問い合わせてみたところ、自分の通った『ハローワーク』では、受講証明書がない場合は添付不要の回答であったが、『失業の認定』時には念のため、セミナーの申込確認メールを印刷して提出していた。
このあたりの細かい運用については、『ハローワーク』毎に異なる可能性も考られるため、『オンラインセミナー』を受講する前には、『求職活動』の実績として認められるか、事前にご自身で『ハローワーク』に確認しておくことをお勧めする。
最後に
この記事では、”『ハローワーク』でサクッと『求職活動』の徳を積む方法” について自分の経験を踏まえてお伝えした。
これは、あくまでも自分の狭い交友範囲内での情報であるが、求人の質としては以下のように感じている。
個人的な伝手・コネ > 有料職業紹介会社 > 無料職業紹介会社 > ハローワーク
『ハローワーク』は、無料で求人を掲載できるため、情報が玉石混合だ。有料職業紹介会社に求人広告を掲載できない会社でも、『ハローワーク』には求人を掲載することが可能なのだ。
もし仮に、『個人的な伝手・コネ』があったり、応募した早期退職制度の特典などで『有料職業紹介会社』を利用できる環境にあるのなら、職探しは、そちらを優先させた方がいいかもしれない。
その場合、『ハローワーク』は、『失業手当』を受給するためだけに利用することになる。そのときに、この記事内容が少しでも参考になれば幸いだ。
※この記事は、個人の見解を述べたものであり、法律的なアドバイスではありません。関連する制度等は変わる可能性があります。法的な解釈や制度の詳細に関しては、必ずご自身で所管官庁、役所、関係機関もしくは弁護士、税理士などをはじめとする専門職にご確認ください。
また本記事は、特定の商品、サービス、手法を推奨しているわけではありません。特定の個人、団体を誹謗中傷する意図もありません。
本記事を参考にして損害が生じても、一切の責任は負いかねます。すべて自己責任でお願い致します。
お知らせ
資産運用に興味のある方は、拙著『資産運用の新常識』をご覧ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
