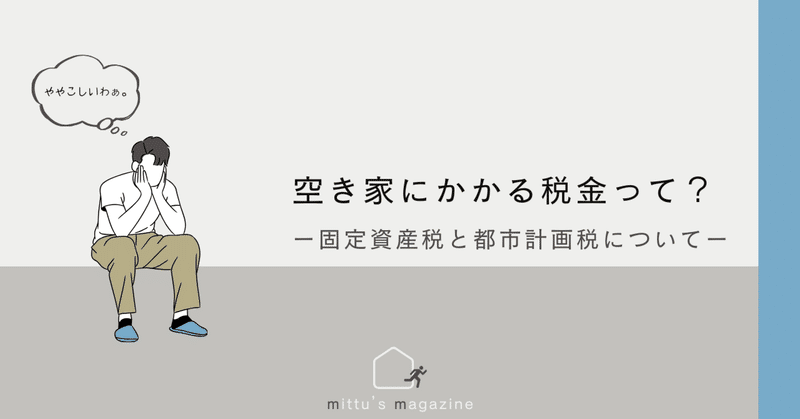
空き家を相続したら。固定資産税と都市計画税について|不動産知識_No.01
こんにちは。mittuです。
この度は『mittu's magazine』をご覧いただきありがとうございます!
今回は【空き家にかかる税金について】勉強しましたが、いまだよく分からんこともあるのでご存じの方にはぜひご教授いただきたいです。
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Today's

Empty House - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ま・え・が・き
私は、市場に出回っていない利用可能性の低い空き家について、その有効活用方法を探求している学生です。
日本では、特に市場に出回っていない空き家の増加が深刻化しています。これから団塊世代の高齢化や人口減少が本格化すると、増加率が急激に上昇すると予想されており、考えただけで恐ろしいですね。
読者の中にも相続などによって使っていない空き家を所有している人がいるかもしれません。所有者にとって、空き家を手放さずに所有することの問題は、維持管理と年間の税金支払いがあります。
使っていなくても税金を払わなければならないのは嬉しくありませんよね。今では、Netflixや英語学習アプリなどのサブスクリプションが主流であり、使っていなくても解約するまで料金がかかります。空き家の税金は、まさに最悪のサブスクリプション版かもしれませんね。手軽に解約することもできず、放置し続けると維持管理コストもかかってしまいます。逆に言えば、その税金を賄えるだけの利活用方法があれば、所有者は手放さずに所有し続けることができるでしょう。ただ、その方法が難しいということですね(^^;)
空き家にかかる税金は2つ
空き家には固定資産税と都市計画税の2つが課税されます。それぞれの税金についての説明は以下の通りです。
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋及び償却資産(これらを「固定資産」といいます。) の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村が課税する税金です。
都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業を行う市町村が、都市計画区域内にある土地や家屋に対して、その事業に必要となる費用に充てるために課する税金です。
つまり、
固定資産税→土地や家屋の価格に基づいて課税
都市計画税→都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てるために課税
ということです。
ただし、都市計画税は都市計画区域内(=用途地域の指定)にあるもの対して課税されるため、区域外(≒開発の優先順位が低い地域)にある場合は非課税になります。
これらの税金は土地と家屋の2つに分けられて課税されます。
そのため、最終的な支払金額は、
土地(固定資産税+都市計画税)+家屋(固定資産税+都市計画税)⇒支払
となります。
具体的な支払金額は固定資産税の課税明細書や土地の課税明細書から算出することができます。
実際の請求金額は?-課税明細書の見方-

上の図は土地における固定資産税の課税明細書です。地域によって、様式は多少異なっています。基本的には土地と家屋の2枚の課税明細書があり、その中でそれぞれ固定資産税と都市計画税が表記されていると思います。
所有者が実際に支払うことになる金額は図に赤枠で示した金額になります。評価額を見て「ギョッ?!」とした方も安堵しているのではないでしょうか。私も最初見たときはただただ金額の大きさに驚き、内容は全く理解できませんでした。今でも完全に理解しているとはいいがたいですが。
つまり、所有者に請求される固定資産税や都市計画税は固定資産税評価額(青枠)に対して様々な減税措置により削減された金額ということです。
赤枠で示した金額はどのように算出されているのか逆算すると、
「固定資産税:所有者が支払う金額」⇐ 軽減税額
←「軽減税額」
【求め方】(課税標準額)×(固定資産税:1.4% 都市計画税:0.3%)
←「課税標準額」
【求め方】(固定資産税評価額 )/(住宅用地特例の対象なら 基本は、固定資産税:1/6 都市計画税:1/3 ※住宅用地の面積により除数は変動)
←「固定資産税評価額」
以上のような方法によって、固定資産税と都市計画税の支払う金額は求められてきます。

家屋にかかる課税明細書の見方も土地とほとんど同じになります。
土地と異なる点は以下の部分です。
家屋自体にかかる税金であるため、住宅用地特例(1/6等)はかからない
家屋は建物の構造形式に対しても別途評価額が追加される
○1について
土地に住宅があることに対しての特例であるため、家屋そのものにはかかってきません。放置空き家が解体されない背景にも、この住宅用地特例による所有者の利点が関係しています。使っていない空き家を解体し、更地にした場合、住宅用地特例の対象外となり3~6倍もの税金を支払う必要が発生するため、放置することが所有者にとって合理的な行動になってしまうという仕組みになります。これへの対策として、空家法(空家等対策の推進に関する特別措置法)が2015年に施行され、周辺環境に著しく悪影響をもたらすような空き家を「特定空家等」に指定することで、空き家が建っていても住宅用地特例から除外されるという動きもあるけれど、権利上の問題もあるからあまり進んでいないとか。余談になりました。
○2について
以下の記事で分かりやすく記載されているので参照して見てください。
簡単に言うと、木造<鉄骨造<鉄筋コンクリート造の順で構造そのものの耐用年数が異なるため、耐用年数が高いければその分評価額が高く設定されるということだそうです。
これらの固定資産税と都市計画税は年に4回の四半期ごとに分割されて請求されるので、負担が少なくて安心です。
最後に
今回は、空き家にかかる税金について、私が勉強した限りでまとめました。
読者の方の所有している空き家の税金はどのくらいかかっていたでしょうか?
なにかしらの方法でその税金分を空き家で生み出すことができれば、想い入れがある家を無理に手放さずに済むと思います。
空き家問題を一発逆転の良い方法はないものですかね〜。
\ご覧いただきありがとうございます/
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
