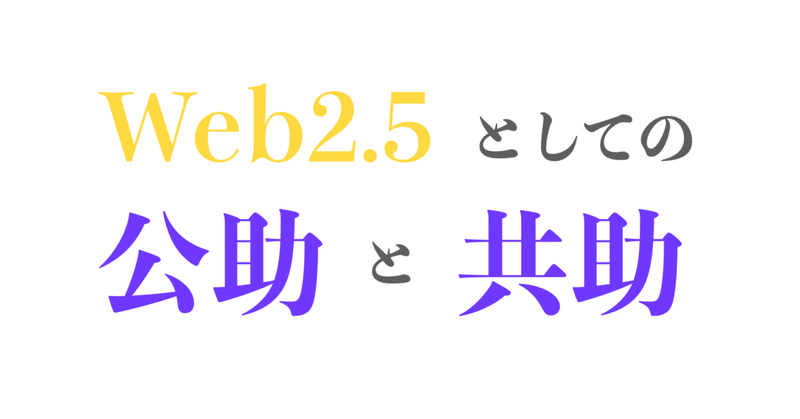
Web2.5としての「共助」
表題の通り、Web2.0プラットフォームにおけるWeb2.5としての「共助」について考えてみたいと思います。
そもそも、Web3ってなんぞやという方もいるので、その話から始めたいと思います。
Web3はユーザーにownをもたらした

Web3を端的に表現したものが上記の図です。
Web1.0の時代において、私たちはネット上のデータを読む(read)ことしかできませんでした。
それが、SNSの登場により、私たちはネット上で自由に表現(write)をすることができるようになりました。
これが、Web2.0の時代です。
しかし、Web2.0のサービスにおいて、データはプラットフォーマーのものでした。
つまり、Web2.0のサービスを利用する限り、私たちの運命はプラットフォーマーに委ねられています。
代表例としてよく挙げられるのが、Twitterにおけるトランプ大統領の垢BAN事件ですね。一国の大統領でさえ、プラットフォーマーに禁止されると、サービスを利用できなくなるわけです。
これが、私たちの運命がプラットフォーマーに委ねられているという所以です。
(Twitterに関して言えば、イーロン・マスクの買収でTwitterもWeb3化していく可能性は大いにありそうですが。)
それに対して、Web3のサービスではユーザー自身がデータを所有(own)できます。
Web2.0で生まれたGAFAM(今は、GAMAMですね)を中心としたプラットフォーマーに対して、インターネットをユーザー自身の手に取り戻していこうとするWeb3の流れは思想からしてとても魅力的です。
私も、Web3について勉強しつつ、 最近はADDressの中で「Web3部」という部活を作ったり、社外のWeb3プロジェクトに参画したりしています。
とはいえ、Web3にはまだまだ詐欺なども多く、かつ技術的にも法律的にもこれからな部分も多いので、Web3が全てを解決するのはまだ先の未来でしょう。
それでは、プラットフォーマーに運命を握られている我々ユーザーには、Web3の到来を待つという選択肢しかないのでしょうか。
そこで考えたいのが、Web2.0プラットフォームにおける「共助」の重要性です。
Web2.0プラットフォームと「公助」
私は、ADDressという多拠点生活のプラットフォームサービスで、コミュニティを担当しています。
かつ、私自身もアドレスホッパーであり、2年ほどADDressを使って多拠点生活をしています。
つまり、運営とユーザー、それぞれの立場で日々サービスに関わっています。
ADDressは、Web2.0の多拠点生活プラットフォームサービスです。
ユーザーの会員情報や予約履歴、オンラインコミュニティでの投稿などのデータは全てADDress社のものであり、ADDress社がなくなると全てのデータは消えるでしょう。
また、他のWeb2.0のサービスと同様に、ユーザーの運命はADDress社というプラットフォーマーに委ねられていて、例えばADDress社にアカウントをBANされるとADDressの利用はできなります。
(現在は、重大な規約違反を犯した場合のみで、ケースとしてほとんどありません。)
ユーザーは、プラットフォーマーであるADDress社に月額4.4万円のサービス利用料を払うことで、サービスを利用します。
そして、プラットフォーマーであるADDress社はユーザーから集めた資金を元手に、より良いサービスを作って提供しようとするわけです。
この形は、いわゆる「公助」の仕組みと言えるでしょう。
「公助」のデメリット
しかし、この公助の構造にはデメリットがあります。
それは、プラットフォーマーへの力の集中です。
昨今、私たちの生活はWeb2.0プラットフォーマーのサービスに依存しています。
例えば、明日突然Gmailが使えなくなったら。Instagramが使えなくなったら。LINEが使えなくなったら。
私たちの社会生活はままならなくなるでしょう。
そんなことは起こり得ないと言うかもしれないですが、実際にトランプ政権下のアメリカでTiktokを使えなくするという話が出たこともありましたし、中国ではFacebookなどが利用できないのは有名ですよね。
また、サービスが利用できなくある場合を除いても、例えばサービスが何らかの(ユーザーが意図していない)事情で不便になるということは容易に想定されます。
つまり、私たちがどんなにそのサービスを利用し、そのサービスを愛しても、我々ユーザーの運命はプラットフォーマーが握っているわけです。
もちろん、我々ユーザーには別のサービスに乗り換えるという選択権は常にあります。
しかし、本当に我々の取れる選択は、サービスを我慢して使い続けるか、サービスの利用をやめるかの2択しかないのでしょうか。
ここに、「共助」の介在する可能性があります。つまり、共助とは、ユーザーのユーザーによる、ユーザーのための自治の仕組みであると言えます。
「公助」と「共助」
共助には、大きく分けて以下の2つの形態があると考えます。
・公助に対する共助(公助vs共助)
まずは、公助に対立するものとしての共助です。
企業で言うところの労働組合や、政治に対する市民団体のようなものをイメージすると分かりやすいでしょう。
プラットフォーマーに積極的に関与し、ときに監視、対立をしてでもプラットフォーマーへの力の集中や暴走を食い止めようとする共助の形です。
・公助を補完する共助(公助&共助)
2つ目は、公助を補完する共助の形です。
公助は公助で機能させつつ、公助とは別の思想やロジックで動く自治機能としての共助を指します。
その共助システムが真にユーザーに寄り添ったものであれば、プラットフォーマーがユーザーの意図しない事情によって一部のユーザーの利益を毀損することがあったとしても、共助によってそれを補完できる可能性があります。
公助で拾いきれないユーザーを拾う、いわばセーフティネットのような共助の形です。
私はADDressというプラットフォーマーの運営にも属する人間として、公助と対立する形態の共助は理想的だと思いません。
プラットフォーマーとユーザーの間に立つ者として、公助と共存する形での共助について考えたいと思います。
DAOと「共助」
それでは、公助と共存する共助の仕組みを作る際に重要なものは何でしょうか。
それは、公助から独立した「意思決定とインセンティブの設計」だと考えます。
Web3において新しい組織の形として注目されており、まさにこの意思決定とインセンティブの設計において1つの理想を示すモデルがあります。
それが、DAOです。

DAOとは、Distributed Autonomous Organization(自律分散型組織)の略で、上の図のように株式会社に変わるWeb3時代の組織の形として注目されています。
その名前の通り、自律・分散しているところが特徴的で、ブロックチェーンにおけるスマートコントラクトとトークンの仕組みによって実現されています。
特に、そのトークンの仕組みが、自律的かつ分散的な「意思決定とインセンティブの設計」を可能にしています。
具体的には、DAOには2つの種類のトークンがあります。1つ目は、ガバナンストークンで、意思決定の設計に寄与しています。
具体的には、ガバナンストークンを持っているDAOの参加者は、DAOの意思決定について発議/投票といった形で参加できるようになっています。
また、2つ目は、ユーティリティトークンで、こちらはインセンティブの設計に寄与しています。
具体的には、DAO参加者のDAOへの貢献に応じてユーティリティトークンを発行し、ユーザーに金銭的な還元を行なっています。
以上のように、2つのトークンの仕組みによって、意思決定とインセンティブの設計を行うことで、従来の株式会社とは異なる自律的かつ分散的な組織を作っていこうというのがDAOです。
そして、この仕組みを部分的にでもWeb2.0のプラットフォームサービスに取り入れることで、Web2.0プラットフォームにおける「共助」を実現できるのではないかと考えます。
つまり、Web2.0プラットフォームにおける「共助」とは、Web3とW3b2.0の間にあるWeb2.5の世界観なのです。
ADDressにおける「共助」
それでは、最後にどのような形でWeb2.0プラットフォームにおける「共助」を実現しうるのか、ADDressを事例に考えてみます。
まず、上記の共助についての話をADDressに当てはめて言うのであれば、前提としてADDress社の公助とは独立している必要があります。つまり、その共助を作る主体は、ADDress社ではなく、ADDress社から独立したユーザー主体の組織である必要があります。
そして、次に必要なのが、意思決定とインセンティブの設計です。
簡単に言うと、ユーザーフレンドリーなADDressを作るためにユーザー自らが意思決定を行なう仕組みと、それぞれの貢献に応じて還元されるインセンティブ設計が必要です。
その際に、もちろんDAOであればトークンを使うということになるのですが、ADDressユーザーの1人1人が仮想通貨ウォレットを持って・・というのは正直なところあまり現実的ではありません。
また、前述の通りWeb3はまだまだ技術的・法律的に実現が難しいところが多いです。
そこで現実解としては、Web3的な発想と将来Web3に移管していくイメージを確かに持ちながら、ADDress内の「共助」の仕組みをWeb2.0サービスを用いながら実現していくということになるかなと思います。まさに、Web2.5という感じですね。
それがどのような意思決定とインセンティブの仕組みであるべきなのかというのは正直とても難しい問いであり、様々なDAOにおいてもまだ答えが出ていません。
しかし、かくいう我々も今まさにその探求の道を歩み始めています。具体的には、何名かのADDressユーザーで、ADDress社からは独立したユーザー主体の組織を作り(ADDress代表の佐別当にはアドバイザーとして参加してもらっています)、新しい意思決定とインセンティブの仕組み、つまりADDressにおける「共助」の形を模索しています。
詳細な内容については近いうちに発表できるとは思いますが、ユーザーが楽しみながらユーザーフレンドリーなADDressをユーザー自身の手で作り、かつそれぞれの活動に応じて還元される世界を目指しています。
ADDressはADDress社だけのものではなくユーザーのものでもあるという話は、以前のnoteでも書きました。
そして今、Web3の思想と仕組みを部分的に取り入れることで、その考えが1つの理想にとどまらず、Web2.0プラットフォームにおけるWeb2.5としての「共助」として実装できる日が目の前まで来ています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
