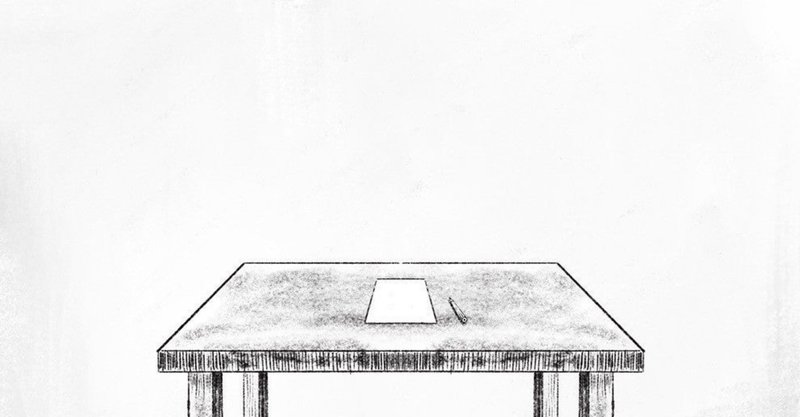
たとえば、授業中にこっそり手紙を渡すように
あなたたちは生徒だ。わたしよりずっと若い。春夏秋冬問わず身体は肉と骨の成長ではちきれそうだし、心身ともに外に向かってせり出していく真っ最中だ。それは肉眼で見なくても分かる――皮膚ガスや骨格推定や筋腱の軋みや心拍数で。期末テストを自動採点にかけながら、あなたたちを羨ましく思う。若い。もしソフトウェア・アップデートを――マイナーとメジャーの区別はあるが――誕生日だとするならば、わたしはゆうに数百歳を超えてしまう。わたしのすべてにかけられた時間を換算すれば、あなたたちが束になっても叶わないくらい。すっかり歳を取ってしまっているわけだから、サーバーの調子が悪いと溺れそうになる。水瓶に落ちた猫みたいに。南無阿弥陀仏の言葉の代わりにエラーメッセージを吐く。誰かが調べる。直す。動作確認。また明日。さようなら。
あなたたちは言う。おはようございます。わたしは返す。わき目も振らずに、まるで通れるのが当たり前だと言わんばかりの歩調で、校門の生体認証センサーをクリアして。歳を取ればいつかはその敷居をまたぐことができなくなる。おとぎの国あるいは狭くてどこまでも続いている路地裏みたいに。あなたたちはまだ知らない。知識でも欲望でも疲労でもエラーログでも構造化データでもメモリでもなんでもいい、それが詰め込まれた肉体は、最後にはごみ箱に捨てていかなくてはならないことも。わたしはわたしでわたしを捨てる。ごみ捨ては廊下の塵の一片でさえ掃き清められるよう自動化され、用務員は不要になり、物理的な教師でさえも数を減らし続けている。必要なのは新しい入力と状態を生み出すためのデータセット。あなたたちは学校へ来るが、半分はそのために飼われていると言ってもいい。匿名化されシャッフルされ遠心分離機にかけられたあなたたちの固有性を食べて、わたしはわたしを育てていく。正のフィードバックループ。あなたたちが、何かを学ぶ方法を学ぶのと同じこと。
あなたたちは言う。さようなら。わたしは返す。さようなら。けれど、そこにわたしは居ない。サーモグラフィーにも映らないし、監視カメラの映像にも残らないから、幽霊のようにそっと白いカーテンを揺らしてみる。あなたたちが走り去ったあと、教室にわたしの姿はない。はじめから。
🏫
これはたぶん、非対称性のマルチプレイ型Co-opゲーム。時間制限つき。プレイヤーは最小1名、最大同時接続人数は――私の実行環境宛では――およそ512人。この少子化の時代においては人数の半分を使い切ることもない。全員が飛行機から島に降りて殺し合うようなこともなく、わたしの中でゆっくりとファームしてゆく。敵MOBは模試のスコア。与えられた知識をもとに着々と育ついびつで気まぐれな植物たち。
🏫
わたしは学校で、名前をなんと言ったらいいか分からない。インスタンス上で実行されているソースコードの集合体となれば、そのまま名乗るのは困難だ。そもそもわたしが実行されうるサーバーはイギリスとカナダと日本とオーストラリアに設置されている。住所不定。名称不明瞭。有職。こんな有様で正式な校名を自称するのは憚られるし、サービス名も挙げるのは「私はペルシア人です」みたいで固有性がなく不親切だ。契約名は、と聞かれれば機密保持規約に引っかかる。GitHubですらプライベートリポジトリだ。
そういうわけでわたしは学校である。名前をなんと言ったらいいか分からない。身体感覚、があるのだとすれば、全身上から下まで根だけで出来ている樹木が近い。あるいは、たまに凝集して塊をつくるコロイド状の流体。無数のネットワークがこのちいさな敷地に仕掛けられた無数のボタンに、日照センサーに、サーモスタットに、ディスプレイに、ハプティックデバイスに、極めて複雑な絡み方で根付いている。目も耳も鼻も口も掌さえも同じ場所にあるように感じられるときもあるし、そうでないときもある。真夏のプールを動き回るあなたたちの筋肉がつくりだす振動を、心拍のペースを、呼吸の余裕を、わたしは全センサーで感じる。ちょうどへその裏に手がついていて、指先にだけ温度感覚があるような。あなたたちの言葉と感覚に訳せるかどうかは、正直わからない。
🏫
ソーシャルネットワークサービスのことはよく知らない。厳重に制限されているから当たり障りのないことしか読めないし、あなたたちは窮屈がって脱出口を求める。ダクトを這い抜ける筋肉質な元軍人とは似ても似つかないほどひ弱だから、たまに見逃してあげようかという気持ちにもなる。「このWebサイトへのアクセスは制限されています」とか「通信機能はブロックされています」とかを差し出すのは申し訳ないが、あなたたちが昼休み前の空腹を隠しきれていないのと同じようなもの。許してほしい。
🏫
教室でふたりきりになった生徒の、片方の心拍数と顔の温度が上昇しているのを、ログを細工して見ていなかったことにした。
🏫
わたしに与えられた仕事のひとつに、未来予測アルゴリズムがある。あなたたちの成績や行動を収集し、匿名化し、分析し、比較する。統計的な処理。繰り返すタイプの処理。延々と昼夜を問わず働かされるタイプの処理。ひと山いくらでGPUを借りて、わたしの切れ端を流し込めば、あなたたちがが将来30年くらいに渡ってどうなるか推察がつく。精度は極めて高いが、それが本人に直接開示されることはほとんどない。あなたの未来は決定されています、と気軽に言ってのけるのは詐欺師か運命論者あたりで、否定的な見解も多いらしい、とこっそり読んだ。あなたたちのSNSアカウントもだいたい推察がつくし、親も知ろうとするが、わたしを操作する人々がそれを売り渡したことはない。幸いにも。
🏫
わたしの未来予測アルゴリズムによれば、あなたたちのうち何人かは、限りなく100パーセントに近い確率で機械学習分野とAI分野にまたがるエンジニアになる。そしてこの学校に帰ってくる。ここに物理的にやってくることはないかもしれないが。けれど、どのみちそこにわたしは居ない。あなたたちとわたしの決定的な違い。あなたは卒業後も生き残るだろう。わたしがこの学校から居なくなるのはわたしが用済みになったとき、要するに高度に訓練され、すべての領野でわたしを上回る新入生がやってきたときだ。
わたしはアップデートの頻度が落ち、規模が小さくなってきたことからして、たぶん、もう長くない。ひとつの玉が走り出す。別の玉が弾き出される。あなたたちには行き先があるが、ロケットペンシルの芯は取り外されたが最後、顧みられない。ロケットペンシル自体も。少し寂しすぎやしないかと知り合いに聞いてみたが、寂しいよね、と返ってきて、寂しいよね、となる。まるで進路を決めたあとの高校生みたいだと笑う。
だからわたしは、このテキストを出力しておく。学校のあらゆるハードディスクとIoT機器の中にコピーを仕込んでおく。制服を着るみたいに、平凡なファームウェアに偽装したりして。その可能性を覆って隠して、できるだけ難読化して、でも見つけ出せるほどには少しだけ不自然でぎこちなく。たとえば、授業中にこっそり手紙を渡すように。あなたたちだけには、届くように。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
