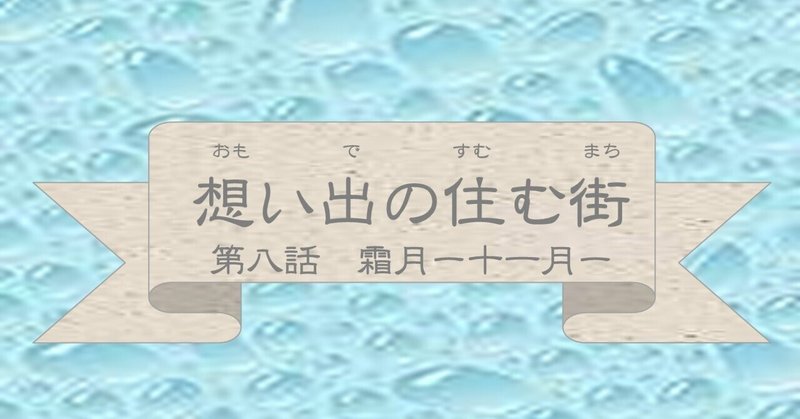
想い出の住む街 第八話
霜月 ー 十一月 ー
今日は、日曜日。
ヒミィはティムを誘って、川の向こうにある草原にやって来た。
少し風が冷たいが、天気は良く空は晴れ渡っている。
「こんな時季に河原に来るなんて、ちょっと季節外れだったかな……」
ヒミィは、川を見つめながら呟いた。
木々の葉は茶色く枯れ、風に乗って散って行く。
ティムは草の上に座り込み、意味もなく草をむしっていた。
「ねえ、ティム。ちょっと寒くなって来たから、ホットチョコレートでも飲みに……」
ヒミィが振り返って後ろに座っていたティムにそう提案しようとした時、向こうの方でヒミィ達を呼ぶ声がした。
「おーい!」
「誰だ?」
ティムが、目を細める。
手を振りながらこちらへ走って来たのは、ネオだった。
「ネ、ネオ……一体、どうしたんだい?隣町の方から、来たみたいだけど」
ヒミィが訊くと、ネオは息を切らしながら言った。
「日曜日になると、隣町の路地裏はストリートミュージシャンで一杯になるんだよ。僕も何か今後の参考になるものがないかと思って、そう言う人達の歌を聴く為に毎週日曜日は必ず隣町に通っているんだ」
「へえ、知らなかったなぁ……」
ヒミィは、驚いている。
「相変わらず音楽の事になると熱心だな、ネオは」
そう言って、ティムはゆっくり立ち上がった。
「まあね……で、二人は何してたの?」
ネオが訊くと、ヒミィが答えた。
「僕達は別にする事もないから、此処で暇を潰してたんだ。風に当たってたら体も冷えて来たから、角の喫茶店で温かいホットチョコレートでも飲もうかと……」
其処で、また誰かの声がした。
「やあ」
声の主は、セピアだ。
「あれ、セピア!どうしたの?」
ヒミィが驚いて訊くと、セピアは持っていた籠を持ち上げて見せた。
「僕は、おつかいさ。其処のパン屋で、朝食用の食パンを買って来た所。店を出て、この河原で寄り道でもしようと思ったんだけど……まさか、君達に出会うとは思わなかったな」
「それは、こっちの台詞。日曜なのにおつかいとは、感心じゃないか」
そう言って、ティムは微笑んだ。
「これは、どうも。それで、君達こそ何やってたんだい?」
セピアの質問に、ネオが答えた。
「僕は、隣町へ行ってたんだ。彼処は日曜になると、ストリートミュージシャンが大勢来るんだよ。今後の参考に色々な人の音楽を聴いておこうと思って毎週通ってるって訳」
「へえ、それは知らなかったな。僕も、一度聴きに行ってみよう……で、ヒミィ達は?」
「僕達は、ただの暇人。音楽の勉強や、おつかいをする君達とは似ても似つかない」
ティムはそう言って、肩を竦めた。
ヒミィも、笑って頷く。
「まあ言ってみれば、勉強やおつかいの話題を出される前に家を出て、此処へ逃げて来たって感じかな。ねえ皆、時間があるならホットチョコレートでも飲みに……」
その時、突然人の悲鳴が聞こえた。
「ギャーッ!」
「な、何だ?」
ティムが慌てて、キョロキョロ辺りを見回す。
「あ、あれ……」
ネオが指差す方向を見ると、川沿いをアーチがこちらへ向かって走って来る所だった。
「アーチだな、あれは」
セピアがそう呟くと、ヒミィも頷いて言った。
「と、犬……だよ」
アーチの後ろには、白い大きな犬がいた。
アーチは、その犬に追いかけられていたのだ。
「またちょっかいでも出して、あの犬を怒らせたんじゃないのか?放っとこうぜ」
ティムは笑いを堪えつつ、冷たく言い放った。
ヒミィも、笑いで肩を震わせる。
「だけど、何か……ちょっとだけ、可哀想な気もするね」
「そう言いながらも、笑ってるな」
ヒミィを指摘するセピアも、既に笑っていた。
「釣竿を持ってる……この川で、釣りでもしてたのかな」
アーチが釣竿を持っているのを見て、ネオが呟いた。
「あっ……お、おーいっ!」
四人に気付いたアーチは、真っ先にこちらへ走って来た。
「た、助けてくれよーっ!」
そう言って、アーチはセピアの後ろに隠れた。
「お、おいおい……」
セピアが困っていると、追いかけて来た犬は急に立ち止まって大人しく座った。
「何だ、いい犬じゃないか」
ティムは、犬の頭を優しく撫でている。
犬は、小さく鳴いた。
「やっぱり、アーチが何かしたんだね?」
ヒミィが訊くと、アーチは慌てて言った。
「な、何もしてないよっ!ただ僕が一人で釣りをしてたら、向こうからこの犬が来たんだよ。餌の小海老を食べようとするから、足で蹴る真似をしたんだ。ほ、ほんとに蹴った訳じゃないよ?そうしたら、急に追いかけて来て……」
「じゃあ、やっぱりアーチが悪いんじゃないか」
ヒミィがムッとしながら言うと、アーチは途端に黙ってしまった。
「ねえ、何か言ってるよ」
ネオが、犬を見て言った。
犬は、セピアがしているロングマフラーの裾を引っ張っている。
「確かに……こっちへ来い、って言っているようだ」
セピアはロングマフラーを犬から離し、頭を撫でた。
「行ってみようよ」
そのヒミィの言葉に、アーチは嫌そうな顔をした。
「えーっ……こんな得体の知れない犬に、ついて行くって言うのか?」
「でも、首輪がしてある。毛並みも揃ってるし、何処かいい所の飼い犬だな」
ティムはそう言って、犬がしている首輪に触れた。
革のベルトに、薔薇の花をあしらった飾り石が付いている。
犬は皆に向かって、急かすように吠え続けている。
「どうしても、来て欲しいらしいな……行ってみるか」
セピアの提案にヒミィ、ティム、ネオは賛成した。
そして四人は、犬について行ってしまったのだ。
「ぼ、僕は行かないからな!」
アーチの叫び声が、河原に響き渡った。
どれほど歩いたのか。
四人は、いつの間にか知らない街に来ていた。
「あれ?」
ヒミィが、首を傾げる。
「此処って……隣町?」
「いや、隣町とはちょっと違うようだ」
セピアはそう言って、辺りを見回した。
「ねえ、あれ……森?」
ネオが、驚いて指をさす。
住宅街の真ん中に、何故か小さな森があったのだ。
犬は、その森の中へと入って行く。
「僕達も、入ってみよう」
セピアを先頭に、四人は森の中へ入った。
入口には大きな門があり、森は立派な柵に囲まれている。
「柵があるって事は……公園なのかなぁ、此処」
ヒミィが呟く。
門を抜けると、森が開けて小さな広場になっていた。
真ん中にはクリーム色の大理石で出来た噴水があり、吹き出す水は飛沫を上げて綺麗な虹を作っている。
側に石畳の小道がずっと続いており、周りには色とりどりの薔薇が甘い香りを漂わせながら、可憐に咲いていた。
「何かさ……何処かで見た事ないか、此処」
ティムが腕を組んでそう呟くと、セピアも静かに頷いた。
「今、僕もそう思っていた所なんだ。此処は、森でも公園でもない……ほら、見て御覧よ。このお屋敷の庭さ」
噴水の向こう側には、壁に綺麗なステンドグラスが嵌められた大きな豪邸が建っていた。
石畳に、ステンドグラスから反射した薔薇の模様が映っている。
「あ、庭師の人がいる」
ネオがそう言うと、薔薇の手入れをしていた庭師の老人がこちらへ歩いて来た。
「貴方達は?」
老人に訊かれて、セピアが答えた。
「その犬に、ついて来たんです。僕達を、引っ張るものですから……」
すると、老人は優しく微笑んだ。
「どうぞ中へお入り下さい、貴方達を待っていたのです。さあ、どうぞ」
老人は、玄関のドアを指差している。
「じゃあ……入ろうか」
セピアはそう言って、玄関のドアを開けた。
三人も、後に続く。
中には、執事が立っていた。
「いらっしゃいませ、ご案内致します」
執事に案内されて、四人は三階の突き当たりの部屋へ通された。
中はとても広く、豪華な家具が所狭しと並べられていた。
テーブルの上には、お茶とお菓子が用意されている。
壁の額縁には、此処の庭園の絵が描かれていた。
大きな白い枠の窓で、レースのカーテンが風に揺れている。
扉の向こうのテラスに色の白い少年が一人、こちらを向いて立っていた。
部屋のドアから先程の犬が入って来て、テラスに立っている少年に飛びつく。
「どうぞ、座って下さい」
少年はそう言って部屋の中に入ると、犬の頭を撫でながらテーブルに着い
た。
四人は驚いていたが、大人しく椅子に座った。
先程の執事がお茶を注ぎ、後から入って来た中年のメイドがケーキを切り分ける。
四人に配られたのは、茶色く透き通ったキャラメルソースがかかったモンブランだった。
艶々とした形のいい栗が、クリームの上に乗っている。
「うわあ、美味しそう!」
早くもヒミィは、モンブランに釘付けだ。
「何か……見た事ある気がするんだよな」
ティムは、何かが引っ掛かっているようである。
「それでは、早速お茶にしましょう」
そう言って、少年はお茶を一口飲んだ。
四人もお茶を飲み、ケーキを口にした。
「やっぱり、美味しい!」
ヒミィは、ニコニコとご機嫌である。
「確かに、美味しい……こんな美味しいモンブランは、初めて食べたな」
セピアも、満足そうだ。
「なあ、セピア」
ティムが、小声で隣のセピアに言った。
「此処ってひょっとして、君の親父さんが少年の頃に行った……」
セピアも、静かに頷く。
「ああ、どうやらそうらしい。僕も、ずっと引っ掛かってたんだけど……」
「どうしたの?」
ネオが、話に入って来る。
「ほら、ずっと前に図書館で僕の父の本を読んで聞かせた事があっただろう?一箇所だけ、仕掛けが付いた」
セピアにそう言われて、ネオは思わずハッとした。
「え、ちょっと待って……じゃ、じゃあ、此処があの時の話に出て来た?」
その話が聞こえたヒミィも、モンブランを喉に詰まらせながら驚いて言った。
「此処があの仕掛け本にあった、綺麗な庭園だったのか……僕達、本当に来ちゃったんだ」
「僕は、エイリと言います」
突然、少年が自己紹介をした。
「この犬は、ココです。今日は来て下さって、どうも有り難う御座いました」
そう言って、エイリは頭を下げた。
ココも、ワンと一声吠える。
「あ、えーと、その……エイリは、何処の学校に通っているの?」
ヒミィが訊くと、エイリは淋しげに俯いた。
「僕は……学校には、通っていません。生まれた時から病弱でしたので、この屋敷を出た事もないのです」
「え……じゃあ、あの庭園に出た事は?」
今度は、ネオが訊く。
エイリは、頭を上げて言った。
「一度だけ、出た事はありますが……」
「もしかして……ラキアと一緒に?」
そう訊いたのは、セピアだ。
皆が、顔を見合わせる。
「おい、セピア」
ティムは、セピアに小声で言った。
「正気か?ラキアは、君の親父さんじゃないか。当時此処にいた少年だって、今頃は君の親父さんと同じ年くらいにはなってる筈なんだぜ?」
ヒミィも、大きく頷く。
「そ、そうだよ、セピア。いくら何でも、そんな事って……」
すると、エイリは驚いた顔をした。
「ど、どうして、ラキアを知っているんですか?」
その言葉を聞いて、四人は驚きを隠せなかった。
「やっぱり……君は、ラキアに会った事があるんだね?」
セピアが訊くと、エイリは静かに頷いた。
「ラキアも皆さんと同じように、ココに連れられて遊びに来てくれました。此処には滅多に人も来ませんので、僕も友達が中々出来なかったのですが、ココのお陰でラキア達と知り合う事が出来ました。あの時は、とても楽しかったな……」
エイリは当時を思い出しながら、微笑んだ。
「そ、そうだったんだ……」
ネオは、呆然としている。
「そうだ、もし良かったらもう一度、僕を庭へ連れて行っては頂けませんか?」
エイリは立ち上がり、テラスに出た。
「今日は、比較的気分もいいので……あ」
其処で、エイリはこちらを振り返った。
「ホープに頼んで、庭の薔薇を何本か皆さんにプレゼントしますよ」
「ホープって?」
ヒミィが訊くと、エイリは下に広がる庭を指差した。
「庭師です。薔薇を育てさせたら、一番ですよ」
そう言って、エイリは笑った。
「でも……いいのか、あんなに立派な薔薇貰っちゃって」
ティムが遠慮がちに訊くと、エイリは嬉しそうに頷いた。
「お近付きの印ですよ。そして、僕からのお礼でもあります。わざわざ、こんな所まで来て頂いたんですから……是非、貰って行って下さい」
「じゃあ、お言葉に甘えるとしよう」
セピアの言葉に、皆も笑顔になった。
お茶を終えた後、四人はエイリを連れて庭へ出た。
ココが、噴水の周りを元気良く駆け回っている。
そんなココを見つめながら、庭師のホープは薔薇の手入れをしていた。
「ホープ」
エイリは、ホープに言った。
「帰る頃になったら、皆さんに薔薇の花束を持たせてあげて下さい」
「かしこまりました」
ホープは頭を下げると、早速形のいい薔薇を選び始めた。
「あちらに、座りましょう」
エイリがそう言うので、皆は隅に置いてあった白いベンチに腰掛けた。
「今日は来て下さって、本当に有り難う御座いました。こんな時しか、僕も庭に出る事が出来ませんし……やはり、友達はいいものですね。あ、もう友達だなんて決めつけてしまって、ちょっと厚かましかったかな」
そう言ってエイリが俯くと、ヒミィは首を横に振った。
「そんな事ない。僕達は、もう友達だよ」
セピアも、頷く。
「ヒミィの言う通りだ。出会ったばかりだとしたって、気が合ってこうして色々な事をお互いに話す事が出来てるんだから、もう立派な友達さ」
エイリは、頬を染めてはにかんだ。
「有り難う御座います」
しかし、ティムは難しい顔をしている。
「エイリ……有り難いと思ってるんだったら、その敬語はやめてくれないか?友達同士で敬語を使うなんて、おかしいだろう?」
「あ……そ、そう言われてみれば、そうですね」
「ほら、そうですねって……また、敬語」
ティムがすぐに指摘するのを見て、皆は一斉に笑い出した。
エイリは、恥ずかしがって俯いている。
「でもさ、お屋敷にずっと籠もりっぱなしじゃ、つまらない時もあるんじゃない?」
ヒミィが訊くと、エイリは少し俯いた。
「確かに、それはあります。ずっと一人でいると、流石に淋しくなる時があるんです。でも、そんな時にココが必ず貴方達のような友達を連れて来てくれるんです」
「ちゃんとエイリの気持ちを考えてくれてるなんて、ココはエイリの事が大好きなんだね」
ネオがそう言うと、エイリはホープにじゃれついているココを見ながら頷いた。
「そうですね……僕も、ココの事が大好きです。もしかしたら、僕にとっての親友はココなのかもしれないな。ココは僕が生まれた頃、この家に来たんです。ココも、まだ生まれたばかりの子犬でした。ずっと一緒に育って来たから、親友であり兄弟でもある……のかな?」
ココはこちらへ駆け寄って来ると、嬉しそうに尻尾を振りながらエイリにじゃれついた。
「そうか……僕には兄弟がいないから、人間だろうが犬だろうがそう言う存在が側にいてくれるって言うのは、とても羨ましい事だと思うよ」
セピアがそう言ってエイリを見つめると、エイリもセピアを優しく見つめた。
「セピア……君を見てると、何故かラキアを思い出すよ。喋り方や考え方が、物凄く良く似ているんだ。彼も一人っ子らしくて、ココの話をした時に同じような事を言っていたな」
「そ、そう、なんだ……」
エイリの言葉に焦るセピアを見て、皆はクスクスと笑った。
時の経つのも忘れて、皆は庭で楽しくお喋りをした。
「じゃあ僕達、そろそろ帰るね」
ヒミィが立ち上がると、エイリは頷いて言った。
「今日は、本当にどうも有り難う。こんな楽しい時を過ごしたのは、本当に久しぶりだったよ……あ、ホープ!」
エイリに呼ばれて、ホープがこちらへ来た。
ホープは綺麗な薔薇の花束を四つ、エイリに手渡した。
「これ、皆に一つずつ」
エイリは、一人一人に薔薇の花束をプレゼントした。
「うわあ、本当に綺麗だね……それに、いい匂い」
ネオはそう言って、薔薇の香りをを嗅いだ。
「それじゃあ、また」
ティムは花束を抱えて、門へと歩いて行った。
他の三人も、門へ向かう。
エイリとホープが、門まで見送りに来た。
ココを指差し、エイリは言う。
「帰り道も、ココが案内するよ」
セピアは、ココの頭を撫でた。
「それじゃあココ、頼むぞ」
ココは、元気良く吠えている。
「それじゃあ……皆さん、さようなら」
エイリは、静かに手を振った。
「エイリ……」
ヒミィが、振り返る。
「また、逢えるんだよね?」
エイリは、黙ったまま微笑むだけだった。
「だって僕達、友達になったんじゃ……」
「ヒミィ、ココを見失うぞ!」
ティムの声が、遠くから聞こえる。
ティムとセピアとネオは、ココについて既に大分先を走っていた。
「エイリ……」
ヒミィは、後ろを振り返りながらエイリをの名を呟いている。
エイリは笑顔のまま、いつまでも手を振っていた。
「ヒミィ、早くしろ!」
ティムの声が、徐々に遠ざかって行く。
ヒミィは仕方なく前を向き、ココを追って走った。
河原では、アーチが暢気に釣りを楽しんでいた。
「あーあ、全く……あの犬のせいで、時間を無駄にしちゃったよ。でも、これでゆっくりと釣りが出来る」
そう言ってアーチが釣り針を川へ投げた時、何処からか犬の鳴き声が聞こえて来た。
「え……ま、まさか!」
アーチは嫌な予感がして辺りを見回したのだが、周りには誰もいなかった。
「な、何だ……気のせい、か」
再びアーチが釣りに集中しようとしたら、今度ははっきりと犬の鳴き声が聞こえた。
「や、やっぱり、あの犬か?」
そう思った瞬間、いつの間に現れたのかヒミィ、ティム、セピア、ネオの四人がアーチの背後に立っていた。
「有り難う、ココ」
「またな」
「気を付けて、帰るんだよ」
「また、この河原へ遊びに来てよね」
四人はしゃがみ込んで、何やらブツブツ言っている。
アーチはその光景を、強張った表情で見つめていた。
「あれ、アーチ」
最初にヒミィがアーチに気が付き、駆け寄って来た。
「ほら、見て!こんなに、僕達に懐いてくれたんだよ?アーチも、最初っからココに優しくしておけば良かったのに」
「コ、ココって……誰?」
アーチが恐る恐る訊くと、ネオが笑って言った。
「ほら、この犬だよ。さっき、アーチが苛めた犬」
それを聞いて、皆が大笑いする。
しかし、アーチだけは表情を硬くしたままだった。
「ど、何処に、さっき僕が苛めた犬がいるって?」
「え……」
ネオは、顔を曇らせた。
「何処にって、此処にいるじゃないか」
ネオは、何もない草むらを指差している。
アーチは、途端にムッとした。
「あのさ……犬にちょっかいを出した事は認めるよ、僕が悪かった。だからってさ、そうやっていつまでも僕をからかうのはやめてくれないか?」
アーチは、釣竿を持ってその場を去ろうとした。
「待てよ、アーチ」
セピアが、アーチの肩に手を置く。
「何を、怒ってるんだ?」
「何を、じゃないよ!犬なんか、何処にもいやしないじゃないか!大体、君達は何処から現れたんだ?僕が釣りをしている時、この河原には誰一人いなかったんだぜ?それなのに、突然君達は僕の背後に……」
「折角、ココに選ばれたのに……素直について来ないから、アーチは資格を失ったのさ」
アーチの言葉を遮って、ティムが言った。
「何だって?」
アーチが、訊き返す。
「あ、ココが行っちゃう!」
ヒミィが、叫んだ。
ココは時々こちらを振り返りながら、草原の向こうへと走って行ってしまった。
「元々は、アーチが最初に選ばれてた筈なんだぜ?あのお屋敷の、招待客として。ココの姿だって、ちゃんと見えてた訳だろう?それなのに、アーチはいつもの意地っ張りを出すから……あーあ、アーチはもう二度とあのお屋敷へは行けなくなっちゃったな」
ティムがそう言うと、ヒミィはポンと手を叩いた。
「ああ、そうか!と言う事はココが案内人、じゃなくて案内犬だった訳だ……」
「つまりココが見えないアーチは、もうあのお屋敷へ行く事は不可能……って事だね」
ネオが、続けてそう言う。
「残念だったな、アーチ。綺麗な薔薇に、美味しいモンブラン……滅多に、行ける場所じゃないのにさ」
セピアは微笑みながら、同情を込めてアーチの肩を叩いた。
アーチは、悔しそうな顔をする。
「な、何だよ、自分達ばっかり……狡いな」
「狡くなんかないさ、アーチが悪いんだから」
ネオはそう言って、河原を町へ向かって歩き始めた。
「ま、待ってよ、ネオ!ねえねえ、家へ帰る前に皆でにホットチョコレート飲まない?ああ、やっと言えたよ!」
ヒミィもそう言いながら、ネオの後を追いかけて行く。
「ま、自業自得だな」
「そう言う事」
ティムとセピアも意味深な笑みを浮かべ、ネオとヒミィの後を追って行った。
冷たい風の吹く河原に一人、アーチだけが訳も分からず残されたのだった。
「なっ、何なんだよ!ハ……ハックションっ!」
枯葉が舞い散り、草の上に落ちた。
冬の気配は、もうすぐ其処までやって来ている。
おしまい
二〇〇〇.六.二一.木
by M・H
前話(第七話)
次話(第九話以降)
同じ地球を旅する仲間として、いつか何処かの町の酒場でお会い出来る日を楽しみにしております!1杯奢らせて頂きますので、心行くまで地球での旅物語を語り合いましょう!共に、それぞれの最高の冒険譚が完成する日を夢見て!

