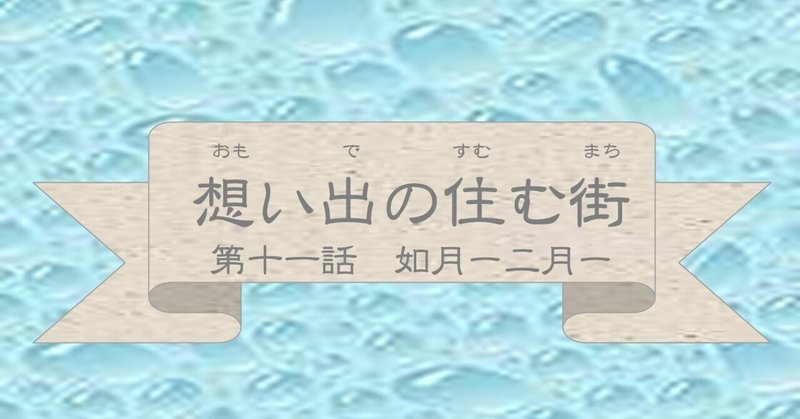
想い出の住む街 第十一話
如月 ー 二月 ー
今月末、卒業式が行われる。
ティムの二つ上の兄、ティセは此処を卒業して上の学校へ進学する事が決まっている。
進学の決まっている卒業生は今月に入ってからあまり授業もなく、学校へ来ない事が多いので校内は心無しか静かだ。
放課後、誰もいなくなった教室にいつも通り五人だけが残っている。
「でも、最上級生がいないってのは気楽でいいよ」
とは、アーチの意見である。
「毎朝律儀に僕を見送ってくれる兄貴が、腹立たしくて仕方がない」
これは、ティムの意見だ。
「えーっ、ティセが?こう言っちゃあ何だけど、いい所もあるんだね」
ヒミィが感心していると、ティムは途端に嫌そうな顔をした。
「どうしてそう、すぐ話を鵜呑みにするんだ……裏を返せば、僕に対しての厭味だとすぐに分かるじゃないか。兄貴の奴、わざと早起きして毎朝毎朝家の前まで出て、手を振ってくれるんだ。僕が出掛けた途端、一日中暇なものだから好き勝手やってるに決まってるのさ。全く、頭に来る」
セピアとネオは、声を押し殺して笑っている。
「そ、そうだよね、ティセだもんね……」
何故か、ヒミィは妙に納得してしまった。
アーチは、溜息をつきながら言う。
「とにもかくにも面倒なのは、各学年ごとの出し物だよ。大体あんなもの、卒業生が喜んで見てくれているとでも思っているのか、先生達は……」
「少なくとも、兄貴は興味ないと言っている」
「やる前から卒業生当人にそう言われちゃうと、こっちもやる気を失うね……」
ティムの言葉を聞いて、ネオは苦笑いしている。
ヒミィ達の学年は全員が出来る楽器を練習し、オーケストラ並みの演奏を披露する事になっている。
何と言っても最大の見せ場は、ネオのピアノソロだった。
「そっか、ネオはソロパートがあるんだよね」
ヒミィがそう言うと、ティムは申し訳なさそうに肩を竦めた。
「悪いな、ネオ。兄貴も別に、そんなつもりじゃ……」
ネオは首を横に振り、静かに微笑んだ。
「いいんだよ、気にしてないから。僕は僕なりに、精一杯やるつもりさ。今月の頭から、アディスに先生になってもらって練習を続けているんだ」
「アディスって……ひょっとして、あのピアノ奏者か?」
セピアは、驚いて目を丸くしている。
そう、アディスとはいつか森で見つけた紺碧のピアノを弾いていたあの少年である。
ネオは、頷いて言った。
「たまたま放課後、誰もいない時に音楽室に入ると彼がいる時があるんだ。勿論、歌い手の少年フィリエも一緒だよ。まあ、本当に運がいい時じゃないと出会えないけどね……」
「神出鬼没だからな、彼らも」
セピアは、彼らを思い出しながら微笑んだ。
「でもただでさえネオはピアノが上手だって言うのに、あのアディスに稽古をつけてもらっているなら益々上手になっちゃうね……プロの道も、遠くないかもしれないよ!」
期待に目を輝かすヒミィを見て、ネオは照れ笑いした。
その時、突然アーチがガタンと音を立てて立ち上がった。
「うわっ、びっくりした!」
「どうした、アーチ」
ティムが訊く。
アーチは、教室のドアを指差した。
「サウバと、ツイネだ……」
「本当だ!どうしたんだい、二人とも!」
ヒミィは、慌てて教室のドアへ駆け寄った。
其処には、以前五人で忍び込んだ幽霊屋敷に置き去りにされた二匹の猫が、大人しく座っていたのだ。
サウバが黒猫、ツイネが白猫である。
「やあ、五人ともまだ残っていたんですか」
名付け親のユマが、教室に入って来た。
二匹を見つけたあの夏以来、五人はユマと共に餌代を出し合っていた。
しかし、ようやくユマの両親からお許しが出たとの事で、先月の年明けから二匹は晴れてユマの猫となったのである。
「やあ、ユマ。二匹とも、元気でやっているみたいだね」
ヒミィが二匹を撫でながら言うと、ユマも大きく頷いた。
「元気過ぎて、困るくらいです。だからこうして、犬でもないのに散歩までしてやってるんです」
「と言うか、学校に動物を連れ込んでいいのか?」
アーチが顔を顰めると、ユマはクスッと笑った。
「実は、夜中も鍵の開いている窓を見つけて、二匹と一緒に学校に忍び込んでます」
「やれやれ、全く。悪い奴だな、ユマも……あの幽霊屋敷の時の事といい、忍び癖があるんじゃないのか?」
ティムがニヤリと笑うとユマも意味あり気に微笑み、黙ったまま肩を竦めて見せた。
「ところで、ユマの学年はもう全体練習始まってる?」
ネオが訊くと、ユマは肩を竦めた。
「卒業式の、出し物でしょう?まあ、有志だけ屋上でやってますよ。他の学年も、校庭の隅や渡り廊下で頑張ってるみたいですね……あくまでも有志、ですけど」
「じゃあ僕達の学年、遅れてるね」
ヒミィがそう言うと、セピアも壁に掛かっているカレンダーを見て頷いた。
「確かに。何だかんだ言って、もうあと三週間しかないからな……まあ、この学年だって有志は練習しているようだけど」
「あ、そうだ」
ユマは廊下を見回し、ドアを閉めると小声で言った。
「湖の周りからその脇に広がる森にかけて、何か変なモノが出るって噂聞いた事あります?」
「何だよ、また幽霊か?」
ティムが呆れたように言うと、ユマは首を横に振った。
「幽霊って訳でも、なさそうですよ。猿か猪、あるいは熊の類かもしれないって、森に入った猟師が証言してるんです」
「それ、危険じゃない?そんな大きい動物が、街にまで入って来たら大変だよ!」
ヒミィが驚いて言うと、アーチは訝しげな表情をした。
「確かに自分の目で見たのかい、その猟師……今まであの森に熊が出たなんて話、聞いた事もないよ」
「そうだね。田舎の方ならそう言う話もよく聞くけど、この街じゃあ滅多にない事だよね」
ネオも、半信半疑のようだ。
ユマは、笑って言う。
「だから、それを確かめに行ってみたらどうでしょうって、勧めてるんじゃないですか」
「何だって?」
アーチは、目を丸くしている。
「皆さん得意じゃないですか、そう言う謎を解明するのが」
「ユマに、言われたくはないな……」
ティムは、不満そうにユマを見つめている。
「まあ、そう言わないで下さいよ。僕はそれでもこの二匹の世話に追われているお陰で、少しは夜遊びの回数が減って来たんですから」
「あ、そ……」
肩を竦める、ティム。
「じゃあまあ、そう言う事で……行くぞ、サウバ、ツイネ」
ユマに呼ばれたサウバとツイネは、二匹揃って鳴き声を上げながら、ユマの後をヒタヒタとついて行った。
「何だよ、あれ……」
アーチは、呆然としながらユマの後ろ姿を見送っている。
「どうするんだ、隊長?」
ティムはセピアの肩に手を置き、顔を覗き込んだ。
ハッとしたセピアが、目を丸くしながらティムを見つめる。
「隊長って……僕の事か?」
「セピア以外、誰がいるってのさ」
当たり前のような顔をする、ティム。
ヒミィも、嬉しそうに言った。
「わあ、隊長かぁ!いいね、それ!確かにセピアは、僕達の隊長だよ。ねえセピア、勿論森へ行くんだろう?」
セピアは、腕を組んで考え込む。
「いいけど……熊となると、少し危険じゃないか?」
「熊じゃないかもしれないだろう?」
ティムが、クスッと笑う。
「それ以外の何か、って事?な、何だろう……」
ネオも、考え込む。
「それを、確かめに行くんじゃないか。ほらセピア、結論出せよ」
ティムに急かされ、セピアは大きく溜息をついた。
「何だか……すっかり僕より皆の方が、探険癖がついちゃったようだな……よし、これから出掛けようか」
『賛成!』
ヒミィ、ティム、ネオは揃って賛成した。
「本気で、言ってるのか?」
アーチは、酷く驚いている。
「森に入るなら、夜よりまだ明るい今の方がいいだろう。すぐに行こう」
セピアの意見に頷き、四人は鞄を持って教室を出た。
「もう……待ってくれよ!」
アーチも、慌てて後を追った。
五人は、湖の脇に広がる森に立っていた。
「中、やっぱり暗いね」
ヒミィの心臓は、ドキドキ高鳴っている。
「そうだね。外は、まだ明るいんだが……取り敢えず、入ってみよう。いざと言う時の為に、携帯ランプは持って来ているから大丈夫だ」
「学校に、何を持って来てるんだよ……」
セピアの台詞に、呆れるティム。
「念の為、木に傷を付けて行った方が良さそうだ」
ポケットからナイフを取り出したセピアは、奥へ進みながら木に傷を付けて行く。
「いきなりその動物に襲われたら、どうするつもりさ!無茶なんだよ、こんな事……」
アーチが文句をつけると、セピアはこちらを振り返った。
「探険に、多少の危険はつきものだよ」
「そう言う問題か!」
全くもって、アーチは納得していない。
しかし、結局五人は奥へ奥へと入って行った。
暫く無言で歩いていたが、一向にその動物が現れる気配はなかった。
「ねえ、もうどのくらい歩いた?」
ヒミィが、ようやく口を開く。
セピアも、時計を見ながら溜息をついた。
「もうすぐ、日が暮れるな……これ以上は、危険だ。今日は諦めて、もう戻ろう」
「ユマに、担がれたのさ。僕は最初から怪しいと思っていたよ、あんな噂」
疲れのせいもあってか、アーチは御機嫌斜めだ。
セピアが、笑ってアーチの背中をポンと叩く。
「まあまあ、アーチ……さあ、帰り道はこっちだ」
仕方なく五人は元の道を戻り、再び湖に出た。
既に空は薄暗く、一番星が光っている。
「どうする?明日も、探すかい?」
セピアが、問いかける。
「僕は、断固反対だ!」
アーチは、即答した。
他の皆が考え込んでいたその時、ネオが叫んだ。
「ね、ねえ、あれ!」
ネオは、湖の真ん中を指差している。
皆は、一斉に湖の方を見た。
「あ、あれは、まさか……」
セピアが、唖然としながら呟く。
湖の上を、白く大きなモノが滑るように歩いていた。
「あ、あれ、あの時の、ペ、ペ、ペ、ペ……」
「ペガサス、だな」
焦るアーチの言葉を、ティムが代わりに言う。
湖の上を歩いていたのは、まさに学校の九月祭で劇に出す筈だったあのペガサスだった。
「た、確かあのペガサス、ハリボテだった筈なのに何故か本物になっていて、僕達が目を離した隙に逃げて行っちゃったんだよね……」
ヒミィが思い出しながら言うと、ネオも何度も頷いた。
「演劇部と、裏方で参加していた美術部が協力して校内は勿論、近所一帯全て探し回ったのに結局見つからなかったんだよ」
「そ、そんなバカな話、ある訳ないだろう?だって……だって、そんな」
否定しながらも、アーチはペガサスから目を逸らす事が出来ない。
大きな背中の翼を羽ばたかせながら、湖の上を歩いていたペガサスは、徐々にこちらへ近付いて来た。
「こ、こっちへ来るよ!」
驚く、ヒミィ。
大きく嘶いたペガサスは元気良く駆けて来て、ヒミィ達の目の前で止まった。
そして、何とネオの頬に顔を摺り寄せて来たのだ。
「ぼ、僕の事……覚えてるの?」
ネオが訊くと、ペガサスは再び嘶いた。
「凄い!凄いよ!」
ヒミィがペガサスの首を撫でると、ペガサスはヒミィにも擦り寄った。
「信じられない……」
アーチは、ただ呆然としている。
ティムも、ペガサスを見ながら呟いた。
「こんな事って、あるんだな……あれから何処に行ったかと思ったら、まさかこんな所に隠れていたなんて」
「まあ此処は街の中でも自然が多い地帯だし、隠れるにはうってつけの場所だ。ただユマも言っていたが、猟師が出入りしているのは気に掛かるな……」
難しい顔で、セピアは腕を組んだ。
ヒミィも、心配そうに言う。
「確かに、そうだね。猟師さんも、何か大きな動物がいるって言う事しか今は分かってないみたいだから、これがペガサスだと知れたら大変な事になっちゃうよ」
「ね、ねえ、これ見てよ!」
突然、ネオが叫んだ。
皆が、ペガサスに近寄る。
「あっ!ひ、酷い……」
ヒミィが、顔を顰める。
何と、ペガサスの羽には幾つか銃弾の痕があったのだ。
「そうか……このせいで、遠くまで逃げられなくなってしまったんだな」
ティムが呟く。
「まあ、そうだろうね。穴が開いてちゃ、こんな羽は何の役にも立たないさ」
と、アーチ。
「でも、血が出ていない。あれ、この銃弾の痕……や、やっぱりこれ、ハリボテ、なの?」
ネオは傷口を見ながら、首を傾げている。
傷口は、確かに生々しい血や肉ではなく木枠や紙で構成されていた。
セピアは、目を丸くする。
「み、見た目は生きているようなのに、結局はハリボテのままだったと言う事か?」
「え、そうなの?」
拍子抜けしたかのように、ポカンとするヒミィ。
「それならそれで、都合がいいじゃないか」
「ど、どう言う事?」
ティムに訊き返す、ネオ。
傷口に触れながら、ティムは言う。
「美術部が作ったんだろ、これ。だったら此処に美術部を連れて来て、直してもらえばいい。羽が治れば、このペガサスだって再び遠くへ飛んで行けるだろう」
「だけど、美術部に居場所を知られたら処分されちゃうよ!」
ヒミィはそう言ったが、ティムは首を横に振った。
「今更、処分も何もないだろう。キットに訳を話して、今月卒業する美術部の先輩達を集めてもらうんだ。一番ペガサスの行方を気にしているのは、彼らだと思うから」
「そうだな……その後どうするかは、それから考えるしかない」
セピアもその意見に同意し、皆もそれに従う事にした。
翌日の、放課後。
ヒミィ達のクラスメイトで演劇部裏方のキットに昨日の事を話し、今月卒業する美術部長のシルル、副部長のロキ、そして部員のレノとライヤを湖まで連れて来てもらった。
「どうでもいいけど、こんな所に僕達を呼び出して何をする気なんだ?」
ロキは、キョロキョロと辺りを見回している。
「何でも、ハリボテを修復する道具を持参してくれって事だったけど……それが、この湖と何か関係があるのかな?キット、どうなんだい?」
「そ、それはですね……」
シルルに訊かれ、キットは焦りながらセピアに耳打ちした。
「なあ、セピア。本当に、此処にいるのか?担いでいるんじゃないだろうな……」
「心配ないさ、キット。もうちょっと、待ってくれないか」
そう言って、セピアは空を見上げた。
「なあ、僕……これから習い事があるんだけど、まだ?」
レノは、早くもそわそわし始めている。
「でも、久しぶりに湖に来たなぁ……僕、進学先が他の街だから、もう此処へ来る事はないかもしれないなぁ」
ライヤは、感慨深げに湖を見つめている。
やがて空は薄暗くなり、一番星が光り始めた。
「あっ、来たよ!」
ネオが叫ぶ。
皆が湖の方を見ると、森の奥からペガサスが走って来た。
「え……な、何、あれ」
レノが、目を擦る。
「ちょっ、あ、あれ、僕達が作ったペガサスじゃないか?」
「えぇ?嘘だろ?だって……えぇ?」
シルルの意見を否定しつつも、ロキはまさかと湖へ近寄る。
ペガサスが近付いて来るにつれ、ライヤは笑顔になって言った。
「た、確かに、僕達のペガサスだよ!ほら、あの耳の所が少し欠けてる。あれ、僕が壁にぶつけてへこませちゃったのを、そのままにしておいたんだもん」
「そのままにしておくなよ、ライヤ……」
呆れて溜息をつく、ロキ。
開いた口の塞がらないキットを見て、五人は思わず笑ってしまった。
ようやく辿り着いたペガサスは大きく嘶き、シルルに顔を寄せた。
「僕達の事、分かるのかい?」
「ごめんね、やっぱり耳をちゃんと直してやれば良かったなぁ……」
ライヤは、嬉しそうにペガサスの首を撫でている。
「信じられないな……」
レノは、目を丸くしたまま動く事が出来ない。
「君達が見せたかったものは、これか」
ロキに訊かれ、セピアは大きく頷いた。
「実は僕達、九月祭の日に学校を逃げ出したペガサスに、偶然出くわしていたんです」
「何だって?」
シルルが、驚いた顔でこちらを見る。
「ペガサスは、美術部が心を込めて作った力作だったんですよね?でも演劇に使用した後は、処分するしかないって話を聞いて……僕達も、物凄く残念に思っていたんです」
ヒミィが淋しげにそう話すと、ライヤもペガサスを撫でながら言った。
「確かに、そうだよ……散々皆で話し合ったんだけど、結局多数決で決まっちゃってねぇ。僕達にとっては最後の作品だったから、出来れば処分は避けたかったんだけど」
「だから僕達、こう思ったんです。皆さんが込めた心や魂が、そのままペガサスに乗り移ったんじゃないかって。そして、処分されたくないと思う気持ちがペガサスをこんな風に、生きているかのように動かしたんじゃないかって……」
ネオの話を聞きながら、レノはフッと笑った。
「普通なら有り得ない話だけど、ハリボテだった筈のペガサスがこうして動いているのを見ると、案外そうなのかもしれないなって、素直に信じられる気がするよ……」
「ましてや、僕達の強い気持ちがコイツを動かしてるんだとしたら、尚更だな……」
そう言って、ロキも微笑んだ。
「それで……これ、見て下さい」
ティムが、ペガサスの羽を指差す。
「こ、これは……何て、酷い」
羽に幾つも残された銃弾の痕を見て、シルルは呆然とした。
「最近、湖の周りや森の中で大きな動物が出たようだと、猟師の間で噂になっています。詳しくペガサスだとまでは知られていないようですが、誰か撃った猟師がいたんでしょうね。ペガサスもこれ以上遠くへ逃げたくても、羽が使えず立ち往生していたようです」
ティムの話を聞きながら、レノは羽に触れてみた。
「傷口部分は、紙だな……ハハハ、何か拍子抜けした。本物みたいに見えるのに、やっぱり中身は僕達が作ったままのハリボテだ」
ライヤは、修復道具を取り出した。
「だから、これがいるって訳だったのかぁ……ねえ、早速直そうよ。キット、手伝って」
「は、はい!」
キットも含め、五人は早速羽の修復に取り掛かった。
空は大分暗く、星の数も増えて来た。
ヒミィ達は、セピアの携帯ランプで修復部分を照らしてあげた。
そしてようやく羽が完全に治った時、ペガサスが嬉しそうに嘶いた。
「お礼、言ってるのかな」
ヒミィがそう言うと、シルルはクスッと微笑んだ。
「そうだと、嬉しいけどね」
「それでどうするんです、このペガサス」
アーチが、訊いた。
四人は、顔を見合わせている。
「まさか、処分する……なんて事、言いませんよねえ?」
再びアーチに訊かれ、四人は同時に微笑んだ。
「まさか!そんな事、しないよ……僕達の大事な子供も同然の作品だもの、再会出来た事も何か運命を感じるし」
そう言って、シルルはペガサスをいとおしそうに撫でた。
「卒業前に、ペガサスを見つける事が出来て良かったよ。君達、本当に有り難う」
ライヤは、ヒミィ達一人一人に握手をした。
「確かに、そうだな……きっとコイツの事が気掛かりで、安心して卒業を迎える事が出来なかっただろうから」
ロキは、優しい眼差しをペガサスに向けている。
「それじゃあ、全員一致で彼を大空の彼方へ放ってあげると致しますか?」
レノの意見に、皆は同時に頷いた。
するとペガサスは再び嘶き、片方の羽を広げてこちらへ差し出して来た。
「え……な、何?」
戸惑うシルル。
ペガサスは、自分の羽をシルルに押し付けて来る。
「もしかして……羽根を一枚ずつ、記念に持って行ってって言ってるんじゃないですか?」
ヒミィがそう言うと、ペガサスは肯定するように嘶いた。
「そんな……いいのかい?」
シルルが訊くと、ペガサスは黙って顔を寄せて来た。
「そ、それじゃあ、美術部卒業生の僕達四人と……演劇部卒業生は?」
キットが、思い出しながら答える。
「部長のハリクと、副部長のティセだけです」
「合計六枚、持って行くからね?」
シルルは優しくペガサスの首を撫でながら、羽根を六枚そっと抜き取った。
ペガサスは満足したように嘶くと、此処にいる十人全員に頬を摺り寄せた。
そして湖の上を滑るように駆け出すと大きな翼を広げ、月へ向かって飛び立った。
「さようなら!」
「元気でやれよ!」
「もう、誰にも捕まらないようにね!」
「ありがとう!」
皆は、空に向かって手を振った。
そして、ペガサスの姿が見えなくなるまでいつまでもいつまでも見送った。
卒業式、当日。
長い長い校長の話や、卒業証書授与の後に行われた各学年ごとの出し物は見事成功し、ネオのピアノソロは特に盛大な拍手を受けた。
顔を真っ赤にしながらお辞儀をするネオを見て、ヒミィは自分の事のように誇らしく思った。
式が終わり、生徒達は全員放課となった。
だが卒業生は勿論、在校生達も正門前広場で名残惜しげにお喋りを続けている。
「何だか、信じられないんだけど……そもそも製作時にシルルからも聞いていたからさ、この羽根はペガサスに使うギリギリの枚数分しか注文してないって。それが此処にあるって事は、やっぱり本当にあのペガサスは見つかった……って事なんだよな」
先々週に羽根を渡された時の事を思い出しながら、演劇部長のハリクは本当に驚いていた。
「まあ正直、この羽根が一番の卒業プレゼントだったかもしれないな」
ティセは、ペガサスの羽根を気障に胸に飾っていた。
「大体今日の卒業式だって、在校生の出し物ほど退屈なものは……」
其処まで言って、ティセは慌ててコホンと咳払いした。
そして、不器用にネオの頭をポンポンと撫でた。
「ま、まあ、その……正直、ネオのあのピアノソロは今まで見て来た在校生の出し物の中で、一番良かった……よな」
それを聞いて思わず顔を真っ赤にしたネオと、つられて珍しく頬を染めたティセを見て、皆は同時に笑った。
おしまい
二〇〇五.四.二二.金
by M・H
前話(第十話)
次話(第十二話以降)
同じ地球を旅する仲間として、いつか何処かの町の酒場でお会い出来る日を楽しみにしております!1杯奢らせて頂きますので、心行くまで地球での旅物語を語り合いましょう!共に、それぞれの最高の冒険譚が完成する日を夢見て!

