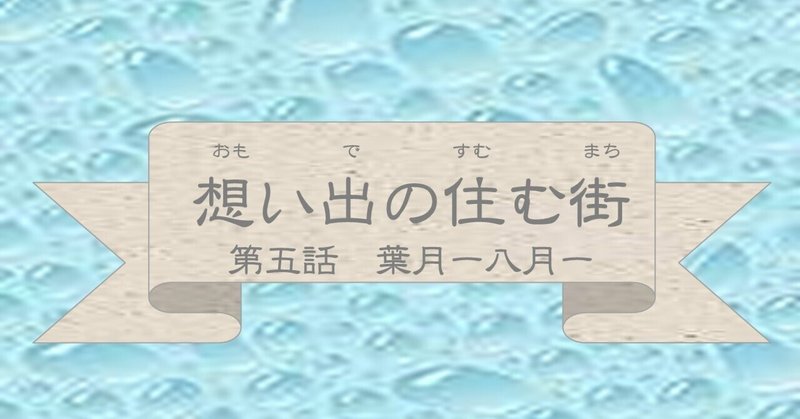
想い出の住む街 第五話
葉月 ー 八月 ー
それは、ランチの時間だった。
「幽霊屋敷、知ってるか?」
食堂のテーブルで、一人の生徒がパンを食べながら小さな声で言った。
それを聞いたもう一人の生徒は、ミルクを飲み干し大きく頷く。
「ああ、聞いた事あるよ。公園の近くの、ってヤツだろ?」
「確か林を抜けた所にある空き地の真ん中に、ひっそりと建ってんだよな。それで、誰も住んでいない筈なのに夜になると恐ろしい爪音と、呻き声が聞こえるんだ」
更にもう一人の生徒もわざと低い声でそう言い、メインのハンバーグを口に運んだ。
「聞いたかい、今の」
隣のテーブルから聞こえて来たその会話に、敏感に反応したのは勿論ヒミィだ。
「どうやら有名らしいな、あの幽霊屋敷は」
セピアの台詞を聞いて、ティムは驚いた。
「何だ、知ってるのか?」
「まあね」
セピアは、クスッと笑う。
「相当古いが、大きなお屋敷なんだ。昔は、かなりの金持ち一家が住んでいたらしい。しかし、大分前から彼処は空き家になっている」
「その金持ち一家は、引っ越しちゃったの?」
ヒミィが訊くと、セピアは首を横に振った。
「いや……いなくなったのさ」
「い、いなくなったって……」
ヒミィの表情が、強張る。
「どう言う事だよ」
ティムが訊くと、セピアはミルクを飲み干して言った。
「一家で、消えてしまったんだよ。近所の人間は、手分けして一家の行方を追った。だが、手掛かりは全くなし。皆が諦めかけたその数日後、近くの海辺の崖の下から娘さんの赤い靴が見つかった。それ以来、捜索を打ち切ったそうだ」
「ね、ねえ、それって……」
ヒミィが言おうとした事を察して、セピアは肩を竦めた。
「さあね……ヒミィが思っているような事が、起きたかどうかは分からない」
「でも……」
ヒミィは反論しようとしたが、セピアは首を横に振った。
「だって靴が見つかっただけじゃ、はっきりとした証拠にはならないだろう?」
「そ、それは、そうだけど……」
ヒミィが、口ごもる。
「ただね、連日の嵐で崖下の波の高さは半端じゃなかったんだよ。それで、皆は捜すのをやめたのさ……住人のいなくなった屋敷は、放って置くには勿体無かった。だから、やがて屋敷は売りに出された」
「売れたのか?」
ティムが訊くと、セピアは少し笑った。
「それが、売れなかったのさ。不思議だろう?前の住人が消息を絶った事もあって低価格だったし、屋敷自体は素晴らしいモノだったから、こんないい物件はない筈だった。買う人が、その事さえ知らなければね。でもこの頃かららしいんだ、奇妙な事が起こり始めたのは……」
ヒミィとティムは、同時に息を飲んだ。
「誰もいない筈の屋敷から、爪音やら呻き声やらが聞こえて来るようになった……」
突然低くなったセピアの声に、ヒミィは肩を震わせている。
「それに気付き始めた隣人が中に入って様子を見てみたが、勿論誰もいない。だけど、必ず決まった時間に聞こえるんだ。段々と気味が悪くなって来た近所の人達は、遠くへ引っ越し始めた。そして、空き家になったその人達の家は次々と取り壊された」
「だ、だから、空き地の真ん中にその家だけが今も建ってるのか……」
セピアの話を聞きながら、ヒミィが頷く。
「けどさ、そんな不気味な屋敷なんだったら他の家同様、さっさと取り壊しちゃえば良かったじゃないか」
ティムはそう言ったが、セピアは首を横に振る。
「それが、そうも行かなかったんだよ。やっぱり、住人の許可がないと……それにそんな不気味な家取り壊して、後から自分の身に何か起きても嫌だろう?皆、気味悪がって屋敷に近寄ろうともしなかったのさ」
「ふーん……なるほどね」
気のない返事をする、ティム。
「それっきり、あの家は今もあのままなんだ。相変わらず決まった時間に、爪音と呻き声を響かせてね」
ヒミィは、すっかり黙り込んでしまっている。
すると、横で声がした。
「で、行くのか?その屋敷に」
三人は、一斉に声のする方を見た。
声の主は、アーチだった。
いつの間にか同じテーブルで、ランチを食べている。
アーチの向かいには、勿論ネオも座っていた。
「いつの間に、座ったのさ。全然、気付かなかったよ」
ヒミィが驚いていると、ネオはクスッと微笑んだ。
「そうだろうね。だって二人とも夢中になって、セピアの話に耳を傾けていたから」
「で、僕等も一部始終聞かせてもらったけど……勿論行くんだろうな、その屋敷へ」
アーチの言葉に、三人は顔を見合わせた。
「行ってどうするのさ。どうせそれが聞こえる時間に屋敷に忍び込んだって、誰もいないんだぜ?何の解決にもならないんじゃ、意味ないだろ?」
確かに、ティムの言う通りだ。
彼等が行った所で誰もいないのでは、意味がない。
しかし、アーチは焼き立てのバターロールを口に放り込んで言った。
「其処を、何とか解決に導くのさ」
それを聞いて、セピアは目を丸くした。
「妙にやる気だな、アーチ。まあ父もこの屋敷の事はよく知っているらしいし、僕としても其処まで言われては行かない訳にも……」
「セピアがそう言うなら、僕も参加するよ」
そう言ったのは、ヒミィだ。
「えーっ、ヒミィも?」
アーチは、皮肉っぽく驚いた。
「ねえ、今日の夜にでも行ってみようよ。どうせ、明日は休みじゃないか」
「ヒミィ、本気か?幽霊屋敷に行くんだぜ?それに、夜遅いんだ。パパやママに、何て言い訳して家を出て来るつもりなんだ?」
ティムにそう指摘されて、ヒミィは忘れていたと言わんばかりに口を閉ざした。
しかし、セピアは言う。
「夜遅くに家を出るのが困難なら、僕の家に泊まりに行くと言う事にすればいい。実際空いている部屋はあるし、ヒミィの言う通り明日は休みだから僕の両親もいいと言ってくれる筈だ」
「本当に?やったーっ!じゃあ僕、今日帰ったら早速支度するよ!憧れの、セピアのパパにも会えるんだね?」
ヒミィは途端に元気になり、カップに被せて焼いてあったパイ生地をスプーンでサクサクと壊しながら、中に入った熱々のクリーミーなクラムチャウダーを食べた。
「あの……僕も、セピアの家に泊まってみたいな」
そう呟いたのは、ネオだ。
セピアは、微笑んで言った。
「勿論、大歓迎だよ。で、ティムとアーチは……どうする?何なら、まとめてお世話するよ。泊まるとなれば帰る必要がないんだから、時間はたっぷり出来る。あの屋敷を探険するには、持って来いだけどね」
ティムとアーチは顔を見合わせ迷っていたが、やがて意を決したように頷いた。
「参加させてもらうよ」
最初に答えたのは、ティムだ。
「遅ればせながら、僕も……言っておくけど、これを提案したのは僕だからね。やっぱり僕がいなきゃ、始まらないと思うし」
何だかんだ言いながら、アーチも泊まりたい様子だ。
「決まりだな。じゃあ今日の放課後、支度が出来次第屋敷近くの公園に集合しよう」
そう言って、セピアはデザートのパンプキンプディングを一口すくって食べた。
放課後。
五人は、屋敷近くの公園に集まった。
空は、もう薄暗くなって来ている。
「で、どうするんだ?大体、屋敷の鍵は開いているのか?」
ティムが、訊く。
セピアは、頷いて言った。
「ああ、鍵は開いている。それは、既に確認済みだ。もうちょっと暗くなったら、人がいないのを見計らって中に入ってみよう」
それからの五人は公園で時間を潰し、暗くなるのを待った。
やがて空は橙色に染まり、見る見る内に薄暗くなって一番星が輝き始めた。
元々屋敷の噂のせいで、明るい時分から誰も近寄らないような道だったので、すっかり人の気配はなくなっている。
「じゃあ、そろそろ行きますか」
頃合いを見計らって、セピアが言った。
四人が、思わず顔を見合わせる。
何処となく、互いに不安の色が見えた。
そんな四人を見ながら、セピアは黙って歩き出した。
公園を出ると、すぐ林がある。
薄暗い林の中は、本当に不気味だった。
時々風で揺れて音を立てる木々のざわめきに、ヒミィは体を震わせた。
「ぼ、僕、何だか……もう、怖くなって来たよ」
それを聞いたアーチが、大笑いする。
「だから、ティムが念を押して言っただろう?幽霊屋敷に行くんだよ、って。大体臆病ヒミィが僕達について来ようなんて考える事自体、間違っているのさ。ま、この林に入れたってだけでも、拍手ものだけどね」
ヒミィは、途端に頬を膨らませた。
「酷いなぁ、アーチ!何も、其処まで言う事ないだろう?僕だって興味あったんだもん、しょうがないじゃないか!それに……もう怖くなんかなくなったよ、アーチのお陰でね!今は恐怖よりも、アーチに対する怒りの方が大きいや!」
二人のやり取りを見ながら、皆は一斉に笑い出した。
今度は、アーチが一人で頬を膨らませている。
「チェッ……」
林を抜けると、今度は住宅街に出る。
幽霊屋敷は、もう目の前にあった。
やはり話の通り、周りに家々はほとんどなく、広い空き地に大きなその幽霊屋敷だけがポツンと一軒建っているだけだった。
「ホント大きいんだな、この屋敷……」
アーチが幽霊屋敷を見上げながら、呆然としている。
外観はボロボロで、もう人は住めそうになかった。
「入ろう」
セピアは何の迷いもなく、屋敷のドアの前へ立った。
四人も、その後ろに立つ。
大きなドアを、セピアはゆっくりと開いた。
ギギギーッと軋む音が、辺りに響く。
中に籠もっていた生温い空気が、ベッタリと五人を包み込んだ。
「ぶ、不気味……」
流石のティムも、ちょっと怯えているようだ。
「やっぱり、鍵は掛かってなかったみたいだな」
そう言って、セピアはゆっくりと中へ入った。
四人も、後に続く。
入ってすぐに、広いロビーがあった。
床には、色褪せて破れかけている赤い絨毯が敷き詰められている。
壁には埃の被った絵画の額縁が、いくつも飾られていた。
棚には白い大きな花瓶が置いてあったが、中の花は茶色く枯れて床に散らばっている。
「僕はこんな不気味な所、近寄った事がないから分からないんだけど……その爪音や呻き声は、全部の部屋から聞こえて来るのかい?それとも、一部屋だけ?」
ネオが訊くと、セピアは思い出しながら言った。
「確か……僕も実際に聞いた訳じゃないから分からないんだけど、周りの人や父の話によると一番上の屋根裏部屋から聞こえて来るらしいんだ」
「や、屋根裏部屋?何だか、それだけでザワッとするよ……」
ヒミィは、やはり怖いようだ。
しかし、アーチは平気な顔で言った。
「だったら、その屋根裏部屋へ行こうよ。其処で、誰か侵入者が来ないか見張るんだ。案外、幽霊じゃないかもしれないだろう?」
「幽霊じゃなかったら、何なのさ」
問い詰めるように、ティムが言う。
「近所に住んでいた人だって確認してるんだぜ、誰もいなかったって。音と声だけが、聞こえて来たんだろう?幽霊以外、ないじゃないか」
それに反論出来なかったアーチは、口を閉ざした。
セピアが、宥めるように笑う。
「まあ、いいじゃないか。それは今日、此処で分かる事だ。早速、上へ行こう」
五人は、ゆっくりと階段を上って行った。
スベスベとした、茶色い木目の手すり。
床と同じく、赤い絨毯が敷き詰められた階段。
隅の方や表面には、埃が被っている。
ロビーの天井は吹き抜けになっており、その天井の大きなシャンデリアには蜘蛛の巣がぶら下がっていた。
壁紙は剥がれ、床は五人が歩く度にミシミシと音を立てる。
その時、何処からともなくガタンと言う音が聞こえた。
五人が、一斉にビクッと体を震わせる。
「な、何、今の!ねえ、何なの!何処から聞こえたのさ、ねえってばっ!」
「落ち着くんだ、ヒミィ!」
取り乱すヒミィの肩を、ティムが押さえる。
セピアは、辺りを見回した。
「大丈夫だ、僕等の他には絶対に誰もいないんだから」
ネオも、強気で言う。
「古い家だから以前から外れそうになっていた額縁の留め金が外れたとか、崩れそうになっている壁が少し崩れたとか、色々理由は考えられるだろう?ただでさえ幽霊屋敷と呼ばれている家なんだ、こんな事起こって当然なんだから、一々気にしてたらこっちの心臓がもたないよ」
「ネオの言う通りだ、先を急ごう」
ネオの意見に賛成したセピアは、更に上へと進んで行った。
ヒミィは、後ろのネオを振り返った。
「ネオ、強いなぁ……僕、見直しちゃったよ」
「えっ?そ、そう、かなぁ?まあ僕も本当は結構怖いんだけどさ、これくらい強がってないと何だか泣いちゃいそうで……」
ネオは、小さくはにかんだ。
しかし、アーチは溜息をつく。
「でも、ネオだって弱虫ヒミィなんかに見直されたって、ちーっとも嬉しくなんかないよな?」
其処でまたヒミィはムスッとし、階段をドカドカ上りながら言った。
「僕は、先に行くよ!」
「お、おいおい、階段が抜けたらどうするんだよ。静かに歩いてくれ、静かに」
ティムは、慌ててヒミィの後を追いかける。
ネオは後ろを振り返り、クスッと笑ってアーチに言った。
「ねえ、アーチ。本当はああやってわざと怒らせて、ヒミィの恐怖をなくしてやってるんだろう?アーチも、素直じゃないからなぁ……」
すると、今度はアーチがヒミィのようにムスッとし始めた。
「うるさいなぁ!ネオのお陰で、僕も怖くなくなったよ……早くしないと、置いて行かれるぞ!」
「はいはい……」
こうして二人は、先に行った三人を追った。
「此処らしいな、屋根裏部屋は……」
セピアが、小さく呟いた。
五人は、ついに屋根裏へ続く階段の前に立ったのだ。
セピア以外の四人は、息を飲んだ。
「覚悟……出来てる?」
セピアが振り返り、四人に訊く。
四人は互いに顔を見合わせていたが、やがて揃って頷いた。
それを見たセピアも頷き、階段を見上げて言った。
「よし、それじゃあ行こう」
屋根裏への階段は今までの階段よりも質素な造りで、ただの木造だった。
薄暗い階段を黙々と上り、やがて屋根裏部屋へ辿り着く。
「此処か……」
セピアが、静かに言う。
階段を上り切った所に、ドアが一つポツンとあった。
「開けるよ」
セピアの声にドキドキしながら、四人は大きく頷いた。
キーッと言う音を立てながら、セピアがゆっくりとドアを開ける。
「うわ、広い……」
ネオが呟く。
其処は、仕切りも何もないただの広い部屋だった。
引き裂かれてボロボロになった枕から飛び出した沢山の羽毛が、薄汚れて床に積もっている。
同様に引き裂かれた毛布が、何枚も投げ出されていた。
壁には、不気味な傷痕がいくつも付けられている。
「な、何、これ……」
ヒミィが、唖然とする。
「随分、散らかっているな。この部屋、何かあったんだろうか」
そう言って、セピアも首を傾げている。
斜め上には大きな天窓があり、満月が見えた。
「月、綺麗だね」
ネオは、暢気に天窓を見上げている。
ティムは一人、冷静に部屋を見回した。
「何か引っ掛かるな、この部屋。家具は何も置かれていない、この五段の引き出し箪笥だけだ。中は……」
この部屋に唯一置いてある家具と言える引き出し箪笥の中を調べながら、ティムは考え込んで言った。
「数枚のタオル、皿、そしてこの玩具……」
ティムが手に取った玩具には、無数の傷が付いていた。
「なあ、何か臭くないか?この部屋」
アーチが、顔を顰めている。
「確かに、少し匂うね……掃除していないせいだろうなぁ」
ヒミィがそう言った時、セピアが唇に人差し指を当てた。
「静かに……下から、足音が聞こえる」
「えっ、そ、そんな……ど、ど、どうすればいいのっ!」
「だから、落ち着けって……」
再び慌てるヒミィを、咄嗟にティムが宥める。
セピアは、高々と積み上げられている布団や毛布の山を指差した。
「取り敢えず、あの陰に隠れよう」
四人は頷き、急いで山の陰に隠れた。
息を潜めて耳をそばだてると、確かにヒタヒタと言う足音が下の方から聞こえて来る。
しかも、それは複数の足音である事が分かった。
「何人かいるよ」
ヒミィが、呟く。
セピアも、頷いて言った。
「ああ。しかも……大人ではないな」
「どうして?」
ネオが訊くと、セピアは険しい表情を浮かべた。
「よく聞いて御覧。僕等が此処を上って来た時は、かなり床が軋んでいただろう?でもこの足音の主は、軋む音を立てていない。と言う事は、僕等より体重が軽い人間だと言う事だ」
「人間とは、限らないぜ」
そう言ったのは、ティムだ。
四人が、一斉にティムを見る。
「じゃ、じゃあ、やっぱり幽霊……って事?」
怯えた表情で、ヒミィが訊く。
「さあ……それは、見てのお楽しみだな」
ティムは、何故か笑みを浮かべている。
その時、足音が屋根裏部屋の前で止まった。
五人が、同時に息を飲む。
足音の主は素直にドアを開けず、ガリガリと爪を立てる音を出し始めた。
その内、ドアの向こうから爪音と共に呻き声が聞こえて来た。
この世のモノとも思えぬ不気味な声に、いよいよ我慢出来なくなったヒミィは悲鳴を上げた。
「ギャ、ギャァーッ!」
ヒミィを見ながら、ティムは横で頭を抱えている。
その悲鳴と同時にカチャッとドアが開き、その姿を見た五人は目を丸くして一斉に驚いた。
『えぇーっっっ?』
「ね、猫……」
ガックリと肩を落とす、アーチ。
そう、幽霊の正体は猫だったのである。
しかも一匹ではなく、真っ黒な毛に緑色の瞳をした黒猫と、真っ白な毛に青い瞳が印象的な白猫の二匹だ。
「器用だなぁ、猫も一人でドアを開けたり出来るんだね」
ネオは、すっかり感心している。
ティムは、少し笑って言った。
「やっぱり、そうだと思った。うちも猫を飼っているから分かるけど、此処は恐らく猫専用の部屋として使われていたんだろう。この毛布や枕は、猫が遊ぶ為に飼い主がわざと用意してやっていたんだな。それにこの部屋の匂いは、猫独特の動物臭さのせいさ」
「なるほど、そう言う訳だったのか……」
アーチは頷きながら、二匹の猫を見つめている。
しかし、セピアは残念そうな顔をした。
「まさか、こんな結果になるとはね……でもまあ、幽霊の謎はこれで解けたって訳だな」
ティムも、頷く。
「多分、近所の人が部屋に入って誰もいなかったと言ったのは、まさか猫だとは思わなかったからだろう。その時もこの二匹は此処にいたんだろうけど、誰も怪しまなかったんだな。でも飼い主もいなくなったこの家に、どうしてこの猫達は戻って来るんだ?しかも、決まった時間に……」
「飼い主がいなくなった事を、理解していないんですよ」
そう答えたのは、知らない声だった。
五人が一斉にドアの方を見ると、其処にはランプを持った一人の少年が立っていた。
『ユマ!』
五人と同じ学校の生徒で、一つ下のユマだった。
「ユマ……どうして、此処に?」
ヒミィが驚いて訊くと、ユマは床にランプを置いて言った。
「この猫達、いつもつるんで其処の公園に来ていて、僕は学校帰りにいつもあの公園を通るから、その度にコイツらの事が気になっていたんです。飼い主がいるような感じじゃなかったから、何処へ帰るのかと後をつけたら、この屋敷に住み着いていた事が分かったんですよ」
「さっき、飼い主がいなくなった事を理解していない、って言ってたけど……」
ネオが訊くと、ユマは静かに答えた。
「色々な人の話を聞いて分かったんですが、この家の主は事業に失敗して借金を抱え込んだらしく、それでこの家を追い出されたようです。コイツらを置いてね……随分と急だったそうだから、この二匹の事まで考えている余裕がなかったんでしょうね」
「そ、そうだったんだ……」
ヒミィは、驚いている。
ユマは、話を続ける。
「嵐だったから、出て行く時に積んでいた荷物がいくつか飛ばされたらしいです。有名な赤い靴の話は、その飛ばされた荷物の一つじゃないかと言われていますよ。それを聞いたら、置いて行かれたコイツらが可哀想になって……僕がたまに来て、面倒を見てると言う訳です」
「なーんだ……じゃあ僕等より先に、ユマが謎を解明してたって事?チェッ、つまんないの」
むくれるアーチの肩を、セピアは笑ってポンと叩いた。
「まあ、そう言うなよ。で、ユマ……この事、他に誰か知ってるのか?」
ユマは、首を傾げる。
「さあ、知らないと思いますよ。僕は、誰にも言ってないから。コイツらの為にも、此処はこのまま残しておいてやりたいんですよ。飼い主とコイツらとの、唯一の思い出の場所な訳だし。誰かに教えたら、面白がって荒らされる危険性があるでしょう?」
「その通り!ねえユマ、僕にもこの猫の世話手伝わせてよ」
ヒミィがそう言うと、ネオも同意した。
「僕もそれ、考えてたんだ。皆でやろうよ、この六人の秘密って事でさ」
「どうだユマ、賛成してくれるか?」
ティムに訊かれ、ユマは快く頷いた。
「そうですね。そろそろ餌代も辛くなって来た所だし、仲間がいてくれると助かります」
「じゃあ、決まりだね。それにしても、この猫……凄く品がいいね、毛並みも綺麗だし」
そう言ってヒミィが背中を撫でると、白猫は静かにヒミィに寄り添った。
「金持ちだったって話だから、相当いいもの食べさせてもらってたんだろう」
ティムも、黒猫を慣れた手つきで抱いている。
「おとなしいな、随分と人に慣れてるじゃないか」
アーチも、ヒミィやティムに懐く猫を微笑ましそうに見つめた。
「じゃあ、今日の所は帰りますか。母が、温かいビーフシチューを作って待ってるからさ。きっとデザートには、焼きたてのバナナタルトが用意されていると思うよ」
セピアがそう言うと、途端にヒミィはお腹を押さえた。
「そっか、今日はセピアの家に泊まるんだったよね。ビーフシチューに、バナナタルトかぁ……それ聞いたら、急にお腹減って来たよ」
皆は、そんなヒミィを見て大笑いした。
「良かったら、ユマもどうかな?」
「ええ、喜んで」
セピアの誘いをユマも受け、皆は綺麗な月夜の道をセピアの家へ向かって歩き出した。
おしまい
二〇〇〇.三.二六.日
by M・H
前話(第四話)
次話(第六話以降)
同じ地球を旅する仲間として、いつか何処かの町の酒場でお会い出来る日を楽しみにしております!1杯奢らせて頂きますので、心行くまで地球での旅物語を語り合いましょう!共に、それぞれの最高の冒険譚が完成する日を夢見て!

