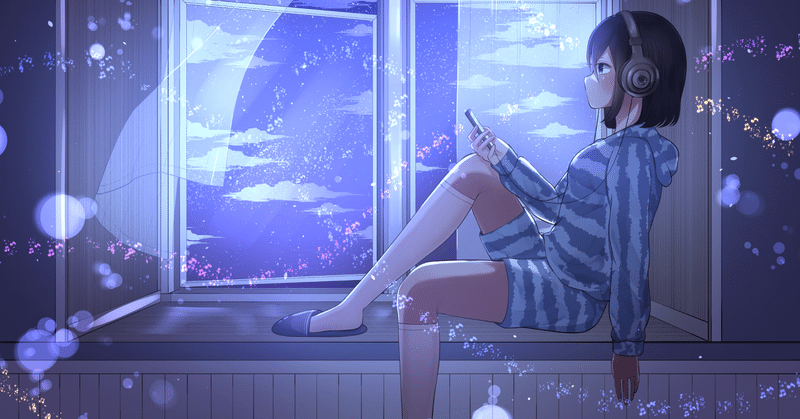
【短編小説】スピカとナノ
イオンのヴィレヴァンで新譜のCDを買い、そのままエスカレーターでくだって、ナノは外にでた。交差点、信号が青に変わって歩きだす。
「でー? 誰のCD買ったの?」と電話越しのスピカがナノにきく。「どーせ、またあのアイドルなんでしょ? そんな面倒なことしなくてもさぁ、サブスクでサクッと聴けば良いのに」
「わかってないなぁ」と、これはナノ。電話を耳に当てたまま、うっすら溜息混じりに。交差点を渡りきって、細い路地へ彼は進んだ。「わかってない。スピカはなーんにもわかってない。円盤であることに意味があるのさ。サブスクは音質がどうとか音圧がどうとかいう以前の問題で、つまりはさ、フィジカルであることに価値があるんだ。好きなものは、目にみえる形でほしいし、いつでも手が届くところに置いておきたいの……少なくとも僕はね。まあ、他人の価値観を否定するつもりはないよ。みんなそれぞれ自分に合った形を選べば良い。今は多様性の時代だし。……話がそれたね。フィジカルな体験に関していえば、その最上位は、なんといってもライヴだよ。彼女たちのライヴをナマで観たことがないのは人生の大きな損失だと僕は思うね。騙されたと思って、スピカも一度行ってみ? 誓ってもいい。どうして今まで見逃していたんだろう、と後悔するよ。でも、ある意味、僕はスピカが羨ましくもある。だって、あの初めての感動をこれから知ることができるんだから。人生観、変わるよ。インドに行くのよりも、ずっと衝撃的。かわいいとかさ、かっこいいとかさ、そんな単純な言葉じゃないんだよね。一言で言い表すことは難しい。うん、なんていうかさ、もう…………すごい。すごいんだ。青色の子が最高だ」
「青色?」
「最近のアイドルは、担当カラーで色分けされているんだよ。青色の子が、僕の推し」
「ナノって、ときどき饒舌だよね。普段はナマコみたいにおとなしいのに。でも、どちらかと言えば信じるよ、その話。ナノが薦めてくれるマンガも映画も、いっつもハズレがないし?」スピカは悪戯な少年のようにヘヘと笑った。「とりあえず、まあ今度そのCD、私に貸して」
通りの角で知った顔をみかけた。二個上の兄貴の友達だ。むこうは停めた原付にまたがったまま、緩くこちらに手を振った。ナノは電話中だったから軽く会釈ですれ違う。顔見知りとエンカウントするなんて、この町では、しょっちゅうあることだ。なにせ狭い町なのだ。どこもかしこも知った顔で溢れている。
耳がハウるくらいにうるさいセミの声。足元に落ちた影が濃い。じりじりと日差しが強く、ちょっと歩いただけでも鼻の頭に汗をかく。
足を止め、ナノは自販機で炭酸のペットボトルを買った。キャップを開いて、一口含む。
遠く、神社で祭囃子の練習をしている音がしていた。和太鼓と、カネと、横笛の。
「来週の夏祭り、クラスのみんなと行くんでしょ?」
「行くよ。ナノも来る?」
「その日は塾だ」
「知ってる。知ってて言いマシタ」
「…………。」
「あれれ? もしかして、ナノも一緒に行きたかった?」
「誰が! そんなこと一言も言ってないし。バっカじゃないの。なんで僕がそんな……、」
「ふぅん……。へえぇ。そっかそっか。なるほどなるほど」
「……なんだよ」
「まあまあ。おみやげに林檎飴、買ってきてあげるから」
「いらない」
「綿菓子のほうが良い?」
「いらないって」
「かき氷?」
「……それ、溶けるから」
「ねえ」
「……」
「ねーえ」
「…………。」
「ねえってば。怒った? ナノー? ナーノー? もお、わかったわかった。来年は一緒に行こ?」
「来年? 来年って……。そんなの、来るかどうかも怪しいよ」
「……どうして、そういうことを言うかなあ、きみは」
「僕は夢をみないだけ。なにせ、リアリストだからね。クラスのみんなを見てよ。誰それと誰それの彼氏彼女の関係についてとか。親とか兄弟、嫌いな先生についてとか、そんなのばっか……。そんなこと言ってる場合じゃないのにね。みんな、気づいていないんだ。もう、この世界がとっくにヤバいってことに。気づいているのは、僕たち二人だけだぜ?」
「私たちは勝つの。絶対」そうスピカが言いきった。
「でも、」
「ナノが応援してる、そのなんとかってアイドル? 勝たなきゃ、ナノのその大事な推し活だって、できなくなるんだよ? それでもいいの? 良くないよね?」
「良くはないけど……」
「でしょ? だったら、」そこまで言って、スピカは急に黙った。携帯電話を耳から離したようだ。彼女は声を張り上げて「あとでいい! あとで食べるー!」と遠くに向かって返事した。
「今の、お母さん?」とナノはきく。
「うん。下から呼ばれたけど、もう一階に降りてった」
「……下?」ナノは眉根を寄せた。「スピカ。きみ、今どこにいるの?」
☓ ☓ ☓
同時刻。スピカは、家の三角屋根の上にいた。屋根の傾斜の中腹に、あぐらをかいて。
スピカの家は高台にある一軒家だから、ここからは町が見渡せる。昔は栄えていたと大人たちが言う商店街。錆びた工場の煙突と、海に架かる赤い橋。通っている高校も。
海面が、脂が浮いたフライパンみたいにギラギラ眩しい。
屋根の上では、日差しを遮る物が一切ない。当然、日傘も持ってはいない。
「暑っつい……」
「夏だからね」と電話のむこうのナノは素っ気ない。
☓ ☓ ☓
将来の夢を持て、と大人たちは僕らに言う――。
「――そんなの、知らん」
とナノは呟いた。
「なに? 今、なにか言った?」とスピカがきいてくる。
一昨日、学校で配られた進路希望記入表のことを思いだす。まだ何も書いていない。鞄の中に入れたままだ。
「スピカは、何かやりたいことってある?」
「夏休みの間に?」
「もしくは、それ以上先のことでも、」
「そうだなあ。キャラメルリボンが食べたいわ」
「アイスクリームの話? きみが一番呑気だね。ははっ。じゃあ、僕はクッキーアンドクリームで」
☓ ☓ ☓
スピカは空を見上げた。かたわらに置いてあった刀を手に取り、屋根の上で立ち上がる。
「――来た!」
青空の雲の遥か先に、米粒大の動く物体を、その目で捉えた。
電話からナノの声。「こっちからも確認できた。大気圏付近に、一……、二……、全部で三つだ」
「違う。まだ来る」
スピカの宣言どおり、黒点が、染みのように、見る見る間に、空に増殖していく。
「……ちっ、前言撤回。予測敵数、百。交戦可能領域侵入まで残り十五秒」
その間にも、連中は彗星みたいな勢いで、ぐんぐんぐんぐん、地表めがけて接近してくる。
刀身を抜いて、鞘を投げ捨てるスピカ。仁王立ち。下唇を舐める。膝をグイと深く沈めて構えた。
☓ ☓ ☓
一方、すでに、ひと気のない児童公園に移ったナノも、背負っていた鞄をベンチで開いて、中から拳銃を引き抜いた。
負けるわけには行かない戦いだ。ただの一度も。
負ければ、全部終わってしまう。
全部、だ。
文字どおり、全部。
学校も、塾も、夏祭りも、花火大会も。林檎飴も。綿菓子も。
だけど、そんなことは口にはしなかった。言わなくたって、そんなことはスピカだって百も承知だ。
今までも、ずっと二人だけで戦ってきたんだ。僕たち二人以外には姿がみえないあの敵と。
「……せめて、次のライブツアーまでは死ねないか」ナノは独り言を呟いた。
もう余裕で肉眼で姿が確認できる高度まで迫ってきている。デカい。バカデカい。どす黒い飛行機雲のような長い尾を空に描きながら落ちてくる。
ナノは、瞳の虹彩のバイオ認証で、銃のロックを解除した。コッキングバーを引き、反対の手の指をトリガーにかける。
「準備はいい?」
「もちろん」とスピカが答えた。
「飛ぶよ」
☓ ☓ ☓
二人とも、親指で電話を切った。
スピカは、屋根を蹴った。
ナノは、地面を蹴った。
上昇。旋回。風が頬に当たる。シャツのすそが大きくなびく。上昇。上昇。目の端に映る町が、オモチャのジオラマみたいに、下のほうに小さくなっていく。
スピカとナノ、二人同時に、声を揃えて宣言した。
「「さあ。生き残りを始めよう」」
(了)
※一部、YouTube朗読版とは内容が異なる場合があります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
