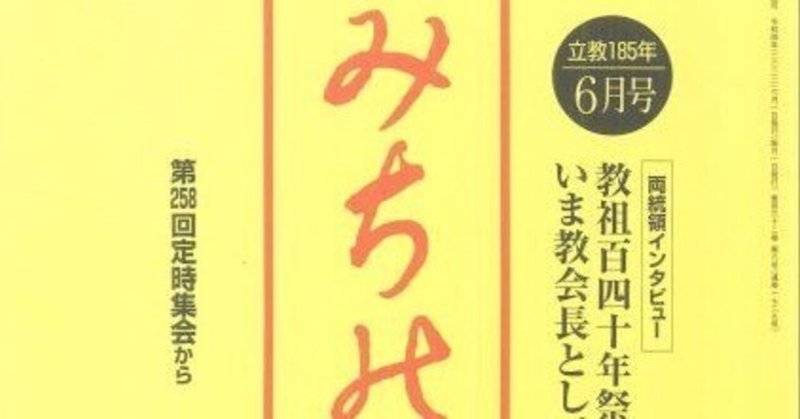
「みちのとも」185年6月号の両統領インタビューを読んで
「教祖百四十年祭三年千日を前にいま教会長としてすべきこと」ということで中田表統領、宮森内統領のインタビュー記事が載っている。インタビュアーは諸井道友社次長である。
どうも「教祖年祭」というと「教祖百年祭」の時に起こった様々な問題や事件が思い出されて、「ねんさい」という言葉を聞くだけで眉を顰めてしまう。ちょうど教会長の自殺があったのも山名詰所だったと思うが、インタビュアーの方が山名大教会長というのも何となく因縁めいている気もしないではない。
『天理教よ蘇れ!』(小山貞市、吉村卓三著 日新報道 昭和61年)を読んだことがある人なら、“百年祭”がどれほど狂っていたのか、よくご存じだろう。ご存命の教祖が本当に喜ぶような「年祭」だったのだろうかという思いがする。「百」という字になぞらえて「白紙に戻って一から」が合言葉でもあったように思うが、あれから30年以上経つというのに白紙どころか、よくなったことは何一つなく、皆が衰退しているだけだと噂するような有様だと思っている。 前置きはこれくらいにして話をすすめたい。
表統領は道の先達である教会長が年祭活動を考えていく上で三つのポイントを挙げていた。要約すると
1 年祭の意義をしっかり心に治めること
2 預かっている教会の現状、現在の姿を、しっかり確認・把握すること
3 三年千日をつとめきる覚悟、心構えをつくっていくこと
まったく従来と変わり映えのしないことをくどくどと言っている印象しかないが、年祭の意義についても教祖の最後のご苦労話を持ち出して、仕切って年祭活動をしなければならないと結んでいるようである。しかし、これでは若い人はついてこないばかりか、古い人も「またそれか…。」と勇むどころか、もう勘弁してもらいたいという気持ちになるのではないだろうか。
教会の現状を確認・把握というが、言われなくても自教会の現状は悲惨なところが多いのではないか。コロナ禍でこの3年で疲弊しきっている上に「名称をお返ししたい」というところも多いと聞く。その上、また三年千日を心定めして苦労して通れと本当に教祖が望んでいると思っているのだろうか。
そもそも天啓を途絶えさせた教団で人間中心なのだから、何とでも言えるし、都合よく解釈できる。本席に代わる天啓者がいて「伺い」を立てればどんな答えが返ってくるのだろうかとも思う。今まで年祭がらみで、多くの苦しんだ分教会の会長がいたことだろう。「みちのとも」にこんな対談記事を書いているよりも、全教会長にアンケートでも取って、“正直なところ、私の代で終わりにしたい”と思っている教会長の数を「しっかり確認・把握すること」をした方がいいのではないだろうか。それほど深刻な宗教離れが進んでいる気がする。
表統領はP19で「こども食堂」を引き合いに出して教会に多くの人が来てもらえるような存在になるため何かしらアクションを起こさなければならないと述べている。確かに朝夕のお勤め、月一回の月次祭、信者宅の講社祭だけやっているようなところは少子高齢化でどんどん衰退していくしかないだろう。
この意見には賛成である。しかし、昔からそのようにやっているところも結構あるのではないか。東本大教会の修徳学園とか分教会レベルでも別法人を立てて、幼稚園や保育所、或いは福祉施設などを経営しているところもあると聞く。私は教会長でも教会後継者でも専門性を活かし、勇んで働ける仕事があるなら、どんどんやるべきだと思う。教会長と施設長の二足の草鞋でも、教え通りに“はたはたを楽にさせる”ものであるなら、胸を張って“事情働き”すればいいと思う。
私が問題だと感じるのは、前回の記事でも書いた“事情働き”である。働くことが後ろめたい、会長がお金を稼ぐことがよくないという風潮があるように感じる。天理教に学問はいらない。世間で働くのは道一条ではない。上から言われることは神の言葉だと素直に守っていればいいのだというおかしな論理。 もう時代が違う。今は全く真逆であると言える。
天理教をやるなら学問もやってクリティカルな視点を持てるようになれ。世間でも働いで、自立して食うに困ることがないようにするのは当然で、自分の仕事を通しても教祖の教えは本物だったんだと確認することを続けろ。しっかり何が本当で何が嘘なのか、見分けられるほど、天理教の教理についても研究していくことが大事だ。百年祭の時のような不幸な過ちをまた起こさないように…。
表統領はP19で次のように述べている。
それから、もう一つ。このたびの教会のお返しということを含めて、いまのお道の状況は、教会は末代、信仰は末代、道は末代ということを、あらためて考える機会を与えていただいていると思います。ですが教内には、そのように受けとめる意識は。まだ低いように感じます。そこには自分の代の範囲でしか教会のことを考えてこなかったという面があるからでしょう。
これを読んだ時、“あらためて考える機会”を与えていただいている。「その通り!」だと思った。今まで考えることも憚られていた。教会制度という教祖も本席も望んではいなかった制度を導入し、江戸時代のような差別階級を作り出し、代が変わっても、そのポジションは変わらず、その体制を“末代”続かせれば教団としては安泰である。“あらためて考えれば”皆がいい加減に気づいて、おかしいと声を上げ、今のような教会制度のままでは“末代”続くはずはないと“あらためて考えて”改善策を出すべきだ。
またP20では表統領は次のように述べている。
理想の教会の姿は、私たちのいまの段階では分からないかもしれませんが、それはあるはずです。なぜならば、親神様・教祖には意中の教会の姿というものが必ずあるからです。仮に、その理想の姿があって、それが100点だとしたときに、「では、いまのあなたの教会は何点?」と尋ねられて「98点」と答える人は、たぶんいないと思います。
私はこれを読んだ時、驚いた。「理想の教会の姿」というが、そもそも親神様・教祖は「教会制度」そのものに反対していたのではないのか?古くは吉田神祇官僚への願い出、金剛山地福寺傘下での「転輪王講社」など布教公認、教祖の勾留を防ぐというために人間が考えだし、教祖の反対にも関わらず応法へ流れていった歴史があるのではないか。
その中も神の社として、ぶれることもなかった教祖は拘留もされ、最後のご苦労もすることになったのではないか。神道直轄天理教会本部を経て、明治41年に一派独立、その頃には教祖も本席もいない、初代真柱も出直し、二代真柱時代に入ってからは革新の時代に入り、更に国家神道に融合していかなければならない時代に入っていったのだと理解している。
つまり歴史的に見ても親神様・教祖に理想の教会の姿などあるわけがないと考えるが、私は認識が間違っているのだろうか。
私は年祭を勤める意義は「復元」を完全なものにし、十年の年祭ごとに本来の姿に戻していくことだと考える。現在の教会制度のままだと間違いなく衰退していく。まずは三年千日かけて、よく練りあい、「教会制度」を廃止し、それに代わる民主的な「講」のような組織運営ができるようにすべきだと考える。それと共に十年ごとに神道色を更に無くしていくべきだと考える。本当に先を見据えるなら日本の宗教から脱却しなければ普遍の世界宗教にはなれないとも考えるからである。
個人の思いを書き連ねましたが、ご意見をお聞かせいただければ幸いに存じます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
