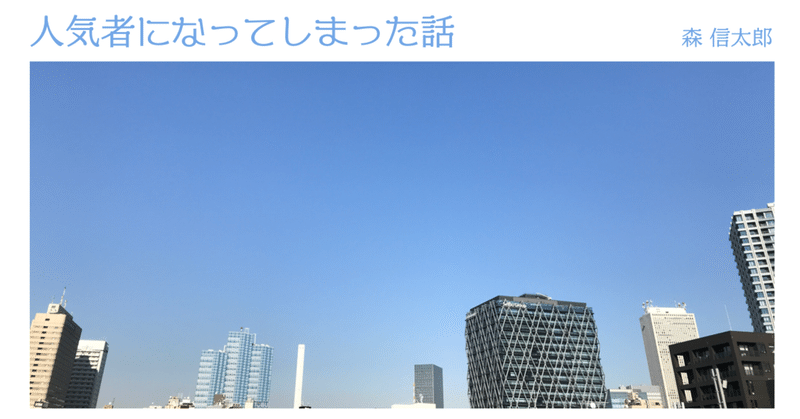
人気者になってしまった話
人気者になりたいと思ったことがないが、なったことがある。自慢に聞こえたら謝る。誤解を招いたことやご迷惑をかけたことを謝罪していろいろして発言を撤回して、結局そのまま居座りたい。だがやはり、それは事実なのだ。
名前はひとつの呪いである、と言いたい。例えば、「珠緒」と名付けられた子はほぼ確実に「たまちゃん」と呼ばれ、次第に「たまちゃん」らしい子に、もしくは「たまちゃん」と正反対の子に育つ。わたしの下の名はどうも立派すぎるようで、小学校のときにはもう「森さん」と呼ばれていた。だからわたしは「森さん」らしく、なんだか常にカギカッコつきで呼ばれているような、すこしだけ浮いた子どもになった。浮いたままわたしは集団の境界を視認し、それを言語化することで笑いをとり人気者になった。それはiOSのデータの引越しのように中学につづき、違う小学校に通っていた級友たちもわたしを「森さん」と呼んだ。田舎ながらも青文字系モデルのような雰囲気があり一時期好きだった同級生Sくんのお姉ちゃんにも、だ。
いままでは「地域」だったフィルターが「学力」に変わる。それが高校への進学だ。わたしが合格した高校には同窓生が少なく、「デビュー」には絶好の機会だったから、どうせならキャラクターを変えてみようと思った。わたしは人気者に飽きていたのだ。
もう山の名も忘れた。文武両道を是とするわが校では、新一年生の交歓のための軽い登山イベントがあった。もちろん、文と武を8:2くらいでやっていきたいわたしにとっては、たいへんふざけた話であった。が、同じ中学のクラスメイト二人はまあまあ楽しみにしており、こいつはどうせ7:3なのだな、と舌打ちが出た。
「高校では目立たんとこうと思ってる」
「ふーん」
ジャージで登れるほどの山だ。臆することはない。行儀よくクラス単位で出発したわたしたちは、まだふにゃふにゃと不安定な人間関係を可視化していった。あっちでグループができこっちで解散し、「ちょっと休むわ先行って」のあと合流した別グループがしっくりきたりして、そんなものはないがさながら、流れるプールでのカクテルパーティーのようだった。そしてわたしは同中の二人がサッカー部で7:3であることを思い知らされており、友情と踏破力の天秤の片方が地についていた。「ちょっと休むわ、先行っといて」
いま考えると絶対におかしいのだが、わたしは山で一人になった。8組中の8組だとしても、担任か体育教師が最後尾を死守するべきだと思う。だがそのときは冷静な思考などできず、わたしはただただ疲れていた。捻挫とも骨折とも裂傷とも無縁で、ただただまっすぐに疲れていた。中学から愛用している「現場の人」みたいな魔法瓶から母親が朝入れてくれたキンキンの麦茶を蓋に注いで飲んだとき、何十本も奥にあるのに露骨に見える太い木の幹から真っ白なうさぎが顔を出し、「ちゃんと量を考えててえらいね」と言った。
歩かねば死ぬ。それに近いことを考えていた。この一本道の登山道で遭難することはないが、だがもし心配した体育教師などが道を引き返してわたしを救いに来て救われて皆の待つ広場的なところに登場したら、わたしは絶対に目立ってしまう。それは承服しかねる!もし級友に大丈夫だったかと聞かれたら、わたしは持ち前のサービス精神で「死ぬかと思った」だの「山をなめてはいけない」だのと言ってしまい、この状況とわたしの風貌が相まって絶対にウケてしまうのだから。
「持ち前」を憎みながら数十分か数時間ほど傾斜を進んでいると、唐突に視界が開け、両端の木が道から漏れる光に染まっていた。導かれるように可視光線のゴールテープを切ると、そこからは一気に下り坂で、その先の広場には級友たちが体育座りでのんびりと過ごしていた。
「あ!森くんや!」
わたしにはもう逃げ場がなかった。級友たちから見るとその坂は花道で、わたしはまるで「ご本人登場」のようにそこを下るしかなかった。「森くんや!」「無事やったんや!」「元気そうやで!」出会ってまだ一週間にもたぬ男子と女子が歓呼の声をあげるなか、わたしは大げさに手を振りかえし、そうして高校生活がはじまった。
次回の更新は2月13日(土曜日)です。
励みになります。
