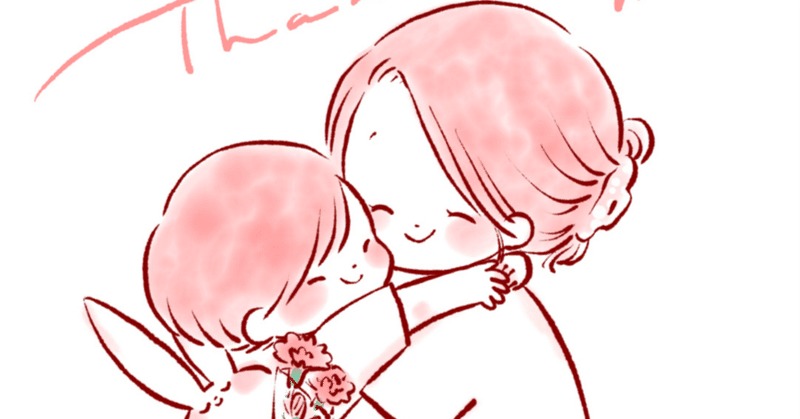
【宗教2世支援者養成講座08】無償の愛、こそがすべて
さて、今回は「宗教2世支援」のもっとも核となる理論についてお話したいと思います。
実際には「支援」の方法や、あり方は、本当に多岐に渡っていて、かなりいろいろな方面、方向性からアプローチしなくてはいけないので、とても大変な作業なのですが、ここでは「コア中のコア」となる、中心的な考え方について説明したいと思います。
宗教2世問題では、表面的には「虐待」や「愛着形成」など、あるいは宗教環境下において生じた「感情の萎縮」等も含めて、心理学的な多様な課題が生じます。
もちろん心理学やカウンセリングのプロの目線からすれば、そうした問題や課題を紐解いてゆくことが重要になりますが、みなさんは「いち支援者」としての立場ですから、基本的な理論をまず押さえておいていただければ良いかと思います。
それは
「無償の愛」
についてです。
宗教環境下にあって育てられた宗教2世は、「条件付きの愛情」を受けています。行動が神の目にかなっているか、あるいは教義や教団の指示に従っているか、教えに「ふさわしい」かどうかといったジャッジメントや強制を常に受けて生活しているという特徴があります。
そうした中で親子の愛情は「子どもをそのままの姿で見る」ということが欠損しており、前回のお話にもでてきましたが常に「宗教バイアス」がかかった状態になっています。
子どもの目線からすれば「そのままの自分を見てほしい」「バイアスのない、本来の親子関係がほしい」と思っていますので、親からの愛情が「条件付き」であることは、人生に暗い影を落とすことになるのです。
========
こうした理由で、宗教2世の支援の核となるのは
「失われていた無償の愛を補完すること」
ということになります。もちろん、親子間の本来の愛情をそっくりそのまま再現することは不可能ですし、また、そもそも対象者とは親子ではないので立場が異なりますから、あくまでも「補完」することしかできません。
しかし、心理学的にも、こうした「無償の愛」を他者からもらうことは、ケアにおいてきちんと効果があり、重要性があるとされていますので、この方法は大切と考えます。
(参考)
引用した記事では「特定の他人」との間に構築された信頼関係についての説明がなされています。
「安心して頼れる存在」がいることが、とても大きな意味を持つことがわかると思います。
さて、無償の愛とは「その人の人となりをそのまま受け止め、親切にすること、親愛を示すこと」です。
けして「言いなりになる」とか「忖度する」という意味ではありません。しっかりそのまま、ありのままでこちらもあちらも「人間同士として、丁寧に接する、親切に接する」ということを意味します。
支援者として「支援しなくてはいけない!助けなくてはいけない!あの人は可哀想なんだから!」ということでもありません。それは、共依存の始まりですし、そもそも接し方が最初から間違っていると言っても過言ではありません。
最終目標は、対象者が「自立した、自分の生き方を選択する人になる」ということですから、支援はそれに寄り添ったものであるべきです。
「支援してあげる」「愛を与えてあげる」「何かしてあげる」
という視点は、誤りです。
もちろん、時には何かのサポートを「してあげる」場面もあるかもしれません。けれど、対象者が一人の、独立した人間であり、そうなってくれるよう望む姿勢を忘れないようにしたいものです。
このように考えると、「無償の愛」に触れてもらう、ということは、それほど難しいものでないことがわかると思います。心からの親切心、心からの共感、心からの心配、といった「ふつうの、誰もが持っている、あたりまえの」感覚で、大丈夫なのです。
そして、支援者である「あなた一人」がそれを抱えるべき問題ではありません。対象者の周りに「一人でも多くの親切な人がいる」ということが実は重要ですから、支援という行為に「がむしゃら」にならなくても良いのです。
ふつうの、当たり前の親切が、たくさん、なんども繰り返される、というイメージを持てばよいかと思います。それこそが対象者が安心して回復に迎えるという環境だと思います。
ただし、具体的には、この「無償の愛」をどのような形で示してゆくか、も支援者の課題になってくると思います。比較的簡単な「声かけ」や、「相談に乗る」といったものから、物理的な手助けや、時には経済的援助などが必要になる場合もあろうかと思います。
カウンセリングや医療などでは、「一定の時間」を切り分け(受診時間等)、また必要な「代金」などを介して支援が行われますから、支援する側とされる側は、「はっきりとした境界線」で区切られます。
しかし、たとえば友人として無償の愛を示す場合などは、「どのライン」「どの時間」「どの区切り」を持ってよいのか、支援する側もされる側も、わからなくなることがあろうかと思います。
無償の愛なのだから、すべてをまるごと、長々と時間の切り分けもなしに行う、というのも違和感を感じますよね?
ですから支援者としては、「自分にできることをどの程度支援するのか」という自分なりの目安を持っておくことが大切と思います。
その目安で線引きをしたとしても「そこが条件分岐」というわけではありません。
お互いが自立した、心身ともに健康な個人であることを大切にするためにも、「自分にできることの目安」は考えておいたほうがよいと思います。
この時に参考になるのが「望ましい親子関係の場合に、子どもの要求を100%あるいは120%受け入れることは、子どものためになるか?」という視点です。
「無償の愛」を持って接するふつうの親子だとしても、親は120%子どもの要求を受け入れるものではありませんし、受け入れるべきではありません。
ですから「違和感を感じたら、率直に言うね」と対象者に言えるような関係を構築できるように、少しだけでいいですから事前に留意しておいてください。
せっかくの愛情ある関係性が、ボタンのかけ違いや「お互いの領域への踏み込み」によって、いびつなものになってしまうことは、避けたいものです。
もしこうした問題が生じそうな時には、支援者も一人で問題を抱え込まず、他者への相談を活用してほしいと思います。
そのためにも、これは私の個人的な意見ですが「宗教2世支援者」同士のネットワークや、ふんわりとしたグループづくりも必要なのではないかと思います。
個々の活動に加えて、宗教2世支援についての研究会のようなものを、整備する必要があるかもしれません。
もし、そうした機運が高まるのであれば、私も心からお手伝いをしたいと思います。
(つづく)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
