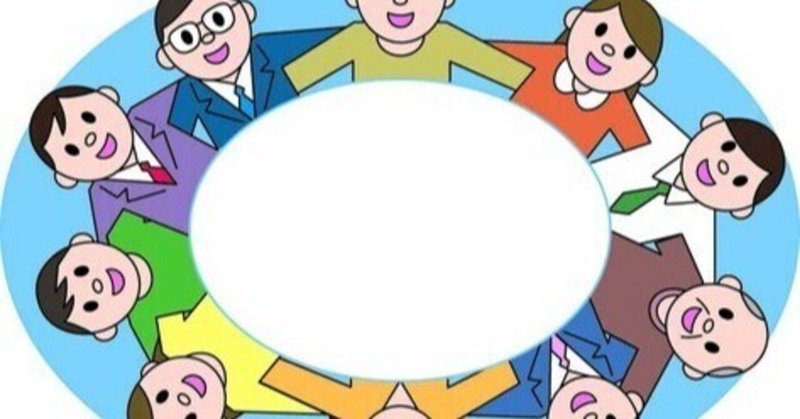
家族で話し合う「防災の輪」
こんばんは、前々回に「基本の4つの備え」の
1「物の備え」、2「室内の備え」、3「室外の備え」をお話ししました。
本日は、「コミュニケーションという備え」について
お話しします。
【大事なことは、家族で行うこと】
・災害時や出火後による出口の確保や帰宅困難になった場合の
安否確認の方法や集合場所を決めること。
・防災ブックの活用
防災対策の基礎が載っている防災ブックを読み、話し合うことで
意識を高めることができます。

【防災訓練に参加しておけば、災害時に慌てることはない!】
各地域で行われている「防災訓練」や「防災イベント」に参加すると
消火器やスタンドパイプなどの使い方を学ぶことができたり、
非常食をいただくことができたりするなど、
楽しい時間を過ごすことができます。
他にも起震車に乗れば、「身体防護訓練」ができたり、
「通報連絡訓練」、「避難訓練」、
「応急救護訓練」(胸骨圧迫やAEDなど)ができたりする
大規模なイベントもあります。

【消防団に入るという選択肢】
消防隊とは異なり、自営業や主婦、学生などの仕事を持ちながら、
火災が発生した場合に、消防活動を行う組織です。
地域の方の命を救うため、活動をしています。
(防災市民組織って何?)
近所の人が互いに協力し合い、自分たちの地域を自分の力で守る組織です。
町会の防災担当者が中心となり、活動しています。
【会社での災害対策】
・3日分の非常食を全従業員分用意する。
帰宅困難者に備える
・防災訓練を行う
(災害ボランティアって何?)
災害発生時から復興に至るまで、被災地のために復旧・復興のお手伝いを
行うボランティア活動のこと。
被災者に寄り添うことや炊き出しなども含まれる。

(現状)
積極的にボランティア活動を行う人が増えたのは、阪神淡路大震災の時。
「ボランティア革命」などといわれるようになった。
東日本大震災でも同様にボランティアを行う人が増えた。
しかし、被災者たちの食べ物を取ってしまう者が現れ、問題となる。
それでもボランティア活動を行う人たちは多く、マイナスなイメージを
持つ人よりもプラスに思う方の方が増えていった。
しかし、能登半島地震の時に、禁止のエリアに入る者や、被災者の家から
金品を盗む者が現れ、ニュースにもなったことで、話題となった。
ボランティアをする、している者にとって自己満足であると思う方も多い。
(最後に、防災の輪って何?)
基本の4つの備えをお話ししてきましたが、
「防災の輪」とは、「学ぶ」、「備える」、「参加する」ということです。
災害の知識を学び、防災グッズを備え、防災イベントなどに参加する。
そういったことをすれば、自分の身や家族、地域の方を救うことや連携することができます。
皆さんも是非、参加してみてください。
本日も読んでいただきありがとうございました。
東京防災
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
