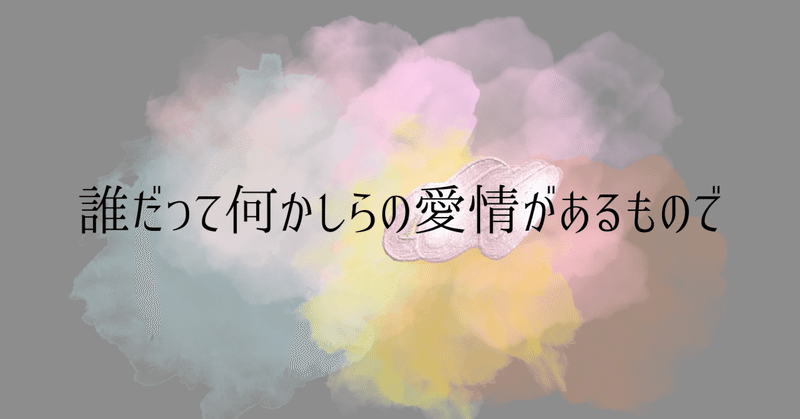
母性に代わるもの
厚底ピザ作
しのぶが初めておばあちゃんの家に一人で長期滞在したのは、小学三年生のときだった。
父と母の離婚調停が思いの外長引き、母方の祖母が一人で住まう田舎へと預けられたのである。一口に田舎と言っても、コンビニが近くになく、やや都心部へのアクセスが悪い集合住宅地や、誰もが田舎と聞いて想像するような野畑や山の連なるのどかな土地などさまざまあるが、しのぶの祖母の邸宅は、まさに後者であった。
一帯に広がる緑の海以外に特徴はなく、特に観光地もなく若者が出ていくばかりのその村は、バスは一日に一本、如何にも地域密着型の店ばかりが立ち並ぶような典型的な田舎ではあったが、都会育ちの幼いしのぶにとっては、不便より物珍しさが勝った。両親とともに過ごした、あの広く小綺麗なマンションの一室は、良くない思い出の方が色濃く残っていたこともあり、しのぶは祖母との二人の時間を至極穏やかに、静かに過ごした。
祖母は穏やかな人だった。しのぶは恐らく、あれより穏やかで温厚な人間とこれから先出会うことはないのではないかと思っている。気に食わないことがあればすぐ金切り声を上げて、その辺のものを引っ掴み、手当たり次第に投げ飛ばす母が、本当にこの人から生まれてきたのかと疑うほどに。それほどに、祖母はさざなみのように穏やかで柔らかいひとだった。ノブくん、ノブくんや、と独特の丸っこい口調と、角の取れた方言は、連日両親の間で交わされる怒号で知らずの内に疲弊しきっていたしのぶの心から棘を抜いていった。冷食と出来合いの麺類ばかりを食べていたことで丸々とした体形も、祖母の作るもので随分落ち着いた。そもそも此処では、買ってすぐに一食分として食べられるものを売る店がほとんどないのである。
離婚調停を終え、なんとか親権を勝ち取ってきた母が迎えに来た時、しのぶは珍しく泣きじゃくって祖母の手を握ったまま離さなかった。死に物狂いで我が子を育てる権利を奪い取った母親は、その姿を見て狂ったように泣き喚き、しのぶの手首に痕が付くまでその手を引いた。祖母が困ったような顔で止めに入り、取り敢えずもう一泊して行きなね、と二人分の食事を出すと、親子は二人泣き腫らした顔でそれを食べ始めた。
しのぶの母頼子は、子どものまま親になったことを、自分自身でも分かっていた。田舎暮らしに辟易として家を飛び出し、電車の路線図も分からぬまま東京に出た。顔立ちにだけは恵まれた頼子は、しのぶの父親である靖夫に出会い、トントン拍子に事を進めてそのまま結婚した。当時、自分はなぜ靖夫に惹かれたのだろうか、と思い起こしてみるが、具体的なことは何も思い浮かんでこない。ただ、この弱肉強食の都会を自分の力で生き抜き、営業マンらしく自分の意見をきちんと言語化できる靖夫が、ただ「なんとなく」都会への憧れで流されるまま東京で生きている頼子には、世界で一番格好良い男のように思えたのだ。
子どもは、欲しいわけでも欲しくないわけでもなかった。ただ、田舎に住んでいた頃は子どものいない世帯の方がよほど珍しく、ただ漠然と自分も子の母親になるのだろうと頼子は思っていた。口煩い義母にせっつかれながら作った子どもは、夫のゴツゴツしたホームベースのような輪郭と、自分の頭の悪いところが似て、正直可愛いと思えなかった。子を産めば、自然と母親らしくなれると思っていた頼子にとっては、「可愛くない子ども」の存在がショックだった。そしてしのぶも、なんとなく、母親に「可愛くない」と思われていることを、薄々感じていた。薄々感じていて、幼少期からそれを封じ込めながら、気性の荒い母親と自身にあまり興味の無い父親の間で上手く息を殺していたしのぶは、決して頼子の思うような「頭の悪い」子どもではなかったが、それは本人らの知り得ないことであった。更に言うとしのぶは、「賢い」子どもというわけでもなく、ただ、子どもらしくない「聡さ」を自然と身につけてしまっていたのである。
だからしのぶは、易々と次の日、自分の我儘を引っ込めた。これ以上愚図れば、母が……何よりも、穏やかな祖母が困ると、分かっていたからだった。
以来、しのぶは毎年、夏休みになると祖母宅へ1人で預けられるようになった。田舎という光景そのものが負担になるということもあり、頼子が息子と一緒に帰省することはなかった。
そうして、三年目……しのぶが、小学六年生になった時の事だった。小学校最後の夏休みも、やはりしのぶは祖母と過ごすことを選び、村へと入った。今年から村の夏は少しだけ変わった。地域興しのためか、小規模ながら夏祭りを開催するとのことだった。中心部のあたりで屋台が並び、いくつかのプログラムが執り行われた後、最後の催しとして花火が上がるのだという。村唯一の交番で配られていたチラシを手に取ったしのぶは、真っ直ぐ祖母の元へ帰った。
「ばーちゃん、これ行こう。おれ、これ行きたい」
そう言って、流し台の辺りで、大根や牛蒡などの根菜を洗っている祖母に紙を差し出すと、すぐに手を拭いてそれを受け取ってくれた。母ならばこうはいくまい、と思うのだ。祖母は頬に手を当てて、あらあらまあまあ、と細い眉尻を落として笑った。
「長さんが言うてはったやつやねぇ。へえー、結構大きいお祭りになるんやろか……」
長さんとは、他界した祖父の弟長次郎で、この村では有名な力持ちだった。力持ち、というだけのことで有名になるくらいには、たいへんな力持ちである。もう50にはなるが、巨躯と色黒の肌、その中で映える白い歯のおかげで、まだ40半ばほどにしか見えないような男だった。
「たのしい、らしいよ。お祭り」
「やろうなぁ、ばあちゃんも行きたいけど……うーん、そうやなあ」
祖母はどこか、返答の仕方に困っているように見えた。そういった表情には目敏いしのぶは、落ち着かない心地でばあちゃんからの返事をじっと待っていた。
「ばあちゃんな、最近ほんまに、足が悪いんよ……ノブくんみたいに、元気で屋台の方回ったり、出来ひんわぁ……」
「足?」
「うん、足腰がね」
そう言って腰をぽん、ぽん、と叩いて見せる祖母が、なんだかいつもより小さく見えた。しのぶは自分のズボンの裾を、ぎゅっと引っ張って握り締める。
「畑は行けんのに?」
そして、気が付けばそんな言葉を吐き出してしまっていた。祖母は僅かに瞼を押し上げて、 ほんの少し驚いたような顔でしのぶを見た。同年代の子どもの中ではいっとう大人しいしのぶは、祖母に対して棘を含んだ言葉を吐いたことがなかった。どれだけ聡くても、まだ齢十二の子どもが、吐いた言葉への責任がどのように自分にのしかかってくるか、全容をきちんと理解している筈もない。言ってしまってから、今の言葉の棘の長さをすぐに理解したしのぶは、小さくごめん、とだけ呟いて、祖母からチラシを引ったくり、そのまま自室へ逃げ込んでしまった。
しのぶは、両親の離婚と共に引っ越したが、その先で上手く友達が作れなかった。人の顔色を窺う癖が付きすぎて、どうにも周りに馴染めなかったのだ。自分の行動が相手の気を損ねないか、その部分にばかりびくびくと目をやってしまい、肝心の、相手の良い部分や、自分との共通点などを見つけられることが出来なくなっていたのである。そんなしのぶが、唯一心穏やかに、誰の顔も窺うことなくのびのびと子どもらしくあれる場所が、此処だった。
今の一言で、祖母は自分をどう思っただろうか。なるべく大人しく、なるべく優しい子だと思われるように振舞ってきたつもりだが、もしかすると、もう「良い子」の枠から外れてしまったかもしれない。「良い子」でなくなった自分は、祖母にまで見放されて、独りぼっちになってしまうかもしれない。この場所に、もう帰ってこられなくなるかもしれない。
しのぶはそれが恐ろしくて、真夏だというのに頭まですっぽりと布団をかぶってじっと体を小さく縮こまらせていた。いつの間にか眠りに落ち、全身が汗でびっしょりとなる頃には、祖母に呼ばれて夕飯の時間になっていた。祖母は今朝と何も変わらず、やはり穏やかでゆったりとしていて、先程のしのぶの発言など全く気にも留めていないようだった。しのぶは内心、ひどくほっとした。固めの根菜と、ほろほろと崩れそうな肉と豆腐の豚汁の味が、痛いほど腹の中に沁みた。美味しいですか?と柔らかく聞かれて、慌ててしのぶは、こくこくと首を勢い良く縦に降った。長年の表情から出来たものなのか、何重にも刻まれた笑み皺を作り、ふふふ、と喉の奥で高く笑う祖母を、しのぶはじっと見つめていた。
祖母の周りは、いつも時間がゆっくり流れているように感じた。都会の忙しなさに常に突き動かされている自分たち親子とは何処か違う。白いパンプスを履いて颯爽と街を歩くオフィスレディの母よりも、早朝から畑に出て野菜の世話をし、焼けにくい体質なのか一年中真っ白い肌に汗と泥を浮かべる祖母の方が、しのぶの目にはいつも優雅に映った。このばあちゃんと、祭りに行きたいな。しのぶは心の底からそう思った。
祭りの当日、しのぶはどこかソワソワとした気持ちで朝を迎えた。どうして自分が浮き足立っているのか、しのぶ本人にもよく分からないのだったが、朝、食卓に並んだ健康的な食事を見渡し、椅子の上で足をぶらぶらさせていると、祖母がその様子を見てくすくすと笑った。口元を小さく指先で隠し、目を細い三日月のような形にして笑う祖母を、しのぶはぱちぱちと目を瞬かせ不思議そうに見つめた。
「そうやったねえ、今日お祭りやもんね。楽しみやねえ」
どうやら、しのぶの様子を見て今日の催し事を思い出したらしい祖母は、ニコニコと笑いながら正面に座って先に手を合わせた。それを見て、慌ててしのぶも手を合わせていただきますをする。
「たんとお小遣いあげるから、楽しんでおいでね。ばあちゃんのことは気にせんと……」
その言葉を聞いて、しのぶの箸が止まった。
「どっかで道に迷うたらね、大人の人に言うたらええわ。梅の家、言うたらすぐ分かると思うからね」
「……うん」
「気を付けて行っといでな」
祖母の言葉は優しい。何も間違ってはいない。しのぶの身を案じる言葉を掛けてくれる。何も言っていないのにお小遣いもくれる。全てが正しい。
だのに、小さな不満を心の内に抱えてしまう自分が、しのぶは嫌だった。心のどこかで、祖母はなんやかんや言っても、自分と来てくれるような気がしていた。そんな筈はないのに。身体的な問題を抱えている祖母と、祭りをわいわいと楽しむことなんて、出来るはずがないのに。いつもより大人しく、少しうつむき加減になりながら朝餉をとるしのぶを見て、何かを察したのか、祖母はいつもよりあまり話しかけてこなかった。それも、しのぶの罪悪感を加速させるのだった。
祭りは、思ったよりも盛況していた。本当に、村中の人間がほとんど集まっているのではないかと思うほどに、どこもかしこも人が溢れていた。赤い暖簾のかかる、煙臭い屋台たちが立ち並び、どの大人も初めての祭りということでやや険しい面持ちであるのに、しのぶは最初怖気付いて、早々に家に引き返そうとしたが、祖母の「楽しんでおいでね」という言葉だけが足を引き止めた。
やがてしのぶは、祖母に持たされた赤いがま口財布を首から下げ、大事そうに握り締めているところを長次郎に見つかった。気の良い長次郎は、地元の子どもらとしのぶを会わせ、共に祭りを楽しむよう笑顔で促してくれた。子どもらはしのぶと違い、小さな甚平や金魚の泳ぐ浴衣などを着ていたが、皆やたらと陽気で、都会から来たしのぶを歓迎した。久しぶりに遊ぶ同年代たちとの時間は、しのぶを癒し、またそれまで胸に巣食っていた妙な靄を少しずつ払拭させた。地元の子どもらは、とにかくキラキラとしているように見えた。マセてもおらず、目の前の楽しいものに目をキラキラとさせ、年相応の可愛らしさがあった。しのぶにとって、その「可愛らしさ」は貴重だった。
「もうすぐ花火やなあ」
金魚鉢のような浴衣を着た女の子が溌剌と言った。もうすぐなのか、としのぶは素直に思った。焼きそばにたこ焼き、フランクフルト、たこせん、りんご飴と沢山のものを食べ、初めて会う子どもらと話しているうちに、盆踊りや和太鼓などの催し物はすっかり見逃しており、プログラム的にはもう最終段階に入ったようだった。
少女の言った通り、花火はすぐに始まった。ひゅーっ、と風船から空気が抜けるような高い音と共に、細い光の線が、淡い藍色の夏の夜空に舞い上がって、無音で弾けた。四方八方に、無数の花弁のように散った花火は、次の瞬間どぉん、という音を衝撃と共に齎した。ばちんと体を弾かれたような衝撃だった。間近で花火が上がるのを見るのは、しのぶにとって初めての体験であった。なんだか、夜の池に細かい花びらの花が浮かんでいるようだと思った。しのぶはその一発が上がった途端、何故か祖母を思い浮かべた。
ばあちゃんは今何をしているのだろう。
あの古びた日本家屋の、縁側の辺りから、一人でこの花火を見上げているのだろうか。祖母のことだから、きっと静かに微笑みながら、あら綺麗ね、なんて小さく呟いて見ているに違いない。あの絵画のような微笑みで、銀白色の髪を垂らしながら……寂しく微笑んでいるに、違いない。
気がつけば、しのぶは走っていた。人混みの波に逆流するように、走っていた。子どもらの呼び声が追いかけてきた。しかししのぶは止まらなかった。やがて他の子どもらの声も、花火の轟音に掻き消されて聞こえなくなった。いつしか聞こえるのは、砂利と泥の混じった地面を蹴る音と、自身の息切ればかり。喉を切るようなその音はひゅうひゅうと鳴り、花火の打ち上がる音に混じる。しのぶの四角い顎を、冷たい汗が伝った。短い毛を掻き分けて拭った額は、細かい汗の粒に塗れていた。
家に着き、ドタバタと忙しなく駆け込む。古く黒い木製の床がギィギィと低い音を立てるが、しのぶには瑣末なことだった。
「ばあちゃん」
家中に広がるような声だった。家屋の中では、花火よりもむしろ、しのぶの持つ子ども特有の高い声の方が大きく響いたのである。しのぶの予想は当たっており、祖母はやはり、縁側の方で硝子戸へ凭れ、片側の肩を預けたままぼうっと空を眺めていた。短い銀白の髪がかかる横顔は、何故かいつもより冷徹に映った。花火の虹色に混じり、ある一瞬白い光に照らされた祖母の顔は、しのぶには到底心中を察することが出来ないほど、深く重たい大人の相貌であった。それは寂寞なのか、はたまた何かを腹に鎮めようとする静かな怒りなのか、或いはそのどれでもなく虚無に近いのかは分からない。ただしかし、近付いてきたしのぶに気が付くと、途端に彼女の眉根が解け、口元が綻ぶので、しのぶは戸惑った。都会の人間らの冷たさとはまた違う、貼り付けるのに慣れたような祖母の笑顔に、しのぶは一瞬、そこに踏み込むのを躊躇ったのである。
「もお帰ってきたんかあ。怪我はないかいな、ノブくん」
「あ……ああ、うん」
「ノブくんおいで、一緒に花火見よか」
しのぶは頷くことをせず、ただ無言のままそちらへ寄り、祖母が背を預ける硝子戸とは反対の方へもたれかかった。何故、せっかく友達が出来そうだったのに祖母の元へ帰って来てしまったのか、しのぶ自身にも分からなくなってしまった。ただそれでも祖母が隣で、今日も百合の花のように淑やかに笑っているのなら。その横顔が、自身と同じく目に映る花火を見つめているのなら……なんだって良いかと思った。
例え、しのぶの前に見せる、穏やかな祖母としての顔が偽物でも、貼り付けられたものでも、良いかと思ったのだ。そもそも先程の表情の移り変わりだって、きっと少し疲れが顔を覗かせただけなのだ。祖母だけは、おばあちゃんだけは、この美しいひとだけは、しのぶの安寧でなくてはならないのだ。
「ばあちゃん、ずっと傍におって欲しい……おれ、ばあちゃんに、ほんまに、長生きしてほしい」
花火に感銘を打たれたように、幼い言葉ながら紡がれたしのぶの言葉に、祖母は嬉しそうに笑った。ははは、と乾いた笑いではあった。だが嬉しそうに笑っていた。しのぶには、嬉しそうに見えた。
「あんたな、東京戻ったら笑われるさかい、方言使わんとき。ここの子とちゃうんやから」
了
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
