
『灰のもと、色を探して。』第5話:起動
騒々しさで、ミリアは眼を覚ました。横を見ると、弟はもういなかった。どうやら、かなり眠っていたらしい。
慌てて着替え、階段をおりる。予想するまでもなく、騒ぎの中心は工房からだった。弟の声が混じっているのに、ミリアはさらなる不安を覚える。
辿りつくと、弟がスミスに取り押さえられていた。その先に会員がひとりいて、あとはその周りを囲むようにしている。
「アッシュ」
堪らず叫ぶと、会員たちがミリアの存在に気づいたのか、スミスまでの道を空けた。元へ駆け寄っても、弟はこちらを見ようとはしない。
「姉ちゃん。こいつ酷いんだ」
スミスに躰を固められているからか、弟は苦しそうに叫んだ。
「なんだと。おまえ、殴りかかってきやがって」
対して激昂しているのは、会員のなかでもかなり古いひとだった。老年に近く、発掘者として前線にいることはもう少ないが、勤続の長さによって待遇は特段によい。
「落ち着け、両方とも」
スミスは、泰然としている。反面、この場をどう鎮めたものかと、思案しているようにも見えた。
「なにがあったの、アッシュ?」
「こいつら、俺たちの手柄を横取りしようとしやがった」
「各会員の運は協会のものだ。おまえらだけの手柄ってことはないんだよ」
「あんたらのものでもない。勝手に取っていこうとするなんて、盗人のやることだろ」
「少し借りるだけだと言ったろう」
「それは、盗む時に使う台詞だ。スミスでも鑑定できないものを、おまえなんかが借りてどうするんだ」
「価値がわからないんだったら、なんでおまえら二人だけ報酬をもらえるんだよ」
吐き捨てるように、老人は言う。報酬がもらえるのか、と少し驚きながら、ミリアは騒動の原因が見えてきていた。
ミリアたちに報酬が出る。新人の成果が認められることに対しての、古参たちのやっかみだ。
「それは、先ほど説明しただろう」
会員たちに聞こえるように、スミスは間に入る。
「腕輪は関係ない。二人の成果はそちらではなく、遺跡に新たな探索の可能性を見つけたことだ。未踏遺跡の発見に対する報酬は、規定通りだろうが」
「単純に壊しただけかもしれないだろう。なんだかんだと言って、スミスは結局こいつらをひいきしたいだけなんじゃないか」
勢いよく言ってから、老人は眼を見開く。顔に、恐怖が刻まれていくようだった。
「俺を、侮辱するか」
アッシュから腕を離し、スミスは自然体で老人に対峙する。その言葉は静かだったが、この場のだれよりも強かった。猛獣の尾を踏んだ狩人のように、老人の表情は急速に曇っていく。
「こうしませんか?」
切り裂くように、透明な声だった。そして、その声の主を、ミリアは知っている。
「ギマライ」
特に意図的といった風でもなく、スミスはその名を呼ぶ。
「スミスさん、おはようございます」
お昼だったが、今日はじめて工房へと出むいたのだろう。ギマライは、ゆったりとした調子で歩いてくる。彼がなにかに急いでいたり、焦ったりするところを、ミリアは見たことがない。
まるで救世主が登場したかのように、老人に広がる安心めいた空気を、ミリアは認めた。
「多分、今日スミスさんは遺跡に行きますよね? 検分するために」
ギマライは、話を続ける。丁寧で、物腰が柔らかく、才気にあふれている。言動も滑らかで、外見も整っているため、街の女たちからの恋慕も集めていた。確かまだ二十をいくつか過ぎたころのはずだが、新古を問わず会員からの信頼が篤く、スミスからも一目置かれている。
ミリアと同期であり、一緒に発掘へ行ったこともある。
そして、ミリアはギマライの声を聞くと、心がざらつく。暗い湖の奥底へ沈んでいる箱。その中身が外へ出たいと騒ぎはじめ、湖に波が立つようだった。
「そうだな」
「ミリアとアッシュも連れていきますよね?」
名前を呼ばないでほしかったが、そう伝えることはしない。会話をしたくないからだ。嵐が通るのを、ミリアはただ待つ。
「あの遺跡の担当だからな」
「私も同行させてください」
変な申し出だった。未踏遺跡が発見された時、次の手続きは二つに分かれる。その発掘者のみで調査を続けるか、会長の同席のもとで行われるかだ。それは、危険の度合いや担当発掘者の熟練度で決まる。そこに別の会員が入ってくることは、まずない。
「なにがしたいんだ、ギマライ?」
「例外とはなりますが、私という第三者が行くことで、みんなも納得するかと思いました」
口角を、ギマライは少しだけあげている。笑っているでもなく、真剣めいてもいない。空気を柔らかくするために、最適な表情を作っている、とミリアは思った。
「価値のわからない腕輪と、未踏遺跡。現時点で、これらの成果が未定だとしても、人はよい方を期待してしまうものです。私もそうです。そして、その発掘者は、スミスさんの我が子同然と言っても差し支えない二人です。失礼を承知で申しあげますが、スミスさんは彼女らの後見人ということを、もう少しご自覚なさるべきです」
スミスの瞳が、一瞬鋭さを増す。それを悟られないためか、スミスは静かに眼を閉じた。
「みんなが懸念しているのは、成果の独占です。私の追行は、お三方にとっても、悪くない話だと思います。やましいことなどなにもない、という証左にもなるわけですから。若輩ですが、この協会に属してから一度も成果を私したことはありませんし、ほかの会員がそうするのを許したこともありません」
周囲から、賛成を示す声があがる。おそらく、ギマライの言い分が正しいと思っているのではなく、早くこの諍いから解放されたいのだ。
そして、ギマライが言うのであれば、という雰囲気が、この協会内には色濃くある。それがミリアには嫌だったが、実際、スミスを相手に真っ向から提言できるのは、ギマライくらいしかいないのも事実だった。勇気なのか打算なのか、どちらにせよ行動力という点で、他者より一歩も二歩もギマライは進んでいる。
考えたくもないことだが、次期の会長はギマライではないか、という噂もあるくらいだ。
「わかった」
眼を開き、スミスは短く言った。感情は、ひとつとして見せていない。
「この件は、ギマライの同道で論を落とす。いいな」
会員たちから、了承を示す返事が相次ぐ。絡んでいた老人は、不愉快という顔を崩さず、足早に工房から出て行った。すぐに散開となり、ミリアは弟と一緒に部屋に戻り、支度を済ませた。場に戻ると、スミスとギマライが二人だけでいた。検分ではあったが、発掘の用具は持っていくようだ。
「むかうぞ。ギマライ、馬車を出せ」
「はい、スミスさん」
「ギマライさん、俺も手伝います」
弟の言動に、不快感を声にしてしまいそうで、ミリアは口を手で押さえる。姉の気を知らず、弟は溌溂としていた。
「ありがとう、アッシュ。ミリア、弟を借りるよ」
「どうぞ」
なんとか、言葉を作った。
「ギマライさんは、すごいなあ。あの場をなんとかしちゃうんだから」
原因が自分だと思っていないのか、外へむかいながら、悪びれもせずに弟はギマライを賛美する。
「ありがとう。でも本当にすごいのは、だれよりも責任のある立場にいながら、俺みたいな者の意見を聞き入れてくれる、スミスさんだよ」
屈託のない笑顔で返しながら、ギマライは弟と一緒に出て行った。実力、才覚ともに申し分のない好青年。弟が彼に憧れる理由は、数えるだけ無駄というものだ。
そして、それを止めたくとも、ミリアには術がない。
明るさが、自らのしたことを、より明るみに出す。
「予想以上だな」
「ええ、まさかこれほどとは」
スミスとギマライが、ぽつりと感想を洩らした。
崩落してしまった遺跡。四人は、昨日弟を引き留めた階段の入口まで来ていた。屋根はとうになく、地下にいながらも、真昼の太陽の射しこみは強い。それでも、階段は途中で見えなくなってしまう。あの時より平静であるせいか、崩れ落ちた部分の大きさは一層拡がって見えた。
「早く行きましょう」
湧きあがる冒険心を抑えきれないのか、弟は早速灯火具を点けていた。腕輪をひとつ、腕に通している。もうひとつは、ギマライが持っていた。
「少しずつ降りるぞ。階段が脆くなっているかもしれん。先頭は俺、殿しんがりはギマライだ」
「はい」
言いながら、スミスはたすきがけした帯を触る。しばらくして、その帯の胸部にある機械から、前方に光が出た。おそらく、発掘された過去の技術なのだろう。手を塞がずに、明かりを担保できる。小型の灯火具のようなものが帯に付いている。
「便利ですね、それ。私に売ってくださいよ」
「発掘者だろう、ギマライ。自分でどうにかしろ」
「仰る通り」
階段は、崩落したあととは思えないほど強固で、そして綺麗な状態だった。もしかしたら本当に未踏なのかもしれない。
降りていくと、やがて完全に陽射しが届かなくなった。折り返しもなく、階段はただ直線に続いていた。四人の階段を降りる音だけが遠く響く。相当な広さのようだった。主な明かりは、スミスとアッシュの灯火具だけとなった。長く降り続けている気がするが、スミスが一段一段確かめるように進んでいるため、実際の深さはわからない。
「スミス、あ、スミスさんは、こういう遺跡は過去に経験したことあるんですか」
不慣れな敬語で、弟は尋ねる。
「俺は、はじめてだよ、アッシュ」
返事のないスミスに代わり、ギマライが相手をする。彼に後ろから見られている、と意識すると、かすかに寒気を感じる。
「でも、ギマライさんは、未踏遺跡を何度も発見してるじゃないですか」
「それはそうなんだけどね、未踏とはいえ、遺跡は遺跡だからさ。基本的にはとても古いし、あちらこちらが風化浸食されて、まあすぐ崩れるのなんのって」
「そうなんですか」
弟は、嬉々としている。暗がりのなかにいても、弟の瞳が輝いていることは確実だった。
「それらに比べ、ここは未踏遺跡のなかでも、当時のものがそのまま保存されているような気がするよ。普通は、ここまで安定した階段なんてないもの」
スミスは、会話に入ってこない。安全の確保に気を割いているのか、単純に話に加わる気がないのか。なんとなく、ミリアには後者に思えた。
「あとは、なんだろうね。勘の範疇を出ないんだけど、安全だと思ってしまう。そういう変な空気が、ここにはある。多分、スミスさんも感じてるんじゃないかな。だから、階段の踏みしめも、徐々に躊躇がなくなっている」
「ギマライ」
叱られ、小さく謝るギマライを見、弟は快活に笑っている。この場を楽しめていないのは、きっと自分だけだ。特になにも起こらず帰れるといいなと、どこかで思っている。
「あれ」
その期待を剥がすような違和感が、前方から放たれている。
「どうした、ミリア」
「いや、この先になにかが見えたような」
「気がしただけじゃないの、姉ちゃん?」
「うるさいわね。そんなことよりアッシュ、腕輪をそうやって変に持って、落として壊れても知らないわよ。せっかく、所持を許可してもらったのに」
正確には、ひたすらに弟が懇願し、ギマライがスミスを説得した、というかたちだった。工房に置いておくと、盗まれる可能性がある、と理屈を添えて。出がけで、ほかの会員たちの眼もなかったため、決裁がおりたというのもあるだろう。それを弟が持っているのは、スミスがアッシュに根負けしたためだ。もうひとつは、第三者であるギマライが所持することで、話は決着した。
どうしても、スミスは際の際で、自分たちに優しさが出る。
「わかってるってば」
少しばつの悪そうに弟は反応してから、腕輪を腕に着け直した。
青い。最初にミリアが認識したことは、色だった。次に、それが光だとわかる。
「うわ」
声にならない声を、弟があげる。その腕が、青い光に包まれていた。昨晩見たものと、同じ定量の光。ただ、色が違い、その大きさは倍以上だった。辺りに、青さが反射していく。
「アッシュ、大丈夫か」
降りるのを中断し、スミスは素早く弟へと寄った。灯火具を取りあげ、階段の上に置く。
「腕輪が、光っているのか?」
背後で、ギマライが呟く。ミリアの後ろから、動く気配は見せない。
光が消える。スミスが、弟から腕輪を取り外していた。
「怪我は」
「ない、と思います。火傷とかも、別に」
「この光、昨日も出ていました。今のは、その時よりもずっと強いですが。あと」
言ってから、ミリアは悔やむ。不確かな情報は、弟のためにも出すべきではない。
「あと?」
見透かしたかのように、ギマライが訊いてくる。話を濁させない、という意思を感じた。
「どことなく、階段の奥にむかって伸びていたと思う」
ギマライへ振りむくことはせず、ミリアは返す。
「なにか、あるのかもね、もう少し先に」
考えながら、ギマライは話しているようだった。
「もう一度、腕輪を着けてみなよ、アッシュ」
「ギマライ」
「大丈夫ですって、スミスさん。害意のある遺物なら、今アッシュは無事じゃないですよ。光も、禍々しさを感じなかったじゃないですか」
淡々と、ギマライは言葉を連ねる。弟の躰など、まったく気にしていないようだった。そしてこれが、彼の本質なのだと改めて認識する。
自分の損得以外に興味がない。彼はそういう人間だ。
「着けてみます」
「駄目よ、アッシュ。危ないわ」
「なら、ミリアが着けて?」
飄々とこちらを見てくるギマライに、やられた、とミリアは思った。彼は、最初から自分にやらせようとしていたのだ。いや、最終的に弟かミリア、どちらかがやればいいと考えていたのか。なんにせよ、ここでの撤退など、ギマライに許すつもりはないということだ。
「ギマライ」
「引き返す、というのはさすがにないですよ、スミスさん。それでは、二人に甘すぎる。得られるものも得られませんし、会員のみんなも、納得しないです」
「平気だって、姉ちゃん。本当に、痛くも痒くもないんだから」
「なら、わたしも着ける。スミス、いいでしょう?」
「ええ。どうぞ」
「あなたには訊いてないわ、ギマライ」
ギマライから差し出された腕輪を、乱暴に掴んで腕に通した。弟も、慌てた様子を見せながら、腕輪を再び装着する。
光が、滲み出てくる。ゆっくりと這うように二人の躰を覆い、包んでいく。灯火具の光と混ざり、妙な彩りを周囲に反射させていく。
そして光の一部が、やはり階段の先に伸びていた。
「なにか異常は、ミリア?」
「大丈夫です、スミスさん。あくまで、今のところはですが」
青い光に眉をひそめながら、スミスは尋ねてきた。
「思った通り、腕輪に関係したなにかが、この奥にあるようですね。これは楽しみだなあ」
高揚した口調で、ギマライは言う。
「行こう、スミスさん」
「おい、俺より先に進むな」
弟は灯火具も持たずに、階段を降りていく。その顔は、好奇心に満たされているようで、どこか焦りを感じさせるものだった。追いかけるように、スミスの重い足音が続いた。
「さあ、ミリア、俺たちも」
ギマライを睨み、ミリアは灯火具を持って二人を追った。最低、と胸中で毒づく。後ろで、ギマライが肩をすくめた気がした。
階下は、正方形の部屋だった。広大で、天井は高い。
「明るい」
思わず、声に出ていた。薄暗かった階段とは異なり、ここは真昼がそのまま落下してきたかのように、眩しい光にあふれていたのだ。
壁と床が、異質だった。すべてが白一色で構成され、素材も煉瓦や版築ではない、金属で造られていそうだった。その内装が光を反射し、さらに室内を明るく照らしている。
「どうやら、太陽の光を集積しているみたいだな」
天井を仰ぎながら、スミスが呟く。その声は、普段より高く聞こえた。
「そんなことが、可能なのですか」
「理論上はな。ここまでのものは、俺もはじめてだが」
「その卓越した技術も、すべてはあの柱のために用意されたようですね」
言われて、ミリアは視線をやる。部屋の中心より奥まった場所に、同じく白色で統一された柱が、ひとつそびえていた。天井まで届きそうで、上に進むにつれ細くなっている。
気づくと、その前に弟が立っていた。
「アッシュ、不用意すぎるわ」
「姉ちゃんは、そこにいて」
遺跡にとって大事な場所であればあるほど、危険は潜む。侵入者を撃退する罠もあれば、こちらを試すような仕掛けがあったりする。時には、命を奪われることもあり、協会内でも毎年死者が出ていた。
そのことを、弟がわかっていないはずがない。事前に、スミスにも厳しく言われているのだ。そこまで考えてから、ミリアの心中にひとつの答えが浮かぶ。
弟は、間近に迫ってきている大きな手柄を、とにかく立てたいのだ。協会の人たちを唸らせるような結果を、手に入れたがっている。ギマライという優秀な発掘者が隣にいることで、その思いは一層強まっている。

「そうはいかないわよ」
駆け寄りながら、声を荒げた。後方から、スミスの舌打ちが聞こえる。
弟の熱量、そしてその反動である焦燥感は、自分たち二人のためだとわかっている。それでも、危険に臨んでいることに変わりはないのだ。
「姉ちゃん、こっちは危ない。戻って」
「どの口が」
「光ってる。腕輪が指していたものは、多分これだ」
会話をしているようで、していないとミリアは思った。弟は、眼前の興味と自分への思いやりで、きっと頭が回っていない。
青い光は、先ほどよりも力強く、柱にむかっていた。
「どうした」
スミスまで、こちらに来ていた。
「すみません。腕輪から発されていた光が、柱と関係あるのでは、とアッシュが言っていて」
振り返り、説明する。視界の隅に捉えたギマライは、その場を動いていなかった。当然だ、とミリアは思う。遺跡の最奥部と推測される場所は、最も慎重に行動すべきところだ。そしてミリアたちは、その最奥部の、さらに重要と思われる位置にいる。ものを投げて歩けるかどうかを確かめ、壁という壁を叩いてからでも、ここに立つのは遅くない。
逆に、やはりスミスはミリアたちに甘いのだ。会長という立場より、亡き父母の代わりに、危機の可能性を共有しようとしてくれている。
「同伴の仕方も、考えなければならないな」
「すみません」
苦々しく溜め息を吐くスミスとは対照的に、ギマライは薄らと笑みを浮かべている。愚かな自分たちを侮蔑し、嘲っているのだろうか。好きにすればいい、とミリアは弟に顔をむける。
成果を得られたとしても、絶対にギマライには分けない。
「姉ちゃん、いいから、離れて」
今の弟には、苦言も制止も届かないのだろう。ただ急せくように、柱と対峙している。
青い光はさらに太くなる。風のように漂っていたものが、道と言ってもいいほどになっていた。
導かれるように、弟は手を柱へ伸ばした。
腕輪から、音が聞こえた。雛が鳴くようでいて、聞いたことのない、短くて高い音だった。
柱が消える。文字通り、輪郭が泡と化し、蒸発するかのように霧散した。
球体が、浮いていた。大人の頭のほどの大きさで、漆黒のそれは、真っ白な空間のなかに突如としてできた穴にも見えた。小さく緩やかに、昇降を繰り返している。
「浮いている、のか」
スミスも、事態に追いつけていないようだった。珍しく、硬く閉じがちな口が開いている。
「すごい」
そう呟く弟の手を、ミリアは握っていた。極まった未知に対し、ミリアは場を見守ることしかできない。
それを見計らったかのように、二人を纏っていた光は、一段と大きく輝きを放った。視界が青く染まり、そのすべてが黒い球体へ吸いこまれていく。
「予想以上だ」
いつの間に近づいていたのか、ギマライが感想をこぼす。しかしミリアには、悪態をついたり、嫌な感情を差しむけたりする余裕はなかった。
躰が浮く。弟と眼が合う。視界がわずかに、歪んだ気がした。
「ミリア、アッシュ」
スミスが叫んだ。その声も、球体へ取りこまれるように遠くなる。
こんな表情のスミスを見るのは、いつぶりだろう。
帳の降りゆく意識の片隅で、ミリアは思った。
ーーーーーーーーーー
こちらのイラストは、ひわ様に描いていただきました。
改めまして、この度はご協力いただきありがとうございました。
ーーーーーーーーーー
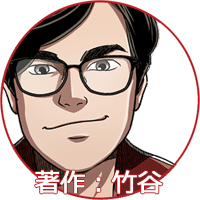
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
