
『灰のもと、色を探して。』第10話:焚火
明と熱。
火を熾す理由は、大別するとそんなところだ。暗がりをなくすためか、暖を取るためか。徐々に勢いの強まる火を見ながら、ヒューは思った。今回は、熱のためである。
「いつ見ても、うまいなあ」
のんびりと、アッシュが言った。火口を作り、発火させる一連の流れを、先ほどから近くで見られていた。
「好きなんですよね、この一連の作業が」
「ヒューがそうやって着々と焚き火を進めてくの、俺も好きだよ」
アッシュは、労せずして火を呼び出すことができる。それでも、火を作る時は、ヒューに任せていた。彼曰く、その行為は魔法に頼ってはいけないような気がする、とのことだった。その感覚は、わからなくもない。
便利であっても、節度や、越えてはいけない線がきっとある。
治癒の魔法は、傷を内外問わず治せる。しかし、感冒は治療しないし、寿命を無理に延長させるような術も唱えることはない。人が付き合うべき不調には、魔法で対抗してはならないという不文律のようなものが、ヒューの中にはある。アッシュにも、火に対する哲学が存在しているのだろう。力は、分別があってこそ力と言える。
中天は過ぎ、そろそろ日没だった。それは、今日の旅の終わりを、三人のあちらの世界への帰還を、そして、ひとりの夜のはじまりを意味していた。
だれが決めたというわけでもなく、これくらいの時間になると、皆で火を中心に車座となり、飲食しながら雑談に耽るようになっていた。
今日は、小川の近くに、場所を取っている。
ヒューにとってこのひと時は、なによりも尊いものだった。
火勢で枝の弾ける音が、耳に小気味よく入ってくる。
「あったかいなあ」
両手をかざしながら、アッシュは間の抜けた声を出した。
「今までは夜の篝のためでしたが、そろそろ寒さが気になる季節ですね」
「太陽の位置も、変わるんだよ」
知らないことだった。この少年に嘘はなく、感じていることがすぐわかる。得意そうな彼の瞳を見つめ、ヒューは微笑んだ。
「そうなんですか」
「夏は、真上にあるんだけど、冬は斜めになる」
「なぜ、そうなるんでしょうか?」
「さあ。そういうものとしか、教わってないなあ。ゾヴは、知らないの?」
「知らないと思います。訊いたわけではありませんが、彼の知識は、この世界特有の現象に限られていますから」
「かゆいところに、手が届かないもんだね」
アッシュの落胆めいた返しに、ヒューは笑い声を立てる。
夜はひとりになる。しかし、話し相手はいた。これもまた、決まりごとのように、毎晩ゾヴとの対話がはじまる。内容は、この世界の過去と現在における、その経緯と展望が主だった。
眷属としての格を取り戻したヒューに、知るべき空白の期間はあまりにも多い。
使徒たちの不在により、眷属たちに誤作動が起きていく中でも、ゾヴは自身の役割を忘れなかった。自らの上位的な存在、という構造上の概念を差し引いても、ヒューは天使である彼に尊敬の念を抱かずにはいられない。
日中、ゾヴは遠慮しているのか、話しかけてこなくなった。その分を、夜に集中させている節がある。ヒューにとって、それは都合がよかった。
皆といる時に、ゾヴの声に応じるのは、どこか後ろめたい。ヒューは全員と話せても、アッシュたちからはゾヴが、ゾヴからはアッシュたちがいないのだ。
その伝言役も、もう少しで終わる。造物主の石庭に着けば、彼らはゾヴと直接話すことができる。そして、再創世が開始される。
そのあとのことは考えない。今はただ、与えられた役割を果たしたかった。
「ただいま」
軽やかに、ミリアは手を振りながら木陰から出てきた。同じく、ヒューは手を振り返す。溌剌とした彼女の表情に、きっと狩りがうまくいったのだとヒューは思った。やや遅れて、ギマライと色丸も姿を現す。
「もうちょっと、ゆっくり歩いてくれないかなあ」
息を荒げながら、ギマライは言う。その後ろに、五匹の兎が歩いていた。今日の食糧だ。
「兎だ。よく見つけたね、姉ちゃん」
「ミリアの追跡は、どんどん上達しているよ。迷いがない」
「身体能力に伴い、五感も研ぎ澄まされているのだと思います」
兎が逃げずに二人に追従しているのは、ほかでもないギマライの操作魔法だった。
死んだ生き物は操れない。殺してしまうと操れなくなり、運ぶのに骨が折れる。ならば、生きた状態で連れてくる、という考えだった。正直なところ、ミリアの膂力なら軽々と持てるはずだが、ギマライの操作魔法の鍛錬も兼ねているようだ。追いこむのがミリアで、連れてくるのがギマライ。そう二人は分担している。
狩りで操作魔法を用いることに、ギマライは抵抗がないとのことだった。やはり、持つものの哲学は十人十色なのだろう。
自分の槍、その先端に巻いていた短剣は、今はミリアが所持していた。巨大な斧は、魔物との戦闘以外ではあまり有用ではないらしい。木々に成る実を採取したり、魚を捌いたりする時、ミリアは常に短剣を用いる。慣れた手つきで取り出すと、眼を閉じ、祈るようになにかを呟いてから兎の頭を斬っていく。血を小川に流しながら、皮を剥いで肉を切り分ける。最初はヒューが担当していたが、やがてミリアが専任するようになっていた。今では、自分よりも手際がいい。
一口大に切られた肉を、集めておいた枝にいくつか刺して、炎の近くに立てる。色丸の分は、そのまま地面に置いた。好き嫌いはないようで、色丸は出されたものはすべて食べる。それで、この丸々とした体型なのか、とヒューは妙に得心していた。食べない部位や内臓は、穴を掘って埋めた。
肉の焼ける匂いが鼻をくすぐり、脂の滴る音が鳴る。
「最近、ゾヴとはどんな会話をしてるの?」
待ちきれないように、枝を忙しなく回しながらアッシュが訊いてきた。
「いつもと変わらないですよ。残りの距離や、地域の風土で気をつけるべきことなど、です」
「でも、毎日なんでしょ?」
「そうですね、日々、進捗は報告しています」
「大変だなあ、ヒューは」
「そんなことないですよ。わたしは今、使命感に燃えています」
拳を作りながら返すと、アッシュは笑った。
「使命感、ねえ」
ギマライが入ってくる。魔法をやっと解除できたからか、少しゆったりとした調子だった。
「それは、再創世する、という使命?」
ギマライは、言葉を続ける。
「同じと言えます。皆さんを、ゾヴのもとへ連れていくことです」
「わたしは、ヒューといられれば満足なんだけどなあ」
血にまみれた手を洗い終え、ミリアが隣に座ってくる。ほのかに、鉄の匂いが漂った。
「わたしもそうなんですけど、こればかりは、わたしがやらないと」
ヒューから見る限り、ミリアは、ゾヴのことが好きではなさそうだった。理由は訊いていないし、訊ける気もしない。会えばきっと氷解するものだと、どこかで楽観している自分がいる。
「もう、食べていいかな?」
「まだ早いわよ、アッシュ。なにもかけていないし」
そのやり取りを聞きながら、ヒューは袋から小さな布袋を取り出した。中には、塩が入っている。旅へ出る際、家からくすねたものだ。道中で、海水から精製した塩を継ぎ足しているため、味は多少変わった気がする。
料理とは呼べない、焼いた肉に塩を振ったもの。しかし、満たされるものがとてもある。それは肉に対する根源的な欲求か、もしくは、一緒に食べる相手によるものか。
ぱらぱらと、それぞれの肉に塩を振った。塩を撒く役目はヒューだった。それも、決めたわけではない。
「いただきます」
我慢できなさそうに、アッシュは串を取ると、勢いよく肉を頬張った。直後、感極まった声を漏らす。
「この瞬間が、なにより幸せ」
「食べるか話すか、どちらかにしなさい」
もごもごと言うアッシュに、ミリアが肩をすくめた。ギマライとミリアは、焼きあがるのを待っている。
「ヒュー、なにか話して?」
ミリアは、甘えるような口調だ。こそばゆさを覚えるが、悪い気はしない。
ここのところ、ミリアたちが灰の国と呼ぶ、この世界の話をすることが多くなっていた。誤作動が起こる前の、世界の成り立ち。魔物の種類や、有名な使徒の奇譚など、眷属として知っていることや、ゾヴに教えてもらったことを話していた。
「そうですね、なにがいいですか?」
「熄岩王は?」
すでに食べ終えてしまい、アッシュは枝で遊びながら言う。同じく完食している色丸も、食後の運動なのか、アッシュに構ってもらいたそうに近くを回っている。
「その話好きねえ、アッシュ」
遥か昔に、使徒でありながら神格化された存在だった。火の魔法に探求を重ね、その上位魔法を見出した。学術的な方面でも功績は多いが、その反動のように色香の濃い生を送っている。もちろん、アッシュが好んでいるのは前者で、後者はまだ話していない。正直、話すのが恥ずかしくもある。
「魔法の種類については、どうかな?」
ギマライが尋ねてくる。話したがっていない自分を、きっと察してくれたのだろう。
「わかりました。今日は魔法の属性についてお話しましょう」
「属性? 俺は、熄岩王がいいなあ」
「彼にも通ずることですから、アッシュさん」
唇を尖らすアッシュに、ヒューは微笑んだ。
「まず、属性というのは、魔法に与えられた位置、と考えてください」
「位置。たとえば、北と南のような?」
「その通りです、ギマライさん。ただ、魔法の場合、属性は左右と上下により決まってきます」
空になった枝で、ヒューは地面に小さく四角を書いた。
「これが、自分のいる場所だと思ってください」
続けて、その上辺に火、そして下辺に水と書く。
「火は、昇ります。有形でありながら無形のように、多少覆ったくらいではどうにもできないほど、空へ空へとあがっていきます。反対に、水は沈みます。どのかたちにも変形できる水は、すべてを潜って、深く深く落ちていきます」
「真逆だね」
「そうですね。そして、どこまでも昇った先には、天があります。神々の領域です。それを見出したのが、熄岩王とされています」
火のさらに上に、ヒューは天と記した。
「神々か。灰の国にも、そういう存在はいるんだね」
ギマライの、抑揚のない口調の中に、なにか針のような尖りをヒューは感じた。いや、気のせいかもしれない。
「はい。おそらく、皆さんの国と、そこまで変わらないかと思いますが」
「だとしたら、信仰深くなっちゃあ駄目だね。きっとなにもしてくれないから」
ギマライは笑い声を立てた。勘違いではない、とヒューは思った。いかにも軽く、という風で、その実、彼の口調はなぜか重い余韻を残している。
「それで? 天を見出したというのは」
ミリアとアッシュに、それを気にした様子はない。ミリアは淡々と聞いており、アッシュは不満げな表情の中に、好奇心が見え隠れしてきている。自分だけが、ギマライの異変を感じ取ったのだろうか。
「ヒュー?」
「はい、ええと、そうですね」
ギマライの催促に、若干うろたえてしまう。今は属性の説明をしなければ、とヒューは浮かびつつあった疑問を霧散させた。
「火の魔法を究めていくうちに、火だけでは説明のつかない魔法が出てきました。それを火と分別するために、天という属性が作られたのです」
「どういう魔法なの?」
前傾しながら、アッシュが訊いてきた。
「たとえば、圧倒的な光で、夜を昼に変えてしまうとか、すさまじい高熱で、大地や海のすべてのものを瞬時にして溶かすとか、そういった類です」
「すごい」
「水にも、さらに上位があるのかしら?」
感嘆の息を吐いて、興奮気味に立ちあがるアッシュに比べ、ミリアは脚を揃えて曲げ、膝のところに手を置いている。彼女は、いたって雑談の域を出ないような雰囲気だ。
「冥、と呼ばれます。こちらは、死者たちの領域で、決して触れてはならないものと伝えられています。実際に、この属性を扱えた使徒はいません」
「へえ。いかにも危なそうな感じだものね」
「かつて、冥魔法を使用できる魔物がいたらしいですが、その際は、墓という墓からひとが蘇り、しかしその外見や精神は別物だったといわれています」
「死者が生き返るわけではない、と」
「その通りです、ギマライさん。死を覆すことは、できません」
すでに、全員が兎を食べ終えていた。水筒を開け、作っておいたお茶を椀へ移す。旅路の途中で見つけた薬草を細かく刻んで、乾燥させてから揉んでおいたものを、昨晩お湯に浸しておいた。その椀を、皆で回しては飲んでいく。アッシュが飲み干して、なお欲しそうな顔を見せたので、さらに注いだ。
「わたしやギマライの魔法にも、属性はあるの?」
ミリアの問いを受け、ヒューは先ほどの四角形の左に土を、右に風と書いていく。
「そうですね。火と水が上下に対し、左右は風と土です。火水土風は、四大属性と呼ばれ、この世界のすべてを作る根幹です。そして、土の上位は金であり、風の上位は雷です」
土の左側に金、風の右側に雷を追記する。
「属性はその上下左右のどれか、またその組み合わせで決まり、ギマライさんの場合は水と雷の合わせで操作となります」
雷の下、つまり、水の二つ右に、操作と書いた。
「それが、なにか変なのかな?」
ギマライから、刺々しさは消えていた。やはり、自分が変に勘ぐっただけなのだろう。
「雷は、上位属性です。天と冥に比較すれば習得が易しいですが、それでも上位であることに変わりはありません。風の鍛錬をたくさん積んで、ようやく使える魔法です」
「ふうん、そうなのか。苦しまずして得ている俺は、幸運ってことか」
言葉を理解しているわけはないが、返事をするかのように、色丸がひとつ大きく鳴いた。
「もしくは、ギマライさんの中に強烈な思いがあって、この結果なのかもしれません。異常は、常にひとの常ならざる意思から生まれますから」
「なるほど。操作ね」
「わたしは?」
言いながら、ミリアはヒューの膝に頭を寄せ、上目遣いでこちらを伺う。気に入っているのか、最近よくミリアに膝枕を頼まれていた。ミリアの方が年上なのに、とは思うが、甘えられていることに、心はふくよかに弾む。高品質な枕となるよう、座り方を直し、手で軽く膝を払ってから、どうぞ、と仕草で促した。嬉しそうに、ミリアはヒューの大腿に後頭部を埋め、眼を細めてこちらを見てくる。満足してもらえたようだった。
「いいなあ」
よくわからない感想をアッシュが漏らすが、意図は問わない。そして、待ちかねたように、色丸がミリアのお腹に乗ってきた。特に気にする風でもなく、ミリアは色丸の顔を撫でる。いつか自分も色丸のようにやってみたい、とヒューは内心で決意を固めた。

「ミリアさんは、すべての属性の中央にある、動物そのものの原始的な力を司る属性で、獣とされます」
四角の中に、ヒューは獣を書き入れる。ミリアのせいで、少し書きづらいのがおかしかった。
「獣。なんか、かわいくないような」
「ふふふ、ミリアさんお綺麗なのに、獣なんです。怖いですね」
「襲うわよ」
わざとらしい威嚇の表情を作るミリアに、ヒューはさらに笑ってしまう。
「質問、ねえ質問」
「なんでしょうか、アッシュさん」
「俺は火以外を使うことはできないの?」
「相性はありますが、できます。ただ、相反する水は、どうやっても習得できません」
「恐ろしい獣のわたしは?」
「獣は、どこにも属さないからこそ、すべての属性を用いることができる、と言われています。とはいえ、これもやはり相性がありますから、あくまでも理論上は、というところですが。ちなみに、わたしの治癒は水と土の合わせですね」
そういえば、ゾヴの属性はなんだろうか。今晩にでも、訊いてみようと思った。
「いやあ、頭が整理できない」
自分の頭をがしがしと触りながら、アッシュが唸る。
「でも、要は好きなのを伸ばせばいいんだよね? じゃあ、俺は火だけでいいや」
「はい。あまり難しく考えず、能力を育てていくことが大事だと、わたしも思います」
「はい、ヒュー先生、まったくわかりました」
仰々しくアッシュは応じ、ヒューはまた笑った。
そして、あたたかだと思う時間は、容赦なく過ぎ去っていく。
くぐもった黒い空を見あげ、ヒューはため息をついた。
三人があちらの世界に戻ってから、いくらか時間が経っていた。風が強い。そう思うのは、ひとりでいるからだろう。火は、少し弱くなっている。
「こんばんは、ヒュー」
「こんばんは、ゾヴ」
まるで眼前にいるかのように、ゾヴの声は届く。そして彼の声は、いつ聞いても美しいと感じた。静かで、ゆったりとしているが、高揚感を覚えるのだ。
「今日は、属性の話をしていましたね」
「はい、ゾヴ。それで、気になったことがあるのですが」
「ほう。どうしましたか」
「ゾヴは、どの属性を備えているのでしょうか」
「なるほど。そうですね」
風がさらに吹く。消えないように抵抗しているのか、焚火は一段と踊った。
「隠すほどのことでもないのですが、内緒にしておきます」
「はあ」
「まあ、お会いした時の楽しみにでもしておきましょう。念のためお伝えしておくと、ヒューや使徒の皆さんとは、別の属性です」
「わかりました。少し、気になっただけですので」
ゾヴにも、内緒にする、といった感覚があるのだなとヒューは思った。それは、今までのゾヴにはないことで、不思議でありながらも、どこか面白かった。
「最後に、ヒュー、確認をしましょう」
ほかの報告事項を済ませると、ゾヴは言ってきた。暗に、対話の終わりを示す言葉となっていた。信心深い神父の祈りのように、日々繰り返している。
「はい」
「ヒュー、あなたの本来の役割はなんですか?」
「村の女として、村とともに生き、新たな生命を育み、村の中で生を終えることです」
「では、今の役割はなんですか?」
「使徒の皆さんを、この命に代えても、造物主の石庭へ連れて行くことです」
「そのために、ゆめゆめ犯してはならないことは?」
「天使、あなたの意向に叛くことです」
「では、ヒュー、また明日」
「また明日、ゾヴ」
一気に、暗くなったと思った。いや、そうではない。火が消えていたのだ。また、ゾヴとの対話に気を取られすぎて、火の管理を怠ってしまっていた。再度点火しようか悩んだが、今日はこのまま眠ることに決めた。
横になる。木々の騒めきと、小川のせせらぎが、途端に場を満たした。ゾヴとの対話による熱は、まだ残っている気がする。
特別な役割。自分にしかできないことを、やらせてもらっている。とても名誉なことで、心からうれしいと思う。そして、それを与えてくれたゾヴには、感謝してもしきれない。その彼の言に背反するなど、考えるだに浅ましい。
まどろんできている、とヒューは思った。睡眠欲を満たす幸福、それ以外のものが、ヒューをやわらかく包んでいた。
眠りに落ちれば、すぐミリアたちに会える。
眠る時に、特段季節を感じる。
暦では、冬が来ていた。人々は家に籠りがちになり、外は自然の猛威に好きにさせている。
アッシュは、寝返りを打った。毛布から姉の頭が出ている。吐息と呼んでもいいような、かすかな息遣いが聞こえる。よく眠っているのだ、と思った。
例外に近い状態で始まった調査は、今では日課となっていた。ほかの会員からの不平は少なくなかったみたいだが、結局は、ギマライがいるなら、と折れたようだ。
ギマライのような人を、大人と言うのだ、とアッシュは思う。やるべきことやり、周囲からの評価が高い。さまざまに、気を遣ったり配ったりしているのだろう。
そういう人になりたいとは思っても、なれるとはなかなか思えない。その世界は自分にはまだわからないし、正直なところを言えば、興味も持てなかった。しかし早く理解し、やっていかなければならないことは、頭ではわかっている。
それでも、考えられるのは灰の国のことだけだ。調査である。しかし、冒険だと思うと、心が自然と浮ついてしまう。
毎朝、日の出とともに灰の国へ渡り、旅を進め、日没により帰る。その生活を続けて、そろそろ三か月が経過していた。
ヒューが言うには、あと少しで造物主の石庭に着くとのことだった。やっとか、という思いと、終着に対する未練が、アッシュの頭で交錯している。
それにしても。
姉は変わったと思う。物事に乗り気であるとか、やる気が感じられるとか、そういう類ではない。やるんだ、というしたたかさが、言動に満ち溢れている。その心があってか、灰の国での姉は自分よりも格段に強くなった。
きっかけは、ヒューだったのではないかと、アッシュは推測する。彼女と出会って姉は変わった。くよくよしたり、変にひとを羨んだりすることが、なくなったような気がする。
それは、嬉しいはずだった。
なのに、胸中に闇色の嫌悪が生まれては蠢き、そして消えていく。夜は、特にその色が強かった。今もそうだった。考えないようにしても、どこかで考えてしまう。
姉に助けてもらうことが多い。言い換えれば、自分は姉を守れていないのだ。灰の国で強くなるには、魔物と戦うことが必要だった。西方への道中で、対峙する魔物の数に差はない。それでも、姉の方がみるみる強くなっていく。
ヒューが説明するには、強さは経験と精神のかけ合わせだそうだ。そして姉は、卓越して心が強い、とヒューは興奮気味に言った。役割の違いも成長にはだいぶ関わる、とアッシュへの気遣いを添えて。
精神の変動。姉が、もとから強かったとは思えない。ヒューとの邂逅が、姉を強くした。
姉の役割は斧を振ることで、自分は炎を放つことだ。前者は近くから、後者は中遠距離からの攻撃を主としている。魔物と直に干戈を交える方が、経験も多く得られるのだそうだ。一瞬で躰を操作できなければ、それは損傷として返ってくる。アッシュの場合は、遠くから場に臨み、適宜要される魔法を詠唱するだけだ。
つまり、経験も精神も、姉に及ばない情況が続いてしまっている。
本末転倒だな、とアッシュは思う。灰の国へ入った時、提示された選択肢に対し、二番目を選んだ。自分の肉体の制限を超え、どこまでも力が届けばいい。そうすれば、時間の経過を待たなくとも、姉を守れる可能性が高まるのではないか。この小さな躰を、気にしないようになるのではないか。
結果、遠くの魔物を斃せるようにはなった。しかし、姉の選択を考慮していなかった。
一番目を選んだ姉は、大男でも扱えないだろう斧を軽々と振り回し、その膂力を轟かしている。戦闘時も、必然的に最前線へ躍り出る。
それでも、姉が弱ければ、自分の出番は増えるのだ。はじめて火尖剣を放った時、姉は損傷がひどく、今にも魔物にやられそうだった。刃が魔物に刺さり、炎とともに消えていく光景を見て、姉を守れたのだという実感が湧き、心の底から嬉しくなった。
その思いは、それ以降で味わえた記憶はない。
「アッシュ?」
気づくと、姉はこちらを見ていた。驚き、躰が強張ってしまう。
「なに、姉ちゃん?」
「それはこっちの台詞よ。上の空で、ずっとわたしのこと見てるんだから」
「いや、ごめん。なんか眠れなくてさ」
「駄目よ、しっかり眠らないと。勝てる魔物にも、勝てなくなるわ」
「そうだね」
姉は、灰の国との往来がはじまってから、普段より規則正しい生活を送るようになっていた。体調がよくないと、斧が重く感じるのだそうだ。自分たちの住む世界と灰の国とで身体能力や感応力は大小変われど、根本的なものは密接に関連している。
「まあ、寝つけないのも、わからなくもないけど。造物主の石庭まで、もうすぐだもんね」
それは、理由としてあるのかもしれない。緊張なのか、興奮なのか。ヒューが目的地としている地に、そろそろ辿り着ける。
「再創世か。そのあと、あの世界はどうなるんだろう」
「ヒューも、わからないと言っていたわね。灰の空は、もとに戻るんだろうけど。そもそも再創世自体、どういうものなのかよくわかっていないからね、わたしたちは」
「たしかになあ。世界を元に戻す、と言っても、大ごとすぎて現実感が湧かないよね。ただ」
ヒューの顔を思い出す。こちらの世界の話をした時、彼女の表情はいつも輝きを増していた。自分たちには当たり前のことでも、ヒューにとっては信じられないことのようだった。
「楽しみにしてるもんね、ヒュー。夕焼けを、見てみたいって」
「アッシュみたいな髪の色、と言ったら、言葉を失っていたわ」
「いい意味かな、それは。まあ、今の灰の空だったら、姉ちゃんの髪色だからね」
「いい意味かな、それは」
二人で、笑い声を立てる。
「ゾヴにも会えるね。少年の声、とヒューは言ってるけど、どんな外見なんだろう。同じくらいの年齢だといいなあ。でも、ずっと造物主の石庭の管理者だから、見た目だけが少年なのかもね。そんなことあるのかって思うけど、灰の国では、なにがあっても驚かなくなったよ」
姉から、返しがない。眠ったのかと思ったが、その眼は開かれたままだった。
「姉ちゃん?」
「ああ、ごめんなさい。今度は、こっちが上の空になっていたわね」
「どうしたのさ」
「最近、考えていることがあるんだけどね」
続きを待つ。姉は、言うか言うまいか、決めかねているようだ。
「ヒューのこと」
「ヒューに、なにかあったの?」
「様子が、おかしくない?」
思い返すが、特に気になるところは浮かんでこなかった。
「俺には、いつも通りに思えるけど」
「そう。わたしの考えすぎかもしれないわね」
「話してよ。俺、鈍いんだと思うし」
姉は話を切りあげようとしている、とアッシュは思った。いつもなら、それはそれで、と止めることはしないのだが、この時ばかりは、話を先へ進めてほしかった。姉の瞳に翳りができている。それは、今までにないことだった。
「ゾヴの伝言役に、終始徹している気がするのよ」
「前から、そうじゃなかったっけ?」
「確かに、出会ったころから、ゾヴという名前は出ていたわ。それでも、ここ最近のヒューは、おかしい。なにを言うにも、するにも、事前にゾヴの許可を得ないとできないかのような」
「ヒューが、自分でなにかを決めていないってこと?」
「そう、なるのかな。冷たい言い方をするなら、なんでもかんでも、ゾヴの声に従う人形のようだわ。わたしが話しているのは、ヒューなのかゾヴなのか、疑いたくなるほどに」
「ううん、考えたこともないから、全然そういうふうには見えないなあ」
思った通りを伝える。姉は、表情から少し緊張を抜いたようだ。
「やっぱり、思い過ごしよね。単純に、ゾヴの名前が出てくるのが嫌なだけかもしれないわ」
「でもさ、仮に」
また、引き留める。単純に、姉と会話したいだけではないか、と思いはじめていた。
「仮にヒューがゾヴの言いなりだったとして、姉ちゃんはどうしたいの?」
姉の眼が、丸くなるのがわかる。考えもしていなかったのかもしれない。
「結局、やることは変わらない気がするけど。灰の国の再創世、でしょ?」
「ええ、そうね」
ここにきて、ずっと合ったままだった視線を、姉は落とした。次の言葉を、探しているかのようだった。
「だけど、再創世できたとしても、ヒューがゾヴの言いなりなのだとしたら、わたしは嫌だ」
「なんで?」
「わからない。嫌なものは、嫌なの」
言って、もう会話は終わりだと言わんばかりに、姉は寝返りを打った。心なしか、頭でさえむくれているように見える。
アッシュは、手を伸ばし、姉の頭に触れる。さらさらとして、あたたかだった。
姉からは、なにも反応がない。もう眠ってしまっているとは思えないが、こちらの相手をする気はないのだろう。
しばらく、アッシュは姉の頭を撫でていた。
ーーーーーーーーーー
こちらのイラストは、まきあっと様に描いていただきました。
改めまして、この度はご協力いただきありがとうございました。
ーーーーーーーーーー
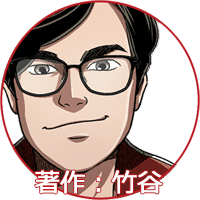
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
