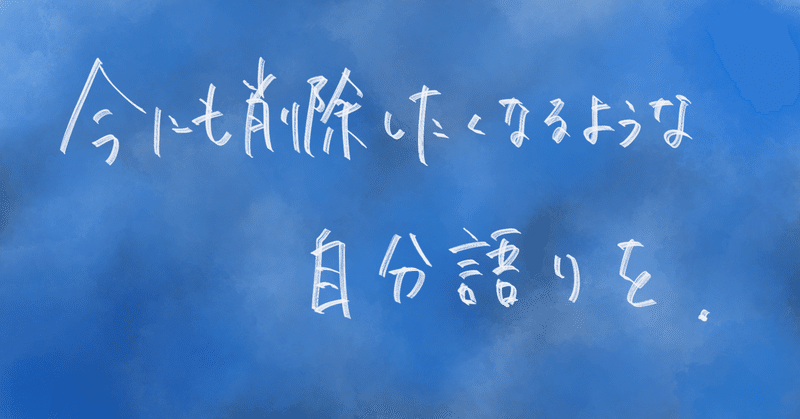
今にも削除したくなるような自分語りを
エピソード3:ミリアッシュ設立
気温も天気も覚えていないが、場所はドトールコーヒーショップ半蔵門店だった。まだ暗くなる前、少しずつ寒さの染み入る薄暮だった。
「杉さん、一緒に会社やらない?」
制作部の部長である杉山剛に向け、竹谷彰人は話していた。何か意を決した風でもなく、自然に言葉が出ていた。いや、何とかそう装っているだけで、コーヒーカップを持つ手は、かすかに震えていたような気もする。
しかし、反応だけの人生はもう、終わらせたかった。震えは、自分で物事を決めた反動だったのかもしれない。
出会った時から、杉山はよく笑う男だった。そして、この時も笑った。この数か月後に、株式会社ミリアッシュは生まれる。
これは、やる気も夢も信念もない元ニートが、会社を作るに至る話だ。
毎日、一日中ずっとゲームだけをして生きていけるなら、どれだけ幸せだろうか。
竹谷が第二新卒として、ゲームイラスト制作会社へと入ったのは、2013年の春だった。入社するまでの1年間は、ニートをしていた。
働こうと思った理由は次にほかならない。新卒時に蓄えた貯金残高がなくなったからだ。お昼にゲーム『Dragon’s Dogma』をして、夕食後にゲーム『メルルのアトリエ ~アーランドの錬金術士3~』をやり、ニコニコ動画でだらだらと動画を眺め、眠りたくなったら眠る。そんな最高な生活をしていたのだが、当然お金はじりじりと減っていった。働きたくなどなかったが、働かなければ生きていけない現状に分厚い背中を押され、90キロの重い腰を上げたのだ。
職場条件は至って単純だ。簡単そうで、正社員で、完全週休2日制。ゲームコントローラーを片手にゆるく探していると、ようやく条件を満たしてくれる求人を見つけた。
未経験者歓迎の、進行管理のアシスタント。
完全週休2日制はもちろん、正社員で社会保険も完備だ。さらには、よくわからないがなんとなく良さそうな響きを持つ、フレックスタイム制とやらを導入しているとのことだった。その好条件で給与が25万円も貰え、さらには年末に賞与も出る。
アシスタントなのに正社員で、しっかり休めて25万円プラス賞与。脂肪のたっぷり蓄えられた体が嘘のように、軽々しくその求人に飛びついた。
すぐさま応募先の会社代表との面接となり、無事に採用となった。
「竹谷さんは、こういう資料とか作れる?」
「はい、大丈夫です、できます、問題ありません」
今推測するに、代表からの問いに間髪入れず前向きな返答をしたところが、採用の決め手となったのではないだろうか。
実際、できるかどうかなど正直わからなかったが、新卒時にちょっと染み込んだ営業会社の遺伝子は、竹谷の中で湾曲して吸収され、何か決定権を持つ人間に対し「できません」と返すことに、抗いがたい拒否感を覚えさせたのだ。もはや営業でもなんでもない。考えることを諦めただけである。
無根拠な自信に溢れた返事を繰り返した竹谷は、面接を通った。
安定した状況で働きたい。アシスタントは楽で簡単そうだ。
そんな思いをむちむちの胸中に秘めた竹谷は27歳、少し絞って85キロで入社初日を迎えた。
『週刊ファミ通』を読むだけで、お金がもらえた。
入社して最初の1か月は、やることがなかった。それもそのはずで、当時会社は設立して1年ほど、入社前の従業員数は5名、新入社員が竹谷含めて4名で、やっと10名に届くかどうかという規模だった。その内、イラスト制作に携わる者が8名。代表と竹谷だけがイラスト制作以外の業務、つまり営業や事務などを遂行する役目だった。そこだけを聞くと、やることが山積して大変そうに思えるのだが、ニートから足を洗ったばかりの竹谷は、武田信玄公も思わず撤回したくなるほどに、指示がなければ動かざること山の如しであった。
「業界のことを学ぶため、ゲーム情報サイトを見て勉強してくれ」
代表からの下知へ忠実に、ネットサーフィンやゲーム雑誌を読んでいるだけで日が暮れ、労働と見なされた。この上なく幸せなことではないか、と恍惚としていた。繰り返すが、最高だった。
当然、そのままグッドエンディングとはならない。グッドというよりは、スウィートだが。
少しずつ、代表から仕事を渡されるようになった。請求書を郵送したり、来客へ対応したり、資料を作ったり、クライアントへ訪問したり。
「竹谷さん、これできる?」
「やります」
採用面接時にも発動した、仮初めの体育会系な応酬技術は当面の間すこぶる効力を発揮し、業務は徐々に増えていった。
人数が少なく会社の業歴が浅ければ、課題は新雪の野のように手つかずだ。やればやるだけ結果となり、また評価にも繋がった。
入社して2年が経った2015年、29歳の竹谷は経営管理部の部長となっていた。代表からは、竹谷が35歳になるまでには社長の座に就いてもらうと言われていた。
次期社長、かつ経営管理部部長。
数年前までニートだった人間が、こんな状況にいるとは、竹谷本人もまったく考えていなかった。
どうしてそんな事態になったかと考えるに、現ミリアッシュ副社長である杉山の存在は大きかったように思う。
杉山は、半年先に前社へ入っていた先輩だった。とはいえ先輩風を吹かされたことは一度もなく、気さくでよく笑い、謙虚で丁寧で、泥酔すると帰路が不覚になるような好青年だった。朝まで歌い踊り明かそうぜ、と誘われた新宿のカラオケにて、開始数分後にご就寝なさった杉山の天使のような微笑みは、その悪魔的な仕打ちと相まって今も忘れられない。彼の名誉のために付け加えると、今はへべれけとならずにお酒を嗜んでいる。それはそれで、一抹の寂しさも感じているが。
仕事にも波長というものがある。そう思うようになったのは、杉山との出会いからだ。
会議での発言や、問題に臨む姿勢。竹谷が1を言うと10まで理解してくれ、逆に杉山の言うことは皆まで聞かず意を汲めてしまう。するするとテンポよく、面白いゲームをプレイするように働けてしまう。こんなに気持ちよく仕事に取り組めるものなんだと、20代後半にして気づいた。
そして、気持ちいいことには、人間は率先して自発的に動く。竹谷の仕事に対する見方が、言いつけを遵守し遂行することから、問題を見出して解決することへと変わっていった。会社に絶えず噴出する問題を自分事として捉え、当事者意識を持って対処する。小規模な会社だからこそ、自分の仕事が会社へ与えるインパクトは小さくなく、その分の責任もあるが、何より楽しかった。
また、社風として、変な上下感を持たずにフラットな関係で仕事ができる。それぞれが自由闊達に意見を言い、とはいえお互いに敬意を忘れず、丁寧に業務を進められる。良質なコミュニケーションはなんて素晴らしいものなのか。
そう思い込んでしまったのは、竹谷の未熟の致すところだった。
部長になり、しばらく経ってから気づく。自分の言葉は竹谷個人ではなく、部長として上から皆に響くということに。同期入社の者たちにそういう嫌いはなくとも、後輩、特に竹谷が部長になってから入社してきたメンバーに関しては、部長という肩書が妙に威を放っていた。
お願いします。やってみよう。その方向でいいんじゃないかな。
そういった頼みやお願いが、指示として受け取られる。会議で竹谷が意見を言うと、なんだかそれが正しいのではないか、という同調めいた空気が生まれる。猛省した要因として、言動が荒く厳しい面もあった。冗談も、受取る側が冗談と思わなければ成立しない。そこに部長という肩書が加わることで、シーソーのように、水平だと思っていた関係に大きな傾きができてしまっていた。
そしてこの状況は、今のままではいけない、と竹谷が強く思う契機となった。言動として表れる前の、思考の部分。そこに問題があったのだ。
会社が成長するために働いていた。
ではなぜ、会社を成長させたいのか。
竹谷の中に答えはなかった。当然だった。安定して楽に生きたくて、簡単そうなアシスタント職の正社員に魅力を感じ、蜜へ群がる虫のように飛びついたのだから。
竹谷には、信念がなかった。
なぜを突き詰めると、何も出てこなかった。だから思考は揺れ、その先にある言葉、行動、習慣、性格、果ては運命までぐらつくのだ。同僚へ語る言葉も、どこかふわふわと浮力を纏う。とどのつまり、それは信念が欠けている証左にほかならない。
何が部長か。そんな状態で次期社長と呼ばれている自分は、いったい何様なのだろう。
焦る。信念を探す日々が始まった。ちょうど30歳で、部長となって1年が経った、2016年の頃だ。過労だったわけでもないが、体重は70キロまで落ちていた。
乾いているのか、それとも、湿っているのか。
当時の責任者たちの中では、ドライかウェット、という考え方があった。淡白と濃厚に換言してもいいかもしれない。端的に言えば、同僚の不安や悩みに対して、付き合う程度や頻度を指している。
「会社を辞めたい」
たとえば、表情の曇った同僚からこのような退職の話を受けた際に、次のどちらかで返すか、といったものだ。
「どうぞ、ご自由に」
「何か不満でもあった?」
もちろん、相手の身上は千差万別なので杓子定規にそう反応するわけではないが、単純に言うとそんな具合だ。竹谷自身は、日によってドライだったりウェットだったり分かれていたように記憶している。
それもそのはずである。繰り返すが、竹谷には信念がないのだ。眼前に分厚い壁、漫画『進撃の巨人』のウォール・マリアが不意に築かれた心地だった。
壁に当たった時、どう打破するか。十人十色の解法があると思うが、多くの人が取り得る手段として、近しい誰かに相談する、というものがあるだろう。
しかし、その手は使えなかった。竹谷は友達が少ない。頼れる先輩や、映画『アベンジャーズ』シリーズのスパイダーマンに対するアイアンマンのような、慕う年上の人物もいない。グループで集まって行動するのが、昔から苦手だった。嫌われていたわけでは断じてない。たぶん。祖先は狼だと信じている。
そうなると、竹谷の採る手段はひとつしかない。本である。
中高生の頃、塾に通えなかった竹谷は、ひたすらに教科書と参考書を読んでいた。その癖のようなものだ。
偉人たちの残した本をぱらぱらとめくった。漫画『封神演義』が大好きなので、太公望が記したとされる『六韜三略』も手に取った。ゲーム『三国無双』シリーズでは孫策や黄蓋を使用していたので、孫氏の兵法も読んでみた。
運命と言えるものがあるとすれば、竹谷にとってそれは、ジュンク堂書店池袋本店の陳列と、祖父の名だった。
その時は確か、『論語』を探して東洋思想のコーナーにいたのだが、『論語』の近くに『論語と算盤』という本が並べてあった。著者の名前に見覚えはなく、渋沢栄一と出ていた。惹かれたのは、栄一という名だ。竹谷の敬愛する祖父、鷲尾栄一と同じ名だったのだ。妙な親近感とともに『論語と算盤』を買い、以降、竹谷は渋沢栄一と『論語』にどっぷりと傾倒していく。祖父の名付け親、つまりおそらく曽祖父母と、当時のジュンク堂書店の陳列には、感謝してもしきれない。令和の世にて、渋沢栄一が新たに一万円札の顔となることは、この上なく嬉しいことだ。
渋沢栄一のどの本だったか、会社のトップにひとを選ぶ指針として、情の厚さを挙げていた。技術や知識ではなく、情であると。
深く、竹谷の腑に落ちた。ドライとウェットは、左右の振れ幅のように表現されているが、そうではない。情に厚いか薄いかは、左右ではなく上下であると。そして竹谷は、情に厚い人間として生きていきたい。そう強く思った。
そこからは早かった。漫画『ドラゴンクエスト列伝 ロトの紋章』にて、悟りの書を前にした賢王ポロンのように、『論語』のひとつひとつの言葉が脳に突き刺さった。制度や予算の設計、採用や人事にも、これまでとは違う力が籠められていった。
決めて、揺るがないことが、これほどの力を生み出すのかと思った。
しかし、そこでまた葛藤が生まれる。
ドライとウェットの並列で物事を見る会社に、情の厚さを大事にすると決め、ドライとウェットを直列で見始めた竹谷が、どこか逸れているような気がしたのである。
同時に、『論語』の中に出てきた言葉が、頭から離れなくなった。
不惑の40、という言葉を聞いたことはないだろうか。40にして惑わず。40歳になるとあれこれ迷わなくなる、という意味で、40歳を迎える際によく使われる言葉だ。
これは『論語』の言葉で、不惑はある一群の文中に出てくる。
そして、竹谷にとっては、不惑のひとつ前の言葉が、何よりも印象深く残っていた。
30にして立ち、である。まさに、当時30歳であった。
軸は決めたが、では、立つとは何か。
結論から言えば、情をしっかり大事にするために、独立して会社を作る。それが、竹谷にとっての立つことだった。
当時制作部の部長となっていた杉山に、よく代表の不満を言っていた。
「こうしたらいいのに」
「なぜああなのか」
そんな、雑多な愚痴に近しいものだ。それがいかに容易で、いかに幼稚であるかということを、感じずにはいられなくなった。
会社を作ったのは、代表である。その会社に、竹谷は正社員として雇われている。ひとの傘に入り、肩にかかる水滴が鬱陶しい、地面に弾く雨が冷たい、と文句を垂れているようなものだった。自分で傘を差せばいい。そうは思っても、ちゃんと差せるだろうかと、妙な恐怖が皮膚を這ってくる。
思えば竹谷は、反応の人生を歩んでいたのだ。
たくさん勉強して、良い大学に入って、良い企業に入って、安定した生活を送るのが至高である。世の中からか、親からか、もしくは学校からか、竹谷はそんな思想に染まっていた。そう言われたから勉強し、スポーツをするように言われたから運動部に入り、大学へ行き、大きな企業で働いた。しかし結局退職し、次に入った会社では、社長にならないかと代表から誘われ、是と返した。
これらはすべて、ただの反応である。
いい加減、その自分に嫌気が差した。
自ら会社を作り、その上で、自分の大事にしたいことを貫く。それしか、竹谷に残された道はなかった。代表に馴らしてもらった、優しく舗装された社長への道を、さあ大変だ、こりゃあ難しいだのと口から零しながら歩くのは、もう無理だった。
安定した生活などというものは、外側からではなく、自身の内側から獲得するものだ。環境に左右されない強さを持つことが肝心で、そのためには、自分で決めて自分で責任を負わねばならない。
もちろん、思いだけで独立できるほど、世の中は甘くはない。竹谷にはものすごく欠けていることがあった。
何もできないのだ。
当然である。数年前までニートをやりながら鼻提灯を作っていたのだから、できることなどほとんどない。
独立できる。のみならず、間違いなくやれる。そう思うに至ったのは、杉山は当然として、もうひとり、制作部支援室の室長だった寺井友志がいたからだ。
杉山を誘った時、竹谷の想定は2人の会社だった。
杉山がイラストを制作し、竹谷がそれ以外をやる。ツーマンセルは、漫画『鋼の錬金術師』のエルリック兄弟や、漫画『スティール・ボール・ラン』で馬レースに出場するジャイロとジョニィからもわかる通り、物事をそつなく運ぶ基本形だ。
断られたらどうしよう、という竹谷の不安なぞ知らんとでも言うかのように、杉山は快諾してくれた。家を買ったばかりで、ローンは向こう何十年もあるのにだ。ちなみにとても素敵な住まいで、知っているひとは知っているが、その中のひと部屋が今のミリアッシュ本社となっている。
しかし、杉山の参画は、竹谷が作る新会社にとっては朗報この上ないが、前社にとってはただの悲報である。
制作部部長の杉山、経営管理部部長の竹谷。代表の直下に役員はおらず、部長である二人が代表の次席に座っていた。代表が漫画『ドラゴンボール』のフリーザなら、杉山がザーボンで竹谷がドドリアである。
30名規模の会社で、ほぼ設立当初からいる、且つ2人しかいない部長が、会社を抜けて独立する。自分が代表だったら、なんとしてでも避けたい事態だったはずだ。
ちなみに、寺井は竹谷の半年ほど後に入社してきた後輩なのだが、年齢は4つ上で、頼れるお兄さんといった存在だ。寺井の入社初日、爽やかな男性が来た、と女性社員たちがグループチャットで高揚していたのを見て、小さからぬ嫉妬を抱いた記憶がある。竹谷にも割かし清涼感はある。器の大きな人間になりたくも、中々そうはなれないものだと知った。
部長2人がいなくなると、代表の直下になるのは、制作部支援室の室長をやっていた寺井だった。つまり、杉山と竹谷が抜けた分を、寺井が埋めざるを得なくなる状況だった。ゲーム『ぷよぷよ』では、杉山と竹谷が束になってかかっても倒せないほどのガチガチな強さを誇るが、用意もなく受動的に社内のナンバーツーへ立たされることを、酷と言わざるしてなんと言おう。
申し訳ない、という気持ちで、代表よりも先に、寺井には話すことにした。杉山と寺井と竹谷で会議室に入り、独立する旨を伝える。なんとなく察していたのか、はたまた3人の中で最も慈愛に溢れた人間だからか、怒りや呆れという表情を見せることもなく、ただ承諾してくれたように覚えている。
そして後日。
「一緒にやりたい」
そう申し出てきた。正気の沙汰ではない。
竹谷は当時、実家住まいの気楽な身分だった。杉山は結婚しており、持ち家に住んでいる。寺井に至っては、既婚で持ち家住まいどころか、2児の父であったのだ。しかも玉のようにかわいい息女が生まれたばかりである。本当にかわいくて、竹谷は熊のぬいぐるみをかなり献上した。背中を押してくれた2人の奥方には、報いても報いきれない大恩がある。少なくとも、ディズニーリゾートには毎年ご同道願いたい。
杉山も寺井も、世辞でなく、気のよく熱心にそして丁寧に働く人間だ。前社に残っていれば、相応の役職や報酬を手に入れられたと思う。転職しようとすれば、引く手あまただったはずだ。今乗っている船にいてもいいし、豪華客船に乗り換えることもできる。
にもかかわらず、2人は、これから竹谷が作ると壮語するイカダに乗ると、なんなら一緒にイカダを作りたいと言ってくれたのだ。なんなのだこの2人は、と大きな嬉しさの中で小さな困惑さえ抱いた。
正直なところを言えば、会社を作ろうと誘っておきながらも、本当に設立まで漕ぎ着けるかなんて微塵も自信がなかった。経験もなければ、知識もない。どこから始めるべきかも当然わからない。
しかし、そんなことはすべて些末で、ここに来てはどうでもよかった。
杉山と寺井が、イカダを一緒に作ろうと言うのだ。できるかできないか、ではなく、やるしかない。そのイカダの作りが甘く、隙間から海水が浸入してこようとも、進めると信じて船出する以外ない。
想定を超え、スリーマンセルとなった。漫画『NARUTO』的にも、『三国志』の劉備三兄弟的にも、漫画『ゆゆ式』として考えても、線が面となり、より強力なパフォーマンスを発揮できる人数だ。また、不思議なことに、3人それぞれ得意な領域が違う。寺井は制作、杉山は制作と営業、竹谷はゲーム。ちなみに、変に仲違いせずやれていることに驚きの言葉をもらうことがあるが、ひとえに杉山と寺井の人格のなせる業である。マンガ『大東京トイボックス』から言葉を拝借すると、杉山と寺井とも、魂が合っているのだ。
代表に3人独立の旨を伝え、了承してもらった。色々清濁ある感情を代表には抱いていたが、喧嘩とならずに新会社を設立できたことは、代表の人格あってのことだと感謝している。
なんとか登記も終え、登記簿謄本を見た際に湧き起こった感慨は、なかなか表現のできないものだった。まだ見ぬ大陸を求めて船を漕ぎ出す心境は、こういうものかもしれない。そう考えるのはきっと行きすぎた感想には違いないが、妙に少年めいた興奮を、この時竹谷は抱いていた。
2017年2月8日、株式会社ミリアッシュは設立された。それ自体はすごいことでもなんでもない。これから何を成すかが肝要なことであり、会社を作った価値である。
そう頭では重々理解できていても、それでも、嬉しかった。きっと、目指そうと自ら決めた場所へ向けて、自らの意志で進む覚悟の対価として得られたひとつなのだろう。
漫画『悟空道』の作者山口貴由先生の巻末コメントには、こうある。
「足を動かしている限り、近づいている」
そう意識して進む。3人で。
エピソード4:名となる文字列
まじまじと、キティちゃんを見つめていた。
新卒で入った会社を辞めてからというもの、冠婚葬祭以外では着たことのなかったスーツを身に纏い、竹谷は銀行の法人用カウンターに座っていた。
会社の銀行口座を、開設に来ていた。
今から20キロ太っていた時のスーツはブカブカで、シルエットはお世辞にも良いとは言えないものだったが、きっと心証が良くなるに違いないと判断してのことだった。漫画『BLEACH』の影響で、ネクタイは細くて黒色のデザインだった。いつか機会があって斬魄刀を佩かせてもらえるなら、迷わず侘助を選びたいところだ。
2月の外気は、まだまだ冷える。しかし、銀行内の強い暖房のせいか、場に慣れていないからか、竹谷の額にはじんわりと汗が滲んでいた。精神の動揺を悟らせてはならない、と持ち前の格安なポーカーフェイスを発動し、場に臨んでいた。
法人用口座の開設にともなった審査のため、渡された申込用紙に必要事項を記入していく。
ミリアッシュ。
謎の文字列を社名欄に書き、代表取締役という、突如偉そうになってしまった肩書とともに、自分の名前を続けて書いた。
応接してくれた女性は若く、新卒から多少フレッシュさが抜けたような印象だった。幾千もの口座開設を担当してきたからか、事務的で、そして竹谷の勘違いでしかないが、どことなくサディスティックな表情を見せていた。真剣かつ冷静な眼差しで、竹谷から受け取った書面に不備がないか確認している。竹谷の字が汚いのは、幼少期左利きだったのを右利きに矯正されたからであり、竹谷のあずかり知らぬ範疇の原因である。本来の利き手なら上手に書けていたはずだ、きっと。読みづらくて本当に申し訳ない。
「いくつかご質問よろしいですか?」
「はい」
女性からの問いに、竹谷は頷く。これも審査の一部なのだろう。凍りついたような視線がなんだか怖いので家に帰らせていだたく、とは返せない。
「ミリアッシュという社名の由来をお伺いしても?」
彼女は、付箋紙とボールペンを手に、まっすぐにそして冷静にこちらを見てくる。カチリと、ボールペンの頭をノックする音が聞こえた。
そんなことを答えるのか。一瞬うろたえた竹谷の視線が、思わず付箋紙に釘づけになる。
つぶらな瞳のキティちゃんが、これ見よがしに大きくプリントされていた。
ミリアッシュの由来。
竹谷とキティちゃんの邂逅など露知らず、女性は付箋紙にそう書いた。キティちゃんとミリアッシュが並ぶ。『ハローキティ』は40年超の時を生き、知らないひとなどいないような世界中で愛されるキャラクターであり、かたやミリアッシュは数日前に作られた、杉山と寺井、竹谷の3人と、法務局の人たちしか知らない文字列である。40歳と0歳。まさか同時に視界に入る機会があるとは思ってもいなかった。
現実味を帯びない光景にまぶたを数度開閉してから、幾ばくかの恥ずかしさとともに竹谷は由来を話し始める。どちらかと言えばキティちゃんよりシナモンが好きです、という冗談を挟む余地は心になかった。
杉山と寺井、そして竹谷は、3人揃って前社の会議室で唸っていた。独立するとは決めたものの、まだなにも動けていなかった。
「社名」
コーヒー缶を両手で丸く包みながら、竹谷は呟く。会社の作り方などどこで学べるのか、という憤りに似た疑問とは裏腹に、検索エンジンというものは驚異的な代物で、会社設立や法人登記といった言葉を打ち込めば、すぐさま色々な情報サイトが出てきた。まったく人類は最高の生き物である。それらをカラカラと回覧し、また熟知したい部分は本を読み、今では設立までのロードマップがわかり始めていた。
本社の所在地は、杉山の家の一部を借りることとなっていた。固定費、特に地代家賃は極力抑えた方が良い、という杉山の提案だった。普通に考えれば、自宅にほぼ毎日竹谷という少々のハチャメチャが押し寄せて来るわけであるから、かなりのストレスならびにハラスメントではないかと思うのだが、杉山はもとより奥方も快諾してくれた。奥方が帰社、ではなく帰宅なさると、杉山と竹谷の「お帰りなさい」がリエゾンするような、文字通りアットホームな会社となった。寺井は自宅にリモートワーク用のスペースを作り、基本的に千葉県で業務を遂行することにした。ちなみに寺井の家は、家庭菜園の域を凌駕した庭があり、瑞々しいアスパラガスや玉ねぎ、稀に肥えたマンドラゴラなども収穫できる。
場所を決め、事業も当然イラスト制作と決まった。次に決めるべくは、社名である。
イラストに関連した名にするか、会社の精神に焦点を絞った名とするか。外面か内面のどちらに紐づけるかで悩んでいた。
元来ゲーム好きな竹谷は、キャラクターの名づけに関しては中々に輝かしい歴史を持っている。ゲーム『テイルズ オブ ディスティニー』ではなにも考えず直球で「アキト」と名を与えた結果、「アキト・エルロン」という未曾有の変異体が誕生したし、ゲーム『ファイナルファンタジーVIII』では、スコールという名の主人公に熟考の末「レヴィルド」と命名した。だれなのか。羞恥心は、突如として過去から真っ赤な致命傷を負わせにやってくる。まさに時は中学2年生であり、その病名こそ発明されていなかったものの、いわゆる中二病に罹患していたことは鏡にかけて見るように明らかであった。
社名の要素となりそうな言葉を、ノートに書き落としていく。イラスト、色、色彩、絵、ペン、クリエイティブ。熱意、誠実、思いやり、仁義礼智忠信孝悌。それぞれを英語に変えたり、日本語のほかの表現を探したりもした。それらの言葉をくっつけては首を傾げ、順番を入れ替えては頭を掻く。
とはいえ悠長にはしていられない。社名を決めなければ、物事が進まないのだ。
なんとかしなければと、藁をもつかむ思いで竹谷はゲームをした。ゲーム機の起動音を聴くと心が安らぐ。あと楽しい。言うまでもなく、我ながら天晴れな現実逃避であった。勉強時の掃除と同様、こういう時の逃避エネルギーはすごいものがある。
しかし、やはりと言うべきか、ゲームはいつだって幸せを運んでくれるものだ。
その時はゲーム『DARK SOULS III』をしていた。知る人ぞ知る高難度のアクションRPGで、発売から1年ほど経っていたが、時折無性にやりたくなってはキャラクターを新規で作りプレイしていた。映画『300』が大好きなので、ほぼ全裸に長槍と円盾というパンキッシュな出で立ちで、ダークファンタジーの世界を闊歩していた。転生するならスパルタ人になり、301人目になりたいほどだ。
濃厚なダークファンタジーだけあって、漫画『ベルセルク』のような、とても静かで狂おしい世界を堪能できるのだが、主人公は色々な所以あって火と関係が深い。プレイヤー自身も、ゲームの結果として火に対して並ならぬ親近感を持ち、日常生活時に「篝火」という言葉が聞こえるだけで、じわりと口角が上がってしまうような現象さえ起こる。
さて、主人公はとある女性キャラクターから協力を得るのだが、その女性は主人公を指して「灰の方」と呼んでいる。ゲーム内で話される言語は英語なので、「Ashen one」だ。
灰。
アッシュを、なんだか良いなと思った。悲しいかな、中二病の残滓は、まだ少なからず脳内を蝕んでいたのだ。
大学時代、竹谷は英語英文学を専攻していた。ゼミでは英国の女流文学を扱い、卒業論文は名著『嵐が丘』を題材に、作者エミリ・ブロンテの死生観を捉えてみせようなどという大二病を発症させていたのだが、個人的な興味は英語の歴史にあった。もう少し言うと、語源が好きなのだ。
「ash」の語源を調べる。すると、元々は「燃える、熱がある、輝く」という意味だったらしい。そこから、燃えた結果として「灰」に転じたのだ。また、「トネリコ」という木の意味もあり、辿れば世界樹の「ユグドラシル」を指す。BUMP OF CHICKENのアルバム『ユグドラシル』からもわかる通り、「ユグドラシル」が嫌いな男の子はいない。かくいう竹谷も、『ユグドラシル』に収録されている曲はすべて気炎万丈で歌える。
一気に、アッシュという言葉に惹かれた。さらに言うなら、竹谷がティーンの時分には、『Dragon Ash』というヒップホップのグループが爆発的な人気を獲得していた。埼玉生まれビジュアル系育ちで、悪そうな奴は大体他人という人生を過ごしていた竹谷少年でも、『Dragon Ash』の沼に五体でもって浸り、なんか悪い感じを出せたら恰好良いなと背伸びをしていた。もちろん、竹谷は『Dragon Ash』も歌う。
アッシュをノートの真ん中に書き、ほかの言葉を周辺に書き落として、接合していく。複数の単語を並べるのではなく、合体させて造語にしたかった。合体させたい思いは、漫画『ドラゴンクエスト列伝 ロトの紋章』の合体魔法から影響が及んでいるかもしれない。氷の呪文マヒャドと風の呪文バギクロスを合わせて「氷刃乱舞マヒアロス」は最高にクールだ。氷なだけに。造語は新語であり、浸透するまでに時間を要するが、検索をかけた時に新会社だけが出てくるようにする、という狙いもあった。
灰になるには、熱を発し煌々と燃える必要がある。そういう風に働いて生きていく。その思いをアッシュに籠める。そして、それは一滴二滴ではなく、数えきれないほどだ。その意図から、「無数の」を意味する「myriad」という単語を引っ張る。「millionも検討したが、アッシュの発音とスペルとの相性が良さそうな前者を組み入れた。
ふたつを合わせて、ミリアッシュとなった。漫画『ドラゴンボール』でいう、フュージョンでありポタラである。そして、最後に少し遊びを入れた。ミリアッシュは、英語表記では「myriashue」となる。「ash」の後に、「ue」が足されているのだ。
これは、英語「hue」に由来する。意味は「色」だ。イラスト制作会社として、色彩に関連する言葉を混ぜておきたかった。英語のスペルが長い時を経て発音から遠ざかったように、「myriashue」も久遠を過ぎ、気づけば「ue」の発音が抜け落ちた、という妄想を採用した。
色、つまりイラストに携わる事業を、灰になるほどの強い赤誠や情熱とともに、無数にやっていく。
ミリアッシュは、ゲーム『真・女神転生』シリーズでいう三身合体のように、3つの親から言葉の力をもらい、この世に生を受けた。
銀行口座の開設審査は問題なく進み、無事にミリアッシュと文字列の入った通帳を受け取ることができた。正直なところ、登記を終えた時より、胸を深く撫でおろした。お金がなければ、会社はなにもできない。応対してくれた女性に感謝を示しつつ、これからはシナモンではなくキティちゃんを好くことを固く誓った。
会社の通帳に資本金である330万円が記入され、竹谷の通帳からは大事に貯めた300万円がさっくりと消えた。自分のお金がなくなることへの恐怖感は、不思議となかった。数万円の買い物では小心者らしく怯えてためらうものの、300万円の規模だと、竹谷の怯懦もアニメ『マクロスΔ』の楽曲の通り『いけないボーダーライン』を越えて、ちょっともうよくわからなくなるのだということを知った。
銀行口座ができたことで、クライアントとの契約書も締結することができた。妙に値の張った法人用の印鑑を、あまりない握力を籠めて押していく。登記簿謄本や通帳、契約書そして名刺に、ミリアッシュという言葉が刻まれていった。
しかし、その文字を見ても実感がなかった。新会社をミリアッシュと命名したが、本当にミリアッシュなんてものが存在しているのか、という妙な感覚があった。名刺を交換する時に、ミリアッシュという言葉が出るとなんだか歯の浮く感じがあった。名が実を伴っていない。生まれた時すでに弾けていたバブルというものは、この感覚に近しいのかもしれない。そんなことを思った。
とはいえ、思春期の竹谷のように、アイデンティティー・クライシスに陥っている場合ではない。ミリアッシュは作られ、最低限の手続きも終わり、仕事はもう来ていたのだ。
設立月は2月だが、3月にはもう売上が経つ見通しだった。出来立てで薄氷のような会社であるにもかかわらず、信じてご依頼をくれたクライアントの皆様には、厚謝とともに仕事で報いるほかない。
とにかく、熱を上げて働いた。幸いにも、業務に臨む際に重んずるべき会社のアイデンティティーは、譲れないものを考えていた。
情である。思う存分、情を大事にするため会社を設立した。それに則って勤めれば、ミリアッシュらしさといったものが作れるかもしれない。しかし、情はそのままでは非常に抽象的なものである。杉山、寺井と同じ認識を持つためにも、しっかり具体化していかなければならないと思った。
社名を決めた時のように、竹谷は再び、ノートと睨めっこをする。
お金がすべてではない。おそらく、百度は聞いた言葉ではないだろうか。
情をどこまでも大事にできる会社にする。そういった思いで、ミリアッシュを作った。
その情のひとつは、まず杉山と寺井への報恩である。ふたりがいなければ、ミリアッシュは生まれなかった。
「ほかの道を選んだ人生の方が、面白く豊かだったかもしれない」
そんなことを、彼らには一度たりとて思ってほしくはない。ミリアッシュを選んでよかったと、音楽グループ『Linkin Park』の楽曲を聴くように、首を縦に振ってもらいたかった。
では、なにで報いるのか。ゲーム『FINAL FANTASY X-2』の楽曲『1000の言葉』という題名のように、感謝を1000回伝えるべきか。
もしくは、お金で応えるか。
その時、会社にあるお金は、資本金の330万円だった。売上が入金されるより先に、役員報酬の支払日が来る。設立1年目は役員報酬を控えめに設定し、会社に現金を残そう。そういったアドバイスも、インターネットや本から学んでいた。その教えに従い、まずは安くして、様子を見つつ上げていこうと考えた。お金がすべてではない。好きな業界で好きなことをやれるのだ。やりがいに満ちている。
しかし、拭えない拒否感が竹谷のふかふかした腹の底に居座る。ふたりに対して恩を返したいと言っておきながら、本心は実のところ、会社が潰れることを必要以上に恐れ、会社にお金を貯めておきたいと考えているのではないか。会社を長く続けていくことこそ第一に優先すべき事項だと、そんな高説をさかしらに掲げ、杉山と寺井という有為の人間をしめしめと安い人件費に繰り入れようとしているのではないか。
怯懦を打ち払い、卑怯なことをせず、真っ当に情を大事にするため、独立を目指したのではないか。ここで覚悟を持って証明せずに、なんのための起業か。私腹を肥やしてどうなる。すでに腹は結構出ている。お金がすべてではない、と名言を軽々に吐くなら、お金が会社に残らなくとも良いのではないか。なぜなら、お金がすべてではないのだから。
余剰なお金を会社に残さず、そして潰さない。
マンガ『HUNTER×HUNTER』のネテロ会長の覚悟を拝借するなら、「難敵にこそ、全霊を以て臨む」こと。その道こそ、竹谷の歩みたいと願う道だ。
役員報酬は、前社時の報酬よりも高い額に決めた。杉山も寺井も、低くて良いと思ってくれていたようだったが、映画『もののけ姫』のアシタカのように、押し通した。竹谷にとって情を大事にするというのは、こういうことを言うのだ。改めて、そう気づけた。
そしてもうひとつ、情を考える上で、ミリアッシュにとってなによりも大切なことがある。
作家との関係だ。
ミリアッシュはイラスト制作会社であるが、内部は杉山と寺井という懇切丁寧なディレクター2名と、ゆるゆるゲーマー1名である。イラストを実際に描いてくれているのは、前社の時から依頼を受けてくれている作家の皆様だった。作家の協力なしに、ミリアッシュは存在し得ない。しても意味がない。
役員報酬と同様に、稿料は前社の時よりも高くすると決めた。ミリアッシュが良い仕事をすればするほど、クライアントからいただく制作料は増え、作家へ支払える稿料の額も上げられる。現状維持では皆目駄目なのだ。クライアントから高い評価をいただき、制作料に反映してもらい、作家がもっと生きやすい世の中を実現していかねばならない。会社に余剰な利益が残ってしまいそうな時は、ボーナスのような形で作家へ還元するか、新たにミリアッシュで仕事を創出し、作家活動の一助としてもらおうと思った。
また、稿料の支払い日を早めていくことも、視野に入れた。
「入金は一刻も早く、支払は極力遅く」
たとえそれが経営と呼ばれる能力の大前提であったとしても、肯んじたくなかった。マンガ『蒼天航路』にあるように、人を顧みぬ刃は武ではない。信念のないスキルやテクニックは、もはや竹谷の吸収したいものではなかった。ミリアッシュから払うお金は、その先にいるひとたちのことをしっかり想像し、早められる限り早めるのだ。
作家は業務委託先だからとか、杉山と寺井はミリアッシュのメンバーだからとか、そういった区別も金輪際しない。その結果、会社の存続が困難な状況が生じたとしても、悔いはない。
そして、もっと作家と会う。イラスト制作はデジタルなものがほとんどで、メールやチャットで仕事は完結してしまう。だからこそ、対面でのコミュニケーションを忘れないようにする。例外もあるが、人間は人間の顔が見たい生き物だ。私は下戸だが、ビールのCMは、飲んでいるひとの表情にこそ購買意欲を刺激される。電車やバスなどで見かける広告も、タレントやモデルの顔で溢れているし、イラストも首から下だけの制作は、衣装デザインを除いてまずない。作家にはミリアッシュの3人を知ってもらいたいし、ミリアッシュは作家を知りたい。なにを見、なにを聞いて生きてきたのか。なにが好きで嫌いで、現状にどんな不安や希望があって、今後どういう仕事がしたいか。
当たり前のことだが、作家も我々も皆生きているのだ。それぞれに生き方があり、ストーリーがある。仕事への姿勢も十人十色である。膝を突き合わせて話し、仕事に悩みがあるなら共有してもらい、ミリアッシュとして解決できるものは解決する。喜びがあるなら、一緒に喜びたい。もちろん、作家によっては会いたくない、と思うひともいて然るべきで、その思いもきちんと尊重する。作家の皆様にとって、最適で最善な環境を常に考え続ける会社が、ミリアッシュである。
なんにせよ、たくさんの作家が、ミリアッシュと出会ったことで未来が多少なりとも上向きになるなら、それに勝る光栄はない。
確かなお金のやりとりを土台に、丁寧なコミュニケーションを取り、信頼関係を築いていく。社内と社外の垣根など吹き飛ばし、ミリアッシュの通奏低音を響かせるのだ。
こと恋愛ものにおいて、負ける方を応援してしまう傾向が竹谷には昔からあった。漫画『ときめきトゥナイト』では主人公の江藤蘭世ではなくライバルの神谷曜子が好きだったし、そこまで恋愛というわけでもないが、漫画『ふしぎ遊戯』では鬼宿ではなく柳宿や翼宿を応援していた。アニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』では、皆が大好きな歌『God knows…』よりも、その後に続けて歌われる失恋歌『Lost my music』の方が好きだ。
しかし、仕事では、相手に選ばれなければならない。情を、作家を大切にするのだと誓うのなら、なおさらクライアントから上位に指定してもらう会社となる必要がある。
イラスト制作会社は、たくさんある。大きな会社もあれば、漫画『左ききのエレン』で言うように小規模なブティック型の会社もある。食べるパイも座るイスも、マルチタップで繋げるコントローラーも数は限られているのだ。前社から続く関係やよしみでやれていたとしても、その温室でいつまでぬくぬくと暖を取っていられるかわからない。
月並みだが、他社との差別化を図らねば、と思った。ミリアッシュは、イラスト制作会社ではかなりの後発である。先輩が長身に筋骨隆々で逞しく見えるとも、早く肩を並べねばならない。後輩だからこそ、先輩がやっていないことを考える。後発には後発の進み方がある。産業革命は英国から始まり、大英帝国は漫画『エマ』で窺い知れるような繁栄を誇ったが、GoogleにAmazon、Meta(Facebook)そしてAppleと、今では後発の米国がしたたかに世界のビジネスをリードしている。
とはいえ、竹谷は凡人である。これができる、と胸を張れることはまったくない。新卒時代には、このぼんくらが、と上司の罵声を浴びたこともあった。
それでも、たったひとつだけ。ゲームだけは、やめなかった。
小学生から社会人へ、年を経て環境とステータスが変わっていくなか、皆が大好きだったゲームは、気づけば竹谷くらいしかやらなくなっていた。社会と世界が拡がり、興味対象が増え、各々がそれぞれの好きなものへと向かっていくなか、竹谷はゲームから離れなかった。離れられなかった。
それを空虚に思う時も、一再ではなくあった。
「子どもがやるもの」
そう言われるゲームを何十年も続けている自分は、どこか欠けている人間ではないだろうか。酒も煙草も飲めず、ギャンブルもやらない。大人の愉しみとされるものを嗜まず、モニターに向かってコントローラーをカチカチと指で弾く自分は、いったいなんなのだろうか。
趣味を見つけようと思った。アウトドアのアクティビティもやった。意味もなく、仕事終わりに街へ出かけることもあった。楽しいと思えたものも、いくつかはあった。
しかしどうしても、気づけばゲームに戻っている。
こんな人生はつまらない。そういう生き方しかできない竹谷も、つまらない。ゲーム依存症という言葉もある。ゲームに喜怒哀楽愛憎悪をぶつけ、また受け取る自分は、病気なのかもしれない。
そして、これらはすべてただの趣味話であり、会社の設立とは微塵の関係もない。
そのはずだった。
『HORIZON ZERO DAWN』というゲームがある。オーバーテクノロジーの失われた原始的な世界で、とある女性が強敵と戦いながら、世界の謎に挑むお話だ。荘厳なグラフィックとアクションの快感、そして重厚なシナリオで、間違いなく名作の一本である。当然竹谷は発売日に買い、すぐにクリアした。おでこを余すところなく出すポンパドールの髪型は昔から好きなのだが、主人公アーロイのポンパドールに惚れ直した。
映画よろしく、ゲームもエンディングにスタッフクレジットが流れる。良いゲームだったと余韻に浸りながら、下から上へ流れゆくスタッフの名前をそれとなく見る。
どれくらいの時間が経ったか。まだ、クレジットは続いていた。映画みたいに長いなあ、となんとなく思った。
そしてふと、胸中にひとつの思いが過ぎる。
同じだ。
映画と同じなのだ。信じられないくらいの人間が携わり、ゲームは作られる。それを信じられないくらいの人間が買い、楽しむ。
法律を犯すでもなく、大の大人が頭を捻りに捻って、どうしたら面白くなるかを圧倒的な熱量で研究して、ゲームは世に出されているのだ。
当たり前のことだ。しかし竹谷にはなぜか、新しい発見だった。
ゲームは人間が享受する、極上のエンターテインメントのひとつでしかない。子ども向けもあれば大人向けもあり、皆で遊ぶものもあればひとりで遊ぶものもある。インターネットに繋いで遊ぶこともできる。それだけ選択肢のある、素晴らしいエンターテインメントなのだ。依存症というが、そもそも趣味は没頭、つまり依存したくてやるものではないだろうか。古代にも音楽や絵画、祭事があった。そして竹谷は、現代の最高級に贅沢なエンターテインメントの味を、長い期間堪能させてもらっていた。
ありがたい。それ以外に、出てくる言葉がない。
恩を返したい。そう思った。漫画『進撃の巨人』で言われたように、ひとはなにかに酔っぱらっていないと生きられない。竹谷にとってはゲームに酔うことだった。酔わせてもらった。30年、ゲームから幸せをもらい続けてきた。次の30年は、ゲームを取り巻くさまざまな物事に、わずかでも明るい影響を残していきたい。太肉中背のぼんくらでも、やれることは、策と心胆を練ればきっとある。
奇しくも、会社を作った。事業はイラスト制作で、ゲーム会社からの依頼が大半を占めていた。
そこに、竹谷の私欲を少し乗せても、良いのではないか。
「CESAに入りたい。あと、東京ゲームショウに出たい」
童子のわがままにも似た声調で、杉山と寺井に伝えた。
CESAは「コンピューターエンターテインメント協会」の意で、たくさんのゲーム会社が所属している団体だ。前社の頃、年に一度のゲームの祭典である東京ゲームショウへ出展した折、その存在を知った。ちなみに前社が東京ゲームショウへ出展したのは、竹谷が企画や損益をせっせと拵えて代表に提案した結果なのだが、最新のゲームを会社のお金で試遊したいという単純な本音を、損益という複雑な建前に化粧したものだった。昔の方が、こういう小賢しさが竹谷にはあった。
しかし、前社ではCESAに加入しなかった。メリットがあるかという代表からの問いに、竹谷が答えられなかったからである。
今もまだ、効果は判然としていなかった。しかし、ふと思うことがあり、竹谷はCESAの加盟リストを眺め、ひとつのことに気づく。
イラスト制作会社で、CESAに加入しているところはなかった。つまり、ミリアッシュが入れば、イラスト制作会社で初めてのCESAのメンバーとなる。オンリーワンかつファーストワンであり、順位ならナンバーワンだ。また、イラスト制作会社で東京ゲームショウへ出展している企業も、ほとんどいなかった。
なら、設立初年度からCESAへ入会し、なおかつ東京ゲームショウへ出展することは、他社の塗り替えることのできない記録をミリアッシュに与える絶好の機会ではないか。
そして私欲としては、CESAと東京ゲームショウの一端を担うことで、ゲーム業界の隆盛に一寸でも貢献できるのではないか。
そんな会社の論理と個人の感情を綯い交ぜにふたりへ伝え、CESAへ入ることとなった。また、東京ゲームショウにも、会社が続く限りは出ることにした。
なんのことはない。今でも充分、竹谷は小賢しかった。
杉山、寺井と話しては、ミリアッシュとして共通した見解を編み出していく。俄かには信じがたいことであるが、3人で差異はほとんどなかった。作家をより大切にしていくことも、CESAへ加入して東京ゲームショウへ出展することも、3人での総意が難なく取れた。変なプライドや他人を出し抜いてやろうといった感情もなく、余計な茶々が入らず話が高速に進む。それだけで、独立して良かったと心から思えるほどだった。時折竹谷が変な挙動を起こしても、ふたりは目を細めて見守ってくれる。猪八戒ひとりに対し、三蔵法師ふたりである。天竺までの旅路が順調とならないわけがない。
話し合った内容を、小綺麗な文にまとめ、会社のウェブサイトに記載していく。ウェブサイトは、だいぶ完成に近づいていた。さまざまな企業のウェブサイトを見て、良いと感じた部分を節操なく取り入れる。先輩から学べることは、数えきれないほどある。そして、CESAへの加入に続き、作家への思いを記載したところの上部へ、漫画『るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-』の明神弥彦のように、見様見真似で理念という文字を加え入れた。
理念。
これが理念というものなのか、と思った。大切にしたいことを大切にする、という3人の意志と、ミリアッシュの存在理由が、理念という形を成して出力されていた。
それから、竹谷は気づく。
ウェブサイト、名刺、メール、契約書。どれを見ても、その文字列に違和感を覚えることはなくなっていた。竹谷は自然に、文字列を名として認識できていた。
ミリアッシュは、もうここにあった。
エピソード1:勉強と祖父
日本発祥の皆が知るスポーツに、ゲートボールという球技がある。しかし、ゲートボールをモチーフにした『ゲートマン』というゲームに見覚えのあるひとは、今や世界で数人しかいない。
『ゲートマン』は、ゲームセンターに置いてあるような筐体、つまり機械である。スティックを用いてボールを打ち、ゲートを通す。ゲートボールを、室内ゲーム機で遊べるようにした代物だ。色々な角度のゲートが代わる代わる出現しては、ポコっとボールを打って、ゲートの内側を通過すると喜色めいた音楽が鳴る。多くのゲームセンターマシンと同じく、1回100円だ。
そこまで広くはない、豆腐のような一階建ての建物。そこに『ゲートマン』は置いてあった。繰り返し100円玉を投入口に放っては、姉とふたりで交互にスティックを握り、どちらが上手か競う。竹谷の幼少期を顧みると、そんな記憶がやや色褪せて残っている。硬貨を溜めておく場所は開放されていて、何度も100円玉を回収しては、プレイすることができた。
竹谷彰人の母鷲尾和子の父、鷲尾栄一。
定年退職の後、祖父栄一は会社を設立し、オフィスを構えた。ふたりがけのソファが対面して2つ設置してあり、間にガラス製のローテーブル。そのテーブルの上には、漫画『名探偵コナン』に出てくるような、置物型のライターがあった。祖父は煙草を飲まないので、来客用だろう。いかにも、昭和然とした事務所である。
異色なのは、そこに試作機の『ゲートマン』があったことだ。
『ゲートマン』は、祖父が作ったゲーム機である。群馬県の病院に運動用のマシンとして、そしてなぜか池袋のとあるゲームセンターに1台だけ置かれていたようだ。どうして会社を興してまで『ゲートマン』を作ろうと思ったのか。疑問に思っても、悔しいことに答えを持つ人間はもうこの世にいない。
また、祖父は老後の趣味として水彩画を始め、それもどこかの施設に買い取られるレベルのクオリティに達していた。水彩画の作業机には、よくわからない硬そうな顔料がたくさん置いてあった。子ども用の絵具しか知らない竹谷は、これでどうやって絵を描くのだろうかと疑問に思ったものだ。塗り絵を手伝ってもらったことがあったが、漫画『ドラゴンボール』の孫悟空の力強く握られた拳に、祖父はこれでもかと言うほど立体感のある柔らかな着彩を成した。
「あきちゃん」
破顔しながら、竹谷のことをそう呼んでいた祖父。
優しく、笑顔で、そして多才。祖父を表するに、それ以外の言葉が竹谷には見当たらない。
頭が良くなりたい。ならなければならない。そういった観念が幼い竹谷の頭に早くから鎮座していたが、それは祖父を見ていたからかもしれない。世にふたりしかいない、竹谷が心からこうありたいと思えるひとの姿。そのひとりが祖父だ。渋沢栄一と鷲尾栄一という、ふたりの栄一。
ミリアッシュとどう関係するかわからないが、なにか根底を流れるものはあるかもしれない。これは祖父と竹谷と、勉強の話だ。
歩き、走り、跳ぶ。
跳んだ先には、どう見ても栗にしか見えない茸が迫っている。しっかりと踏み、さらに跳躍する。煉瓦を叩くと茸が現れ、食べると倍は背が伸びる。亀は踏むと、甲羅を蹴飛ばすことができた。
1985年9月13日、国内で史上最高級に売れたゲーム『スーパーマリオブラザーズ』は発売された。そしてその4日後の17日、東京都の調布で竹谷は生まれた。だれに抱かれても泣かない強靭なメンタルの赤ん坊だったようで、親の連れて行く先々で大人気を誇り、結構早く訪れた人生最後のモテ期を、モテ期と認識することもなく満喫していた。
神妙な顔つきの姉と異なり、女の子に見間違われるほど愛らしい容姿を宿した竹谷は、幼稚園の先生から贔屓されるくらい可愛かった。そのまま麗しく成長できなかったことは、人生が思うように進まない好例であろう。なかなか完治に至らぬ根強い夜尿症以外はなに不自由なく、幸せな幼少期を過ごした。
父はサラリーマンで、母は専業主婦。姉は面が変。なんとも一般的な家庭で育つが、今思うに、ひとつだけ特色がある。
映画の保護者的な視聴制限が、ほぼなかったことだ。
両親が故意にそうしていたかは知らないが、家では基本的に、どんな映画でも居間で流していたように覚えている。とはいえ、さすがにホラー映画は観たことがなかった、と思ってから、『シャイニング』を視聴した結果エレベーターに当分乗れなくなった記憶がよみがえる。セクシャルな成分が濃いものを除き、父母は当時人気のあった大体の映画をレンタルビデオ店で借りてきていた。いや、これも正しくない。『スピーシーズ』のような、エロス多めの映画も観ていた。それが助兵衛なものと認識できるほど成熟できていない頃だったが、なんとも自由闊達に刺激を受けていた。
ほぼと言ったのは、例外があるからだ。今でこそ違うが、当時はコメディ映画を観ることができなかった。なにが悪いのかジム・キャリーが出演しているものは特に駄目で、映画『マスク』をやっとのことで見させてもらえた。映画以外でもお笑いに対する風当たりは強く、テレビ番組『ダウンタウンのごっつええ感じ』はことさら敵視されていた。
インプットがあれば、アウトプットもある。幼稚園の年中の時、好きなものを絵に描きましょうと言われ、男児が先述のマリオを描いている中、竹谷だけ映画『ティーンエイジ・ミュータント・ニンジャ・タートルズ』を描いた。タートルズの亀たちは「カワバンガ」と鬨を発して事態に取り組むが、当時まったく意味がわからないながらも真似していた。今も理解していないが、発するに口が喜ぶ言葉である。その翌年、同じように好きなものを版画にしましょうと言われ、男児がゲーム『ロックマン』を描いている中、竹谷だけ映画『ターミネーター2』の最終場面、アーノルド・シュワルツェネッガー演じるT-800・モデル101型が、自らに埋まっているチップを破壊するため溶鉱炉へ身投げする感動的な一幕を描いた。どちらも、先生は苦笑していたような気がする。
今でこそゆるふわゲーマーとして毎日ゲーム機を酷使しているが、幼稚園児ではコントローラーを満足に操作できないからか、映画の方が記憶に残っているものが多い。しかしもちろん、ゲームもしていた。特に記憶に残っているのは『ファイアーエムブレム 外伝』だ。半ば強制的に次のステージへ進む前作『ファイアーエムブレム 暗黒竜と光の剣』と比べ、心ゆくまでレベルを上げてから戦いへ臨める今作は、竹谷の肌に合っていたようだ。この頃からすでに、地道に経験を積んでから場に臨みたいタイプだったことがわかる。さらに遡ると、人生で初めて手にしたゲームソフトは『ドラゴンボール3 悟空伝』という、すごろくと3Dダンジョンを合わせたようなアドベンチャーゲームだ。クリリンが殴られるドット絵を見て笑い転げていたように覚えている。クリリンはなにも悪くない。竹谷の性格が悪いのである。
幼稚園の思い出は、その程度だ。鼻血を自ら止血して先生に褒められたり、お弁当のコロッケを床に落として泣き、そのまま眠って気づけば母が迎えに来ていたり、という断片的な記憶はあるが、果たしてこれが本当にあったことなのか、後世の竹谷による都合のよい創作なのかは判然としない。ひとつだけ間違いなく言えることは、童謡『南の島のハメハメハ大王』を歌う時、ひたすら「かめはめ波」の一連のフォームを取っていたことである。
楽しいや面白い。悲しいや寂しい。そんな感覚はあれど、幼稚園の時の竹谷には、悩みや不安といったものはなかった。おそらく言葉がまだまだ頭の中で形成されておらず、従って考える力もなかったからだろう。
コンプレックスを初めて抱いたのは、小学生になってからだったように覚えている。とある言葉が、起点だった。中高生を経て大学受験を終えるまで、その言葉は竹谷の脳内を片時も離れなかった。
頭の良し悪しを、竹谷の中で指し示すもの。
「塾」である。
まだ学校で習っていない、なんなら教科書にも載っていないことをすでに知っているクラスメイトがいる。そのことが竹谷には驚愕だった。そうして、塾という存在を聞き知る。割り算は塾で学んだと、中学校を受験するために塾へ通うのだと、クラスメイトは言う。年齢の近い従兄弟も、塾へ通い始めた。
塾へ行っているひとは、おしなべて頭が良い。つまり塾は、頭の良いひとが行くものだと思った。頭の悪い自分の行くところではない。ゲーム『ストリートファイターII』や『マリオカート』で友人にまったく勝てないのも、『ダライアスツイン』で最終ステージまで進めずゲームオーバーとなるのも、竹谷の頭が悪いからだ。
劣等感のようなものが、竹谷の中で少しずつ確かに醸成されていった。
そんな小学生時代の楽しみのひとつは、群馬県みどり市にある祖父母の家で年越しをすることだった。最初は両親と一緒に行っていたのだが、高学年になると、電車の時間や乗り換えの順番が書かれたメモ用紙を握りしめ、浅草から赤城まで走る特急りょうもう号にひとりで乗った。自宅から3時間程度の片道切符に乗ることが、最高に楽しかった。テレビ番組『ひとりでできるもん!』の通り、ひとりで物事を完遂できる誇らしさというものは、小学生の竹谷にとってはひとしお甘美な味がしたのだ。
「あきちゃん、よく来たねえ」
終点の赤城駅では、祖父が車で迎えに来てくれ、助手席へ素早く乗り込むと、祖父母の家までの道のりを満面の笑みでもって眺めていた。今でもその街並みは、鮮明に思い出せる。祖父母と竹谷の3人で年を越し、車でやってきた家族がその後合流する。それが、竹谷にとっての年末年始の通例となっていた。
そろそろ小学校の卒業が近づいた折、中学生への抱負、といった内容の作文を書くこととなった。中学生になったらどんなことをしたいか、といったものだ。竹谷はそこに、勉強をがんばりたいと書いた。
「頭が悪いから、ほかのひとより、何倍もがんばらなくてはいけない」
頭の出来を極端に気にする小学生。その作文を読んだ母は、息子がいつの間にこんなことを考えていたのかと、驚きに息を呑んだらしい。
中学生になり、小学校では2クラスしかなかったのが、9クラスになる。一気に生徒数が増えた。ホームルーム早々、担任の先生が、自主学習をするようにとクラスへ言ってきた。宿題がなくとも、率先して予習や復習をすること。竹谷は、言われるまま従順に頷いた。毎日、授業で習ったことを専用のノートへまとめていく。
毎日、毎日。機械のように。
その甲斐あってか、中学1年生の最初の全校テストで、竹谷は20位以内に入った。5教科500点満点のところ、450点以上を取ったように記憶している。クラスでは2位か3位だった。その結果に、竹谷は少なからず驚いた。そうして気づく。どうやら、担任から言われたことへ忠実に、自主学習を進めていたのは竹谷だけだった。
意外と皆、大したことない。かすかに幻滅しながら、そんな風に考えた。
勉強すれば、結果が付いてくる。上位にいることの快感を覚えた竹谷は、勉強に一層の時間を費やし、常時学年10位以内に居るようになった。
部活はバスケットボール部に入っていた。言わずもがな、漫画『スラムダンク』の影響である。人生で初めて買った音楽CDも、アニメ『スラムダンク』の楽曲『あなただけ見つめてる』だった。登場人物の中では三井寿が好きだと嘯き、3ポイントシュートが得意なふりをしていたが、単純にコートを走りたくなかっただけである。すごい疲れるのだ。勉強とは対照的に、真面目に部活動に勤しむことが竹谷にはついぞできなかった。しかし、辞めることはしないのだから、なんとも中途半端な存在である。ちなみに、先日カラオケでアニメ『スラムダンク』の楽曲『世界が終わるまでは』を流し、ワンフレーズごとに代わる代わる歌い、三井寿がモニターに出てくる時に歌っていたらお酒を呷るという遊びをしたのだが、意外と三井寿は出てくる。色んな三井寿がいるのだ。下戸の竹谷にとっては、参加の仕方が難しい余興ではあるが。
それにしても、竹谷が先輩後輩といった概念に大いに当てられたのは、バスケットボール部が最初だった。
「『センパイ』というのは、1年とか2年早く生まれただけで、なんであんなに威張るんだろう?」
漫画『ハイキュー!!』で孤爪研磨も言っているように、竹谷も訝しんだ。小学生から空手を続けていたのも手伝って、「殴れば倒せるのに」という傲慢で乱暴な考えも持っていたように思う。なんにせよ、多感な時期に浴びた先輩後輩の上下関係は、まったく理解できないものとして映った。そしてその感覚は年月とともに濾過され価値観となり、今なお竹谷は、無意味に偉そうな態度を取る人間から距離を置こうと動く。不老不死なら、偉そうにしてもいいと思う。
祖父母の家での年越しも、中高生になるとやや意味合いに変化が起きる。祖父母が就寝した後、居間の掘りごたつで暖を取り、参考書と問題集を並べながらテレビのチャンネルを紅白歌合戦に合わせて、鉛筆と消しゴムを両手にカウントダウンへ臨むようになっていた。なにかと誘惑の多い自分の部屋と違い、祖父母の家はテレビくらいしか娯楽がない。しんしんと冷え、静まり返った一戸建ての掘りごたつは、勉強にうってつけだった。
竹谷が中学3年生のころ、祖母に先立たれてから、祖父栄一は自炊もするようになっていた。元旦、家族が揃う前に祖父とふたりで食べるお雑煮は、母の作るそれとはまた違った味付けながら、とてもおいしかった。祖父にできないことなど、ないとさえ思うほどに。祖父とふたりで過ごす空間と時間は、竹谷にとって最高級の贅沢品だった。
少し時間は前後するが、2000年8月26日にプレイステーション初となるドラクエ、その名も『ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち』が販売された。高校受験に向けた勉強真っ盛りの竹谷にとって、気になるあの子が大人になりゆく夏の終わりに超ド級のキラータイトルが出る、その辛苦を想像いただけるだろうか。悶々としていても脳内にスライムやスライムベスが現れては消えるので、勉強効率が落ちるだけだと判断して買ってもらった。200時間以上はプレイしたが、それでも学力を落とさなかった自分を褒めたい。そう、勉強するためにゲームは必要なのだ。
ただの自慢となるが、高校へは、同じ学校を志望していた生徒会長を押しのけ推薦で入学した。学力を始めとする竹谷の諸々の数字が、彼より高かったという話だ。
学校というものは、畢竟学力のある生徒に弱い。勉強さえできれば、校則を無視しても叱られることもない。そんな歪んだ認識を抱きながら、竹谷は高校へ入っても勉強を止めなかった。
「初心者でも遅くないわよ。手取り足取り教えてあげる」
バスケットボール部で舐めた上下関係の辛酸に辟易し、当時まだなかったがアニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』のように音楽バンドで体育館を沸かせたいなどと若気を至らせていたのだが、色気ある美人先輩マネージャーの誘いにまんまと乗っかり、バレーボール部へ入った。思春期の妙である。
結局また、意味不明な年齢の圧力に苛まされる3年間が始まる。中学の時と同様に、不真面目ながらも辞めないという中途半端な部員だった。ちなみに美人先輩マネージャーはふたりいたのだが、片方は先輩エースアタッカーのスパイクをレシーブした恋仲であり、もう片方はレシーブしたかったがボールが来なかったという始末だ。神聖な体育館でなにをしているのか、あの先輩らは。バレーボールをやり給え。
さらに言うなら、顧問のせいかバレーボール部の伝統なのか運動着の規則が厳しく、Tシャツはハーフパンツにインして、そのパンツも膝が見えていないと駄目だった。あまつさえ、靴下はふくらはぎを覆うほど長いものでなければならなかった。同じ室内球技のバスケットボール部と比較するにその洒落っ気の彼我は天地で、七分丈のハーフパンツにくるぶしソックス、ノースリーブのきゃつらを見ては、このような環境下でバレーボール部がモテる道理はない、と年頃の高校生らしく悲嘆に暮れた。
顧みれば、先輩エースアタッカーが美人先輩マネージャー相手に桃色三角形を拵えていたわけであるから、単に竹谷がモテなかっただけである。どうして左様に暗鬱たる情況へ陥ったかは、現在追憶するに色々と理由は見つけられるのだが、ここで述べる必要もないので割愛する。
勉強に部活に、気づけば竹谷は高校3年生になっていた。
ひたすらに続けた勉強の習慣により、校内で竹谷より学力のある人間はいなくなっていた。漫画『DEATH NOTE』の夜神月のように、学年首位を争う優等生となっていたのだ。もっとも、帰路に怪しげなノートが落ちていたら即刻交番へ届けただろうし、自称死神の異形が眼前へ現れたら、完治した夜尿症が白昼堂々再発したに違いない。
「頭良いねえ」
「勉強教えて」
男女問わず、周囲からこう言われることも自ずと増えた。そう声をかけられることを、煩わしいとさえ感じた。どうして、こんなレベルの問題がわからないのだろう。解答が用意されている問題を、難しいとなぜ思うのだろう。読めばわかるではないか。
自分のことを、頭の悪い人間だと思っていた。
しかし、他者に評され考えを改める。竹谷は、頭が良いのだと。
模試を受けることも、好きになっていた。早く結果が見たかった。とにかく満点に近い点数と、高い偏差値と、判定がAだらけな字面を眺め、上位であることを確かめたかった。
そう思う竹谷には、黒々とした快感が漲っていた。高いお金を払って塾へ通っても、竹谷に勝てないひとたちがたくさんいることが、嬉しくて仕方なかったのである。
そして、ほかの人間を軽んじた。
勉強もろくにできない、頭の悪い連中ばかりだと。
時計の針は、未明だということを教えている。
だいぶ遅い、むしろ日付としては早い時間でさえあるが、父も母も、姉も起きていた。
涙声だけが、時計の音以外で唯一場に生じていた。
その声の主は、竹谷である。童心に帰ったように、嗚咽まじりに喉を震わせている。
第1志望の国立大学に、竹谷は落ちていた。
号泣の理由は、ただそれだけのことだ。しかし、竹谷にとっては、開かれ、前途洋々に輝いていた未来が、突如鈍い金属音とともに閉ざされたような思いだった。
自分は頭が良いのではなかったか。なら、当然志望校に受かるではないか。その結果に到達できなかったのは、結局のところ、竹谷の頭が悪いことにほかならない。
頭が良いなどと高慢になること自体が、頭が悪いことの裏付である。模試に満悦し、手段である勉強を目的に履き違え、他人を嘲笑った。その罰が見事覿面となった。ざまはない。
浪人して来年また受験する、という選択肢はなかった。ちょうどその1年前、父の勤めていた会社は不況の煽りを受けて解散となり、実際の金額の多寡は知らないが、家のお金が潤沢でないことは高校生の竹谷でも理解していた。そもそも、大学受験に際しても、塾に通う経済力はなかったのだ。
だから、国立大学に入らなければ、と思っていた。私立はお金がかかる。また、父の会社がなくなるより以前に、姉は私立大学へ入っていた。姉弟揃って私立へ行くなんて、土台無理な話だ。そこまで勉強に打ち込まなかった姉を、憎んでさえいた。
勉強のできる竹谷は、お金のためにも、国立大学へ入らなければならない。そんな考えのもと、食事と睡眠以外は机に向かった。当初行こうと思っていた国立大学の偏差値を余裕で超える学力を身に付け、志望校のレベルを上げた。それでも模試の判定はすこぶる良く、間違いなく受かるだろう、と担任の先生からも太鼓判を押された。
しかし、そうはならなかった。
「一体どうしたんだ、竹谷?」
不合格の旨を学校へ伝えた時の、担任から来た反応だった。そんなこと、こちらが知りたかった。どれだけの時間を勉強に費やしたと思っている。もっとも、不合格の理由を知ったところで、合格となるわけもない。
滑り止めとして受験し、合格した大学はいくつかあった。そのうちのひとつが、早稲田大学である。しかし、国立大学を落ちた場合、第2志望として行きたいと思っていたのは、別の大学だった。早稲田大学は、いわゆる記念受験というものだった。高田馬場駅から大学までの道を、クラスメイトと談笑しながら歩くほどのお気楽ぶりだった。偶然、得意なところが設問として出題されただけである。
にもかかわらず、大人は皆、早稲田大学へ入るよう誘導してくる。だれしもが知っている、有名な難関大学。世界的なネームバリュー。
竹谷をよく知るひとは察してくれると思うのだが、竹谷はひとからなにか奨励されると、途端に反発したくなるような天邪鬼を心に飼っている。反逆の心ならゲーム『ペルソナ』シリーズのように覚醒しそうなものだが、ただ反対したくなるという、ぐにゃりと曲がった性格が出ているだけである。血気盛んな10代わんぱく小僧においては尚更、その天邪鬼さは頂点だった。
違う大学へ入りたい。その感情は刻一刻と強まってくる。反比例するように、早稲田へ行くべきという空気は竹谷の周りを重苦しく囲んできていた。
そして竹谷のストレスは、限界を迎える。
「本当は、勉強なんてしたくなかった」
両親から、何度目か早稲田を推奨された時だったように記憶している。堰を切ったように、一度開いてしまった口は、声を立て続ける。不合格となった不甲斐なさや悔しさを、八つ当たりに変化させ、竹谷は泣きながら話す。塾に通わせてくれなかった両親、国立大学を目指すこともなく、私立大学へ入った姉。ただ、竹谷の努力不足でしかないものを、自分が落ちたのは家族のせいであると、当たり散らした。勉強そのものを目的にし、数字に耽溺していたのは自分であるのに。
さらに、この頃の竹谷には夢があった。いや、厳密には夢ではない。ただの憧れであり、戦隊ヒーローになりたがる童子と大差ないようなものだ。
「お笑い芸人になりたかったんだ」
両親は当然として、姉も初耳だったはずだ。それどころか、仲の良いクラスメイトにさえ言っていない、秘めた心。
小さい頃、竹谷家ではコメディが禁止されていた。その反動か、高校生の竹谷はお笑いコンビ『ダウンタウン』の松本人志やビートたけしの著書を書店で買い漁っては読み、だれかを笑わせることに対して軒並みならぬ尊敬を抱いていた。
「でも」
勉強しなければならない、という漠然とした義務感。父の会社が解散し、家庭にお金がないだろうという状況。そして、竹谷がたまたま勉学に結果が出せたこと。そういったものに、雁字搦めとなっていた。
お笑い芸人を目指すなど、絶対に言えなかった。そういうものさえなければ、竹谷は自由を得て、お笑い芸人になれたかもしれないのに。
被害者ぶった理屈を大仰に掲げ、竹谷は家族を執拗に責めた。環境を恨んだ。本当に目指すなら、目指すなりの行動を起こすものだ。つまりはこれも、ただの憂さ晴らしに過ぎない。結果を出せなかった自分の、薄っぺらく軽いプライドを守るために、ありとあらゆる外的要因を引きずり出して責任を転嫁したのだ。
号泣する竹谷に家族はどう反応していいかわからず、ただただ竹谷の気持ちが治まるまで話を聞いてくれていた。
本当に情けなく、思い返すだに悶絶しそうになる。よくここに書いたと、自分を褒めたいとさえ思う。
自分のために世界や社会があるわけではない。期待通り物事が進む保証もない。そんな当たり前のことを、竹谷はようやく知ったのだ。
国立大学には、後期受験というものがある。竹谷が落ちたのは前期なので、後期も受ければ合格の可能性はあった。しかし、竹谷はその選択を取らなかった。矮小な精神は擦り切れた襤褸となり、立ちあがることを拒んだのだ。ましてや、前期受験の日である2004年2月25日、試験が終了次第大急ぎでゲームショップへと駆け込んだ竹谷は、吟味に吟味を重ね、発売から1年ほど遅ればせながらゲーム『真・三国無双3』を買ったのである。大学受験のためゲームを封印してから、丸1年が経っていた。後期受験どころではない。竹谷は今や、三国統一という大義を成し遂げなければならないのだ。
泣き腫らして落ち着いたのか、周囲から諭しに応じ、早稲田大学へ入ることはもう決めていた。一般的に、早稲田への入学は受験戦争において成功と見なされ、クラスメイトからは羨望の視線で見られもした。何年も浪人して、されど入れないのが早稲田で、だから、竹谷の大学受験は成功なのである。言い聞かせるように、何度も胸中で思った。
それでも、入りたくないという気持ちは残った。自分にとっては、失敗でしかなかった。ちょうどその数年前、早稲田大学は未曽有の性的暴行事件で連日ニュースに取り上げられていた。性犯罪に嫌悪を覚える性格もあってか、どうしても良いイメージを持てなかった。
そんな折だ。
「じいちゃんから」
母が、手紙を渡してきた。祖母に先立たれてから、祖父栄一は少し弱々しくなっていた。何度か、入院もしていたように記憶している。脳溢血で、言葉が若干不自由になっていた。
ペンを持つ手も、強くはなかったはずだ。
それなのに、竹谷に手紙を書いてくれた。
彰ちゃん
合格おめでとう 頑張ったね
去年のお正月 群馬へ来た時の頑張りの
様子姿 彰ちゃんを思い出すよ その時の
ゾーニの一杯 旨いと言ってくれた、忘れないよ
彰ちゃんが未だ歩けない 小さい頃 一日長時間
一人で母さんの来るのをハイハイし乍らこの部屋
に居た頑張りが姿そのものえらいよ
ぢいちゃん今後居る場所が変わっても
彰ちゃんの将来をもう少し見て生きていくよ
これからは無茶はしないで 上手に勉強してね
そして 社会に立上る姿を見たい。
読みやすいとは、お世辞にも言えない。
話の時系列も飛び飛びで、支離滅裂である。
しかし。
祖父栄一が竹谷を愛してくれている。それだけは、ありありとわかった。
「合格おめでとう」
祖父からの一言。そのたった一言に、竹谷は目の醒める思いだった。
頭の悪い自分が、頭が良くなりたいと願い、勉強し続けた10年は、この時のためにあった。だれよりも尊敬し、こうなりたいと思う存在である祖父に、おめでとうと言ってもらうためだったのだ。
「じいちゃん、あきが早稲田に合格したのかって、ものすごく喜んでたよ。会う人々に、自慢してるみたい」
母が、祖父の状況を付け加える。目で祖父の文字を追い、耳で母の言葉を捉える。自ずと、竹谷の顔から笑みが零れた。
失敗は成功ではない。そして失敗は、他者の評価に寄らず、自分がそう思えば失敗である。竹谷の人生において、大学受験は成功とは言えない。
しかし、祝福してくれるひとがいた。
不合格がなんだというのか。竹谷の努力を喜んでくれるひとが、こんなにも身近にいた。祖父だけではない。父も母も、おそらく姉もだ。それが、なんと幸せなことであるか。
頭の良し悪しなど、心底どうでもいい。
結果を求めて努力することは、竹谷にとって生きていく上で非常に大切なことだ。そして追えば追うほど、自分の想定に沿わないことは、無尽蔵に出現する。結果は伴わないし、計画はひらひらと覆る。しかし、目線をあげて進む間に、志を同じくするような人々が、自然と近くにいる。そんな時、漫画『ムヒョとロージーの魔法律事務所』で語られるように、「本当に人に要るのは努力の成果や、才能の成果より、好きな人達」であると感じ入り、また次なる目標へと進んでいくのだ。「大切なものは、ほしいものより先に来た」と、漫画『HUNTER × HUNTER』のジンのように、胸を張って言い続けるために。
その数年後、祖父鷲尾栄一は長逝する。寿命だった。祖父が誇りに思う早大生として、竹谷は火葬場の煙突から空へ混ざりゆく煙を見送った。
学歴を賛美するつもりは毫もない。ただ、竹谷が勉強と出会い、勉強し続けたその果てに、祖父の笑顔があっただけだ。
努力が報われたと思うのに、結果が要らない時もある。そんな場合が、あってもいい。
一歩でも、祖父のような人間に近づけているだろうか。葬儀の進行する中で、そんな恥ずかしいことを、恥ずかしげもなく思った。祖父の手紙にあるように、竹谷が社会へ立上る姿を、祖父は見ることができなかった。悔やんでも、そればかりはどうすることもできない。
今、往年の祖父のように会社を設立し、日々あがいている竹谷の姿を、祖父はどう思うだろうか。少し考えてから、詮ないことだと、緩い息が漏れる。
どんな竹谷になったとしても、きっと祖父は優しく笑ってくれるだろう。故人の思いを勝手に推量するのはよくないが、竹谷の祖父鷲尾栄一は、間違いなくそういう人間だ。
そして竹谷も、そのようでありたいと心から思う。
エピソード2:自殺病
今から書くことは、フィクションだと思ってほしい。
いかに熱い海と書けども、6月の熱海は、まだまだ寒い。
旅館で着替えた浴衣をまとい、竹谷は海に面して立っていた。曇天に眺める海面は、空を反射し灰色に見える。砂の色も暗い。
孤独にひとりぼっちではないし、だれかとしっぽりふたりきり、というロマンスでもない。
竹谷の所属する営業部が、先月ものすごく良い成績を出した。その褒美として、会社から与えられた社員旅行だった。
50人程度の部署で、そのうち新卒は、竹谷を含めて10名くらいだった。4月に入社してまだ2ヶ月であり、上司とも同期とも、そこまで親睦を深めているわけではない。
突然、クイズ形式の大喜利を、部長が始めた。テレビ番組『内村プロデュース』を模倣した体のものである。
「この海で、このあと一体なにが起きるでしょうか」
まさに内村光良のような声色で、部長がお題を出す。ご丁寧に、押せばピコンと音の鳴る小道具も持ってきていた。
上司や先輩たちが、受けを狙って解答していく。ビーチフラッグをする。全裸で走る。首まで砂に埋まる。虚心坦懐に言えば、とても成人の集まりとは思えないような、くだらない内容ばかりだった。
なかなか部長を納得させる面白い回答が出ないなか、いかにも思いついたという風で、部のエース営業マンがボタンを押す。回答権を指し示す高い電子音が、竹谷には処刑器具の軋む音に聞こえた。
「新人が全員、脱いで海に飛びこむ」
もったいぶった間が流れる。そして部長は当然に、数字、換言すれば売上を作ってくれる営業マンに優しい。
「大、正、解」
叫ぶように声をあげてから、部長はからからと笑った。一拍遅れて、周囲からも笑い声が轟く。部長が笑う内容は、笑っていい内容である。
新卒社員がずらっと、下着のみで立ち並ぶ。もちろん男性だけであり、つまりは竹谷もマンガ『ドラゴンボールZ』のベジータの息子を穿いているだけだ。
ありがた迷惑にも、助走に適した堤防が海に面して作られていた。カタパルトの滑走路よろしく、最短の助走で最長の飛距離を稼げるような長さである。
やるしかない、という空気が、ゲーム『ペルソナ5』のメメントスのように、新卒の集合意識下に流れる。新卒のひとりが、早く終わらせようと言わんばかりに率先して走り、そして跳んだ。部長を始め、先輩たちの笑い声があがる。
当たり前だが、竹谷はなにひとつ面白くなどなかった。日頃海に行くようなタイプでもなく、真夏でも真珠かと見間違うほどの白き肌を持つ竹谷が、なぜ黒く曇った寒空の下、海に飛びこまねばならないのか。別に禁断の恋をした人魚でもないのに。
次のひとりが駆ける。
今思えば、日和らずに竹谷もとっとと続くべきだった。
「竜巻旋風脚」
跳ぶや否や同期はそう叫び、片脚を大地と平行に上げ、駒のように回転しながら海へ落ちた。
知る人ぞ知る、ゲーム『ストリートファイター』シリーズで大活躍する格闘技の必殺技である。厳密に言えば、空中で竜巻旋風脚を出せるようになったのは『ストリートファイターIIターボ』からであり、奴の飛んだ軌道はほぼ『ターボ』のそれであった。
そうだ、この同期は、少し阿呆であった。どうせこの身滅ぶなら面白く、と戦国武将が賛同しそうなことをする。問題なのは、この同期には大義がないことだ。突如後悔が竹谷を巡るが、もはや是非もない。
「おもろいなあ、あいつ。ええやん、次のやつも技をやれ、技を」
抱腹しながら、部長は言う。
2008年6月、22歳の竹谷はかくして、熱くない熱海の海にほぼ全裸で落ちた。産声を上げてから常時インドアおよび陰キャである竹谷は、修業でもないのに冷えた水へ潜ることになるとは思ってもみなかった。
ゲームでは何度出したかわからない技。そして子どものころ、幾度となく真似をした技。技の名は、昇龍拳と言う。ただ、ゲームと違うのは、対戦相手などどこにもおらず、着地点が地面ではなく海面ということだ。
「昇龍拳」
聞こえ始めた笑い声は、海水の中で遠く響く。
上司の指示は、王よりも絶対である。嫌な気持ちに襲われても、反抗しようなどとは到底思えない。退職という選択肢も、竹谷の頭には寸毫たりとてなかった。せっかく入社できた会社である。たった数か月で「さようなら」なんて、間違いを認めてしまうようで無理だった。ましてや竹谷は新卒である。「とりあえず3年」という言葉も重くのしかかり、会社を辞めることはそのまま、社会人としての死に繋がる。そう思いこんでしまっていた。
死ぬのは、だれだって怖い。
数年後、対極的に、竹谷は死にたかった。
社会人としての死を恐れに恐れ、一段また一段と、自殺への階段を踏みあがっていく。
働くことは、好きだったはずだ。大学生の時、バイトの日を心待ちにしていたように覚えている。それが、社会人となり数年が経ち、なにも感じなくなっていた。
「あの頃は楽しかった」
夜、頬を刺す疼痛に起こされながら、そんなことを呟く。
お酒に極めて弱いことは、だいぶ前から知っていた。未成年であるにもかかわらず、なぜ自身のアルコール体質を知っているかは実に摩訶不思議なことであるが、往々にして、ひとはなぜか成年となる前に飲酒の適不適を知っている。
「普段どんな活動されてるんですか」
「みんなで遊んだり飲んだりしてるよ」
大学生活の特典であり華と言えば、サークル活動である。2つ上の姉は、オールラウンダー系というなんだか格闘家みたいなジャンルのサークルへ入り、日々遊びに飲みに大忙しだった。学生の本分は一にも二にも遊びである、と言わんばかりに。
竹谷も世の大学生に続けと、いくつかサークルの新入生歓迎会などに顔を出していた。
旅行、美術、仏像、お笑い。
たまたま竹谷の行ってみたサークルがそうであったのか、もしくはサークルとはそういうものなのか、活動内容を質問して返ってくる答えは、遊びと飲みだった。
悲しいことに、どのサークルを体験しても、面白さといったものが竹谷には感じられなかった。お笑いサークルも、普段はみんなでサークル部屋に籠り、ゲーム『スーパーボンバーマン』をしているらしい。せめて『スーパーボンバーマン3』であってほしかった。ルーイに乗りたいのだ。どうせゲームに勤しむのなら、竹谷はさっさと家に帰り、『サイレントヒル4 ザ・ルーム』をやりたかった。話が逸れるが竹谷はホラーゲームの金字塔『サイレントヒル』シリーズが大好きで、個人制作のホームページが全盛期だった高校生の時は「バイオハザード・サイレントヒルを考える会」というウェブサイトによく出入りしていた。中でも『サイレントヒル2』に出てくるクリーチャー「三角頭」を愛している。
サークルに入らず家でゲームをする竹谷を、両親は多少なりとも心配していたように覚えている。人生のゴールデンウイークとも呼ばれる大学生の時期に、もっと遊ばないでどうするのか、といった論調だ。竹谷は人生で一度も「勉強しなさい」と言われずに育ったが、ついに親のゆるふわ教育方針は佳境へと到達し「もっと遊ばんか」となった。当時はまだ言葉がなかったが、パーティーピープルな姉と比較していたのだろう。
そんな矢先、暇そうにしている竹谷をどこからか嗅ぎつけたのか、高校時代の部活の先輩からバイトの誘いが来た。
「なんのバイトですか?」
「塾講師」
小中高とほぼ通わなかった塾。その講師のバイトを誘ってくるのだから、なんとも皮肉めいた帰結である。ちなみにこの先輩は恋のエースアタッカーとして名を馳せていたのだが、その話はエピソード1に譲ってあるので、お忘れの方は再読願えればと思う。恋のエースアタッカー先輩も、大学生となり晴れて恋の塾講師先輩となったわけであるが、竹谷が講師として働き始めた頃にはすでに、同じく先輩の、古風に言うならマドンナ講師と恋愛関係にあった。神聖な塾でなにをしているのか、あの先輩らは。授業をし給え。
サークルに入る気が皆無だった竹谷は、なにとはなくその誘いに乗った。実際のところ、講師が新しく講師を紹介すると一万円がもらえるらしく、恋の講師先輩はその紹介料を目当てとしていた。そしてそのお金は、紹介人と被紹介人とで折半するのが通例だったらしいのだが、お前にはやらん、と一言はもらったものの、ついぞ一円ももらえることはなかった。そんなひどいことがあるのか。
続けてみると不思議なことに、講師は竹谷の性格に合っていたようだ。教えなければならない事項を時間配分しつつ考え、とにかく生徒が笑ってくれるよう努める。言葉遣いに気をつけて、抑揚や高低を意識して話す。
「竹谷先生の授業は面白い」
そう評されることが嬉しかった。お笑い芸人になりたかった竹谷のフラストレーションは、面白さを第一に掲げた授業という形で発散された。
塾講師の仕事を熱心に続けられた理由として、目的や意義の魅力は大きかった。生徒たちの、志望校への合格。塾生それぞれの人生の、岐路に立ち会うのだ。
最終目標を志望校合格に置き、学校や模試で塾生に良い結果を残してもらう。熱意をもって授業へ取り組み、塾生のモチベーションを上げ、学習に集中できる環境を作る。無形商材であり、且つ出資者はサービスを受ける塾生自身でなく保護者である。難しい仕事ではあるが、その分成果を出し、信頼され、塾生と保護者の双方から喜びの声を聞くことは、とびきり充実感を得られるものだった。
また、だれかになにかを教える、ということは、想定以上に知識の量を必要とする。中高生対象の英語を担当した竹谷は、単語や文法の知悉は当然として、なぜそうなったかという経緯を探っていった。やわらかく散りやすい知識が、段々と凝り固まっていき、揺るがないものとして結集していく感覚は、なかなかに気持ちがいい。たとえば、腕を意味する英語「arm」は、はるか昔「くっついたもの」といった意味を持っており、つまり体にくっついているものだから腕で、腕にくっつくものだから武器「arms」で、武器を持って声を上げるから警戒を示すアラーム「alarm」となり、全身武装した出で立ちをしているからアルマジロ「armadillo」である。さらに言うなら、高校生の竹谷がまったくモテなかったのはワックスで髪をねじりすぎていたからだ。髪は粘土ではない。どんなことにも理由がある。そして理由は興味を引き、塾生のやる気を少なからず引き出せた。
週に2日から始まった塾講師のバイトは、気づけば週5日に増えていた。平日皆勤である。小学生と異なり、中高生の授業時間は基本的に夕方以降となる。授業を終えたあとも、自習している生徒の質疑応答をするため、塾から退出する時間は日付変更するかしないかというのが常であった。当然ながら、サークル活動をする余裕はなく、バイト三昧の日々となる。土日祝日には模試や保護者説明会等が入ることもあり、週に7日働くこともままあった。地獄のミサワ先生の『惚れさせ男子』のひとり「すなお(27)」からお言葉をいただくなら、「実質1時間」しか寝てない日も割とあった。
受験のある年次、つまり小六、中三、高三は、塾業界では絢爛の年であり、生徒の入塾数が増大していき、そして生徒数に伴い業務が過酷となっていく年である。
塾講師となって1年が経過した折、ご指名により中三の学年主任を竹谷は頼まれた。当時の塾では最大規模となる塾生の成績を見、10名前後の先生たちと連携を取りながら、授業や会議を進めていった。チームでことに当たる竹谷の働き方の姿勢、そのベースとなるようなものは、間違いなくここで形成されたと思う。ほかにもいた主任候補のベテラン講師たちから、塾の今後を考えて2年目の竹谷を主任に推してくれたのは、ほかのだれでもない恋の講師先輩であった。経験の浅さを理由とした反対意見もあったようだが、彼の采配あって竹谷は無事に主任となり、貴重な経験を積ませていただいた。恋だけでなく、仕事もきっちりと考えられる先輩であった。それはモテるわけだ。得べかりし紹介料のことは、もう忘れることにした。
ゲーム『ファイナルファンタジーV』にたとえて、宿題が「ゴブリン」のような雑魚敵、模試が「ギルガメッシュ」や「ツインタニア」といった中ボスであるなら、受験は大ボス、つまり「エクスデス」である。意図せず手に汗握るほど、緊張で盛りあがるバトルが大ボスであるのと同様に、塾講師のもっとも甲斐ある瞬間のひとつは、受験日である。受験日には、早朝から試験開催地の最寄り駅や学校の門前に立ち、懐炉で手を温めながら塾生が通るのを待つのだ。塾生が来ると、握手とともに激励の言葉をかけて見送る。強張っていた塾生の表情が、講師たちを見つけることでふわりと和らぐ。
「いつも通りにね」
「行ってきます」
勇気を宿した笑顔を見せながら、決戦の地へ挑む塾生の背中に、講師たちは祈る。応援しかできなくとも、応援することだけはできる。だれかの幸せを願うことは、それ自体が幸せなことである。
そして、合格発表の日も、この上なく大切な瞬間だ。朝から講師たちは教室に集まり、電話機の前で待機する。当時はスマートフォンというものがなく、また講師は生徒と私的に繋がることが不文律ながら禁止されているので、携帯電話も使用できなかった。電話が鳴るのを、講師一同固唾を飲んで待ち続ける。会話も少ない。電話が鳴ると、かるたをやっているかのように講師たちは我先にと受話器を取る。塾生が名乗ると、担当している先生に代わる。
「おめでとう」
「そうか」
およそ講師の第一声は、このふたつに分かれる。言うまでもなく、前者が合格で、後者が不合格である。悲喜は当然入ってしまうが、生徒の努力を労い、電話を終える。中学一年生から見てきた生徒であれば、3年間の記憶の奔流が、心を瑞々しく通るのだ。塾講師でなければ、体験できない感動がある。
結局、4年もの間、つまり大学生中ずっと塾講師を続けることになったのだが、辞める時に塾生からもらった手紙や色紙は、今でも大事に保管してある。先日読み返したのだが、まあとにかく妙にこそばゆい。しかし改めて、塾生たちの人生に少しでも良い影響を残せたのなら、講師冥利に尽きると深甚に思った。
チームで仕事をする面白さと、事業の意義。
当時はこれといって考えることもなかったが、竹谷が人生を謳歌するにあたり、不可欠なものが塾講師の仕事には明々とあった。
企業へ電話をかけて、商談の時間設定をすることを、テレフォンアポイントメント、略してテレアポという。
竹谷が新卒として営業会社を選んだ理由は、苦手分野を克服したいと思ったからだ。元来ヴィブラニウム製の筋金が入ったひと見知りで、初対面の相手には敵意はなくとも睨むことしかできないような人間である。
その自分を、なんとかして変えねばと思っていた。そして、営業を仕事にすれば、否が応でもひとと話すわけであるから、ひと見知りだのと駄々をこねる暇もなくなるのではないかと思ったのだ。
テレフォンを名に含むだけあって、まずは電話で相手に興味を持ってもらう必要がある。確率で話すならおおよそ1%程度、100件かけて1件アポイントが入るかどうかといったものだったが、少しでもその数値を上げたかった。電話する時の話し方の原稿、通称アポトークを作り、さらにはレコーダーを買って、自分の話し方や声を録音し、把握することに努めた。竹谷の喋りの原型は、この頃に築かれたのだろう。多い時には、朝から晩までで400件くらい架電したように覚えている。
商材は複合機、平たく言うならコピー機である。コンビニエンスストア等に置いてあり、10円でモノクロコピーができる、その機械だ。さまざまな会社へ電話をかけ、アポイントを取っては、訪問し購入してもらう。1台大体50万から200万円ほどする代物だ。企業とはいえ高い買い物であり、また毎年壊れるほど脆くもないので、なかなか売れる商品ではない。
関東圏のあちらこちらへ行き、初対面の社長相手にものを売るという経験は、暗い性格も手伝って正直心労が尋常でなかった。だが、商談を通じて社長と仲良くなり、無事に売れ、社長が契約書に印鑑を押す時の高揚感は軒並みならないものがあった。居座ってしまい怒られたり、門前払いされたりすることも二度三度ではなくあったが、どうすれば社長の気に入ってもらえるかを考え、コミュニケーションを取り、最終的にはコピー機を買ってもらう。商品ではなく、竹谷を買ってもらったのだ、と思える瞬間だった。
しかし、新卒二年目となった頃に、ある思いが頭を掠める。また1年間、毎日テレアポをするのかと。いつもの弱虫が出た。そして虫は、自らの意思と関係なく算出を始める。1日300件として、1週間の5日稼働で1,500件、ひと月で6,000件、年間で概算すると72,000件。肩と耳の間に受話器を挟みすぎて、あごが曲がって炎症ができていた。70,000件以上、電話をかける人生がまた始まる。体の異常に連動するように、竹谷の心も白旗を振り始めていた。
そんな折、新しく子会社を作るにあたり、新会社の管理部門を募集している旨を、社内報で竹谷は知る。営業と異なり歩合がもらえるようなことはないが、着実にスキルアップができ、年次とともに給料が上がっていくような仕組みがそこにはあった。スキルアップできる環境、という言葉ほど今や胡散臭いものはないが、当時の竹谷はテレアポから逃れたい気持ちに亡霊のごとく憑かれ、新会社の管理部へ可及的速やかに応募し、なんとか所属することとなった。
とはいえ、テレアポとコピー機を売ること以外、竹谷にできることはなかった。そのため、しばらくは本社の管理部へ赴き、研修漬けとなる。殊更エクセルに関しては厳しく指導され、ベストセラー『神速Excel』には遥か遠く及ばないものの、高速エクセルくらいの速度は会得できた。ゲーム『ドラゴンクエストVI』で言うと、「ばくれつけん」は打ちこめないものの「はやぶさぎり」なら繰り出せるようになった。
無事に研修も終わり、新会社での管理部も高波あれど楽しく過ごしていたのだが、新会社の損益が良くなかった。新会社の社長は本社に戻り、部長からやり直すという運びとなってしまう。燃え盛る炎のように、急速で激しい人事決定であった。
そして、火の粉は竹谷にも降りかかる。
「竹谷、俺についてきてくれない?」
新会社での仕事を楽しんでいた竹谷に、社長はそう誘ってきた。
「そのお誘いは大変ありがたいのですが」
竹谷は断る。歴史ある本社で、がちがちに踏みしめられた管理業務を歯車のように遂行するより、新しい環境で、最初から管理部として働けていることに価値を見出していた。
「寂しいこと言うなよ。竹谷、俺についてきてくれない?」
そんなやり取りを、何度かした。ゲーム『ドラゴンクエスト』シリーズでは、「いいえ」を選んでも進まないお決まりのパターンがある。それを現実で体験することがあるのだ。
ドラクエのいいえパターンを覆せなかった竹谷は本社へ戻り、営業本部という営業部と管理部の間に立つ業務に従事する。漫画『銀魂』の万事屋のような仕事である。数値を作ったり、分析したり、お偉方の秘書役としてゴルフ場や宿を予約したり。また、営業部からの管理部への批判が出ればやんわりと管理部へ申し出をし、逆に管理部から営業部への不満が出た際は、ユーモアを交えつつ営業部へ意見を伝えた。マルチタスクが得意です、などとお洒落に言えるようなものではない。圧力で形成された不快な手に後頭部を力ずくで押さえられ、泥沼へ深々と顔を沈められる。窒息する、と思う寸前にだけ顔を引っ張られ、気まぐれに呼吸を許されているような状況だった。
ここは墓場だった。
さらに、営業本部では新しい上司のもとに付いたのだが、竹谷はこの上司とまったくそりが合わなかった。ひとつのミスを、30分くらいかけて責められる。その時間でミスを取り戻せるとは思っても、上司は自らの気が済むまでなじってきた。周囲でそれを聞いている人々も、触らぬ神に祟りなしと、傍観を決めこむ。出社する竹谷の足取りはゲーム『DEATH STRANDING』で荷物を持ちすぎたサム・ポーター・ブリッジズのように重く、帰る時間もゲーム『ペルソナ3』の影時間ほどに遅い。退勤時間を過ぎてから開始された会議では、怒号と罵声が飛び交い、終わるころには帰る電車がなかった。もちろん、宿泊代が経費として認められることもない。
粘着質な上司。累積を止めない業務。ひとをひととも思わない罵倒。
今すぐ死ねよ。
そんな言葉が、挨拶のごとく行き交う。耳は慣れ、やがてなにも感じなくなった。
しかし、どうやら心は慣れないみたいだ。
蝸牛のように這いずってくる異常に、竹谷はまったく気づけていなかった。
人生で初めて、MRAを受けていた。脳血管を立体的な画像として抽出する検査である。
「ストレスですね」
「そうですか」
右頬を押さえ蠢く痛みに耐えながら、医師のコメントに返す。
「ストレスでなにか発症するのは当然ではないか」
そうは思いながらも、医師へ八つ当たりしても仕方ない。
三叉神経痛。
そう診断された。聞いたことのない病名だ。竹谷の場合は、右の小鼻の奥。そこの神経と血管の重なり具合に、問題がありそうと言われた。そこを起点に、目や頬の神経を伝うように痛みが走る。形用するのが難しいが、無数の尖ったやすりで顔の内側を削られるような痛さ、とでも言えばいいだろうか。頻度や程度はその都度異なるが、酷い時はあまりの痛さに涙が勝手に出て、顔は大きく歪んでしまう。
「どうすればいいですか」
「環境を変えた方がいいと思います」
「さも簡単そうに言うではないか」
再び当たりたくなっても、医師もそう助言するしかないのだろう。
三叉神経痛は、原因がまだ突き止められていない。とりあえずカルバマゼピンという薬を服用すると症状が和らぐから、それが処方されるといった塩梅だ。多数の罹患者がその薬で改善するらしいのだが、竹谷はいよいよ効果を得ることができなかった。
薬が駄目なら、次は手術である。首裏から頭蓋骨に穴を開けて、右の小鼻の起点となっていそうな神経と血管が、重ならないよう分けてテープで固定する。脳の近くを手術するので、後遺症が残る可能性もわずかにある。ほかに、ガンマナイフというレーザー手術もあるが、これもなぜ効くのかはわからない。選択肢の少なさと、その選択の不明瞭さに、竹谷はどれも選ぶことができなかった。
最初に違和感を覚えたのは、2010年秋の25歳、出勤する前にシャワーを浴びていた時だった。洗顔フォームを手にとり、顔を洗う。その時、ずんと重いなにかを、右鼻の奥に感じたのだ。もちろん、原因は皆目わからない。頬を擦っていた手を止め、シャワーの流れをそのままに、ただ困惑していたように覚えている。洗顔が、この日から少し怖くなった。
次は違和感でなく、もっと明確な熱さのようなものだった。2011年の初夏、体重90キロの巨漢竹谷は毎日ラーメンかカレーライスを食べていたのだが、その日はササミチキンカレーだった。タバスコを適量かけ、ピザっぽく食べるのが好きだった。大口を開けて頬張り咀嚼した時、名著『赤い実はじけた』のように、右鼻に熱さが広がったのだ。痛さとも違った、弾けるような熱さ。洗顔時と同様に、妙な緊張で汗を吹き出しながら、口元へ差し出したスプーンを持つ手が止まる。この時から、食事にも恐怖を覚えるようになった。
無意味な仮定だが、この時にしっかりと対処していれば、未来は変わったかもしれない。しかし、発症する頻度の低さに、竹谷は危機感を抱くことがなかった。
熱さはやがて痛みとなり、顔の右側を走った。
初めて痛みが生じた時は、もう記憶にない。ただただ、焦ったように覚えている。顔が痛くなる、その理由がまったくわからないのだ。口を動かすと、ビキビキとした疼痛が顔の奥から表面へ浮かんでくる。食事や歯磨きはもちろん、くしゃみも、喋ることさえ怖くなった。さらに酷い時には、歩行や立ち上がる動作でさえ痛苦の起点となった。
もう少し、三叉神経痛を説明することを許してほしい。ゲーマーめいた解説となってしまうが、三叉神経痛はゲージとトリガーで構成される。格闘ゲームやRPGなどでよくある、超必殺技のようなゲージである。時間の経過とともに、ゲージは溜まっていく。その速度は一定ではなく、速く溜まる時もあれば、遅々として進まない場合もある。そしてゲージが満タンになると、本人の意思とは関係なく、超必殺技が発動するのだ。トリガーとなる行為として、飲食や洗顔といった口周辺に刺激を与えるものがあるが、トリガーなしで発動することもある。無論、対象は自身であり、大ダメージを受ける。そうするとゲージは空となるが、また蓄積されていき、ゲーム『ファイナルファンタジーVII』のように、リミットブレイクするのだ。
程度と頻度も極端で、三叉神経痛の機嫌が良い時は1日に1発でダメージも小さく、「これくらいで許したるわ」と去ってくれるのだが、ご機嫌斜めの時は、過去最高記録でいくと、数秒のインターバルでもって数十秒の激痛が生じる。当然、そんな状況下では眠ること能わず、虚空を見つめて朝を待つ日もあった。
三叉神経痛の困るところは、特定の難しさに依る。普段、生活をしていて、小鼻の奥に痛みが生じたら、ひとはどうするだろうか。竹谷の例を取れば、まず耳鼻科へ行った。鼻の奥が痛いです、と症状を告げたが、医師は首を傾げるだけだった。次に、歯科へ行った。歯茎や神経が良くないのかもしれないと思ったからだ。しかし、異常はなかった。
「とりあえず経過を診たいのでまた来てください」
生ビールを頼むかのように経過観察と言われても困る。痛みの原因がわからない苛立ちも相まって、その後パフェをしこたま食べて歯を汚した。
インターネットの時代で本当によかったと、心から思う。症状を試行錯誤しながら入力しては検索をかけていたところ、三叉神経痛という病名に至ったのである。その説明を読み、思い当たる項目の多さに大きく首を縦に振った。どうやら1万人にひとりの確率で発症するようで、その少なさでは、検索してもあまり出てこないわけだ。左利きもAB型も割合は10%、そこに三叉神経痛の比率を入れると、竹谷はおおよそ0.0001%しかいない人間である。出しどころのないマウンティングができるようになった。
あまりの痛さに、銃の所持が許されている国では、自ら顔を撃ってしまうらしい。
そうして付いた別名が、自殺病。
竹谷が思うに、痛みは当然として、病名や原因が判然としない不安から、自殺へと進んでしまうのだろう。竹谷はインターネットのお陰で病名に勘所がつき、とりあえずの不安からは逃れることができた。なんの病気がわからなければ、向き合うことすらできない。ましてや、発症例が極めて少ないわけであるから、その暗中模索の孤独感たるや想像するに苦しいものがある。三叉神経痛に悩んでいるひとがいたら、どうか竹谷を紹介してほしい。竹谷には、三叉神経痛と付き合ってきた十年間の経験がある。三叉神経痛を専門に研究している医療業界の方も、ご連絡を心からお待ちしている。
三叉神経痛と診断されてのち、竹谷は丸4年勤めた会社を退職する。とにかく顔が痛かった。どれがトリガーとなるかもわからない。ひとと話すことさえ怖かった。遅かれ早かれやってくる痛みに、耐えることしかできない。
社会的に死ぬとか、どうでもよかった。
もう、竹谷は働けない。
痛みがやってこないことを祈りながら、ゆっくりと静かに、歯を磨く。口を微動だにさせたくない。いつ来るかわからない超必殺技に怯えながら、痛みが誘発されないよう、ひたすらに動かない。動けない。動きたくない。仰向けでも俯せでも、痛みが安眠を妨げに来るが、座椅子に浅く腰をかけると誘発されなかった。座ったままで、ようやくうつらうつらと、眠ることができた。
治るかわからない、いや、おそらく今生で付き合い続けなければならない病気。いつ竹谷が鬼籍に入るかは知らないが、向こう何十年もこれが続くのか、と思った。
繰り返すが、三叉神経痛が発症する人数は極めて少ない。ゆえに、発熱や鼻炎といったものと異なり、共感が得られない。顔の奥が痛い、と言われても、家族も知人も、想像しかできない。優しくも過剰な心配は、手前勝手ではあるが、しんどいと思う時がある。
なぜ自分が。という疑念も脳裏を何度かよぎった。悪いことも少なからずしてきたかもしれないが、竹谷よりもっと悪意に満ちた人間はいる。どうしてそういうひとたちが健康体で大手を振って歩いているのに、竹谷は座椅子にうなだれ、恐怖に苛まされているのか。
わかっている。世界は自分のために存在しない。死に至る病ではないだけ、ありがたいと思うべきだ。世の中には、竹谷など比較できないような大病との対峙を余儀なくされた人々がいる。
そう思っても、理不尽に対して怒りが湧く。そして怒れば怒るほど、やり場のなくなった感情の隙間に、悲嘆が入りこんでくる。
もう働く気など、一寸たりとてない。頑張ろうという活力もない。ただ、死んでいないだけだった。
生きられない。
自殺を考えなかったと言えば、嘘となる。恐怖と痛みから手っ取り早く逃れるには、そう感じる自身を消してしまえばいい。
眠れず、睡眠不足で、思考も覚束ない。食事も、恐怖が勝ち、進まない。口を動かさずに飲めるゼリーやヨーグルトを摂取する。飲み下す際のごくりという動作でさえ、トリガーとなる時もあった。
欲望のすべてに、どんよりとした恐怖がまとわりつく。怯えて、欲を満たそうと思えない。心臓が勝手に動くから、やむを得ず命が保持できているだけだった。
自室の座椅子に座り、動かず、竹谷はただ前方を見つめる。電源の消えたテレビ画面に、無表情かつ無気力で、伸びるがままの髭を蓄えた、ぶくぶくと丸い自分の顔が反射されていた。
そのテレビ台に、漫画が数冊置いてあった。元あった場所へ戻さず、部屋のあちらこちらに漫画は散在している。
ひとつ、手に取った。ぱらぱらとめくる。大好きなマンガ『SKET DANCE』の14巻だった。
それから、竹谷は笑った。口角を上げたことがトリガーとなって、待っていたと言わんばかりに激痛が顔を走る。右手を頬に当てて、痛みを紛らわすようにさする。左手でマンガをめくる。痛さに、涙が流れた。
笑い声を立てて、痛くて泣きながら、竹谷は笑う。痛みが引き、やがて涙も止まった。
まだ、笑えるではないか。
なにかが、自分の中で氷解していく感覚があった。
テレビの電源を点ける。押し入れから、任天堂のゲーム機『Wii』を取り出した。そこに、買ったまま部屋の隅に積んでいた、ゲーム『ゼノブレイド』のディスクを挿入する。オープニングが始まり、途端に竹谷は壮大なファンタジーの世界へ入りこんでいた。月曜日になると近くのコンビニエンスストアへ行き、『週刊少年ジャンプ』の最新号を買った。連載の始まったマンガ『ハイキュー!!』が最高に面白かった。深夜アニメが楽しかった。『這いよれ!ニャル子さん』と『つり球』と、『ヨルムンガンド』が観たかった。
どれもこれも、続きが気になって仕方がない。
痛みに眠れない夜は、ゲーム、漫画、アニメをどこまでも堪能できる贅沢な夜となった。三叉神経痛が間断なく激痛のシグナルを脳に送るが、不思議と怯懦な気持ちは軽減している。
断言できる。『エンターテインメントという薬』は、確実にそしてしたたかに存在するのだ。人知れず、ひとりで楽しめるエンターテインメントは、多くのひとりを救っている。
エンターテインメントが、たったひとつの処方箋だった。それにすがり、竹谷は生にしがみつく。激痛に呻き泣いても、笑い続けた。楽しむことをやめなかった。
エンターテインメントがあったから、竹谷は生きられた。
三叉神経痛は、徐々に引いていった。頬に痛みが走らない幸せを噛み締めながら、それが束の間の平穏だということもわかっていた。遅かれ早かれ、また高波はやってくる。眠れない夜も、死ぬまで何度も経験するだろう。
しかし、すぐそばには、エンターテインメントがある。どこかのだれかが練り上げてくれた、極上の楽しみがある。
痛みに立ち向かうのに、これ以上心強い味方はない。
エンターテインメントの世界に骨を埋めようと決心したのも、今顧みれば当然の因果に思える。衣食住ではなく、医療でもない。しかし、生きる上で必要だと信じている。少なくとも、激痛と恐怖に対して、それはそれは大きな効果があるのだ。
1年後、なんとか会社に勤め始めた竹谷は、気さくな酒豪ファイター杉山と、次いで優しき菜園家シューター寺井と出会う。
ミリアッシュを設立するまで、あと5年。
エピソード5:太陽と太陽と
MacBookのトレードマークである林檎を、かじるようだった。
2016年、前社で経営管理部の部長をやっていた竹谷は、ある打合せに参席していた。
「イラスト制作会社同士、敵対せず関係を深めていこうよ、竹谷くん」
当時の代表がそう思い立ち、先輩かつ競合のイラスト制作会社へ打診し、実現した場だった。
眼鏡の奥の瞳が、ぎらついている。熱された言葉を、止めどなく放ってくるひとがいた。
もちろん、その話は面白く、刺激と学びになることばかりであったのだが、竹谷はとにかくMacBookのモニター背面にある林檎にすべての気を取られていた。
『大東京トイボックス』という漫画がある。ゲーム業界を舞台に、ゲームへの情熱を余すところなく注ぎこむゲームクリエイターたちを描いた最高傑作だ。
その主人公の名は、天川太陽という。いつも赤色のジャージを身にまとい、不精髭が絶えない。そして太陽という名に恥じぬほど、ゲームへ対する熱気を全方位に発している。竹谷のSNSの似顔絵アイコンは、光栄なことにその作者うめ先生に描いてもらったものだが、服を『大東京トイボックス』の天川太陽の赤いジャージか『スティーブス』のスティーブ・ジョブズの黒いタートルネックかを選択する際、竹谷は迷わず前者を選んだ。それくらい愛してやまない漫画である。
その天川太陽が、MacBookの林檎を手に持ち、かじりつこうとしている。彼は、背面いっぱいに、黒のマジックで描かれていた。
「竹谷さん、なにかありますか?」
打合わせの終盤、代表が訊いてきた。なぜか、チャンスだと思った。
「そこに描かれているのって、天川太陽ですよね」
対面している男性に向け、竹谷は自然を装い質問する。イラストの事業や理念といった内容でなく、単純に『大東京トイボックス』の話を持ち出したことに、実のところ気後れしていた。
そうです。
そういった類の返答が来ると思っていた竹谷は、思わず線のような目を見開いた。
「魂は合ってる」
腰を上げて高らかに言いながら、その男性は、手を差し出してくる。「魂は合ってる」という言葉は、天川太陽の名台詞中の名台詞である。勢いに気圧されつつも、竹谷は慌てて握手を返した。
彼の手は、当然のごとくに熱かった。
株式会社サーチフィールド代表取締役社長、小林琢磨。
サーチフィールド社は、大先輩のイラスト制作会社で、そのクオリティの高さは噂で聞き及んでいた。会社のウェブサイトを折々訪ね、メンバー紹介のページで小林さんの似顔絵を見ては、どんなひとなのだろうかと想像していた。そんな彼と一番に握手ができたのは、代表ではなく竹谷だった。それが、なんだか誇らしかった。
有名な俳優や、憧れの野球選手と握手を交わせた、少年じみた喜びのようなもの。生まれてから今まで、竹谷はアイドルや音楽グループを含めてもだれかの熱心なファンになるということがなかったが、この日、小林さんのファンになった。
天川太陽が描かれたMacBookを所持しているだけあって、まさに太陽のようなエネルギーに満ちたひと。
星には、恒星、惑星、衛星とあるが、言わずもがな太陽は恒星であり、恒星は巨大な銀河を形成する。それは星でなく、人間でも同じことである。
小林さんという恒星との邂逅は、別の太陽のような巨星に繋がっていく。
そのきっかけは、必然かもしれないが、『大東京トイボックス』の天川太陽だった。
竹谷はゲームが大好きである。もちろん、音楽も映画も、アニメも漫画も大好きである。どれが欠けても、生きられない。
自分のことは、所謂「漫画好き」と思っていた。毎日のように書店へ赴き、なにか面白そうな漫画はないかと、90キロの体躯で練り歩いていた時期もあった。だれかの漫画の知識の少なさに、両手をあげながら小馬鹿にした覚えもある。まったくどうしようもない漫画ハラスメントだ。
その自分が、いかに小さい存在であったか。
株式会社ミリアッシュを設立した時、まず挨拶に行きたいひとがいた。
「漫画大好きっ子。ナンバーナインの小林です」
動画や記事の中で、そう自らを紹介するひと。
手を握り返してからというもの、竹谷は小林さんを調べることが輪をかけて多くなった。彼は、色々な事業を展開されている起業家であり、同時に経営者だった。
その事業のひとつに、マンガサロントリガーというものを見つける。漫画がたくさん置いてあるバーのような場所で、ノマドワーカーとして使用もできれば、イベントの開催もできるところだ。
面白そうな場所だと思った。そして、行ってみたいと素直に感じた。小林さんの居る時に行ければ、なおのこと良い。
そんなことを考えていた折、あるイベントが見つかる。
第一回未来物語会議。
漫画『左ききのエレン』の作者であるかっぴー先生、漫画『彼女のいる彼氏』を描かれている矢島光先生、そしてコピーライターの阿部広太郎先生の3人が、各々の作品についてトークする催しで、小林さんが司会を担当するものだった。日時は2017年2月11日。ミリアッシュの設立日から、わずか4日後だった。
神か仏かマザーハーロットか、もしくは超越的な存在が、竹谷に与えた好機だと思った。すかさず、副社長杉山とともに竹谷は参加を申し込む。
イベント後の懇親会で、竹谷は早速小林さんへ近寄った。
「独立しました」
なんとか、言葉を紡ぐ。急ぎパワーポイントでデザインした、いや、デザインとも呼べないような間に合わせの名刺を、そそくさと小林さんへ渡す。電話番号もなければ、ロゴもない。内容も紙質も薄っぺらい名刺だった。
「ミリアッシュ?」
そんな言葉が一体全体この世にあったか、という感想を表現するような、それは見事な疑問符だった。小林さんを責めるつもりは一寸もない。名乗る自分も、ミリアッシュなどというものが実在しているのか、まだまだ半信半疑であった。
「おめでとうございます」
小林さんは、朗らかに寿ぎの言葉をくれた。さらに、会社の経営について、情熱をもって色々な話をしてくれた。以前お会いした時よりも、近い距離感で、時間を過ごすことができた。
しかし。
ある不安が、フカフカした腹の底にじっと沈殿している感覚があった。
きっと、小林さんに覚えられてはいない。
今日は仲良く話せても、明日はまた見知らぬ他人となってしまう。悲しいが、確かな現実であった。竹谷には人目を引くような外見もなければ、話題の沸騰しそうな事業実績もない。そんな人間を覚えろと言い寄るほうが、荒唐無稽である。
なんとかしなければ。冴えないながらも焦りだけは一人前な竹谷は、ひとつだけ解決策をひねり出す。
とにかく、たくさん会うことだ。もはや解決策と呼ぶさえ恥ずかしい。
幸いにも、マンガサロントリガーでは交流会や勉強会といったイベントが多く、訪ねられる機会は多かった。考えるより、足繁く。心に残るような印象の程度がないなら、頻度で勝負するしかないのだ。
「竹谷さんは、いつもいますね」
まみえる小林さんは、いつも笑顔で、竹谷と談笑してくれた。その頃小林さんは、10年に渡って続けた株式会社サーチフィールドの代表取締役を退き、漫画事業に特化した株式会社ナンバーナインに集中すると発表したさなかだった。10年続けた会社への思い入れは、竹谷にはまったく窺い知れない。自負も地位は当然として、それらをはるかに上回る愛情もあったはずだ。勇退の心に、竹谷は一層惹かれた。会社は異なり、登らんとする山は違えども、登ってやるという意志を同じくするひと。身勝手ながら、そんなひとと出会えた幸運を、ありがたいと思わずにはいられなかった。
少し時が経ち、2018年10月26日。会社を設立してから、1年半が経過していた。
竹谷は、その日もマンガサロントリガーにいた。普段より、幾倍も心を張り詰めて。
『マンガ新聞』というメディアがあった。新しい漫画や、知る人ぞ知る漫画について、熱量の入ったレビューが並ぶウェブ媒体である。レビュアーの方々は、色々な業界から集まった、漫画をこよなく愛する猛者たちである。そしてレビュアーたちは月に一度集まり、PVの多かった記事や最近の面白い漫画について話に華を咲かす。
小林さんからの招待で、竹谷はその定例会に呼ばれていた。
知らないひとやいない実業家の堀江貴文氏や、『ドラゴン桜』や『宇宙兄弟』といった名作の編集を担当されていた佐渡島庸平氏が、その会合には出席している。小兎のような竹谷の緊張感を、ご想像いただけるだろうか。
さらに、マンガサロントリガーでの定例会では、なんでもいいから一品持ち寄りというルールがあった。なんでもいい、と言われると、私服可の面接と同様に、妙に勘繰ってしまう。ゲーム『ファイナルファンタジーV』の武器チキンナイフが大好きなチキンの竹谷においてその勘繰りは最果ての地へ到達し、どうせ皆超絶にお洒落で高級なものを持参するに違いないと考え、副社長杉山の奥方から雑誌『FRaU』を借りて読みこんだ。ファッション・カルチャー・ライフスタイルについて書かれた雑誌である。いなり寿司、豆大福、カヌレ。ここまで調べれば、もう選択を間違えるわけがない。しかしカヌレとはなんだろう。
ゴゴゴゴゴ。
重い扉が開いたり、古い機械が鈍く動いたりしているわけではない。漫画『ジョジョの奇妙な冒険』には、緊張感を演出するために「ゴ」や「ド」といった音が、原稿を縦横無尽に走り抜いている。嘘に思うかもしれないが、実際その音が聞こえていた。
ただ、これは竹谷が緊張しているからではない。堀江貴文氏や佐渡島庸平氏と一緒に、卓に座している男性から発せられていた覇気である。
ちなみにその男性は、九州発のレストランチェーン「長崎ちゃんぽんリンガーハット」の餃子を持参していた。
竹谷は、自分の手を見やる。指からぶら下がったビニール袋には、東京都府中の名物である餃子が入っていた。結局、等身大ありのまま、つまりレットイットゴー作戦を採用していた。高価で洒落っ気ある料理やスイーツの中、あえて餃子があるのも逆に悪くないだろう。そう狙ってのことだった。
その末に、餃子が被るとは。なんてことだ。
実は、二度目だった。
その半年ほど前、田町で開催された交流会で、竹谷は初めてその男性と名刺交換をした。
株式会社サイバーコネクトツー代表取締役社長、松山洋。
名前は知っていた。小林さんのSNS等で、顔も拝見していた。しかし、会う時が来るとは思ってもいなかった。
テレビ番組『奇跡体験!アンビリバボー』で特集されるような、ゲーム業界の雄を前に、竹谷は縮みあがっていた。
「た、竹谷と申します。イラスト制作会社をしています」
「そうですか。よろしく」
おそらく、時間にして一分にも満たなかったはずだ。名乗り、会社の説明を簡潔にする。名刺こそしっかりとデザインされたものになっていたが、それで、話は以上だった。
松山さんはとても丁寧に、竹谷の言葉を聞いてくれた。ただ勝手に、竹谷が威圧感を覚えていただけである。
名刺交換が終わると、竹谷には後悔しかなかった。きっと松山さんは、竹谷のことをもう覚えていないだろう。たくさんのひとが来ていた交流会である。印象が薄ければ、記憶からも早々と消えてなくなる。ましてや松山さんは、竹谷とは比較しようもないほど、多くのひとに会い続けている。覚えてもらえるわけがない。繰り返すが、竹谷には秀麗な眉目も、特出したセンスや才能もない。熱意を訴えることも、できなかった。
そして、たくさん会って自然に覚えてもらおうにも、松山さんとの会い方など、竹谷には皆目わからなかった。
そう思っていた中の、二度目のコンタクトであった。『マンガ新聞』の定例会に、松山さんがいたのだ。お酒をしこたま飲み、漫画への情熱を存分に迸らせて。
「実は以前、ご挨拶させていただいたことが」
「ああ、そうだっけ」
小林さんに紹介してもらい、竹谷は再度松山さんと言葉を交わせた。当然に、松山さんはなにも悪くない。半年前の一分弱を覚えているほうが、土台不可能な話である。
マンガ新聞の定例会は、二次会がほぼ必ずある。稀代のサウナ好きである小林さんに誘われ、竹谷は初めて水風呂の快感に溺れた。水だけに。冷たさに、年甲斐のない悲鳴も出た。そして小林さんは松山さんと大の仲良しなので、松山さんもサウナに同道されている。
鎧を脱ぐとは、しばし耳にする言葉だが、ことサウナにあたっては鎧どころか褌さえ脱ぎ捨て、裸体で対面する。そしてサウナと水風呂は、熱の急激な上下による苦楽のようなものである。インスタントラーメンのようではあるが、瞬間的に、苦楽を共にした仲になれるわけだ。なお、松山さんのサウナでの珍事は枚挙に暇がないが、サイバーコネクトツーの社員の皆様に叱られる未来が若干見えるため、ここでは割愛させていただく。
いや、せっかくなのでひとつだけ紹介させていただきたい。水風呂に入る際、その冷たさに耐えるため、松山さんは漫画『からくりサーカス』の登場人物である加藤鳴海の技「硬気功」を再現する。気合とともに、両手の人差し指と中指を立て、正面にまっすぐ突き出すのだ。鉄の檻とかを曲げたりはできても、水風呂の冷気に効果があるとは、原作では描かれていない。それよりも、突き出した手の先に見知らぬひとがいると、どこはかとない気まずさの流れる妙技である。
「松山さん、硬気功、せめてこっち向いてやってください」
都度、竹谷がこう申しあげるまでが一連である。
月一で開かれる『マンガ新聞』の定例会で、竹谷は小林さん、松山さんとご一緒させていただく機会が増えた。その分、竹谷は松山さんのことを知っていく。ちなみに、まだこの時期は「ミリアッシュの竹谷さん」と、松山さんからは呼ばれていた。
知れば知るほど好きになる。松山さんは、そんなひとだ。
常に戦線に立ち、業界を、ひいては社会全体のことを考え、アクションを起こしている。企業の代表としてビジネスを、つまり利益を出すことは当たり前に考えていても、面白さに対しての真摯さが尋常ではなく、異常の数倍である。ご自身の写真ひとつでさえ、エンターテインメント性の有無を考えている気さえする。小林さんと「琢磨、まっちゃん」と呼び合う関係になるのも、心から頷けた。ふたりとも、漫画『太陽の戦士ポカポカ』なのだ。
そして、竹谷は己の不明を恥じる。ゲームを愛している、などと嘯きながら、『.hack』や『NARUTO-ナルト- ナルティメットヒーロー』、『ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル』、『鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚』といった名だたるゲームを作った会社の社長のことさえ、竹谷はなにひとつ知らなかったのだ。厚顔無恥、ここに極まる。
もっと、松山さんと話したい。もくもくと、そんな欲が天然パーマの頭をもたげた。
世界とは不思議なもので、思うことは、ふとした折に現実となることが多い。物事の良い面を見るひとには良いことが起こるし、悪い面を探してしまうひとが良いと言えない状況へ陥りがちなのも、同様の理由からであろう。
松山さんと会う機会を探す竹谷は、それより前の自身と比較し、アンテナが切り替わっていた。「アウトレンジ・レクリエーション」という言葉を、SNSで見かけることが増えた。いや厳密には、会いたいと思っていたからこそ、その言葉を認識できる脳になっていたのだ。
「アウトレンジ・レクリエーション」は、サイバーコネクトツーの東京支社で月に一度開催されている交流会である。猫の手も借りたいほど多忙な松山さんがしっかりと臨席し、サイバーコネクトツーは福岡だけでなく東京にも拠点があるということを、積極的に外へ向け発信している。だれでも気軽に参加でき、なんと会社見学もさせてもらえる。
松山さんのようなひとに、どうやって会えばいいのか。そんな竹谷の悩みは悩みではなく、ただ情報を入手できていないだけであった。月に一度、手続きひとつで会える場が用意されていたのだ。竹谷は再び自らの無知に赤面しながら、申し込みのボタンをクリックする。
「アウトレンジ・レクリエーション」に集まったメンバーは、サイバーコネクトツーならびに松山さんのファンや、ゲーム業界の方そして漫画家さんと、さまざまな人たちだった。そういった方々が、松山さんと同じ時間を過ごしたくて集まる。改めて松山さんの力に竹谷は驚いた。もちろん、集まった方々もそれぞれコミュニティがあり、「アウトレンジ・レクリエーション」が契機となり、新たなご縁が生まれ、色々なイベントや遊びにお呼びいただく光栄に浴せた。
ボードゲーム会へお誘いいただくこともあった。ひとと話すのが得意でない竹谷は、正直なところボードゲームに苦手意識を持っていたのだが、せっかくのお誘いであるからと、苦手意識を払拭しようと思い馳せ参じた。
場所は「アウトレンジ・レクリエーション」と同じく、サイバーコネクトツー東京支社で開かれるとのことだった。当然、松山さんもいらっしゃる。何度かお誘いいただくうちに大井町にも通い慣れていき、阪急百貨店の大井食品館へ行けば大抵のおいしいご飯やお菓子を揃えられることがわかった。駅近くにある「おふろの王様」は、色々な種類の温泉はもちろんサウナも完備され、帰り際に寄ると幸せな気分になれる。互いが好きな食べ物を買って持ちこむのが、サイバーコネクトツー東京支社にお邪魔する時の通例であった。あまり思い出せないが、皆で食べるためのお菓子を少々と、小粋なお弁当を買っていくことが自分なりのルーティンだったように覚えている。決して、もう餃子は持っていかない。
メンバーは「アウトレンジ・レクリエーション」とは異なれど、ゲームや漫画といった、エンターテインメント業界の人たちばかりで、会へ参じる度、多くの繋がりを作らせていただいた。
そして、その場には、やはり松山さんがいらっしゃるのだ。
「竹谷さん、最近いつも松山さんと遊んでいますね」
お会いするひとから、このようなお褒めの言葉をいただくことが多くなった。それだけ、松山さんと一緒にいること自体がすごいという証左である。すべて本当にありがたいご縁であると、うるさいかもしれないが、何度でも言いたい。
「いつもまっちゃんとばかり遊んで、俺とは全然遊んでくれない」
ナンバーナイン小林さんからは、こう冗談を言われる始末だ。ちなみに、ナンバーナイン社とミリアッシュの代表は、会ったらラーメンを食べなければならない、という覚書を締結している。契約書の草案を弊社の顧問弁護士に確認してもらったのだが、今まで相談した中でもっとも多いレベルに赤ペンの入った覚書が返ってきた。ラーメンを食べる、という真面目に遊んだ契約書に、遺憾なく全実力を投入してくれた弁護士には、ここで改めて御礼を申しあげたい。さらに言うなら、竹谷は常時減量中であるため、小林さんにお会いしてもラーメンが食べられないのが心苦しい限りだ。無事に痩せきった暁には、ラーメンマンになるほどたらふくラーメンを食し、見事リバウンドを成し遂げる所存だ。
これを書いている時点では、毎週のように松山さんとご一緒する予定が入っている。このような事態、昨年の竹谷には予想だにできていなかったことだ。もはやしつこいくらいだが、誘ってくださる皆さんにも、SNSに「ミリアッシュ竹谷」と社名をしっかり記載の上投稿してくれる松山さんにも、その松山さんに覚えてもらう契機を作ってくれた小林さんにも、感謝以外を想う余地がない。
天川太陽から小林さん、小林さんから松山さんへと、出会いの輪はカチリとはまり、繋がっていった。太陽は、別の太陽と親しい。日々急速に流れる時間とともに変動していく関係の中、繋がりが別の繋がりを連綿と生んでいき、竹谷の人生を豊かにしてくれている。報恩したいと思うことばかりが増えてきた。いただいた恩を返しきれない。そう思いながら毎日を生きることは、それ自体が贅沢なことだと、改めて思う次第である。
竹谷の出会ったひとたちは、すべて太陽のごとく大きな星々だった。感化されて、飲み会や遊びの企画を少し始めた竹谷にも、いくらか太陽の化身の血が混ざり、アニメ『天体戦士サンレッド』の楽曲『溝ノ口太陽族』のようになってきているのかもしれない。それは竹谷の中では強い変化であり、そして無変化の寂しさと比較し、往々にして変化は良い兆候である。
きっと、前社に残ったままの竹谷では、こんな僥倖に預かることはできなかっただろう。独立不羈になると決め、会社をせっせと作り、心身ともに鍛え磨いて生きようと思ったからこそ、巡り会えたひとたちだと信じている。
そしてひととの出会いこそ、自分だけでは起こり得ない変化をもたらしてくれるものである。ゆえに今築きつつある関係を一層大切にしていこうと、竹谷は一再でなく、口の酸っぱくなるほど自身に言い聞かせている。
エピソード6:点のかたち
超大型巨人の視点は、高所恐怖症にとってはかなり怖い。
高速バスに乗り、博多駅から1時間と半分、大分県の日田市に大山ダムはある。比類なき歴史的傑作漫画『進撃の巨人』の作者諌山創氏を輩出したこの地は、2020年秋「進撃の日田」として場所やお土産等を『進撃の巨人』と連動させた企画を始めている。大山ダムはまさにその中核で、主人公級の登場人物であるエレン・イェーガー、ミカサ・アッカーマン、そしてアルミン・アルレルトの銅像を造り、ダムの高い天端を劇中に出てくる壁「ウォール・マリア」に見立て、さながら超大型巨人を見上げるようにかれら3人は屹立している。
きっかけは、クラウドファンディングのプロジェクトだった。いくつかクラウドファンディングをビジネスとしている企業はあるが、この件は2021年Forbes JAPANの「日本の起業家ランキング 2021」で3位に入ったことで記憶に新しい、家入一真氏が代表を務めるCAMPFIRE社発のものであった。
「竹谷さん、大分へ行きませんか?」
そもそも、竹谷がこうして大分県日田市は大山ダムの天端から山々と一緒に人類を見下ろし、その高さに震え慄きながら超大型巨人と諌山創先生に想いを馳せているのは、突如ポコンと通知の来たLINEからだった。
遠藤寛之。背と笑い声が高く、よく食べよく眠り、まるで依り代のような髭と髪を併せ持つ好青年。彼からの突然で粋な誘いがなければ、竹谷はこの美しくて怖い景色を拝めていない。飛行機に乗って宿泊込みの旅へ一緒に行く、という話を、ためらわずに誘っていただきありがたい限りだ。
しかし、彼との距離は、最初から近かったわけではない。幼馴染でもなければ、中学生や高校生からの付き合いでも、新卒で入った先輩後輩といった間柄でもない。
今回は、まず遠藤さんとの出会いを書こう。そう思い、記憶の糸を手繰りよせていって気づく。この話は、遠藤さんから始めるべきではなかった。
したがって、ここまで書いておいて大変恐れ入るが、遠藤さんにはいったん退座していただくほかない。
杉山剛は、可愛らしい瞳を輝かせる。
「ビールを取ってくれた」
株式会社ミリアッシュの副社長と社長、という関係となる数年前、当時イラスト制作会社の同僚兼先輩であった杉山は、そう感想を述べた。
その前日、彼は新宿で開催された交流会へ行っていた。昔も今も、クライアントへの訪問や交流会への参加が生じた際は、先方の印象や新たに知り得た情報など、特筆すべき事柄をメンバー間で共有するようにしていた。
「面白いひとがいた。同い年だった」
杉山は、このふたつの感想に、先ほどの句を続けた。
交流会というのは、エンタメ業界では頻繁に開かれるイベントで、飲食をしながら名刺交換をし、互いのビジネスを知ったり、これまでにない繋がりを求めたりする場である。数名から、大きくは数百名に及ぶ規模もある。当時は主に責任者の杉山と竹谷が、遊撃軍よろしくあちらこちらに出ていた。
ここでひとつ申しておきたいのは、杉山も竹谷も交流会がそこまで得意ではない、ということである。
「ご挨拶させてください」
そう見知らぬひとにお声がけするのは、こと竹谷のような元ニートの仄暗い人間にとっては、それこそ超大型巨人のようなハードルの高さがあった。また、大人の切り札であるお酒の力は、下戸では頼むに命が関わる。
当然だが、交流会には色々なひとが来る。正直に申せば、あまり波長の合わない方もいる。しかしビジネスであるから、と自らを鼓舞し、名刺を三刀流する勢いでご縁を作らんと臨んでいた。今にして思えば、交流会への参加も始めたばかりで、見知った戦友のような存在がいなかったのも起因していたのだろう。
そしてそう考えれば、彼は当時の杉山と竹谷にとって、果ては現ミリアッシュにとっての、最初の戦友と言える。
笹谷崇。株式会社セガに勤める、お酒をよく飲むがあまり食べず、髭と髪のきちんと手入れされた、クレーンゲームが上手すぎて「UFO王子」という異名を持つ、もとい仕事を担う男性。
杉山から即座に紹介され、なんだか周波数が合致し、今では月に何度も会っては色々なことを一緒に楽しむ間柄となった。
笹谷と竹谷。パンダの界隈からすれば全幅の賞賛を浴びせたくなるような名前のふたりは、このようにして邂逅を果たした。
きっかけは、杉山が取ろうとしていたビール缶を、彼が優しく取ってくれたことだった。これは竹谷のあずかり知らないお酒の力、その余波と言って差し支えないだろう。
その後も、交流会へは継続して顔を出すようにした。Facebookで繋がると、共通の知人がたくさんいる、といった場合も増えてきていた。今すぐ仕事が欲しいわけでは豪もない。現時点でなにもなくとも、いつかきっとなにかがある。いつだって可能性はなくなりはしない。会社にとって、そして竹谷にとって良い出会いがあることを祈りつつ、どの場にも参じるようにしていた。
そこには、やはり大体笹谷さんはいた。ふたり同じく1985年生まれ、ということも手伝って、敬語や敬称は急速に剥がれ落ち、もはや笹谷さんではなく「ささやん」と呼ぶに至っていた。
「言ってもまだ、数回しか会ってないよね」
仲が良いですね、といただくコメントに対し、互いに見合わせて笑う。竹谷は自分の知人をささやんに、ささやんは彼の知人を竹谷に紹介し合う。継続は力なり、とは古代の魔法の言葉であるが、その古さゆえの力は強大で、交流会に出れば出るほど、知り合いは雨後の筍のごとく増えていく。
繰り返しとなるが、竹谷は交流会が苦手である。大勢が集まっていると、隅っこで小さく落ち着いているのが心地よい。よく吐く妄言となるが、祖先は孤高な狼なのだ。しかし、苦手な食べ物をちょっと美味しいと舌が判断する時があるように、交流会を楽しいと感じる時がちらほらと見つかり始めていた。
その理由の中で大きく光るひとつの要素は、ささやんのように、異なる会社に属する人間であっても、同じ時間を面白く共有できる仲間のような存在に出会えることだ。漫画『HUNTER×HUNTER』のジン・フリークスから台詞を引用するなら、「オレに生きた情報をくれる」という状況である。未知の道中を楽しむために、これほどありがたくて心強いものはない。
時折生まれる大きなご縁に喜びつつ、竹谷は交流会や飲み会へ出続ける。前社を退職し、株式会社ミリアッシュを立ち上げてからはなおのこと、新しい繋がりに対して貪欲になっていたように思える。
そして往々にして、思うことは、思うからこそ現実になる。
長くて細くて、そしてお洒落だ。
耳から入ってくる情報は、実に騒がしい量だった。今日も今日とて、都内で行われている交流会に竹谷は来ていた。100人ほどが集まっており、参加者には事前に参加者情報の列挙されたリストが配られていた。
参加者リストの一行を、食い入るように見つめては、視線を少し遠くへ外す。その先には、これもまた参加者に渡されるネームプレートが、とある人間の胸元に提げられていた。
眼鏡の力にこれでもかと頼り、やや離れたところにあるネームプレートの会社名と名前を読み取る。あまりじろじろ見るのもよくないので、あくまで素っ気なく、白々しくなく。教室の後ろの席から、黒板近くに座る意中のあの子を、不自然にならず視界へ収めるように。
株式会社サーチフィールド。遠藤寛之。
間違いない。参加者リストを見てからというもの、ずっと探していたひとだった。
サーチフィールド社は大先輩のイラスト制作会社で、前社に在籍していた時も、ミリアッシュを設立してからも、その筋骨隆々な背中を常に見上げていた。代表取締役である中山直人氏や副社長である長谷川洵氏、また取締役である笹淵久子氏とは食事をご一緒したことはあっても、交流会といった不特定多数の集まる場でサーチフィールド社の方と知り合うことはこれまでになかった。同業の方とは、たくさん仲良くできるなら仲良くしておくことに越したことはない。そんなことを考えていた竹谷は、光沢のあるネームプレートからきらりと見えるサーチフィールド社の名前を見て、もう繋がりたい衝動が堪えきれる限界へと近づいていた。
しかし。
もう一度となるが、細くて長身で、なんだかお洒落なのだ。カタカナを用いるなら、イケメンというものだ。
感情とは裏腹に、頭は行動にブレーキをかけてくる。なんだかお洒落なひとは、こと竹谷においては、話しかけづらいのである。原宿や表参道を歩く際、妙に緊張するのと似ている。
とはいえ、交流会もそろそろ終わりの時間が近づいていた。この場を逃せば、すれ違ったままとなってしまうかもしれない。それだけは避けたかった。どんなに勝手にATフィールドのようなバリアを感じ取っていても、破らねばならない障壁はある。
「あの、ご挨拶よろしいでしょうか」
「はい、ぜひぜひ」
話してみると、なんとも話しやすく、エネルギー溢れる方だった。百万回言われただろうフレーズだが、ひとを外見で判断してはいけないのだ。
こうして、遠藤さんとのファーストコンタクトは成し遂げられた。そのあとのことは、あまり語れるようなものではない。上手く行っている関係ほど、他人の興味を引かない事象はないだろう。
しかし、それを重々承知で少しだけ述べるなら、なんと実家が徒歩10分程度の距離で、埼玉県さいたま市にある中浦和という最寄り駅からの帰り道も、最後の曲がり角まで一緒ということが判明した。帰路に点在する、ファミリーマートの数で盛り上がれる。同じ業界にいながらも出会わず、30年もの時間同じ空気を吸い同質の水を飲んでいたこととなり、さらには同じプラザホテル浦和に併設されたボーリング場で打ち上げをし、その上階にある同じバーミヤン中浦和駅前店のドリンクバーを頼んでいたことになる。そういうご縁もあるのだなと、改めて思い知った。
そして彼は、同業の企業に勤めているが、同業ではなかった。
遠藤寛之を通じ、竹谷はクラウドファンディングに出会う。
4という数を日本は忌み嫌う傾向が強いが、別の一面として、四角形からもわかる通り強固なバランスが4には含まれているようで、起承転結の四コマ漫画や東西南北の方角等、一度聞いたら忘れられない響きを持つ言葉も作られている。漢字を4つ並べて生まれる言葉は四字熟語とされ、アニメ化もされた小説『有頂天家族』の金閣銀閣兄弟のように、捲土重来や融通無碍といった四字熟語はたくさんのひとに愛用されている。漫画『るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-』に出てくる強敵の志々雄実は、弱肉強食という四字熟語を信念としてよく使い、当時小学生だった竹谷は「所詮この世は焼肉定食」と言い換えて遊んでいた。なお、樋口一葉は四字熟語ではない。
古来から続く四字熟語であるが、新しく作られるケースもいくらかあるように見受けられる。個人的に大の苦手な言葉である「自己責任」はおそらくその一例で、2000年代に入ってからちらほら使われ始めた四文字であるように思う。責任は自分で負うものなのだから、わざわざ自己と頭につける理由がなく、またこの言葉を使う状況のほとんどが「私には関係ない」と他人を突き放す時なのも、なんだか好きになれない。
話が逸れた。四字熟語ライクな言葉なら、これはもっと最近になってから用いられてきた言葉だろう。
地方創生。
東京圏でなく、地方を活性化することで日本社会を広く維持しようという思想を指す。竹谷は専門家でないため誤っていたら謝るしかないが、町おこしや村おこしもその一環と言えるはずだ。
そして、その地方や地域に特化してクラウドファンディングを展開していたサービスにFAAVOというものがあり、それは当時サーチフィールド社の事業のひとつで、つまりは遠藤さんの担当していた業務であった。知り合った頃にはすでに、彼はクラウドファンディングに精通しており、素人の竹谷にあれこれと教えてくれた。クラウドファンディングとは、単なるお金集めではないこと。よく進むプロジェクトと、そうでないプロジェクトの要素。ほかにどのようなサービスを他社が展開しているか。
その他社のひとつに、株式会社CAMPFIREがあった。
遠藤さんとの出会いから半年後、FAAVOはCAMPFIRE社に事業譲渡され、随伴してかれはサーチフィールド社からCAMPFIRE社のスタッフへと天地を新しくする。
遠藤さんがCAMPFIRE社へ移ってからも、一緒に遊んだり、食事を共にしたりしていた。面白いプロジェクトを彼からキュレートしてもらい、竹谷個人または法人ミリアッシュとして、支援させていただくことも多々あった。現在ミリアッシュのウェブサイトには今日に至るまで支援してきたプロジェクトの件数と総額を記載しており、これは他社には中々できないだろう内容でもあると自負しているのだが、まさに遠藤さんとの関係性あってのものである。
遠藤さんは見た目そのままのナイスガイで、ささやんと同じく交流会で知人を紹介してくれ、また、CAMPFIRE社の方々とのご挨拶の機会を設けてくれることもあった。誘われるがまま、人生で初めて宮崎へ飛び、CAMPFIRE社の宮崎支部の立ち上げの瞬間を、CAMPFIRE社の皆様と一緒にお祝いさせていただいた。代表の家入一真氏にご挨拶もできれば、宮崎の美味を堪能でき、さらにはへべすくんという、宮崎名産の柑橘系果物であるへべすの化身にも運よく遭遇できた。
そしてCAMPFIRE社のひとりに、現在はサービスが終了しているが、当時クラウドファンディングのミニ版と言えるフレンドファンディングサービス、その名もpolcaを展開していた責任者の方がいた。クラウドファンディングでは通常、支援額に見合ったリターン、つまり返礼品のようなものが必要だが、polcaではそこは重要視されず、少しのお金をただお渡しする。バーチャルYouTuberことVTuberの生配信でのスーパーチャットや、ピクシブ社の運営する総合マーケットサービスBOOTHのBOOST等、投げ銭を経験できるものはあちらこちらに存在していたが、竹谷が初めて投げ銭そのものの魅力を強く感じたのは、polcaであった。
誕生日だから祝ってほしい。財布をなくして落ち込んでいるから慰めてほしい。両親に旅行をプレゼントしたい。Nintendo Switchがほしい。
そういう雑多で人間らしい感情や欲望がpolcaには溢れ、なんとなく「しょうがないなあ」と知人のような気持ちで数百円を払う。ひとによっては「なぜそんな他人ごとにお金を払うのか」と訝しんでも当然であるが、竹谷にはどうしてか、この寄付めいた投げ銭が大変魅力的に映った。
そんな折だ。
「polcaのチームブログに寄稿してくれませんか?」
遠藤さんを通じて、このような話がpolca側より届いた。自分でよければ、と二つ返事で応じ、polcaの面白さの原因を自分なりに考え、ああでもないこうでもないと文章をこねあげた。
まだそんなにひねくれていなかったからか、送った文章は無事polcaのチームブログに載り、遠藤さんやpolcaの責任者の方からは感謝をいただいた。どれくらい読まれているかは竹谷の知る範囲ではないが、それよりも、自ら書いた文章がなにかの媒体で読まれることに、こそばゆい嬉しさを抱いていたように覚えている。
その媒体は、何だったか。
掲載されたウェブサイトを眺めながら、ひとつの言葉を覚える。
note。なんとなく文字としては見かけていながら、しっかりと隅々まで目を配ったのはこれが初めてであった。
これは、即刻盗むべきものかもしれない。
そう思い、チームブログを始めたい旨を、すぐさま会議の議題として出した。いつも通りの竹谷のわがままであるが、杉山寺井の両名はいつも通り快諾してくれ、方針は「好きなものを好きと言う」に決まった。次いで、竹谷はカタカタとブログ用の文を書き始める。好きなものを好きと、しっかり言うために。
そうしてこしらえていった最初の文章は、自分のこれまでの話だった。好きなものを好きと言う、そのテーマはどこへ飛んだのか。いきなり逸脱した内容へなったと頭では理解していても、憑りつかれたように、指をキーボードへ叩きつけていく。この世に絶対はないが、これがミリアッシュと竹谷にとって絶対必要だと思った。その思いに比例して、文字数もどんどん膨れ上がていった。
2019年8月29日、公開した株式会社ミリアッシュ設立に到るまでの話は、ありがたいことに反響も大きく、たくさんの方にお読みいただいた。今もなお大変お世話になっているサイバーコネクトツー代表取締役松山洋氏や、ナンバーナイン代表取締役小林琢磨氏からも高評価を頂戴し、ミリアッシュと竹谷をより深く知っていただく契機を作ることができた。
そして、noteを間借りした竹谷の冗長な自分語りは、思いがけない新たな出会いを生み出す。
「竹谷さんとお話してみたいです」
チームブログを始めました、というFacebookへの投稿に対し、そうコメントをいただいた。
アニソンカラオケバーZのオーナー、生明康之。竹谷のようなオタク垂涎憧憬のディープな街中野で、老舗のアニソンカラオケバーを続けてこられてきた大先輩だった。生明さんとは、先に述べたような交流会でご挨拶をしてのち、緩くSNSで繋がっていただけの関係だった。
竹谷の文を通じ、その関係に変化が生じたのだ。
もちろん即答し、中野でお食事をご一緒しながら生明さんのお話を聞いた。漫画『ジョジョの奇妙な冒険 Part7 スティール・ボール・ラン』の登場人物ジャイロ・ツェペリの言葉の通り、”納得”を優先するために会社勤めを辞めて独立された経緯等、お聞きしていて面白く、そして共感させていただくものばかりであった。
そして、意気投合と表現するだけでは足らないようなこの信念の共鳴は、望外の事態を呼び寄せる。
「ミリアッシュさんに作っていただいたイラストを、アニソンカラオケバーZに飾らせてください」
そんなことがあるのか。喜び驚き、再びの即答とともに、8周年をお祝いするイラストを寄贈させていただいた。本当にありがたいことに、現在でもそのイラストはアニソンカラオケバーZさんで一番目立つだろうお立ち台のすぐ傍に飾っていただいている。
ちなみに、初めてアニソンカラオケバーZさんへこっそりとお邪魔した際、生明さんは不在であったためご挨拶できずじまいであったが、竹谷はこれまでにないほどの緊張を経験することとなった。
考えてみれば当たり前のことなのだが、そこはアニソンのカラオケを楽しむバーなのである。渡されたマイクを握りしめ、なにか重圧が伝わってくるかのように、竹谷はじわりと四肢に汗を感じていた。立っている場は、段差のあるお店の角、先述のお立ち台である。いくらかの知り合いでないお客たちと、盛り上げ隊という煌びやかで明るい女性たちが、竹谷が歌うのを眼前で待っている。
歌うことは大好きだが、人前で歌うとなると話が変わる。緊張感のあまり、張り詰めた弓の震える弦の、その切っ先によく似た横顔となっていたに違いない。
そもそも生粋の下戸である竹谷は、ひとりでバーへ入るのに高い敷居を勝手に感じ、UFO王子のささやんに同道をお願いしてさえいた。そしてそのささやんは、スマートフォンを構え、撮影のスタンバイが完了している。
小刻みに揺れる手を必死に抑えながら、竹谷はBUMP OF CHICKENの『カルマ』を歌った。
必ず、僕らは出会うだろう。
その歌詞が示す通り、ささやんと遠藤さんとは必ず出会った。そしてさらに、アニソンカラオケバーZオーナー生明さんとも、「必ず」と言えるような出会いが生まれていた。
それにしても、ひとりで行く勇気のなかった竹谷に同道してくれたささやんの、なんと心強いことか。ここぞという時の精神的支柱として、いつも寄りかからせていただいていると改めて思う。
王子の徳の高い愛は、竹谷のような捻じくれた民にさえ行き届くのだ。
やや時間が過ぎ、2020年、めでたそうな数字の並び方とは反比例するかのように、世界は語るまでもなく未曾有の様相を呈していた。
幸運にもミリアッシュはあまり影響を受けず、今まで以上に報恩を意識して働いた一年間だったが、これはどちらかと言えば少数派で、思うように働けない人々の方が圧倒的に多かったはずだ。
もちろん、飲食しながらみんなでカラオケを楽しむ、アニソンカラオケバーZさんも例外ではない。現在でこそ席数減少と徹底除菌でリスクに取り組みながら営業されているが、それでも春頃は営業を停止せざるを得ず、その時の生明さんの心中は、竹谷ではとても計り知れない。
しかし、やはりというべきか、「ジョジョ好き」は苦難に挑む闘志があるのだ。
「コロナショックを受け、現在クラウドファンディングを検討してるのですが、CAMPFIREの担当者をご存知の方いましたらご紹介いただけると有り難いです」
2020年4月7日、生明さんはFacebookでこう発信された。竹谷が漫画『鬼滅の刃』の技霹靂一閃のごとき速さでコメントしたのは、想像に易いことではないだろうか。
「熱意あるひとを紹介できます」
もちろん、遠藤さんを指している。直後、生明さんに遠藤さんを紹介し、なんと一週間後の2020年4月13日、アニソンカラオケバーZさんのクラウドファンディングは始まった。この速度から、『風の谷のナウシカ』の「火の七日間」のように、高く火柱を上げているおふたりのガソリン量をご推察いただけるだろう。そして、そのプロジェクトのトップバナー画像は、ありがたいことに弊社で制作させていただいたイラストだった。
それからおよそひと月後の2020年5月15日、信じられないことに、アニソンカラオケバーZさんのクラウドファンディングは、500,000円という目標金額を大いに吹き飛ばし、漫画『ドラゴンボール』の界王拳も結構びっくりのおよそ6倍、2,972,297円という額を集めて無事終了した。
およそと言ったのは、足らなかったからではない。
後日、生明さんと遠藤さんと3人で、クラウドファンディングの達成を祝う会を開いた。もちろん、場所はアニソンカラオケバーZさんの地である中野だ。
その時、生明さんが照れながらこう言ってきた。
「本当に誰だかわからないのですが、クラウドファンディング中、ポストに4万円が入っていたんですよ」
それを聞き、遠藤さんと竹谷は一寸固まってからどよめく。説明を重ねるが、クラウドファンディングには、支援した額に応じてリターンがつく。ふるさと納税の返礼品と同じような感じだ。
そのリターンさえ不要という、ただただ純粋な応援の寄付。支援額は、実は3,012,297円だった。
生明さんが8年もの期間、平均寿命80歳とすると人生の一割をかけ、丁寧に丹念に続けてきた仕事の結果。そのひとつが、如実に顕現していた。信頼は基本的に不可視だが、まれに何かを媒介して、ポツリと目の前に出てくるのだ。
寄付をされた方も、その結果を作り上げた生明さんも、筆舌に尽くし難くかっこいい。竹谷もかっこよくなれるよう、もっと頑張らねばと改めて意を固くした。
余談だが、来年2021年の早いうちに、竹谷はアニソンカラオケバーZさんで一日店長をやる予定だ。もしよければ、万障繰り合わせの上お越しくださればと思う。
ささやんと夜もすがら遊び、遠藤さんの熱い手を握って振り、noteを生明さんに読んでいただき、今こうしてそれぞれの出会いを書いている。それらは本来別個で、竹谷の小宇宙に並んでいたものであったものだが、まるで星座が出来上がるかのように連なり、大きなひとつとなった。漫画『鋼の錬金術師』の「一は全、全は一」というのは、漫画『ハイキュー!!』の「すべてのプレーは繋がっている」というのは、漫画『HUNTER×HUNTER』の『大切なものは、ほしいものより先に来た』というのは、きっとこういうことなのだろう。
今日大切にする誰かとの点は、明日出会うだれかとの点へと連なっている。月並みだが、点は線となり、線は面となり、面はかたちとなっていく。なにかのかたちを成すには、まずは点がなければならない。
2021年は、早いもので、ミリアッシュは5年目となる。大台に乗るその1年間、ひととの出会いをどう意識していくかは、すでに答えが出ている。
エピソードn:魔法の数字
私事ですが、という枕詞がある。
Twitter等のSNSで、たとえば有名なタレントやアイドルが結婚を発表する際に用いられるような言葉だ。プライベートゆえにインパクトの強い事柄を、なんとかソフトランディングさせるべく使用され、読む側は、その五文字を目視するあいだに少しばかりの心構えを許される。しかし中には、それを逆手に取り、その魔法の言葉を活用しながら、「ランチを食べました」などと衝撃性ゼロな発信をする者もいる。
さて、私事ですが、2021年初夏、叔父になりました。
姉が、子を生んだ。元気な男の子だ。姉にとっては初子で、竹谷にとっては初めての甥となる。
面と向かって会うことにハードルが積まれている情勢ではあるが、最大限の注意を払って、何度か会いに行った。初対面の時は、甥は赤子というより嬰児そのもので、お風呂に入れたりミルクをあげたり、抱き方の下手っぷりに泣かれたりしながら、まるで別の生物に接するかのような心地だった。それから早くも半年が経った今、すっかりクリームパンのように丸々とした甥は、いかにも赤ん坊といった出で立ちでこちらを見ては、なにが面白いのかアケケと笑うように成長していた。
この際だから正直に言うと、自らを棚に上げた話だが、姉のことを結婚できない類の人間だと思っていた。働くのが好きで、酒が大好きで、日々終電ギリギリで帰宅しては時折吐き、翌朝にはそのことをからりと覚えていない。酩酊状態で終電を逃した姉の身を案じ、親に内緒で車を駆って迎えに行ったこともある。実に、我ながらできた弟である。
「占い師によると、来年結婚するんだって」
そう得意顔で言ってきて、竹谷は肩をすくめたことが少なからずある。おかげで、占術は当たらない印象しかない。いや、最後の占いだけは当たったことになるので、まさに当たるも当たらぬもというものだ。
姉が結婚し、さらには子を生む。数年前の竹谷が聞いたら、「またまた、戯れ言を申されますな」と一笑に付したに違いない。しかし、現に姉は会社を休んで酒を断ち、帝王切開で出産をした。文字通り身を切った姉には、ただただすごいとしか言えない。
そうして、姉は母となった。物腰は柔らかくなり、甥に熱心に話しかけ、家を切り盛りしている。
それは姉に生じた変化であり、変化には理由がある。語弊があるかもしれないが、ひとりでは食事もできない、小さな小さな子を前に、母たらんと変わったのだ。
また、変化は母と父にも及んでいた。
気づけば、母は祖母へ、父は祖父へと変わっていた。母の孫に対する溺愛ぶりはある程度想像できたが、どこまでもぶっきらぼうな父が赤ん坊をあやすところは、まさか夢にも見なかった。
そして竹谷も、叔父になっていた。使えるようになるのはまだまだ先だし、喜ぶ顔を見せてくれる年齢ではないと重々知っていても、衝動を抑えきれずiPadを貢いだ。もう少し成長したら、ゆくゆくはイラストレーターやゲームクリエイター、はたまたeスポーツ選手を目指してほしいと願いつつ、無責任にゲームをプレゼントしていく所存でさえある。
そんなことを甥に対して思う中、ひしひしと心に迫るものがあった。
甥は未来そのものである、という思いだ。
竹谷家は、ずっと4人家族だった。その中で最も若い竹谷は36歳で、紆余曲折はあったものの、ゲーム業界に骨を埋めることを決意し、今を生きている。姉は、会社員ライフを謳歌していた。父と母は、家のローンを完済し、ふたりの子育ても終わり、Netflixや『ドラゴンクエストウォーク』を気ままに楽しんでいる。
つまり、それぞれの生き方がそれなりに固まった状態であり、あえて尖った表現をするなら、ゆるやかに死にゆく不変のコミュニティだった。
そこに、新しい生命がひとり繋がった。静まりかえった湖面に落ちた一粒の雫は、幾重にも波紋を作る。そして、波に水の生命力を見るように、コミュニティにしたたかな波動を感じたのだ。
それは、甥という小さな存在が成し遂げた、大きな変化にほかならない。
「甥が生まれてから、竹谷はよく家族の話をするようになった」
知人にこう言われ、確かに、と思った。これまで母、父、姉としていた一対一の会話に、甥が入ってきていた。たとえば、姉と私と甥、姉と母と甥、母と父と甥、といった風だ。当たり前だが、甥は話せない。しかし、ふたりではなく、なぜだか3人で話しているという確固たる感覚がある。また、3人だからか、竹谷家のコミュニケーションの絶対量は、ここ数年で疑いなく最大値を更新している。
「甥は、どんな人になり、どんなことをするんだろうね」
そういった話が、とても楽しい。そしてそれが、新たに生まれた命が持つ可能性の素晴らしさであり、愛すべき人間の尊さなのだと思う。
毎日のように姉から送られてくる甥の写真は、今では楽しみのひとつとなった。義兄と甥と、3人で写る姉の表情は、いつも優しい。
写真を見ていて、ふと思い至る歌があった。
「男と女が子を持ち、3人家族」
最近知った歌、『Three Is A Magic Number』の中に出てくる一節だ。3は魔法の数字である、とひたすらに熱唱しているのだが、その理由のひとつをこう歌っていた。
2に1を足すのだから当然だろう。初めて聴いた時、そう思った。しかし同時に、なにか唸らせるものを感じた。姉の家庭はもちろん、甥を通じた竹谷家のあり方も、3が鍵となっている。
それからというもの、歌の影響もあって、竹谷は3に感じ入ることが多くなった。さらに少々歌詞を借りると、「テーブルを立てるのに脚は3つ必要」であるのと近しく、生まれて初めて設立した会社であるミリアッシュは、3名で作り、3名で続けている。初めてプレイしたゲーム『ファイナルファンタジー』も『ドラゴンクエスト』も3で、『真・女神転生』、『ペルソナ』も3だ。そういえば、生まれて初めて書いたnote、つまりこの『今にも削除したくなるような自分語りを』も、エピソード3から始まった。
竹谷にとって、「私事ですが」は魔法の言葉ではないが、「3」は明らかに、強い力の籠められた魔法の数字である。
今日もまた、ポコンとメッセージアプリの通知が入る。姉から、甥の動画が送られてきていた。
甥は、自分の両の手で両足を力強く掴み、剣呑な面持ちで足指の匂いを嗅いでいた。
「できることが増えていくなあ」
笑ってから、姉にそう返す。
甥の世界は、笑顔に彩られている。そのうちに背も伸び、言葉も覚え、夢に目を輝かせる時も来るのだろう。
どのような夢かは、甥だけに追い追い楽しみにするとして、今より実現できやすい可能性に満ちた世界にするため、叔父は毛の後退してゆく頭をもっと捻らねばならない。
過去に得た知見で現在の物事を良くし、未来の後世へ繋ぐ。人間の根幹をもう一度心に刻み、もう一日を生きていく。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
