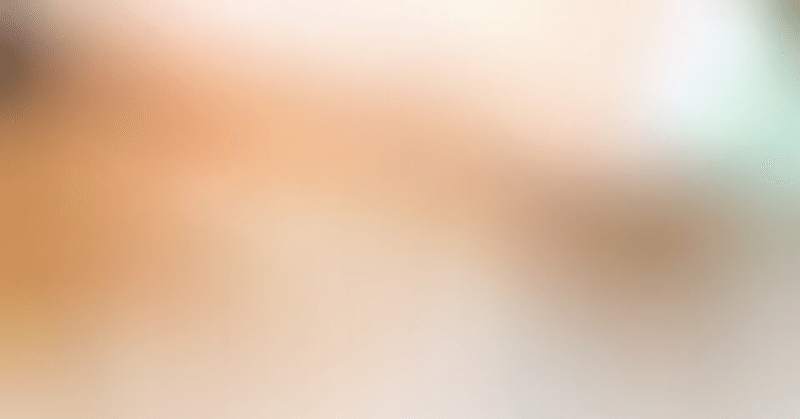
致命傷
濡れた制服が肌に張りついて気持ち悪い。
「なんで」
吐き出した言葉は無意識のうちにため息へと変わっていた。
甘く寂しい香りに鼻先を撫でられて、オレンジ色がちらつく。まだ秋なんだなと絶望的な気分になる。他の子たちは“もう秋だ”と焦燥感に駆られているのかもしれないけれど。
吸い込んだ空気で喉の奥がひりつく。伝えたい言葉が何一つ音に出来なかったときのような嫌な感じ。乾いた咳が出た。校舎の屋上から叫ぶなんて、するもんじゃないな。
そういえば、金木犀の香りには鎮静効果があったはずだ。喉も、そのずっと奥の痛みも鎮めてくれやしないか。
見上げた空は、その花の色に染まり始めている。道理で寒いわけだ。まあ、髪と顔が濡れなかっただけでもよしとしよう。
色褪せたフェンスに上体を預けるとガシャンと大きな音が鳴った。ぼやけたフェンスの向こう側に校門へと急ぐ生徒達の姿がある。しかし、こちらに気づくものはいない。誰も気に留めていないのだろう。今更、私がどんな奇抜な行動をしようが彼等にとっては道端に空き缶が転がっているのと変わらない。瑣末な出来事だ。
ただ、世界には酔狂な奴もいるもので、彼女は今日もこうして騒がしい私を満足そうに眺めている。
先生に叱られないギリギリの長さに調整されたスカート。そこから投げ出された白く細長い足が妙になまめかしい。なんだか見てはいけないものを見ている気分だ。見られているのは私なのに。
「見てて楽しい?」
冷ややかな視線を投げてやるが、こんなぐちゃぐちゃでドロドロの顔で凄んだって怖くもなんともないのだろう。その証拠に彼女は口元を緩めたまま『うん』と言った。うん、じゃない。
「あんま見ないで」
顔を背けてそう言うと「はーい」と間延びした返事と「私の唯一の趣味が奪われちゃったなぁ」という綿飴みたいな恨み言が聞こえてくる。
まぁ、別にそれでいい。助けてほしいわけじゃないし。
ヒーローもヒロインもいらない。
ただ、そこにいてほしいだけ。
それだけだ。
「ほら帰るよ」
両頬を手の甲で拭い、できるだけ浮上させた声を出す。声が可愛いと褒めてくれるときの彼女の顔が、私はとても好きなのだ。涙声なんて勿体ない。これも一生教えてあげるつもりはないけど。
だから、一拍遅れてクスリと笑う音がしたのは、きっと気のせいだ。
「仰せのままに」
彼女はほんの少し勢いをつけて立ち上がった。スカートを軽く払うと、帰ると言いつつ動こうとしない私の隣へやってきて、少し逡巡したあと足元に投げられたままのスクールバッグを拾い上げる。濡れ鼠になったそれは私のものだ。
「やめなよ。汚いから」
「汚くないよ」
そう言って不思議そうな顔をする。なら、さっき躊躇ったのは私が嫌がるかもしれないと思ったからか。
「…濡れちゃうからやめなって」
彼女の手から奪い返したスクールバッグは未だに水滴を垂らしている。
私より泣き虫かよ。
「また派手にやられたね」
その声に頷きながら、こんなにずぶ濡れだと中に入ってる教科書も無事ではないだろうなとぼんやり思う。
お前たちも眠って忘れてしまえたらいいのにね。可哀想。
「この辺に並べて明日の朝まで放置してたら乾くでしょ」
「そうやって宿題やらないつもり?」
「まあ、不可抗力で仕方なく?」
「えー!宿題写させてもらおうと思ってたのに」
「残念だったね。今回は君がやって私が写すんだよ」
「もう!好きな子には意地悪したくなるタイプなの?」
唇を尖らせてそう言うものだから、私は口元を緩めて『うん』と言った。
明後日の方向を向いていた瞳が私を捉え、わずかに細められる。睫毛が長いなと思うのは、もう境界線の向こう側なんだっけ?随分と昔に誰かからもらった言葉を惟る。
「落ち着いた?」
海松色の瞳が不安そうに揺らぐ。それは相変わらず綺麗で彼女によく似合っていた。
私には、似合わない色だと思った。
頷く。
「殺される以外擦り傷だから全然平気」
「あんたのそういうところ嫌いじゃないよ」
そう言ってひどく楽しそうに笑う。笑った時の喉の音が好きだ。お気に入りの瓶に詰めてソファの下に隠しておきたい。
あ。私の自意識が過剰ではないのなら愛おしそうにと言った方が正解だったのかもしれない。薄く色づいた頬を見てそう思った。引っ張られて体温が上がりそうだ。けれど、それではあまりに悔しいし負けず嫌いが疼くので、なるべく強気に答える。
「好きとは言ってくれないの?」
彼女は一瞬驚いた顔をしたが、悪戯っぽい笑みを浮かべて私の髪を撫でると、掬い上げたその一房にキスをくれる。
「そんな泣きじゃくった顔じゃなかったら考えてあげる」
平均身長の私よりも少し小さいくせに、顔も声も可愛いくせに、それは、まるで王子様だ。
紅潮しそうになる耳や頬を髪で隠すように小さく頷いて頑張ると呟いた。髪を伸ばしていてよかったと思う。
「ねぇ、まさかそんなことないと思うけど馬鹿なの?」
「馬鹿って言うな」
水の膜が張って視界がぼやける。
あと少しで零れ落ちるというとき、頬を包むように細い指先が優しく触れた。柔く摘まれる。かるく爪を立てられて目を瞑った拍子に左目から涙が一粒零れた。
「だったら頑張るなよ」
それを彼女の指先が掬い取る。
瞬き。右目から滑り落ちる涙を彼女の唇が追いかけるのが見えて咄嗟に両手で防御壁を作る。
「ダメ」
「なんで?いつもこれよりすごいことしてるのに」
「君が」
ひやり。人差し指が唇に触れた。
これは名前を呼んでほしいときの合図だ。
「丹夏が…汚れちゃうからダメ」
ほら私濡れてるしと、それらしい言い訳とともに押し返す腕に力を込めると不服そうな顔をされる。そんな顔したってダメなものはダメだ。耐えきれなくなって視線を落とす。
「ねぇ」
彼女の声色と体温は、私より少し低い。
その指先は傷跡に心地良い。頬から首筋を滑り胸元のリボンへと逃げていくのを名残り惜しく思ってしまうくらいには……
「な、に」
ふわりと身体の内側が甘くなる。あぁ、金木犀の香りには媚薬の効果もあるんだっけ。そうだ。声が震えるのは、きっとそのせいだ。絶対、そう。
「擦り傷程度でもさ。心臓に当たったらきっと死んじゃうよ」
慣れた様子でリボンを解いた指先が、透けたブラウスの上からブラのワイヤー部分をなぞった。
驚いて制止の声を上げる前に、彼女が呟く。
「卒業まで半年以上もある」
波打った海松色は宝石のようだった。
「…半年と少し我慢すれば終わるよ」
「唯愛のそういうところは好きじゃない」
「そか」
嫌いと言わないところが愛おしい。
私も好きじゃないよ。そう言うと彼女は押し黙った。
「どうしても不安なら、当たらないように祈ってて」
「…祈ってるだけであんたが助かるなら、いくらでも、なんでも、する」
長めの前髪が影を作り、宝石が隠された。
綺麗な瞳を持つ彼女が前髪を長くする理由が、鬱陶しい前髪が好きだと私が言ったからだなんて、本当たまらない。
「なんでもはしなくていいよ」
なのに、今は顔が見たいだなんて、おかしいね。
「唯愛のためなら、なんでも、するよ」
どうして君がそんな顔をするの?そう言いかけて、私も同じ顔をしていそうだから何も言えなくなった。
「なんなら百日詣りでもしようか?」
「やめて」
想定したよりも大きな声が出てしまって小さくごめんと口にする。
「もう助かってるから……」
特別なことはしなくていい。何かを与えてくれるから好きだなんて思いたくない。どうかお願い、神様にはならないで。
「そのままでいて」
丹夏がいるならなんだって平気だよ。本当。本当なんだ。心の中で呪文みたいに呟いた。
彼女はそんな私を見透かしたように薄く笑う。
なんだそれ。憎たらしい。
華奢な手首を捕まえて強く引き寄せた。小さく声を上げてよろめいた身体を抱き締めながら、あぁ結局、彼女まで汚してしまうなぁと思った。
「そんなことする暇があるなら、その100日間、私にちょうだい」
息を呑む音がする。
当然だ。普段こんな恥ずかしいことは言えない。誰か私の代わりに、可愛らしくてそれらしい言い訳を考えておいて。
「ぜんぶちょうだい」
羞恥と悔しさで発音がひらがなになる。
今は面白いからという理由で黒色がかった黄緑色の瞳に映してもらっているが、それがいつまでも続くとは思えない。なんて言うと彼女は怒るだろうけれど、正直それがとても怖いのだ。
だが一方で、こうも思う。
半分優しさで作られた薬があるように私の半分は嘘で組成されているし、もう一つくらい嘘になったところで変わらない。それに、未練があった方が幼気だ。なんて。
何度か瞬きをして涙が零れないことを確認していると、彼女が指を絡めてきた。指先にキュッと力を込められて水分量の高くなったペリドットとぶつかる。
「いいよ、あげる」
今度は私が息をつめる番だった。
「折角だし、100日後に結婚しよっか」
それは優しさと嘘のどちらだろう。
それとも。
彼女の手を握り返した。
「……うん」
さぁ、100日後に答え合わせをしよう。私だけの×××
どう転んでも、きっと致命傷だ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
