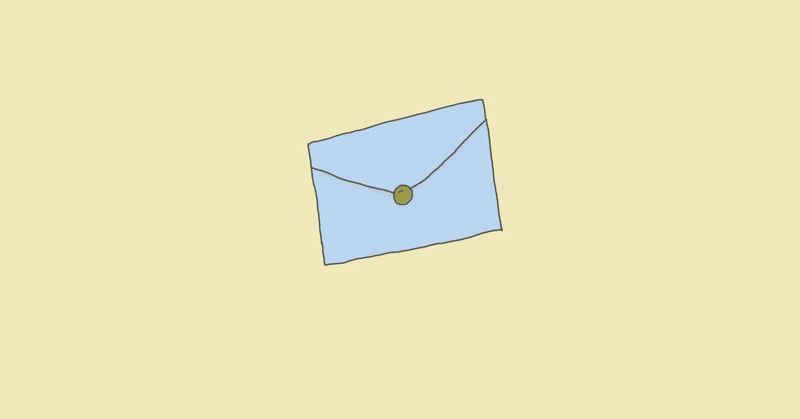
Y.I. 様
お久しぶりです。元気にしていますか。
唐突にそう言われても、君は僕のことなど何も覚えていないかも知れない。仮にそうだったとしても、仕方ないとは思う。だって、君と僕が最後に会ったのは、もう30年以上も前、小学校の卒業式のときにまで遡らなければならないから。
本当なら僕も君も、卒業後はそのまま隣にある公立の中学校に進学するはずだった。そうなるものだと思い込んでいたし、それ以外の可能性をどうして思い描けただろう。
結局、僕がその中学で学ぶことはなかった。半年余り籍を置いてはいたけれど、そのまま登校することなく別の学校に転校することになってしまった。そして君と再会することなく、今日まで時間は流れすぎてしまった。
どうして僕が中学を変わり、忽然と姿を消さなければならなくなったのか、詳しい経緯を知っている人はいなかったんじゃないかと思う。だってそれを説明できる唯一の人間だった僕が本心を一切誰にも話さなかった(厳密には話せなかった)から。でも、そのために無根拠な憶測がはびこり、かえって変な噂すら流れたとも聞いている。あるいはそのせいで君が僕を「関わるべきでない人」として記憶から消し去ってしまっていたのだとしたら悲しい。
もっとも、あの頃、僕自身が逃げも隠れもせず、堂々としていられたのなら、そんな噂も流れなかったに違いない。でも当時の僕は自分の身に降りかかった予想だにしない変化に戸惑い、混乱し、何もできなかった。春の雪崩に容赦なく押し流される景色を、ただ黙ってやり過ごすしかなかった。そのことについて、まずは書きたいと思う。
中学入学を控えた春休み、僕は自分の身体に起きた変化に気付いた。夜、トイレに行き電灯をつけても部屋が暗い。不審に思い天井に目をやった。おかしいのは電灯ではなく、自分の視力だった。視野の左上周辺が暗く濁っていた。
それから数日もしないうちに不穏な暗闇は拡大し、元通り見えるのは右下のわずかな部分だけになった。市内にある大学病院で診察を受けると、家に帰ることを許されず、そのまま緊急入院することになった。卒業式を終え、一週間も経っていなかった。夢と希望に満ち溢れていた中学生活への道はあっけなく立たれ、長く険しい闘病生活がはじまった。
それからは毎月のように手術を受けた。手術のたびに視力は落ち、見える映像が歪んでいった。勉強は病気が治ってからでいい、そう暢気に回復を信じて治療を受けていた自分が、もしかしたらもう治らないのではないかと感じたのは、7月を過ぎた頃だった。主治医から障害者手帳の取得を勧められた。その方が医療費の控除や福祉サービスの支援を受けられるから、と。
僕は頑なに拒んだ。でも、子供の言い分など聞き入れてもらえるわけもなく、僕は障害者のレッテルを負わされることになった。と同時に、今の視力はこれ以上回復しないことを悟った。そしてそのころを境に、もう無邪気には笑えなくなった。
その後も治療は続けられた。でも結局僕の視力が回復することはなかった。暑い夏が終わろうとしていた9月、手は尽くしたが回復の見込みはないと主治医に告げられたとき、僕の目は光をかすかに感じられる程度までに悪化していた。それはもはや視力とさえ呼べない代物だった。勉強どころか、満足に一人で歩くことすらできなくなっていた。
9月末、何度か中学の先生が面会にきた。先生方はおそらく、僕が学校へ戻れるか、確認をしたいらしかった。そう、君の通うあの中学校。僕の通うはずだった中学校だ。
もしあのとき、何としてでも学校に戻りたい、またみんなと勉強したいと懇願すれば、あるいはその通りになったかも知れない。でも、僕はそうしなかった。できなかった。どうしてだろう? きっと、失明して無力になった自分を、誰にも見せたくなかった。もう昔の自分でない自分を、白日の下にさらしたくなかった。その時は、それがとても恥ずかしいことのように思えた。
その後、僕は逃げるように、遠くの街にある盲学校に転校した。今ならわかる、失明したばかりの僕を周囲の人たちが懸命に支えようとしてくれていたこと。でも、どうしても当時の僕は新しい学校にはなじめず、いらだち、何も受け入れられず、ほとんどの時間を自宅の一室に引きこもって過ごした。
部屋から聞こえてくる中学のチャイムを聞くたび、僕の胸はじりじりと締め付けられた。自宅から目と鼻の先にある中学で青春を謳歌し、新しい世界へ羽ばたく君やかつての友人を想像すると、自分がみすぼらしくて、情けなくて、でもどうしようもなくて、たまらなかった。本当なら自分もその中にいたはずなのに、どうして運命はこうも残酷なのか。そんなとき、今すぐにでも君に会いたい、でも会えないという思いがいつも胸の内で交錯していた。
僕は君のことがずっと好きだった。はじめて会ったのは小学校1年のときで、僕のほっぺたをつついて下の名前で呼びかけてきた君の屈託ない笑顔に、子供ながらに戸惑ってしまった。
小学4年のとき、はじめて隣の席になった。抜き打ちのテストで消しゴムを忘れて困っている僕に、そっと君が自分のを貸してくれたこと、今でもはっきり覚えている。
高学年のクラス替えで同じクラスになれたことも、修学旅行で同じ班になれたことも、広島行きの新幹線で隣同士の席になれたことも、その場の流れでグループで映画を観に行くことになったとき、隣の席に座ってくれたことも、日毎に大人びていく君の横顔とともに、脳裏に刻まれている。
けなげに咲く小さな花のように、君はいつもやさしく、笑顔が素敵だった。誰に対しても、僕のように地味で取り柄のない存在にも、いつだって分け隔てなくその魅力を差し出してくれた。その魅力は、ちゃんと見る人にしかわからないぐらい繊細で、単純で目立ったものを好む大多数の人々には決してわからないぐらい、特別なものだった。そんな君を、僕はいつも憧れと尊敬の眼差しで見ていた。君みたいな素敵な人に好かれるような人になりたいと強く思った。
それぐらいの年頃の男子にあるように、不器用なふるまいしかできなかったのは、気持ちをうまく表現できなかったから。話しかけられても仏頂面しかできなかったその裏で、僕の心は激しく脈打っていた。君がいてくれたおかげで、人を好きになるってことが、生きているのがこんなにも素晴らしいことに気付けた。どうしようもなく苦しかったけれど、それ以上に嬉しかった。
やがて卒業を迎える頃になって、僕はひそかに決めていた。中学生になり、環境が変わっても君への思いが変わらないのなら、この気持ちを正直に伝えよう、と。
卒業式が終わり、教室に戻ったとき、ふと見ると君は窓際の席で静かに泣いていた。よく晴れた日で、春の木漏れ日が美しく顔を照らしていた。
それが君を見た最後だった。
病気の発症がせめてあと3か月遅かったなら、セーラー服姿の君と、学校でとりとめない話ができたかも知れない。休日の昼下がり、一緒にどこかへ出かけ、夢や目標について語り合えたかも知れない。告白して、あるいは君を驚かせたかも知れない。
すべてが果たされないまま終わった。何もできない自分が悲しかった。悔しかった。もう死んでしまいたいと幾度となく思った。
でも、それと同時に、またいつか君と会えるんじゃないかというかすかな期待を抱いていた。その日のために、なんとか生きなければいけないとも思った。またいつの日か巡り合えたときに、胸を張って笑顔でいられるように。
眠れぬ夜を重ね、不毛な葛藤の日々がいつまでも続いた。ぎりぎりで下した決断は、家を出てこの街を離れることだった。
中学を卒業した後、僕は慣れ親しんだ大阪を捨て、東京の高校に進んだ。国立の大学付属で寄宿舎を備えた盲学校だ。過去の自分と決別し、誰も知り合いのいないところで新たな人生を送りたかった。君のことも忘れられると思った。できれば忘れたかった。
別に東京に憧れがあったわけでもない。むしろ僕は地元をこよなく愛していた。場所なんてどこでもよかった。ただ、負けたくなかった。このままで終わりたくなかった。憐れまれたり見下されたりしたときに感じた屈辱を晴らしたかった。障害があっても強く生きられることを証明してみせたかった。何もできない自分の無力さを克服したかった。
その後、僕は大学に進み、就職し結婚した。もちろん詳細を語りだせば長くなるけれど、一行で要約すればありきたりな人生だ。でも、一歩間違えれば、あの時東京行きを決めることがなかったなら、僕は狭く暗い世界に引きこもったまま、めそめそ生きるだけの存在だったかも知れない。そうだとしたら、僕は今こうして手紙を書くことすらできなかっただろう。ねえ、信じてもらえないかも知れないけれど、小学生の頃、学年で一番太っちょだった僕は、中学生になってびっくりするぐらい体重が減ったんだよ。道ですれ違っても気付いてもらえないぐらいに。
若気の至りもあり、ときには無茶をして、たくさんの人に迷惑をかけたけれど、同じぐらいたくさんの人のやさしさに支えられ、老いゆく身体を引きずりながら、今なお生きている。それは大なり小なり誰だって、きっと君だって同じなんじゃないかな。僕の知らない街で、同じく年を取った君が幸せに暮らしていることを、僕は信じている。
ところで、どうして今頃になってわざわざこんな手紙を書いているのか、君は不思議に思っているかも知れない。こんなにも時間が流れ、人も世も移り変わった今でさえ、君のことを夢に見るときがあるんだ。厳重に鍵をかけておいた記憶の箱を、容赦なく蹴飛ばすみたいに、強烈で圧倒的な夢を。
夢は無意識からのメッセージと言う。そのメッセージにどんな意味があるのか、本当のところはよくわからない。でも、そこには今を生きる僕が向き合うべき何かが隠れているんだと思う。失明した13歳のとき、中学に戻れなかったこと、君と再会できなかったこと、思いをちゃんと伝えられなかったこと。断ち切られた願い。果たされなかった夢。
本心を言えば、君も同じように感じていてくれたなら嬉しいと思う。僕のことをふと思い出し、あるいは夢を見て、懐かしくも切ない気持ちになってくれているのだとしたら。でも、悲しいぐらいに時間が流れた今ならわかる。仮に失明せず同じ学校に行っていたとしても、僕は君の特別にはなれなかったこと。すでに新たな世界への一歩を踏み出していた君にとって、僕はもう中学生の時点で「過去の人」になっていたこと。もしあの頃、君が僕を少しでも特別と思ってくれていたなら、君から僕に連絡を取るなり、会いに来てくれるなりできたはずだよね。恋愛の行方という意味ではどの道を辿っても結果は同じだった。それでも、君に会い、直接思いを伝えたかったというのは僕のエゴなのかな。
すべては終わってしまったこと。でも、これだけははっきり言える。僕に人のやさしさを、ぬくもりを、寄り添うことの大切さを、人として一番大事なことを教えてくれたのは君がはじめてだった。君はいつまでも僕にとって掛け替えのない、特別な人。どうして忘れることができるだろう。たとえもう会うことがなかったとしても、この気持ちは変わらない。
ありがとう、心から。この手紙がいつの日か、回りまわって君に届くことを信じて。
さよなら。いつまでも元気で。
T.N.
