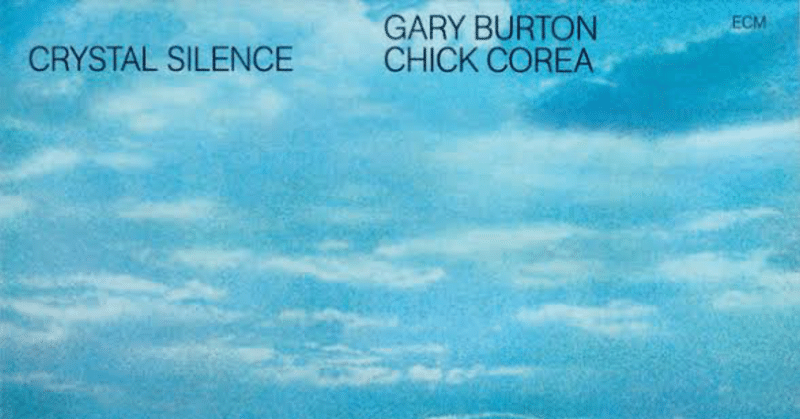
ジャズ記念日: 11月6日、1972年@オスロ
Nov. 6, 1972 “Falling Grace”
by Gary Burton & Chick Corea
at Arne Bendiksen Studio, Oslo, Norway for ECM (Crystal Silence)
前紹介曲からちょうど一年後、ジャズビブラフォン(鉄琴)のマスター、ゲイリーバートンとチックコリアのピアノによるデュエットアルバム。
7回のグラミー賞を受賞しているバートンは、4本のマレットを操るテクニックを駆使して現代ビブラフォンを開拓した功績がある。
スタンゲッツに起用されて注目を浴びるようになったが、採用されるまでゲッツが探していたのは、ビブラフォン奏者ではなくてギター奏者だった。

ベースは本曲を作曲したスティーブスワロー
そう言えば、キースジャレットがギタリストとしてゲッツにスカウトされたと回想していた時期と年代的に被りそう(以下紹介曲に記載)。ギタリストが見つからずにバートンに辿り着いた、という経緯なのかと邪推する。
本作の二年前に収録されたバートンとキースの共演アルバムが存在するが、その際にはこの話で盛り上がったのではないか。

アルバム名の通り、クリスタルクリアなトーンときめ細やかで几帳面なスタイルを共有するチックコリアとECMとの相性も良く、続編が何枚か存在している。本作は、ミュンヘンジャズフェスティバルでの、この二人のデュオによる一曲限りのジャム演奏を聴いたECMレーベルの創業者マンフレートアイヒャーが、アルバム化したいとしつこく懇願、ベルリンジャズフェスティバルに二人をブッキングして欧州に呼び寄せ、その後にオスロのスタジオで録音したという経緯で生まれたもの。

演奏記録が残っている
因みに、この直前、1972年8月26日から9月11日まで、ミュンヘンオリンピックが開催されていた。

当初予定していた9/10から9/11に変更された
ゲイリーバートンはバークリーでの講師歴もあって新人発掘にも長けており、自身のバンドからパットメセニーや小曽根真が巣立っていった。既に引退しているが、晩年期には現ジャズギター界の若手のホープ、ジュリアンラージを起用していた。
バートンの自叙伝の翻訳本がある。記憶も鮮明で、自らが歩んだジャズの歴史の一部の事実が包み隠さずに記載されているのが面白い。

自身のキャリアに沿って、修行時代から独立して現在に至るまでのストーリーの中に、如何にジャズ界がドラッグに塗れていたのか、演奏を共にしてそのツアーマネージャーまで務めることになったスタンゲッツの破天荒さ、痴呆となったセロニアスモンクの晩年、本アルバム制作に至る経緯、パットメセニーとの出会いやその賞賛等々、ジャズ界の内情が興味深く記載されており、文章も口語体で読み易い。
バートンの公演を観に行って感じたのは、演奏や進行が、知的、理路整然としていて、清潔感もあり、如何にもその性格や価値観が一貫性を持ってステージに反映されているということ。それと、自ら難解な曲に挑んでベストを尽くす姿勢と、当時まだ新人だったジュリアンラージを前面に押し出して後継の育成を意識して行っていたのが印象的だった。
曲は、ジャズギタリストの父親的存在のジムホールから直接推挙されたとして同自伝に登場している、バートンが長年連れ添ったベーシスト、スティーブスワローによって作曲されてスタンダード化したもの。
本演奏は、オスロの透明な空気感を背景に、僅か2:40秒の長さに耳がついていくのが精一杯なほど玉手箱のように音が極限まで詰め込まれている。愛弟子メセニーとの同曲のデュオ演奏映像を見てみると、縦横無尽にバートンのマレットが駆けずり回っている事からも、その難易度の高さが視覚的に良く把握が出来る。
さて、ビブラフォンに興味を持たれた方は、こちらもどうぞ。先ずは、バートンがビブラフォンの父と評したライオネルハンプトン
新主流派の一人で、バートンと同年代のボビーハッチャーソン
最後に、チックコリアに興味を持たれた方は、本作8ヶ月前に収録されたハードボイルドなゲッツとのエレキピアノによる共演作をどうぞ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
