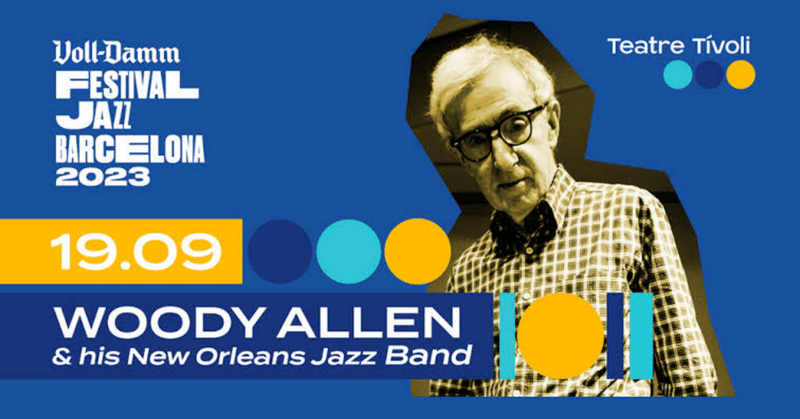
【プレイリスト】9月に聴く9月録音のジャズ
「September 長月」オリジナル解説書(CD一枚分)
※1日単位「今日のジャズ/ジャズ記念日」の元ネタですが、録音年月日順で、記載内容も異なります
※選曲後記が最後にあります
※音楽を聴いてから解説を読む事をお勧めします
※録音日、曲名、演奏者、収録場所、レーベル、アルバム名の順で曲の情報が記載されています
20 & 26, 1956 “Come Rain or Come Shine”
by Kenny Drew, Paul Chambers and Philly Joe Jones at Reeves Sound Studios, NYC for Riverside (Kenny Drew Trio)
マイルスデイビスと同年五月にマラソンセッションを敢行したリズムセクションが、当時のブルーノート一推しのピアノ、ケニードリューと組んで、創業者がオーディオマニアで出版業界出身という、こだわりのありそうな、スタイル、ストーリーと音質に凝ったリバーサイドレーベルに録音。同じ東海岸レーベルでも、リハーサル無し一発録りでその場の雰囲気を重視するプレスティッジ、入念なリハーサルでクオリティーの高い新曲を発表していくブルーノートと、音質と企画で差別化を図って、モンク、エバンス、ウエスモンゴメリーらを擁し、独自のポジションを築いたリバーサイドは、前二者と共にモダンジャズ三大レーベルとして扱われる。この三レーベルの創設者はユダヤ系で、たまたま黒人が主たるジャズというニッチな領域でビジネスを展開した結果というのが一般的な見解のようだが、ユダヤ系人種が自ら体感している人種差別に対して寛容な背景もあるだろう。ここでのドリューの演奏はオーソドックスながら、力強く子供用のおもちゃピアノのような音でパーカッシブに鍵盤を叩くのと、1:27からのようにメロディーを下方に崩していくフレーズ、「チャラララ、チャラララ」というメロディーをお得意の様に多用して若々しく活気溢れる内容で、良く聞くと右手と左手で別メロディーを進行するようなモダンな演奏もこなしているが、ハードバップの域を出ず、五月の最終曲にある後年に欧州に移住してからの落ち着いた演奏とはテイストが随分と異なる。音階と共にテンションが上がったと思いきや下げて落ち着くように繰り返す事でスイングするベースのチェンバースが、ドリュー同様に活力あるトーンで寄り添って絡み付き、堂々としたソロを奏で、それを受けたフィリーが『シャカシャカシャカ」を連発してからモードチェンジして加速する。演奏を牽引するチェンバースは、この日の翌日にフィリーを従えてブルーノートでの初リーダーアルバムの収録が控えていたという事実で合点が行く。豪華なハロルドアーレンとジョニーマーサーの手にによるミュージカル曲がスタンダード化したもの。
22, 1957 “Asiatic Raes” aka “Lotus Blossom”
by Sonny Rollins, Wynton Kelly, Doug Watkins and Philly Joe Jones at Van Gelder Studio, Hackensack, NJ for Blue Note (Newk’s Time)
前曲から約一年、引き続き登場するドラムのフィリージョージョーンズが、前曲のブラシからスティックに持ち替えて、力強くダイナミズムに溢れた演奏が特徴的で、それはアーティストに敬意を評して個性を活かすレーベル、ブルーノートとテナーのソニーロリンズの意向が交錯して生まれたものだろう。ベースとの組み合わせは前年に収録された六月二曲目と同じだが、楽曲と音のテイストが前者の明朗なお祭り大合奏から様変わりして無骨なハードボイルド調となっている。作曲はトランペット演奏者のケニードーハムで、曲名は「蓮の花」。ロリンズのブローの力強さは数多ある録音の中でも指折りなのは、相性の良いフィリーに触発されてのもの。約80秒の長いドラムソロが与えられていることからも信頼の高さが理解できる。入念に練られたアレンジでブルーノート特有の中音域寄りの特性において奥行き感のあるドラムの中で左から象徴的に叩き出されるシンバルの「キンキン、カンカン」を如何に響かせられるのか、がオーディオの面白さで、音場を狭めてまで凝縮された音作りをするのがブルーノートとルディバンゲルダーの凄み。この二人に立ち会うピアノもベースも肉体勝負。途中で、バッパーパッパーパッパーと、1:20から1:35にかけてお得意のモールス信号を入れて間合いを整えてモードをチェンジしてからバンドが疾走し始めた後のジェットコースターのように予期せぬ展開を見せるのがロリンズの奇想天外さ。
12 & 13, 1958 “Tea for Two”
by Blossom Dearie, Ray Brown & Ed Thigpen
at New York for Verve (Once Upon a Summertime)
激しい前曲とはBlossomの名前繋がりでゆったり一息。初めにレコード針を落としたようなノイズから始まるのも粋な演出。甘く耳元で語りかけるような歌唱法は長期滞在していたパリ時代に確立したものと推測する。それもフランス語で特徴的なサ行とタ行のアクセントが艶かしく記録されている。そして選曲も「シェルブールの雨傘」等を手掛けたフランスの大作曲家ミシェルルグランによるもの。そして英語版作詞は再びジョニーマーサー。オスカーピーターソンを支える伴奏者がデアリーのピアノ弾き語りとタッグ、どちらかと言うと軽めに録音されるレイブラウンのベースが雄大な重低音で捉えられているのが嬉しい。本レーベルのVerve設立者のNorman Granzも、ブルーノート設立者のAlfred Lion同様に東欧系ユダヤ系移民で、ジャズ・アット・ザ・フィルハーモニック(JATP)と題したコンサート・シリーズを興行し、出演したミュージシャンをマッチングするなどした演奏を録音、世に送り出して一大レーベルを築いたが、エラフィッツジェラルド、オスカーピーターソンのマネージャーを担ったり、ディアリーらのアーティストを発掘するなどに加え、黒人の地位向上に多大なる貢献をしたそう。
7, 1962 “Soul Bossa Nova”
by Quincy Jones Orchestra incl. Roland Kirk, Phil Woods, Jim Hall and others at A&R Studio, NYC for Mercury (Big Band Bossa Nova)
ジャズトランペット奏者で、マイケルジャクソン黄金期のアレンジャーとして大成するクインシージョーンズが著名ジャズミュージシャンを招集してボサノバのビッグバンドを編成、録音したのが本作。三年後にボサノバの名盤『ゲッツ/ジルベルト』でグラミー最優秀録音部門賞を受賞し、後にビリージョエル作品等で名を成すフィルラモーンのプロデュースという豪華な組み合わせだから音楽も録音も悪い訳がない。クラシック録音のように音場の広さと奥行き、多数の楽器の定位が捉えられている上にデフォルメされていて短い曲ながら印象深い。著名ミュージシャンも多数参加しており、軽快なフルートソロは盲目マルチプレーヤーのローランドカーク。作曲はジョーンズでユーモアに満ちた一度聴いたら忘れない印象的なメロディーが受けて、テレビ番組や映画に度々登場、1998年フランス開催のワールドカップテーマ曲で世界的な認知を得た。この手法の集大成がマイケルジャクソンの綿密かつメリハリの効いたアレンジで、バックバンドを実力者が固めたのは勿論、『Bad』に至っては、ジャズオルガン第一人者のジミースミスをソロで起用して全世界のスポットライトを当てた。レーベルは、ジャズとしては珍しくシカゴで設立され、それまで主流だったラジオではなく、ジュークボックスを使ったプロモーションにより成長を遂げたマーキュリーで、サラヴォーンやダイナワシントンを擁した。このレーベルも創設者はユダヤ系で、ジャズへのユダヤ系人材の貢献は計り知れない。
13 & 15, 1962 “Loads of Love”
by Shirley Horn, Kenny Burrell, Gerry Mulligan, Hank Jones, Milt Hinton, Osie Johnson and others at NYC for Mercury (Loads of Love)
マイルスの後押しでニューヨークに進出してデビューしたシャーリーホーン。ハスキーボイスで「あ」に「゛」が付いているのが歌声の個性。サ行の発音も特徴的で前々曲と比較すると白人と黒人の発音の差がよく分かるし、ボーカリストとしての崩し方や間の取り方も、良し悪しではなくて個性として比べると興味深い。1:10からのオーケストラ伴奏は期待の表れのような豪華なオールスター布陣を交えてのもの。キレの良いドラム、主張しないが適度に間合いを取って存在感を示す、ハンクジョーンズの楽しそうに合いの手を入れるスインギーなピアノが左に、それに対話するかのような間合いで刻まれるケニーバレルの粘るブルージーなギターが右に、助さん角さんのように鎮座して、中心となるボーカルを引き立てて心地良く流れる展開が良い。作曲はロジャース。オーディオ的には前半のカルテットも、その後のオーケストラも質が高く、何よりもホーンの存在、そして口元が目の前に現れるのが絶妙。ジャズクラブのステージが演奏者と共に目に浮かぶレベルに敬服する。
17, 1962 “Caravan”
by Duke Ellington, Charles Mingus & Max Roach at Sound Makers Studio, NYC for United Artists (Money Jungle)
直後に予定されていた、飛ぶ鳥を落とす勢いのコルトレーンとの共演を見据えていたのか、男爵エリントン、63才にして血気盛んなが有望株の若手ミュージシャンと組み、自作の名曲をスタジオでトリオ録音。どういう経緯でこうなったか知る由もないが、若手二人が挑発モードで演奏を始めても怯まずに横綱相撲のように受け止めて対峙、それ以上の迫力で押し返すエリントン。ここでは若手に触発された、というよりも自らを鼓舞して意図的に若手を煽るような力強いタッチ。結果、三人が演奏に何かをぶつけるような怒りモードで化学反応を起こして、音楽だけではなく楽器まで壊れてしまうようなヒヤヒヤ、スレスレ感が何度聴いても飽きない理由か。49秒目からトリオが疾走して59秒目からのドラムに合わせて階段から転がり落ちていくようなエリントンのメロディーがドラマティック。エリントンは若手に、年配だからといって遠慮せずに自分の個性を思う存分表現しなさい、という事を教えたかったのかもしれない。結果、エリントンも若手からの刺激を吸収、指折りに過激な演奏が生まれた。なんと言ってもブイブイと力強いミンガスのベースと、六月のCDでカリプソのドラムを陽気に叩いていたのとは別人のようなシリアスなローチ、これ程までに過激なジャズは稀有でエリントンが、若いのもなかなかやるじゃねえか、と嬉しそうにピアノを弾く、というより三者拮抗の打撃戦のように叩く姿が思い浮かぶ。
18, 1962 “It’s Easy to Remember”
by John Coltrane, McCoy Tyner, Reggie Workman & Elvin Jones at Ruby Van Gelder Studio, Englewood Cliffs, New Jersey for Impulse! (Ballads)
前曲の翌日にもう一方のコルトレーンがレギュラーカルテットでバラードアルバムを録音。バラードが、あまり得意ではないという評判に違わず、全体的にぎこちない印象だが、それがまたコルトレーンの魅力。一説によるとコルトレーンのサックスのマウスピースの調子がいまひとつで、力強くブローが出来ないために、収録時にバラード曲に切り替えたとの由。それが事実かどうかは定かでは無いものの、このアルバムでのコルトレーンの音色は確かに硬いし、時に神がかったように感情と演奏がシンクロするコルトレーン絶好調の演奏とはかけ離れて、感情がかなり先行した印象を受ける。もしかするとリードのせいではなくてエリントンとのバラード曲での共演が控えているがために、前哨戦としてレギュラーカルテットでバラードアルバムに取り組んだ、と考えるのが自然なのかもしれない。通常はパーカッシブなマッコイタイナーのピアノが影を潜めて、後に作曲集アルバムを発表する程に敬愛するエリントンを意識したかのような演奏。同レーベルのインパルスは、その後にVerveでボサノバを、そしてフュージョンを普及させたCTIに携わり、名作を多数輩出してジャズ界に貢献した名プロデューサーのクリードテイラーが立ち上げて、コルトレーンと契約、本作品等で売上を牽引して、その拡大に大きく寄与した。このアルバムも例に漏れずロングセラーとなり、日本のテレビ番組のバーでの一献シーンに度々登場している。が、最後はバラードにしては容赦無いエルビンのドラムロールで幕を閉じるのも印象深い。
26, 1962 “My Little Brown Book”
by Duke Ellington, John Coltrane, Aaron Bell & Sam Woodyard at Rudy Van Gelder Studio, Englewood Cliffs, New Jersey for Impulse! (Duke Ellington & John Coltrane)
前曲から八日後、歳の差27年の両者が合流。前々曲で若手相手にエネルギッシュに暖まったエリントンだが、激しい演奏をするはずのコルトレーンが拍子抜けするほどの大人しさ。マウスピースの調子が引き続き悪いのと巨人を前に緊張した事が重なったからだろうか。そしてコルトレーンに追い討ちをかけるかのように、希望した録り直しは却下された。エリントンは、それが最善なのだから一発録音が良いと諭して録り直しは行われなかったそう。本人が満足していない演奏にエリントンは本当に満足していたのだろうか。しかも前々曲のセッションでは何度も録り直しが記録されているのとは対照的なエリントンの判断は何故なのかと勘繰ってしまう。完璧を目指して録り直すコルトレーンの態度に対する、ジャズの本質的な姿勢を教える為のショック療法か。だとすると、もっとヤンチャして良いぞと前々曲では煽り、ヤンチャしているコルトレーンには音数吹けば良いというものではないから一音一音、1セッション毎に大切に演奏しなさい、と後継者たちに伝道師の如く伝えたかったのかもしれない。それゆえにエリントンはコルトレーンの課題であった音数の少ないバラード曲を選定、それを控えたコルトレーンが予習するかのようにレギュラーカルテットでバラード曲を演奏、記録を残し、エリントンとの共演に臨んだ、とも考えられる。前曲のタイナーは、このエリントンの演奏に酷似しており、コルトレーンがエリントン風に演奏するように指示したのではないかと勘繰りたくなる程。そして向上心旺盛なコルトレーンは、両者の記録を残して違いを確認したかったのかもしれない。このアルバムでは、伴奏者がエリントン側とコルトレーン側で分かれていて、テイストが異なるが、このアルバムだけの相性で言うとエリントン側に軍配が上がると考える。この曲は、エリントンの懐刀と評される『ラッシュライフ』等を手掛けたビリーストレイホーンによる作品。因みに、ここまで五曲続けて1962年の九月録音。この月にビートルズがデビュー曲の『ラブミードゥ』を録音してロックの大衆化で音楽業界が様変わりしていく先鞭を付け、ケネディがアポロ計画を推進するスピーチをするなど冷戦が本格化、人種差別の激しい南部にあるミシシッピ大学に黒人が警官に擁護されながら登校した際に暴動に発展するなど公民権運動が激化していく。世相の流れを受けてジャズもこの後、混迷の時代を迎える。
2-5, 1964 “April in Paris”
by Sammy Davis Jr. & Count Basie Orchestra arranged by Quincy Jones at Bell Sound Studios, NYC for Verve (Our Shining Hour)
両巨匠の組み合わせによる演奏。ベイシーによるビッグバンドの経済的維持、大スターながら商業的には当時スランプとされる稀代のエンターテイナー、サミーデイビスJRが組んで、クインシージョーンズがアレンジするという、これもまた豪華な組み合わせ。緻密に計算されたアレンジで、メロディーのリードを取る右側と追随する左側の掛け合いのように優秀なミュージシャンによる抜群のアンサンブルが堪能できる。終わると見せかけて「ワンモアタイム」の掛け声の後で、更に盛り上げるのはエンターテイナーたる演出。サミーの声も発音も、見出してくれた恩人のシナトラら、大衆受けした歌手同様にハッキリとしていて癖がなく分かりやすい。因みに名前にJRが付くのは、一般的には、偉大な父親の存在を受けて命名されるもので、語弊を恐れずに言うとボンボンが多い。そして命名後に父の名前にはシニアが付くが、そのデービスシニアはダンサーで名を成した。あのマイルスについて言うとルパン三世の如くリアルなIIIで、シニア、ジュニアと続いた三代目。マイルスの父親は歯医者で、確かにボンボンだったらしく、チャーリーパーカーに気に入られたのは、演奏のみならず、クスリを調達する資金を兼ね備えていたから、という説もある。作曲は「言い出しかねて」等を作曲したヴァーノンデュークによるもの。地名絡みでは、六月の最終曲の”I like New York on June”もあるが、デュークは更に”Autumn in New York”というスタンダード曲も手掛けている。
22, 1965 “Unit 7”
by Wes Montgomery, Winton Kelly, Paul Chambers & Jimmy Cobb at Rudy Van Gelder Studio, Englewood Cliffs, New Jersey for Verve (Smokin’ at The Half Note)
フュージョンに路線変更する直前のウエスの絶好調な純ジャズ演奏。三年前の六月のクインテット演奏を機にレギュラーバンドとなった相性抜群でノリノリのウイントンケリートリオとの息もピッタリ、場数を踏み、進化・成熟して名人芸的な一体感に溢れる、かといって手加減しない刺激的なアドリブのコンビネーションが味わえる。先ずはピアノの何処までも果てしなく聴いていたいソウルフルなソロから始まり、これまたとめどもない雄大でブルージーなウエスの管楽器的なソロ、メロディーの上下運動でグルーブを絶えることなく安定的に送り出すチェンバース、ジミーコブによる機械仕掛け的になりがちなビートを微妙なテンポの揺らぎと音の強弱を刻む事で飽きることの無いリズム、考える事なく純粋に音楽にのめり込むことができる、まさにご機嫌な音楽。特に4:52秒からのウエスとケリーの一心同体のようなアドリブの掛け合いから始まるバンドの疾走感は類稀なレベル。そして冒頭のケリーのソロ中のウエスのさり気無いバッキングが秀逸。ジャズクラブ、ハーフノートでのライブというアルバム名ではあるが、本曲はルディヴァンゲルダーによるスタジオ録音で、所謂ブルーノートサウンドに類似してはいるものの、プロデューサーが後にフュージョンを開拓したクリードテイラーで、ウエスの左スピーカー寄りの配置や構成面等は商業的に工面された印象を受ける。テイラーはこの録音に立ち会いつつ、モンゴメリーとヴァンゲルダーを起用した、二年後に設立されるCTIのフュージョン構想が芽生えていったのかもしれない。ウエスと共演歴のある名ベーシスト、ジャズミュージシャンとしては珍しいフロリダ出身、サムジョーンズの作曲。
18, 1966 “Forest Flower: Sunrise”
by Charles Lloyd, Keith Jarrett, Cecil McBee & Jack DeJohnette at Monterey Jazz Festival, CA for Atlantic (Forest Flower: Charles Lloyd at Monterey)
新感覚のジャズの名演。カリフォルニア州海沿いで温暖なモンタレージャズフェスティバルでの心地良い海風が流れるような演奏。レーベルのアトランティックは、ジャズで大成して、その後にR&Bやロックに拡大して一大レーベルとなったように、機を見る才覚がここでも発揮され、本アルバムは人気を博し、のちにジャズロックと形容された。アトランティックの共同創設者の一人もユダヤ系との事。映画を含めた米国エンタテイメント産業とそれを支える弁護士には、ユダヤ系が多い。映画産業を牽引するパラマウント、フォックス、ユニバーサル、コロンビア、メトロゴールドウィンメイヤーの創設者もユダヤ系という事もあるだろう。人種で言うとアメリカ人ネイティブの血を引くとされるテナーサックスのチャールズロイドは、フォーキーでアメリカーナ、時にフリーキーなスタイルの演奏者としても、若手発掘にも優れており、ここでは、若き日のキースジャレットとジャックデジョネットが起用されている。テンポが目まぐるしく入れ替わる中で、強弱を付けたジャズの伝統に縛られないフレッシュで煌びやかな旋律と楽譜に束縛されないポリリズムのリズム感が斬新で注目を浴び、その後のマイルスバンドへの起用に繋がる。このモンタレーから車で二時間ほどの距離にあるサンフランシスコでは、この頃ヒッピー文化が花盛りで、その自由を追求するマインドに影響を受けるような演奏で、奏者のファッションもアフロだったり、どことなくヒッピーっぽい。この翌年に同地でジャニスジョプリンやジミヘンが参加したポップフェスティバルが開催される。そこでジミヘンがギターに火を放つ演出をするステージが生まれた。最後に曲がプツリと切れるのは、絶え間無く続く二部構成のため。
19, 1979 “Theme from New York, New York”
by Frank Sinatra with Vincent Falcone, Jr. orchestra arranged by Don Costa at Western Recorders, Hollywood for Reprise (Trilogy)
ジャズボーカルの王様、フランクシナトラ。マーティンスコセッシ監督、ライザミネリとロバートデニーロがジャズ演奏者として登場する恋愛映画『ニューヨーク、ニューヨーク』からのテーマ曲で、『キャバレー』や『シカゴ』と同じくガンダーとエブのコンビが手掛けた。その映画によって曲はヒットする事は無かったが、シナトラが取り上げてアレンジを加えたところ大ヒット。 NYヤンキースのオーナーのお気に入り曲で、球場ではヤンキースが勝利すると『六甲おろし』の如くに本曲が流れるそう。出身の東海岸的な印象の強いシナトラだが、本曲を含めた多くの作品が、実は西海岸で録音されている。意外ではあるが、拡大した音楽産業が、ハリウッドの一大エンターテイメント産業の一部に組み込まれた、と考えると整理が出来そう。ブロードウェイミュージカル調ながら、オーケストラを含めて開放感溢れて空気感が明るく軽いのは、西海岸録音だからかもしれない。オーケストラも映画音楽のような番人受けするトーン、展開とアレンジで、シナトラとオーケストラの組み合わせは鉄板だと改めて確信する。この曲でのシナトラの歌い方は、演出的には通常のクリアな発声では無く、特に後半にかけて喉を大きく開いたダミ声的な表現となっているのが面白い。ニューヨークの都市が生まれた記念日は収録前日の9月8日。そういう演出なのか、そうで無いにしても知っている演奏者は意識していたかもしれない。ニューと名前が付く地名は大体イギリス植民地の新たな地名だが、ニューヨークはイギリスのヨーク公に習っての命名。その前の名前はニューアムステルダム、オランダ領だった。ニューヨークの発音は、ネイティブ発音ではヌーヨークに近く、シナトラも、これに従っていることが分かる。
1-5, 1982 “Liberty City”
by Jaco Pastorius
at Japan (Budokan/Festival Hall/Yokohama Studium) for Warner Bros. (Invitation)
Recorded Live at Budokan (Tokyo), September 1st, 1982 Festival Hall (Osaka), September 4th, 1982 Yokohama Studium (Yokohama), September 5th 1982
ジャズベースの変革者、ジャコパストリアス。エレキベースをギターのようにメロディアスに速弾きするなど、超絶テクニックで独創的なスタイルを創造、フュージョンの第一人者となったウェザーリポートに加わりフュージョンを開拓するなど、その後のベース奏者に多大なる影響を遺した。この演奏はライブ録音とは思えない、一糸乱れぬビッグバンドと、その上に浮遊するアナーキーなギターやハーモニカによる計算されたアドリブがカオスに陥らずに絶妙なバランスを保つ構成美が素晴らしい。それも音楽の軸にベースが鎮座しているためで、ここでは素直にベースに耳を傾け、如何にユニークな奏法と音楽の世界観を生み出しているのかを鑑賞したい。そして、凄腕ミュージシャン他ちを捉えた録音のクオリティーが素晴らしい。控え目で大人しい日本の観客の反応もあってか、演奏開始直後と最後に拍手が僅かに聞こえる位で、ほぼスタジオ録音に匹敵するノイズレベル。音にうるさいジャコが細かく口を出したのか、世界に誇れる録音技術レベルに日本が到達した証となった。このスタイルは、ジャコのインタビューから察するにR&Bやファンク、前曲のフランクシナトラといったポピュラーミュージックを、ベースから入らずに音楽全体とメロディーから捉えて、それをベースに置き換えるという工程を経て生まれたように考えられる。ベースプレイヤーだからベースから入る、という考え方では無いのだ。そして音楽をジャンルという概念に囚われずに自由に受け止めて取り込むのもジャコの天性で、結果としてジャズ、ロック、ファンク、R&Bがクロスオーバーする世界観を創り上げた功績は計り知れない。音楽を素で受け止めて、ベースで表現する自由な発想は文化が入れ混じるフロリダ育ちが影響していそう。ジャコ作曲で、曲名通り自由な人種のるつぼ的な多様な楽器が入り混じる音楽。レーベルはワーナー。音楽市場が拡大してエンタテイメント産業の一部として定着、音楽専用チャネルのMTVは、この前年に誕生している。
1984 “I Hear A Rhapsody”
by Chick Corea, Miroslav Vitous & Roy Haynes at Willisau & Reutlingen, Europe for ECM (Trio Music, Live in Europe)
演奏も音も明快でクリアな、コリアによるECMレーベルの本拠地、ドイツとその隣スイス録音で構成されたライブアルバム。三月の名盤トリオ作品が長きに渡って余韻を残して、16年の時を経て待望の再結成を果たし、ツアーに出た際の収録。前作では新進気鋭の緊張感みなぎる斬新な、個々が我が道を果てしなく突き進むスタイルで登場したが、今回は歳を重ねてリラックスした雰囲気の中で聴かせる音楽優先の協調的な音楽となった。トリオの復活には前年にキースがスタンダーズのアルバムをリリースした影響があるのかも。ECMらしく透き通る繊細感とリアリティを重視した録音。コリアの軽快なピアノに付かず離れず、予定調和の範囲内でアドリブを展開する溌剌としたヘインズとビトウスの絶妙な掛け合いが聴きどころ。フュージョンの先駆者たるオールスターグループ、ジャコも在籍したウェザーリポートで初代ベーシストを務めたのは伊達では無い。曲は、1940年に制作されて、翌年には三人の異なる歌手の演奏がトップ10入りする程のヒットを記録したポピュラーソング。録音場所のロイトリンゲンとヴィリサウは、チューリヒを跨いで車で約三時間の距離にある小規模都市。恐らく普段はクラシック音楽が演奏される由緒ある会場でのパフォーマンスでエコーが若干かかっているのが特徴だが、音響と録音が良いのは、演奏後の拍手喝采の響きで確かめられる。
20 & 21, 1989 “Theme For Ernie”
by Steve Khun, Miroslav Vitous & Aldo Romano at Ferber Station Studio, Paris, France for Owl (Oceans in the Sky)
前曲の五年後、引き続き欧州域内、Owlレーベルの本拠地、パリでのトリオ録音。欧州はジャズ低迷期でも根強い人気があるためか、電化の波に乗らずにレーベルがアコースティックジャズをコンスタントに送り出していく。ベースが前曲と同じビトウスだが、ピアノがアメリカ人のスティーブキューン、ドラムがイタリア人のアルドロマーノという組み合わせ。同じ欧州でもクリスタルクリアな前曲のECMに対して、本作は落ち着いた空気感と重厚感があり、ベースの弦やボディ、シンバルの鳴りと響き方を比べると違いが良く分かる。この曲は、41年前に録音されたコルトレーンの名盤『ソウルトレーン』での名演が際立っているが、これにオマージュする様に倣い心酔したように落ち着きのあるキューンの演奏も素晴らしい。加えてベースのビトウスのさり気無い伴奏も、意を汲み取ったメロディー優先のソロも心に沁みる。コルトレーンが気張らずにリラックスした状態でのバラードは、とても上手いし、味わい深く、その最たる例がこの曲の元バージョン。それはコルトレーンと同年生まれながら、その録音の前年に31歳で亡くなったアルトサックス奏者、Ernie Henryに捧げる曲だからかも知れない。そうした名演があり、何年経っても色褪せること無く、飽きられずにミュージシャンの心を惹きつけて、引き継がれるのがスタンダード化する要因の一つでもある。ドラムのブラシが撫でるように叩く姿が目に浮かぶシンバルの響きと振動を如何に長く再現出来るか、がオーディオ課題。
16, 1992 “Basin Street Blues”
by Keith Jarrett, Gary Peacock & Paul Motian at the Deer Head Inn, Pennsylvania for ECM (At the Deer Head Inn)
キースジャレットの故郷、フィラデルフィアにある同氏思い出のジャズクラブでの再演という企画。自身によるライナーノーツには、このクラブでスタンゲッツのギター伴奏をしたところ、スカウトされたとの記述があり、天才が認める天才は何をやっても凄いというエピソードと、その後にマイルスバンドに加わるチックコリアとキースまで発掘するスタンゲッツの目利きの凄さ。スタンダードトリオの同じくピアノやベースも流暢に弾きこなす天才のジャックデジョネットに代わって、ここではキースが影響を受けたビルエバンス最良のパートナーの一人だったポールモチアンがキースに寄り添ってシンプルに空間を重んじるドラムを叩いているのがミソ。月影に照らされて、ひっそりと佇むジャズクラブのモノクロのカバー写真が彷彿させる、虫の鳴き声が聞こえそうな初秋の雰囲気が録音から感じ取れるため、九月に通しで聞きたくなるアルバム。前々曲の反射の多い石造を彷彿させる硬い音場と異なり、適度に抜けの良い、どちら事いうと優しく音を吸収する木造の音響が、更にリラックスさせる要素か。その中でも、特にこの曲、慣れ親しんだ親密な環境だからか、キースのウニウニという唸り声が多い。傾向として、唸り声の多さと大きさに演奏の質が比例するという個人的な見解から言うと、本演奏は指折り。緊張感漲るキースが珍しくリラックスして音楽に没頭しているのが吉と出て、何度聞いても飽きない心温まる演奏となった。キースは幾つかブルースと名の付く楽曲の演奏記録を残しているが、そのブルースについて、この演奏から約五年後にウイントンマルサリスに噛み付いて論争を起こした事がある。曰く、テクニックがあって物真似がどれほど出来たとしても、心に訴えるものが無いのは芸術足り得ないと。その必須要素たるソウルとブルースを持ち合わせない象徴としてウィントンを名指しして矛先を向けた。曲がりなりにもジャズ不遇の時代もアコースティックジャズを続けて来た自負からすると、彗星の如く現れて注目を浴び、ジャズの復活に貢献した反動で、若くてチヤホヤされて天狗になった存在が神経質なキースには気に障ったのかもしれない。ここでのキースは、その発言を裏切らない、唯一無二の自発的に感情移入した独自の演奏を聴かせる。
【後記】
初秋の九月は、夏と秋のミックス的な季節感を感じさせる演奏と、ストーリーの軸は1962年のジャズ界の活況、特にその中でのエリントンとコルトレーンの共演に至る流れが軸となっている。従ってアメリカの特にニューヨークとニュージャージーに録音が集中しているが、日本、フランス、スイス/ドイツを含めることが出来た。日本では抜群の音響を誇っていた大阪のフェスティバルホール、そして由緒あるスイスのヴィリザウジャズフェスティバルの存在を初めて知った。
そのコルトレーンについては、当時、バラード系の大人しめの収録が多く、その心境が気になって仕方ない。間違いなくエリントンとの共演はその生涯のクライマックスのひとつのはず。この期間の迷いがあって悟りに至るのか、、、ドルフィーの存在というご指摘も頂いて、なるほど、と思った。ドルフィーが共演時にコルトレーンを凌ぐ演奏を繰り広げたから面食らって、どの方向に向かうべきか迷った、なんて事も十分にあり得る。
そして意図した事ではないが、ジャズボーカルが四曲といつもより多いのが九月の特徴。中でもシナトラの『ニューヨークのテーマ』は気分が高揚するので個人的なお気に入り。
横道外れ話で言うと、ジュニア/シニアとセシルマクビーの名前について触れてみた。
個人的には、出来事が二つ。一つ目は、NHKラジオ番組の「ジャズ・トゥナイト」の「名盤誕生日」の企画で、名前付きでリクエストが取り上げられたこと。
二つ目は、一週間のバルセロナ出張が入ったため、スペインから七時間遅れの日本との時差を考慮しながら掲載するという初の試みを行ったこと。残念ながら、出張中にジャズを聴く事は出来なかったが、ちょうど”Festival Jazz Barcelona”が始まったところで、滞在中に俳優でクラリネット奏者のウッディアレンのコンサートが催されていたので、今月はその写真を採用した。ユダヤ民族楽器的な位置付けのクラリネットを手にするとは、如何にもアレンらしい。因みにバルセロナ往路は、ロシア上空を避けてなんとアリューシャン列島をアメリカ大陸側から抜けて北極を通るという空路でした(以下)。平和の有り難みを身をもって感じた出来事でした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
