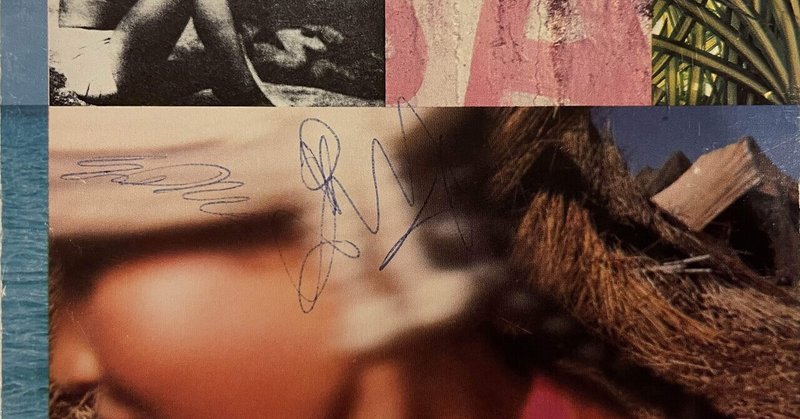
【プレイリスト】10月に聴く10月録音のジャズ
「October 神無月」オリジナル解説書(CD一枚分)
※1日単位「今日のジャズ/ジャズ記念日」の元ネタですが、録音年月日順で、記載内容も異なります
※選曲後記が最後にあります
※音楽を聴いてから解説を読む事をお勧めします
※録音日、曲名、演奏者、収録場所、レーベル、アルバム名の順で曲の情報が記載されています
26, 1956 “If I Were a Bell”
by Miles Davis Quintet (John Coltrane, Red Garland, Paul Chambers & Philly Joe Jones)
at Van Gelder Studio, Hackensack, NJ for Prestige (Relaxin’)
マイルス、30歳にして自らのスタイルを確立して量産体制に入った時期、僅か二日間で4枚を収録するマラソンセッションの一枚からの作品。録音ブース内部から「演奏した後で曲名を言うから」とマイルス独特のダミ声で、外側で待機するスタジオエンジニアに話しかけて指スナップでリズムを取ると、ピアノが八月7曲目と同様の「ウェストミンスターの鐘」のメロディーを裏拍子から弾き始めて、バンドがテーマに入るという粋な演出。マイルスがリーダーシップを発揮してバンドを引っ張る姿が窺えるが、バンドメンバーは分かり切ったかのように追随する。ソロがマイルスからコルトレーンにバトンタッチされるとマイルスの規律から解放されたかのようにバンドが更に躍動する。マイルスの緊張感と規律を促す睨みは相当怖いが、それがクオリティの高い演奏を生み出した要因の大きな一つである事は間違い無い。マラソンセッションとはいえ、同年の五月と十月の二回に分けて行われていて、四枚に分散する形で収録されているが、後者の方が明らかに演奏の質が高く、各メンバーの円熟味と演奏の場数が、多分に影響していると思われる。伴奏者の中でもベースのチェンバースのブレない躍動感に満ちた演奏は素晴らしい。曲はミュージカル『野郎どもと女たち(Guys and dolls)』の挿入歌で、この演奏からジャズのスタンダードとして定着して行く。リハーサル無く、ぶっつけで録音して、スタジオのやりとりまでリリースするのがプレスティッジらしさ。だからこそ短期集中録音が成立したと言える。
8, 1957 “Come Fly With Me”
by Frank Sinatra and Billy May Orchestra
at Capitol Recording Studios, CA for Capitol (Come Fly With Me)
この曲と収録されたアルバム名の「一緒に飛び立とう」の通り、世界中をシナトラの歌で仮想旅行する、という企画アルバムからの一曲で、今回の世界中の季節を味わう選曲と同じコンセプト。北大西洋ノンストップ便が就航し、海外旅行が身近なものになりつつあるタイミングでのタイムリーな企画アルバムでヒット。「80日間世界一周」や、「秋のニューヨーク」、「四月のパリ」、ロンドン、ブラジル、ハワイにまつわる曲で構成されている。シナトラとビリーメイオーケストラは相性が良く、このアルバムの商業的成功を受けて、ダンス楽曲編成の”Dance”と、ラブソングにまつわる”Swing”のタイトルで”With me”三部作が作られる事になる。このタイトルソングは、オリジナル曲でビルボード一位を記録、シナトラの代表的な持ち歌の一つになり、トムハンクスとディカプリオが共演した「キャッチミーイフユーキャン」の映画等に頻繁に取り上げられている。それまでバンド上位だった歌手との関係性をシナトラが覆して、バンドを指名して主導権を握るスタイルは当時としては画期的な出来事で、まさにパイオニア。遠慮の無いシナトラ中心の音楽進行となり、歌唱力と独特の歌の崩し方が存分に活かされているので高揚感がある。それだけシナトラは実力があり、売れていて発言力があった証とも言える。
10, 1957 “Pennies From Heaven”
by Stan Getz and the Oscar Peterson Trio (Ray Brown, Herb Ellis) at Capitol Recording Studios, CA for Verve (Stan Getz and the Oscar Peterson Trio)
1957年10月のキャピトルレコーディング第二弾。前曲から二日後、スタンゲッツとオスカーピーターソントリオが西海岸で合流して録音した終始気張らずに心地良く、清流の如くに活力みなぎるテンポで進行する上機嫌な演奏。同年七月にアームストロングと録音したオスカーピーターソンのバンド編成をドラム抜きとして、代わりにハーブエリスのギターがパーカッシブなリズムを刻むのが音楽としてもオーディオ的にも聴きどころ。ゲッツによる止めどなく溢れ出る明朗なアドリブメロディーを主軸にして、高度ながらさりげなく軽々と追随して変幻自在に演奏していく各伴奏者のアドリブが素晴らしい。特にゲッツに躍動感を持って寄り添う楽しげなピーターソンのピアノは名人芸の域。そこにギターが終始さりげないビートを刻み、ベースが歩調を合わせてスイングして盛り立てるとなるとゲッツもさぞかし気分良く演奏できただろう。大作詞家ジョニーバークが手がけた同名の映画のタイトル曲でビンググロスビーが原曲を歌った。
17, 1957 “Makin’ Whoopee”
by Ben Webster, Oscar Peterson, Ray Brown, Herb Ellis and Stan Levey
at Capitol Recording Studios, CA for Verve (Soulville)
前曲から更に一週間後、西海岸に留まったであろうオスカーピーターソントリオが、1940年代から活躍した数少ない白人ドラマーの一人で、チャーリーパーカーやマイルスとの共演歴がある実力派のスタンリービーを加え、エリントン楽団で花形演奏者を担ったモダンジャズテナーサックスの開祖の1人であるベンウェブスターの伴奏に回り、前曲と同じくキャピトルスタジオで録音したのがこのアルバム。同じテナーとレーベルでも、若手の有望株のゲッツから実績十分な貫禄ある大御所テナーに入れ替わって、新旧テナーのスタイルの違いは勿論、伴奏者が前曲の同年代でイケイケでハッピーなパーティースタイルから転じて、控えて主役に敬意を表する黒子に徹するところも対照的。ウェブスターは、演歌で言うとコブシを利かせるソウルフルなスタイル。一方のゲッツは、ウェブスターと比肩されるレスターヤングのスタイルを踏襲したブローのコブシが少なくクールな華やかさ。前曲と比較すると同じスタジオながら、印象がこれ程変わるのは、プロデューサーの意図と演奏者の相性が反映されての事だろう。大手で老舗のキャピトルレコードは、本社の地下駐車場スペースに録音スタジオを擁したが、ここまで三曲続けて同スタジオの収録。円盤が積み重なったようなユニークな建物だが、この円盤がレコードをモチーフにしていると分かると合点がいく。結婚を題材にしたミュージカル向けに作られたこの曲は、スタンダードを超えてポピュラーソングとなっており、エルトンジョン、ロッドスチュアートやシンディローパーにもカバーされている。
30, 1958 “Harlem’s Disciples”
by Art Blakey, Lee Morgan, Benny Golson, Bobby Timmons & Jimmy Meritt
at Van Gelder Studio, Hackensack, NJ for Blue Note (Moanin’)
テクノロジーの進化と共にSPからLPが生まれてレコードの再生時間が延長されると、それまで一曲3分程度のSPが、LPでは片面20分を超え、そこからアルバムという複数曲から構成される楽曲のコンセプトが生まれるようになる。この曲はジャズの名盤、「モーニン」に収録されたドラムサンダー組曲という本サックス奏者のベニーゴルソンによる三部構成曲の締め括りの第三部で、当時の飛ぶ鳥を落とす勢いのバンドの活力に満ちた演奏を聴くことが出来る。ブレイキーの音楽と演奏の両面における統制の行き届いたリーダーシップから叩き出される、聴衆の体を無意識に揺さぶらせてしまう強靭でタイトなリズムに乗って、先鋒トランペッターのリーモーガンが鮮烈なソロで心を鷲掴み、1:18からの急展開において、ドラムのリズムに触発されたかのように軽やかに弾むボビーティモンズのスリル感に満ちたぴの旋律が格好良い。僅か三分足らずで音楽の構成と演奏力、それを牽引する力強いドラムで強烈な印象を残すブレイキーの演奏は何度聴いても素晴らしい。
9-10, 1959 “I Concentrate On You”
by Abbey Lincoln, Tommy & Stanley Turrentine, Julian Priester, Ray Bryant, Bob Boswell & Max Roach at Universal Recording Studios, Chicago for Mercury (Moon Faced and Starry Eyed)
シカゴ生まれのこの歌手は、アメリカ初代大統領のエイブラヒムリンカーンの名前を拝借して、アビーリンカーンと名乗り、女優としても活躍した。本ドラマーのマックスローチの作品に参加、その後伴侶となり、公民権運動に関わった影響か、黒の衣装を身に纏った写真が多く残されている。ボーカリストとしては、力強い芯のある歌声が特徴。出だしにおいて、右からドラム、左からピアノという配置による展開が視界が開けるようなステレオ感。ローチの「チーチキ、チーチキ」というライドシンバルのレガートに乗って、ボーカルを引き立てるように絡み付くようなメロディーをタレンタイン兄弟がトランペットとサックスで奏でる。トランペットの後、軽快なソロを取るのが、エリントンからパットメセニーまで、幅広く息長く活躍したトロンボーン奏者のジュリアンプリースター。そして端正なピアノのレイブライアントの伴奏もキレが良くローチのドラムとの相性も良い。フレッドアステア主演ミュージカル映画、”Broadway Melody of 1940”用にコールポーターが、スタンダード曲となった”Begin the Begine”と共に提供した。
14, 1960 “Just In Time”
by Lee Morgan, Clifford Jordan, Eddie Higgins, Art Davis & Art Blakey
at Universal Recordings, Chicago for VeeJay (Expoobident)
前曲同様にシカゴ録音なのは、同地における黒人夫妻のレコード店から拡大して立ち上げられたレーベルのビージェイだから。このレーベルはジャズというよりは黒人向けのありとあらゆる音楽を世に送り出した。前々曲リーモーガンの生命の息吹を感じさせるキレの良く、ファットトーンと形容されるふくよかな音色が心地良い。録音的にはマイク近くで演奏するも、微妙にエコーがかかっているのも心地良い要因の一つ。リーモーガンとアートブレイキーを除き、シカゴ拠点のミュージシャンが伴奏を務め、懐の深い鳴りのするアートデイビスのベースのスイング感も心地良く、ピアノのエディヒギンズのピアノも勢い良く短く纏めあげる美学を感じさせる。何処かで聴いたことがあると思いを巡らせると、トランペットは、ウイントンマルサリスのスタイルが酷似。実は二十年以上前に、今聴いても新鮮で時代を感じさせない完成度の高い型が出来上がっていた。アートブレイキーは数あるミュージシャンを発掘・育成したが、トランペッターとしては、初期にこのリーモーガンを、晩年期にマルサリスを擁したので、脈々と引き継がれるジャズメッセンジャーズの歴史の中で、間接的に影響が及んでいるのかも知れない。後半のベースとのデュオの部分も聴いていて体でリズムを取りたくなるような幸せ。
20, 1960 “For Heaven’s Sake”
by Tina Brooks, Blue Mitchell, Kenny Drew, Paul Chambers & Art Taylor at Van Gelder Studio, Englewood Cliffs, NJ for Blue Note (Back to the Tracks)
前半、陰影のあるマイナー曲が似合うテナーのティナブルックス主導のゆったりした内省的なメロディーで、まったり進行しつつ、2:24からスイング感が加速、3:29にブルーミッチェルが場違いな位の明るいトランペットで登場して、その派手で力強いトーンと音運びから、全体の歯切れが良くなり、突如として迷いが晴れて道が開けるような流れが面白い。ムードメーカーが試合をひっくり返すかのような展開で、主役のテナーですら影響を受けるかのように後半のトーンが明るめに転じ、両者が絡むと合わせ味噌のような絶妙なバランス。ミッチェルは、アートブレイキー同様に若手有望株を多数輩出したホレスシルバーのバンドの出身。前曲6日前録音のリーモーガンとの比較で言うと、音色に煌びやかさがあるのが共通点か。垢抜けた明るさや、後にファンクやフュージョンも手掛けた柔軟性は、フロリダ州マイアミ出身というバックグラウンドの影響か。5:28にドラムが止まると、物足りなさを覚えるのは、如何に地味ながら進行において燻銀のアートテイラーが存在感を示していたという証。ビリーホリデーが歌った事で脚光を浴びてスタンダード化した。曲名の和訳は「(一生の)お願いだから」。
24, 1960 “Body and Soul”
by John Coltrane, McCoy Tyner, Steve Davis & Elvin Jones at Atlantic Studios, NYC for Atlantic (Coltrane’s Sound)
前曲から更に四日後、同じニューヨークながら別のレーベルとスタジオ録音。冒頭のベース音程の違和感と、それを加速するマッコイ特有のパーカッシブなピアノのテンションが高く不協和音スレスレ感が新鮮な響きの伴奏。コルトレーンの名盤の一つ、マイフェイバレットシング(JRの「そうだ、京都へ行こう」CM曲)を彷彿させるのは、同セッションの録音だから。にも関わらず、この曲は見送られて四年後に発表されている。コルトレーンは常に新たなスタイルを求めて探求し、それを他メンバーが追随することで極みの領域に達したという。その極地の一つがこの演奏で、原曲を重んじながらも新たな曲のような斬新なアレンジを加えて、コルトレーンならではの作品に仕立て上げ、一度聴いたら頭から離れない鮮烈さ。一般的には下からソロイストを支える伴奏、特にピアノのバッキングが挑戦的に斜め上から降って来て緊張感を醸し出しているのが画期的。コルトレーンは、音楽及びメンバーを毎回試行錯誤する事で、常にスタイルを磨き上げたとの事。演奏のコンセプトが固まるとメンバーも厳選するようになり、この後、エルビンジョーンズの力強さに引きずられる事なく応えられる芯と安定感を兼ね備えたベーシストを模索、この曲のデイビスからレジーワークマンを経て、ジミーギャリソンに入れ替わり、所謂「黄金のカルテット」が完成、孤高の境地に突き進む。七曲後のアルバムにも同曲が収録されているように、秋の夜長に相応しいイメージのこの曲は、ミュージカル曲を、アームストロングが取り上げてからスタンダード化して行くが、その録音も1930年の10月、その後、テナーの開祖の1人コールマンホーキンスによるビバップの先駆け的な録音も1939年の10月という記録が残っている。これこそまさに、秋にしっくりくる音楽。そしてこの曲がジャズスタンダードランキングで栄誉ある一位となっている。
16, 1961 “Manteca”
by Phineas Newborn Trio (Paul Chambers, Philly Joe Jones) at Contemporary Records Studio, LA for Contemporary (A World of Piano)
ピーターソンに引けを取らないテクニシャン、西海岸に拠点を置いたフィニアスの絶好調な演奏。マイルスのリズム隊、ベースのポールチェンバース、ドラムのフィリーリージョーンズと共に西海岸録音という企画は、アートペッパーの名盤と同様の”Meet The Rythme Section”と言える。フィリーがコンテンポラリーだとリズムが明快に録音される。シンバルの鳴りは前月二曲目との比較で顕著なように、タイトで音場の幅の広がりがあるワイドレンジな「横」のコンテンポラリーに対して、重く厚みのある凝縮された押し出し感のある「縦」のブルーノート。オーディオ的には、この二者択一の究極の選択を迫られ、とらえたエネルギーをどう鳴らすかは、好みが分かれるところ。端的に言うと、視界を開きたいか、遠くまで見通したいか。1:17からのフィニアスの両手高速フレーズは一体どうなっているのか理解に苦しむ程の難解さ。そして1:50からの「タラララ、テレレレレレ」のフレーズを随所に登場させるユーモア。その後ろでボクシングのワンツーのように畳み掛けてコーナーに追い詰めるがの如くのドラムのフィリー。負けじと和音の高速フレーズで押し戻すフィニアス。ここまで来ると肉弾戦の様相だが、本人達は嬉しそうに笑顔で演奏しているのだろう。最後のテンポの不協和音はフィリーの遊び心。作曲はディジーガレスピー、ジョンレノンによると、この曲に触発されて作られたボビーパーカーの”Watch Your Step”(1961)をビートルズでカバーして、ビートルズの”I Feel Fine”と”Day Tripper”のモチーフにしたとのこと。本曲の孫として捉えると確かに似ているかも知れない。
5, 1962 “Liebesträume”
by Ike Quebec, Kenny Burrell, Wendell Marshall, Willie Bobo & Garvin Masseaux
at Van Gelder Studio, Englewood, NJ for BN (Soul Samba)
誰しもが聞いたことがあるはずの馴染みのある、この曲を当てるのは結構難しい。クラシックでは、耽美で背筋が伸びるような緊張感を持った印象の曲だが、ここではリラックスした、なんとなく懐かしさと親しみを感じさせる演奏となっている。如何にもブルーノートの特徴的な中低音主体の録音で、テナー本来の生々しさと深みがケベックのトーンの優しさと渋さと相まって、秋の情景が目に浮かぶ。「横」と「縦」の話で言うと、前曲の視野が広けた印象から、この曲になると視界は狭まるものの正面の見通しが開ける感じ。ブルーノートレーベルの影の立役者、ケベックは、演奏のみならず、モンクをはじめとする有望なミュージシャンの紹介、そしてスタジオ送迎のドライバーなど、ブルーノートに多大なる貢献をした。前月のジャズの歴史的録音ラッシュの翌月の録音で、この頃にはジャズの多様化が進んでいる事が分かる。曲の正解は、ほのぼのとしたリラックスした雰囲気のボサノバ調ながら、なんとあのクラシックの大家、フランツリストの有名曲「愛の夢」。どちらかと言うとテンション高めの曲調を、さりげなく演奏し切る発想と柔軟性は、まさにジャズの本領発揮。クラシック曲をジャズで、しかもボサノバ調で演奏する発想に天晴れ。
1964 “Limehouse Blues”
by Joe Pass, John Pisano, Jim Hughart & Colin Bailey at Pacific Jazz Studios, Hollywood, CA for Pacific (For Django)
英国作のスタンダードは、第二次世界大戦前にロンドンに実在したチャイナタウン、Limehouse地区での物語を題材としたもの。ここでは活力と勢いに満ちたジョーパスのリズムカルなギターが楽しめる。ノーマングランツに見出されたパスはこの曲を好んで演奏していたようで、ジャズのソロギターアルバムの金字塔となっている、”Virtuoso”の二作目にも登場している。アルバムの名前の通り、映画にもなった伝説的ジプシージャズギタリストのジャンゴラインハルトに捧げられた作品。ジャンゴがバイオリンのステファングラッペリと共に二本のリズムギターとベースを伴奏として五重奏団を組んで、この曲をレパートリーとしていた事を受けて、同曲をリズムギターを従えて録音したものと推測する。パスがベースとデュオで切れ目無い「テロテロテロテロ」と快活な高速フレーズでリードを取ると、伴奏ギターとドラムが加わわって、粋な間合いで演奏を加速させ、曲を通して速い展開ながら手を替え品を替え刺激を与え続けているのも聴きどころ。パスによる0:54の「キュイーン」フレーズと1:20からの和音攻めは、典型的なジャンゴ奏法。レーベルのパシフィックは、ロスアンジェルスで設立されて名前の通りウエストコーストジャズを白人主体で牽引した。
20, 1964 “You Look Good To Me”
by Oscar Peterson Trio (Ray Brown, Ed Thigpen) at RCA Studios, NYC for Verve (We Get Requests)
曲良し、演奏良し、録音良し、という三拍子揃った記録の中でも、最高峰の一枚に挙げられる、オーディオチェック用の定番楽曲。「縦」と「横」のバランスが高次元でバランスしているからで、冒頭のベースの弓弾きのふくよかさ、トライアングル、ドラムのシンバルやスネアの響き具合でオーディオ機器の実力や特性が推し量れる。ここで惜しみない力を発揮しているベースの権化の一人、レイブラウンは、走り過ぎて手数が多い傾向のあるピーターソンに対して先回るアンカーのような演奏をする事で手綱を引き、聴き手にとって最適なバランスを保つという、単なるベーシストを超えた音楽監督的な役目を果たしているかのよう。ペンシルベニア州のピッツバーグ出身で、双璧のベースの名手、ポールチェンバースも同郷。同州のフィラデルフィアからも、本シリーズに登場しているジミーメリット、アートデイビスに加えて、コルトレーンに起用されたスティーブデイビス、レジーワークマンとジミーギャリソン、第二世代のジャコパストリアスやスタンリークラーク、近年ではクリスチャンマクブライドと、一流のベーシストが誕生したり育った地でもあり、理由を探りたくなるほど。因みに録音当時は東京オリンピック開催中で、翌日に「裸足のアベベ」がプーマの靴を履き、マラソンで金メダルを獲得している。
20, 1966 “Mercy, Mercy, Mercy”
by Cannonball Adderley, Nat Adderley, Joe Zawinul, Victor Gaski & Roy McCurdy
at Capitol Studio, LA for Capitol (Mercy, Mercy, Mercy! Live at “The Club”)
マイルスの名盤に参加したアルトのキャノンボールアダレイは、この曲に代表されるソウルジャズを開拓する。曲の冒頭での本人によるアナウンスは、エレキピアノを演奏するジョーザヴィヌルの作曲という紹介と、その曲に託されたストーリーを語る。聴衆の掛け声が混じるライブ調ながら、実はキャピトルスタジオでのラウンジ風仕立てのな録音との事。ザビヌルはこの後にマイルスに引き抜かれ、その後に一世を風靡したウェザーリポートを結成する。この曲は万人受けするメロディーが受けてジャズとしては異例のビルボードチャートの11位にランクインした。冒頭のアダレイのコメントは以下。
You know, sometimes, we are not prepared for adversity. When it happens sometime, we are caught short. We do not know exactly how to handle it when it comes up. Sometime we do not know just what to do when adversity takes over. And I have an advice for all of us. I got it from our pianist, Joe Zawinul who wrote this tune. And it sounds like what we are supposed to say when you have that kind of problem. It’s called “Mercy, Mercy, Mercy”.
簡単に言うと「逆境に直面したら、神に御慈悲を唱えなさい」というようなアドバイス。公民権運動とベトナム反戦デモがピークを迎えた動乱の情勢を意識しての楽曲なのかも知れない。終始、黒人訛りの掛け声がかかるが、音楽に即座に反応するタイミングが絶妙で音楽の一部に溶け込んでいる。キャノンボールは激しくファンキーにブローするものの、割り切ってかアドリブは殆ど無い。2:51から始まるベースと味わい深いトーンのウーリッツァーエレキピアノのゆったりとした絡みが、大きく押し寄せる波のようなノリを醸し出していて心地良い。ウーリッツァーを使用した録音の先駆けで、この後にクイーンの”You’re My Best Friend”やピンクフロイドの”Money”等にも登場する事になる。
30, 1978 (also Oct. 31; Nov. 1, 2) “Blue and Green” by Bill Evans, Larry Schneider, Toots Thielemans, Marc Johnson & Elliot Zigmund
at Columbia Recording Studios, NYC for Warner Brothers (Affinity)
エバンスがハーモニカのトゥーツシールマンスを迎え、ポールサイモン等のポピュラーソングをエレキピアノを交えて駆使し、モダンなスタイルで披露する。楽曲、ハーモニカとピアノの組み合わせが秋の雰囲気にピタリとハマる。シールマンスのメロディーセンス、表現力と音のふくよかさによる貢献は、エバンスに引けを取らず、素晴らしい。エバンス晩年のベーシスト、マークジョンソンのデビューアルバムだが、臆せずに登場時から正確なテンポで高度なベースラインを刻んでいる事が分かる。音質は今ひとつながら、秋の夜長にしっぽりと聴きたくなる、味わい深い哀愁に溢れたアルバムの一つ。曲はエバンスが参加しているマイルスデイビス屈指の名盤、”Kind of Blue”に収録されている”Blue in Green”で、そこではマイルス作曲とのクレジットも、エバンス自身によると自らが作曲との話。印税をマイルスに回すための紳士協定があったようだが、同年に自身のトリオでマイルスとの共作楽曲とクレジットして収録、本アルバムでは”Blue And Green”と曲名を変更してまで収録としている経緯を見ると、著作権を巡る複雑な事情があることが窺える。
1976 “Teen Town”
by Weather Report (Joe Zawinul, Wayne Shorter, Jaco Pastorius & Alex Acuna)
at Devonshire Sound Studio, North Hollywood, CA for Columbia (Heavy Weather)
前々曲を作曲、演奏したオーストリア人のジョーザヴィヌル率いる実力者揃いで構成された「ウェザーリポート」による天才ベーシスト、ジャコパストリアス作曲作品。当時最先端のシンセサイザーを利用した、近未来的なワクワク感に満ちた作風。アルバムではラジオやテレビで頻出の名曲、”Birdland”に続く短い二曲目で、まさにアルバムの展開を司る、三分弱の繋ぎの一曲。ジャコのベースにタイトなドラムとパーカッションが追随し、ザビヌルのシンセサイザーが浮遊しながら調和、その上にウェインショーターの虚無僧ソプラノサックスが舞い踊って疾走する。これだけのスピードを見事なリズム感で揃えられるのは実力者揃いといえども容易ではないはずだが、当時のビデオを見るといとも簡単にこなしているように見える。唯一演奏において、タイトなリズムに縛られない印象のショーターであっても、このリズムにピタリと合わせて揺らぎと人間味のある味わいを加えるという芸達者さ。短い曲ながらスリリングな展開が凝縮。因みにジャコもマイルス同様にリアルな三世。三世まで続くと才能が開花する確率が高いのかも知れない。シンセサイザーのタッチが若干ワンテンポ遅れてやってくるのが当時のテクノロジーの限界のような気もするが、これがまた機械的では無い、良い意味でのアナログ加減の個性と風情を生み出している。
1981 “Are you going with me?”
by Pat Metheny Group
at Power Station, NY for ECM (Offramp)
フォーキーな楽曲で前曲のジャコを起用したトリオによるデビューアルバムを発表してから5年、グループを組み、所謂ノリの軽い耳心地の良いフュージョンとも異なる、音楽を聴くと情景が目に浮かぶ映画のようなストーリーテラースタイルの音楽で、ブレずに音楽を進化させ、ファンを着実に増やし、遂に本作でグラミー賞を初獲得する。目玉がこの曲で、繰り返される「タッタ、タッタ、タタッタ」のリズムに乗って、当時としては最新鋭のギターシンセサイザーを駆使した哀愁に満ちたソロが展開される。メセニーは、今でもこの曲をライブのレパートリーとしていて、その際には必ずギターシンセサイザーを持ち出して熱演している事から、頭の中で一般的なギターでは無い音色と音作りのイメージが出来上がっているのだろう。もう一方のキーボードのシンセサイザーも、前々曲からの流れを汲みつつ、トランジスターの進化の恩恵を受けてエレキピアノから発展を遂げていて、これまでに無い音楽の味付けとなっている。アルバムジャケットは、”TURN LEFT”の印象に残るオレンジ色の道路表示。スタジオに篭って長期間に亘って緻密な作品作りをするメセニーだが、本作は10月録音と明記されていて、感受性の強いメセニーだけに秋の到来と深まりを感じさせるアルバム。日本でもテレビ番組やラジオでも度々BGMとして採用されている。ジャズの新たな潮流の一つ。
【後記】
何処からどのように貰ったのか全く分からないが、遂に新型コロナに感染してしまった。八月の帯状疱疹の発症から免疫力の低下の兆候はあったが、まさか自分が、というのが実感。幸いにも症状は軽く、微熱、倦怠感と喉の痛みが十日程続き、ある程度治ったものの、咳と痰の絡みが感染から三週間過ぎた今でも残っている状況。咳が始まると止まらないので、早く治って欲しい。
さて、比較的暖かい今年の10月ながら、秋の夜長に合わせたしっぽりとした曲と、その合間に繋ぎの口直し的なリフレッシュする曲を挟んだ構成。ブレイキーの”Harlem’s Deciples”とウェザーリポートの”Teen Town”が短い曲ながらスパイスとして効いている。
地域的にはアメリカ中西部最大の都市、シカゴとフィラデルフィアを取り上げてみた。シカゴは大都市だけあって、ミュージシャンの数がそもそも多いのと、フィラデルフィアは優れたベース奏者を多数輩出している点について触れてみた。
時代的には1957年のキャピトルスタジオ録音の三作からハリウッドの当時の充実したジャズ業界を窺う事が出来る。一方、1960年収録の三作は曲調がまるで異なるのが印象的。この辺りでモダンジャズはハードバップが成熟の域に達してモードジャズ等に多様化して発展して行く兆候が読み取れる気がする。
そしてウェザーリポートやパットメセニーグループといった八十年代を象徴する演奏の紹介は今月にして初となる。純ジャズも良いが、八十年代の華々しいステージを彷彿とさせる楽曲にもまた良さがある。
表題の写真は、その紹介曲でも触れた、その80年代を代表するパットメセニーの名盤、”Still Life”のメセニーとライルメイズのサイン付きアルバムジャケット。サインを貰ったのは秋頃の公演かと思っていたら、実際には二月だったので、自分の季節感の感度の疎さを改めて思い知らされた。
今月もお付き合い、どうも有難うございました。11月も宜しくお願いします!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
