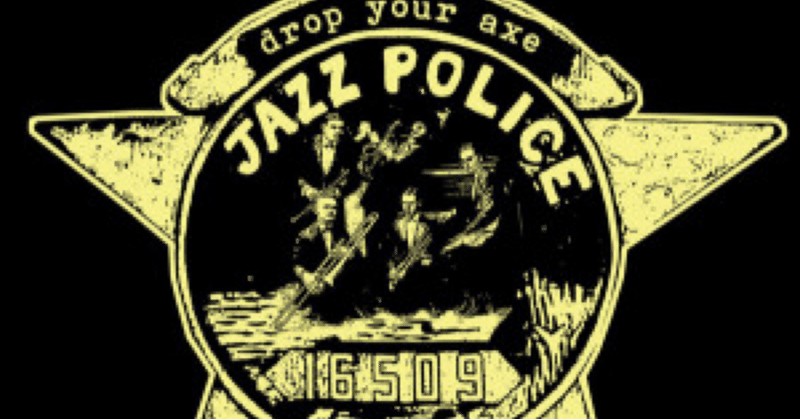
【プレイリスト】11月に聴く11月録音のジャズ
「November 霜月」オリジナル解説書(CD一枚分)
※1日単位「今日のジャズ/ジャズ記念日」の元ネタですが、録音年月日順で、記載内容も異なります
※選曲後記が最後にあります
※音楽を聴いてから解説を読む事をお勧めします
※録音日、曲名、演奏者、収録場所、レーベル、アルバム名の順で曲の情報が記載されています
23, 1955 “The Theme”
by Jazz Messengers (Art Blakey, Kenny Dorham, Hank Mobley, Horace Silver and Doug Watkins) at Cafe Bohemia, NYC for Blue Note (At the Cafe Bohemia, Vol. 1)
ブルーノートレーベルのハードバップスタイルの型は、その誕生間も無い頃から確立していた事が分かる貴重なライブ録音。迫力あるドラムを口切りに予め構成された主旋律から始まり、コードに沿った各メンバーのアドリブソロが続き、ベースとドラムソロと掛け合いを経て、主旋律に戻って終焉するジャズの大定番の型は今から約65年前に発明され、今でも主流として定着している。各メンバーのソロの間に、カンカン、キンキン、ドコドコ、バシーンと、不規則なアドリブで喝を入れ、疾走感を生み出すスタイルはアートブレイキーの本領。独学でドラムを習得したためか、従来の枠組みに縛られずに新たな奏法を生み出して現代に連なるジャズドラムの基礎を築いた。今や一般的に普及しているドラムセットは、アメリカの産物で、その過程にジャズがある事が判明している。南北戦争が終焉した頃に普及していたマーチングバンド音楽では、打楽器はクラシックのオーケストラ同様に一人一楽器担当だったが、それを一人で複数演奏出来るように、空いていた足に着目する所から始まる。先ずは大きなバスドラムを地面に設置し、右足に担当させて叩く事で両手と共に二つの打楽器の演奏が可能となった。そしてジャズの初期の時代にシンバルを上下に合わせて、進化したペダルによって両者を足で操る発明が組み合わされて出来上がった。このハイハットは、一説によると、打楽器演奏者が足でリズムを取る動きを見た観客が、その足の間にシンバルを挟むという発想から生まれたらしい。ブルーノートの型も、この時点で完成されている。それは、創設者ライオンの耳による企画とクオリティーの維持、ルディバンゲルダーによる図太い録音、フランシスウルフによる写真と、それを活用した後にリードマイルスが手掛けるジャケットデザインの組み合わせで構成されている。
3, 1957 “Softly, as in a Morning Sunrise”
by Sonny Rollins, Wilbur Ware & Elvin Jones
at The Village Vanguard for Blue Note (A Night at the Village Vanguard)
ニューヨークの名門ジャズクラブ、ヴィレッジバンガードでの数あるライブ録音の記念すべき第一作目が、このアルバム。ライブ録音は、実はテクノロジーの進化に支えられて実現している。巨大で持ち運び不可だった録音機器が技術の進歩で持ち運び可能となり、ドラムの音の増幅が不要な100人も入れば一杯になる会場でも録音が可能となった。唸り声と共に鬼気迫るエルビンの煮えたぎるヤカンのような圧のあるドラムと、メロディーとリズムで主導権を握る勢いのアグレッシブなベースの力強いビートで、これ程までにも後ろから煽られても流されずにマイペースを貫いて朗々と吹き上げるロリンズの凄さ。このトリオは、コードに縛られてしまう制約を嫌ってピアノを排除して、自由度が高い演奏を狙ってのものだが、それだけに一人一人に音の重みがのしかかる。三月の一曲目が、同年、同じトリオフォーマットでのロスアンジェルス録音と同様だが、朗らかでユーモアに溢れるムードとは打って変わって遊びの隙が無いシリアスな極致で、曲名の「朝日のようにさわやかに」とは対極の「日没のように陰鬱に」の様相。名門ジャズクラブで遠慮すること無くその場の流れに沿うアドリブで対峙する三人が紡ぎ出す音楽、これこそ、まさにジャズ。
18, 1957 “Since I Fell for You”
by Lee Morgan Quartet (Sonny Clark, Doug Watkins, Art Taylor) at Rudy Van Gelder Studio, Hackensack, NJ for Blue Note (Candy)
前曲から15日後、音色、スタイル、メロディーも格好も、どれを取っても華々しいトランペットのリーモーガンを渋い伴奏者が固める。本録音時19歳と若くして成熟していて、迷いなく無く吹き切るモーガンの堂々たる演奏は4:30にハイトーンからの崩しでクライマックスを迎える。ピアノのソニークラークの目立つことの無いが、これ誰だろうと興味を抱かせる不思議な個性はここでも発揮されている。ブルーノートのアルバムで聴いたことが無くて気になるピアノは大抵の場合、ソニークラークだったりする。冒頭での重量感あるベースメロディーと共にゴーン、と響くドラム、シャキッと鳴る右スピーカーからのハイハットの演出が、マイナーからメジャーに転ずる音楽の展開と共にドラマチック。前月もさながらの豊作な1957年、同時期を過ごされた諸先輩方が羨ましい。
14, 1958 “Reflection”
by Roy Haynes Trio (Phineas Newborn, Paul Chambers) at Rudy Van Gelder Studio, Hackensack, NJ for New Jazz (We Three)
ジャズの初期から90歳を超えてまで演奏を続けたロイヘインズは軽快でキレの良さが全面に有りつつも、捉え所のない変幻自在なリズムと、シンバルの響きの美しさが特徴。黒人清音派の代表格。それを象徴するかのような、シンバルを叩いた直後に素手で押さえる事で、キレのあるバシバシとしたリズムから始まり、軽やかで変則的に入れ替わるビートと、ハイハットの快活さが颯爽としていて心地良い。軽快さ、瞬発力とキレという意味ではフィリーと同系統だが、粘り気が少なく洗練されている上品さがあるのが特徴。ピアノのフィニアスはドラム好きなのか、ドラマーから好かれていたのか、このヘインズの他、フィリー、エルビンとのトリオ作品もあり、前月の演奏でのフィリーとの演奏を比較すると、それまでは認識出来なかったドラマーの個性が明らかになり、新たな発見がある。これがジャズの飽きない面白さ。捉え所のない変幻自在なリズムを歌を歌うかのように繰り出し続けるヘインズの創造性とテクニックの高さを堪能したい。
16, 1958 “I Can’t Give You Anything But Love” by Sonny Clark, Jymie Merritt & Wes Landers at Rudy Van Gelder Studio, Hackensack, NJ for Blue Note (Blues in the Night)
前曲から二日後、また別のピアノトリオがルディバンゲルダースタジオで収録。若干篭りがちな粘りのある重めのタッチでゴロゴロと弾くという、ソニークラークのトーンに特徴はあるものの、演奏スタイルそのものが、オーソドックスなために、ブルーノートのハウスピアニストとして起用されながら、記憶に残らない事に起因しているのかもしれない。メジャーな明るい曲でも、演奏に何処か陰が付き纏うのが特徴でもあり、これが本国アメリカとは異なり、日本での高い人気に結びついていて、それは、このアルバム名となっているブルースによるものなのかも知れない。2:18からのメロディーは、他曲”Walkin’”から引用と思われ、ドラムが心得たかのように、それに追随する。アドリブの大半は他の曲やイディオムと呼ばれるフレーズの塊で構成されている場合が多く、ジャズには、この元ネタを探すという楽しさもある。モダンジャズの開祖、チャーリーパーカーは、ポピュラーソングからクラシックまで、イディオムを相当数持ち合わせていて、それをコード進行に合わせて瞬発的に使い分ける事で超人的な演奏を行っていたという研究もある。
13, 1959 “My Ideal”
by Kenny Dorham, Tommy Flanagan, Paul Chambers & Art Taylor at Rudy Van Gelder Studio, Englewood Cliffs, NJ for Prestige (Quiet Kenny)
十一月第一曲目に登場したトランペッター、ケニードーハムによるアルバム、その名も邦題「静かなるケニー」。打って変わってアルバム名を象徴するような終始リラックスしたムードの内容。リーダーとなってマイペースに自らの表現に徹しているからか、伴奏者も、それを慮ったかのように同調して寄り添い、控えめなトーンと手数で心情的に和ませてくれる優しさがある。リーダーの雰囲気をさり気なく掴み取り、違和感無く同化する凄みは、主張の少ない名サイドマンが結集しているから。しっとりと流れを作るベース、控えめながら気の利いたピアノのバッキング、これらは一曲まるまる耳を傾け続けてみると、その名人芸の凄さが分かる。そして何よりも、右スピーカーから終始流れる、なんでも無いような地味なドラムのブラシの音、最後に途切れると虚無感を覚え、それまで心にお落ち着きを与えていたという、存在感の大きさに驚きを覚える。これもまた偉大なる職人芸の形の一つ。1930年公開の「パリのプレイボーイ」の主題歌がスタンダード化したもの。
2, 1962 “Monk’s Dream”
by Thelonious Monk Quartet (Thelonious Monk, Charlie Rouse, John Ore & Frankie Dunlop) at Columbia 30th Street Studio, NYC for Colombia (Monk’s Dream)
モンクは崩しと揺らぎの人。リズムや和音を意図して変則的に崩して印象を残すが、それは独自のタイム感があって、揺らぎとして表出する。その揺らぎの最たる例が、シングルトーンで不規則に叩く、0:31からの表現で、子供がおもちゃのピアノで実験するかのような遊び心がある。ここでは、リーダーとなったモンクの意を汲んだメンバーの伴奏が極み。鬼才の尋常ならぬ外し方、崩し方、間合いの入れ方、モンクの全てを理解して、型にはまらない、そして遠慮しない伴奏が素晴らしい。モンクが外して裏を行くとして、その更に裏を行ってバランスを取る事でモンクの世界観を創り出せるのは、並々ならぬモンク愛があるからだろう。例えば、モンクのピアノを前提に上下にモンクの裏リズムで合いの手を打つドラムとの高度なやりとりは熟練の技で、特にピアノソロにおける両者の音楽的な対話は、本人達は単に遊んでいるだけかも知れないが、唯一無二の凄みがある。オルガン奏者、ラリーヤングの1966年11月録音”Unity”のアルバムに収録されていた曲を採用したくて相当迷ったが、作曲者によるオリジナル演奏には残念ながら及ばず、次点とした。
1965 “Walk On By”
by Gabor Szabo, Richard Davis, Sam Brown, Sadao Watanabe, Gary McFarland, Francisco Pozo & Grady Tate at Rudy Van Gelder Studio, Englewood Cliffs, NJ for Impulse! (Gypsy ’66)
不思議なヨレヨレトーンによるギターが印象的で、それ程美味しくもないのに三ヶ月に一回、理由も無く食べたくなるような町中華のように、忘れかけた頃に聴きたくなるのが、ガボールの個性。ハンガリー出身で、所謂アメリカの教科書的なジャズギターのスタイルでは無いユニークなヘタウマさが、根強い人気を裏支えしている。音楽のジャンルを跨ぐクロスオーバー系の先駆者としての功績があり、この曲も偉大なポピュラー音楽の作曲家、バートバカラックが手掛け、ディオンヌワーウィックが歌って本作同年に全米でヒットしたもので、このように取り上げられた結果、ジャズスタンダード化した。ザボは、良い意味で拘り無くポピュラーソングを取り上げ、ロックミュージシャンのサンタナとも共演したように、音楽を求めるがままに、結果としてクロスオーバーしたのではないか。この曲はアルバム名の通り、ジプシー的な打楽器によるアレンジが随所に加えられているのと、ちゃらーん、と昭和なアコースティックギターをかき鳴らす伴奏、それとは対照的な世界のナベサダによる端正なフルートが聴きどころ。この音楽の方向性が、後のウエスモンゴメリーによるフュージョンへの系譜に連なっていると考える。
13, 1965 “Unforgettable”
by Oscar Peterson, Hank Jones, Barry Galbraith, Richard Davis, Mel Lewis etc arranged by Manny Albam at A&R Studio, New York for Limelight (With Respect to Nat)
オスカー、亡くなったナットキングコールを追悼して歌を歌う。真似ているのか声がやたらと本人に似ているのと歌も上手い事に驚かされる。ピアノの弾き語りかと思いきや、歌に専念していて、伴奏は落ち着きのあるテイストの控えめなハンクジョーンズによるピアノが寄り添っている。と言うことは、オスカーはスタンドアップスタイルで歌に専念していたのだろうか。オスカーは、ナットキングコールのスタイルを踏襲して、10月三曲目のギターとベースでドラムレストリオを結成して成功を収めたので感謝の想いもこもっているはず。アルバム名が秀逸で「ナットへの敬意」と「ナットについて」をかけている。レーベルはMercury系のLimelightで、クインシージョーンズが当初率いていたが、ここでのアレンジは、前曲を歌ったディオンヌワーウィックとも組んだことのあるマニーアルバムが仕切っている。ナットの原曲のアレンジは、映画「上流階級」の音楽も手掛けた名アレンジャーのネルソンリドル。
4-5, 1969 “Golden Slumbers / You Never Give Me Your Money” by George Benson, Arranged by Don Sebesky at Rudy Van Gelder Studio, Englewood Cliffs, NJ for A&M Records (The Other Side of Abbey Road)
ビートルズの楽曲も相当数、ジャズのスタンダード曲化されていて、二曲前のアルバムにも「イエスタデイ」が取り上げられている。ここでは、名盤アビーロードの楽曲をジャズでカバーするという企画で、ジャズオーケストラの巨匠の一人、ドンセベスキーによるアレンジをバックに、存分に唄うジョージベンソンによるボーカルとギターを堪能したい。企画もプレイスタイルも、前年に亡くなったウエスのフュージョン路線を踏襲した大衆に向けたもの。ザボが開拓、ウエスが普及したフュージョンの系譜をベンソンが引き継いだ形。この曲は、オリジナルB面で特徴的な、ビートルズの最期に相応しいドラマチックな8曲からなるメドレーから、ボールマッカートニーの二曲を取り上げて構成されている。この作品、なんとオリジナルのビートルズのアルバム発売から僅か一ヶ月後に録音されている。が、発売はそこから半年以上先となっているのは、権利許諾の問題だろうか。ジャケットも、ギターを抱えたベンソンがマンハッタンの道路を一人で歩いて渡るという、微妙にオリジナルを模したシュールな写真。
6, 1971 “They Long To Be Close to You”
by Carmen McRae, Jimmy Rowles, Joe Pass, Chuck Domanico & Chuck Flores at Dante’s, Los Angeles, CA for Atlantic (The Great American Songbook)
カーメンの西海岸における大定番ライブアルバム。アメリカのポピュラー曲で構成された選曲、カーメンのサポートに徹した、伴奏者によるレベルの高い演奏、その場に居るような親密感のある状態の良い録音、と三拍子揃った完成度の高い二枚組。この曲では、ベースとのデュオから始まり、ピアノのジミーロウルズが粋なアクセントを入れ、ギターのジョーパスがさりげないバッキングでカーメンを盛り立てる。ジョーパスは、カーメン、サラ、そしてエラとはデュオで複数枚のアルバムを残しているように、女性ボーカリストとの相性が良い。このアルバム内でも、カーメンから、”One and Only, Joe Pass”と最大限の賛辞をもって紹介されている。1:50頃の笑い声はカーメンが茶目っ気で歌詞を「金髪」から「茶髪」に崩したアドリブに観客が反応したものだろうか。カーメンのボイスコントロールが最初から最後まで存分に味わえる一曲。バートバカラックが作曲、カーペンターズが歌い、前年に大ヒットした。この頃にはヒット曲を即座に取り上げる柔軟さがジャズに定着してきたと言える。
6, 1972 “Falling Grace”
by Gary Burton & Chick Corea at Arne Bendiksen Studio, Oslo, Norway for ECM (Crystal Silence)
ジャズビブラフォンのマスター、ゲイリーバートンとチックコリアのピアノによるデュエットアルバム。7回のグラミー賞を受賞しているバートンは、4本のマレットを操るテクニックを駆使して現代ビブラフォンを開拓した功績がある。スタンゲッツに起用されて注目を浴びるようになったが、その当時ゲッツが探していたのは、ビブラフォン奏者ではなくてギター奏者だったとの記録がある。そう言えば、キースジャレットがギタリストとしてゲッツにスカウトされたと回想していた時期と年代的に重なる。バートンとキースの共演アルバムが存在するが、その際にはこの話で盛り上がったのではないか。アルバム名の通り、クリスタルクリアなトーンとスタイルを共有するチックコリアとECMとの相性も良く、続編が何枚か存在している。ゲイリーバートンはバークリーでの講師歴もあり、新人発掘にも長けており、パットメセニーや小曽根真が巣立っていった。曲は、共演歴のあるベーシスト、スティーブスワローによって作曲されてスタンダード化したもの。
1977 “My Song”
by Keith Jarrett, Jan Garbarek, Palle Danielsson & Jon Christensen at Talent Studios, Oslo for ECM Records (My Song)
前曲に引き続きECMレーベル作品。キースはスタンダーズでのスタンダード曲とソロ即興演奏のイメージが強いが、メロディーメーカーとしてスタンダード曲も生み出していて、その代表曲がこれ。ヨーロッパ人によるメンバー編成でソプラノサックスのヤンガルバレクを交えたニューエイジ系のテイスト。このソプラノサックスは、後にポピュラー音楽としてクリスマスアルバム等で大ヒットした、フュージョン的なケニーGに影響を与えているかのように聴こえる。この曲はジャズと言えるか?そして、ケニーGはジャズミュージシャンなのか?答えは人それぞれで定義は難しいが、ここはキースの言葉、「ブルース、魂が篭っているか」を信じたい。そこに、ジャズの主要構成要素たる即興、演奏者間のインタープレイによる共振共鳴とメロディーやリズムの崩しが揃っていれば、立派なジャズと言いたい。譜面を忠実に弾く、アルバムを再現する、予定調和というようなハプニング要素ゼロの演奏はジャズとは言えない。その定義からすると、ケニーGの音楽はジャズからは遠いのかもしれない。ジャズにはミュージシャンの音楽に対する信念が宿っており、聴衆に迎合する耳障りの良いマーケティング音楽では無い。ここでのキースの演奏は、ほぼメロディーに徹し、軽やかな鼻歌と共に展開され、即興は最後部にさりげなく現れる。そこに至る道のりは耐え忍びつつ感情を表出する演出がツボで、涙腺を刺激する。
19, 1978 “In Your Own Sweet Way”
by Joe Pass & Niels-Henning Orsted Pedersen at Chappell Studios, London for Pablo (Chops)
名手二人によるデイブブルーベック作曲のスタンダード曲の演奏。ジョーパスのソロと伴奏を自由自在に行き来する名人芸、北欧の超絶技巧ベーシスト、ペデルセンによる速弾きを交えた息の整った絡み方が凄い。ベースでギターソロ並みのフレーズを悠々と弾いてしまう程なので、何をするにしても性急さが無く余裕感が漂う。八月のジムホールとロンカーターとのデュオ演奏と比較すると、雰囲気で聴かせる前者とテクニックで推してくる本作との個性が現れる。ペデルセンはテクニックがあり、リズムもピッチも正確無比なため、目立つ欠点が無いことを自負した上で、ロンカーターのチューニングとピッチを、酷くて聴くに堪えないと公に批判した。そう言われて八月のロンカーターの演奏を聴くと、確かに心許ないモヤモヤさがあって、これがピッチコントロールの甘さに起因しているのかも知れないが、それもまた個性。一方、非の打ち所がないペデルセンは、上手いのだが、あまりにも真面目過ぎるのか演奏自体に面白味が少ないという側面もある。ここでは、デュオで自由度が高い事と、ジョーパスという伴奏の名人と組む事で、刺激的な演奏となっている。録音はペデルセンがいるからかロンドンで、レーベルは、このメンバーにピーターソンを加えたトリオ作品も輩出しているパブロ。
18-19, 1993 “Love For Sale”
by Jacky Terrasson, Ugonna Okegwo & Leon Parker at Clinton Recording Studio “A”, New York for Venus Records (Lover Man)
セロニアスモンクコンペティションの優勝者というと、本作のフランス人ピアニスト、ジャッキーテラソンや、テナーサックスのジョシュアレッドマンがいる。本作は日本のレーベル、ヴィーナスが先見の明でデビューアルバムをプロデュースしたもの。その後、テラソンはブルーノートに転ずる。コールポーター作曲の大定番スタンダード曲を、大胆でパーカッシブなアレンジを施して強い印象を残す。強弱とスピードのメリハリも肝ながら、ドラムのレガートに促されるかのように疾走していく演奏が心地良い。3:35からモンクのフレーズ、その後にコルトレーンの「至上の愛」のメロディーが登場するように、遊び心が満載されている。ピアノとドラムに耳が傾くが、堪えてベースに集中すると如何に高度な水準でピアノとドラムの間のバランスを取っているか、が分かる。
【後記】
秋の深まりを感じさせる11月は、少し黄昏たような演奏で構成されている。そして振り返るとポピュラー系のスタンダードがバカラックの二曲を含めて計三曲。そして、何と無くしんみりとした空気感が伝わってくるライブ演奏が三曲、欧州録音も三曲、ピアノトリオも三曲とバランスが良いように思われるが、残念なのは八十年代の作品が含まれていない点。まだまだ改善の余地がありそう。内容としてはオスカーピーターソンの貴重な歌唱が聴きどころ。そして各演奏のつながり、そのメリハリのある流れをどう作り出すのか、には苦心した。
初登場となるギタリストのザボとベンソンは、取り上げたかったので、ようやく登場という感じ。両者共に60年代のポピュラーソングを題材としているのでその比較も面白い。
トピックとしては、キースジャレットの演奏で取り上げて本記事のタイトル写真にもあるジャズポリス。キースやパットメセニー自身によるジャズポリス的な発言から垣間見える共通項は、感性に訴えかける芸術性(オリジナリティやユニークさ)へのこだわりと商業主義傾倒(迎合)への批判というところか。その対象となったケニーG、これからのホリデーシーズンに向けて街中で何度も耳にしそう。その際にジャズなのかどうか改めて判断してみたい。
街中で耳にする、と言えばイオン系のスーパー、「まいばすけっと」で流れている音楽が、モダンジャズで、これまでに取り上げた曲を何度も耳にしていて、ブラインドテスト的な観点からもいつも楽しみにしている。かなりハードコアと言える以下の演奏までかかっているのだから、そのお気軽なイメージとは裏腹に面白くてつい通ってしまう。
さて、来月で本テーマによるシリーズは最終回を迎えます。今月も有難うございました。来月も宜しくお願いします。
【追記: 2023年12月7日】
たまたま早く目が覚めて、眠れないので理由も無くNHKの「ラジオ深夜便」を流していたら偶然にも4:42からケニーGの代表曲”Songbird”がかかったので、独断のジャズポリス判定をしてみた。その曲だけの感想を言うと、ジャズとは別カテゴリー。音楽的には良いし、サックスも上手いけど、耳心地良いように予め計算されて作られた上で演奏されているかのように、まさに予定調和に聴こえてしまう。結果として音楽に対峙する、というところまで向かい合えなかった。ではなんのカテゴリーかと言うと、この演奏だけを聴いて思ったのは、BGM。その次にかかった曲が、ハンズ・トゥー・ハンズという、1台のピアノに2人の奏者が向かって演奏するユニットによるエルトンジョンの”Your Song”だったので、この演奏のジャンルを調べてみたら「インテリア系サウンド」とあって、なるほど、言い得て妙と思った次第。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
