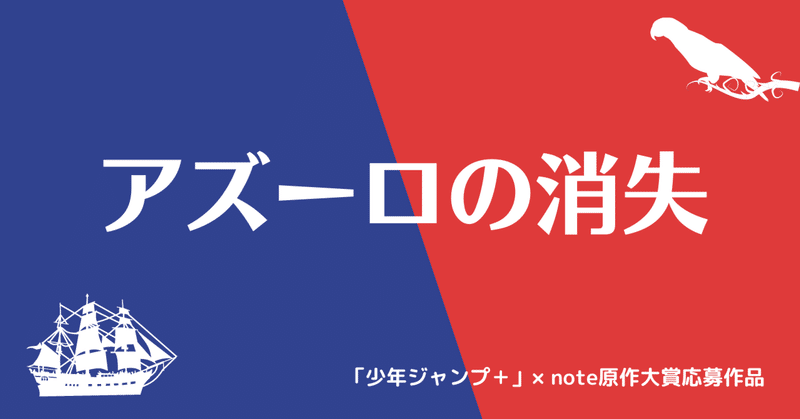
【小説】「アズーロの消失」第1話
大理石を敷き詰めた通路が朝の空気にひんやりと冷たい。粗末な編み草履は年中同じなので、これが冬であれば凍えるような思いをしながら窓を開け放っていくところだが、初夏を迎えてこの冷たさが心地よくなってきたのが嬉しい。閲覧室、談話室、研究用の小部屋。空気を入れ替えていくと、昨日の夕暮れから止まっていた時間がいきいきと動き出す気配がする。新鮮な海風で満ちたそれぞれの部屋が、勉学や研究のためにやってくる今日の利用者を迎え入れる。その様子を先んじて想像するのがロミは好きだった。
貴重書の収められた書庫以外の場所を全て換気してしまうと、ロミは箒を片手に玄関ホールへと向かった。この王立図書館は二階建てで横に長い、それは広大な建物である。全体を毎朝掃除するのはとても無理だが、建物の顔ともいえる玄関ホールだけは毎朝隅々まで掃き清める。職員は大勢いるが、まだ十歳の少年にもかかわらず見習いとして特別に働かせてもらっているのはロミだけなので、自然、ホールの掃除はロミの役目となっていた。それは彼をとても誇らしい気持ちにさせた。こんなに立派で美しい場所の掃除を任されているなんて。振り仰ぐと吹き抜けのホールは二階上部から円形のドームへと続いていて、この街随一の建造物である王宮とよく似た造りになっている。少しクリーム色の強い壁や床の石が、天窓から差し込む朝の陽射しでまばゆく輝いている。思わずロミは首から提げた涙型の青いペンダントにそっと触った。こんな素晴らしい場所で働いたり勉強したりする幸運を与えて下さって感謝します、アズーロの女神様。
開館時間が近づいてきて、後方のカウンターにぱたぱたと数名の職員が降りてきた。箒を手近な壁に立てかけ、ロミは玄関ホールの壮麗な扉を片方ずつ開けにかかる。重い扉をぐいぐい押して開き切ったとき、ちょうど高台の王宮からカランカランと鐘の音が響いてきた。
「おはよう、ロミ。」
「おはようございます、ヨハンさん。」
扉の外で待っていた常連である元大学教授のヨハンは、肩から提げた麻袋を重そうに背負い直して閲覧席へと向かった。あの中にはいつもどおり沢山の資料や虫眼鏡など、研究用具一式が入っているはずだ。ヨハンはかつてこのメルヴァの街の王立大学で天文学を教えていた。一時期は請われて大都市であるフーラや、南方のベリーニの大学でも学生を指導していたという。今では高齢で隠居の身だが、この図書館に通って今も現役で研究を続けている。
「ここにはどの街の大学にも負けないほどの書物があるからね。」
ロミがここで働き始めたばかりの頃、ヨハンはそう教えてくれた。
「メルヴァは繁栄しているし、昔から学問にはお金を惜しまないから。君はまだ実感できなかろうが、幸せなことなんだよ。」
この街は群を抜いて識字率が高いのだ、ということもヨハンが言っていたことだ。メルヴァでは学校できちんと読み書きを習う。活版印刷が徐々に普及してきたとはいえ、まだまだ高価な印刷の教科書を一人一冊与えてくれる。この図書館でも印刷された本が割合を増やし続けている。もちろん、手書きの写本の量には比べるべくもないが。
ロミは壁から箒をとって、扉の外へ出た。潮の香りをたっぷり含んだ風が穏やかに髪を撫でた。眼下にメルヴァの街並みが広がり、その向こうは果てしない海だった。数え切れない交易船がメルヴァ港の沖合に浮かんでいた。停泊している船からは次々と荷が運び出されている。穀物、香辛料、織物。もちろんこの街に届けられた品もあるが、ここから陸路で内陸の街へと運ばれるものも多い。積荷を下ろさない船はこの港を中継地として、遥か遠くの別の大陸まで航海を続けるという。小型の漁船は早起きなのでもうあらかた視界にはいないが、それでも数隻は沖で網を引っ張り上げている。空の水色と海の緑がかった青。そのグラデーションはいつも変わらず美しかった。海はきらきらしてきれいだ、とロミは改めて思う。きれいだけど、働く場所ではない、と。
メルヴァはパルレーネ半島北部の港街であり、同時に一つの都市国家でもあった。近隣にはフーラ共和国や内陸のケルシュ共和国があるが、メルヴァは王政を敷いた一つの国だ。大きく拡大発展したフーラや肥沃な土地を持つケルシュとは違い、この小さな漁師町メルヴァが独立した都市国家として存在を続けているという事実は、驚くべきことなのだった。
メルヴァが海路の交通の要所として繁栄しているのは立地が好条件というのもあるが、寄港税が低く抑えられていることが大きな要因だ。他の港より安く停泊できるのなら、とメルヴァを選ぶ船は自然と多くなる。そうすると人や物の行き来が盛んとなり、更に街は活気づく。いや、それよりそもそもメルヴァが他の国より潤っている最大の理由は別にある。他国にはない貿易品があるからで、これを輸出できる国は今のところ世界中でこのメルヴァだけだと聞く。それは水、塩っ気のない真水、飲料水だ。もう何世紀も前、この地方で研究をしていた技術者が偶然海水を真水にまで濾過する方法を考案した。それがこのメルヴァの街の起源だと言われている。今では巨大な樽や、時には美しいガラス瓶に入れられて、パルレーネ半島全域は元より船で辿りつけるところならどこにでもはるばる運ばれていくようになった。
こうしたことのほとんどは本で得た知識に、ガリエッティ博士の歴史の授業を足して知ったことだ。博士はこの王立図書館の第一司書で、博識ぶりにおいて右に出る者はいないと言われる温和なおじいさん先生だ。とても頭がいいけれど、ちっともそれをひけらかしたりしないところが誰からも好かれる所以だった。ロミは一年前にこのガリエッティに声をかけられ、それがきっかけでこの場所で働くようになった。学校に行かず、ここで勉強しながら司書の見習いとして働く。ロミには夢のような話だった。博士が両親を説得してくれたので、ロミはそれからすぐに学校を辞め、ここで朝から夕方までを過ごすようになったのである。
昼時の最も忙しい時間が過ぎた頃を見計らって、ロミは市場へ向かった。図書館からものの五分も坂を下れば、長々と連なった市場の白い天幕に辿り着く。そのすぐ向こうは港だった。ロミは図書館の食堂で昼食を食べたあと、二、三日に一度はここへやってくる。昼休みの短いひとときを両親や弟、それから友達と過ごすためだ。友達といっても、それはほぼ一人に限られているのだが。
両親が営む店に着いてみると、ちょうど二人が一息いれているところだった。店は半分が魚を売る普通の魚屋であり、半分がその魚を調理して野菜と一緒に丸パンに挟んで出す、軽食屋だった。とはいえ狭い店先で座って食べるような場所はなく、大体は市場で働く人や子供たちが買っていっては歩きながらかぶりつくような気安い店である。衣をつけてかりかりに揚げられた小魚の香ばしい匂いが漂っている。きょろきょろと見回したが、売り子をしているはずの弟、ミーノの姿はない。ロミが問う前に母が海の方を顎で指し示した。
「カリーナちゃんと桟橋へ行ったよ。」
母親の胸元にはロミと同じ形、同じ色のペンダントが揺れていて、それが陽の光できらりと光った。父親は早朝の漁と昼時の忙しさに疲れてぼんやりと腰を下ろしていたが、その胸にももちろん同じ飾りが見え隠れしている。
メルヴァの街は独自の宗教を持っている、珍しい二神教の都市国家だ。アズーロ神とローザ神である。
アズーロ神は青い神という意味であり、水甕を掲げた女神の姿をしている。王宮や、パラッツォと呼ばれる礼拝所の彫像では、美しい顔を少し俯けて横顔を見せている。その表情は慈悲深く、どこか哀しげでもある。ローザ神はバラ色の神という意味で、書物を開いて片手に持った男神の姿をしている。まだ若いその顔を真っ直ぐ前に向け、知恵ある者の鋭い眼で正面を見つめている。
市民は必ずどちらか一方の神を信仰する決まりになっていて、ロミの家では代々アズーロ神を崇めてきた。もちろんどちらを信仰したところで制度上何か違いがあるわけではなく、アズーロ信者だからといってローザ神やその信者のことを蔑むようなことは決してない。逆もしかりだ。元来が平和な街である。ことさら自分がどちらの信仰かを公にする必要もないし信仰を移ることも個人の自由だ。それでもわざわざ信仰を移ろうとした話などは聞いたことがないし、皆自分の神様のことが大好きなので、必要がなくともその神が表す色を身の周りに取り入れたがる。大体は涙型のペンダントをつけることが多い。青に白を混ぜてコバルト色に、もしくは赤に白を混ぜてバラ色にしたガラスを涙の形に加工し紐で結わえてあるような簡易な商品なら、安く手に入る。ガラス細工はパルレーネ半島の幾つかの街で工芸品として栄えており、メルヴァにも職人が多い。友人であるカリーナの父もガラス職人だ。そんなわけでロミの一家もそのようなペンダントを一揃い持っていて、家族四人でぶら下げているのだった。
涙型は水を表していると言われている。そう、我が国無二の貿易品、真水のことである。この技術があるからこそちっぽけな異教の都市国家が独立を保つことができていると誰もが言う。あの図書館の常連、ヨハンもしきりとロミに話してくれたことがある。
「異教徒同士ではこれまで多くのいさかいが起こっているし、それがいつまた起きるかわからない。それでも万に一つこのメルヴァを攻め真水の濾過技術が散逸してしまえば、困ったことになるのはどの国もわかっているのだ。真水は文字通り命に関わるからな。だから他国は手を出すよりこのメルヴァと友好関係を築くことを選ぶ。メルヴァは危険な国ではない。ローザ・アズーロ教・・・他国では二つの神の名をくっつけてそう呼んでおるそうだが、それを無理やり外へ広めようとする国でもない。ならば信仰のことは構わず、真水を輸出してもらったり寄港地として港を使わせてもらったりする方が利口だ、とね。」
そんな会話を思い返していると、ふと我に返ったように大きな伸びをした父親が、ガラス瓶の水を飲み干してロミの方を向いた。
「なあロミ、そろそろミーノに網の張り方を教えようと思ってな。」
ロミは驚いた。自分は漁に関心がないが、それでもミーノがまだまだ足手まといになっていることは知っていた。
「でもミーノはまだ歳が足りないし、舟に酔ってばかりじゃないか。」
「それがあの子、この頃すごいのよ。」
母が横合いから身を乗り出してきた。父も表情を崩して続ける。
「魚の群れの場所を見つけるのが上手いんだよ。最初の二、三回はまぐれだと思ったが、今日は二ヵ所も指し示してその両方にクパが群れ集まっていた。こいつらは海中の結構深い場所にいるからな、海の色合いが変わるといってもなかなか見つけられるもんじゃない。それをあいつは立て続けに見つけたんだ。かなり筋がいいんじゃないかと思う。いい漁師は勘が必要だし、目もいいもんだ。」
いつも厳しい顔つきをしている父が嬉しそうに話をすること自体が珍しかった。それはなぜだかロミを落ち着かなくさせた。この感情は正体がわからないから嫌いだ、とロミは思った。ロミは眩しい通りへ再び戻ると、そそくさと桟橋の方へ足を向けた。
桟橋にはミーノとカリーナが草履を履いた足をぶらぶらさせて座っていた。カリーナは長い髪を後頭部の上の方で一つに束ね、赤い紐でぐるぐる巻きにして房の半ばまでをつんと上向きになるように結わえている。この髪型はメルヴァ王の娘であるダニエラ様が街に出る際に好んでしている髪型であり、当然街の娘は子供も含め皆この髪型をしたがった。なにしろダニエラ様はメルヴァで慕わぬ者のいない素晴らしいお方なのだ。他に兄弟姉妹はいないから次の国王になるお方であるのに、供を一人か二人つけただけで気さくに街にお出かけになり、身の回りの物を買いにも行けば市場を通られることもある。王立図書館、つまりはロミの職場に顔を出されることもある。ロミは臆して後ろへ引っ込んでしまうのだが、それでもその笑顔を離れた場所から眺めるだけで、ぽおっとなってしまうほどだった。
そんなだからもちろんカリーナだって髪型を真似しているし、ミーノに至ってはまだ幼いこともあり、ダニエラ様があんなお優しいことをおっしゃったらしい、ダニエラ様がこんな素晴らしいことをしたらしい、などとうるさくて仕方がない。
「あ、ロミったら、聞いてよ。」
カリーナが赤い髪紐を揺らしながら立ち上がり、こちらへ駆けてきた。バラ色のペンダントも胸で跳ねている。カリーナの父親のガラス工房はロミの家の斜め向かいで、彼女とは幼馴染みである。歳はロミと同じで、学校は午前のクラスに出ている。もちろん彼女のつけているペンダントも父親が工房で作ったものだ。
「ピッコロ、なんだか感じ悪いの。カモメの群れが来てたから教えにきたんだけど、全然はしゃいでくれないしさ、いつもみたいに笛も吹いてくれないし。つまんないったらありゃしない。」
ピッコロ、とカリーナは弟のことを呼ぶ。「小さな」という意味だ。以前はよく三人で遊んで回ったものだった。ロミとカリーナは二人とも好奇心の塊のような子供で、そこに小さなミーノがくっついてくる、というのがいつものパターンだった。しかしロミが図書館で働くようになってからはそれができなくなり、カリーナはピッコロ・ミーノと二人でよく遊んでいる。いや、遊んでくれている、というべきだろう。
「一体何をむくれてるんだよ、ミーノ。」
後ろからロミが声をかけると、ミーノは振り向きもせずにぶつぶつと答えた。
「別に、むくれてなんかないけど。」
その言い方からして不機嫌な様子が窺えた。普段は素直で明るく、両親の言うこともよく聞くし、ロミのことも慕い頼ってくれている。周囲はどうしても王立図書館で働くロミを注目しがちだが、それを妬むどころか逆に自慢に思ってくれているようだった。一緒に遊ぶことができなくなり、寂しく感じている節はあるが、これまでそれを不機嫌という形で出してくることはなかった。友達はカリーナ以外にもそれなりにいるようだが、やはり実の兄とあまり顔を合わせられなくなって寂しいのだろうか。もしかしたら父親からのプレッシャーを必要以上に感じているのかもしれない。ロミを漁師にすることを諦めざるをえなくなってから、父はミーノを海に伴うことがずっと増えた。ロミは勉強以外も何でも器用にこなすから、漁にまつわるあれこれも見よう見まねで覚えるのが早かったが、ミーノは不器用で要領が悪い。父親は悪気はないのだが兄弟を比べがちで、だからミーノの手際の悪さにはいらいらすることも多いようだった。
「父さんと海で何かあったのか?」
ミーノは答えない。桟橋から足をぶらぶらさせたまま遠い海を睨みつけている。カリーナに服の袖を強く引っ張られても動こうともしなかった。
メルヴァの街は漁師が多いので、早寝早起きの家もまた多い。ロミの家も夕食をとったあと、両親は用事を済ませるとさっさと二人の部屋に引き上げてしまう。ロミはミーノと二人部屋だが、ミーノも学校と遊びと店の手伝いに、最近は漁まで加わって疲れ切り、ベッドに入るとすぐ深い眠りについてしまう。大抵最後まで起きているのはロミだった。
「お兄ちゃん?」
二段ベッドの下から心細いような声がしたのは、ロミがガリエッティに出された課題について考えながら眠りに落ちかけていたときだ。いつもならとっくに眠っている弟の声にロミは驚き、シーツをのけて下段を覗き込んだ。ミーノは顔が半分隠れるぐらいまで両手でシーツを引き上げ、身体全体を斜めにするような格好でロミを見上げていた。
「どうした、眠れないのか?」
難しい質問を投げかけられたみたいに困惑した表情をする。眉を寄せて黙り込むなど、およそ普段のミーノらしくない。今日は昼から何だか様子が変だ。ミーノは時々ロミに甘えてくることもある。両親は漁と商売で常に忙しく、一緒にいるからといって遊んでくれるわけではないから、やはり寂しいのだと思う。その気持ちはロミにもわかるが、今はやめてほしかった。睡魔はもうそこまできている。下を覗き込む姿勢のままで眠ってしまいそうだ。
「誰にも言わない?」
「ああ、言わないから何だよ?」
瞼が半分塞がってくる。ロミは覗き込むのをやめて仰向けの姿勢に戻った。耳だけは下に注意を払っているつもりだ。
「あのね、父さんが言ってたことだけど、僕、勘でわかるんじゃないんだ。僕、僕、本当に見えるんだよ。」
だから何を?言葉が声となって出ているのかもわからない。もう眠りまでひと押しだ。
「魚の群れがね、見えるようになったんだよ。魚が見えるって言うより、僕、海が見えなくなった気がするんだ。」
そうか、うん、海が見えなくなったんだな。海が。え、海が見えない?ロミを襲っていた睡魔は一瞬にして霧散してしまった。さっきより大きく下段を覗き込む。
「う、海が見えないって何だよ?」
薄暗い中でミーノの身体が震えているのがわかった。泣き出しそうになっているのだ。ロミはびっくりして、次の瞬間にはぴょんと床に飛び降りた。
「おい、どうした?どうして泣くんだよ?」
「だって海が見えなくなってきちゃったんだもん。前みたいに青くなくて、し、白っていうか透明みたいで、だから魚の群れも岩も海藻も見えるんだ。海だけじゃなくて、空も白いんだよ。ずっと曇りかと思ってたんだけど、今日カリーナがカモメが飛んでるって指差して、でも空が白いからカモメが見えなくて、それでやっぱり変だって。それで、」
堰き止めた水が溢れ出すようにそこまで一気に喋ってしまってからしくしく泣き出したミーノが恐怖で満たされていることを、やっとロミは悟った。怖いのだ。弟は自分の眼に何か問題があることに気づいてから、今まで誰にも言わずにいたのだ。
「ミーノ、それっていつからなんだ?だからその、」
「海が見えなくなってから?」
あまりに異様な言葉をロミは口にしたくなかった。黙っているとミーノが続ける。
「多分、前の新月休みぐらいから。パラッツォのガラスの色がいつもと違ってて。女神様に射す青い光がいつもよりずっと薄い水色っぽく見えたんだけど、お日様が雲に隠れてるのかと思ったんだ。」
休みの日の朝にはどこの家でも家族揃ってパラッツォへお祈りをしにいくのが決まりだ。パラッツォは街に幾つもあり、近いところへ行けばいい。ロミ家は市場の北西に位置するパラッツォへ行く。中に入ると東の方角にローザ神とアズーロ神の彫像が立ち、それぞれの後ろに大きなステンドグラスの窓がある。ステンドグラスは昔、この街のガラス職人がこしらえたものだ。ローザ神の後ろの窓はバラ色、アズーロ神の後ろの窓は藍色を中心としたグラデーションのガラスで、船や魚、花などの模様が表現されている。朝日を浴びてそれらは輝き、白い大理石の彫像に美しい色を落とす。決まった時間に皆が一斉に祈ったり歌ったりというようなことはなく、それぞれの家族が並べてある椅子に腰かけて静かに神を思う。無事に日々を送ることができるのを感謝し、家族の健康や漁の成功を祈る。ロミはこの間の新月休みの日を思い出そうとした。まだ数日しか経っていない。あの日はちょうどカリーナとその父親も同じ時刻にやってきたので隣同士に座った。ロミの父とカリーナの父が少し言葉を交わし、母はカリーナの頭をくりくり撫でた。ロミはいつものようにしばらくは静かに祈っていたが、そのうちカリーナと言葉を交わすため、ミーノの隣を立ってカリーナの座っている方へ回り込んだ。あのときミーノはどんな顔をしていただろう?ロミはそのことを少しも思い出せなかった。
「それからちょっとずつ変なことが起こって。海が透明みたいになって魚が見えちゃうこととか、空が白っぽいこととか。それからこれ。」
と言ってミーノは胸元から外してベッドサイドの小机に置いていた青いペンダントを手に取った。紐を持ってガラスの部分をぶらぶらとさせる。
「これも僕、見えない。」
「何だって?」
ロミはその青い物体が揺れるのを見つめながら、不安が膨らんでくるのを感じ取った。
「紐は見えるけど、先っちょのガラスんとこが白っぽくぼやけてる。青いものがどれも見えなくなったみたい。昨日漁の後にパラッツォに寄ってみたけど、青いガラスはもう白にしか見えなくて。一番怖いのは眼なんだ。人の眼。学校のエズ先生とか市場の八百屋のおばさんとか、眼が青いでしょ。それも白く見えて白目ばっかりみたいで、怖くて顔が見られなくて。」
一気に喋っているうちに恐怖の感情が高まってきたのだろう、ミーノは再びしゃくり上げ始めた。
「だから漁で見つけるのも赤とか黒の魚の群ればっかりなんだ。青い魚は海と一緒に見えなくなっちゃってるから。本当なら青い魚の群れが一番多いはずなのに・・・」
「漁の話なんてどうだっていいじゃないか!」
ロミはミーノがなぜそんな話を持ち出すのか理解できなかった。ミーノは涙をぬぐいながら、とても悲しそうな顔をした。
「だって、父さんは喜んでるから。僕、今まであんまり役に立たなくて。頭も良くないし力もないし船酔いもするし。だけど魚の群れを僕が言い当てるようになってから父さんすごく嬉しそうにしてる。僕の指差す方に舟を漕いで行って、僕が言った深さに網を下ろすんだ。そうしたら大量に魚がかかる。当たり前だよね、だって見えてるんだから。そういうことがここ何日かの間に十回ぐらいあったんだよ!おまえは素質があるって。これだけ海を読み取ることのできる人間はそうそういないって。波が見えなくなって船酔いもしなくなったし。」
ロミはしばらく声が出せなかった。自分の感情を読み取るのに時間がかかった。怒っている、自分は怒っているとまず思ったが、何に対して怒っているのかが上手く掴めなかった。父親に対してだろうか。こんな思いを弟にさせているとも知らずに?それとも弟の気持ちに気づいてやれなかった自分自身に対してだろうか。わからない。わからないけれど、ともかくまずは医者だ。医者に診てもらわねば。
「ミーノ、このこと父さんと母さんには言わなきゃ。ミーノの眼には何か、よくわからないけど何か悪いことが起こってるんだ。クリニカのお医者さんに診てもらって、」
「嫌だ!」
ミーノは短く叫んだ。そして自分で自分の声の大きさに驚いたようにぐっと息を飲んだ。
「絶対言っちゃ駄目だ。誰にも言わないって最初に約束したじゃないか。」
確かに寝ぼけ眼でロミはそう約束した。しかしその時点ではこんなに深刻な話だとは思いもしなかったのだ。一体どうしたらいいだろう。ミーノはまだぐずぐずと鼻をすすりながら、シーツに潜り込んでしまった。ともかく急いでクリニカに連れていかなければ。ロミはその夜ほとんど眠ることができなかった。一人で抱え込める問題ではなかった。ガリエッティの顔が何度も浮かんでは消えた。両親に言えないのなら、頼めるのは博士ぐらいしかいなかった。いやでも・・・、ロミの思考はまとまらず、東から最初の朝の光が部屋に差し込むのをじっと待つしかなかった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
