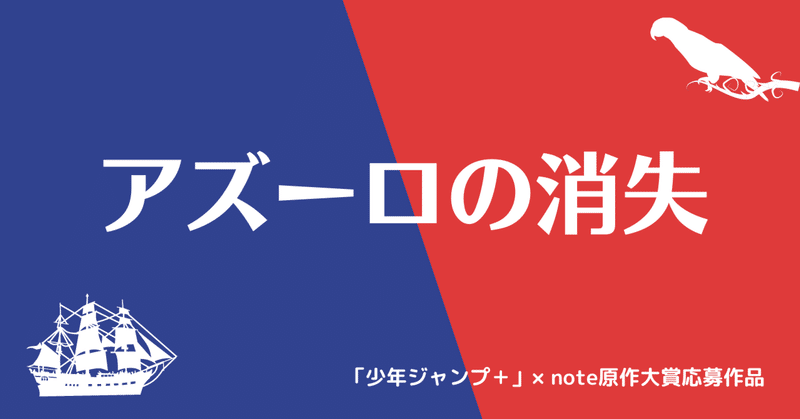
【小説】「アズーロの消失」第3話
その夜やってきたのは、しかしその医師ではなかった。そもそも医者ですらなかった。落ち着かない様子で腰掛ける両親を背にロミは窓から通りを窺っていたのだが、細い路地の向こうに現れたのは奇妙な出で立ちの女だった。
釣りランタンを持っているが顔の上半分はヴェールで覆われて全く見えない。ふわりとした幅広のズボンを履いていた。女でズボンを履くのはメルヴァでは小さな子供ぐらいである。何より眼を惹くのは肩に乗せている大きな鳥だ。鉤のように曲がった嘴をしている。ロミは家族の方を振り返った。
「来たみたいだよ、女の人だ。」
「今日の先生じゃないの?」
真っ先に反応したのはミーノだ。今は母親の座る椅子にぴったりくっついて、片手は母の膝の上に乗せている。帰宅してから両親には、クリニカに行ったことと、今晩医師が直接家まできて説明してくれることを簡単に話した。父親は、どうして先に自分に言わなかったのだと二人を叱ったが、医者が家まで来る理由がわからず、不審がった。
ノックの音が響き、入ってきた女はやはり風変わりだと言わざるを得なかった。ヴェールの裾から覗く髪は前下がりのおかっぱで赤毛、口には暗い赤の紅を塗っている。室内の明かりでは黒にも見え、薄気味悪かった。それでも王宮の紋章の入ったローブは見間違えようもなく、女が王宮の遣いだということは一目でわかった。ロミはもちろん家族全員がその紋章を凝視した。
女は部屋の上部を見回すと、空いていたランタン掛けに自分のランタンを吊るし、その上に鳥を留まらせようと右肩を持ち上げた。鳥は大人しくひょいと飛び移る。鮮やかなエメラルド色のオウムだった。それから女はやおらこちらに向き直った。
「本日は突然このように訪問し、誠に失礼とは存じますが、非常に重要なお話がございます。」
こんなに硬い喋り方をする女は見たことがない、とロミは思った。両親にも緊張が走ったのか顔が更にこわばる。ミーノは母の膝に抱き着くようにしている。
「私は王宮で国王直属の部署である内務部に所属するジルマと申します。女がこうした職務を司るのは珍しいことゆえ、驚かれるのも無理はありませんが、」
そこまで女が喋ったときに、頭上でカタ、と音がした。全員が思わず振り仰ぐと、小首を傾げて先程の鳥がこちらを見下ろしている。
「ああ、言い忘れておりました。あのオウムは念のための護身用に連れております。安全な街とはいえ、夜の女の一人歩きは危険が伴いますので。」
「あの鳥、強いの?」
おずおずとミーノが尋ねた。そこで初めて女はふわりと笑みを見せた。口元しか見えないが、その両端が持ち上がる。
「ええ、あの嘴で噛まれると痕が残るほど痛みます。でも何もしなければ襲ってきたりしないわ。」
ミーノに話しかけるとき、女の口調が和らいだことにロミは気づいた。女は姿勢を正して全員をぐるりと見回すようにする。
「話を戻しましょう。ミーノさんの身体的な問題についてご両親がどこまでお聞き及びかわかりませんので、私からもう一度ご説明させて下さい。」
女が話した内容は、今日の医師とのやり取りや検査について整然とまとめられたものだった。父も母も顔を青くして説明に聞き入った。母は途中から目尻に涙を浮かべ、父は厳めしい表情で女の口元を睨みつけている。海の青色が見えなくなったために魚群が見えていた、というくだりでは眼を剥き、考え込むように腕組みをした。
「お気持ちは察するに余りあります。視界が部分的に白く欠ける、というのは想像するだけでも不安であり、不便でしょう。高齢であればまだしもこんなに幼いのですから。慣れないうちは気持ちの悪いものだと聞いております。」
「聞いて?」
思わずロミは声をあげた。この違和感はクリニカで感じたものと同じだ。そう、あの検査用の冊子は青色が見えなくなったと訴えてくる患者用に用意されたものだった。
「あの、この病気になる人は他にもいるんですか?」
女はヴェール越しに視線をさっと移動した。言葉を探すような間がある。
「ええ、確かにお兄さんのおっしゃるとおりです。この症例はミーノさんが初めてではありません。我が国ではまれに発生するもので医師にも広く知られております。後天性青色色盲と呼ばれるものです。」
「青色色盲・・・」
母親が呟くように繰り返す。
「ある日突然青いものが霞んだり白く置き換わったりという異変を感じます。ただお気付きのように、このことは一般には知られていません。私はその理由をご説明するために今日ここへ参りました。」
息継ぎもせずに立ったまま喋っていた女が、ここでいったん大きく息を吸った。
「この症状を発症した方にはとても重要なお役目がございます。これは確かに病ではありますが、同時にとても優れた特殊な能力を得た、とも申せます。この能力を得た者は王宮に上がり、王に最も近い役職で任務に当たっていただきます。これは建国当初からの決まり事で、王族と一部の官職にある者しか知りません。クリニカとは連携しておりますが、彼等もこの症例の者が現れたなら直ちに王宮へ連絡せよ、と伝えられているのみです。」
「ちょ、ちょっと待って下さい、」
思わず母が声を出したが、女は一気に話してしまうと決めているかのように、更に続けた。
「詳しい職務内容は極秘事項ですが、私もお近くでいつも見守っております。ミーノさんには住み込みで仕えていただきますが、勉学もこれまで以上にしっかりした教育を受けられるでしょう。望むなら、絵や音楽など専門の授業を受けることもできます。給金は毎月一万ナリルをお支払い致します。」
「い、一万ナリルだと!」
今度は父が悲鳴のような声をあげた。一万ナリルは、漁と店舗からなる一家の収入の十倍以上はある。途方もない額だった。
「このような話ですので当然の額かと心得ます。ご両親はミーノさんを立派な漁師にされるおつもりだったはず。それを突然王宮に上がれなどと。強く激しい怒りが湧いて当然です。でもミーノさん、あなたはこのメルヴァに必要とされています。その優れた力は選ばれた者にしか出現しません。その力をどうかお貸し下さい。国王もそれを強く望んでおられます。」
ミーノは母親の膝からおずおずと手を離すと、小さな声で女に尋ねた。
「国王様のお傍なら、ダニエラ様もいる?」
女の口が再び優しく弧を描いた。
「あなたはダニエラ様のことがお好きなのですか。」
「・・・ダニエラ様が好きじゃない人なんていないよ。」
「もちろん、国王にお仕えするということはダニエラ様にお仕えするということです。常にお傍においでになるでしょう。」
母親が慌てて口を挟んだ。
「さっきから何だか大袈裟に聞こえるけど、住み込みだからって帰ってこれないわけじゃないんでしょう?」
女はミーノに合わせてかがんでいた身体を伸ばした。
「もちろんです。ただ頻繁には難しいでしょう。半年に一度か、年に一度。国の中枢で働けば軽々しく公言できない情報も多く知りますので。」
「僕、何をするの?」
ミーノの問いかけに女は再び笑みを浮かべたが、もう答えはしなかった。言うべきことは言った、という態度だった。
「明後日の早朝、王宮の最初の鐘が鳴る頃にお迎えに参りますので、身の回りの、大切にしているものだけお持ちください。また、周りの方にはミーノさんが王宮で仕えることになったと、それだけお伝え下さい。眼のことにつきましては他言無用とお心得を。これは国王のご指示です。それでは。」
「あ、明後日って、」
父も母も急いで何か尋ねようとしたが、女は身を翻し、オウムを肩に留まらせて出ていってしまった。
王宮の居室に戻り、ヴェールとかつらを外してじっと鏡を見る。不気味に光る赤黒い口紅もすぐに拭きとった。眼が充血している。いけない、あれしきのことでこんなに打ちのめされていては。しばらく眼を閉じ、込み上げてくる涙が治まるのを待つ。
部屋を出て通路を曲がったところでルダイオンに出会った。
「泣いていたのか?」
顔をそむけ、拒否の態度を示す。
「だから言っただろう。あの者に告知をするのはあなたの仕事ではない。なぜ自分を追い込んでまで関わろうとするのだ。誰が行こうが同じことだ。」
「同じではありません。」
女は今度はきっぱりとした口調で言い、顔を正面に向けた。
「他の者が行ってはどんなやり取りだったのか、私が知ることができません。」
「後から報告を受ければよいではないか。あなたに嘘をつく者などおらぬ。」
女は明らかに怒っていた。肩を震わせる。
「嘘をつかれるなどと思ってはおりません。でもそれでは本当のことがわからない。ミーノというあの幼い者が怯えていたのか、自らの病を疎んでいたのか、それとも王宮へ上がれると聞いて少しは嬉しく、誇らしく思うのか。家族の反応は。そうしたことの全てを私は知りたいのです。」
「知ってどうする?」
「少しでもあの者の痛みを分かち合いたいのです。」
「それを国王は望んでいない。・・・まあ、だからこそあなたはこういう行動を取るのだろうが。」
ルダイオンは深い溜め息をついた。
「ルダ、あなたはこれまでもずっとそういう冷めた心でこのことに関わってきたのでしょう?私にはそれが理解できない。あなたも国王も血の通った人間なのですか?メルヴァの民に教え諭している良心への忠誠や他者を労わる心や平等や、そういったものとあまりにかけ離れた行いだとは思わないのですか?奴隷貿易には手を染めない。海洋国家同士の争いにも宗教紛争にも加担しない。平和の象徴たるメルヴァの根幹にこのようなことがあるなどと他国に知れたら一体どんな申し開きができるのですか?」
「だから知られないように尽くしている。何事にも必要悪というものがあるのだ。わかっておるのだろう?ダニエラ。」
ルダイオンが何を言わんとしているのか、ダニエラにはもちろんわかっていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
