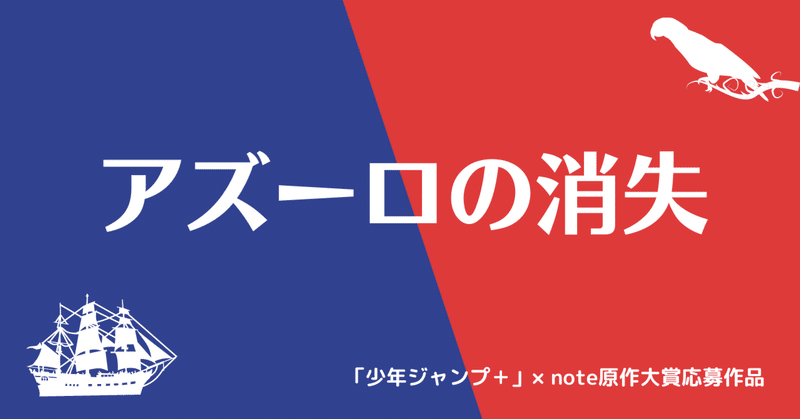
【小説】「アズーロの消失」第2話
翌日、ロミはガリエッティに書誌学や化学を習ったあと、昼休みに医学書の書架へ向かった。午前の授業中、博士にミーノの件を尋ねてみたい気持ちを抑えるのに苦労したが、まずは自力で調べたいというのがロミの性格だったし、弟との秘密をそう簡単に人に漏らすのは気が咎めた。
一階の奥にある医学書の書架は今日もひとけがなく、ロミは医学事典のページを繰った。眼球の断面図などが並んでいて気味が悪い。専門的な用語が多いのでちゃんと理解できるわけではないが、眼病のページに生まれつき赤と緑の区別がつかない色盲というものがあり、これが一番ロミの関心を惹いた。しかしミーノが訴えているような症例は見つからない。
ふと視線を上げると二階の執務室から出てきたガリエッティと眼が合った。博士はちょっと見下ろしただけで人がどんな種類の本を調べているのか、棚の位置でおおよそ見当がつく。今もそのようにロミの場所を見定めると、白衣を翻して足早に階段を降りてきた。案の定、やってきた博士は心配そうな顔で尋ねた。
「今日は何だか授業中も顔色が悪いような気がしたんだが・・・どこか調子でも悪いのかね?」
そう言いながら、すでに視線はロミの開く事典のページに注がれていた。眉間に皺を寄せたのがわかる。
「眼病の項目か。もしかして視力が落ちてきたのではないかな?眼は使い過ぎると焦点を結ぶ力が落ちて遠くのものが見えにくくなるからの。」
「いえ先生、僕じゃありません。」
否定したロミは次の言葉に迷った。ミーノとの約束はあるが、博士は博識だから弟の症状について何か思い当たることがあるかもしれない。ロミは急にからからに乾いてきた唇を舐めた。
「あの、先生・・・先生はある日突然決まったものが見えなくなる病気のことをご存知ではありませんか?」
博士の眉間の皺がさらに深くなった。
「視力が落ちている訳ではありません。視力が落ちるというのは見える世界の全てが見えにくくなることでしょう?その、その人が言っているのは違うんです。ここに、」
ロミは開いていた医学事典を博士の方へ押し、ページを数枚戻ってみせた。
「先天性色盲というのが載っています。でもその人は生まれつきそうだった訳ではありません。急に・・・あるものが見えなくなって。」
「ふうむ、一体何が見えなくなったのかね?その人物は。」
博士の落ち着いた声音に励まされるように、ロミは口を開いた。
「青色です。青いものすべて、です。海や空や、とにかく青い色が見えなくなって白や透明になったと。」
博士は考え込むように眼をつむり、腕を組んだまま黙った。周囲には誰もおらず、窓の向こうに咲く濃いピンク色の花を太陽がギラギラと照らしていて眩しい。ロミは期待を込めた気持ちで待ったが、博士は首を左右に振って眼を開けた。
「ああ、ロミ君。申し訳ないがワシもその症例については聞いたことがない。だから余計に心配じゃ。ロミ君、早くその人をクリニカへ連れていってあげなさい。その人はロミ君の友人か何かかな?」
博士はロミを気遣うような優しい口調で問いかけた。ロミは弟とはっきり言わなかったことですでに気が咎めていたが、「その人」と言えば言うほど事実を言いにくくもなってしまった。
「・・・はい、あの、友達です。早くクリニカへ行くようにします。」
ロミの言葉が終わらぬうちに、博士は大きく頷いた。
「そうしてあげなさい。なんなら今から行っても構わんよ。午後の仕事は誰かに代わらせよう。なに、この街の医者は優秀だ。きっと手立てがあるだろうよ。」
博士はロミの肩を優しく叩いた。
博士の言葉に甘え、結局ロミは午前中に溜まった返却本を棚に戻す作業だけ終えると足早に図書館を出た。市場の隅から店を窺ったが、客の相手をしている母親と魚を捌く父親の立ち働いている姿が見えるだけで、ミーノは見当たらなかった。少し離れた広場の方から拍手の音が響いている。そちらを覗くと人形芝居が行われており、ミーノが一人離れた階段に座ってそれをぼんやり眺めているのが見えた。
「ミーノ。」
声をかけるとミーノは肩をびくんとさせて、ロミを振り仰いだ。
「お兄ちゃん?お昼休み?」
目に見えて元気がない。いつもなら最前列で芝居を見ていたミーノなのに。
「店の手伝い、すぐ戻らなくても平気か?やっぱりクリニカへ行こう。図書館は今日はもういいんだ。」
嫌がるかと思ったが、ミーノは意外にも大人しく、というより怯えたような顔で頷いた。
「あんまり魚が獲れすぎて父さん喜んでるけど、ちょっと怖がってる。他の漁師の人達に何か言われたみたい。父さんだけ毎日大漁すぎるから。」
ロミは弟を引っ張って立たせると、にこっと笑ってみせた。
「大丈夫だよ、ミーノ。お医者さんは頭がいいんだ。きっと治してくれるよ。」
確証のないことを請け合うのが苦手なロミは、それでも弟を不安がらせないためにそう言い、広場からミーノを連れ出した。
クリニカの小さな入口をくぐると診察に来ている人の姿はほとんどなく、ロミはほっと胸を撫で下ろした。首からすっぽり被る膝までのマントのような服を着た受付の女性が、どうしたの?と尋ねてくる。弟が眼が痛いんです、とロミが簡潔に答えると、女性はすぐに二人を診察室へ通してくれた。
医師は父親より少し若そうな、顔の四角い男性だった。簡素な木の椅子に座って、こちらもマント状の服を着ている。ロミとミーノにも椅子を勧めてくれた。
「親御さんの付添いはないのかな?」
「はい、僕達だけで来ました。」
医師は穏やかそうな茶色い眼をしており、そのことにロミは少し勇気づけられた。ロミは一つ深呼吸をすると、弟の眼に起きている奇妙な現象について、つっかえつっかえ話し始めた。
医師は質問を挟み、メモをとりながらロミの話を聞いてくれた。そして時々、細めた眼をミーノの方に向けた。弟がこの数日で生活にも困るようになってしまったことを語り終えると、医師はメモしていた紙から顔を上げ、ミーノの方へ身体ごと向き直った。
「君にも二、三質問していいかな?」
ミーノがおずおず頷き返すと、医師はガラス製の濃い青の文鎮を机の上から持ち上げた。
「今、君の眼にこれはどう見える?」
「白い・・・もやもやしたもの。」
ミーノは医師の手元を凝視して、か細い声で答えた。
「先生の指先までもやもやして欠けてる。」
そうか、と呟きながら、医師は自分の指が実際欠けているのではないかと確認でもするかのように、文鎮を持った右手の先をじっと見つめた。
「そのペンダントは、」
医師が今度は服に隠れたペンダントの紐を指差したので、ミーノはそれを引っ張り出した。美しいコバルト色のガラスが現れる。
「ああ、君のお家はアズーロの女神を信仰しているんだね。それはどう見える?」
ミーノは首を縮めるようにして涙型のそれを見つめた。
「同じ、もやもやした白い塊。」
医師は少し考え込むような仕草をしたあと、小さく息を吐いた。
「ミーノ君、このことはお兄さん以外に話したかい?」
ミーノはぶるぶると首を振ってみせた。
「お兄さんの方はどうかな?」
ロミの頭にガリエッティがよぎったが、肝心なところは隠していたのだから言ったことにはならない、と思いたい。
「いいえ。」
医師は何度か小刻みに頷くと、椅子を立ち、壁際の戸棚から数冊の薄い冊子を持って戻ってきた。中の一冊を開いてミーノに差し出す。
「ここに書いてある絵がわかるかな?」
ロミからもよく見えた。ベージュの紙の真ん中に大きく黄色い丸が描かれ、その中に緑色で三角が描かれていた。刷りの掠れていない高級そうな多色刷りだ。
「丸と三角。」
ミーノはすぐに答えた。医師は頷いて次のページをめくった。こちらも黄色の丸は同じだが、その中に今度は濃紺で四角が描かれている。ミーノは眼に力を入れるようにして、しばらくそのページを見つめていた。
「・・・わかりません。」
「どういうふうに見える?」
「さっきみたいに黄色い丸があるのはわかるけど、真ん中は白いもやもや。」
医師は今度は頷かず、真剣な表情で新しいページを開いた。大きな群青色の丸の中に赤い菱形。ミーノは諦めたような顔で首を振る。
「全部白くて、全然見えない。」
医師は十ページほどあるその冊子を一枚ずつめくっては、ミーノにどう見えるかを尋ねていった。様々な青と、赤や黄色など他の色合いがセットになっているページが続く。ふとロミは微かな違和感を覚えた。用意してあったみたいだ。この本、青と他の色がセットになったページが嫌に多い。まるでこういう症例のための本であるかのように。ロミは机に置かれた他の二冊の表紙を伸び上がるようにして見たが、無地の表紙に何の手がかりもなかった。
冊子を最後までミーノに見せてしまうと、医師はそれをぱたんと閉じ、他の二冊と合わせて仕舞いにいった。そして戸口から顔を出してモリー、と呼びかける。すぐに足音がして先程の女性が現れた。二人の声は聞き取れないが、女性の顔色がはっと変わるのをロミは見た。医師は最後に何事かを言いつけると、彼女を押し出すようにしてドアを閉めた。慌てて遠ざかる足音。ロミの心臓はどきどきと音を立てている。
「さて、君達にまず言わなきゃならないのは、このことをご両親に話す必要がある、ということだ。」
戻ってきた医師が言うと、弾かれたようにミーノは顔を上げた。
「どうして?僕の眼、すぐ治らないの?」
医師はミーノを労わるような眼で見つめた。いっそ憐れむような眼で。ロミの胸にまた違和感が広がった。
「それも含めてご両親と一緒に話さなければならない。これは・・・大事な話だ。今晩ご両親はお家におられるだろうね?」
医師の言葉が急に圧力を増した気がした。ミーノが不安な眼でロミと医師を交互に見ている。夕陽が沈もうとしているのか急に部屋が翳り、青色以外の色彩も全て奪われていった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
