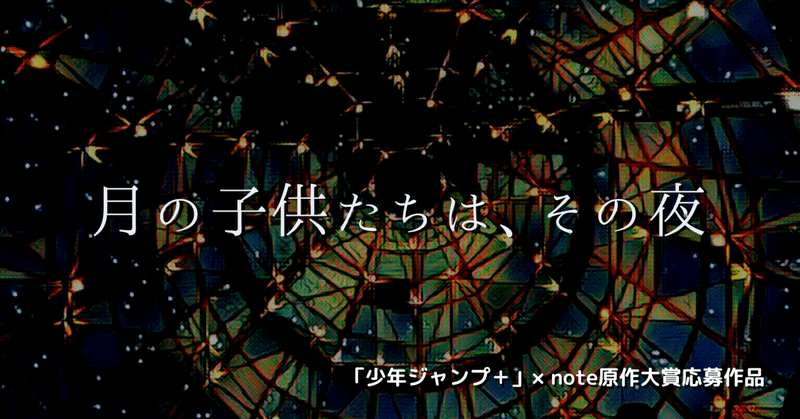
【小説】「月の子供たちは、その夜」第1話
〈M〉
周期百二十年のワルター彗星が南の夜空に出現して三日が経つ。予測よりも明るい等級となったそれは緑色の尾を長く引いて、地球から仰げば濃紺の空に留まり続けているように見える。世界はその話題でもちきりなのに、リュンはアメリカの研究施設に二週間ほど前から缶詰になっていた。NASAの惑星探査機が持ち帰った塵を調査する研究チームに呼ばれたからだ。詳しいことは知らないが、リュンが呼ばれるということは、磁気性の何かが新たに発見されたということだろう。私にとっては、リュンがいないということだけが濁った沼地のように胸に広がる。
「百二十年なんて嘘でもわかんないよね、この眼で次を見ることなんてできないんだし。」
リュンがアメリカに発つ前、彗星のことで私が言葉を漏らすと、リュンは静かな笑みを、横顔だけで返してみせた。
「僕達は数値で証明するしかないんだよ、ミュイ。その数値の正確さを増すために、観測したり計算したりするんだ。僕達の知らない先の世代のために。」
もちろんわかっている。わかっているけれど言いたくなるときがある。リュンがリュンであることをわずかにでも揺るがせようとして。でもそれが意味のない行為だということは、この長い日々の中で承知している。今まで、リュンがリュンでなかったことなど一度もないのだから。
私は今、アイに後ろから抱きすくめられる格好でブランケットにくるまり、ベランダの向こうの夜空を眺めている。窓は大きく開け放たれていて、ここ数日で急に身体に染みるようになった初秋の風が、裸の肩に心地よい。私はリュンの真似をして、時折こうして床に座り込んだり寝転がったりし、とても長い時間、空を見上げる。南の空高く月が見える部屋。リュンがこだわって探し歩いたマンションの一室。ふいにアイがくしゃみをする。引き締まった大きな胸が小刻みに動く。
「寒くないか?」
頭の後ろから声がして、私は首を振る。わざとアイの胸板に当たるようにぶんぶんやったら、おい、と頭を押さえられた。湯船に浸かって温まったのに、まだ下着姿のまま恋人同士みたいにくっつきあっている。さっきまではベッドの上で、向かい合わせでいろんな手順を踏んでいた。これがリュンならどんな感じだろう。その空想を、私は頭から締め出す必要がない。それは許されたことだった。私は存分に思いを巡らせる。これがリュンなら。私の身体を少し手荒に扱っていた、あれがリュンだったなら。私はもっと幸福だろうか。ほんとうのさいわい。『銀河鉄道の夜』でジョバンニが問い続けていたっけ。リュンと触れ合うことが本当の幸いなんだろうか。もう慣らされてしまった、決定的に何かが欠けているこの感覚は埋まるだろうか。アイがまた、大きなくしゃみを二回する。
「俺、寒いから服着るぞ。」
ブランケットをはだけてアイの胸から身体を離すと、急に身震いが出た。それでもまだ雲のない夜空を見上げて飽きない。秋の空にはあまり目立つ星がないけれど、私は意外にそれが気に入っている。冬が巡ってきて、どの角度からも完璧な星座であるオリオン座や、真っ白なシリウスがぐるぐる回り出す前の序曲。私達が季節を実感するのは、ファッションでもなければ食材でもない。いつだって空の星々だった。大学のサークル棟の屋上に寝そべって、並んで夜空を眺めた頃から。あの頃、それが世界のすべてだった。主流の天文部からはぐれた少人数の天文サークル。ちっぽけな校舎の屋上と落っこちそうな空と。あれから社会に出て時間が流れ、私達は天体に関することだけでは到底生きてゆけなくなった。たった一人、リュンだけを除いて。彼だけがあの場所に留まることを許されている。夜空が世界のすべてだった場所に。
「それにしても明るくなったもんだな。」
アイの言葉が、彗星のことだとわかるのに少し時間がかかった。空を眺めたまま物思いに耽るのはいつものことで、私は深く息を吐いた。振り向くと、長袖のTシャツにブラックジーンズという格好に戻ったアイが、間接照明の淡い明かりの下で簡易な望遠鏡を組み立てている。手際良く三脚を開きネジを締め、レンズを覗く。そのまま空に向けるのかと思ったら、壁を背に座る姿勢になっていた私の方へ焦点を合わせる素振りをしながら、鳳凰座だ、とおどけてみせたので、私は苦笑しながらブラと薄手のニットを拾って身につけた。胸の谷間に七つほくろがある。この場所に固まっているのが嫌で気にしていたのだけれど、アイはこれを初めて見た夜に、フェニックスとおんなじ並びじゃん、と繁々眺めてから唇をつけた。フェニックス。和名で鳳凰座。南半球の空に輝くその星座を、私は実際には見たことがない。アイはフェニックスの星一つ一つに舌を押しつける。アルファ星、ベータ星と呟きながら。そのうち私は我慢できなくなって、アイの頭を抱え込む。そのときアイの頭蓋は腕の中でなんだか小さく思える。フェニックスを舐めとられると思うと、私は行為の前からぞくぞくしてしまう。ほくろが密集しているのは今でも好きじゃないけれど、アイにそうされるこの部分を、疎ましくは思わなくなった。
リュンのこの部屋に置きっぱなしにしている数種類の紅茶から、ライチの香りづけがされているフレーバーティーを選び出し、ケトルを火にかける。リュンは部屋でまったく自炊をしないから、このコンロは私が紅茶用のお湯を沸かすためだけにあるみたいだ。私とリュンが飲むための。もしくは私とアイが飲むための。アイは大砲でどこかに狙いを定めるみたいに膝立ちになって望遠鏡を覗いている。目に馴染んだアイの姿。今でも変わらず私達のリーダー。天文サークルで部長だった頃そのままに。アイに従っていれば、私達は間違えることがなかった。土星の輪の美しいカーブを愛でたり、アイスクリームを掬い取りながら遠い星雲を観測したり、雨が降ればその雨の音を聴きながら部室で缶チューハイを飲んだり。アイに任せておけば日々は最良に過ぎていった。部員は皆、アイを拠り所としていた。もうポラリスと称していいんじゃない?そう言ったのは私より一つ上のラムだった。悔しいけど私達、忠実に北極星の周りを回ってるってわけね。あのとき顔を顰めたラムはちっとも悔しそうじゃなかった。
茶葉とたっぷりの湯を入れたポットを蒸らしていると、うっとりするライチの香りが満ちてきた。窓を閉めたアイが、ごつごつしたダイバーズウォッチを腕に嵌め直しながらダイニングテーブルにやってくる。彗星を眺めていたというよりは、気持ちを切り替えていたのだろう。私と身体を合わせた後は、罪悪感を特別な場所に仕舞い込むのに少し時間がかかる。そして全部どこかに置いてきたみたいなあっけらかんとした態度を取ろうと努めるのだ。
「なにそれ、すげえ甘い匂いじゃん。南国みたいな。」
新しく買ってきた紅茶とわかってくれたようで、嬉しくなってこくりと頷く。
「リュンと違って紅茶の入れ甲斐があるねぇ。」
「あいつは紅茶が酢醤油に変わってたって気付かんだろ。」
天文馬鹿、なのだ。特に月にかける情熱は空恐ろしい。だから、その昔誰かがリュンと名付けたのが定着した。Luneはフランス語で月を表すが、それはルナと同じ語源だ。ルナ、ルナティック、狂気。そう言えばリュンの居場所をはっきり把握していない、とふと思い当たる。
「リュンって今、アメリカのどこだっけ?ニューヨークとか?」
カップに口をつけていたアイは、漫画みたいにきつく力を込めた眼で私をぎろりと睨む。
「あのさあ、おまえそういうこと俺に訊くの、ちょっとは躊躇しろよ。」
それからもう一口紅茶を啜って、ワシントンDCだよ、と教えてくれた。そうだ、ワシントンDC。ホワイトハウスのあるアメリカの首都だという初歩的な知識しかない。私にとってリュンはいるかいないか、百かゼロなので、場所にはあまり関心がないのだ、とアイに説明しようかと思ったが、やめた。アイが言いたかったのはそういうことではないだろうから。私、このまま行けるところまで行くことに決めたの。いつかリュンに宣言したとき、リュンは微笑んで頷いた。何かを少しだけ諦めてしまったような微笑みだった。同じことをさっきアイに言ってみたら、アイは苦しそうに眉を寄せて羽を広げるフェニックスに顔をうずめた。そんなアイの表情は、私を落ち着かない気持ちにさせる。
ライチの香りの紅茶を飲み干したら、アイは帰ってゆくだろう。私もベッドのシーツを替えてカップを片付けたら、鍵をかけて彗星降る夜へと出ていく。リュンを待つ暮らしへ。ほんとうのさいわい。私はそのことに満足している。
〈I〉
ブラックホールに引き込まれつつある星の破片を想像する。相対性理論ではブラックホールの周辺は空間同様に時間もひずんでいて、地球からもしも観察できればその破片はいつまでも留まって見えるという。俺達三人にお誂え向きの喩えじゃないか。
昨日の夜、リュンの部屋のベッドでまたミュイを抱いた。本当に欲しいものがお互い手に入らないから、その代用だとでも言うように。このまま出口のない毎日を送り続けるわけにはいかない。そのことばかり考えていたのに、ミュイはこのまま行けるところまで行くと言い切った。自分のどこかに怯えを感じ、それはミュイを乱暴に扱うことに繋がった。それでもミュイは落ち着いたもので、こちらを安心させるように俺のうなじを撫で続けていたのだから困ったものだ。
朝から少し薄雲が出ていたので心配したが、午後になると雲は東へ一掃され、絶好の観測日和となった。比較的長い百二十年周期の彗星出現という一大イベントのため、勤務先の天文台では子供達を集めての観測会が間もなく始まる。普段は大望遠鏡の調整やプラネタリウムの点検に精を出している俺みたいな機械屋も、こういう時は手伝うことになっている。子供は昔から好きだったし、子供相手に星の見つけ方や神話について語っていると、大学時代を思い出した。後輩の頭をはたきながら望遠鏡の調節の仕方を偉そうに教えていた頃。二年下だったミュイは理系部員ばっかりのサークルで初の文学部生で、俺もリュンも面白がったものだった。絶妙の調和がとれていた頃。懐古趣味はないつもりなのに、最近そういった記憶が油断すると矢のように降りかかってくる。成す術もなく射抜かれ、思い出の鋭利さに息を呑む。
リュン、俺は今、おまえを傷つけたいんだ。こうして子供達の歓声を楽しみに、沢山の双眼鏡や望遠鏡を並べているこの瞬間も。おまえがアメリカの東海岸で微弱な磁気データを集めていたのと同じとき、俺はおまえの部屋でミュイと裸の胸をつき合わせていたんだ。おまえの見たことのないあのパーフェクトな配置のフェニックスに吸いついて、一つずつ舌で数を数えたんだ。反らせた首を下から見上げる構図、きつく瞼を閉じて嫌々をするみたいに顔を振る瞬間。俺はおまえの知らないミュイを幾つでも挙げることができる。だがそれを告げたところでリュンは全く傷ついたりしない。そんなに具体的に話すなよ、などと苦笑で済ませるのが関の山だ。傷つくのは俺の方だろう。悔しくて混乱し、結局最後は本当のところに行き着いてしまうだろう。俺が欲しいのはミュイじゃなく、おまえなんだ。俺の気持ちを拒まなかったのなら、おまえには選択する義務があるんだ。罵倒の後で、今度は哀願するかもしれない。心も身体もそっくり俺に渡してくれと。いくら今までどおりのリュンがそこにいても、もう同じ宇宙物理学の研究仲間とか親友などという配役には戻れないのだ。何を訴えたところでリュンには一ミリの打撃にもならない。惑星みたいに瞬きもせず、選べないんだよ、と無残にも宣告するだろう。変わらない優しさでもって。どうしてこんな袋小路に絡めとられてしまったのだろう。男に恋愛感情などこれっぽっちも持ったことのなかった俺が、あの夜、リュンに魅せられてしまった。
観測会が始まると、天文台前の広場は親子連れでいっぱいになった。子供達は緑がかった光の筋を見上げて大声を上げ、自慢げに夜空を指さした。熱心な男の子が二人、作業着姿の俺に走り寄ってきて、彗星の明るさについてなかなかユニークな質問をしてきたので、こちらも熱を入れて説明した。
一段落して腰を浮かせたところを見計らって上司が声をかけてくる。
「逢沢君、今朝のメール見た?」
見ましたけど。返答に詰まってぶっきらぼうな答え方になってしまう。
「エンジニアの募集なんてなかなかないと思うんだけど、興味ないかな。ウチから出せれば嬉しいんだよね。期間は長いけど滅多にできない経験だし、若かったら僕が行きたいぐらいだよ。ちょっと考えてみて。」
上司は陳腐なドラマによくあるみたいに俺の肩をとんとんと叩いて行ってしまう。ニュージーランドの天文台で交換研究員の募集。研究職二名と技術職一名。三年期限で延長の場合もあり。今の職場に籍は置いたままにできるとスタッフメールにはあった。異国の天文台に勤務できるなんて、心が動かないわけがない。日本とは全然違う星が頭上を覆う国。未知の望遠鏡に新しい顔ぶれ。それでも今の俺はそこに飛び込む勇気を持てない。勇気?それは言葉が間違っていないだろうか。そんな格好のいい言葉ではない、もっと黒々した塊。俺には手放せないものがあるのだ。手放せないし、手にもできないものが。
〈L〉
探査機が持ち帰った物質が珍しい磁気性を帯びているからデータ解析に参加してほしいということで、一カ月ほどワシントンDC近郊の宇宙研究センターに滞在することになった。世間はワルター彗星のニュースばかりだし、調査チームの他のメンバーも目の前にある宇宙の塵と同じぐらい彗星に関心を向けていたが、僕にとってはどちらもたいして興味を惹かれる対象ではない。おそらく今、日本にいたとしてもそれは同じだったろう。僕はセンターを出てホテルへの道を辿りながら、少し開けた場所へ出ると空を仰いだ。月齢零、つまりは新月の月が望めるはずもないけれど、それでもその気配だけでも感じたくて。明るい光源である月の隠れた今回の彗星接近は観測にとっては絶好のタイミングだ。だけど僕は上手く元気が出せないでいる。もやもやした、名前のつけられない不安が胸の中心に居座っている。大丈夫。僕は自分に言い聞かせる。見えなくたってお月様はそこにいるから。歩いても歩いてもお月様はついてきてくれるから。この地球にいる限り。それでやっと少し安心した心持ちになって、僕はホテルのエントランスの重いドアを開ける。
僕は普段、天体物理学の研究所で月の磁気を研究している。地球の衛星である月が、どれだけこの地球という惑星に影響を及ぼしているのかを調べているのだ。研究員の中には、学生時代から同じことをやり続けている僕を軽蔑している人間もいる。興味深いテーマなら他にいくらでもあるだろうと言いたいのだ。もちろん僕にもそれは理解できる。まだ解明が不十分な遠い宇宙。膨らみ続ける宇宙の境目や、更にその外側のこと。新たに誕生したブラックホールが放つ微かな熱量のこと。でも僕は月からのデータを集めて数式を修正したり、新しい仮説を立てたりし続ける。僕の興味のほとんどすべては月という天体に向けられている。月のことなら何もかも知りたいし、月の研究に関しては世界一でありたい。そのくせ本心では研究なんてどうでもいいと思ってもいる。画面上のデータを解析したり、研究所の大型望遠鏡で月面のクレーターを詳細に観察したりするより、この自分の眼で月をただ見上げていられたら。それだけで毎日を過ごしていけたらどんなにか僕は安らかだろう。部屋の床に寝転んでベランダの向こうの月を眺めると、僕は女神の視線を身体中に感じることができる。彼女が僕を見守ってくれているのがわかる。その青い光が窓から差し込んできて、僕の身体を撫でてくれる。僕にはもう何もいらない。この今の暮らしも、足元の硬い大地も、太陽さえも。現実とそれ以外のものの境界が極端に薄らいで、僕は夜空を浮遊しているような気持ちになる。月は更に僕を煌々と照らしている。その感覚を僕は、幼い頃からずっと持ち続けている。毎晩僕は月を眺め、夜空を飛んだ。僕にはそれだけしかなかったけれど、それで本当に充分だった。
重い荷物を背負って部屋に帰ると、ダイニングのテーブルでミュイがうたた寝をしていた。テーブルには紅茶のカップと薄い文庫本が置かれている。宮沢賢治か中原中也。ミュイは彼らの詩の一節、特に星や銀河が出てくるそれをよく音読してくれる。でも僕はそのフレーズを思い出すことができない。荷物を置くため寝室のドアをそっと開けて中に滑り込む。望遠鏡や双眼鏡のケースが、出ていった時とは違う位置に置かれている。きっとここでミュイは彗星を観ていたのだろう。おそらくはアイも一緒に。僕はむしろほっとした気持ちになる。もう随分前から、ミュイとアイが関係を持っていることは知っていた。僕には二人は似合いのカップルに思えた。どうして二人は僕なんかに執着するんだろう。僕はそんなのには全然値しない。あの想いをお互いに向け合ってくれたなら、それが二人にとっても最善なんじゃないだろうか。そう、僕にとっても。
「あれ、リュン、帰ってたの?」
振り返るとミュイが立っていた。嬉しそうにはにかんで、前髪を気にしてひっぱりながら。うん。僕は頷き、バックパックに手を突っ込んでビニール袋に入った長方形の箱を引っ張り出す。これ、お土産。ミュイはびっくりしたように眼を見開くと、白い手を差し出して袋を受け取る。それから手にしたものを物珍しそうに眺める。
「無理しないでいいのに。仕事のときは私のことなんか、忘れてていいんだよ。」
僕は困ってしまう。忘れていた時間もたくさんあった。ミュイのことも他の誰のことも。それを伝えた方がミュイは安心するのだろうか。僕が言葉を返せずにいると、ミュイは含み笑いをし、今度はつくづくと僕を見つめる。宝物を前にした子供のような表情をして。やがて箱の包みをぱりぱりと破ると、
「わー、チョコレート。お茶淹れてくるね。」
と、狭い部屋なのに駆け出すようにして行ってしまった。僕はベランダの窓から夜空を眺め上げる格好で床に座る。新月から数日経っただけの月が、この曇り空で見えるわけがない。気持ちがぐっと不安定になる。月の気配のない夜。荷物の中から大事な資料を取り出し、洗濯物などを仕分けしていると、ふわりと甘い匂いがして、一つずつ形の違うチョコレートと紅茶を載せたトレイを持ってミュイが戻ってきた。僕の座っている横にそれを置くと、背中に背中をくっつけられるよう、くるりと向きを変えて座る。これがミュイの、いつものスタイル。彼女はいろいろ僕に試してみて、背中だけを譲歩させたのだった。パブロフの条件付けの実験みたいに根気よく。今では僕は、それをわずらわしく思う気持ちは起きない。特に今日みたいな月の見えない夜には。ミュイもそれをわかっている。だから彼女は大抵、月のない晩にやってくる。雨の日とか曇りの日とか新月の夜とかに。ごめんね、ミュイ。僕は胸の中でだけ呟く。美味しいね、これ。アメリカどうだった?ミュイが僕の肩甲骨の辺りに頬をもたせかけている。
〈M〉
PCにデータを打ち込み続ける。書名、本の識別番号、書店名、冊数。小さな出版社の事務部門はたった二人だ。理系の出版社で、扱っているのは専門書がほとんど。内容はほとんどわからない。それでも今日みたいに新しい天文図鑑の注文をさばいていると少し嬉しい。後ろのページにはもちろんリュンの名前があったから、月に関する記述は間違いなくその手になるものだ。もちろんそうでなくても、天体の写真を眺めると充分心穏やかになる。それに付随する物語や詩が頭に浮かぶ。宮沢賢治の描く白鳥座の二重星アルビレオや石炭袋をこの目で確かめたくて、天文サークルを覗いた。天文部は敷居が高かったから。そしてリュンやアイに出会った。アイは部長としてサークルを率い、毎週のように観測会を企画したり半年ごとの合宿計画を練ったりしていた。それに対してリュンは不思議な存在だった。部室にいることはほとんどなく、サークル会議にふらりとやってくる時は大抵白衣姿。頭に寝癖がついたままのときも多く、研究室で暮らしているのではないかと後輩達に噂される人だった。そして夜の観測会にはほぼ皆勤でやってきた。木星と土星の接近を望遠鏡でとらえようと部員がはしゃいでいる横で、リュンはただ屋上の柵にもたれて全然違う方向を眺めていた。そこには必ず月が輝いていた。
「おまえもちょっと輪に入れよ。木星の衛星が結構きれいに見えてる。」
アイがそんなふうに呼びかけると、リュンはゆったりと身体を起こしてこちらに向かってくる。闇の中から浮かびあがるように。微笑んでいるとわかり、私はその静謐な印象から目を離せなくなる。宇宙のどんな現象より、リュンの方が私には神秘だった。
だからリュンが私に初めて興味を持ってくれた夜のことはよく覚えている。観測にいい加減飽きたメンバーがてんでにビールを飲んだりポテトチップスを齧ったりしていたとき、私はアイと月の神話について話していた。当時はまだ工学系に転向する前で、アイはリュンと同じく宇宙物理学を専攻していたが、天文に関する伝承とか神話にも驚くほど詳しかった。ポリネシアだかミクロネシアだかには母なる月の神話があって、私達は皆、月の子供ってことになってるんですよ。アイが知らないと言ったその話を少し得意になってしていると、ふいに空気の密度が増す気配がして、リュンが傍にきた。それ、ほんと?私は心臓が膨れてくるような緊張を覚え、途端にその知識の信憑性に自信がなくなった。答えられずにいると、おまえさー、とアイが笑い出した。
「こえーだろ、その顔。おまえ、月の話になると眼の色変えすぎ。美結ちゃんってさ、宮沢賢治とか、宇宙の出てくる物語を調べてんだって。そういうアプローチ、俺等には新鮮よな。」
アイの方に視線を向けていても、リュンが私の横顔を窺っているのがわかった。月の子供か。リュンは何かを懐かしんでいるような声を出した。
「その国の子供達はきっと幸せなんだろうね。」
たまらずリュンの顔を振り返って、その表情に私は打たれた。なんて慈愛に満ちた顔をするんだろう。リュンの興味を共有したいと思った。文学的な方面から月のことを調べたら、これからも私に関心を持ってくれるだろうか。私は月にまつわる伝承を集めては、観測会で会うたび、リュンに披露してみた。リュンは楽しげに耳を傾けてくれたけれど、最初の夜に感じた距離まで近づいてくれることは、もうなかった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
