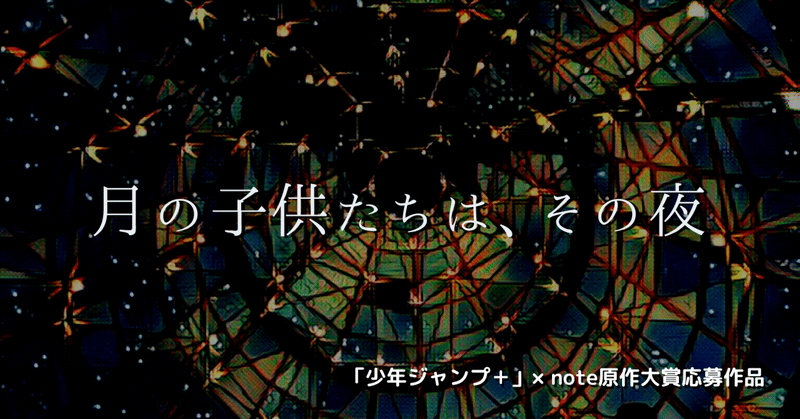
【小説】「月の子供たちは、その夜」第2話
〈М〉
冷たい雨が降るなか、駅前のカフェの自動ドアを潜ると、すでにラムはテーブルに陣取って赤ペンで何やら一心に書き込んでいた。ごめん、待った? 声を掛けると、慌てて散乱した答案用紙らしい紙をかき集める。
「ううん、採点してたから大丈夫。」
サークル仲間だったラムは、今では隣町の中学校で理科の教師をしている。私達は一つの季節に一回ぐらい会って、近況を報告しあう仲だ。ラムはラムの、私は私の言える範囲の近況を。どう、相変わらず忙しい?注文を終えてから私が尋ねると、ラムはうーんと首を傾げ、ついでに思いっきり伸びをしてみせた。
「先生的な忙しさにはもう慣れちゃったからね。でも今三年の担任だから、それはまあ大変なんだけど。」
ラムの口調は昔どおりさばさばしている。ラムレーズンアイスばかり食べてるから、ラム。あの頃サークルでは符丁のようにニックネームで呼び合うのが流行っていて、私達はいまだにその呼び名を使っている。
「でも何か哀しいときあるよね。先月の彗星んときもさ、私、校庭で観測会企画したのに、ウチの学年ほっとんど誰も来なくて。受験も大事だけど百二十年に一度だよ、百二十年に。それ言うと父兄がキレるから言わなかったけど。」
それから前のめりになって、ミュイは観た?と尋ねてくる。私は砂時計とともに運ばれたアールグレイのポットを少し覗き込みながら頷く。
「観たよ、リュンの部屋で。リュンはいなかったけど。」
私がリュンのアメリカ行きのことを説明すると、ラムは眉を持ち上げる。信じられない、と言いたい場面のいつもの癖で。そして実際、信じられない、と声に出す。
「すごいよねえ、それで付き合ってられるって。そもそもさ、私はリュンのことがいまいち苦手だったし。何考えてんのかいつもよくわかんないじゃない、あの人。」
私はラムのこういう物言いが好きだ。特にリュンに手厳しいところが。私は黙って、ラムが想像しているだろう私とリュンを思い描いてみる。世間に普通に存在する幾多の二人のように、映画を観て笑い合ったり、バルで美味しいワインを飲んだり、お互いの腰に手を回したりすることを。何でもないはずのことに内在されている眼が眩むほど神々しい光のことを。けれどそんな光はリュンには必要ないのだった。リュンに必要なのは月の光だけ。惹かれ始めた頃からそれをもっとちゃんとした質量で理解していたら、まだ引き返せる場所で背を向けていただろうか。そんなことが頭をよぎって我に返る。なぜ急に背を向けるなんて。砂時計はとっくに落ち切ってしまっている。慌てて金属のストレーナーをカップに引っ掛け、紅茶を注ぐ。
「そうそう、最近アイと連絡取ってる?」
しばらくお互いの仕事の話をしたあとで、ラムは急にそんなことを言い出した。私は落ち着いて、たまにリュン経由で、と悪びれもせずに嘘をつく。ひやりともどきりともしなかったことに我ながら感心する。そう、悪いことなど何もしていない。リュンに照らして正しいことであるならば、私は何だってできるし嘘ぐらい簡単につく。そっか。ラムはちょっと考えるように視線を彷徨わせる。
「ここんとこアイ、全然連絡くれなくなっちゃったから心配してたんだけどね。彗星んときも。前はサークルの延長でいろいろ企画してくれてたじゃない。」
彗星のときは天文台の観測会があったみたいだし。私がそう答えると、ラムにとってはそこまで重要な事ではなかったのか、まあそうだよね、と言ったきりまた別の話題に移ってしまった。もう昔の仲間は、ラムも含めて新しい世界で暮らしていた。複雑になった人間関係と、その一つである過去のサークル仲間。それはせつないことだけれど、そのせつなさを掘り進めると、どこかで羨望を掘り当ててしまいそうな気もした。あの濃密な星空の世界から別の次元へ踏み出せた人。私はしばらく、ラムの話を聞きながらアイのことに思いを巡らせていた。過去の思い出になりそうな関係を現在進行形に繋ぐ努力をしていたのがアイだったのに。アイがラムや昔の仲間に連絡を取らなくなったのは忙しいからなんかじゃない。そんな理由で、アイはアイであることをさぼったりしない。アイがドアを閉ざしがちになったのは、混乱を抱えているからだ。日を追うごとに深くなってゆく痛み。それを私は何とかしてあげたいと思う。アイにはいつまでも冷静沈着とした私達の部長でいてほしいから。皆を導くポラリスであり続けてほしいから。アイは一人で抱え込んでしまっている。迷う必要などないのだ。リュンを好きになる気持ちは私が一番よくわかる。あの磁場に踏み込んでしまうと容易に抜け出すことなどできない。それがアイで、私はよかったとさえ思っている。アイならリュンを傷つけないだろうから。間違ったことなどではない。リュンを愛して、でも私が必要なときは必要としてくれたらいい。私もそうしているつもりだから。
私だってちゃんとした返事をもらったわけじゃない。アイの車でそう口にしたのはいつだったろう。蠍座のアンタレスが鈍くて赤い光を放っていたから、夏だったことは確かだ。学生の頃、サークルの皆で出掛けた川原まで車を走らせてもらう。確認したいことがあった。あくまで最終確認。いくら隠していても私にはわかる。わかりすぎてこちらが苦しくなるぐらい。昔みたいに花火もお菓子もなく、私達は停めた車の中でしばらく黙って夜空を見上げていた。
「ねえ、アイってリュンのこと、好きなんでしょ?」
そう尋ねると、アイは静かに息を吸い込んで、いっぺんに吐き出した。アイに全然似合わない、地を這うような溜め息だった。
「まあ、おまえにはばれるわな。俺さあ、自分でもおかしいって思ってんだけど。卒業直前までそんなこと考えたこともなかったのに。」
髪の毛を手でぐしゃぐしゃにするアイが近しく思えた。私と同じ。リュンに惹かれ、一緒にいたいと願う。それが思うようにいかない。世間一般で言うところの充足には足りない。
アイはしばらくハンドルの上で組み合わせた両手に突っ伏していたが、意を決したようにしゃんと起き直った。
「こないださ、リュンに打ち明けたのよ、もう黙ってらんなくて。ミュイと付き合ってるのはわかってるし、俺は別に二人の仲をどうこうしたいわけじゃなくて。ただ話して・・・話して蔑まれたかった。気持ち悪いでも何でもよかったのに、」
なのに、無反応だった?アイが言い切れずにつっかえたところを補うと、アイは困惑したような表情で私を見た。どう説明しようか少し考える。ボリュームを絞ってかけていたFMを、アイはそっと切った。
「私もやっとわかってきたんだけど、多分リュンって自分に想いを向けられるのが怖いみたい。だからそういうとき、反応できなくなるの。スイッチオフ。それは相手がアイだからとか男か女かとか関係ない。だって私もそういう反応されたし。」
意味がちゃんと掴み切れないのか、アイは随分長いことハンドルに置いた自分の手を見つめていた。それからゆっくりと口を開いた。
「なあ、おまえらの関係って、」
「付き合ってることに、私はすることにした。周りにどう言おうとリュンは嫌そうにしないし、否定もしないから。でも、私だってちゃんとした返事をもらったわけじゃない。彼氏彼女らしいことは何にもしたことない。アイと同じ。付き合ってる風を装ってて、アイを苦しくさせてた?」
初めての生物を見るみたいな眼で、アイは改めて私を見た。リュンの柔らかな眼差しとは対照的な鋭い瞳をしていると思う。
「それって・・・俺の比じゃないじゃん。おまえ、辛いだろ。」
辛いという言葉はストライクゾーンからだいぶ外れているように思えた。リュンの傍にいられたら、私は幸せ。辛いはずなどない。向き合ってくれなくても、意思表示をしてくれなくても。興味の対象が他に、手の届かない夜空にあっても。手を握ることすらできなくても。ほんとうのさいわい。
「ねえアイ、手を、握ってみてくれない?」
あのとき、無意識的に言葉が出たと言えば嘘になる。誰かに触ってほしいと思った。もう長い間、誰とも触れ合っていない。辛いなどとは微塵も認識していなかったのに。誰か。リュンがその候補から外れるのなら、同じ痛みを持っているアイに。アイはしばらく態勢を変えないままハンドルへ前かがみになっていたが、やがて私の身体を助手席から引っ張り上げるようにして、両腕で身体ごと包んでくれた。クーラーの効いた車内で、アイの胸は温かかった。人と触れ合うってこんなに温かだったんだ、と驚いた。私はそのことをすっかり忘れていた。
アイはここのところ、より一層疲れた顔をしている。そして前より少しだけ乱暴に私を抱くようになった。何かに怯えているように。何かから逃げるように。私の胸に顔を埋めているとき、アイの顔は子供みたいにみえる瞬間がある。そういうときには私はリュンを思うのをやめて、アイの頭を抱き締める。ママみたいな気持ちになって。
カフェを出ると私は傘を開き、駅へ向かうラムとは反対に歩き出す。
「じゃ、今日もリュンのところに寄るから。」
ラムは呆れたような顔をしてみせて、こんな大雨にご苦労様なことで、とおどけて手を振った。私は胸の中でラムに反論する。大雨なのに行くんじゃなくて、大雨だから行くの。月の光がないとリュンは元気がなくなるし、それにこういう晩はいつもより少しだけリュンが優しくなるから。いつも優しいリュンだけど、月のない夜はいつもよりちょっと多めに私と向き合ってくれる気がする。だからごめんねお月様。私は傘をわずかに持ち上げて暗い空を見上げる。悪いんだけど今日は一日雲に塗り込められていて。リュンを私の元に返して。私は早くあの部屋に辿り着きたくて、靴が濡れるのも厭わず足を速める。ビルを吹き抜けてくる風が、耳元でごお、と鳴った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
