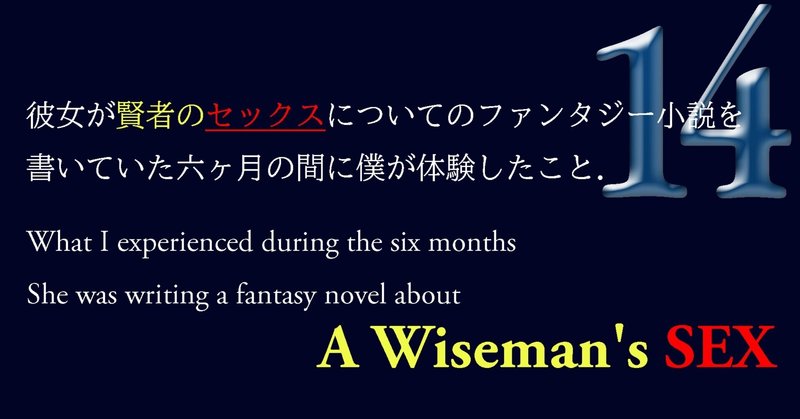
賢者のセックス / 第14章 一等星と六等星 / 彼女がセックスについてのファンタジー小説を書いていた六ヶ月の間に僕が体験したこと
大磯
四月も四週目に入った平日の午後、僕たちは品川駅の一二番ホームで東海道線の熱海行き各駅停車に乗った。大磯駅まで一時間。僕たちは隣り合って座っていたけれど、会話はほとんどなかった。かといって二人ともスマートフォンを見たりすることもなく、音楽も聞かなかった。ただただ、僕たちは無言で隣り合って座っていた。時折触れるソラちゃんの肩から体温が伝わってくるたびに、僕のみぞおち辺りで何かが蠢いた。
大磯駅で降りてタクシーに乗って一〇分後。僕たちは大磯プリンスホテルのロビーにいた。ここに来ようと言い出したのはソラちゃんである。二日前の夜、書斎の中のソラちゃんから突然こんなメッセージが届いたのだ。
会社の福利厚生のポイントが溜まってるから、大磯プリンスホテルのスパで使いたい(21:26)。
君も来るよね(21:38)。
僕は少しだけ逡巡したけれど、結局はこんな返事を書いた。
大丈夫。行けます(21:44)。
本当なら大喜びでついていくはずなのだけれど、何故か僕の心は沈んだままだった。ソラちゃんのことが嫌いになっていたわけでは、もちろんない。それどころか、僕の頭の中の仕事と家事以外の全ての部分はソラちゃんのことでいっぱいなのだ。
でも、この時の僕はソラちゃんとどう接して良いのか、全くわからなくなっていた。少しでも余計なことをすれば、ソラちゃんと僕の関係を決定的に壊してしまうのではないか。そんな恐怖感が僕を虜にしている。年度始めの業務ラッシュと小説執筆で寸暇も惜しいはずのソラちゃんがわざわざ僕を一泊旅行に誘う理由もわからない。もしかしたら、慰労会代わりなのではないか。ここで別れ話を切り出されるのではないか。そんなことすら僕は考えてしまう。
僕たちが案内されたのは、最上階にあるオーシャンビューのツインルームだった。久しぶりに見る本物の海だ。荷物を置いて手を洗った僕は、ソファに座ってぼんやりと波を見つめていた。水平線の近くを少し大きな貨物船が横切っている。
突然ソラちゃんが僕の隣に座った。座っただけでなく、僕の方に身体を寄せている。四月に入ってから、まだ一度もソラちゃんとキスしていないことを僕は思い出した。セックスも四〇日以上していないはずだ。
そのまましばらくの間、僕たちは黙って海を眺めていた。こんな状況で、なお肩を抱くことも、手を握ることすらも出来ない自分に僕は呆れていた。セックスのパートナーがセックスをしなくなると、ただの知り合いになってしまうわけだ。
「場所を変えたらどうなるかなあと思って」
突然発せられたソラちゃんの言葉に、僕は困惑した。
「場所を変えるって、ここに来るってこと? ここに来るとどうなるの?」
「私たちさ、今まで私の家でしかしたことないじゃない」
「……セックスを?」
「そう。だからね。5W1HのWHEREを変えて実験してみようかなって」
「ここで?」
「うん」
そう言いながらソラちゃんは僕の肩に頭を預けてきた。いつもの香水とは違う、深い森の中のような不思議な匂い。僕はまた自分がソラちゃんとセックスをするらしい、ということに不思議な感慨を覚えていた。
肩に頭を預けたままのソラちゃんが尋ねた。
「ねえ、キスして良い?」
僕たちはゆっくりと唇を重ね、お互いに少しだけためらってから舌を絡ませた。故郷の駅のコンコースの風景を見ながら僕はそっとソラちゃんの肩に手を回し、徐々に手を下に降ろしていった。でも、僕が目指すものはどうしても見つけられなかった。唇を離したソラちゃんが、僕を見上げてにこりと笑った。
「これ、フロントホックなんだ」
神聖器官
それから僕たちは順番にシャワーを浴びて、ベッドの上で裸で抱き合った。カーテンは開けられたままだったけれど、僕もソラちゃんも気にしなかった。ここを覗けるのは鳥だけだし、海と空と雲を見ながら抱き合っていると、自分たちがこの世の始まりに顕れた神々のように思えた。高御産巣日神と神産巣日神もこんなふうにセックスをしたのだろうか。
僕はソラちゃんの太ももの内側に二回、唇を触れさせてから、まだ少し水気が残っている陰毛をそっとかき分けてクリトリスを探した。これまで僕たちは明るい場所でお互いの身体に触れるセックスをしたことが無かったから、僕はソラちゃんのクリトリスを見たことがない。
それは、とても小さな薄桃色の、優しい丸みを帯びた器官だった。でもこれはクリトリスの目に見えるほんの一部分で、実はクリトリスはペニスと同じくらいに大きな器官なのだと、以前にソラちゃんが教えてくれた。ただ、女の人の体の中にほとんど全てが隠れているから小さく見えるだけなのだと。
それどころか、クリトリスとペニスは途中までは同じ細胞から同じ手順で作られるのだそうだ。この話を聞いた時の僕は不思議な気分だったけれど、こうして間近でクリトリスを見てみると、何故かすんなり納得出来てしまった。僕にペニスがあるようにソラちゃんにはクリトリスがあり、僕が性的快感を求めてソラちゃんにペニスを差し出すように、ソラちゃんは性的快感を求めて僕にクリトリスを差し出す。何も違いはない。性的快感は誰にでもあるのだから、それを感じるための器官が備わっているのは当たり前だと思う。味を感じるために舌があるのと同じだ。
ソラちゃんのクリトリスは、尊厳をまとった神聖な器官に見えた。ペニスが神聖ならば、クリトリスだって神聖なのだ。この二つはほとんど同じものなのだから。だから、僕は祈りを込めて舌の先でクリトリスにそっと触れた。ゆっくりと。最高級の洋菓子を舌先で味わうように。
やがてソラちゃんの膣口から透明な液が溢れ出してきて小さな雫になった。僕は記憶にないくらい固く大きくなっている自分のものにコンドームを着け、ソラちゃんの中へと入っていった。僕のものは三度ソラちゃんの中を行き来して、四度目でソラちゃんの一番奥に辿り着いた。そこで僕は動くのを止めて、ソラちゃんと抱き合ったまま目を閉じた。
ソラちゃんの息遣いやシーツがこすれる音に混じって、西湘バイパスを行き来するトラックの音がかすかに聞こえている。僕たちは時々キスを交わしながら、ずっと抱き合っていた。性器を繋げた状態で抱き合いながら、僕たちは必死で言葉を探していた。僕は何か言わなければと考えていた。ソラちゃんも同じことを考えているのがわかった。それは触れ合った肌を通して僕に伝わってきた。僕たちは肌と粘膜を介して深くわかりあえるのだ。
でも、それだけでは足りない。何かが足りない。
最初に口を開いたのはソラちゃんだった。
「ごめんね。……ごめんなさい」
「何を謝ってるの?」
「何だろう? 何かな。謝りたくなったから」
「ソラちゃんは謝るようなことはしていないと思うけど」
「謝ったらだめ?」
「だめじゃない。どんな言葉でも良いからソラちゃんの言葉をもっと沢山聞きたい」
「私たち、最近全然喋ってなかったもんね。セックスもしてなかったし」
「キスもしてなかったよ」
「ほんとそうだね」
「ソラちゃん不足だった。ソラちゃん不足で死にそうだったよ」
「ごめん」
「今日だけは言わせて欲しい」
「何を?」
「ソラちゃん、愛してる」
僕は止まっていた腰をゆっくりと動かした。ソラちゃんの息づかいはすぐに甘い喘ぎ声になり、僕の腰の動きが早くなるにつれてそれは叫び声に近くなった。僕は天谷戸の青々とした田んぼの幻を見ながら、ソラちゃんの中に大量の精液を放った。
射精を終えた僕はそっとソラちゃんの膣から僕のものを抜き、コンドームを外して捨てた。ソラちゃんの傍らに戻った時、賢者が僕とソラちゃんの間にいる気配を少しだけ感じた。
褒められたい
その後、僕たちは太陽が沈むまでベッドの上で色々な話をした。この四〇日間あまり感じていたソラちゃんとの距離感と辛さと破壊衝動について、僕は素直に話した。久しぶりに賢者タイムがあったことも。それを聞いたソラちゃんは、少しだけ照れくさそうに目を伏せた。
「私も最近ずっと辛かったんだよ。辛かったっていうか、何でこんなに書けないんだよってずっと思ってた」
「書けなかったの?」
「書いては消して、書いては消して。ずっとそれ。書いててドキドキもワクワクもしなくて。君と二人で調査を進めてたときには、あんなにドキドキワクワクしてたのに、何でなんだろうって」
でも、この時の僕たちにはその理由がわかりかけていた。この小説は僕たち二人が力を合わせて作っていたのだ。もしかすると、この小説が生まれ出るために僕たち二人を呼び寄せていたのかもしれない。だから僕たちは手を繋いでいる必要があったのだ、きっと。
それからソラちゃんはベッドの上をごろごろと転がりながら、書きかけの小説のことを詳しく話してくれた。僕がセックスの最中に見る風景と街が見ている夢、縄文時代から現代まであの土地で営まれてきた人びとの生殖活動、そして人びとが神話に託してきたものというモチーフは固まっていて、主人公カップルが様々な謎を解きながら事態の真相に迫っていく話になるのだという。
ソラちゃんが一番悩んでいるのは物語のクライマックスをどう作るかで、それによって書き出しから全く違うものにしなければいけないらしい。
「伝奇ものっぽくするか、セカイ系にするか、いまだに悩んでてさ」
「それ、どう違うの?」
「伝奇ものだったら読者の不安感を高めていかなきゃいけないから、暗い場所や古いものの描写を多めにする。神社とか古文書とかね。文体はねっとりとした感じ。何かを知っているらしい謎キャラも出す。セカイ系はボーイミーツガールもののバリエーションだから、若い子だけ出して今風の日常生活を淡々と軽めの文体で描きつつ、突然女の子にとんでもないことが起こる展開にする」
「女の子に起こるんだ?」
「典型的にはね。『最終兵器彼女』とか「まどマギ」とか『ペンギン・ハイウェイ』とか。でも男の子でもそれは構わない。「エヴァンゲリオン」のシンジくんは男の子でしょ」
「あれもセカイ系なの?」
「元祖セカイ系だよ」
「ソラちゃんはどっちを書きたいの?」
「それがわからないから悩んでるの。どっちのバージョンでも最初のところを書いてみたんだけど、なんかしっくり来なくてね。あの街が言ってるんだよ。違うよ、自分はそんなものを書いて欲しいんじゃないよって」
そう言ってソラちゃんは枕に顔を埋めた。
僕はそっとソラちゃんの頭をなでた。
するとソラちゃんが枕に顔を埋めたまま「もっと撫でて」と言ったので、僕は何度もソラちゃんの頭を優しく撫でた。僕が手を止める度に、ソラちゃんは「もっと」と言って僕を促した。僕に頭を撫でられながらソラちゃんはつぶやいた。
「私もさ、たまには褒められたいよ。いつもいつも褒める側でさ。疲れちゃった」
「褒められてないの?」
「褒められてるけど」
「言ってることの意味がわからないよ」
「みんな、結果は褒めてくれるんだよ。東大入って凄いとか、外コン入って凄いとか、起業して成功してるの凄いとか」
「うん」
「でも小説は結果が出てないから、誰も褒めてくれない」
「そうなんだ」
「でも私は褒められたい。頑張ってるねって。頑張ってるの偉いねって」
「うん」
「だから、褒めて」
「ソラちゃん小説頑張ってるの、偉いよ」
「もう一回」
「ソラちゃん小説頑張ってるの、偉い」
「ちゃんはいらない」
「え?」
「ちゃんはいらない。二度言わせるな」
「ソラ、小説頑張ってるの、偉い」
「あと一回」
「ソラ、小説頑張ってるの、偉い」
「満足」
そう言いながらソラちゃんはごろりとベッドの上を転がって仰向けになった。ついでにソラちゃんは掛け布団を持っていってしまったので、僕は少し寒かった。でもしょうがない。レディファーストだ。
神々の光
日が完全に落ちた頃、僕たちはホテルのレストランで食事を取った。僕は一年ぶりの外食で、しかもソラちゃんと二人でする初めての外食でもあった。ソラちゃんの向かいの席に座った僕は、安物のカジュアルな服しか持って来なかったことを軽く後悔していた。モスグリーンのブラウスとゆったりした白いパンツを身に着けてメイクをしたソラちゃんは、僕の恋愛感情の分を割り引いてもなお神々しく光り輝いて見える。魔女というより女神。僕たちは不釣り合いだ。少なくとも見た目に関しては間違いなく。
夕食の後、ソラちゃんは僕を従えてスパに向かった。
「このために来たんだからね!」
ソラちゃんの全身から、久しぶりの魔女オーラが漂っているのがわかった。
大磯プリンスホテルのスパは三階にフロントと更衣室があり、四階に各種のサウナと屋外温水プールがある構造だった。一足先に着替えを済ませて四階の長椅子で待っていた僕を見つけたソラちゃんは、有無を言わさず屋外プールへの同行を求めた。左手には、防水ケースに入ったスマートフォンがある。左の首筋には僕がうっかり付けてしまったキスマークが見えているけれど、ソラちゃんは全く気にしていない。
「これよ、これ」
ソラちゃんが西の空を指差して叫んだ。
「これが見たかったんだ。ほら見て。富士山!」
たしかにソラちゃんの指差す先には富士山の形をした巨大な山があった。僕は実際の富士山よりも、正三角形の上の方を切り欠いた図形に富士山っぽさを感じるらしい。富士山の向こう側には壮大な星空が広がり、そこから見下ろせば小田原らしい街の灯から左の相模湾に向かって小さな光の帯が水平線まで遥かに続いている。伊豆半島の海岸線だろう。神々の光と、人々の光。
プールに人影はまばらだった。ゴールデンウィーク前の平日、しかも世界はいまだ新型コロナウイルスのパンデミックの中にある。僕だってソラちゃんに誘われなければ、ここに来ることは無かっただろう。
プールの端に手をかけて夜空を見上げていたソラちゃんが突然、いつもとは違う声で何かの暗誦を始めた。バリキャリ魔女の低い声ではなく、セックスをしている時の甘く高い声でもない。まるで冬の夜空の星の光を音にしたような、とても澄んだ声だった。
ああ! 子どもたち、これらの名前をよくおぼえておきなさい! とても美しい名前だ! そうして、大空に、天頂に、きみたちの頭上に、地平線のぐるりに、それら私の少年時代の星々をさがしておくれ! それらの星は、必ず同じ道を通って、きみたちの少年時代の上にのぼり、通り過ぎてゆく……
大人になれば、星のことをもっとよく知るようにはなる。けれど、暗い大空のひろがりの中で星たちが光っているのは、きみたちのためなのだ。そのひろがりから生命(いのち)がわたしたちの方へやってくる……
そして生きるということはたぶん、夢なのだ、ただし、きみたちが星を眺めているなら、それは美しい夢……
『犬のバルボッシュ』福音館文庫 2013年
水と風の音の合間に聞こえてくるソラちゃんの声に、僕だけでなく周りにいる人たちもそっと耳を傾けているようだった。僕がソラちゃんに近づいて行くと、ソラちゃんはまるでそうするのが当然といった顔で、僕の胸に背中を預けてきた。ソラちゃんが着ていたのは黒地に何かの花がプリントされた、露出度のかなり低いワンピースの水着だったけれど、それでも僕の心拍数は上がった。
「今のは何?」
「アンリ・ボスコが書いた『犬のバルボッシュ』って小説の中に出てくる一節。素敵でしょ?」
「それもファンタジー小説なの?」
「広い意味ではね。今の日本でファンタジー小説と呼ばれているようなものには繋がらないけど。アンリ・ボスコはフランスの小説家でね。四回もノーベル文学賞の候補に上がったんだよ」
「どんなお話なの?」
「主人公の少年が伯母さん、といっても年齢的にはもうおばあちゃんなんだけど、この伯母さんと一緒に伯母さんの実家に行くの。ところが二人が家を出ると次々にあり得ない現象が起こって、それを避けるために伯母さんはどんどん脇道に入り込んじゃう。でも伯母さんは何も気にしないで、いきあたりばったりに旅を続ける。二人は色々なアクシデントに遭遇するんだけれど、その度に通りがかりの誰かが助けてくれて、最後は少年の家に無事に戻って来る。種明かしをすれば、少年は伯母さんの夢の中で伯母さんの人生を旅の形で追体験していましたってなるんだけど」
「誰かの夢の中を旅するんて、まるで僕たちみたいだね」
「そうかな?」
ソラちゃんは僕に背中をくっつけたまま、夜の水平線を見つめている。
「色んな人が、誰かの夢の中を旅していると思うよ。たまたま私たちは人じゃなくて街が見ている夢の中に入っちゃったけどね。でも……」
水の中でソラちゃんの左手が僕の右手を掴んで引っ張った。僕は左手を伸ばしてソラちゃんの右手を探した。すぐにソラちゃんの右手が僕の左手を捕まえた。今、僕たちは恋人同士に見えているのだろう。
「最後は自分の夢の中を歩きたいよね」
「街の見る夢から出るの?」
「出ても良い。出なくても良い。夢の中で見る夢だって、夢なんだよ。君は能を見たことはないの?」
「ないです。すみません」
ソラちゃんがクスクス笑った。
二人の写真
「能でよくあるのは、脇役が見ている夢の中で主役が昔の夢を見ているって構造でね。ただし、それは過去に向かう夢なんだよ。主役は過去を懐かしんで、それで満足して成仏しちゃうの。でも、私は嫌だな。誰の夢の中にいるのでもいいから、自分の未来を夢に見ていたい。……って今、思った。私はまだ成仏したくないから」
僕は黙ってソラちゃんの言葉を聞いていた。ソラちゃんの両手が水の中で僕の両腕を掴んでいる。
「でね。今日わかったんだ。私にはまだ君の力が必要。街が見る夢の中で私の夢を見続けるためには、君が必要」
ソラちゃんは僕の両腕の中で空を見上げている。僕はソラちゃんの言葉の続きを待った。
「アンリ・ボスコも酒見賢一も、私から見たらあそこで光ってるアルクトゥルスやスピカみたいなものでね。ノーベル文学賞候補四回とか、もう意味わからないレベルの人じゃない。二人とも子供の頃からずっと見上げてたお星さまなわけ。彼らだけじゃないよ。君の好きな『ソードアート・オンライン』だって『キノの旅』だって『ノーゲーム・ノーライフ』だって本当、すごいと思う」
ソラちゃんからラノベのファンタジーの名前がスラスラ出てきたので、僕は少し驚いていた。
「私もね、あんな一等星じゃなくていいから、せめて六等星くらいにはなりたいんだ。一次すら通ったことがないけどさ。それでね。何で私は小説を書いてるのか今日ずっと考えてたの。有名になりたいのか。褒められたいのか。自分の理想を追求したいのか。どれもあるんだけど、これが一番大事だなってさっき思ったのは」
そこでソラちゃんはふっと黙ってしまった。しばらく待ってから僕は尋ねた。
「思ったのは、何?」
「笑うなよ?」
「笑うかもしれない」
「笑ったら殴る」
「殴られても良いけど」
ソラちゃんは小さく肩をすくめた。
「……繋いでいきたいんだよ。光を。空いっぱいのお星さまから私のところに降ってきた光をさ。ファンタジーの光を。ナンシー・スプリンガーやマイクル・ムアコックやひかわ玲子や上橋菜穂子からもらった光を、次の誰かに。私が一等星にならなくても良い。せめて、光を繋ぎたい。今、笑ったでしょ。あとで殴るからね絶対」
たしかに僕は笑っていたけれど、それはソラちゃんが素直に話してくれたことが嬉しかったからだ。でも、殴られるのは構わない。
「君って賢くて気が利くんだけど、おっとりしてるところもあって、私がどんな突拍子もない話をしてもとりあえず聞いててくれるよね。そういう人と定期的にゆっくり話をしないと、私は名前の通りにふわふわとどっか飛んでいっちゃうんだなあって今日、思ったの。一番大事なことを見失っちゃうぞって。私が地に足をつけておくために、君が傍にいてくれると嬉しい。だから、もう少しだけ私に付き合ってよ」
「少しだけ、なの?」
僕の質問への返事は無かった。
不意に僕はソラちゃんとキスがしたくなった。でも、この時の僕にはそれをする勇気が無かった。だから、キスの代わりにソラちゃんを少しきつめに抱きしめて我慢することにした。ソラちゃんは特に抵抗しなかった。僕たちは温かい水の中でぴったりとくっついたまま、空を見上げてふわふわと漂っていた。
しばらくしてソラちゃんはプールサイドに置いてあったスマートフォンを拾い上げ、僕に渡した。
「ねえ、写真撮って。ナイトプール。インスタに上げて自慢するから」
僕は一〇枚ほど構図を変えてソラちゃんの写真を撮り、スマートフォンを返した。するとソラちゃんは僕の腕を引っ張って笑った。
「一緒に写ろうよ」
「僕とソラちゃんが? そんなの撮ってどうするの?」
「私たち、二人で写った写真って一枚もないでしょ。だからさ、記念に撮っておこうかなと思って」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
