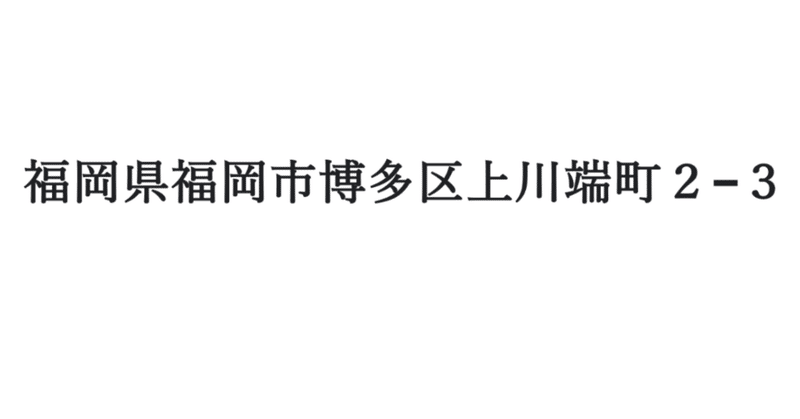
シリーズ 昭和百景 「博多・祇園マーケットの戦後 喜劇王 小松政夫をつなぐ点と線」
幻のマーケット
かつて戦後の一時期、その場所は強い魅力を放ち、衣食を求める、擦れたゲートルを履いた復員者や、着のみ着のままの引揚者を惹きつけた。そこは、どこまでが住居で、どこからが廃墟かさえ分からぬ、境区を不敵に融合させた異界ともいえた。
2007年夏、博多の街で、そんな誇らしくも懐かしいヤミ市の「末裔」に遭遇した。それは、私が捜し求めていたヤミ市マーケットの原風景だった。
引揚者の戦後が始まった場所
1945年8月15日の終戦直後から、博多は大きな賑わいを見せた。中国方面からの引揚者は博多に、ロシア方面からは舞鶴へと続々と到着する。そして、旧日本軍の復員船ももちろん、博多の港へと到着した。
博多の街は、復員し故郷へと向かう者たちが、列車に乗り込む直前、まずは腹を満たすために最初に訪れる“補給基地”となったのである。博多は「戦後」という新たな時代の礎の地ともいえた。
博多は終戦直前、B29による大規模な空爆を受けて、市街地は壊滅的な打撃を受けている。その日、筑豊のある町にいた永井龍雄は、上空高くを、キラキラと太陽の光を反射して銀色にきらめく無数の機体が横切っていくのを見たという。
上空高く、その銀色に輝く大型の魚群の周囲では、銀紙が舞うように、小さな光がさんざめいていた。B29を追撃に向かったのか、小型の戦闘機が空中戦を演じているようだった。
「しかし、ありゃいかん。かなわん。ぜんぜん数が違った」という永井の言葉を裏付けるように、福岡には焼夷弾の雨が降った。そして福岡は焼け、終戦を迎えたのだ。
その直後から、福岡の街角、至るところにヤミ市が立った。そのなかでももっとも栄えたもののひとつが祇園のヤミ市だったのである。そこには、日本でも有数のヤミ市が広がっていた。
上海で終戦を迎え、帰国後は焼け跡の渋谷駅前で屋台を出していた星野林吉が、最初にたどり着いたのも博多だった。林吉はかつてこんなことを言っていた。
「博多では、軍を免除されるときに五百円をもらいました。それとどこまでも乗り降り自由の切符を一枚渡されました。東京に帰るにしても、お腹が空いて仕方ないから、まずはなんか食べないといけないと、それで博多駅のそばのヤミ市で食べ物を探したんです。それで、イカのスルメかなんかを買ったでしょうか。ほかにもついつい買ってしまって。でも、物がないときだったから、ヤミ市で売っているものも高くて高くて……。渋谷についたときには百円を切ってしまっていました」
終戦当時、博多駅は現在の場所より、かなり西寄りにあった。現在のJR博多駅博多口を出ると、目の前を大博通りが走る。その通りに沿って西へとくだり、国体通りとぶつかる周辺、現在、大型のパチンコ店がある付近が博多駅だった。つまり祇園はかつての博多駅前に栄えたヤミ市だったのである。
洋品店リラと上海帰りのリル
博多山笠で有名な櫛田神社にほど近い場所に、気になる小路があった。初夏の熱気も、その小路に入れば、穏やかに冷まされてしまうようだった。そこは不思議な冷気を孕む場所だった。はじめそれは、モザイク模様に組まれた路上のタイル地が見せる錯覚のせいかと思ったが、違った。
その小路に「リラ」というとても小さな洋裁店が、ひっそりとある。その店の、シャッターの収納を兼ねた看板の文字が、知らず、意識を惹きつけていたのだと、ある日、気づいた。
店といっても、奥行きは2メートルもないだろう。外からでも、店のなかは一目ですべてがうかがえてしまう。
店の脇やまわりを、居酒屋や小さなスナックに囲まれたリラには、今はもう、骨董屋か博物館でしか見ることのできなくなった、黒い光沢を放つ、シンガー社製の足踏みミシンが置いてある。奥の壁際だった。
はじめてリラの前を通ったとき、たしか、こんなことを思った。〈リラって変わった名前だな。まるで……〉
その小さな洋裁店の名前は、戦後の一時期、大流行した歌謡曲「上海帰りのリル」を思い出させた。「上海帰りのリル」は、かつて第二次世界大戦中に上海の日本人街で見かけた女性が日本のどこかに戻ってはいまいかと、戦間期の大陸を懐かしんだ歌だった。リルとリラ……。
博多には復員者や引揚者の日本人に交じって、中国の軍人もまた、占領軍として上陸してきた。
少し前に取材したことのある、東京の新橋や銀座のヤミ市で商売を成功させた王長徳という元中国軍人の話をすると、それまで穏やかだったリラの女主人の表情が一瞬、曇った。
「儲かった人の話? それはいいの……。いい思いをした人の話は、いいの……」
その中国人を知っているわけではなさそうだったが、目には明らかに嫌悪感を漂わせた。
博多でいちばん古い建物
しかし女主人が、その場所にリラを構えたのは終戦直後のことではなかった。昭和30年代の後半に来たという。
「その頃はね、まだ中州がとってもよかったの。今とはぜんぜん違ったわよ。今は洋服がサイズが合わなくなっても直そうとすることもないでしょ。今も中州には少しだけそういう人が残ってるけど、昔は今とはぜんぜん比べものにもならないくらいに中州の景気がよかったから」
それは、石炭がまだあった頃ですかね、と私は訊いた。
昭和30年代後半といえば、それは九州の炭鉱が相次いで閉山を迎える「最期の瞬間」ともいえた。「宵越しの金を持たない」炭鉱マンたちが落とす派手な銭とともに中州の勃興はあったことを、女主人の話は匂わせていた。
「うーん、どうかしらね。でも、とにかく中州の栄えかたはぜんぜん違ったわね」
リラから中州までは、それこそ、橋ひとつ隔てたわずかな距離にあるといっていい。そんなことを話している際で、話し込んでいる私の姿に遠慮したのか、店の外に、クラブのママらしき気品と貫禄の漂う中年の女性が立っていた。リラに直しに出した服かドレスを受けとりに来たのだろう。
商売の邪魔をするわけにもいかず、辞去しようとする間際、女主人はこんなことを付け加えた。「中もね、もうすごい賑わってたんですってよ。この建物は終戦直後からあったって聞いてるわよ。権利関係が複雑すぎて、取り壊すに壊せなくて、戦後から今までずーっと残ってるのよ。博多じゃいちばん古い建物だって聞いてるわよ」
なか……?
店を出た私は、数メートル離れた場所に、まるで防空壕へのトンネルのような、人ひとり入るのがやっとの暗く小さな入口をみつけた。その“穴”は奥へと伸びていた。人の出入りはなかったが、そこが中への入口だとは、言われるまでまったく気がつかなかった。
その建物こそは、終戦直後から今なお残る、「祇園マーケット」だった。リラは、そのマーケットへの扉を開いたのだった。幾度となく通り過ぎていて、その暗い穴の向こう、その中に、終戦直後にもっとも賑わったマーケットが広がっているなど、一度として想像したことがなかった。
穴の前に立ち、上を見上げて、息を呑んだ。三角地に立つ、リラの入るその三階建ての建物の形状は、かつて王長徳が日本にマーケットをつくるときにモデルにした上海の三角地菜場のそれだったのだ。
戦後、新橋、自由が丘、学芸大学前とヤミ市のただなかで近代的なマーケットを建てた王長徳の放った言葉が甦った。
「三角の場所は道路が交わって、人が集まるから。そういう場所は栄えるんですよ」
王がマーケットを建てた場所も、多くが三角地だった。博多・祇園の小路脇にぼっこりと開いた縦穴には、微かだが風が流れ込んでいくようだった。
午後4時をまわり、追い山慣らしの始まった櫛田神社の境内には、山笠の「櫛田入りタイム」を告げるアナウンスと、それに続けて沸く男衆や観客の歓声が響いていた。
そんな頂点に達した喧騒と熱気を、その穴は静かに、小さく吸い込んでいるようだった。祇園の三角地にある祇園マーケットは間違いなく、終戦から62年の時間を経て、今もひそかに呼吸していたのだ。
200歩のなかの小宇宙
博多を訪れる観光客に知られる麺屋「かろのうろん」は、祇園マーケットの三角形の建物が立つ一画にある。この「かろのうろん」の前から建物を一周して戻ってくれば、歩幅50センチ弱の足で196歩を数える。三角形の一階部分は、建物の内部にすっぽりと入る祇園マーケットと、その外側の通りに面した商店とで占められている。その上階はアパートで、現在も入居者が暮らす。
この200歩に満たない小さな場所で、今となっては「ひと知れず」と言っても過言ではないほどに密やかに、祇園マーケットはその命脈を保っていた。
マーケットには4つの入口があった。
仄暗いマーケットに根を張る「貸台」
朝の5時半、この祇園マーケットは仕入れを終えて店に戻ってくる店主たちの出入りでもっとも賑わう。原付のバイクが魚の入った発泡スチロールを載せて戻ってくれば、また別の入口には、仕入れたばかりの野菜が詰まったダンボール箱が山積みされる。
そこには男の姿だけでなく、女の姿もあった。お世辞にも「若い」と呼べる風貌の者はいない。その建物の周囲をぐるりぐるぐると3周も4周もしながら、そんな暗く小さな穴から出入りする商店主らしき人影の行き来を眺めていたが、店主がなかに入っていった後ろから、意を決して、体を突っ込ませた。
日差しは、通りを挟んで東に建つ萬行寺の境内高くから容赦なく降り注いでいた。夏の朝に慣れた目が、穴に入った途端に視力を失い、それは一瞬、恐怖を呼んだ。運動靴の先が引っかかる足元の怖さを拭おうと、のめるように突っ切ると、そこには不思議な回廊が延びていた。
雨漏りでやられたのだろうか。天井の板は歪み、ところどころ破れ、腐り、くすんだ傘の真下に垂れ下がった裸電球が熱を発している。人気は少なく、店とはいえ、そこにはまるで地面の上にそのまま台を敷いて野菜を並べたかのような、青空市場とも屋台ともつかない、広い空間が広がっていたのだった。それは、写真や本でしか知らなかったヤミ市の光景そのものだった。
周囲わずか200歩に満たない建物のなかは、想像をはるかに超えた空間の拡がりを感じさせた。だからだろうか、キーンという耳鳴りとともに、カランカラン、カラランコロンと、下駄の音が近づいてくるような幻聴さえ覚えた。
実際にはそれは、国体通りに面した別の入口の脇に店を構える魚屋の主人が乗る、原付バイクのエンジンの音だった。戻ってきた主人は今では探すのも難しいほどの粗末な小型テレビをつけ、店なのか居間なのかわからぬ入口の内側すぐの場所に椅子を置き、ひと仕事が終わったとばかりに寛ぎ始めたのである。
横を見れば、今は誰も使っていないと思われる生鮮品を並べる銀色の台の脇の真っ暗な場所で、この主人の女房らしき女性が横になっていた。
この主人の店もいたく不思議なものだった。生鮮台に魚も切り身も並ばず、無数の鯛を泳がせた大きな生簀が、暗がりに置かれただけだった。水槽はだいぶ冷えているのだろう、出入口の脇に置かれているためか、外気に触れて、表面には小さな水滴が密集していた。
マーケットのなかは3メートルか4メートルごと、あるいは明らかにそれより短いものもあったが、台は各々きちんと仕切られ、それぞれに店子やオーナーがいるとのことだった。ところどころスッポリと、虫食いのように空いている台の上には、丁寧にも、「貸台」と書かれた告知と、連絡先の電話番号が記されている。
その「貸台」の正面で八百屋を営む奥さんに頼むと、気さくに仄暗いマーケットのなかを案内してくれた。最初に奥さんが指さして見せたのは、天井だった。
「これ、見てちょーだい。もう、年々、天井が下がってきて危ないのよ。でも誰が修理をしたらいいのかとか、ぜーんぜん、わからないの。もう危なくって、危なくって。ここはね、建物の権利が複雑すぎて修繕もできないのよ。凄いでしょ、この建物。まあ古いまんま、よくもってるわよね」
なかば朽ちかけている天板の間から梁がのぞき、その梁のコンクリートさえ、表面が削がれ、なかの鉄筋がむき出しになっていた。
「いやーこれは凄い。しかし、よくこれだけのものが終戦直後から今まで残っていますね」
私の言葉に、奥さんはくったくなく、むしろ胸を張って応えた。「そうでしょ。まあ、なかは凄いけど、建物は丈夫なのよ。この間の地震でもなんともなかったんだから」
地震とは、2005年3月20日に福岡県地方を襲った、震度6弱の地震のことだった。この地震で福岡市内の高級マンションでさえ壁や内壁にヒビが入るなどの被害があったと、伝えられていた。
だが、「地震でもなんともなかった」という建物の住居部分に、現在どんな人物がどのような縁で住み着いているのかは、もはや祇園マーケットの店子でさえ容易には知ることができないようだった。
ある日の朝、このアパートの住人らしき年配の女性がなにやら水仕事をしているのに出くわしたことがあったが、こちらの姿を認めると、話しかける隙もなく、すぐに部屋のなかへ引っ込んでしまった。すべてが住居かと思えば、たまたま立っていたその場所のすぐ脇には「上海エステ」なるマッサージ屋が店を構えてもいた。
祇園マーケットの一階に入る八百屋の奥さんが、野菜を置いている台をめくって、ふと、こんなことを話してくれた。
「ほら見て。これね、この板の下にコンクリートがあるでしょ」
奥さんの膝の上、こちらの膝のすぐ下のあたりまでの高さに、見れば巨大なまな板を横に立てたようなコンクリートの板が、通路と直角に交わるかたちで固められている。さらにその上に、横長の、まるで壁を仕切る大きな建材パネルのような、これもまたコンクリートの板が乗っている。そのまた上に、材質さえわからぬ、白塗りのベニヤ板のようなものを敷き、そこに野菜などを並べているのである。
奥さんは、その台を指さした。
「この台はね、終戦直後の、それこそヤミ市のときからあるんですって。もともとここにヤミ市があって、そのうえに建物を建てたんですってよ。だから、これがヤミ市のときからの唯一の名残りね。もともとはこんなものの上にそのまま物を置いて売ってて、それでその場所にこういう建物をつくったわけよ」
足元に目を向ければ、床とは名ばかりで、土の上に直にコンクリートを流したようにも見える。そのためか、路上の凹凸を均さずに、そのまま固まったようでもあった。
「路上ヤミ市起源説」を裏付ける構造
それにしても謎なのは、この祇園マーケットの構造だった。仮に、上空からコンピューターグラフィクスで骨格だけを透かしてみれば、2つのV字を交差させるようなかたちで展開しているようにも見えるだろう。あるいは、大きな三角形のなかに、その一辺を利用したもう一回り小さい三角形を作ったような按配にも。とにかく、三角のビルの一階部分、祇園マーケットだけは、また別のV字、あるいは三角構造になっていた。
奇妙にも思えるこの造りこそは、この屋内型マーケットの「路上ヤミ市起源説」を裏付けているようでもある。祇園マーケットの敷地のほうが当初の姿で、その動かしがたい場所を取り込み、可能な限り敷地を延長して確保した末の「三角地」であったのか。三方に鋭く延びる三角形の建物は、ビルを建てた者々が抱えていたであろう飽くなき土地への執着を今に伝えていた。
ところで、いびつな三角構造を重ねているからだろう、この建物には空に吹き抜けた中庭が2つできた。V字を交差させたこの建物は、外見の単純さからは想像できないほどの複雑さを同居させていた。同時にそれは、三角という形状がもたらす絶対的な安定感と無縁ではなかった。この建物の設計者があえてこの構造を採用したのであれば、それは恐ろしいまでの卓見だといえた。奇数の支点が育む安定性は、数理学上の基礎概念としても知られている。
たとえば、カメラの三脚などはこの概念を利用したものである。四脚ある椅子はがたつくことがあるが、三脚では絶対に脚が浮くことはない。V字構造を重ねたかたちの祇園マーケットの建物は、いわばこの安定性を二重にまとっている構造になる。戦後60年もの時間を凌いだ後になお、震度6弱の激しい揺れに耐える剛さは、建物の内部構造を眺めて、初めて納得できた。
1945年の終戦の日からほど遠くない博多で、この建物は、まさにどっしりと焼け跡に腰を据えた。
「小松政夫さんなら知ってるんじゃない」
「ついこの間まで、そこの乾物屋のおばあちゃんが生きてたんだけど、つい2、3ヵ月前だったかしら、亡くなっちゃったの。あのおばあちゃんが終戦直後からずっといて、なんでも知ってたのにね」
奥さんにとっても、この建物の素性とかつての全貌を知る古老の死は、至極無念といった様子だった。その奥さんが続けた。
「でも、ここね、終戦直後に、あの小松政夫さんが住んでたんですってよ。上にね。上にいたんですって。それで、博多に来るたびに、そっちの『かろのうろん』に来て食べていくらしいのよ」
笑いにドラマにと、今も多くの人びとに愛される俳優の小松政夫さんが、かつて祇園マーケットに住んでいたのだと、奥さんが、まるで自分だけのアイドルとの思わぬ縁を無邪気に、自慢するように繰り返した。奥さんは、中庭を隔てた隣りの通路から、また別の魚屋を呼び寄せて、念を押すように言った。「ねっ、小松政夫さんもいたのよねっ」
魚屋も迷いなく相槌をうち、ちょうどこの上じゃないかな、と住居部分の上階へ指を上げてみせた。俳優「小松政夫」は、祇園マーケットの希望でもあるようだった。
「今はみんなそれぞれ、中州とかお客さんを持ってるから、そっちに卸したりして商売をしてるけど、そりゃ終戦直後は買い物に来る人で、このなかはもうびっしり人が埋まってたんですってよ。小松政夫さんなら、きっと知ってるんじゃない」
祇園マーケットのなかには、魚屋や八百屋などもっぱら同業種の店が集まっていた。それは現在の店舗の立地戦略からは考えられないことだった。競合店が同じ場所に店を構え、ひしめきあうなど、商売のイロハに反しているようにさえ思える。
しかし、東京・上野のアメ横もそうであるように、ヤミ市の跡地だったといわれる場所では、こうした同業種が軒を連ねる場所が多いのも事実だった。それは権利や権益を確保するにあたっては有益な形態だったのだろう。数こそ力、なのである。アメ横も祇園マーケットも、商業空間としては時代遅れにさえ見えながら今日まで生き延びてこられた理由は案外、そんな単純なところにあるのかもしれない。
小松政夫さんは終戦直後の祇園マーケットで何を見たのだろうか??。
八百屋の奥さんの無邪気な喜びに、いつしか、ブラウン管の上で覚えた小松さんの顔が笑いかけ、胸が高鳴ってくるのだった。
小松政夫少年の風景
小松政夫さんの持ちネタに、中学生が学生服の詰襟を立てて背広風に装い、ストリップ劇場に潜り込むというものがある。シャッシャッっと、まるで氷板を包丁ででも掻いているような涼しげな手つきで首の後ろから襟を立てる演技は、小松政夫が生来の役者であることを改めて感じさせる。
『楽屋の王様 ギャグこそマイウェイ』(竹書房)というDVDにも収録されている、この小松さんのコメディが、博多での体験をネタにしたものであることを知ったのは、この夏だった。
祇園マーケット4階の「舞台」
「クツひもをほどいてね、それを、立てた詰襟のまわりに巻いて。ストリップ劇場の入口に行くと、『あんた、中学生じゃないのか』なんて言われるわけよ。それで『いや、違います』なんて言ってもばれることがあってね。それで、先生にカーン、カーンなんてよく殴られちゃってね」
そんな小松さんが少年時代を過ごしたのが、祇園マーケットだった。かつて福岡でもっとも栄えたと語り継がれる祇園。終戦から60年の時間を超えていまもまだ建つ祇園マーケットの建物で、終戦直後、9人家族の小松家は暮らしていた。
自身の自伝的作品である『のぼせもんやけん』(竹書房)のなかで、小松さんはその場所をこう記している。
「僕の家は、博多駅からほど近い、山笠で名高い櫛田神社の裏門のすぐそばの、瓦町というところにありました。当時では珍しい豪華四階建てのビル!」
えっ、4階建て?
小松さんと会う前、これは記憶違いではないのか、と思っていた。国体通りを中洲へと向かう右手に立つ祇園マーケットの建物は、商店の入った1階部分の上は、どう眺めても3階までしか数えられなかった。
「戦後、なーんにもない焼野原の真ん中に、まさしく白亜の殿堂が建っていたんだから」
当然のことながら、そんな鮮やかな小松さんの記憶が間違いであろうはずはなかったのだ。
「あそこに住み始めたのは昭和22年か23年頃だったなあ。かなりモダンな雰囲気だったね。それでほら、屋上のまた上に部屋があったんだ。もうそりゃ、当時としては設備も最新でね。窓も左右に開くのじゃなくて……なんて呼ぶのかな、下から上にあげて開くやつで、外国の窓みたいだった。イタリア風のだって聞いたことがあるよ」
今でも外壁は乳白色に吹き付けられてはいるが、おそらく完成直後の建物は、終戦直前に大空襲に見舞われ、それこそ焼土と化した博多の土地でひときわ目を引いたに違いなかった。
1階部分の内部には、魚屋、八百屋に乾物屋と今でいう大手スーパーの食品売り場さながらの「祇園マーケット」が広がり、夕方ともなれば買い物に訪れる客で狭い通路はいっぱいになった。
「想像を絶する賑やかさでね。夕方になると、客を呼び込む声が響いたんですよ。『シャーシャーシャーシャーイラッシャー』なんて声で、客がビッシリだった。ひとの洪水ですよ」
その祇園マーケットは、2階と3階部分が賃貸のアパートになっている。そして、国体通り沿いの一角だけが、変則的に4階建てになっているのだった。この通りに面した一角の2階から4階までが小松家だった。その窓の外には――。
「国体道路は天皇陛下が来るっていうのでつくった、いわゆる50メートル道路だけど、その国体道路を挟んでうちのちょうど正面に、まだその頃は呉服屋があってね。反物を売ってたんだけど、子供心にあるとき、『おじさん、それ一尺より短いよっ』って言ったら、『子供はだまっとけ!』なんて言われたこともあったかな。この50メートル道路のところに、夜は屋台が並んでね、天ぷらから、ラーメン、寿司までね。金魚すくいなんかもあったけど、一杯で60匹も捉まえるのがいてさ」
毎年夏が近づけば、国体道路を見下ろす小松少年の部屋のほぼ正面に、山笠が立ち、そして、博多どんたくの大きな舞台が組まれると、祇園の町は一気に夏の暑さに突入する。
「6月の終わり頃になると、舞台を組み始めるでしょ。『もっと右ー、もっと左ー』なんて言って、大人たちがやってるわけ。そんな掛け声を聴くのが楽しみでね。どんたくも、今みたいに企業のスポンサー絡みじゃなかったからね。そこでギターやったり、みんながいろんな芸をするわけ。で、そういう芸が終わると、芸人は飲ませてもらうわけで、そこ以外にもそういうステージがあっちこっちにあったの。博多の人たちは、みんなこういうステージを見て育った。それに、そういうステージもそこだけじゃなくて、あっちこっちにあったからね」
福岡は全国でも有数の芸能人輩出県として知られるが、その芸達者な風土は博多の町なかだけに留まらない。炭鉱で栄えた九州の旧産炭地域全体では、早くから楽団演奏会や観劇が庶民のかけがえのない娯楽として根付いていた。九州を代表する歓楽街・中洲の「呑む、食う、打つ」の粋な所作のなかには、「観る」ことも溶け込んでいた。
小松少年が連日、そんな舞台で三々五々繰り広げられる芸を眺めていた時代、「ちょっと贅沢をしようと思って中洲に行くと、キンスズっていう洋食屋があって、そこは50円だった。かろのうろん屋は15円だった。でも、中学生のときに一個5円のコロッケを45日間食べ続けたことがあったかな。うちの姉が、祇園小町なんて言われるほど美人だったこともあって、姉目当てのお兄さんたちが『ねーちゃんによろしく』なんて、くれるんですよ。それを毎日、食べ続けた。あと、クジラの肉のビフテキっていうのがあった」
博多の町で異彩を放つ「白亜の殿堂」とはいえ、風呂は銭湯だった。
「だから、カメの湯とかムサシ湯とか、あたりはどこに行っても風呂屋だらけ。冷房なんかはまだなくて、夏は風呂屋に行くと扇風機があるぐらい」
そんなある日、小松少年は思い立つ。
「4階に上がってみようと思った。それで、そこを舞台にしてチケットをつくって客を呼んで、みんなに見せようと思った」
国体道路から眺めるどんたくの舞台と、集まる群衆、それを取り囲むように夜ともなれば屋台が連なる。いつしか、窓外に見下ろすそんな賑やかな祭りの絶え間ない拍動が、小松少年のなかに芽生えた新しい情熱を育んでいったのだろう。今も記憶に残るこの情景を、小松さんは「テキヤの檜舞台」と呼んだ。
「だから、わたしの笑いは違う。ほとんど人から教わったもんだけでやってきた。観て聴いて、体験したこと。笑いは焼け跡からだね。祇園マーケットの4階での舞台が、演技の開眼だったね」
「白亜の殿堂」の過去・未来
この祇園マーケットのビルは創業者どころか所有者さえはっきりはしないが、今でも、小松政夫さんの父がオーナーだという説は根強い。
「親父は博多の紳士録には必ず名前が載るような人でした。服はいつも英国製。靴も必ずオーダーメイド。銀縁眼鏡に口ひげを蓄えた、絵に描いたような明治の紳士でした」(小松政夫著『のぼせもんやけん』竹書房)
「そんなこともあって、その建物でも一番いい場所を、4階まで全部使うことができたのでしょうね。うちの親父が建てたと俺は理解してた」
ただ、そこにどのような経緯と資本で「白亜の殿堂」とさえ呼ばれたモダンなビルが建つことになったのかは、もはや小松さんも覚えていない。
「たしか、引揚者連合会とか厚生会とか、そういうのがあって関係していたような気もするなあ」
子供の頃の遊びの話は懐かしい。
「3時45分と5時になると紙芝居屋がきてね。ドラとかキリキリキリなんて音まで立ててね。太鼓を使ったり、ヒューなんて音を出したりもして。そこに、ポンポン菓子とかキビ団子売りとかもありましたね。でも、祇園は博多を知るには一番のところですよ。祭りの多さのなかにどっぷり浸っちゃったりね、人情とかね」
小松少年はときに、祇園から距離のある大壕公園にまで足を延ばした。
「月曜日の朝はやくに行くんですよ。すると、まだきれいなタバコの箱なんかが残ってた。タバコではピースの箱が一番きれいなんだけど、その空き箱をポンと捨ててあるやつを拾ってきて、それをきれいに切ってトランプをつくったりね。あとは大根でハートとかダイヤの形のハンコをつくったり。ビールのカンカンを拾ったりして缶蹴りをしたり、紐をつけて缶で竹馬を作ったりして遊びましたね」
そんな、遊び疲れた小松少年を迎えたのが、祇園に建つ「白亜の殿堂」だった。
「でも、そんなものがなぜ60年間も残ったかということですよね。まわりはなーんもなかったわけだから。いい時もあったけど、今まで残っているのが不思議ですよね」
小松政夫さんは、今でも仕事で博多へ行くと、祇園マーケットに立ち寄る。
「こそこそって行ってね。それでもう崩れそうな階段上がってみたりして、いっそいで思い出を掻き込んでね」
小松政夫さんの優しい目尻は、どこか懐かしい雰囲気を漂わせていた。
小松の親分っー。思わず、そう言葉に出して呼びかけたくなった。
櫛田神社の境内に立っていたとき、観光客らしき女性の声が聞こえた。
「なにあれー、すっごいいい感じなんだけど。あんなところに住んでみたいー」
思わずその方向を見上げれば、9月の声とともに一気に猛暑が去り、涼の漂う櫛田神社の境内の向こうに、祇園マーケットが建っていた。
その若い声は、不意に、6年前に物故した萩原延壽の言葉を呼び起こした。
「現代日本の革新は、保守と斬り結びながら後ろ向きに、現在までに獲得したすべての価値ある財産を継承しようとするために重い足取りで、未来に向って歩いてゆかなければならないのではないだろうか」(『自由の精神』)
ヤミ市という終戦直後に芽生えた“革新”が、若人の目に触れ、その感性に届いたとき、祇園マーケットはその止まりかけた足取りを未来に向けて進める、新しいエネルギーを獲得したのかもしれなかった。 (敬称略)
小松政夫さんは2020年に他界されました。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
