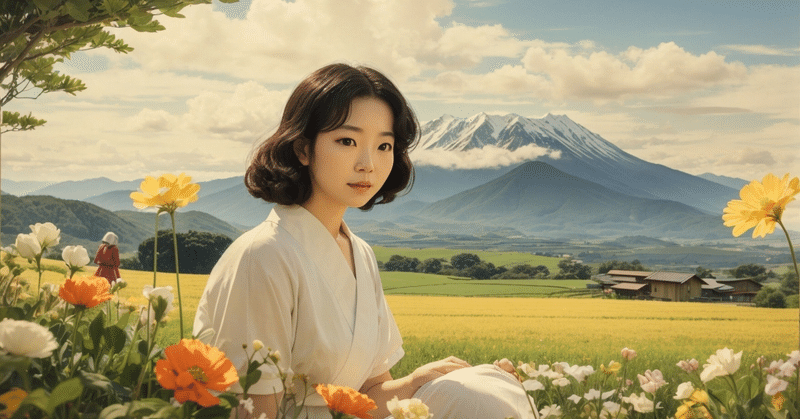
シリーズ 昭和百景 「“戦後政治の床柱”を見守った、女の一生 総理の乳母 久保ウメ」
歴史の陰に女性あり。
久保ウメさんはまさに、そんな言われ様を、自らの人生を賭して体現したひとりであったのかもしれない。
岸信介、安倍晋太郎、安倍晋三と続く政治家たちをまさにその最奥で見守った女性であった。
私はそんな彼女の言葉に敬意を持てども、一度として暴露趣味の嫌らしさを感じたことはなかった。
彼女は安倍家を離れてなお、おそらく最後まで安倍家を守り続ける、そんな矜持に満ちていた。
ただ、彼女に誤算があったとすれば、それは“知り過ぎた女”であった彼女を取り巻く、周囲の者たちの「意図」までは想像していなかったことかもしれない。
誰が彼女を疎んじたのかと言えば、おそらく誰が指示をしたわけでもなかったのだろう。
誰が彼女という存在を懸念したのかと言えば、おそらくそこには具体的な名前は浮かんではこないのだろう。
彼女は、固有名詞なき空気という見えない全体性によって、ふるさとでその存在を封じられることになったのかもしれない。それもまた、ムラにおける言葉なき意思であったのかもしれない。
あるいはさらに大仰に言うならば、戦前の日本からつながる「首魁なき、犯意なき全体主義」とでも呼びうるのだろうか。
残念ながら、本稿にはスキャンダルも、暴露話も登場しない。
ただ、自らが欲するがままに戦後政治の季節を見守った、それも戦後政治の床柱とでも評されるべき国民的政治家を守った、あるひとりの女性の一生である。
そんな女性の最晩年、縁あって言葉を交わすことになった私は、彼女の言葉の断片から、戦後の季節を辿ることを試みた。
原稿用紙では約300枚ほどの分量になります。
第1章
妖怪の残影
岸信介と60年安保
乳母、久保ウメ
久保ウメは結局、帰郷後、晋三に再会することなく逝ったのだろう。
ウメの葬儀の場にも、母、洋子の姿はあったが、晋三の姿はなかったと、集落の者たちは密やかにささやいた。
晋三の乳母と呼ばれたウメは、安倍晋三の悲願ともいえる、安保法制の国会成立を待つことなく、郷里の山口県油谷の小さな町で最期を迎えた。
私の手元に残ったのは、ウメが生前、語り遺した七本のテープだった。
羽田空港を発って半日後、山口県の小さな村に降り立った。
福岡空港から地下鉄と新幹線で小倉を経由し、在来線を乗り継いで下関まで出る。さらに山陰本線に乗り換えて一時間半は優に費やす。降り立った「人丸」駅は、駅とはいっても大阪や東京の人間には想像もつかないほどにそれは小さく、質素だった。
駅舎と呼べば、嫌味にさえ聞こえかねないその姿は、「小屋のような」という形容が一番ふさわしいようにも思えた。
列車が到着し、客が降りると、ロータリーとさえ呼べないような駅前の小さな広場に並んだ数台ばかりのタクシーは、まるでピストン輸送でもしているように、せわしなく村のなかへと発進しては、すぐにまた戻ってくる。
まだ夏の日差しが強く残っていたけれど、ずいぶんと静かなところだった。何よりも、珍しいぐらいに牧歌的な風景が残っていた。
政治に詳しくもない一般人にとっては、政治家「安倍」といえば、安倍晋三ではなく、その父である故・晋太郎の方が馴染み深かった。その晋太郎は「総理になれなかった悲運の政治家」として記憶に刻まれてきた。訪れたこの村には、その晋太郎の墓が今もなおある。
山口に来たことは何度かあった。
山口と聞けば、今よりもっと若い時代、瀬戸内海側の宇部空港に降り、萩や津和野までレンタカーで走ったことを思い出させた。
けれど、明治維新以降、これまでに七人もの宰相を生んだ「政治家の土地」としての印象以上に、吉田松陰や西周を生んだ「思想家の土地」としての山口県も好きだった。でも、それは決して矛盾するものでもないだろう。
「思想」の土壌がある場所に「政治」が育まれることに思いをはせれば、第二次大戦後においても山口県が中央に送り出す「政治の鼓動」は強く脈打っていて当然だった。
沖縄返還を実現した佐藤栄作や、日米安保条約の改定をめぐり日本列島をその是非で沸かせた岸信介も、山口県の出身だ。
その佐藤栄作と岸信介とは、実は兄弟である。その岸を祖父にもつのが、小泉純一郎という日本の政党史上、きわめて稀な「変人宰相」の〝ほまれ〟を掲げた内閣でメキメキと頭角をあらわした安倍晋三という政治家だった。
そんなことを考えれば、晋三という政治家は、描くべきドラマの種には事欠くはずがなかった。
だがなぜだろう―。
人丸駅前の牧歌的な風景と、海からの湿った風と山からの乾いた風が適度に交じり合って体全体を包む潤った開放感の心地よさとは裏腹に、諦めにも似た絶望感に襲われていた。
それはきっと、東京を発つ前に聞かされた、ある政治記者の言葉が気になっていたからだと思う。
「久保ウメさんという女性がいる。安倍家のすべてを知るという女性なんだが、どうも東京を離れてしまったみたいだ。みな探しているのだが、行方が知れない。山口のほうに戻っているとも言われているが連絡がつかないんだ。彼女さえ見つかれば生々しいエピソードが聞けることは間違いないんだけど……」
なぜ、そのウメが、長く安倍家を取材してきた政治記者たちの間でも〝行方不明〟となっているのか、それはその時点ではまったく予想もつかなかった。
ただ、ある意味で「ダークホース」ともいえる晋三の浮上と、彼の自民党幹事長就任によって、にわかに安倍家周辺への取材攻勢が活発になっていることはうかがえた。
きっと、その政治記者の言葉は、自分自身に対する一抹の歯がゆさのようなものでもあったのかもしれない。
〈どういうわけだが、ウメが見つからない〉という。
ウメの名前を聞いたのはそのときが初めてだったから、果たしてなぜ、「安倍」とは苗字の違うその女性が「安倍家のすべてを知る」とまで語られているのかを知る由はなかった。
でも、ウメの名前を告げた政治記者の深いため息混じりの声を聞けば、どうやらその女性はたしかに、安倍家への〝表参道〟に向うものにとってはどうしても避けて通ることができず、〝裏門〟からのぞこうとするものにとっても必ず目にするはずの、安倍家の核心を知りうる立場にいる女性であることは間違いないことは納得できた。
かつて将軍にぴったり寄り添い、一生を仕えた側用人さながらに、安倍家にあったのがウメという女性だったのだろうか―。
それならば、晋三が自民党幹事長という要職に就任した晴れ晴れしいはずの瞬間に、なぜその居所がわからないというのか。
「自民党をぶっ壊す」
小泉純一郎がそんな過激な口調で、自民党の旧習を「因習」として弾劾し、その破壊を錦の御旗に、それを象徴するかのように派閥ごとに調整された大臣人事を拒否してきたことはすでに広く知られていた。
それがいかに異例なことなのかは、政治を語るには勉強不足の身であっても、思い当たるところはあった。
八〇年代、日本政治について綴られた書物を紐解くと、そこには「自民党政治」の一節があった。
そこに書かれていた内容は今でも頭に残っている。まるで、自民党こそが唯一、総理大臣を輩出する唯一の政党であることを前提にしたかのような記述だった。
自民党では、当選回数を重ねることに派閥内の序例が上がっていき、そして幹事長、政調会長、総務会長の三役を経験し、大蔵大臣や外務大臣、通産大臣など主要閣僚を経るといよいよ総理への道が現実のものとなる、と。あたかもそれが、ひとつの定められた「システム」であり、「法則」でさえあるかのように、断定的に記されていた。
実際、それはそのとおりだった。八〇年代後半のその時期、確かにそうした階段を踏んでいったものが間違いなく総理大臣となっていった。
選挙のたびに国会での与野党が逆転しうる議会制民主主義を採用していながら、総理大臣を輩出するのがあまりに長い時間、自民党というひとつの政党に託されていた現実を、そののち、人々はこう呼んでいた。
「五五年体制」
その五五年体制の最中に生き、まさにその体制が定めた「総理への階段」を駆け上がっていたのが安倍晋太郎という政治家だった。
たぶん、いや、間違いなく小泉純一郎という政治家は、仮にこの五五年体制が現在まで続いていたならば絶対に自身が総理になる巡り合わせはありえなかったことを、誰よりも自身でこそ深く自覚しているに違いなかった。
「自民党をぶっ壊す」、そう叫びながら、自民党がどう「ぶっ壊」れたのかは、実際のところ言葉ほど明確には、その現実は見えていなかった。
ともすれば、「変人」「宇宙人」とさえ呼ばれる小泉だから、彼の目には自らが果たしえた成果が誰よりもはっきりと実感できていたのかもしれなかったけれど、少なくとも国民のひとりとしてのこの目には、「郵政民営化」しか頭になかった〝プロジェクト政権〟が、むしろ政権成熟期に向って徐々に、「構造改革」へと国民の視点と焦点を意図して散らせていっているようにさえ見えた。
それは決して「直情径行」で「ひとつ覚え」のような短絡さではなくて、まぎれもない国民誘導の「高等戦術」に思えてならなかった。
小泉が、総裁任期の終了を視野に入れ始めた頃、突如引き立てて国民の前にさらしたのが、安倍晋三という男だった。
歴史の教科書や政治評論家が語るように、五五年体制が崩壊して久しい今日だとしても、小泉純一郎に引き立てられての晋三の出現は、やはり突飛であることに違いはなかった。
野球にたとえれば、より鮮明だった。
テレビ朝日の『テレビタックル』という番組で、自民党の代議士が開陳していたたとえは分りやすかった。
たしかに、巨人と自民党はよく似ていた。
甲子園に出場した経験を持つ超高校級の元球児を五万と抱え、レギュラーに定着できない者でさえも他球団に出せば四番クラスが務まる選手がベンチを暖めるのが巨人だとすれば、自民党もまた同様に、くすぶり続けるエース級がそれこそ掃いて捨てるほどいた。
その巨人でさえ常に優勝できないのと同様に、層の厚さが組織としての強さを必ずしも保証するわけではなかった。
だが、巨人と自民党をくらべることの本質は、層の厚さがもたらす影響ではなかった。
そこに晋三の出現を重ね合わせると、エース級ぞろいの自民党で、それこそいきなり二軍のファームにいた晋三を一軍に引き上げ、しかもベンチスタートではなく、ある日突然に四番バッターとして打席に立たせたことを意味していた。
もちろん、晋三本人にしてみれば、そこに「据えられるだけの理由」があるのだろう。だけど、ひとをめぐる評価は常に、本人の言葉ではなく、よくも悪くも外の人間が定着させるものであることを考えれば、晋三の幹事長就任は間違いなく、誰の目にも驚天動地の人事に他ならなかった。
小泉が晋三の親父、晋太郎を知らないはずはない。さらに、そこにまつわる「悲運」の系譜もまた、自民党員としての小泉であれば、これまで耳にせずに生きてきたはずはなかった。
だから、小泉が晋三をある日突然に自民党幹事長のイスに座らせたとき、そこに小泉が込めた「もうひとつの暗喩」を見取らないわけにはいかなかったのだ。
それは、五五年体制下の自民党で総理のイスを目前にして逝った安倍晋太郎と、いまや突然の抜擢で「小泉改革の象徴」に祭り上げられようとしているその息子、安倍晋三との、皮肉なまでの運命の対決とも言えた。
小泉は、こう考えていたのではなかったか―。
〈安倍晋太郎は古い自民党の政治家として生き、そのなかで伸し、そしてそれがために総理のイスに座ることもできなかった。ならば、その息子である晋三を新しい自民党の象徴として据えることで、ひとつの血脈のなかでも古い世代と新しい世代が決別することを印象付けられる〉―と。
晋三が幹事長に就任したとき、メディアはこぞってその四九歳という若さを取り上げた。
でも、小泉が本当に狙ったのは、五五年体制の申し子である親父と、小泉体制の象徴となった息子という血脈の決別に込めた「小泉劇場の総仕上げ」にあったのではなかっただろうか。
たしかに、この伏線の込み入った話を、小泉が国民向けに考えていたとはあまり思えない。このシナリオは政治の素人である国民向けというよりも、むしろ、永田町の玄人衆にも意外とウケ、さらに効果的であるのかもしれなかった。
小泉が素人と玄人、どちらにもまんべんのない効果の浸透を狙っているのだと、あえて深読みしてみれば、実は小泉純一郎という政治家とは、自身が掲げる「直言居士」どころか、とんでもなく稀な、化け物のような「アジテーター(誘導家)」であって「デマゴーグ(謀略家)」であって、そして「マヌーバー(策士)」に違いなかった
〈オレの後に、再び、古きよき自民党の復権を狙う守旧派にトドメを刺す〉
そんな小泉劇場の最後の総仕上げに、舞台に引き上げられたのが晋三だとすれば、実は「若さ」に勝るさらに深い効果を、政界周辺には与えるはずだった。
安倍家の要諦は、女たちが押さえていた。
晋三の祖父に当たる岸信介元首相の長女である母・洋子と、そしてもうひとりが消息を絶った老婆、久保ウメだった。
洋子は政治家の娘として生まれ、夫・晋太郎を政治家として支えながら岸家―安倍家という閨閥のノレンを守ったのである。
そしてウメは、岸信介の首相時代に始まる四〇年に及ぶ半生を、安倍晋太郎とその息子・晋三まで、政治家三代に奉公した人物に他ならなかった。
多忙な政治家の屋敷で家事や育児の一切を仕切り、ときに夜討ち朝駆けの政治記者たちをも右に左にさばくことで家庭を守ったのだった。
安倍家を知るものならば誰もが、ウメを「安倍家の台所のすべてを知る女」と呼び、そしてこうも呼んでいた。
「晋三の乳母」――。
そのウメが、安倍家がハレの日を迎えた、わが子のように育てた安倍晋三が四九歳というという若さで自民党幹事長に就任したタイミングで、姿を消したのである。
安倍家ゆかりの、山口県・油谷の小さな村に着くと、ウメの実兄である久保芳雄という人物を訪ねた。しかし、古くからの自民党員であり、「私は安倍家に近すぎるから」と、終始慎重に言葉を選んでいた芳雄はついに最後の最後まで、東京からすでに郷里に戻ってきていたウメの居所について口を割ることはなかった。
いや、それは決して非難すべきことではないと思った。むしろ美しいほどに芯の通った〝封建意識〟だと感じたほどだ。
「安倍家のすべてを知る女性」が自らの身内だからこそ、軽々しくメディアにその姿をさらさせるようなことをしてはならないのだ。「近すぎるほど」の関係にある、安倍家を〝護る〟ためならばこそ。
あの時、芳雄から一通りの古い思い出話を取材した最後に、あえてこう訊いた。
「ほかに、安倍家について詳しい方をご存知ありませんか?」
芳雄の目はそのとき、座っていた土間の天井に向って、わずかにそれた。
「さあ、思い当たりませんな……」
そのとき、芳雄からウメの消息が語られることを、半ば期待し、半ば諦めていた。
どちらかといえば、芳雄の口からこそ、ついにウメの消息を語って欲しいという、希望のほうが強かったかもしれない。なにしろ、ウメの帰郷を知りながら、ウメの消息はその小さな村の誰からも語られることがなかったからだ。
ウメの実兄である芳雄の口が〝嘘〟をこぼしたとき、村人の態度が「ウメの帰郷を言いそびれている」だけではなく、やはり「隠していた」という悲しい現実を突きつけられたのだ。
国民的な人気を得て出世の階段を上っていく晋三と、それを護る安倍家の本丸である小さな村で、あまりに日本的なムラ社会の現実を突きつけられたようで、複雑な気持ちになった。
いったい、この口を封じられた、ウメはどんな女なのだろう―。
しかし、そんな芳雄には残念なことだが、芳雄の自宅を訪れた翌日、ついにウメの居場所に辿り着いたのである。
ウメはたしかに、東京・世田谷区の安倍邸から、自身の故郷であり安倍家の地盤でもある村に帰っていた。そして、岸家から安倍家へと政治家三代に奉公していた頃の話を聞くことができたのだった。
油谷の町で、ウメは驚くほど垢抜けて見えた。
紫を基調にした花柄のワンピースを着れば、山陰のこの小さな村には不釣合いなほどに、きれいに映えていた。
首に巻いたワンピースの柄と揃いのスカーフが、左肩に上品に乗っているからでもない。
初対面の客人に接する恐れのない表情と、相手に警戒を抱かせない柔和な目は、多くの政治家の妻たちと同じもののように思えた。
ウメは政治家の妻だ。
そう確信した。
「このたびは安倍晋三さんの幹事長就任、おめでとうございます」
そう切り出すと、ウメは目を細めて座を促した。
「ありがとうございます。晋ちゃんもほんとにね。でも体が弱いから心配なんですよ。晋ちゃんは内臓が弱いから」
二〇〇三年九月のことだった。
祖父、安倍寛という政治家
油谷湾から掛淵川に沿ってしばらく川上に向って土手の上を歩いていく。あたりには照りつける太陽を遮る木陰さえない。田んぼの稲はまだ黄金色の穂をつけていなかったから、川をはさんだ前後左右には一面、吹きわたる風で波打つような深い緑の海が広がっていた。
まだどれくらい離れているだろうか。先のほうに橋が見えた。きっと道路が走っているのだろう。
なんのためか、ひとが集っているようだった。
近付くにつれ、橋のたもとには一〇人ほどのお年寄りたちが集っているのがわかった。
そこに、山のほうから、街宣の音が聞こえてきた。
こちらに向って近付いていたのだろう。スピーカーから流れる音が、牛の啼き声と混じりながらも、徐々に大きくはっきりと聞こえるようになってきた。
「……きし、のぶお、…きし、のぶおでございます。きし、のぶお、きしっ、のぶおで…」
都会であれば、その繰り返しが不定期に途切れ、沿道から返される支援者の合図や通行人のひやかしにも返礼を返してみせる。
「きし、のぶお、き…あっ、ありがとうございます。ご支援ありがとうございます。きし…、あっ、御仕事お疲れ様でございます。わざわざのご声援、誠にありがとうございます。必死に最後のお願いにあがって…、ただいま、きしが直接、みなさまのもとにお願いにあがっております」
と、ウグイス嬢の暗唱されたアナウンスが途切れては、沿道に返礼するわけだけど、ひと気のない田んぼのなかの畦を広げたような道を走ってくるためか、沿道に通行人などいるわけもなく、生の声とは思えないほど、テープさながらに、アナウンスは見事なまでに淀みなく繰り返されていた。
「きし…、きしっ…、きしっっ…、きしっっっ…」
と連呼された名前を聞いて、やっと、その時が、参院選の最中であったことに気付いたのである。
街宣車は、いよいよ橋のたもとへ到着すると、炎天下をわざわざ待っていた村のひとびとのそばに車を止めた。
橋の少し手前の土手の上にたたずみながら、その光景を眺めていた。
けれど、たすきをかけて面相の小ぎれいな男性が人々の列を左から右に、手を握って動いていくさまをみて、かつてウメの兄から聞いたこんな光景を思い出していた。
晋三のもうひとりの祖父であり、安倍晋太郎の父、安倍寛の選挙の様子である。
寛は一八九四年に生まれ、東京帝大法学部を卒業後、現在の山口県・油谷一帯を治めた旧日置村の村長などを務め、一九三七年に衆議院議員に初当選する。それからはさしたる困難もなく戦歴を重ねたかといえば、ことはそう単純でもなかった。
初当選から五年後の大政翼賛選挙では、寛は大東亜戦争に反対を表明し、なんと非推薦での選挙戦となった。
苦しかったのは、支援者たちだった。
当時はまだガソリン自動車などという高価なものは容易には調達できず、村の者々が選挙のために用立てたのは、木炭を燃やして動かす木炭車だったという。
このとき直接に聞いた話は、以前、週刊誌に採用され、そのなかで記事に転載されているので、それを引くことにしたい。
当時の激しい選挙の思い出を教えたのは、地元・山口県油谷町在住の久保芳雄だった。
「寛さんの選挙は、大政翼賛会に反対して、非推薦で出た選挙だったからねえ。大変な苦戦でしたよ。一㍍はあろうかという長い巻物に〝なんぼ安倍が九銭(苦戦)でも、一銭足せば当選となる〟というスローガンを書いてねえ。あともう一息、なんとか、あともうひと力を貸してくれって、それは必死の選挙じゃった」
同じく安倍家の実家近くで健在だった植山一男も述懐する。
「あの選挙は大変じゃったなあ。寛さんのお母さんの姉にあたる安倍ヨシさんという伯母が当時、安倍家にいてね。このヨシさんは、厳しい人で通っていたんだけど、彼女が〝きっとやります。やらせます。安倍ヨシ〟と書いたチラシを自ら持って歩いて配っていたなあ。大政翼賛会に属さずに戦う選挙じゃから、今からは想像もできんようなもんじゃったよ」
軍部独裁の時代に、こともあろうに大東亜戦争に抵抗して戦ったのだから、その苦労は筆舌に尽くし難かったに違いない。
長く晋太郎の秘書を務めた奥田斉(81)がいう。
「大政翼賛会に参加しないで出馬した人たちは、みな落選していきました。しかし、安倍寛さんだけは当選したんです。一億総特攻などと言っている時に、戦争反対をいうんですから、もちろん特高警察にもマークされていました。演説会にも、特高や憲兵はいつも尾いて歩いていた。当選してからは、村長と国会議員を兼務ですよ。身体が弱かったから、村長室にベッドまで置いて、仕事をしていましたね」
(週刊新潮 平成15年一〇月九日号)
寛の初当選からまもなく七〇年になろうとする〇四年、安倍家の三男坊として生まれた、晋三の実弟にして岸家に養子として出されていた岸信夫が参議員選に立候補していた。
政治家としての安倍家の初陣を支えたのが木炭車だった時代を思うとき、末裔ともいえる岸信夫がひとけのない畦のなかをガソリン車で楚々と走ってくる姿を重ね、意外に、道具は進めど風景はかわらずだな、などとも思うのだった。
だけど、そこに集っているひとの数の少なさと、そしてその面々のいずれもがあまりに年かさの行き過ぎた、まさに長老と呼ぶに相応しい身なりであることに鑑みれば、岸家に安倍家が合流することによって育まれてきたこの「王朝」は確実に寂れ、そして瓦解への終着点に向かって進みつつあるようにも感じた。
思想は三代かかって成熟もすれば、三代かかって破綻もしよう。
安倍家、岸家のどちらから数えても、実に晋三こそが、今後を占う運命を背負わされた、肝心の「三代目」なのであった。
油谷にはもう、直接に寛を知る人物は少なくなってしまったが、若い頃のウメもまた、寛と言葉を交わした貴重な証人のひとりだった。
ウメの記憶に残る寛の印象は「すらっとしてね、いっつも姿勢がよかった」のだという。ただ、それには理由があった。その姿勢の良さを寛に直接訊ねると、「これはコルセットですよ」と返ってきたそうだ。寛は結核とか脊椎カリエスを患っていた、そのためコルセットをしていた、だから姿勢がよく見えたのだ、とウメは教えてくれた。
やはり、現在も油谷に住む古い住民のひとりは、在りし日の寛の様子を覚えている。
日置村の役場に勤めていたこの女性は、仕事の用を伝えに、山の中腹にあった寛の自宅に上がった。
「仕事のことでお伝えに上がると、いつも、部屋の真ん中の布団に臥せっていたのを覚えています。体が悪いのは知っていたので、軒先から布団で横になる寛先生に声をかけていました」
安倍家は代々、体が弱い。
「岸の血筋は呼吸器が弱くて、安倍のほうは消化器が弱い」というウメの言葉を裏づけるように、油谷の古い衆に寛との思い出を尋ねれば、必ずと言っていいほど、寛の病弱な体にまつわる記憶が浮かび上がる。
寛は、帝大卒のエリートでありながら、同時に経歴からは想像のつかない苦労も重ねていた。
古くは地元で醤油や酒の醸造蔵などを営んだ商家に育った寛は、政治家を志す以前に、東京で三平商会という自転車屋を興し、そして事業に失敗する。
すでに元陸軍大将の娘・静子を嫁に迎えていたために、ここで悲劇が起きた。事業の失敗がもとで、寛と静子は晋太郎が誕生した直後に離縁する。
離婚そのものが末代までの恥として語り継がれる古い時代、長男が誕生した直後のこの悲話は、村人の好奇の目を引かずにはいなかった。
現在も古い者たちの間では、その離婚の原因については様々に語り継がれているが、やはりお金の問題がそこに潜んでいることは確かなようだった。商売の失敗とそれに伴う妻・静子の実家からの借財、家風の違いや自身の実家との財力のバランス……。ウメはそんな事柄を並べながら、肝心なところになると言葉を濁してしまった。
商家に育ったとはいえ、寛が大学を出るころには、すでに家業は人手に渡っていた。果たして何が寛を事業欲に駆り立てたのかは今となってはわからないが、三平商会を興そうとした以外にも、若いころの寛は旺盛な事業欲を見せていたという。
ウメが「パパ」と呼ぶ晋太郎は、実の母を知らない。父の寛自身もまた、実は一〇歳の頃に時両親を失い、「母なき子」として育った。わが子にも同じ轍を歩ませたのだ。寛と晋太郎、父と息子がともに、幼時に孤独な境遇にあった不憫さを、ウメは物語った。
何事にも歯切れのいいウメだったが、寛と静子の離婚が嫁の実家からの強い要求によって「引き離された」ことを詳らかにするときは何かためらいがちだった。話のなかで、寛が後に晋太郎に語った「詫び」の言葉は強く胸を打つのだった。
晋太郎は、山口中学、第六高等学校を経て東大法学部に入学した後、一時期、海軍予備学生として〝兵役〟に出ている。
晋太郎が海軍にいたとき、寛は次のように言ったそうだ。
「悪かったな。おまえのためにも、新しい女房はとらなかったんだ。寂しい思いをさせたな……。でも、生きて帰ってくれよな」
そこで初めて、晋太郎は両親の別離の真相を悟る。
〈父と母は愛し合っていたのに別れざるをえなかったのだ。〉
さらに遡って、山口中学時代、晋太郎は〝失踪〟したことがあった。
多感な思春期の真っ只中、産みの母を知らない晋太郎は母を捜そうと、あてもなく油谷を飛び出した。目指したのは東京市の新宿である。そこには晋太郎が産声を上げた産院があり、界隈を歩きまわったというのだ。
東京まで汽車で二〇時間は優にかかる時代のことだ。ただただ、母親の痕跡に近寄りたい一心で、出生の地を放浪したのであった。
こうした晋太郎の未だ見ぬ母親への強い思慕は、妻、洋子が晋太郎の没後に書いた『わたしの安倍晋太郎』でも、裏付けられている。
むしろ目を引くのは、なにごとにも、無味で恬淡とした印象さえ与える洋子の語り口であり、それはこの場面でも感傷的な情緒を漂わせることなく、感情の澱みはない。
主人の出身は山口県の油谷町となっておりますが、生まれたのは大正十一年に結婚した両親が新居を構えた東京の四谷で、大正十三年四月二十九日でした。ところが、父・寛と母・静子は、実家どうしの確執が原因で離婚となり、生後八十五日で父の故郷である油谷町に引き取られましたから、生母の顔を知らずに育ったのです。父・寛は、後妻をもらうと晋太郎が継子になるからかわいそうだと言って再婚せず、主人は、乳母になってくれた親戚の小島ミヨさん、大叔母のヨシさんなどの手で育てられました。
子どものころから母に会いたいという気持ちが強く、その消息を尋ねまわって、そのことを口止めされていた親戚の者を困惑させたようです。ついに東京の新宿あたりにいるらしいと聞き出して、中学、高校のころは夏休みなどに父・寛に連れられて上京すると、父には内緒で、結婚写真を頼りに探して歩いたそうです。
岡山の第六高等学校に入ったのは戦時中で、わずか一年半で繰り上げ卒業となり、東京帝大に推薦入学しましたが、主人は同時に特攻を志願して海軍滋賀航空隊に第十五期呼び学生として入隊いたします。このとき主人は、結核で病床にあった父・寛と徹夜で話し合いましたが、すでに母が亡くなっていることを初めて知らされたのです。
「お母さんとの仲はよかったんだよ」
とも聞かされたそうです。
本人はのちに知ったのですが、母・静子はその後、横浜正金銀行(東京銀行の前身)に勤務する西村謙三さんと再婚しましたが、結核にかかって昭和十一年六月に、三十一 歳の若さで亡くなりました。主人が母を探して歩き回っていたときには、その人はもう、この世を去っていたのでした。
晋太郎はこうして、父親の異なる兄弟を知ることになる。
それが日本興業銀行の役員を務め、後に合併後のみずほホールディングスの会長にまで登り詰めた西村正雄であった。
だれよりも、晋太郎の気持ちを知っていたのだろう。寛は、「新しい母」を作ることのむごさを、決して子に与えてはならないと独り身を守り続けていたのだった。
寛自身も幼くして肉親の持つ無垢の抱擁を失い、誰よりも孤独だった。だが、晋太郎の「知らぬ母」を持たないことが、寛にとって、息子・晋太郎に貫いた親子愛のかたちだった。
「悪かったな。……でも、生きて帰ってくれよな」
父からこう告げられたときの晋太郎の心中は涙雨に濡れた。ウメは、そんな話を晋太郎から聞かされたという。こういう話をしたのは初めてだと、その語り口の語尾は照れを隠すように跳ねた。
晋太郎から自分だけに打ち明けられたという話をこぼすとき、ウメの目じりに刻まれた深い皺は、とても幸せそうな旋律を放っていた。その様子はまるで、小さな恋を語る少女のようにだった。
晋三が、北朝鮮に拉致された被害者の家族に大きな理解を示し、厚い信頼を勝ち得た背景に、「祖父」と「父」の哀しみを観てとっていたとすれば、その〝タカ派〟の実相が理解できた。
ウメが晋三の背に見たのは、父・晋太郎から引き継いだ「外交」を果たすという政治家としての業ではなかった。それは、安倍家の「イエの慟哭」を知る晋三にとってはより身近な、肉親を喪うことの哀しみに他ならなかった。
そして、「プリンス」「イケ面」といった、当世風の華やかな修飾のどこかに悲壮感の匂いも漂うとすれば、それが逆に国民の〝母性本能〟をくすぐりもする。
だが、振り返って思い起こせば、その人気が「冬のソナタ」に狂乱した国民性のその延長にあるのだとすれば、「流行」が孕む危うさもどこかにちらついていたのかもしれない。
政治家、岸信介という祖父
一方、晋三が、もうひとりの祖父である「岸信介のDNA」を看板として掲げるとき、その〝伝説〟は、大正まで遡る。
国立大学の行政法人化と前後して次々と新築の研究棟が立ち並び、様変わり激しい東京・本郷の東京大学で、戦前から一貫して変わらないものがあった。
もはや帝国大学時代からの唯一の「名残り」とさえ呼べるその遺産は、正門上部にある。そこには、天皇家の象徴である菊の御紋が刻まれている。
そのためか、この東大正門は、開かずの御門でもある。現在も、学生や職員は通常、正門の脇にある通用門から出入りしている。
その昔、この正門が正式に開かれる日が一年に一度だけあった。戦前、東京帝国大学の卒業式がそれに当たる。
卒業式当日、厳かに目一杯まで開け放たれた正門に、カツカツと、蹄の音が近づいてくる。馬によって牽かれた一台の御車だけがその御紋の下を通過することを許され、煉瓦造りの古い学び舎のなかへ入場した。
東京帝大の卒業式に臨席した天皇陛下からは、各学部の主席卒業者に〝恩賜〟の「銀時計」が与えられていた。
大正九年、そこに、晋三の祖父・岸信介の姿があった。
そして、そこに伝説が生まれた。
〈岸は見事に主席で卒業したものの、自らの意思をもって大蔵省へは行かず、農商務省(後に農林省と商工省へ組織分割)へ入省した。『銀時計組』で将来を嘱望される身でありながら、後の日本の工業立国化を先見した類まれな慧眼の持ち主だった…〉
この「銀時計組」は、岸を語るときには、必ずといっていいほど持ち出され、長く語り継がれてきた伝説である。同期には、後に民法の大家となる若き日の我妻栄がいた。
〈岸と我妻は、ともにすべての科目を全優で卒業し、首席の座を分けた『銀時計組』だった……〉
しかし、岸信介の「大秀才」ぶりを大衆に決定づけるこの逸話は、たしかに〝伝説〟以上のものではなかった。
岸が帝大を卒業する二年前、天皇陛下による卒業式臨席の慣例は廃止されていた。当然、恩賜の「銀時計」を与えられた計三二三人のなかに岸信介の名前は残っていない。
強烈な個性はときに、事実を超えた伝説を産み落とす。
今なお多方面で深く信じられているこの銀時計の逸話は、岸の〝凄み〟こそが浸透させたものともいえた。
岸は第二次大戦後、A級戦犯として巣鴨刑務所に服役しながらも公職追放から復活し、首相にまで上り詰める。そして、暴漢の凶刃を凌ぎ、日米安保条約の改定を内閣総辞職と引き換えに断行する。
その政治運の強さは、鵺のような捉えどころのないしぶとさと相まって、岸に「昭和の妖怪」という呼称さえ与えた。
そんな凄まじいまでの執念の源泉が果たしてどこにあったのかと考えたとき、ウメは、かつて岸から告げられた〝あの話〟を思いだすのだった。
八七年に九〇歳で死去する岸の晩年のことだった。すでに八〇年には妻・良子に先立たれ、岸は御殿場の屋敷で寂しく過ごしていた。
岸がまだ、現職の総理大臣だった頃、渋谷・南平台にあった私邸の外では日米安保条約の改定に反対するデモ隊のシュプレヒコールが連日連夜続けられ、機動隊との小競り合いを繰り広げられた。そんな喧騒も遠い昔の、懐かしささえ感じる〝平和な春〟だった。都心に比べ、緑の多い御殿場で、岸は毎朝のように散歩を楽しみ、朝食の卓に着いた。
共に移り住んでいたウメの頭は、岸の毎朝の体調と糖尿病の食事管理のことでいっぱいだった。長く仕え、慣れた間柄とはいえ、元首相であり、なおも政界に隠然たる力を持つ岸の世話には気が張った。
ある朝のことだった。
ウメの目に、野草の花が目に留まった。花は、食卓の上に、小さく咲いていた。覚えのない花だった。
〈あらっ。あたしじゃないわ……おじいちゃまかしら。でも、おじいちゃまがわざわざ花なんて、まさか……〉
驚いた素振りを見せるウメに、岸が好々爺よろしく、嫌味なく応じた。
「ああ、私が採ってきたんですよ」
そんなやりとりは、ウメにとっても岸とのいい思い出だった。今日も起きているのか、朝食を摂ってくれるのかと、日々心配しながら過ごしていた頃だったから、元総理大臣という人物が野に咲く花を手折って飾るとは考えもしなかったと、ウメは当時を振り返った。
心穏やかな瞬間も覗かせていた岸は、体調のいいときには西新橋の個人事務所に顔を出すなど、引退後も旺盛な活動意欲を見せていた。その〝妖怪〟が、ふと洩らしたことがあった。
朝の六時にウメが起きると、岸はいつも先に目覚めていた。自分よりも早くに目を覚ます岸が、まだ寝静まっている時間から小忙しく動いているわけではなかった。岸は、ウメが起きるまでは静かにしていた。
年寄り特有の朝の早さかと思えなくもなかったが、体調のこともあり、なぜ毎日そんなに朝が早いのか、ウメはあえて訊ねてみたという。
「あんたを起こさないように、六時までは待っているんだよ」
それはウメにもわかっていた。しかし、火急の仕事に追われているわけでもない、老いた今、岸はなぜそんなに朝早くから目を覚ましているのか、気になって仕方がない。
そんなウメの懸念を見透かしたように、岸は続けた。
「巣鴨にいたころね、毎朝、カツカツという踵の音が廊下に響くんだよ。戦犯として処刑される者の房の前で音が止まるからね、それで今日の処刑が誰なのかってわかったんだよ。だから毎朝、靴の音が聞こえると、今日は俺か、明日は俺かって、みな、音が自分のほうにくるのかどうかを、部屋のなかで息を殺して気配を探っていたんだよ」
それが、冬であればまだ暗い、朝の四時ちょうどだったという。
「それ以来、どこにいても朝の四時になると目が覚めてしまうんだよ」
史実としては、毎朝四時に、必ず戦犯が処刑されていたというのははなはだ怪しい。だが、ウメの話を聞く限りでは、「巣鴨刑務所に収容されていたとき」の体験が、岸の心と体にあまりに深い傷を刻んだのは間違いない。
後に不起訴が決定し、釈放こそされるものの、開戦当時に商工大臣だった岸にとっては、最後までその身柄の処遇は予断を許さなかった。
絞首刑か不起訴かの運命を分けた理由について、岸は最期の瞬間まで「会議への出席の有無」だと考えていた節がある。天皇に対して開戦方針を報告することを最終決定した、ある日の「政府大本営連絡会議」に、岸はたまたま欠席した。
岸はウメに、偶然こそが生き延びるツキをもたらしたとばかりに、こう繰り返した。
「会議に出なかったから助かったんだ。ある人が私が出席していなかったことを証言してくれてね、それで処刑されなかったんだ。助かったんだ」
〝妖怪〟のその魁偉ぶりが、占領軍の胸先三寸で戦犯として処刑されるかどうかの、死線を彷徨った者だけが持つ強さだとすれば、日米安保の改定を巡る学生たちのシュプレヒコールも、世論の罵声も、暴漢の凶刃さえも、見える敵に向かうことは、恐れるに足るものではなかった。
その岸が自らの言葉で、やはり処刑に怯える心境をこう語っている。
どうやら、ウメが聞かされた話とも符合する。
……具体的にいつごろ出所できるかの見通しは、皆目見当がつかなかった。友人の弁護士三輪寿荘君(後の社会党代議士)らを通じて、断片的に情報を得られたが、〝万が一〟が実現するにしても三年や五年ということはあるまいと考えていた。その時期は、結果として意外に早く到来したが、とにかく市谷の旧陸軍省に設けられた軍事法廷では、東条さん以下の裁判が着々と進行している。こちらにはまだ呼び出しがないが、裁判の結果によってはどうなるかは分からない。処刑の時刻は真夜中か夜明けときいているが、もしかするとこれが最後の夕食になるかもしれない、という想像が頭をかすめ、翌朝目がさめて、『今日も一日もうけたか』という毎日であった。こういう心理状態のもとで出所までの三年三カ月を過ごしたことは、その後の私の人生にとって、計り知れない価値となった。こういう経験は、まねをしたくともだれしも味わえるものではない。人間の運であり、天の配剤であるとしか言いようがない。出所の日、私は自分の天命について深く感ずるところがありかつ期するところがあった。
(『岸信介回顧録』)
翻って、GHQによる「恐怖の時」を耐えしのいだ岸が、運命の強さを確信したとすれば、それは紛れもなく、孫である晋三の政治生命に受け継がれているようにも見える。
小泉純一郎の首相就任にともなう異例の〝出世〟は、そこにひとつのツキを感じさせた。与党代議士とはいえ、晋三はそれまで、政局でとりたてて大きな存在感を放つわけでもなく、政策通として霞ヶ関で政治的な指導力を発揮したわけでもなかった。
いわば陣傘議員のひとりに過ぎなかった晋三が、〇三年に自民党幹事長に抜擢され、そして〇五年の第三次内閣改造で官房長官に就任する。
あまりに多様な〝手腕と実力〟が交錯する政界で、局面こそが「ポスト」を結実させる。離合集散の瞬間の綾に、確かなものなどあり得なかった。小泉劇場と揶揄され、風雲急のごとくに次々と目先の政局が変化するなかで「ポスト」を上り続ける晋三が、大きな拠り所とするのが、「人気」というツキだった。
だからこそ、晋三を評するときに引き合いに出される、岸信介に〝通じた〟タカ派ぶりは、ウメの目には決して重なるものとしては映らなかった。
自らの体験によって裏打ちされた岸のツキと、政治局面という外の状況がもたらした晋三のツキとが異質のものであることを、ウメは見抜いているようだった。
乳母として、物心つく前から育てた晋三の要職就任を喜んでいないわけではなかった。だが、強い政治信条が今の晋三の立場をもたらしたと無邪気に信じるには、ウメはあまりに長く政治をそばで見すぎてもいた。
そう感じさせるひと言をウメの口から聞かされたとき、それはまるで、政治評論家が、ある政治家のバブル人気を一刀両断に斬って捨てたかのように響いた。
ウメは、晋三の「今」を「ヤワ」の一語で表現した。そして、今の時代は女性が「ヤワ」を好むと世相も評した。
一瞬、ウメが晋三ではなく、誰か別の政治家のことを言っているのではないかと、わが耳を疑った。
乳母であるウメの言葉だからこそ、それはひとりの政治家にとっては、冷酷でさえあった。
ウメにとって晋三は、身びいきをもってしても実力以上に大きく見せるべき存在ではなく、「ヤワ」な魅力として映っていた。
なるほど、タカ派という毀誉褒貶を孕んだ形容の一方で晋三に与えられた「イケ面」「プリンス」といった称号は確かに、女性の好奇心をあからさまに含んでいた。
細面で小顔の晋三の売りが「現代女性のヤワ好き」にあるという冷ややかな悟りが、八〇の峠を越えようとする老婆の言葉であることを考えれば、二度驚かされた。
死線を彷徨った体験が育んだ、岸の人間としての〝強さ〟がもたらしたツキと、晋三の「ツキ」はあまりにもかけ離れていることを、乳母の言葉は冷淡に告げていた。
ところで、岸が戦犯として収容されている自らの境遇や東京裁判そのものを果たしてどう考えていたのか―。
次の言葉が、すでに巣鴨刑務所から釈放されたあとの、「尊厳」を取り戻したときのものであることを割り引いても、ウメのいう晋三の「芯の強さ」が、やはり「血の強さ」を源流としていることを感じさせるようで面白い。
戦後、多くの知識人、言論人、そしてだれよりも戦争当事者の多くが自らの言動の多くを自己否定し、「転向」してみせたのだ。
それなのに、岸は……
発言の是非は受け取る側に任せるけれど、あくまでも状況の変化を超えて自らの信念を変えることがないという性格の一端をのぞかせているようだ。
この血を晋三が受け継いでいるというのだから、ウメのいうように「こうと決めたら絶対やっちゃうわよ」という晋三の「芯が強く」、裏を返せば「頑固一徹の性格」も、理解できるのだった。
『岸信介回顧録』は、巣鴨刑務所と東京裁判の回想から始まる。
やはり、よほど〝思いいれ〟のある経験だったのだろう。
西洋人が支配権を持っていた占領軍ならではの〝恩赦〟の意味があったわけでもないだろうけれど、岸が「巣鴨」を釈放されたのは、クリスマスイブだった。
少し長いけれど、岸の戦後認識を端的に表している遺されたもとしてはほかには散見することの少ない、貴重な証言なので引用してみたい。
昭和二十三年十二月二十四日午前、私は東京の巣鴨刑務所から釈放された。二十年九月十七日の午後、連合軍指定の戦争犯罪容疑者として、横浜の米第八軍憲兵司令部に出頭して以来、三年三ヵ月ぶりで私は五十三才だった。
私は太平洋戦争が開始されたときの国務大臣として、戦争の経過ならびに結果については重大な責任を感じている。多数の人命、財産を失い、日本国土を荒廃させたことは、国民に対して申し訳ないとしか言いようがない。ただ、その責任のとり方として、勝者である占領軍が、一方的に断罪するやり方には心理的に反発を感じ、法理論としても納得できなかった。
今ここで、戦争裁判の当否について詳細に論ずるつもりはないが、戦争裁判を通じて日本国民のなかに、「日本は戦略戦争をした、悪いことをした」という受け止め方が、戦後三十年たった今日でも根強く残っているように思われる。はなはだしきに至っては明治開国以来、日本のしてきたことはすべて侵略であり悪である、という解説、教育が未だに幅をきかせているような状態も見られるので、ここで一言述べてみたい。
書き出しこそ、鳴りを潜めているけれど、ここからが急転、舌鋒鋭い。
軍事裁判は戦後ニュールンベルグと東京で開かれた。東京の、正しくは『極東国際軍事裁判』の裁判所条例及びA級戦犯容疑者二八名に対する起訴事実を考察して、第一に指摘できる点は『文明』という名前を原告として開かれた裁判が、実体は戦勝国の戦敗国に対する一方的、恣意的な制裁であって、何ら法理論の裏付けがなく、裁判に値しないということである。
(中略)
米国を中心として連合国の初期の対日占領政策の基本は、戦争の責任をすべて日本国民に負わせ、日本国民が今日受けている困苦や屈辱はすべて自業自得であると思い込ませる点にあり、その意味で東京裁判も絶対権力を用いた〝ショー〟だったのである。多くの費用と人命の損失で結末を見た東京裁判が、その後の世界平和の進展にどれほどの価値を持っているかは、今日までの国際情勢の変遷を見れば明らかであろう。太平洋戦争中の最大の無差別殺人である、広島、長崎に投下された原子爆弾に対する責任は、東京裁判では全く不問に付せられたが、そのことが戦後においても激烈な核戦力増強競争を出現させ、人類全体をして破滅か存続かの重大局面に立たしめているのである。戦争裁判は戦争直後という異常な雰囲気、心理状態において、戦勝者の一時の報復心を満足させることはできたであろうが、真実の解明と、法と道義による世界秩序の確立には役に立たなかったといっても過言ではないであろう。
東京裁判はドラマとしては壮大で、また深刻きわまりなかったが、今は、人間の知恵の浅さを思い知らせたことと「文明」の名に汚点を残したという記録に過ぎないのである。
こういうわけで、巣鴨に収監されている間も「我々は、法律に違反した犯罪人である」という意識は全くなかった。あるものは勝者対敗者の関係であった。その関係において、敗者は勝者の手によって裁かれ、処刑されるのはやむを得ないと覚悟していた。従って、死は免れないものの、それまでに我々の意見、立場を堂々と主張し、日本だけが悪事を働いたという一方的な押し付けに反駁し、彼らの理非曲直を明らかにして真実を後世に伝えん、と意気軒昂といってもよい心境であった。
明日は生きるか死ぬかの〝獄中〟にあって、本当にこれほどまでの揺らぎない信念を持ち続けていたとすれば、自分が生まれる前の時代にあって、まさにそこには〝妖怪あり〟と認めざるをえない。
これほどの信念だから、警職法やら安保条約の改定やらと、後世での評価が極端に二分される仕事を、良くいえば「やり遂げた」のだろうし、悪くいえば「強行できた」のかもしれない。
岸自ら、巣鴨時代を「意気軒昂といってもよい心境」というだけに、確かに精気みなぎっていたのは間違いないらしい。
次のエピソードを見つけたときは、苦笑いするしかなかった。
ある日、散歩の途中で岸と顔が合うと、
「笹川君、きみはどうだい?」
と、にやりと笑ってかれは自分の股間をさし示した。
「どうかしましたか」
とたずねると、岸信介は、
「ぼくは一物が元気で困る。まさかこの歳になって、中学時代のように独りで楽しむ行為でもあるまいし、まったくこいつを自分ながらもてあましている。巣鴨生活で最大の苦痛はこれだよ」
と、大声で笑った。精力盛んなために男の一物がそびえたつばかりでなく、ときには夢精するというのである。おどろいた笹川は、
「危機に臨んで睾丸をさぐり、だらりと下がっておれば大丈夫とは人のいうところであるが監獄生活の夜な夜なに一物憤然と怒り立ち、焔のごとく燃え狂い石のごとく固ければまずその人は心身ともに健全なる証拠、一物の怒りを制御しかねてぼくに告白した岸君はやっぱり世評にたがわぬ骨ぶしの男、まさに官僚群中の豪傑組筆頭たるの資格満点であった」 (『巣鴨の表情』一九七頁)
(『巨魁 岸信介研究』)
妖怪ぶりでは、決して岸に劣らない逸話を数多く残した、あの笹川良一が驚いていたというのだから、もはやこれは岸の功績うんぬんを置いても、同じ日本人としてその「怪傑」ぶりに乎々喝さいするばかりであった。
そんな、揺るぎない信念を貫いた「気」も「俗」も含めた岸を「『百万人といえども我ゆかん』の覚悟で、それを政治生命を賭けてやり遂げた」と称えてみせるのが孫の晋三なのだ。
ところで、私の保守主義について、もう一点触れておくとすれば、やはり祖父の影響でしょう。祖父はまったくの明治生まれであり、まったくの戦前育ち。私にとっては別世界で少年期、青年期をおくった人間です。私が青年時代に祖父から聞かされた話の数々は私にとって新鮮であり、少なからず影響を受けたと思います。
一方、父は大学以前の教育は戦前ですけれども、それ以降は戦後です。そうすると、戦争というきわめて悲劇的な経験をしていますから、そのことが非常に大きく思想形成に影を投げかけていたわけです。どうしてあんな戦争になってしまったのかとか、それに対する世代的な反省とか、そういう懐疑的な所がやはり多かった。
けれども祖父の場合は、先の大戦に至る前の、ある意味では日本がたいへん飛躍的な前進を遂げた〈栄光の時代〉が青春であり、若き日の人生そのものだった。だから、それが血や肉になっている。そこの違いが実に大きかったわけです。
祖父はそうした時代に、きわめて大きな自信を持っていた。そうすると、興味を引かれるのは、皆が「とんでもないものだ」と思っているその戦前の時代に、強烈な自信を持つというのは、一体その背景にあるものは何だろうということです。
(中略)
それと、政治家としてどうあるべきかということに関しては、祖父はこれは「結果責任」で一貫していました。
(『「保守革命」宣言』)
そうして、晋三は今からちょうど一〇年前に、「私の『保守政治家宣言』」にいたるのである。
こんな数々の言葉を書物から紐解いてきたとき、もしかしたら、安倍晋三という若い政治家の「原風景」とは、岸信介の「壮絶な戦中体験」を〝擬装的〟に取り込みながら育まれたものではないか、と思えてきた。
そんな感じは、ウメとの会話のなかで、ある奇妙なことに気づいたとき、心証として強く訴えてきたのだった。
国民が政治家の思想を知ろうとするとき、結局はその人間が発した言葉から知る意外にはない。
今のように政治報道がエンターテイメント化されていないかつてはなおさら、言葉は無駄に消費されることもなく、長くそれを発した政治家の実像として残像を止めていたはずだった。
そんな言葉にこそ思想が顕れて、言葉からその思想を汲むのだとすれば、実に興味ぶかい記録が残っている。
もう亡くなってしまったけれど、かつて、ある有名な作家が、岸信介の言葉からその人柄を分析していた。
昔のものだから、文章は少し硬いけれど、この文章に出会ったとき、アタマのなかを閃光が走った。
岸信介という晋三の祖先の思想を解きほぐしているのは、これまでに書かれたもののなかでは、これを置いてほかにはないと思うのだ。
岸は巣鴨刑務所から釈放されたのちも、しばらくは公職から追放されていた。
岸信介が追放解除になったのは、昭和二十七年四月二十九日、講和条約の発効による。この時から彼の政治運動が始まった。
その頃、岸信介等の運動のことをある記者が質問に来て、戦犯で追放解除されたものが日本の政治の再建などを口にするのはどうかと言ったところ、岸は次のように答えている。
「私は巣鴨生活で過去一切は清算した積りだ。したがって自分としてはその資格はあると思う。他から東条内閣の閣僚だとか軍の手先だとは言われるかも知れない。それはある程度事実なんだから止むを得ないが、現在の自分の気持としては元商工大臣とか翼政総務とかそんな過去の経歴にこだわる気持は毛頭ない。」
これは、日本語の表現として非常に巧みなものである。追いつめられて吐いた言葉でありながら、逆に前に乗り出した言葉である。『過去一切』を巣鴨で『清算』したというのは、性格には切棄てたという意味であるが、何となく罪をつぐなってしまった、という感じも漂う、『清算』という帳簿上の術語は、このように罪は洗われたという意味に使われる。彼はそう使っている。そして、それ故に自分は日本の政治再建を企てる資格がある、と飛躍する。日本語の曖昧さを実にうまく使っている。そう言っておいてから、軍の手先だったのは真実だ、と事実に即したところへ一歩退く。だが最後のところを注意して読むべきである。商工大臣、翼政総務だったことにこだわらない、というのは、もとの高い身分を自分の既得権として持ち出す意志はない、という意味である。即ち、持ち出す意志がないというのは、それを主張しないが、それは事実であったから、人は認めるだろうが遠慮する、という意味だ。即ち、元のような高い地位の者として扱われることを遠慮するというのだ。ところが、その元の地位なるものは、すぐその前に言っている非難される地位なる『東条内閣の閣僚とか軍の手先』というのと同じものなのだ。非難されるのは当然だ、と言っておきながら、そんなに元の高い地位を気にかけないでくれ、と世間が自分を高く評価するものと予定して遠慮しているのだ。
「こだわるつもりはない」というのは罪にこだわる、というのと、高いもとの地位にこだわるというのと、両方にかけ、後の方にうまくしぼってしまった表現である。相手の方は、どう致しまして、やっぱりあなた様は元商工大臣です、といわねばならないところまで持って行ってしまう言い方である。日本語はあいまいで、アンビギュアスで同語両義の場合が多い。人心を一新する、などというと、自分に何の失敗もなかったので、人々が単に厭きたから、改めようと言うことになる。同時に、私の与えた悪印象を一掃しようという意味にもなる。
(「岸信介氏における人間の研究」伊藤整『週刊コウロン』)
なるほど、記者から尋ねられた瞬間の、当意即妙の答えのなかに、これだけの含蓄と意志と、それに深謀遠慮があるというのだから、恐れ入る。それを見抜いた伊藤整の切れ味もさすが、というべきだろう。
国会議事堂の正面からのびる道は、皇居のお堀端に向って、気をつけて歩かなければ気づかないほど、やわらかな坂になっている。
その地形は、安保改定にゆれる当時も変わらなかった。
こんどの国会デモの長い隊列の間をぬつてあのなだらかに傾斜した不定三角形の道を何回も上り下りしている裡に、謂わばきらめいては消える遠い虚空のなかの小さな白い物体のように脳裡に浮んだ想念が二つある。
そのひとつは、神のいない空虚な神殿を広大な群衆のねり歩く祭典がおこなわれているがごとくに、いわば権力がひとつの象徴と化してもはや空虚な神殿となつているところの国会を、巨大なデモの隊列が盲目的な祭典を行つてめぐり歩いているのではないかという幻想ふうな印象である。勿論、この国会のなかがまつたく空虚な神殿であるというのは言い過ぎであろう。そのなかには単なる権力の象徴があるばかりではなく、無理やりに支えられた権力の不思議な部分がおしこめられているのである。にもかかわらず、もはや権力がそこに存しない筈の空虚な周囲を、、巨大なデモの隊列が絶えまなくめぐり歩いているのではないかといつた盲目的な祭典の印象が私に覚えられたのは、このデモの隊列を構成している人員が、その生産点においてすでに動かすべからざる権力をかたちづくつているところへの自覚に徹底していないごとくに見えたからである。請願デモという言葉にしめされているごとくに、向う側にある権力の意志によつて事態の方向をようやく換えてもらうという気分、即ち自己は事態の変化をもたらすところの権力者ではないという不思議な考え方がそこに窺われたからである。
この神なき神殿をめぐる盲目的な祭典という印象のほかに、もうひとつしばしば脳裡にひらめいた印象は、この空虚な神殿を警備している警官の隊列が、不意に一せいに横にむかつて歩き出し、そこが裸かになつたら、内部にあつて空虚な神につかえている神官達はどのような恐怖を覚えるだろうかという印象である。支配者が彼等を防衛する盾を失い裸かにされたとき、全から忽ちにして無となる自身の空虚な実体をどん底まで実感する恐怖の瞬間が、まざまざと味あわれるに違いないからである。しかし、勿論、これら二つの印象は、いわば喜ばしいプラスも多く見出されるデモの隊列のなかで、きらめく小さな光のように思い浮べられたところの幻想なのである。
(『罠と拍車』埴谷雄高)
この「空虚な神殿」の頂上を目指し、歩いてきたのが、安倍晋三だった。
もちろん、それは晋三に限らずとも、政治家となった者のすべてが目指すべきところであるのかもしれない。
だとすれば、まさしく「総理のイス」は、誰もが憧れながら、そんな現実感の伴わない空虚さのなかの究極の高みに置かれているのだろう。
六〇年の安保改定当時、増える群集は、国会から、官邸、そして祖父・岸信介が住む南平台の邸宅をも取り囲み、いよいよ治安維持を名目に、自衛隊の出動までが検討されるに至っていた。
繰り返し、ウメの脳裏を去来する光景があった。
外では、今日もまた、「安保反対」を叫ぶ学生たちのデモ隊が渦巻いている。
表通りから玄関に入ろうものなら、家人だろうと石が投げられ、危険きわまりない状況である。
ただ、その当時の南平台の岸邸は、ウナギの寝床のように奥行きが深かく、石は家屋までは届くことはなかった。
休日にそぐわない喧騒を横目に、ウメは台所や応接間を行き来していた。と、そこに、誰かが不意に裏の勝手口を開ける気配がし、のぞくとそこには佐藤栄作が立っていたのだという。
国道二四六号線沿いには現在も養命酒の本社ビルが建つが、そこから南平台の細い路地を入ると、岸邸の屋敷裏に通じていた。佐藤が岸の実弟とはいえ、教えた覚えのないそんな道を通って勝手口に辿り着いたことにウメは驚いたという。
「ああ、表は騒がしいからね。裏からきちゃったよ」
警備も秘書もつけずに、安保反対の騒動のなか、勝手口にぶらりと現れた佐藤は、飄々とした表情でそう応えた。
そんななか、窓外から聞こえてくる「安保反対」のシュプレヒコールが否応なく耳に残った幼い晋三は、岸の前で「あんぽはんたーい」の戯言を繰り返してジャレた。岸は、そんな晋三を叱ることもなく、柔和な眼差しで見つめていたとウメは語った。
晩年の岸は、熱海市若林に、およそ一六〇〇㎡もの別荘を所有していた。
この別荘でかつて起こったある出来事を思うとき、やはり岸―晋太郎―晋三という三人の総理と総理候補を輩出したこの王朝が辿った運命を戦後政治の歴史に重ねて、不可思議にして皮肉なめぐり合わせに恐れ入るのである。
安保条約改定の断行をめざす岸は、幾たびも絶体絶命の状況に追い込まれていた。
しかし、そのたびに、それこそ〝妖怪〟のごとくに不気味に状況のなかを蘇ってみせた。
やがて警職法の審議が国会で行きづまり、安保条約改定の時期尚早論も出て、岸政権は危機に瀕し、岸信介は三十四年一月二十四日に総裁公選をくりあげておこなう。
このとき熱海会談というのがあった。一月早々に、岸は反対勢力の領袖である大野伴睦、河野一郎の両実力者を熱海の別荘に招き、岸政権への協力を依頼する。
児玉誉士夫の書いたものによると、岸信介が当時の副総裁・大野伴睦にむかって、
「自分のあとの総裁は、ぜひあなたに」
と暗示しつつ協力を頼むと、大野は、
「佐藤栄作くんさえ、今後の言動に気をつけてくれれば……」
と淡白にこたえたという。
(『巨魁』)
警職法の改正は、岸が安保改定とともに進めていた、岸内閣の二大課題のひとつだった。
いささか、状況が複雑だけれど、この情景は、安保条約の改定に向けて行き詰まった状況を打開するために、岸が熱海の別荘に有力者を集め、総理のイスを大野に〝禅譲〟することと引き換えに安保改定への協力を取りつけた場面ということになる。
この情景を知ったとき、つくづく熱海というのは近代日本の「鬼門」だな、と思うのだった。
その意味は、政治家にとってももちろんだけれど、その熱海で数人が囁いたその結果に大きく左右されるという意味で、むしろ国民にとっての「鬼門」ということになる。
岸は結局、この約束を反故にし、大野は総理のイスを逃したのだった。
毀誉褒貶の激しい岸の政治家としての人格で、こっぴどく岸を嫌う人々がまず間違いなく一致してあげものといえば、この熱海会談だろう。
ところが、まさしくこの情景を、やはり児玉という虚実ないまぜの人物が語ることに示されているように、この熱海会談の内容の真偽については、これまた定かなものがなかった。
もし、日本に権謀術数史というものがあれば、紛れもなくそこに刻印を記すであろうこの熱海会談について、孫の晋三が、岸に直接尋ねたことがあった。
例えば、安保を成立させるために大野伴睦さんを説得した。その中で、大野さんに次の政権を渡すという念書を書き、大野さんを騙したと世間的にはいわれていました。そこで、その念書の件は本当なんですかということを、ある時、私と祖父と私の伯父とで昼飯を食べている時に、伯父が聞いたんです。
おそらく、「伯父」とは、岸の長男である岸信和であろう。
「あれは、確か書いたなあ」と祖父はいいました。伯父も私もその回答にはショックを受け、伯父はさらに「本当にそう思っていたんですか」と核心にふれる質問をしました。祖父は食べながらちょっと考えていた。そして、「あれを書かなければ、安保はどうなっただろうか」と一言いったんです。
生真面目で正義感の強い伯父は「政治家というのは悪いなあ」と言いながら私を見ました。私はなんとなく伯父に同意したように記憶していますが、私の気持は整理できていませんでした。一般の道徳からいえば、総理大臣が念書まで書いて大野さんを騙したわけですから、これはとんでもないことでしょう。しかし、ではそれをやらなかったらどうなったのか、ということです。
ここから急転、晋三は祖父・岸信介の語った歴史の真実を目の当たりにして、みずからの政治信条に引きつけてこう結論する。
例えば、当時の大野派の協力が得られない。党内もうまく行かない。よって安保条約も成立しない。とすると、人間の普通の社会での道徳は完うできるけれども、政治家としての本来の使命は完うできないでしょう。だとすれば、日本の運命はどうなるのか。だから、政治家は「結果責任」をより厳しく問われなければならないのではないか、とその時私は漠然と感じたわけです。
(『「保守革命」宣言』)
孫が、この祖父の語りから自身の政治信条を導き、あるいは補強していく姿には、ある種の慈しみさえ表れているように思ってしまう。
それは、晋三自身が記しているように、かつて京都大学の学生時代、全共闘の学生運動に身を投じていた岸信和が、親父の口から語られたこの歴史的な〝非難〟の場面を聞き、純朴に「政治家というのは悪いなあ」と感じ入ったのとは対象的に、晋三は一方でその場面がみずからのなかでは否定には至らず、むしろそこに、結果責任を優先すべきであるという、「目的のためにはあらゆる手段を尽くして見せる政治家の業」ともいうべきものを観たという風景にほからならいのだ。
この岸と晋三とをつなぐ流れを見たとき、やはり晋三は、来るべき総裁選に「勝ちにくる」のは当然だし、もしかしたら勝つかもしれないな、と予感した。
晋太郎に欠けていたのは、まさにこの「勝つためにはときに手段を選ばない」執念であったのかもしれない。
そして、それは、常人の道徳観に照らせば、「卑怯な器」であるのだろう。
この卑怯さこそ、実は、「政治的体質」とでも呼びうるもののようにも感じた。
長らく、「political maneuver」という西洋の概念に対する日本語としての適訳を探していたのだけれど、熱海会談の話を紐解いたとき、初めてこれに「政治的体質」という語感がしっくりくるのだ、と納得した。
それにしても、この熱海会談が安保改定を成功させた決定的な瞬間だっと見えなくもない。
この熱海では、明治年間の一八八一年に、それこそ国会そのものの運命を決定付ける歴史的な会談が行われていた。
伊藤博文、大隈重信、井上馨の三人が終結し、国会開設について話しあったとされる、元祖「熱海会議」がこれにあたる。
ところが、国会設置という日本の政治史上最大のドラマであるにも関わらず、この熱海会議の記録はいっさい遺されていない。
ではなぜ、記録が残っていない会談がそもそもあったといえるのか、という疑問が沸くけれど、それは、一八八一年一〇月一四日付けで福沢諭吉から出された伊藤博文と井上馨の両氏に充てて送られた手紙にそれが記されているだけなのである。
日本の近代史上、節目となる事件をめぐってこうして舞台になるから、「熱海」とは、国民にとっては鬼門さながらなのだった。
それに、まるで「熱海」は、連綿と続く「密室政治」の象徴のようでもある。
安保改定への協力と引き換えに大野への総理のイス「禅譲」を誓う岸―。
その取り引きこそ、五五年体制を貫いた自民党による「総理決定過程」そのものではなかったか―。
そして、そうであれば、まさしく岸も一役買ったその「五五年体制」の哲学と伝統によって、安倍晋太郎は総理候補となり、そして総理のイスを逃したのだった。
九〇年四月、現職総理の小渕恵三が脳卒中で再起不能となったとき、有力政治家数人が角突合せ、赤坂のホテルの一室で次の総理を決定し、その結果「森総理」が誕生した。
そのとき、その前近代的な野蛮さを弾劾せんばかりに、世論は沸きに沸く。
でも、その〝野蛮〟こそが、岸を始祖とする王朝としての始まりを決定づけた安保改定の実現という「伝説」を生んだわけだった。
ならば、やはり晋太郎は、王朝の本流として、王朝の哲学である「禅譲政治」だからこそ敗れた、「体制のあだ花」であったのかもしれない。
そして、ついに既存体制の破壊を掲げて現れた小泉純一郎という異質の統治者がいた。
自民党政治の骨髄ともいえた派閥政治を全否定するその小泉が、自らの政権の四番バッターに抜擢したのが晋三だから、祖父により近い信条の親和性を感じ取り、育んだ自らの存在意義が、自らが引き継ぐ王朝の存立哲学の「逆説」としてあるとすれば、何よりもそこに政の非業さが見てとれるようだった。
ちなみに、まさに「五五年体制」こそが、密室政治の紛れもない最盛期であったことを示すあるインタビュー記事を、ある時見つけてしまった。
毎日新聞の記者からフリーランスのジャーナリストとなった大森実と、児玉誉士夫との対談は、くだんの岸―大野という禅譲政治の懐の奥深くを無遠慮なほど赤裸々に語っていて面白い。
このインタビューは、「大森実直撃インタビュー」という題で、『大森実 戦後秘史』の第一巻に収録されている。
大森 それから例の安保の前、帝国ホテル光琳の間における誓文問題。あなたと北炭の萩原吉太郎、大映の永田雅一を立会人として、首班後継者を大野伴睦とするという誓約書を岸さんが書いたという事件の真相が聞きたい。
児玉 そうです。
大森 あのときの岸の後継者問題では、あなたは藤山(愛一郎)を推したんですか。
児玉 私は藤山を推さないです。あのあと大野伴睦を推しました。
大森 だけど、大野伴睦には岸がやらなかったわけでしょう。
児玉 やらないです。
大森 結局は池田勇人に後継バトンが引き継がれましたね。
児玉 そうです。それで、約定によっては大野に渡し……
大森 そうですね。(岸信介は、三木、池田、灘尾に閣外に出られたので、孤立感から大野を後継者に仕立てた)
児玉 (はじめの岸構想では)河野に渡し、河野の次が佐藤だったんです。いいですか。
大森 はい、そうです。
児玉 それで、いよいよ今度、内閣がああいうふうになったとき、大野さんが「約束が違う。岸はおれを第一番にするといったじゃないか」というから「それは先生悪いぞ、この条件ができたときは、大野と河野が車の両輪のようになって岸を守る、盛りたてるという約束じゃなかったか。それを大野先生、あなたがコトを急いで、岸が最後の断末魔のとき、入閣してくれというのに、あなたは入閣されなかったじゃないか」と。
大森 うん。ああ両輪にならんか。片輪がおちたということか……
児玉 「岸内閣をつぶしたのはあなただ、はっきりいえば。だから、これはあなたがいう権利がないんだ。ないけれども、約束は約束だからぼくはあなたを支持しよう」と。
大森 うんうん。
児玉 「じゃ、岸さんとこへ行ってきてくれ」というんですよ。それから、岸さんと「新中川」かなにかへ行きましたよ、いっしょに。で、「岸さんどうだ。大野に譲らんか。一月でもいい。約束は守らないといかん」といったら、「きみ、正気で大野に譲れというのか」というから「半分正気だ」と。「それはおもしろい言葉だな。半分正気とはどういうことだ」というから、「情においては譲ってもらいたい。しかし、実際は無理だろう。大野先生が議会の答弁ができるとは思えない。複雑なあの国会の答弁は難しい。だから、実際は不可能だ。だけど、そこをなんとかして譲る。あんたは譲りたいんだが、大野さんの方でおれは無理だというように話をもちかけたらどうか、名案が生まれようじゃないか」といってやったんですよ。そして河野に、私は入閣しろといったんです。
大森 うん、うん、うん。
児玉 そこで河野はしなかったでしょう。
大森 しないです。
児玉 それで、あのときも、あの連中がみな政治では私より大先輩ですよ。それが、「池田は絶対入閣しないからだいじょうぶだ。のたれ死にだからおれの方に回ってくる」と大野さんは威張ってたですよ。「とんでもない、池田はあしたの午後入閣する」といったんですが、池田は入閣したでしょう。
大森 うん。(三木、灘尾を裏切って入閣した)
児玉 だから、天下は池田のところへ行ったでしょう。
大森 そうです。そうです。
児玉 岸から池田にいっちゃったでしょう。
大森 はいはい。
児玉 (その前に)鳩山がダメになってから、石橋と岸の争いでしょう。(次の談話で訂正されるから原文のまま)ところが、河野さんは最初、読売の正力についてたんですよ、ほんとうのことをいうと。それはぼくは知ってるんだ。「仕方がないが、正力が頼みにくるから正力を出そうや」というから、「それはダメだ」と。
大森 正力が総理大臣ですか。
児玉 「それはとてもダメだ」といってるところへ佐藤さんが私のところへ来まして「相談がある」と。
大森 佐藤栄作が?
児玉 栄作がね。「きみ、兄貴を推薦してくれ」と。
大森 おまえやったらどうだといわれた?
児玉 いうから、ぼくは「それはどうかな」といったら「そうもいかない。とにかく車の両輪を破ったのもこっちだし、次に池田に譲るとき、大野に譲らず池田に譲った経緯があるから、今度池田から佐藤」と……池田からあれにいったんですか、岸さんから池田にいって、池田から佐藤でしょう。で、私のいまの話は、岸さんのなるときだ。
大森 そうでしょうね(訂正を容れる)。
児玉 おもしろかったのは岸さんがなるとき、『河野を岸につけろ』というんですよ。佐藤栄作がきて。
大森 はい、はい。さっきの話はそのときのことですね。
児玉 いまちょっと間違えた。それから、そのとき佐藤栄作が、「この前、吉田のところに兄貴(岸信介)があいさつに行った。自分(岸)が立候補するから頼みますといったら、吉田が『きみの立候補にはおれも賛成だ。いいよ、だが、児玉と縁を切ってくれないか、岸君』と兄貴はいわれた。そのとき、兄貴がどうしてかと聞いたら、吉田が天下をはなして(政権をほうり出して)、政権が鳩山に行ったとき、わたしが広川弘禅をこっちへとって、私が斡旋(保守合同)をやったでしょう。それが頭に残ってるわけです。『あんな悪いやつはない。あれと縁を切ってくれたらきみ(岸)を応援する』といったんです。そしたら兄貴(岸)がいうことには、『それはダメだ。あなたも戦争中(近衛上奏文事件)、憲兵隊にぶちこまれたとき、監獄の中で、あの留置場の中で友だちができたでしょう。いまなお欲も得もなく、彼らとつきあってるでしょう。児玉とおれとは、そういう戦争前からの仲なんだ。なにもあれは、いちいち口出しするわけじゃない。別にあれを条件に応援されるというなら、私は結構です』と兄貴は帰ってきたんだ。そういう兄貴(岸)をきみ(児玉)は助けないとはおかしいじゃないか」というから「わかった。それはやろう、それでは河野だけじゃなく大野もひきずりこもう」と。
大森 ああ。
児玉 河野はもちろん応援です。「きみがそこまでいうならおれはやる」といって。で、また(ぼくが)大野のところへ行ったら、石田博英とか、信州から出ている……
大森 倉石
児玉 「倉石が反対だから困るなあ」というんですよ。「いや、そういわないでやってみてくれ」といったら、「岸は自分がなったらおれ(大野)をのけ者にするんじゃないか」というので、「いまは、私があなたのところへきたが、あなたがいいといえば、私が入れ違いに(岸を)すぐ呼んでくるから、それであなたと約束してくれ」といったんです。それで「岸はおれに頼むというな」と(大野が)いうから「いいます。まちがいなくいいます」といったんです。そしたら「それならいいだろう。やってみよう。倉石も博英もみなむこうだけどもなんとかやってみよう。しかし岸がおれに頼まんとまずいな」といったから、「いま来る。もう来ることに時間が決めてあるんだ」といったんです。ところが(岸がきてみると)「よろしくお願いします」しかいわないんですよ、岸さんが。そのときに、「閣僚の人選、その他全部あなたと相談の上」といえば、これ(大野)はのったんですよ。それを(岸が)いわなかった。
大森 ああそうですか。
児玉 たったひと言足らなかった。で、結局石橋湛山になってしまい、石橋が病気で倒れたので岸がなれたんです。
このインタビューが記録されたのは一九七四年五月二五日だった。
児玉が一方的に語るこの「舞台裏」がどこまで正確なものかは、もちろんわからない。この話の登場人物の複雑な人間関係を読み解くのは、それこそ専門の政治記者でなければわからないかもしれない。
けれど、生々しい臭気さえ伝わってくるこの会話のなかで、ある分かりやすい原則が貫かれているのはよくわかる。
それは、総理のイスををめぐって、次は誰に「譲る」とか、「渡す」とか、「頼む」とか、あまりに話が小さくまとまっていることなのだ。
ここまでの生々しさを突きつけられてしまうと、結局、総理のイスとは、政策や人柄とはまったく無縁の、「譲る」「渡す」「頼む」世界の、半径の小さいムラの人間関係で、ときにめぐり、ときにめぐらずのものなのかもしれない、と、改めて愕然としてしまった。
こんな小さなムラの掟によって、国民が生きる大きな世界が規定されてしまうことを、岸王朝というひとつの歴史を多少なりとも垣間見た気になったところで、初めて実感したのだ。
仮に岸王朝の末裔が「安倍晋三」という人間だとすれば、産経新聞に掲載された晋三自身の次の言葉は示唆に富む。
「思想家ではない政治家に求められるのは、理念は理想をあくまで追求することではなく、現実の世界で結果を出すことだ。そういう大きな判断を政治家はしていかなくてはいけない。」(二〇〇〇年五月十五日付朝刊)
徹底した現実主義が、岸王朝の真髄とも映った。
第2章
雌伏の時
幼少から米国時代
政治家の家に仕えて
大正一四年八月六日生まれのウメは、意外なことに幼少の一時期を東京でも過ごしている。
千代田区の麹町小学校で過ごしているわけだが、公立とはいえ、その頃の麹町小学校といえば、実は名門中の名門だった。
東京には、現在こそその名残が薄れつつあるものの、御三家と呼ばれる名門小学校が文字通り三つあった。
一〇〇年来の歴史を持つ、文京区の誠之、千代田区の番町、麹町の各小学校といえば、ときに都下の有力者の子弟が学区を越えてこぞって集まり、まるでお決まりのように、一高―帝大コースを歩んでいったのである。
それは現在まで変わらない。
その頃の誠之・番町・麹町が名門とはいえ、それはよく考えれば同時に不思議な光景でもある。
選抜試験を施さない公立の、それも小学校がどのようにして〝名門〟足りうるのか、と知らない者は思うかもしれない。
それもそのはずで、当時は、その小学校の学区であった文京区西片や、千代田区番町・麹町に居を構えていることそのものが、まさしく日本を代表する最高の「エスタブリッシュメント」であることを示していた。
現在のように高級住宅地が、いってしまえば都内全域に散在しているのではない時代、「お屋敷街」といえば、まさにウメが通った麹町小学校あたりに限られていたといっても過言ではなかった。
だから、麹町にも帝大教授の子弟であり、かつての貴族院議員の係累であり、果ては子爵の末裔まで、およそ日本の上流階級だけが軒を連ねてムラを作っていたというほうがピッタリとくる。
つまりそれは、裏を返せば、なかなかに「鼻持ちならない」場所でもあった。
昔から、教師までもが「私たちは歴史と伝統ある、そして数多の優秀な先輩方を輩出してきた誠之の…番町の…麹町の…」という訓示を好んで連呼し、児童にその理屈なき自覚刷り込んでいた。
ウメと向かい合うなかで感じられた、彼女に漂う気品に同居してどこか漂う気位の高さのようなものは、ウメが番町小学校に通っていたと聞いて、初めて納得できるところがあった。
わずかながらウメ自らが学歴について触れたことがらをまとめると、小学校は父親が麹町に居住していたことから番町小学校に通っていた。麹町はある意味で当時の上流階級が好んで集っていた地区であり、ここで素養が備わったと考えれば合点がいく。小学校を卒業して女学校へ進む段階で、ウメは故郷の山口県に戻り、長門にあった県立深川女学校へと進学した。
縁あって岸信介が住まっていた渋谷・南平台の屋敷に勤めることになるのはもちろん女学校を出てからのことだけれど、女学校卒業からふたたび上京するまで間、ウメが何をしていたのかは、実のところはっきりとはしない。
それは、たいへんな落ち度だった。
病院に〝幽閉〟されてしまう前のウメに何度か会った時は、まさかこんなかたちでウメに「会おうに会えない」日が来るとは予想だにしていなかったから、ウメの話を聞いているときも、それは自然な流れに任せるようにしていた。
ウメの感情の流れに沿って、できるだけその起伏を汲み取ろうと心がけていたから、若い日の経歴について根をつめて聞くのはいつでもできる、とそんなことを思っていた。
でも、それが失敗だったわけだ。
そこで、ウメを知っている油谷の人々に話を聞いてみると、意外にもウメが地元・油谷で保育園の先生をしていたという話が出てきた。
ウメの口から「保育園の先生をしていた」とは聞いたことがなかった。
でも、その姿を知っている古い住人が言うのだから、きっと間違いないのだろう。
一度、ウメから「若い頃は、証券会社に勤めていたこともあった」という話を聞かされたことはあった。
保育園と証券会社、いずれも女学校を出てからの経歴ではあるだろうけれど、いったいどちらが先で後なのか、今となっては確認するのもままならない。
ただ、保育園の先生をしていたと聞くと、ウメがのちに岸邸から安倍晋太郎の家に移り、晋三や兄・寛信など子供たちの面倒を見ることになった経緯が理解できるようにも思えた。
晋太郎や妻・洋子は、岸邸の台所を切り盛りしていたウメに子供を扱う経験があるからこそ、全幅の信頼を寄せて「住み込み」として招いたのだろう。
岸邸から、それこそ安倍家に仕えるようになった詳しい経緯をウメが語ったことはなかったけれど、きっとそこには政治家として外での付き合いに忙しい晋太郎夫婦が、子どもの相手を探していたという事情があったことは想像に難くない。
晋太郎の妻・洋子は岸信介の娘ということで旧知の間柄であり、岸の妻・良子とは互いに一を口にすれば一〇までを察する仲であったことはウメが打ち明けている。
場合によっては、幼子二人を抱える洋子が、母親に相談し、そこでウメに白羽の矢が立ったのではないかと思っている。
ウメの記憶では晋三が「二歳半」のときにはもう面倒を見ていたというから、この〝推測〟は当たらずとも遠からず、だろう。
晋太郎夫婦は、長男の寛信の下に晋三を抱え、その晋三も二歳をすぎて知恵がつき始めたのを見かねて、誰か家庭内を切り盛りしてくれるしっかりした人を……、と考えたに違いなかった。
ウメによれば、晋太郎のことは岸邸の頃から間近でつぶさにその姿をみてきた。毎日新聞の記者を辞めて、岸の首相秘書官として南平台の屋敷に詰めていた晋太郎とは毎日のように顔を合わせていた。二人は年は違えども、それはわずか晋太郎が二歳年長であるに過ぎなかった。ほぼ同年齢の二人が、ひとつ屋根の下、岸信介の周辺で忙しい時間を過ごしていたのだ。
もちろん、そこにはすでに晋太郎と結婚した洋子の姿はあったけれども、思いのほか気が合ったという晋太郎との仲関係性は、ウメが後に岸邸から安倍家へと移ったあとに、より一層、太い絆として育まれていく。
洋子の婿、安倍晋太郎
晋太郎が岸信介の娘、洋子と結婚したのは、一九五一年五月五日のことである。
面白い話がある。
実は、この晋太郎と洋子が結婚することになった話にも〝諸説〟があるのだ。
ひとの色恋話に色がつきものといえば、いささか講談めいても聞こえるけれど、この話は晋三の祖父、岸信介に連なる「人柄と家系の匂い」が漂ってくるので、今一度紐解いてみたい。
ノンフィクション作家・岩川隆が自著『巨魁 岸信介伝』で元代議士の福家俊一の話として紹介している。
岩川自身がいうように、話が「うまくできすぎている感がある」のは確かだけれど、でもこの一節を読んだとき、あまりの傑作に思わずニヤリとしてしまった。
岩川の『巨魁』が最初、ダイヤモンド社から刊行されたのは一九七七年のこと。
ニヤリ、と意地悪な笑みがこぼれたのは、そののち九二年に、当の安倍洋子自身が語った結婚にいたった逸話を知っていたからかもしれない。
だから、福家の話を読んで、ハハア、パズルははまったな、と思った。
ひとつの「一九五一年五月五日結婚まで」の時間を埋める事実が、大きな時間の流れを置いて、初めて浮かんでくることが、驚きと同時に、政治家をめぐる「話」が時間によって色褪せずに、むしろときとして艶を増しさえするその不可思議さを象徴しているようで面白かったのだ。
では、まずは、『巨魁』に記された福家俊一の話から。
福家は、岸信介とは満州時代からの深い仲にあった。その頃、岸はA級戦犯として巣鴨刑務所に収容されていた。
終戦直後に引き揚げてきた福家は、そのころ京都で漁業市場の経営をおこなっていたが、とつぜん佐藤栄作(当時鉄道総局長官)の電話を受けた。
「至急、上京してこい」
という。
「混んだ列車に乗るのは厭だよ」
とこたえると、
「ほかでもない、兄貴からの頼みなんだ。是非、相談にのってくれ」
といい、
「進駐軍の列車に乗ってもらうよう手筈はついている」
とのことであった。そこで福家は、暖房のきいたがら空きの特別車輌に乗って上京し、佐藤とともに巣鴨へ行った。金網のむこうに姿をあらわした岸信介は、やせてひょろ長く、顔は眼と歯だけのようにみえた。岸は福家にむかうと、
「わしは、死んでも死に切れん心残りのことが一つある」
という。なんだ、ときくと、二人の子供の将来についてであった。まだ未決のころであるから、遺言にひとしい頼みである。
岸には長男の信和と、長女の洋子という、二人の子供がいた。その将来を危惧したのだという。
「信和が、難波大助になってもらっちゃ困る。いまの生活さえ変えさせればあとはどうにか男一匹で生きていくじゃろう。……それに娘の洋子のことじゃ。あれを男として立派な奴に嫁にやりたい。わしの体験からいって、相手は政治家や実業家というよりも新聞記者がいいと思う。時代の流れがそうなる」
と、かれはいった。
岸信介がこれからは新聞記者だと語ったとすれば興味深いが、そのとき依頼を聞く福家は胸がつまったという。信和はそのころ京大生として全学連の委員長をつとめていたのである。岸としては、共産党だけは困るという心境らしい。戦犯容疑の父を持った境遇もあって、共産党全盛の折から、反抗的に左翼運動にはしったものと思われた。
当時、知識人や有力者の子弟が左翼運動に走るのは、それこそ時代の流れともいえた。それこそ若き日の堤清二しかり、政治家、実業家を問わずに少しばかり政治状況に目を向けるさかしさと、何よりも〝余裕〟のあるものが当時の左翼運動の先頭をむしろ誇らしげに走っていた。
戦後に生まれた第二次ベビーブーム世代には実感が伴わないことが多いかもしれないけれど、第一次ベビーブーム世代の人々にとっては、若い一時期、「ずいぶん頑張っちゃったな」と、密やかな心当たりのある者は多いはずだった。
しかし、第一次ベビーブームのさらに親の、まさしく「戦中派」世代は気が気ではない。戦後、進駐軍による占領下と、日本経済の回復期に向って、「赤狩り」と「反乱分子」への抑圧は嫌が応にも高まっていく。
我が子の思想信条はともかくも、我が子の「身」そのものを案じるのは親として、生物として本能的なものでもある。
岩川は続ける。
「わかりました」
と引き受けた福家は京都へ帰ると信和を呼び出し、暴力まがいにかれを将軍塚に引っ張りあげて、
「きょうは福家俊一じゃない。オヤジの代理としてきくからこたえろ
と、詰問した。きけば卒業の単位はすべて取得しているという。そこで、
「いいか。田布施に帰れ。わかったな」
と説得したというのである。信和は悩み抜いたらしいが、けっきょくは父親の気持を受け入れて田布施に帰り、岸信介と山口中で同期生の中安閑一(当時専務)がいる宇部興産に就職した。いまは西武石油会社の常務取締役である。
もうすこし福家の話をつづけよう。
……娘の洋子の相手については、福家はもともと新聞界出身であるところから情報あつめをつづけていた。そのうちに毎日新聞政治部の長坂慶一という老記者から、
「おい。灯台もと暗しだぞ」と電話がかかってきた。「今松陰の息子が政治部にいる」というのである。今松陰とはほかならぬ翼賛選挙で出てきた安倍寛代議士のことをさしていた。安倍は福家にとっても囲碁を教わった先生であるから、その息子となれば花婿候補者としてわるくはない。福家はまたまた進駐軍列車に乗って上京し、新橋の闇市の焼き鳥屋で安倍晋太郎という男に会ってみると、なかなかの人物である。その足で佐藤栄作のところへ行き、同じ山口県人同士でたがいに家柄も承知だということで否も応もない。田布施の岸家から母娘を呼んで一ノ橋の佐藤邸で見合いさせた。
安倍晋太郎としては上司への義理もあってとにかく会ってみようという気持ちだったらしいが、福家がみるところ、見合いしたとたんに二人ともひと目惚れといった風情であった。その結果を佐藤栄作が巣鴨に報告にいくと岸信介は大いに喜び、
「安倍代議士ならわしもよう知っちょる。その息子なら会わんでも安心できる。ご先祖のお導きじゃ」
と安堵した表情であったという。
この「一ノ橋の佐藤邸での見合い」は、洋子自身の口によると、次のようになる。
わたくしが安倍晋太郎と初めて会ったのは、昭和二五念六月のお見合いの席でございました。渋谷の南平台のレストランでフランス料理をいただいたのですが、父の叔父に当たる松岡洋右外務大臣(第二次近衛内閣)のコックとして出入りしていた橋口さんのお店で、その店がなくなってから隣の土地に父の家がつくられたのですから、南平台にはよほど縁があったのでしょう。それはともかく、当時、晋太郎は毎日新聞社政治部記者をしておりましたが、父が望んで新聞記者を結婚相手として探し、本人を気に入って、わたくしに会わせたのでした。
(『わたしの安倍晋太郎』)
ところが、ここから事態は思わぬ方向に転んだ。再び、福家のスジ書きに戻ると……。
しかし、この縁結びは以上で終わったわけではない。しばらくすると安倍のほうから、この話はなかったものとしたい、と申し出てきた。福家が安倍に会って話してみるとどうも要領を得ない。そのうちピンとくるものがあった。当時は読売の大争議がいままさにはじまろうという雰囲気で、いまからは考えられぬほど左傾化した世の中だった。安倍は戦犯の娘をもらうそうだ、というので新聞記者仲間から村八分にされていたのである。まさに時代の波といえよう。
「じゃあきくが、娘が不満なのか」
と福家がたずねると、
「いや決してそうじゃない」
とこたえる。
「好いてるのか」
とふたたび問うと、安倍は、
「好きです」
という。かれとしても悩み抜いたうえでのことだったろう。やむを得ず福家は佐藤栄作を引っ張り出して赤坂の料亭でふたたび安倍晋太郎と会い、いろいろと話し合った結果、「もらいます」ということになったという。岸信介が巣鴨から釈放されたのは、それよりのちのことであった
(『巨魁』)
真偽不明のこの妙に情景の細かい話を、当の洋子が知ってか知らずか、九六年に発刊された自著『わたしの安倍晋太郎』ではたしかに、一時、「見合い話」が停滞したことを明らかにしている。
ところが、思わぬところでこの縁談に反対が出ました。母方の祖母が、安倍本人を見てはいないのですが、新聞記者という職業に好感を持っていなかったのです。なにしろ朝も夜も時間はおかまいなしにやってきますし、礼儀知らずでずうずうしいというのが祖母の印象であったのです。安倍のほうにはこちらから返事もしないでいたものですから、そのまま没交渉で時が過ぎました。
のちに、父が養子でしたから祖母に遠慮があったのだと評する人もおり、また「戦犯の娘と結婚するのか」と、当時は左翼的な言動が主流であった記者仲間から主人が指を指されたからだという解説もありました。しかし、わたくしの感覚では、祖母の反対があるので無理にどうこうするのではなく、なんとなく途絶えていたということなのです。
その間、いくつか縁談は持ち込まれたのですが、やはり主人のほうがいいと思っておりましたから、その後はどなたともお見合いはいたしませんでした。十一月になって、佐藤の叔父の口ききでしたか、主人とまた会うことになりました。お見合いの仕切り直しなんて聞いたことがありませんが、ぜひにということでしたから、わたくしにはわかりませんが、さて、なにがこちらの値打ちを高くしたのでしょう。
洋子の記憶に従っても、先の「福家の話」と、奇妙に符合する場面があることにハタと気付く。
やはり、佐藤栄作が絡んでいたことはどうやら間違いなさそうではあるのだ。
ともかくも、ずいぶんと時代がかった舞台回しとお膳立てのうえで、晋太郎は洋子と結ばれ、〝タネ〟が仕込まれる算段と、あいなった。
そして、岸信介が「ご先祖のお導きじゃ」と洩らしたというその末に、安倍晋三が生れ落ちた。
乳母とはいえ、晋太郎や晋三を政治家としての側面からも冷静に観察してきたウメにもまた、政の血は流れていた。
聞けば、ウメの実家も古くからの自民党員だった。晋太郎の父・寛に遡る安倍家は、確かに由緒ある政治家の家系だったが、ウメ血筋はさらに古かった。
法学者としてフランスから日本に民法典を運び、晩年は貴族院議員も務めた井上正一が、血縁だというのだ。井上は、後に明治大学の建学の礎にも、その名を記している。
遠い親戚にあたるのだと言いながら、ウメはトランクのなかからその井上の写真を取り出して見せてくれたことがあった。それは、縦に一五センチほどの木枠の写真立てに納められていて、やはり東京から旅行用のトランクに入れて持ち帰ってきたものだった。
ウメは小さい女ひとである。ただ、向き合って話をしていると、その小柄さを何倍にも膨らませたような、ゆったりとした貫禄を放っていた。
そんな不思議な魅力が、安倍家の主たちに胸襟を開かせたのかもしれなかった。
すい臓ガンを抱えて御茶ノ水の順天堂大学病院に入院していたとき、病室でウメは晋太郎に政治家として何をやりたいのか訊ねたことがあったそうだ。
晋太郎は、「俺も何かひとつ、あれは安倍がやったというものを遺してみたい」と応えたという。
そんな誰にも言えないような気持ちでも、晋太郎が自分にだけは打ち明けてくれていたという思い出を、ウメは実にうれしそうに話すのだった。
それは唐突のようでもあったが、てらいは微塵も感じさせなかった。むしろ、その一言によって、晋太郎を語るときに、次第に「パパ」と呼び、率直な親しみを表すウメに対して、大きくなり始めていたもやもやした思いが、多少なりともカタチを見せ始めたような気がした。
ひとつの疑問が胸の中でわだかまっていた。しかし、言葉に出せば、それはあまりに低俗な響きを放ちそうで怖くもあった。
それは初め、ウメが独身だと聞いたとき、反射的に湧いたものだった。八〇歳になった今日の日まで、ウメは一度も結婚したことはなかった。
縁談話も相当あったとウメは言うが、結局は独りを選んだ。
生涯独身の女性に恋がないと思うのは、浅はかである。胸張り裂けんばかりの恋を経て、激しく懊悩した結果としての「独身」は、あるいは美しささえ放つ。
政治の季節とはいえ、財界人やマスコミなど、各方面から岸邸への出入りは多く、そのころ、まだ若いウメにはたびたび縁談が持ち上がったというのだ。お相手のなかには、今でも健在で誰でも知っているような人がいて、結婚してくれと言われたこともあったと、恥ずかしそうな微笑を浮かべながら話してくれた。かといって、縁談に応じ、結婚してしまえば必然、「住み込み」はやりづらくなる。
ウメにとって結婚は、岸―安倍家という「場」と疎遠になり、遠ざかってしまうという、何よりも決定的な寂しさを覚悟させるに行為にも等しいものだった。
ウメのなかで、晋太郎は小さいころからの憧れの存在でもあった。竹馬の時期から、ウメは晋太郎を知っていた。
油谷のあたりでは、いいところの坊ちゃんで、同時にガキ大将然とした子供を「ダン坊」と呼ぶ。
この晋太郎のダン坊ぶりは、村落対抗の運動会に轟くほどの俊足ぶりに加え、少年同士のケンカでもおおいに発揮された。 集落ごとの少年たちのいさかいに、ほかの子供たちよりも背が倍ほども大きく、圧倒的な存在感を持つ晋太郎が出ていくと、不思議と場がおさまるのだった。
何より、アタマの良さはあたりで群を抜いていた。
時代は、「一村一神童」のころである。大人たちでさえ、あたりで晋太郎の名を知らぬ者はなかった。
そのダン坊と、南平台の岸邸で単に出会うどころかいっしょに住み込んでいた。その頃の晋太郎は既に洋子と結婚し、総理秘書官を務めながら、政界進出を見据えた政治家見習いの時期にあって、前途洋洋の路が開かれようとしていた。
わずか二歳年長の晋太郎は、輝いて見えたに違いない。ウメでなくとも、その清々とした丈と雰囲気、そしてまもなく政界に打って出ようとのぼりゆく故郷の若き英雄の姿に、男としての魅力を感じない女性はいなかっただろう。
「パパはね…」というときのウメは、確かに「女」を感じさせた。それは、晋太郎の妻・洋子を意識した言葉にも思えた。自分だけに打ち明けてくれると、そう思えた瞬間、女は男の愛を感じるのかもしれなかった。
ウメのその自負に満ちた物言いは、少なくともウメが晋太郎の死後から今日まで、ひとつのことを自らの内に秘め、日々、確認し続けているのだろうと想像させた。
ウメは晋太郎を愛していたのかもしれなかった。
縁あって上京し、岸の側用人のごとくにすでに政治家への仕え方を心得ていたウメにとって、「惚れ込む」こととは、短絡的な情欲の契りとは切り離されたものだった。
だからこそ、縁談に応じることは、ウメにとっては二つの嘘を自分に強いることを意味していたのだろう。
愛していない男と結婚するという嘘。
そして、〝愛する〟晋太郎への自身の気持ちを裏切る嘘である。
ウメは結局、自らの気持ちに素直に生きることを選んだ。そして、岸―安倍家に仕えたおよそ半世紀の日々は過ぎた。
〝愛した男〟の息子が幹事長に就任したのを見届けて、ウメは油谷に戻った。そこは、大きな愛で見守った男が眠る場所でもあった。
政治家以前の晋ちゃん
晋太郎を語るとき、「パパ」と呼んでいたウメの晋太郎に対する思慕は、やがてその「パパ」の子である晋三に注がれていた。
ウメは晋太郎に赤坂界隈の焼肉店でご馳走になったといっていたが、晋三にも「食卓の記憶」があった。
最近は、家で食事をする機会がなかなかない毎日ですが、自分も政治家の息子だったので、子供のころ、家族の団欒という場はほとんどありませんでした。特に父が三回目の選挙で落選した時、まだ小学四年生だった私は、兄と二人、東京で生活し、地元にいた両親とは離れ離れの生活でした。そんな中で、時々父が東京に帰ってくると、必ずといっていいほど、その晩の食卓は〝すき焼き〟でした。当時(昭和四十年頃)は、まだ高度経済成長の時代に入ったばかりで、日本もそんなに豊かではなく、牛肉など贅沢品。それが、すき焼きは肉を生卵につけて食べるというものですから、父が帰ってくる喜びと合わせて、子供ながらにとても嬉しかったことをよく覚えています。
毎回、必ず論争になったのが、味付けについてでした。父は辛い味が好み。私と兄は甘い方が好きで、よく言い合いになったのを覚えています。
父は口数が少なかったので、学校であった出来事で会話が弾むということはありませんでした。でも、普段、兄と私は母の代わりにお手伝いさんに世話をしてもらっていましたので、たまに母が作ってくれる食事、とりわけ、月に一度、父が帰ってきたときに家族で囲むすき焼きは、格別に美味しく、楽しい記憶として残っています。
そのせいか、今でも、妻とはもちろん、母や兄の家族が集まるときは、決まってすき焼きです。ただ不思議なことに、外ですき焼きを食べるということはないのです。家で食べるものという感覚なのだと思いますが、それだけ子供のころの思い出が強く残っているのだろうと思います。
母がよく作ってくれたかまぼこの千切りとウニを和えた酒のつまみのようなもの。これも大好物で、これは妻に受け継がれ、今でもよく食べています。
父が晩年、病院で闘病生活を送っていたとき、差し入れでちらし寿司をいただいたことがありました。既に味覚が衰えた父に代わって、そのちらし寿司を食べましたが、これがまたすごく美味しかった。食べられない父の横で食べるのは哀れだと思い、別の部屋で食べようとすると、父が、『ここで食べなさい』、と。
父の秘書を務めていた約十年の間も、子供のころと同様、あまり話をすることはなかったのに、この時は、色々な話をしてくれました。政治は離合集散を繰り返すもの、その時々の判断が大事であることなど、政治家になって十年、そのときの父の話を思い出す機会も増えました。また、祖父(岸信介)の秘書官をしていたときの、岸派の分裂の話も聞きました。父は一九九一年に亡くなりましたが、その直後、安倍派は分裂しました。父には何かそんな予感がしたのかもしれません。(「食卓の記憶 安倍晋三」)
この文章を読んだとき、心のなかで、何かに大きくつまづいた。
「普段、兄と私は母の代わりにお手伝いさんに世話をしてもらっていましたので、……」という一節がトゲのように刺さったのである。
便宜上なのかもしれない……あえてウメの名前を出す必要のない文脈だから、「お手伝いさん」とするほうが、むしろ、話がすっきり通るのも確かだろう。
だけど、晋三が自民党幹事長のときに書かれたこの文章を、ウメの目には入れたくないな、と思った。
「…久保うめさんは、選挙運動から家庭のことまで、わたくしたち夫婦の三十五年間のよき協力者であり、いわば『戦友』でもある人…」(『わたしの安倍晋太郎』)と、洋子が戦友とまで呼んだそのウメが、晋三のなかで「お手伝いさん」程度のものであったとするならば、なんだか悲しすぎてやりきれなかった。
もちろん、お手伝いさんという呼び方のどこにも間違いはないし、冷静にみればむしろ、ウメの安倍家のなかでの立場を何よりも正確に言い表しているのかもしれない。
この文章が載ったとき、ウメはすでに東京を離れ、郷里の油谷に戻っていた。
ウメが戻った先でもこまごまと晋三が書いたものを目にしていたとは思えない。
妹の郁子が言うように、「テレビで晋三さんをみると、いろいろと思い出しては話していた」のだろうけれど、訪問したときも、スクラップブックに切り抜きをしているような、そんな風情はなかった。
それに、下関からでさえ片道で二時間近くかかる油谷にいては、いつどの雑誌に載るかわからない晋三が書いた記事や、晋三について書かれた記事をくまなく渉猟するのは、何よりも至難の業だと思えた。
だからきっと、ウメが、自分のことを「お手伝いさん」と書かれたこの記事を目にすることはなかっただろう、と自らを納得させることができた。
でも、もしかすると、ウメが晋三を想う気持ちほどは、晋三はウメを想っていないのかもしれない。
親しみを込めたひとを呼ぶのならば、もっとほかに、いくらでも呼び方はあるのではないか、と思った。
あんがい、次男坊の晋三は、それほど人情味厚くはないのだろうか……。
北朝鮮の拉致被害者の家族に対する応対を、メディアを通じてみている国民は、きっと映像を通じて流れているあのぴったりと寄り添う光景を、過剰に膨らませて晋三という人間のイメージを作り上げているとも考えられた。
母代わりの乳母と、お手伝いさんとでは、天と地ほどの感覚のずれが、その表現を素直に受け取れば、感じられてしまう。
あるジャーナリストが、かつてウメにインタビューした折、ウメからこんな話を訊きだしていた。
ウメ お風呂に入るときに、なんかここ黒い。面白いなと思って、何かなと思って、「あなた、きょう転んだね」と言ったら、「ううん、転ばないよ」って。「どこか転んで打ったでしょう。痛かったでしょう」と言ったら、「ううん、今日はなにも転ばないよ」と言って、洗ってやってお風呂へ入れて、よく考えると、朝お兄ちゃんのことばっかりやっていると、自分がすねちゃって。これがすねたらテコでも動かない。
Q なんかちょっとそういうの聞いたことあるな。意外とすねる。
ウメ 幼稚園のかばんをかけたのを、バス停までおんぶしていって。あれはおんぶが好きだったというのは、やっぱり……。
Q 甘えっ子というか。やっぱり足りない。
ウメ ちっちゃいときにしっかりというのが足りなかった
ウメが幼少の晋三を語る、他愛もない話だけれど、なんだかウメと晋三の距離感が見えているようで面白い。
ウメにしてみれば愛情をかけている行為そのものが、幼い晋三には伝わらない…、もしかしたら、晋三にとってのウメはある時期以降は煙たい存在でもあったのか、とも勘ぐってしまう。
幼い子が親の愛情を素直に受け取らないのは、特段異常なことだとは思えない。
でも、子が親もとを離れ、そして常にすり合わさっていた密着感が離れたときに、本来は郷愁と、状況に対する客観的な感覚が生まれるの事実だろう。
晋三にとってみれば、それはウメが郷里に帰り、みずからが幹事長となったその時期がそれに当たっていてもおかしくない。
そして、まさに愛着が甦るべきその瞬間の「お手伝いさん」だからこそ、哀しみは増すのだった。
その晋三を、実の両親である晋太郎と洋子はどう見ていたのか。
洋子の言葉がある。
主人が病気になりましてからは、晋三はよけいにいつもそばについておりました。その間、二人はいろいろ話しておりましたが、もう晋三が跡を継ぐことははっきりしておりますし、とくに遺言めいた言葉もなかったようでした。ただ、「死に物ぐるいでやれ、そうすれば道は開ける」と激励されたとのことです。
主人はだいたいやわらかい表現はしない人で、病床でも、晋三の姿が見えないと、
「どこに行ってたんだ。秘書なんだからしっかりしなくちゃダメじゃないか」
と叱っておりました。寂しくもあり、晋三のことをいちばん気にしていたのでしょう。
「おれも甘いところがあるけれど、晋三もおれに輪をかけたようなところがあるからな」
と言ったり、
「ちょっと心細いようでもあるけれど、なんとかやってくれるだろう」
と、半分冗談のように言いながらも、やはり頼りにはしているようでした。
晋三は思うことをはっきり言うので周りも気にしておりますが、主人の若いときもものをはっきり言い過ぎて、わたくしはそばでヒヤヒヤすることもありました。選挙区の方が陳情にこられて話を聞いたとき、「ああ、それはダメだ」と簡単に言うことがあります。
「せっかく来てくださったのに、そんなに頭からダメダメと言わないで」
と言うと、
「できないことは初めからわかっているのだから、それを気を持たせるような言い方をするのはかえって不親切なんだ」
と申します。それにしてももうちょっと言い方があるのにと、気を揉むことがよくございました。
主人は子どもの教育にもしつけにも、そううるさいことは言いませんでした。もっぱら自然体ということのようで、親のふだんのものの考え方、行動から、子どもは受け取るべきものを受け取るという姿勢だったのです。ただ「人に迷惑をかけるな」「人をだますな」「人の悪口を言うな」「男は自分で決めてやれ」ということは、わりときびしく言っておりました。
もっとも、こういうこともございました。子どもたちが中学から高校ぐらいになりますと、クラブ活動などでだんだん帰りが遅くなります。たまに主人が先に帰りますと、
「まだ帰らないのか、こんなに遅くまでなにをしているのか」
と、きびしい口調で申しますから、
「わたくしはいつもやかましく言ってますから、たまにはあなたがおっしゃったほうが、効き目があるでしょうから、今日は帰ってきたらしっかり注意してくださいな」
と頼むのですが、いざ子どもあ帰ってくると、豹変して、
「お、帰ったか、小遣いは足りているか」
になってしまいます。
政治の道の跡継ぎとしての晋三は、主人が、安倍寛と岸信介の信念に生きる芯の強さというものを見てきたように、安倍晋太郎のことはもちろんずっと見てきていますし、安保のときの岸信介のようすも子どもながらに見ております。安倍寛の血といい、岸信介の血といい、なにかのときには命がけで事に当たるというきびしさは、ものの本で読んだというのとはまた違って、身近な空気として体得しているということはあると思います。その覚悟ができていて政治の世界に飛び込むのですから、わたくしに異存があるはずもございません。
ただ、主人が幼児から育ってきた体験にくらべ、物心ついたときには『総理の孫』として育っていた晋三には、まだまだこれから何事にも初めて知ることが多いはずで、それが、わたくしの案じているところなのです。
(『わたくしの安倍晋太郎』安倍洋子)
安倍晋三は成蹊大学法学部を七七年に卒業してから七九年に神戸製鋼に入社するまでの二年間を、南カリフォルニア大学で過ごしていた。
その米国逗留時、晋三はしょっちゅう胃腸を壊しては東京に電話をかけてきたと、初対面の日にウメは言っていた。安倍家は代々体が丈夫な家系ではないと言い、晋太郎がガンを患ったこと、そして晋太郎の父である寛は呼吸器が弱かったことを引き合いに出した。晋三の場合は消化器に不安を抱えていて、それが心配なのだという。
ウメの言葉だけでは、晋三の体の弱さが先天的なものなのか、後天的なものなのかははっきりとは分らなかった。
だけど、村人からは、こんな話も聞こえてきた。
選挙のたびに見られる光景だったという。
選挙運動のわずかな合間を縫っては口に運ぶ食事のおり、食べた直後に便所に走ることが度々あったという。
そんないつもの光景を見ながら、村人はこう思っていた。
「ああ、神経に障ると、すぐに腹が下ってしまうのだ」
今でこそ、過敏性腸症候群(IBS)という病名がつき、いくつものクスリさえ用意されている症状にも見える。
いずれにしても、ウメの話ともあわせれば、晋三は先天的な身体の弱さに加えて、極度の緊張にも弱いことを想像させた。
生まれついての性格だといってしまえばそれまでだけど、心持ちのありようという点では、後援会の関係者の中にはこんな声もあった。
晋三の兄、「寛信さんのほうが、晋太郎先生譲りでゆったりと構えて気が大きく、堂々としているところがある」。
ところで、晋三は八二年には会社員生活に見切りを付ける。
きっかけは、父である晋太郎が外務大臣に就任したことだった。
このとき晋三は二八歳になっていた。
この秘書官時代にも晋三は、大きな会合で晋太郎の名代を務めると、しばしば落ち着きのない様子が目立ったという。
「しょっちゅう目なんかキョロキョロさせてね、みっともないんですよ」(関係者)
そんな話を聞くと、運輸大臣時代から都知事の今まで、癖とはいえ、異常とも思えるぐらい頻繁に目をしばたたかせる、石原慎太郎の姿と晋三の姿が重なってもしまった。
顔の表情のなかで、目の動きはとりわけ敏感に人々の印象に直結するものかもしれない。
なぜだろう。
顔のかたちや口や鼻や目の位置が、整形手術でもしない限りは決してひとが抗えない、先天的な印象を与えるとしても、目の動きやその表情は、顔の印象をあるいはまったく異なったものにさえ見せてしまう。
怖そうか―、優しそうか―、臆病そうか―、おそらくひとは相手の目を見てその雰囲気を読み取っているとはいえないだろうか。
だから、目はきっと、その人間の感情の機微を表すもっとも大事な部分であって、それは大衆に訴える力が必要とされる政治家にとっては、決定的な〝道具〟であり、〝武器〟であるに違いなかった。
その肝心の目がキョロキョロと動いて治まらないのだから、後援会の関係者が若き晋三に、政治家の素質として一抹の不安を覚えたのも無理はない。
さすがに、自民党幹事長―内閣官房長官と大役を踏んだいま、テレビ画面からは、晋三がそんな〝神経の細さ〟をうかがわせることも少ない。さらに、二度目の総理に就いた現在では、見事なまでに堂々たる風格さえ漂わせつつあるようにも見える。
次の指摘はそれを象徴しているように映る。
「安倍の国家観のもうひとつの特徴は運営にあたっての首相の優位性に対するこだわりだ。二〇一四年二月一二日の衆院予算委員会で、集団的自衛権行使の是非をめぐる憲法解釈に関連して次のように指摘している。
「最高の責任者は私です。……政府の答弁に対しても私が責任を持って、その上において、私たちは選挙で国民から審判を受けるんですよ。審判を受けるのは、(内閣)法制局長官ではないんです、私なんですよ」(柿崎明二『検証 安倍イズム』)」
でも、それが大役にあるがゆえに、「演出」が効いた場面だけを国民が見させられているとすれば、実際のところはわからないものでもあろう。
もちろん、演出が効くのであれば、それは、たいていのことが慣れと訓練でいかようにも克服できることを意味している。
でも、もし先天的なハンディがあるとするならば、それは克服に費やす時間と努力が他人よりも必要だという点で、確かに「ハンディ」なのかもしれない。
ウメが、晋三の決定的な弱点として懸念するもう一つの大きなものは、晋三の滑舌の悪さだった。
晋三の父、晋太郎が死去するのが九一年―。
その瞬間から、母・洋子を始めとする側近たちは、演説での晋三の早口ぶりを戒め、矯正に努めてきた。
確かに、より多くの有権者に語りかける言葉はゆっくりと、そして耳に心地よいものであることが必要だ。
だけど、その「早口演説」は場数を踏めば矯正されるとしても、そこには再び、先天的なハンディがはだかった。
ウメの証言によれば、晋三は通常の人よりも歯が四本少ないという。下顎が小さすぎたため、生えてこなかったのだと。歯が生えても出てくる場所がないため横から生えてきて二本抜いたり、通常は生えてくるべき歯があと二本生えてこなかったり、ということだったという。だから、それもあって人よりも発音が芳しくなく、早口になれば余計に聞き取り辛いため、つねに注意していたらしい。
冬の寒い夜には、ウメが小用に立っている間に「寒いよ」と、布団に潜り込んできた晋三だった。そんな、まさに母同然のウメだからこその、緊密な逸話だと思えた。
実際、晋三の発音に注意して耳を傾ければ、「あいうえお」の母音と母音の間に挟まる子音の発音に違和感はあった。
ときに、若干だが飛んだり、濁って聞こえるときがあるのだ。
もちろん、テレビ番組など、予め会話が想定できる、比較的、発声に余裕がある場面ではこうした発音の〝弱さ〟は気にならない。
でも、立ち話で記者たちのぶら下がり取材に応えるときや、興に乗って力を込め始めると、とりわけこうした子音の不明瞭さがしばしば耳につくようだった。
言葉の発音は、歯と舌の位置に大きく拠っているのは当然だから、ウメの指摘も、なるほどと思わせた。
一方で、その気質に目を向ければ、晋三の持つ剛直なまでに芯の強い性格が、政治という刻々と変化する変幻自在の綾をもたらす世界では、ときに「弱さ」にも転じる可能性を、ウメは冷静に見極めているようだった。
まだ晋三が小学校に上がる前の話である。
ある日、安倍家は朝から緊迫していた。居間では、晋太郎、洋子、そして寛信と晋三の四人が張り詰めた空気のなか、睨みあっていた。
はたからうかがうには、何か幼い兄弟がしでかした粗相が晋太郎の癇に触れ、寛信と晋三の二人が父から審問されている様子だった。
どうやら寛信はすぐに謝った風情だが、睨みあいの輪は解けない。
果たしてどういうことか、とウメは気を揉んでいた。
一時間、二時間……、刻々と時は過ぎ、もはや半日に及ばんとするころ、ついに声が洩れた。
強情な晋三もやっと謝ったのか、と思いきや、ウメは仰天した。
「えーい、おまえはしぶといっ」
たまりかねて音を上げたのは、なんと晋太郎ではないか。
結局、晋三は長時間の黙秘に耐え抜き、父親が降参する顛末となった。
後からきけば、晋三は「自分がやったことではない」と、まったく身に覚えのないことを言われたといって怒り、ついには、濡れ衣を着せられようとする状況に徹底的に抗い続けたのだった。
ウメの証言も交えながらここに紹介した話は、安倍家周辺では設定や情景を変えながら、縷々語り継がれている有名な逸話のひとつである。
そして、この話がいまだに強い命脈を保っていることを考えれば、それはほかでもない、晋三の「芯の強さ」を肯定的に〝魅せる〟ものとして語り継がれているのだろうことを理解させた。
もちろん、ウメ自身も目の当たりにしたこの記憶が〝創られたもの〟だとは思えなかった。
ただ、偶然だろうか―。
晋三の祖父である岸信介にも、同じような逸話が残っている。
それは、急須のフタをめぐる、岸と叔父との話だった。
ノンフィクション作家の岩川隆は『巨魁 岸信介研究』のなかで、こう紹介している。
ある日二階にあがって叔父の部屋を見るともなく見ると、ちょうど茶を飲んだそのままの状態で茶器がおかれていた。ものめずらしさに叔父が愛用する急須をとりあげてなかをのぞくと、二、三服飲んだあとの緑茶の真青な瓶から急須に湯をそそぎ、それから蓋をしようとして、どうしたはずみか、その蓋を下にあった盆の上に落してしまった。
あっというまもない。蓋は二つに割れてしまった。びっくりするやら慌てるやらした信介は、そこですぐ叔父か叔母のところへ行ってわびればいいものを、浅はかにひた隠しに隠し、知らぬ顔をした。もちろん、すぐに発見されて、だれがやったのか、と詮議がはじまった。
「信介じゃろうが」
といわれても、最初に嘘をついたため白状することができなくなった。ついに最後まで知らぬ存ぜぬの一点張りで犯人が出ず、不思議な事件として終わった。
晋三の代に至った安倍家周辺で、この岸の逸話を真似たわけではないだろうけれど、「強情ぶり」だけをみれば、二つの逸話は不思議なくらいに重なって見える。
とにかくも、ウメは晋三のその「芯の強さ」を、今の状況に引きつけてみせた。北朝鮮の拉致問題にしても、晋三は自分がこうだと思って始めたことは最後までやり遂げるだろう、と。拉致被害者の家族が仮に「もう結構です」と言ったとしても成し遂げる、とウメは読む。
そして、亡き晋太郎とも重ねてみせる。晋太郎は、誰がどうしてくれなかったからこうなったとかいう、恨みがましいことは、四〇年間一緒にいたなかで一度も聞いたことがな、それが晋太郎のすぐれた点だった、と。他人のせいには絶対にしない。その代わり、自分に覚えがないことであれば、どんな相手でも徹底的に向き合う、その正義感の強さだけは晋三に受け継がれている、と。
だけど、正論を掲げ、信義に厚い性格が、魑魅魍魎が腹芸を繰り広げる永田町で、常に吉と出る保証はもちろん、ない。
対北朝鮮外交が与えた晋三の〝タカ派〟という称号は、そんな性格の一端を確かに象徴していた。
いったい、この安倍家の「芯の強さ」はそれこそどこに「芯」を持つのだろうか、と考えたとき、ウメは、ひとつのヒントを繰り出してみせた。
実は、その損得勘定を欠落させた親子の剛直ぶりを物語る逸話は、晋太郎の初出馬にまでその脈を遡らせる。
晋太郎が初出馬した五六年の選挙は、山陰の村を二分する、それは文字どおりの大変な騒動を引き起こした。
日本の村々では、いまや死語とさえなった「村八分」という言葉がいまだ恐怖の余韻を保っていた頃のことである。
時代を経た今でこそ、それは因習と軽く言い流しうるものかもしれないけれど、日本中、いたるところで「村八分」は、強い、拘束力のある〝制度〟として定着していたのである。
山陰の寒村を二分するほどの大騒動ともなれば、これは言葉以上の、勝つか、負けるか、負ければ生き地獄か追放かの「必死の決意」であったことは疑いなかった。
そんな時代背景の最中、既得権に抗い、晋太郎を祭り上げて立ち上がった者たちがいた。
古く、現在の山口県・油谷一帯を治めていた日置村の村長を経て衆院議員を務めた、晋太郎の父親である安倍寛が死去して以来、その地盤や後援会は、周東英雄が引き継いでいた。
地盤を譲られたとはいえ、その周東も順当に当選を重ね、大臣をも務めるに至っていた。地元の権力者といえば、紛れもなく周東の名前が深く根付いていたのである。
その周東の地盤に乗り込むかたちで晋太郎が当選するためには、自らの父の地盤を再び奪い返すという、情容赦のない弔い合戦の様相を呈することになろう。
これだけでも、小さな村々で戦乱の嵐を巻き起こすには十分すぎるほどである。
そこに加えて、周東はよりによって、晋太郎と妻・洋子の仲人でもあった。
土地特有の義理人情も、今よりさらに露骨に、色濃く残る時代である。
仲人にさえ弓引いた晋太郎の覚悟の深さへの関心よりも、人々の関心は、「今の権力者」か「明日の権力者」かという、より現実的な問題に向けられたことは間違いない。
油谷で水産加工業を営んでいた中嶋春男は、青年の日の光景を語ったことがあった。
「そりゃ晋太郎さんが寛さんの息子だと言っても、寛さんが死んでからもう二〇年。もう地盤や後援会も代替わりしていましたから。それに晋太郎さんを担ぐことに決めた若い衆と、現職の周東さんを推す古い衆との間では激しくやりあうことになりました」
温厚な晋太郎が、恩義のある周東に弓を引くことになる、〝謀反の出馬〟を決意したのには、もちろんワケがあった。
大きな義憤が晋太郎を出馬に衝き動かした。
それは、次のような状況によって引き起こされた。
自民党総裁選で、周東が、晋太郎の岳父である岸信介に票を投じなかったことが分ったからだった。
周東は当時、岸とは異なる派閥にいた。確かに晋太郎の父・寛の地盤を継いでいるとはいえ、もはや代替わりして久しい義理を、政界渡世のなかで貫き続けるわけにもいかなかったのだろう。
晋太郎が「義父のかたきを」と思ったとすれば、それは周東にとっては気の毒すぎる、逆恨みというべきものだった。
当然、周東にも、自らが属する派閥の長たる「親父」がいる。今の親父を立てずしては、党人かたぎの世界で明日はなかった。
一方の晋太郎は、自らの出馬を決意すれば頑として譲らず、そして初陣を勝利で飾った。
自分自身に信を立てれば、徹底的に事に当たるというその性格は、ウメにしてみれば、晋太郎の姿に晋三が大きくダブって見えるのだった。
そんな語らいを聞けば、やはりウメは晋三を慈しんだ乳母だと思わせた。
元総理大臣の娘、洋子
昭和の妖怪とさえ呼ばれた元首相・岸信介の娘であり、晋太郎、晋三と親子3代を支えてきた、そんな〝豪気〟な洋子。政治家の「娘」「妻」「母」とその立場は微妙に変えながらも、洋子の人生こそは、誰よりも政とともにあった。
ウメにとって、何よりも〝あのとき〟の光景を忘れることはできない。
晋太郎が三回目の選挙で、思いもかけず落選の憂き目に遭ったときだった。
落選後、下関を中心に支援者らに御礼やお詫びの〝敗戦処理〟をしていた晋太郎が、いよいよ東京に戻ってくることになった。そのときだけは、洋子も母・良子に「洋子ちゃん、パパを迎えに行きなさい」と促され、羽田に向かったのだった。
そして、洋子は晋太郎とともに自宅に戻ってきた。当時、安倍家は、係累でもある佐藤栄作邸のそば、世田谷区・代沢にあった。
落選の報に接し、いつもより湿った空気の玄関を入り、茶の間の隣の座敷に足を踏み入れたその瞬間だった。
晋太郎は崩れ落ちた。
まるで転んで倒れるように、座敷に突っ伏し、「ワアーっ」と男泣きに大泣きしたという。落選してしばらくは山口に留まり、地元支援者たちへのお詫びも済ませてきての帰宅だった。ずっと堪えてたのではないかとウメは感じた。それまで抑えていたものが一気に出たのだろう、と。
そのときの気持ちを、ウメは晋太郎から後にこう聞いた。
「親が死んだときにも感じたことがない、生まれて初めての辛さだったな」
そんな晋太郎の言葉は、ウメにも納得できた。
晋太郎は、もう立っていられないという感じで、転がって泣いてたという。その光景を前に、寛信と晋三の兄弟は驚きを通り越し、立ち尽くしてしまった。父の怒る姿は知っていても、父の泣く姿を見たのは初めてだったのではないかと、ウメは回想した。
初めて見た、体裁を構わず無念に打ち震える父親の背中を眺め、まだ九歳だった晋三が口を開いた。みんなと一緒の小学校に行く、と。
子供ながらの精一杯の慰めだったのだろう。学費を気にして、私立の成蹊小学校に通っていた晋三が近くの公立校に転校してもいいと、唐突に口にしたのだった。
他の代議士とはちがって、自分の家は会社も何もない、明日からどうするのか。
晋三が続けたそんな言葉に、ウメも驚いたという。
ウメは笑いながら、「子供がご飯の心配したんだから」と当時を思いだす。その横にいた寛信はなにも言わず、きっと「晋三と一緒に学校を変わらないといけなくなったら、いやだな」などと思っていたのかもとも。
座敷に崩れた晋太郎と、彼を慰め、場を繕う晋三。立ち尽くす長男の寛信。
その傍らで、洋子がこう呟いたのを、ウメは確かに覚えている。
「男ってダメね……」
その一言だけだったという。洋子は豪気な性格ですんだことは仕方がないという主義の人だったことをウメは継ぎ足した。
この辺りは、洋子の父である岸信介からの血の流れを感じさせる。
一九五七年、石橋湛山と争った末に岸が総裁選に敗れたときのことだった。
直後、気落ちしているであろう岸のもとを慰めに訪れた番記者は驚かされたという。「麻雀でふり込んで負けたという感じ。過ぎた話はしてもしょうがねえや、という感じであった」(『巨魁』岩川隆)。
血は争えないとは、よく言ったものである。
そんな洋子の夫・晋太郎は「総理に一番近い男」とさえ呼ばれながら、そのイスを逃したがゆえに一転、「悲運の政治家」という報われない称号をもって語られ続けていた。
今、わが息子・晋三が再び「総理に一番近い」場所にいるとするならば、洋子がその務めをいかようにも果たそうとするのは、至極当然のことだった。
総理のイスは狙えるときに獲る――。
深い失望を与えた八六年の「中曽根裁定」――。
時の宰相、中曽根康弘が、竹下登と宮沢喜一、そして安倍晋太郎の三人のうちからひとりを選び、後継者に指名しようとしていた。結局、中曽根は竹下を択び、晋太郎は負けた……。
おそらく、すべてと言っても過言でない人々にとってトラウマとなり、その瞬間から時間さえ止まり続けているのが安倍家の〝本丸〟であり、晋太郎の郷里、油谷だった。
「安倍」を推す者たちの誰もが崩れたあの日、洋子の不惑の様は、ウメの目にはっきりと刻まれている。
すんだことは仕方がないという主義の洋子は、そのときも変わらなかったという。
晋太郎と竹下は、ともに五八年の選挙で国会の絨毯を踏んだいわゆる「政界同期」である。だが、晋太郎はその後、三回目の選挙で落選しているため、その時点で竹下のほうが当選回数では一回多かった。
ところが、下馬評では「安倍で決まり」という空気が支配していた。
油谷の小さな集落は、町を挙げた祝いのボンボリ作りに追われていた。誰もが、山口県から八人目の首相が誕生するものと信じ、祝賀ムードに包まれていたのだ。
すでに、多くの記者が途切れることなく油谷を訪れ、その〝瞬間〟に備えている。
もっとも、晋太郎が政治家として立つころには、父・寛も他界して久しかった。
地元・油谷には、名家の出である名残りらしきものは何も残されていない。
「これでは、安倍家を送りだした油谷の面目がない。押し寄せるメディアに応対する応接間ぐらいは用意しなければ」
そう決意し、油谷のある人丸駅前に三〇〇〇坪の土地を持つ木村病院は、急遽、晋太郎の総理就任のための〝応接室〟を着工した。木村病院と安倍家とは縁戚関係にある。
そして、木村病院の主人、故・木村義雄は、かつて安倍家を物心両面で強力に支援した七人衆「北斗七星」の一人でもあった。
寛が急逝した当時、まだ学生だった晋太郎に選挙は間に合わない。そこで、晋太郎に時機が来るまでの〝つなぎ〟として、「北斗七星」の木村に白羽の矢が立った。
ただ、医師の仕事と国会議員を両立するのは不可能に近い。どちらをとるか――。
「ならば、晋太郎さんが選挙に立つまで」と決意し、木村は寛の後援会を引き継ぎ、当選を果たす。
その時から木村家にとって、晋太郎の総理就任は代をまたいだ悲願となる。
総理の地元として、来訪客の応接用に新築した部屋には、カウンターも設えた。酒も振る舞えるようにと、考えたのである。
たったふたまとはいえ、総理総裁の地元としての体裁を考えた「特別室」の建設に、木村家は当時としては破格の二〇〇〇万円を費した。
それまでも、晋太郎の選挙となれば、木村病院の敷地は選挙事務所に早替わりしていた。運動員の世話から食事の用意まで、木村病院は安倍家そのものだった。
その木村家の人間が、いまここにきて、安倍家にはもう懲りごりだと憤るのである。
「安倍家のために使ったお金は億を下りませんよ。でも、もうやりません。六〇年以上、選挙をやってきて、こんなことになるとは思わなかった。もう、本当におしまいっ」
「億のカネ」とは、縁戚関係のよしみもあったのだろう。確かに、晋太郎が選挙に立つころにはもう、まとまった金を用意するほどの余力は安倍家にはまったくなかった。「家」はずっと昔に傾き、寛も早くに世を去っている。晋太郎の人柄もあり、木村家は世代を超えて「億というカネ」を注ぎ込んでまで支えてきた。
晋太郎の総理就任のために二〇〇〇万円をかけた特別室も、長い年月を経ながらやっと日の目をみようかという今年、いったい何が木村家の感情を、喜びではなく、強い怨嗟の念に駆り立てるのか――。
それは、どこまでも高まる洋子への耐えがたい怒りだった。
〇六年一月、下関から長門まで、選挙区一帯を訪れた晋三と洋子の一行は、油谷の晋太郎の墓にも立ち寄った。
その帰りがけ、洋子は人丸駅前の寿司屋に入った。そしてその足で、三代にわたり世話になった木村病院にも顔を出すものと、誰もが思っていた。
しかし、洋子が木村病院の敷地に足を踏み入れることはなかった。
木村病院は、洋子が腹を満たした寿司屋の、小さな通りを挟んだ正面にあった。
油谷の小さなムラで、素封家の木村家が誰よりも安倍家を支援してきたことを知らないものはいない。目の前を素通りされた木村家のメンツは完全に失われた。
「選挙のたびにあれだけ世話になっておきながら、当選した後に報告も、礼の電話の一本もなかった。だけど、晋太郎さんがいるころは、その分を晋太郎さんがとてもよくおもんぱかってくれるから、晋太郎さんの人柄だけを私たちは慕っていたからね……」
洋子が、「安倍家のために億のカネを使った」という木村病院を素通りするようになった理由は、うかがい知れない。晋太郎だけでなく、幼い寛信や晋三もまた、油谷を訪れれば我が家のように遊んでいた三〇〇〇坪の木村家である。
〈ただ、もしかすれば……〉
あの時の、縁戚だからこその最大の気配りが、むしろ洋子の怒りと憎しみを買ったのかもしれない――。
かつてこの木村病院に、ひとりの患者が運び込まれたことがあった。もっぱら地元の患者が多いこの病院にとって、東京から飛行機で〝運ばれた〟患者が来るのは異例のことだった。この中年の女性患者は精神的にもかなり危険な状態にあった。
手首に刃をあて、風呂に浸かり、幾度となく自殺未遂を図っていたのだ。
山口・宇部空港に到着すると、この女性とぴったりと寄り添っていたその妹は、車でまっすぐに木村病院を目指した。
その時点では、生命が危ぶまれるほどの容体ではなかったが、自殺未遂を繰り返す精神面の不安定さは、もはや人目につく関東に置いておくには〝危険〟すぎた。
女性が到着すると、木村病院では心身の療養をと、最高の待遇で迎えた。
この女性が自殺未遂を図ったことが外に洩れれば〝こと〟である。週刊誌にでも知られれば、何を書き立てられるかわからない。その点、政治家御用達の、どんなに口の堅い東京の病院よりも、木村病院は安心できた。
運びこまれた女性は、洋子の実子で、晋三にとっては弟に当たる信夫の養母・岸仲子だった。安倍家の〝身内〟の病院ならば、と周囲は考えたのだろう。
岸信介の長男・信和と仲子の夫婦には子がなかった。そして「おじいちゃま(岸信介)との間で、女が生まれたらあげない、男が生まれたらあげるという約束」(ウメ)は果たされ、晋太郎にできた3男は養子として岸家に引き取られた。その信夫は、〇四年の選挙で参議院議員に当選する。
この養母・仲子も実は、油谷の出身である。久保ウメとも、山口県立深川女学校で同期だった。仲子の母方の係累には、日産の創業者で〝政商〟としても名を馳せた故・鮎川義介がいる。
信和と仲子の二人は現在、神奈川県で健在と伝えられるが、この自殺未遂騒動を機に、岸家と安倍家との関係の歪みは決定的になってしまったという。
仲子ときわめて親しい人物が、仲子の心境を代弁する。
「信夫さんが大きくなって、自分が養子だということがわかってからのことでした。洋子さんが、わが子かわいさに、仲子さんから信夫さんを引き離そうとしましてね。そりゃ、養子に出したものの籍を抜こうとか、そういう目に見えたことではなかったんです。ただ、洋子さんはやはり産みの親として信夫さんが愛おしかったんでしょうね。それで、仲子さんが精神的に参ってしまったんです。そりゃもう見てて哀れなぐらいでした。だって仲子さんはね、信夫さんを小さいころから慶応に行かせて、そりゃ可愛がったんですから。それで大きくなったら、あんたは私の子よって感じで洋子さんがしゃしゃり出てきたように感じたら、気も参ってしまうでしょうよ」
具体的に洋子の行動の何が仲子を精神的に追い詰めていったのかについては、その人物は言葉を濁した。だがそこに、血の軋轢の一端を感じることはできる。
安倍家に嫁いだものの、岸信介の血を受け継ぐ洋子と、岸家に嫁いだ「外の血」である仲子。嫁―姑にも似た女同士の〝潜った〟鞘当てがあったとしても、不思議ではない。
確かに、洋子は九二年に出版した自著の中でも、信夫に対しては、わが子同然の並々ならぬ強い母性をうかがわせていた。信夫がまだ住友商事に勤めていたサラリーマン時代の話である。
ところで、信夫は岸信介直系の孫ですから、地元では政界入りを期待する向きもあるようです。これまでの「岸信介の後継は安倍晋太郎」と言われていた状況が変わり、「安倍晋太郎の後継は安倍晋三」ということになり、そうなると「岸の後継は岸」という図式が登場するわけでしょう。そうした世襲的な考え方の是非は別として、政治の家系は内側の事情だけでなく、周囲のさまざまな期待や思惑にも関わりを持ちながら、引き継がれていくようでございます。もっとも、信夫本人にはいまのところ、その意思はないと聞いております。いずれにしても、周囲の雑音に惑わされずに、自分の確かな判断と決意で行動してほしいと思います
(『わたしの安倍晋太郎』)
表向きは信夫をあくまでも「岸の子」といいながらも、やはり微妙に「わが子」としての愛情がにじみ始め、そして最後には「母の願い」に至ってしまう。
ウメによれば、実のところ、洋子は女の子が欲しかったのだという。幼い女の子を見ると、「連れて帰りたいわね」というようなことを耳打ちしてくることもあったという。
実のところ、女の子が生まれれば養子に出さずにすんだのに、女の子を産んで手元に置いておきたかった、そんな思いを洋子は抱いていたとウメは強く感じた。
仲子と洋子、どちらにとっても、「信夫」という子をめぐり、心の修羅を生んだであろうことは想像できる。
「仲子さんはそんな一件もあって、ほとほと岸家がいやになってしまったんですよ。それで、岸家から籍を抜いてしまったんです。もちろん、今でも一緒に暮らしていますよ。ちょっと足の不自由な信和さんの面倒を見ながら、仲むつまじいですよ。でも、どうしてもいやだったんですって。岸家の籍に入っていることがね。夫婦でいると、岸家に何かがあったときに喪主を務めないといけないでしょ。それがもう、どうしてもいやでいやで、たまらなかったんですって」(仲子の親友)
以来、岸家から届く年賀状から、仲子の名は消えた。
離婚が本当だとすれば、岸家に嫁いだ仲子の、「岸家の血」を嫌わせた、想像を絶するストレスの大きさがわかる。
洋子の著書『わたしの安倍晋太郎』を紐解けば、そこには洋子自身が密やかに燃やす、強烈な毛並みへの執着心が顕れている。それは一種、異様な雰囲気を漂わせている。
「これだけ話題になりましたのも、世界に類のない兄弟宰相を出した家系につらなるためでもありましょう」と、書き出しから「世界」を持ち出し、大きく構えたこの節には、『わたしの安倍晋太郎』というタイトルを思わず疑うほどに、晋太郎の家系である安倍家の話は一切出てこない。
「佐藤、岸、安倍の一族には……」とはいうものの、この「ファミリー・プライドの家系」と銘打たれた記述のほぼすべてが、父である岸信介と、その弟・佐藤栄作の家系を誉めそやすことに費やされている。
その自負に満ちた家系史の開陳はこう始まる。
注意し読めば、表向き卑下したように見える箇所も、それは直後の誉れへの「転」であることが見て取れる。
父の著書には「佐藤家は貧乏でこそあれ家柄としては断然飛び離れた旧藩時代からの士族」であり「学問をする殆ど唯一の家柄」で、秀才が続出しており、それが「ファミリー・プライド」であったと、書いてあります。田布施の名家である佐藤家と岸家のつながり、その家系についてちょっと触れておきます。
曾祖父に当たる佐藤信寛が「ファミリー・プライド」の頂点とされておりますが、この方は旧萩藩士で吉田松陰に軍学を教えたことがあり、のちに島根県令に任ぜられました。その子・信彦は漢学者で山口県議を務め、三男二女を残しました。長女・茂世は男まさりの才女でしたが、祖父・信寛に可愛がられ「嫁に出すな」との遺言で、同じ田布施の士族岸家から秀助を養子に迎えて佐藤分家を構えました。ここに岸信介と佐藤栄作が生まれます。
佐藤本家は……
と、九ページにわたり、このような記述が延々と続く。
それは結局、安倍洋子にとっての「プライド(矜持)」が、「安倍家」にではなく、あくまでも兄弟宰相を生み出した「岸家」という「ダイナスティ(王朝)」にあることを窺わせていた。
そして、同時に「岸家のプライド」を誰よりも強く、確かに受け継いだ洋子がいたのであれば、岸家に嫁いだ仲子の苦悩も察することができた。
政界有力者に未公開株を譲渡した、リクルート事件の醜聞が晋太郎を襲ったことがあった。
抜きつ抜かれつの報道合戦が繰り広げられていた八九年四月の、ある晩のことだった。
洋子の、晋太郎を激しく罵る声が響いていた。
「あなた、毎日(新聞)の出身なんだから、記事ぐらいなんとかしなさいよっ。なんとかならないのっ」
部屋からは、凄まじい剣幕であろう洋子の、罵声ともとれる声が洩れる。
毎日新聞の記事を潰せ、と洋子は晋太郎に迫っていた。翌朝、毎日新聞がリクルートから〝顧問料〟を受け取っていた政治家のスクープ記事を準備していたのだ。そこには晋太郎の名が取り沙汰されていた。
晩年、「あれは、俺は本当に知らなかったんだ」と晋太郎がため息をついたといわれる一件だった。
実際、晋太郎はある対談でこう語っている。
リクルートの問題も、言い訳するつもりはもちろんないんだけれど、私の知らないところで――知らないことが多いんですよね。実際は。しかし、知らないからといっても責任はもちろんあるわけです。
(『新世紀への架け橋』安倍晋太郎)
後の報道によって、リクルートが顧問料名目で支払っていたカネは、洋子に対するものとして〝話〟は定着する。
果たして、何が洋子をそれほどの怒りに駆り立てたのかは、傍目にはわからなかった。その晩、そのおどろおどろしい発作的とも思える罵りは、空が白み始めるまで止むことはなかった。
この話は、後援会関係者からたびたび聞かされた、「お兄ちゃんの寛信さんは晋太郎さん似で、晋三さんはお母さんそっくり」という「気質」を思い起こさせた。
北朝鮮外交やNHK問題での、しゃにむに刀を振り回すかに映る、晋三の猪突猛進ぶりは、強い理念が育んだ「信念」ではなく、母親譲りの気質、辛辣にとれば「発作」とさえ感じてしまう。
ある時、晋太郎は幼なじみの女性にこう洩らしたことがあった。
「うちの台所(財布)を見てご覧よ。メチャクチャだよ。驚くよ」
自宅で、そう屈託なく呆れ果てて見せたその晩、晋太郎は独りだった。
「あらっ、洋子さんたちは?」
こう訊くと、食卓に着いた晋太郎は答えた。
「みんな、高橋さんの自家用飛行機で、オーストラリアにゴルフに行ったよ」
バブルの時代、旧長銀(日本長期信用銀行)の資金を後ろ盾に、海外でのリゾート開発で名を馳せた「バブル紳士」の高橋治則も〇五年、六本木のサウナで急逝した。
ときに際どい交友関係との遊行にも、ウメは洋子とともに、一度ならず同行した。
株相場も、銘柄は東京ガス、東京電力に始まって、凸版印刷などずいぶんとやったと、ウメは話してくれた。
そんなウメ自身の言葉を思い起こせば、間違いない。
ウメは、「知りすぎた女」だった。
「知りすぎた女」はやはり生前の晋太郎が洩らしたカネの話も覚えていた。いつ頃のことかは定かではないと前置きしながらも、「政治というのは金がかかるものだな」と言っていた、と。
晋太郎がまだ岸の秘書官時代の話である。
当時、南平台の岸邸のなかに蔵があり、そこに大きな金庫があったという。それが、「一晩ですっからかんになっちゃったよ」と晋太郎が仰天したというのだ。
金庫いっぱいの金が一晩で霧消する現実を見て、新聞記者上がりとはいえ、晋太郎もよほど驚いたに違いない。
ウメもまた、玄関先で「岸先生にたしかにお渡し下さい」と、菓子折りの「ハコ」を受け取ったことがあった。
中身の詳細までは分からなかったが、「ハコ」の重さでお菓子ではないことは、受け取ったときに分かったという。そして、すぐにそれを奥へと持って行ったのだ、と。
この話を聞いて、私はこれこそ、決選投票にまでもつれ込んだ、五六年一二月の総裁選のときではなかったか、と睨んだ。
晋太郎が毎日新聞社を退社し、当時は外務大臣を務めていた岸の秘書官となったのはその五六年一二月である。
「金庫の金が一晩で…」とは、まさにすべてを賭けた瞬間だったのではないか――。だとすれば、それは総裁選以外にあるのだろうか。
そして、きれいごとでは済まされない、凄まじいまでの政の現実を父親のもとでつぶさに目にしてきた洋子が、「屈辱」を覚えたのは、まさに夫、晋太郎に総理のイスが巡ってこなかったことであったはずだ。
佐藤栄作、岸信介という二人の兄弟宰相を輩出した「岸王朝」のなかで、わが夫・晋太郎の負け戦に、洋子が雪辱を誓わなかったはずはない。
父が「勝ち」、夫が「負け」、そして我が子・晋三に勝負のときが訪れたとき、洋子が何を狙うのか、その執念のすべてをどこに注ごうとするのかは、あまりに自明のことではないか。
第3章
意思を継ぐ者
安倍晋太郎死去と出馬
再び消息を絶ったウメ
二〇〇三年九月に幹事長に就任した晋三がやがて政権を獲るようなことになれば、世代交代が完全に完了するという、それは自民党内の危機感を決定付ける小泉劇場の「最終章」の幕開けにほかならなかった。
この深読みに過ぎる邪推を確信に変えたのが、〇五年秋の総選挙で自民党が圧勝した後、新人議員らを前にして小泉が放った次の一言だった。
「(次の総裁選を前にして)これからすごい権力闘争が始まるよ。勉強になるから、しっかりと見ておいたほうがいい」
やはり、小泉自身が安倍を要職に置き、自らの後継者のコマのひとつに置いたことの意味を誰よりも分っていたのだろう。
〈自民党が〝沸騰〟する〉はずの状況を。
小泉が、八〇人を超える新人議員を前にしてその言葉を放ったとき、晋三は、自民党幹事長から、内閣官房長官に就任していた。
その頃のことだ。
〇六年一月、湾に面した小さな海辺の村から、ひとりの女が姿を消したのだった。
三年前にも一度、〝行方不明〟になった、「久保ウメ」である。
なんとも、不思議なことだった。
ウメの行方は、内閣官房長官・安倍晋三に近しい者たちの間では、「極秘」とされていた。
「極秘」とは、なんと大げさなことかと思った。
でも、すでに八〇歳を超えた、背丈一六〇センチにも満たない老女の消息を、安倍家周辺が頑なに〝匿している〟背景には、ある事情がうかがえた。
それは、いよいよ安倍晋三が小泉純一郎の後を襲う、自民党総裁候補の最右翼と目され、そして〇六年九月にまさしくその総裁選挙が迫っていたからだった。
きっと、〇六年九月の総裁選は、晋三の地元選挙区の後援者にとってだけでなく、山口県民にとっても、戦後八人目の宰相を生むかどうかの大きな期待がかかった祭りであったに違いないのだ。
もちろん、それは同時に、晋三の選挙地盤である山口県下関から長門にかけての山陰では、あまりに長く待ち望んだ春の日和が訪れることを意味していた。
首相の座を目前にしながらすい臓ガンに倒れ、総理就任への願いを果たさずに逝った、晋三の父である晋太郎の無念を晴らす、「お国」を挙げての雪辱戦でもあったであろう。
普通に考えれば、なるほど、ならばそれは喜ばしいだけのことではないのか、と思われた。父の無念を抱えながら、子がいよいよ父の果たせなかった悲願を成就させようとしているのだから。
その永田町の政治状況と、故郷に帰っていたひとりの老婆との間になんの因果があるのだろうか、と疑問が湧くのも無理はない。
でも、〇三年の〝行方不明〟の顛末を知る者としては、これは見逃すことのできない大きなサインのように思えてしまったのだ。
そのウメが〝施設〟に入れられたと知った、安倍家の遠い親戚は、ため息まじりにこうつぶやいて見せたのだ。
「ああー、口封じされたんだわ。あの病院に入れられたらもう…。外から鍵がかかっている部屋もあるんですよ」
ウメは幼稚園に上がる前の幼い晋三のむつきを換え、幼稚園への往来に手を引き、背に乗せた。
おそらく誰よりも安倍家を愛し、安倍家に尽くしたのだった。そのウメが、自らの存在を疎んじられる状況に置かれてしまったとするならば、それはどれほどの皮肉だか知れなかった。
何よりも状況は、次の言葉が象徴していたように思う。
「ウメの話が本にでもなったら困るわ」
ウメを捜す者がいることを知った、晋三の母・洋子の言葉だった。
捜しているのはほかでもなかった。……私だった。
〇六年に入って、ウメの消息が再びつかめなくなっていたその傍らで、永田町界隈には、ウメは「危篤で面会謝絶」「洋子さん以外は誰も居場所を知らされていない」という話が流れていた。
でも、それがウメを世間から遠ざける一種の〝はったり〟であることを、確信していたのだ。
ウメの親族のひとりが、電話口でこう声を潜めていたから……。
「実は正月にも皆でご飯を食べたんです。テレビで晋三先生を見ると今でもいろいろと思い出すのか、しきりに話していましたよ」
そして、毎年、夏になるとウメに会いに油谷を訪ねていた私に「極秘」を貫くのは忍びないと思ったに違いなかった。
その人間は、家人にさえ聞かれるのを憚るように、ウメの入っている施設の名を、一層押し殺した声で囁いた。
その施設の場所を聞いて、思わず、アッと驚いた。
だって、それはウメの処遇を考えるにはあまりに辺ぴすぎるように思えて、予想していた手厚い場所とはあまりにかけ離れたところにあるように思えたからだった。
岸信介のころから政治家三代にわたって仕えた「乳母」ならば、きっとその老後は、大きな町の特別養護老人ホームか介護マンションのようなところで過ごすに違いないという、ある種の〝偏見〟をもっていたからだった。
だから、ウメの所在にたどり着く前に、自らのその誤った偏見のせいで、ずいぶんと遠回りをしてしまっていた。
下関と長門の、県に登録されている大手の特別養護老人ホームや介護施設を数十ヵ所捜し出し、そのすべてでウメが入院しているか、さもなければ入居しているかを訊ねていたのだ。
でも、そのどこにもウメの痕跡はなかった。
それもそのはずだった。
当のウメは、下関から山陰本線で二時間ほどの山あいの病院にいた。
木も生えていない平らな野原が一面に広がる、通称・千畳敷の広がる山頂を乗り越え、日本海の湿った空気が吹き降ろす田畑の中に、その病院はあった。
その日は、春の匂いはするけれど、まだ三寒四温のただなかにある寒い朝だった。
面会時間の始まる午前九時に到着し、面会票に氏名と住所を書き込んだ。
病院は神経内科と内科が専門のようで、敷地内には老人ホームも併設されているようだった。
お年寄りの患者が多いほど、朝の病院は込むはずだったけれど、ロビーにはほかには誰もいなかった。でもそれは、神経内科を掲げたその病院の外来事情によるのだろうな、と勝手に悟ってみる。
受付に面会票を提出すると、間をおかずして、にわかに騒がしくなった。
「あっ、ウメ様の…」と絶句した受付の女性は露骨にろうばいし、裏に走った。
ロビーの長イスの上へ、ウメに持ってきた手みやげの紙袋を置きながら、その職員の背中を目で追って、早々に、参ったな、と思った。
案の定、ほどなくして、ウメではなく、事務長が登場した。
中年というには歳のいった初老の事務長は、当たりの柔らかい物腰とは裏腹に、妙なほどの警戒感を漂わせ、そして頑固だった。
「ウメさんがこちらにいることはどちら様から……?」
「はい、ご家族ですが」
なんと、当たり前のことを訊くのか、とこちらこそいぶかしく思った。
「極秘」「危篤」と周囲にかん口令が敷かれているなかで、家族から聞かずして誰がウメの居場所を知りうるというのだろうか―。
すがすがしいほどの速やかな返答に、フームと、事務長はなぜか合点がいかない様子だった。そのワケはすぐに明らかになるのだけど、そのときはまだ、その病院が、思っていた以上に〝特殊〟な場所だとは考えもしていなかった。
そして、面会を渋る事務長が押し問答の末に奥に引っ込むと、次は医者が現れて丁重に別室に招き入れた。白衣の前のボタンを留めながら呼び込んだところを見ると、事務長に説得されて、わざわざこの珍客のために白衣を羽織って、しぶしぶ登場したといったところだろうか……。
「ご本人様からは、ご入居のときに親族の方以外は面会させないことで、同意書を頂いております」
医者は抑揚のない、乾いた声音でそう告げた。
いったい、何を唐突に言っているのだろうか、とそう思った。ウメが〇五年の秋に倒れたことは、ウメの妹である郁子から聞いて知っていた。きっとそれがもとで「危篤」「面会謝絶」といった話が流れているのであろうことも推測していた。
郁子の話では、確かに軽い痴呆が出始めていることも間違いないようだった。
「きっと、こちらに帰ってきて気が緩んだんでしょうねー。本当に急に悪くなってしまって」
痴呆症状が出ているのが本当ならば、それこそ「ご本人様から同意書」とは、笑止に値する話だった。
痴呆のある患者の「意思」を、どのように担保できるというのだろうか。
それも、本人が「親族以外は面会させないで」とは、ずいぶんとウメらしくない話であるようにも思えた。
ウメは、よほどのことがない限り来訪者を常に歓迎する、「来るものは拒まない」大らかな女性だった。
でも、もう状況のすべてを呑み込むことができた。
病院はとにかく、誰もウメには会わせたくないのだ。
きっと、ではその同意書を見せて欲しいとすごめば、この医者は次にこう言うに違いなかった。
〈いやいや、それは患者様のプライバシーの問題がありますので〉と。
個人情報保護、精神保健福祉法と、使っている当人でさえ解釈を十分に理解しているとさえいえない関係者がすぐに持ち出すのが、この「人権保護」だった。
病院側が「会わせない」と突っぱねる限り、それ以上の押し問答はまさしく時間の浪費に近かった。
そして、あろうことか―。
それでは、と差し入れに持参した、桜の模様の入った湯呑みと節句祝いの小さなひな人形の置物を言付けようとしたけれど、なんと病院側はそれも拒否したのだ。
その傍らで、事務長と婦長は安倍家の関係者に電話をし、「お引取りを」と玄関へ促したのだった。
そこに来て、ついに〝反撃〟に打って出た。
「本人に面会の意志さえ確認しないで、それではまるで幽閉ではないですか…本人の意思に勝る権利はないでしょう」
誰が聞いても当たり前の話だと、我ながら思った。彼らは思わぬ反転攻勢に、これまた露骨にろうばいし、たじろいだ。
実際、彼らがウメに面会者がたずねてきた事を、ことここに至ってもなお知らせてもいなかったのだ。このまま引き下がれば、ウメは未来永劫、会いに来たことさえ知らないままだ。
病院長の横に立ち、「精神保健福祉法が……」「精神保健福祉法で……」とハト時計のように繰り返す小太りの婦長は、にわかに目つきの鋭くなったその言葉に本気の度を感じたのか、突然折れてみせた。
「……確かにそうかもしれません。では、ご本人に確認だけはしてきますので」
そういって、婦長は事務長を残し、再び視界から消えた。
残されて途方にくれながらも、ウメから届いた手紙や写真などを事務長に見せながら、「やはりウメさんにさえ面会者が来たことを知らせていなかったのか」と、形勢逆転に乗じ、やおら批判めいた言葉を繰り出していた。
そんな強硬なやり取りそのものに不慣れだったのだろう。
事務長は、婦長や医師らが外したすきを見て、こうもらした。
そして、その言葉こそがすべてだと、密かに悟った。
「遠いところを来ていただいたのに申し訳なく思います。うちも普通ならば面会はできるんです。ただ、ウメさんは政界におられたということもありまして……」
思ったとおりだった。
戻ってきた婦長は、まるで最初から決まっていたかのような答えを開陳した。
「今ね、私ひとりでは、訊いてないということにはなりませんのでね、みなさんのいる前でウメさんに訊いて来ました。ウメさんがはっきりとご返事されませんでしたのでね、それではお会いになられないということでよろしいですね、ということを確認してきました」
すでに分りきったそんな答えを聞いて、それにしても妙な話だな、と思うのだった。
「危篤」「面会謝絶」「痴呆で前後不覚」などと言われるウメはやはり、グループホームのような集団生活を立派にこなしているではないか。
この病院が併設する老人ホームでウメは暮らしているのだろう。
婦長が思わず口走った言葉こそ、それを証明していた。
「みなさんのいる前で……」と。
いったいこの茶番にひとしい寸劇のシナリオを誰が書いているのだろうか―。
そのとき、やはり事務長が不用意に語った一言が強くかつての記憶を呼び起こしてくるのに気付いた。
なぜ会えないのか、と押し問答をしている最中のことだった。事務長は思わずこうもらした。
「ご存知のとおり、前の事務長がウメさんのお兄さんでいらっしゃったものですから。そのお兄さんにただいま連絡いたしましたらば、お宅さんを存じ上げないといっておりまして……」
ウメの「お兄さん」のことは、もちろん知っていた。
この病院からそれほど遠くない場所に暮らす、久保芳雄であった。
久保芳雄が、自らが事務長を務めていた、いわば〝身内〟の施設にウメを入れているのであれば、なるほど、守りが堅いはずである。
病院を放り出された私がテクテクと無人の駅に向かうその途中で、決してどこにも落き忘れることのないように、東京から肌身離さずに持ってきたウメの〝形見〟の感触をしっかりと確かめていた。
「いつかは私の人生を残したい」
それは、かつてウメから託された録音テープだった。
安倍晋三の父親である、安倍晋太郎が育ったのがこの油谷の村だった。安倍晋太郎もまた、自民党幹事長や通産大臣、外務大臣を歴任した、名実ともに大物政治家だった。その晋太郎が亡くなってからもう二〇年以上になる。
長く自民党の若いプリンスとして名を馳せ、将来の自民党総裁候補として目されてきた晋太郎が急逝したのが九一年五月だった。
戦後の一時期をのぞけば、日本では与党・自民党の党総裁であることが国会での総理大臣としての首班指名を受けることに直結していた。つまり、自民党の総裁であることは日本の総理大臣であることを意味し、総理大臣であることは自民党総裁であることを表すのが常識ともいえた。
でもそこには、ごくごく稀な例外もあった。自民党総裁でありながら総理大臣のイスに座ることができなかった河野一郎という政治家がいた。
この河野が総理になれなかった逸話も、永田町ではしばしば語られる悲劇だったけれど、自民党で今なお根強く語り継がれる「悲劇の伝説」といえば、晋太郎の話を置いてほかにはなかった。
八六年のことだった。どれだけの国民が当時、自分たちを取り巻く、かつてない豊かで恵まれた時代状況を意識していたのかは分らないが、日本は「バブル経済」のまっただなかにあった。土地や建物といった不動産類の価値がべらぼうに急騰し、土地成金、不動産成金が、それこそ日本列島のいたるところに生まれていた。
そのバブル経済が生まれた当時の内閣は、「政界風見鶏」などと揶揄もされた、あの中曽根康弘が率いていた。その中曽根内閣のもとに、次の世代の自民党を背負って立つと目されたエースたちがいたのだ。
それが竹下登、宮沢喜一、安倍晋太郎の三人の政治家だった。このうち、竹下と宮沢は順当に総理となり、一時期、日本の政権を担ったけれども、晋太郎だけがその願いかなうことなく、逝った。
すい臓ガンだった。
それ以来ずっと、政治に詳しくもない一般人にとっては、政治家「安倍」といえば故・晋太郎を指し、その晋太郎は、「総理になれなかった悲運の政治家」として記憶に刻まれてきた。
安倍晋三の乳母・久保ウメには、色褪せることのない鮮明な思い出があった。
晋三の父・晋太郎が病魔に襲われた八九年のことだった。
東京・御茶ノ水の順天堂大学附属順天堂病院の特別室――。
すい臓ガンという病名を知らされずに横たわっていた晋太郎のそばに、明け方まで寝つけない晋太郎のため、しばしばウメが泊り込んでいた。
同じ時期、すぐ下の階には国民的歌手の美空ひばりも入院していた。
世に知られた政治家と芸能人がひとつ屋根の下にいるだけに、特別室とは言え、日中の病棟は見舞い客の出入りも多く、それなりに賑やかだった。
そのためか、夜になり消灯を迎えると、静けさの訪れは寂しさを呼んだ。
晋太郎は病床では本を読んでいることが多かった。週刊誌以外ならば何でも手元に寄せた。小説ではとりわけ時代物を好み、なかでも司馬遼太郎はよく読んでいた。
深夜、病室の静寂に耐えられなくなると、ウメと晋太郎の二人は、明け方まで滔々とおしゃべりを続けた。
「いやだー、いやだー」
夜になると、晋太郎は声を発した。そのたびにウメは晋太郎に、背負って病室から逃げるにしても、長身の体躯を背負えばその小柄な身では足が地面に擦れてしまうから無理だと言った。口相撲をとったり昔話をしたりしながら、朝の四時まで喧嘩ばかりしていたと。
九〇年からの再度の長期入院では、わずか二歳年長で同郷のウメを相手に、晋太郎の「昔話」は尽きなかった。
まだ晋太郎が学生の頃の、父・寛が亡くなった日の回想もあった。
ウメによれば、晋太郎は自転車に乗って駅まで向かい、汽車通学をしていた。ある日の朝、下関から特急に乗ろうとしたところ駅のプラットホームでどうしても片足が列車に上がらなかったという。
「片足がどうしても乗らなかったから、おかしいと思って人をやらせたら、親父が亡くなったんだ」
それを聞いて晋太郎は泣いたのだという。
そんな湿っぽい話もあれば、ウメが晋太郎を励まそうと、息子たちの話題を振ることもあった。
あるときは晋三の実弟である岸信夫に子が生まれることを告げた。信夫は安倍家の三男として生まれ、生後すぐに岸家に養子に出されていた。大学卒業後に住友商事に入社し、晋太郎の入院時は海外に赴任していた。現在、信夫は参議院議員である。
「寛信(三菱商事)は社長は無理でも、真面目に勤めれば重役ぐらいにはなるだろうな。晋三は自分が後を継ぐって言ってるからな…」
そんなふうに、晋太郎は深夜の病室で寛信と晋三の将来を語ることはあったが、養子に出した信夫のことには決して触れなかったという。
ウメにすれば、励ます話題のつもりだった。だが、「誕生」の話から何を想ったのか、晋太郎は突然、握り締めた拳を突き出した。
「ぜんぶ、自分が生まれたときに握って出た業だな」
唐突な所作にウメが躊躇していると、晋太郎はもう一言、こぼしたという。
「あんたもな」
最期の瞬間まで本当の病状を知らされていなかった晋太郎とはいえ、長引く療養と痩せていく体を前に、己に残された時間を知らないはずはない。
「業だな」。ウメには、それは近づきつつある終わりの時を見据えた覚悟のように思えたそうだ。
四〇年間一緒にいてその一言だけだったというが、そう語ったときの表情は決して絶望的な寂しさではなかった。ウメは〝嬉しそうに〟苦笑してみせた。あたかも女房冥利に尽きる、そんな風情だった。
やはりひとりで逝くのが寂しかったのではないか、だから「あんたもな」とこぼしたのではないかと、ウメは言葉の背景を読んだのだ。
体調がよく、気力が甦る時には、こんなやりとりもあった。
「とにかく、何かひとつだけやりたいな。あれは安倍晋太郎がやったというものをな」
ウメにとっても、晋太郎との思いはひとつだった。掛け合いのつもりではなかったが、本心がすぐに口を突いた。
「北方領土をおやんなさいよ」
「まあ、そうだな」
晋太郎は照れながら応えたという。
そんな会話から遠くない日、九一年四月一八日、晋太郎は紺の背広に着替えて、病院から来日中のソビエト連邦大統領(当時)、ミハイル・ゴルバチョフとの会談に赴いたのだった。
晋太郎ほどの照れ屋はいないという。しかし、素朴なものを持ってる人物のほうがよく、晋太郎の人柄は変わらぬ素朴さなのだと。ウメによれば、そんなところはどこか、晋三にも受け継がれているらしい。
しかし、父・晋太郎が北方領土問題に賭けた「悲願の業」が、北朝鮮問題における晋三の外交意識に引き継がれたとする見方は、あまりに美談めいている。
ウメは安倍家の「業」に別のものを見ていた。
それは、晋三にとっては父方の祖父にあたる元衆院議員の安倍寛と晋太郎に共通する、「母なき育ち」にどこか影のようにつきまとう「寂寥の業」として映った。
ゴルバチョフとの会談からひと月足らずの五月一五日、晋太郎は入院先の順天堂病院で不帰の人となった。六七歳だった。
晋太郎の末期の水を取ったのは、他ならぬウメだった。
晋太郎は生前、自らのルーツについて「俺のところは朝鮮の系統だ」と、そして「韓国に行ったときでもですごくもてた」とウメに話していた。納棺前の亡き骸の清拭を手伝ったとき、ウメはそのことを納得したのだという。
ウメは、ガンを患ってから末期の水を取るまで、晋太郎のすべてを見届けていた。入棺のときに清拭し、実際に見て触れた骨格の感じから、聞いていた通り日本人的ではないなと思ったそうだ。肩の幅から下までまっすぐ定規引いたような骨格は、完全に韓国の体型だと感じ取ったという。足もすんなりと長く、晋太郎が自らを語った話を思い出し、ひとり頷いていたのだという。
そして、国の損益だと思えるほど「ほんとうに惜しい人を亡くした」と、晋太郎への思いと思い出は尽きることなく、まだ元気に本気で働ける時間があったならばと前置きして、いくつかの持論も展開された。
当時、ソ連とアメリカは押さえていたから北朝鮮の問題も早くに解決していたのではないか。色々なところでしわ寄せがきて、疲れ果ててしまったのではないか。育てたら立派に仕事を果たせたと思うが、それをもう少し勇気のある、少しでもいいから声だけ出してくれるような人がそばにいたら……。
そして、安倍家の本流が津軽の五所川原であり、安倍貞任や宗任、そして阿倍清明と同じ先祖につながっていて、世に出るべくして出た。晋三も出るべくして出てきたというのだ。晋太郎は途中で亡くなったが、晋三は役目を果たしていくという信念を持っている、と。
王朝が新しい時季を迎えたとすれば、それは間違いなく、晋太郎を喪った翌九二年だった。
若い頃から、政治家という職業を継ぐことを口にしていた晋三にとって、すでに腹のなかは〝出馬〟で決まっていたに違いない。
しかし、九三年の総選挙をにらんだ、それは雌伏のときでもあった。
それは、王朝が今後もその脈を永らえさせることができるかどうか、あるいは洋子には一抹の不安も拭いきれない、不安の季節でもあったかもしれない。
者々はそのとき、伊豆に集まっていた。
家に閉じこもっているのもつらいものですから、わたくしと晋三夫婦は暮れの三十日から伊東の川奈にまいりました。寛信夫婦は、嫁の曾祖父のおられる神戸に牛尾さんご夫妻と一緒にお伺いし、帰途、川奈に合流いたしました。大晦日と正月二日には三人だけでゴルフをいたしましたが、三日は寛信と久保さんも加わり、寛信の嫁は夏に第二子を出産予定ですから見物でしたが、にぎやかに過ごしました。その夜は家族水入らずで、久しぶりに心ゆくまで話ができたのです。
川奈には父と来たこともありまして、子どもたちにもおじいちゃまとの思い出があるのですが、主人が元気なころに二、三度まいりましたので、やはりいろいろと思い出されることもございました。そのころの元旦は自宅でお客さまをすませて、その夜に川奈に入ったのですが、暮れからまいりましたのはもちろん初めてでございますから、なにかお正月のような感じはいたしませんでした。
晋三の出馬についても話は出ましたが、なにしろいつ総選挙があるかわからないものですから、あらたまって覚悟のほどを話し合うということもなく、準備の状況を聞いたり、地元の活動の手順を確認するようなことですませております。いずれにせよ、草の根掘り起こし時代からの実績がございますから、その部分はわたくしと久保さんが受け持ちますが、あとの県連関係や企業関係、そして若いグループについては晋三が担当するということになっております。
選挙のあり方に納得できないという寛信も、手伝いはしてくれると言います。かつて主人の選挙では、兄弟が勤めを持ちながらスケジュールをやりくりし、たがいに振り分けて車に乗ってくれておりました。晋三が加古川工場におりましたときは、夜行列車で戻って朝には工場に入るのですが、溶鉱炉の上を行き来するというので「落っこちて鉄板にならないでよ」と申しますと、「片足落したのもいるよ」とおどかすのでした。その晋三がこんどは候補者になるのですから、片足どころか両足を突っ込んでの選挙です。落ちるなどは禁句で、しっかり歩いてもらいたいものです。
(『わたしの安倍晋太郎』)
さながら、王朝直系の者たちによる鳩首会談といった趣だろうか。
ところで、洋子自身の口がいうように、「政治の道の跡継ぎ」とは国民にとってはいったいどんな意味があるのだろうか、と思うことがある。
安倍家を米国の政治一家として知られるケネディ家になぞらえる例えも耳にしたことがあるけれど、二世、三世の政治家が永田町にゴロゴロいるのを見聞きすると、ひねくれ者の身としては、なんだかゾッとしてしまう。
近代日本の「立身出世」システムは、まさしくこの世襲を廃止することで成り立ってきたはずなのに、それはまさしく建て前にすぎないということなのだろうか。
政治家だけでなく、日本では弁護士も、医者も、まるで「継ぐべき家業」であるかのように錯覚されているように思えてならない。
それぞれの職業にどのような人格と能力の適性が必要なのかはわからないけれど、だけど、いずれの能力も、すぐれたものが必要とされるものであるならば、それは限りなく、一身専属の能力であるはずだ。
もちろん、人格も能力も、教育や伝統や自覚によって磨かれうるものだから、大きな意味で「継ぎうるもの」だというのはわかる。
だけれど、幼少のころから「親父の跡は俺が継ぐ」といっていたことが、政治家の素質としては何も担保していない、と思うのだった。
政治家の場合、それは地盤と看板を継ぐということを意味するのだろうけど、それこそまさに「禅譲政治」の最盛期を生きてきた自民党政治の象徴そのものに、どうしても見えてしまう。
禅譲政治…さもなくば、五十五年体制の……。
晋三こそは、こうした旧態依然とした自民党が築いた、少し皮肉な言い方をすれば、祖父の代から営々と築き上げられた「自民党」という政治システムの反語(アンチテーゼ)として小泉純一郎に日の当たる場所に引き出されてきたのだから、その晋三の原点が「政治家としての後継ぎ」というのは、ちょっと残念に響く。
晋三が幹事長にした〇三年からこれまでに、自民党の旗艦よろしく声高に主張し続けてきた「国益」も「外交」も、「憲法改正」も、それはまさしく自民党政治の主張そのものにほかならない。
おそらく、その主張を野党側からみれば、まさしく「ミスター自民党」の保守本流であるのだろうに、小泉純一郎あっての安倍晋三という産み落とされた過程に目を向ければ、晋三という存在は、いわば自民党にとっての、まさに「逆子」のようなものだった。
それをわかっていて、あえて晋三を立てたところに、小泉純一郎という政治家の狡猾さがのぞいているように思うし、こうした戦略(ストラテジー)にはない戦術(タクティクス)はきっと、凡庸な秀才には測り知れない理解可能なものとして、目に映ることにさえなるのだろう。
そして、それがまた、〝見えない〟ものへの畏怖を呼び起こす……。
例えれば、総理大臣・小泉純一郎と、官房長官・安倍晋三という、定石どおりの戦略をとらないゲリラの戦いに、陸士・海士卒の士官たちはなすすべもないといったところだろうか。
秀才はゲリラとの戦いに決して勝利できないとなれば、ベトナム戦争を思い出すまでもなく、小泉政権の「勝利」はその誕生から予見できた。
でも、国民にとってみれば、そんな瑣末な戦いは、自民党内部での話だから、直接に関係ないともいえる。
小泉政権の最大の成果であり、課題であり、問題ともなりうるのは、この在任期間中に官邸機能がかつてないといえるほどに強化されたように見えることである。
肥大化した官僚機構の裁量行政と、その内質に浸蝕するまでに一体化した既得権を削ぎ落とすところに、小泉の掲げた「郵政民営化」の狙いがあったのだとすれば、それは〇五年の夏の衆院選での自民党大勝で見事に実現した。
それを可能にしたのも、もはや省庁主導の行政立法を退け、官邸主導で一点突破を図った〝作戦〟にあったともいえよう。
明治以来の既得権を破壊しようとするのだから、そこには凄まじいエネルギーが必要だったのは確かだろうし、その過程でのさまざまな抵抗と障壁と、そして反応のすさまじさは、もはやメディアを通じて衆目が一致するところだろう。
第4章
混乱の季節
政治家としての安倍晋三
現された頭角と〝原風景〟
安倍晋三の存在を世に知らしめたのは、今となっては武勇伝の域に達した、〇二年の電撃的な小泉訪朝での、あの発言である。
「もし拉致を認めないで謝罪しないなら、席を立って帰りましょう」
この発言が洩れた背景には、どうやら晋三陣営からの記者連への〝手柄〟のリークだという話が根強くある。
晋三自身によるリーク説が本当だとすれば、確かに、見事なまでにその意図する効果はあったに違いない。
実際に、この発言によって晋三の「タカ派」という評価が浸透したのは間違いなかったが、むしろ北朝鮮をめぐる「タカ派」ぶりはこの時点もそれ以後も、決してそのイメージの足をひっぱるには及んでいない。
むしろ、〈毅然とした態度をとることのできる外交姿勢〉としてプラスの評価に結びついているように思えた。
その証拠に、この発言以後も晋三の人気は衰えるどころか、さらに世論調査でのポイントは上昇したのだった。
そして、ついに内閣官房長官というまさに国家権力におけるこれ以上はない中枢にまで彼を押し上げる。
でも、世論調査での支持率の推移だけをみれば、何よりも晋三の人気を支えていて、決して国民から否定的には受け取られていないこの発言に、震える思いがしていた。
素朴な怖さがあった。
「席を立って」しまったら、外交はその瞬間に終わってしまうからである。
もちろん、「席を立って」みせる外交も必要なのかもしれない。でも、席に座り続けることが外交の真髄でもあろう。
もちろん、実際の外交とは人間と人間の会話であって、対話だと思うから、それは理念や理想や、ましてや学問の次元とはかけ離れたものなのかもしれない。
でも、日本はこれまでにも、「席を立つ」ことの怖さは何度も経験しているはずだった。
かつて、外交官の松岡洋右が「席を立ち」、国際連盟を脱退して、日本は太平洋戦争の泥沼に突入していったように、そんなおろかなことが今起きるとは到底思えないけれど、席を立つことは対話を放棄することだから、外交においては、その行為は何よりも禁忌なことなんじゃないかと、思っていた。
でも、安倍晋三という政治家がもし、誇らしげに「「もし拉致を認めないで謝罪しないなら、席を立って帰りましょう」なんて語ったとするならば、それはきっと国の威信を、言葉は悪いけれどはき違えているんじゃないか、とさえ感じてしまう。
これが、「芯が強い」性格のゆえだとしても、いったいそれだけの理由で、彼の外交意識がカタチづくられたとはにわかには信じられなかった。
いったい、何が彼のそうした意識と行動の底にあるのだろうか―。
この英雄的な歓喜さえもって迎えられたこの発言を、あえて否定的に見たとき、若い彼のこんな発言を見つけてしまった。
それは、今からちょうど一〇年前、『「保守革命」宣言』という著書のなかで、晋三自身が語っていた。
そこには、晋三の外交論の原型が垣間見えている。
少し長いが、彼の外交に対する〝原風景〟が生々しく表れているように思えるから、引用してみたい。
まず、外交というのは、お互いに自分の国益を守るために必死の努力をする場であるということです。つまり、単に仲良くなったからといって、あるいは同情してもらったからといって、どうにもなるものではない。そういうことをまず、政治家は踏まえておかなければならないと思うのです。
私も、父が外務大臣時代に、一緒に外交交渉に同行するといったことがありました。当時のソビエト連邦などでは当然、盗聴器が仕掛けられている中での交渉、というようなものでした。共産圏での交渉というのは誠に大変な作業だな、とその時私は感じたわけですが、その時随行の外交官にこういわれたわけです。「こんなこと、共産圏だけだと思ったら大間違いですよ」と。
イギリスだってアメリカだって、そんなことをやるのは常識ですよと。それがないと思っているのは日本だけですよと。そういうことを外交官から聞いて、私は非常にびっくりしました。外交というものは、まさに武器を使わない「戦い」なんだなと。
最近、新聞で報道された橋本通産大臣(当時)の電話をCIAが盗聴していたという話。あれは当然やっていたことだと思います。要するに、外交というのはそういう場だということです。ですから、その事実をやはり忘れてはならない。こっちが誠意をもって交渉しているのだから、あっちも多分分かってくれるだろう、などといっていたら外交などというものは成り立たない。そういう甘い感傷のもとに一方的に譲っていったら、果てしなく譲歩しなければならなくなる、という話でもあるわけです。
外交というものが油断のならないものであるという話のついでに、中国についての話も紹介しておきましょう。中国というのは、非常に客のもてなし方がうまいですから、何とはなくいい気持ちにさせられてしまう。日本の場合、そういう情の部分には非常に弱いという面がありますから、中国はそういう点で実にうまく付け込んでくるわけです。
かつて、蒋介石の生誕百年の時でしたか、彼の「遺徳顕彰」記念事業というのを日本でやることになった。父が外務大臣の頃です。ところが、その時の中国の外務大臣、呉学謙だったかが、それはやめてくれといってきた。鄧小平も、蒋介石は犯罪者だと、自分も彼には殺されそうになった人間だから、これは何としても止めてくれと。そこで、祖父がその責任者で、父はまさに板ばさみの立場にあったんですが、ともあれ外務大臣として、これに防戦あい努めることになったわけです。
そんな中で、ある日、中国大使が私を昼飯に招待した。一体私ごときに何を、と大使館へ行ってみると、岸信介を中国に招待してもいい。満州へでもどこへでも、好きなところへ国賓待遇で行ってもらう、というような話をしてきたのです。若き日の思い出の地に、きっと行ってみたいでしょう……と。
私は一瞬グラッときましたが、ともかく話を祖父に伝えた。しかし、祖父は行かないといいました。私が思うには、やはり祖父とすれば、行きたくない筈はなかったと思うんです。しかし、その話には乗れない――と。中国外交の深謀遠慮を祖父は十分に心得ていたわけです。
この話は中国外交の戦略性の一端を物語る一例でもあります。中国外交は言葉でがんがん攻めるだけではありません。必ず、からめ手からも攻めてくる。そして、目的を達成しようとする。単純な国じゃない、と痛感した次第です。
もう一つ、李登輝総統と、広島のアジア大会が始まる前に会った時の話です。李登輝総統は、自分を日本に呼んでくれといいました。で、中国はその場合は、アジア大会に参加しないといっているけれども、自分は中国人だから分かるのだが、そんな単純な国じゃない、というのです。
まずアジア大会に中国が参加しなかったら、だれが一番損をしますかと彼はいいました。日本も困るでしょうけれども、一番損をするのは中国なんですよと。実は彼らとわれわれは、分からないだろうけれども、いろんなところで対話をしている。表面的には、けんかをして、今にも戦争をしそうだけれども、彼らはわれわれの経済力を必要としているんですよと。だから、あまり単純に考えるというのは禁物だと彼はいったわけです。
日本の場合はやはり純情にすぎるから、これはとんでもないことだ、断固として是正を要求する、などと抗議されたら、本気にそう思ってしまう。そして、ここは仲良くしなければと、徹底して下手に出ていく。
しかし、国と国というのは、一般の道徳律とは違って、ただ表面的に仲良くすることのみが、必ずしも全てではないということなんです。それ以前に、譲ることのできない国益というものの存在があろうし、むしろ喧嘩して初めて生まれる本当の相互理解というものもあるわけです。
この点、ヨーロッパなんていうのは、まさに永年、お互いを侵略しあってきた間柄だから、実にしたたかです。平気でブラフをかけ合う、激しく非難し合う、なんてことをする。ところが日本は、そういうところで、若干純粋に過ぎる所があるわけです。ともかく誠意を示さなければ、とまず譲歩を考える。
これを直さないと、実は世界の中でやっていけないのではないか、というのが実は私の外交観でもあるわけです
晋三が四一歳のときに開陳されたこの「外交観」を紐解けば、なるほど、「席を立つ」ことが自然な流れのなかで理解できるようにも思えた。
この言葉が、彼が総理総裁候補となるはるか前に記されたものであればこそ、そこには世論の支持を過剰に意識しない、素直な心情が表されているのではないだろうか。
それにしても、「喧嘩して初めて生まれる本当の相互理解」とは、やっぱり少しゾッとしてしまった。
外交上のブラフ(はったり)が、無事に「相互理解」として終着する保証はないだろうし、「喧嘩して」みせて、実際にそれが激しい紛争に突入してしまう例など、太平洋戦争前も、その後も、それこそアジアに限らない世界史を繰れば、いくらでも最悪の例が散見できた。
晋三のいうように、「譲ることのできない国益という存在」が大事なのは確かだろうし、「日本の場合はやはり純情にすぎる」というのも、多くの国民にとって違和感はないだろう。
だが、外交が一筋縄にはいかない高度に戦略化された国家収攬のせめぎあいだとすれば、もし、「ブラフ」を道具にその国益の実現を図ろうとすれば、いつかはきっとそれを〝棍棒外交〟と呼ぶ人々や国が表れるだろうし、いずれは国際社会のなかで否定される瞬間も訪れないだろうか、と考えると一抹の不安は残った。
外交が、いついかなるときも決して結果を確信できない作業であるとするなら、「席に座り続ける」ことと「席を立つ」ことの間には、大きな違いがないようにも見える。
だけど、決定的なのは、席を立てば対話は途切れ、席に座っていれば対話は続くという大きな機能の断絶にほかならない。
晋三の「芯の強い」性格が、こんな外交観に、それこそ〝無防備〟に直結しているとするならば、それはとっても怖いことだと、改めて思うのだった。
さらに、ウメの指摘する「徹底的」というキーワードで解けば、なるほど、思い当たる場面はいろいろとうかがえた。
父・晋太郎の後を襲ってからこのかた、スキャンダルらしいスキャンダルに見舞われることさえなかった晋三を、初めて展開次第では深刻にもなりうる問題が襲ったは〇五年のことだった。
同年、一時世情を沸かせたNHKの番組改編を巡る、朝日新聞に対する晋三の執拗なまでの反撃ぶりは記憶に新しい。
朝日新聞が報じた、番組放送前に晋三や中川昭一がNHK幹部を議員会館に呼び、番組編集に介入したとされる問題である。
中川は、一定の反論を示しながらも、大仰に徹底抗戦を構えようとはせずに、世論の温度を計った〝深追い〟を避ける姿勢で臨んでいるように見えた。
それに対して、晋三はここぞとばかりに猛烈な全面闘争を繰り広げた。
マスコミをも掌中に取り込もうと、柔らかな物腰の一方で恫喝の棍棒を手放さない、政治家〝特有〟の動きとは無縁だった。
無防備なほど露骨に表に立ち、いざ正面から四つに組まんとする姿に、ウメの不安は募るのだった。
そんな少年のような素直な拳の振り上げ方は、政治の世界では、ときに致命傷にさえなりかねないことに、ウメは気付いていた。
政治家の〝鼎の軽重〟
ウメの鮮明な記憶のなかで、これだけ多彩な逸話を残した岸信介や安倍晋太郎に比べて、晋三を語るときの修辞があまりに〝拙い〟のである。
ときに、半世紀近く前の思い出でさえ、生々しいまでの鮮度を甦らせて語り継ぐウメでありながら、晋三の人間性を語るときだけは、その表現があまりに乏しくなる。
晋三の魅力については「ヤワ」であり、晋三の人間性については吉本新喜劇で知られる「吉本興業」であると端的だった。
晋三にむつきをあてがった乳母として、その〝我が子〟を評価する言葉は明快ながら、ともすれば質感が感じられないのだった。
「吉本興業」とは、特に晋三の学生時代、友人を呼んでは裸踊りや宴会をしていたころの場面を指し、意外とひょうきんだという、晋三の性格の一端を言い募っているのである。
〈場面を生き生きと語ることに長けているウメのなかで、晋三だけが語り部の技をもってしても、うまく表現しきれないのだろうか……〉
ウメの観察眼には、間違いなく見事なものがあった。
晋三がまだ小さい頃、親に代わってお小遣いを渡すのもウメの役目だったが、金銭感覚も晋三と兄の寛信とではまったく違ったという。朝、たとえば100円を基準に必要な金額を訊いた場合、寛信は「さらにあと70円要る」といくらか余分に残るように多めに応え、一方の晋三は所持金を申告して基準の100円に不足しているだけの金額が必要だと言うのだ。だから、晋三は商社勤務は向かず、ましてや政治のお金なんかを差配するのには困るのではないかと気を揉んでいると言う。政治家という職業柄、場所が場所だけに、今これだけある、とはさすがに言えるものではない、ということだ。
だが、こうした幼児期の逸話は掘れば尽きぬことなく湧いてきたが、晋三の思想や理念の成熟を、鮮やかに脚色するほどのものは、ついぞ耳にすることができなかった。晋三と直接会った多くの人にとっても、それは同様だった。晋三は実に人間性を描きにくい政治家であるように思えた。
とりわけ、その政治信条や理念の原型を垣間見せるような、個性の臭気をプンプンと発散させる青年期の「核」が、ウメの記憶をもってしても見出せないのである。
苦心の末に、政治家としての晋三の外交意識の原型のようなものを見つけたのは、やはり彼の著書のなかでだった。
『「保守革命」宣言』で、晋三はみずから「変革を自己目的化しては絶対にいけないと考える。変革という言葉それ自体に酔ったり、それを自己目的化するということがあっては絶対にいけない、と考える」と書き、そうした意味で「私は明らかに保守主義者であることを自負しています」と宣言している。
「変革を自己目的化しては…」とは、「改革」というスローガンを声高に叫ぶ小泉内閣のもとで〝台頭〟した晋三にとっては運命の皮肉に聞こえなくもない。
それはさておき、晋三は今からちょうど一〇年前に書かれたこの著書のなかで、青年期のこんな話も開陳している。
自ら語っているのだから、それは多少は誇らしげであって、少なくとも自身が「信ずるところ」が大きいのだろう。
そうだとすれば、それは晋三みずからが「見せたい姿」であるわけで、自身によって語られる逸話として、それこそ強烈な自負に裏打ちされたものだと見ることができるだろう。
それに、ウメの口からさえ若き日に「政治家向きであると思わせるタネ」さえほとんどのぞかせないのだから、本人の口からとはいえ、政治意識の萌芽が語られているのは何よりも貴重かもしれない。
私がそうした保守主義というものを考えるに至った経緯のようなものについて、触れてみたいと思います。
私の高校時代は、丁度七〇年安保の時代でした。当時は、「革新」ということが殊更に持て囃された時代ですが、そういう中で、「進歩的文化人」といわれた人達に対しては、むしろ何となくうさん臭いものを当時から感じていた、というのが正直な所でしょうか。彼らは、単純な「善玉」「悪玉」図式でもって、当時の政治を盛んに論じていました。しかし、世の中そんなに単純なのかな、ということをいつも思っていたわけです。
晋三の〝告白〟を信じれば、これは東京の私立・成蹊高校に通っていた時期の話になる。
たまたま、私の父も祖父も政治家だった。しかもそのいずれも、その人たちが最も打倒しなければならないとしていた「当の相手」でもあったわけです。自分としては父も祖父も、そんなに「悪人」だとは思わない。それなりに、この国がどうあるべきか、ということを真剣に悩んでいた。むしろ真摯な一政治家でさえあったと思うんです。それをきわめて明快に「善玉・悪玉論」で片付ける人達に対して、人間とはそんな簡単なものではないんではないか、と思わざるを得ませんでした。
同じ著書のなかで、晋三はドイツの政治学者、マックス・ヴェーバーを持ち出して、祖父・岸信介の「政治家は結果責任」という信念を、ヴェーバーの『職業としての政治』に論じられた「責任倫理」と並べてみせている。
でも、人間社会を『善玉・悪玉』の対抗図式に落とし込む考え方にここで抵抗する晋三は、やはりドイツ人学者、カール・シュミットのもうひとつの有名な、捉え方次第では善か悪かの勧善懲悪の単純な思考図式にも並びうる「友敵理論」を知らなかったとすれば、それはいささか辛辣にみれば、晋三は都合のいい部分だけしか、第三者の意見で補強していないことになる。
西洋、東洋を問わず、先達の言葉で自らの文脈を補強するこうした言説は、えてしてそれを語っている本人の自己満足以上にたいして訴える力を持たないようにも思う。
係累が実際に起こした現実の政治行動を、歴史的な学者の論理で補強しようとするには、ちょっとお粗末な感じを受けるというのが、一有権者としての正直な感想でもある。
ともかくも、晋三の告白はいよいよここからが面白い。
倫理社会という科目があって、その先生なんかは、むしろ七〇年を機に、この安保条約は廃棄しなければならないとの考え方でした。クラスの雰囲気も同様です。けれども、私は詳しくはしらないけれども、自分の立場上、一言ぐらいは文句をいわなければならないと思っていた。そこで私は先生に質問したのです。「安保条約を廃棄しなければいけないと先生はいうけれども、もちろん条文をお読みになっておられるんですね」と。
実は私は、その段階では条文を読んでいなかったのです。ところが、先生の顔色がサッと変わって、岸信介の孫だから読んでいると思ったんでしょう。だから変なことはいえないと思ったのか、きわめて不愉快な顔になって、突然安保条約から話題を変えてしまったのです。私としては、「何だそんなものなのか』と思う。何となくうさん臭いと思っていたものが、そこで決定的になってしまったという次第です。
このいささかケレン味の強い告白を読んで、むしろ決定的な気持ちになってしまった。
実は、この告白の文脈を注意深く読み解けば、晋三自身は何も語っていないに等しい。
結局、寓話さながらのこの話の筋は次のようなことになる。
自分自身でさえ安保条約を読んでいなかった晋三が、祖父が絡んだこの条約については、「存在感」を見せねばと、教師に対して「読んでるのでしょうね」と〝ブラフ〟をかけた。
すると教師は、その晋三に対して「では、あなたこそ読んでいるのであれば、君の考えを述べなさい」とはいわず、見事に晋三のブラフにはまり、安保の話題を避けた。
その光景を見て、晋三は「うさん臭さが決定的になった」というけれど、教師をやり込めた晋三自身が、実はその段階で「条約を読んでいた」という〝手玉〟をもっていなかったことを誇らしげに活字にしていることそのものが「うさん臭く」感じてしまう。
晋三が、やはり同じ著書のなかで語っていた言葉を思い出してしまった。
「むしろ喧嘩して初めて生まれる本当の相互理解というものもあるわけです」
もちろん、教師との掛け合いと外交とは次元が大きく異なるものではあるけれど、もしそこに同じ人間が立ち会うとするのならば、その「芯」は共通することになる。
この本を著したとき、晋三は四二歳だった。
その年齢を「若干にして」ととるか、「その歳にもなって」ととるかは、人それぞれだけど、いずれにしても、齢四二の代議士にして自らの手で活字にする逸話にしては、あまりに「底が浅く」感じてしまうのは、未熟すぎるか、あるいは「現実政治をわかっていない素人」だからかもしれない。
四二歳の瞬間まで、高校時代からのこの「思想の継続」を保ってきた晋三が、五〇を過ぎ、いよいよ総理大臣候補として大きく名をあげている今の瞬間にもまだ、このいささか拙い感さえ漂うハッタリの思考を引きずってはいるわけは、絶対にないであろう―。
国民を代表する一国の総理大臣になろうとする人物なのだから、それぐらいの期待は持っていたいとも思う。
でも、そんな期待も、晋三を父の代から知る支援者たちの語りと、ウメの表現の貧しさとに重ねてみれば、やはりそれが希望にしてもあまりに淡いものかもしれない、という思いが募り、勝るのだった。
晋三とヨット遊びをしたことがあるという比較的近しい支持者の口からも、晋三の人柄を示すだけの、生き生きとした情景が語られることは限りなく少なかった。
古い世代から、晋三と同世代にいたるまで、「晋三」という存在はもっぱら、岸や晋太郎の延長でしかないようにさえ見えた。
たとえば、応接室の中まで晋三のポスターや後援会のパンフレットを貼りつけるほどの熱心な支持者にとっても、晋三を支持する理由は「昔」にあった。
かつて、村の若い衆が晋太郎の出馬を聞きつけ、あるとき晋太郎が住み込みで首相秘書官を務めていた渋谷・南平台の首相官邸まで駆けつけた。
そのとき、わざわざ玄関口まで出迎えた晋太郎は、彼らを岸に紹介した。
「今度、僕の選挙を手伝ってくれることになった方々です」
岸は気さくな雰囲気で歓待し、「それは頼もしい。晋太郎をよろしくお願いします」と頭を垂れた。
村の若い衆にとっては思わぬ大物の登場だ。それだけでなく、岸はなんと、うら若い見知らぬ者に「よろしく」と頭を下げたのである。訪れた者には忘れられない思い出となった。
話はそれで終わらない。
それから後、晋太郎の国会議員の勤続を祝うパーティーでのことだった。
金屏風が映えるひな壇のそばに、杖を持って座っていた岸は、パーティー会場の遠くにいたひとりに手招きをして呼び寄せるとこう言った。
「あんたー、心配しておったよ。あれ以来、一度も顔を見せんかったから。どうしておったのー」
岸はもう何十年も前に、南平台を訪れた「若い衆」の顔を覚えていたのである。その後も晋太郎の後援会活動をしていることを話すと、岸はことのほか喜んだという。
「そうか、それはありがとう。晋太郎を助けてやってくれ」。岸はそう繰り返し、幾度も手を握りしめた。
〈たった一度だけ会った自分のことを覚えていてくれた〉
その金屏風を前に岸とともに納まった写真を、この支援者は今も大切に飾っている。だが、うっすらと目に涙を浮かべたその口からは、ついに晋三の魅力を語る言葉はこぼれなかった。
晋三の代に至った支援者にして、いまだに岸と晋太郎への思慕が支えであるという状況は、岸や晋太郎の偉大さを示す美談というよりも、今となってはむしろ、政治家としての本質的な魅力が問われかねない晋三の〝貧相〟にさえ映った。
もちろん、晋三の親友の話などからは、学生時代の晋三の、飾らない日頃の人間性を伝える逸話も散見もできた。
たとえば、週刊誌ではこんな話も紹介されていた。
「大学4年の秋、こんなことがありました。安倍はあんなに裕福な家なのに、お小遣いは月5000円しかもらっておらず、よくアルバイトで小遣い稼ぎをしていました。たまにアルバイト代が入ると、六本木に行って焼肉を食べたりしたものですが、ある時、ロアビル前の外苑東通りを六本木交差点に向かって歩いている時、向こうから来た2人組の暴走族風の大男と安倍の肩がぶつかったんです。向こうが〝おい、お前!〟と因縁をつけて来た時、安倍が〝何だ!〟と凄い剣幕で怒鳴ったんです」
向こうはケンカ慣れしている暴走族で、こっちは成蹊大学のボンボンである。
「反射的にこれはヤバイと思った私は、〝おい、行こう!〟と安倍を引っ張っていこうとした。でも、彼は一歩も引かず、〝ふざけんなよ!〟と、なおも暴走族とやりあったんです。すると、安倍の迫力に、向こうが〝ふざけるなよ〟という捨て台詞を吐いて、引きました。ケンカ慣れしている奴らも、安倍が持っている独特の雰囲気に〝ヤバイ〟と思ったのでしょう。私が、暴走族と別れたあと、おまえ無謀なことをするなよ、と言ったら、〝どうしてだよ。あいつらの方がぶつかって来たじゃないか〟と言いました。彼の正義感の強さと、その醸しだす独特の迫力には、驚くと思いますよ」
(週刊新潮 平成一五年一〇月一六日号)
これは、秋保浩次という、晋三について書かれた記事や書物に親友としてたびたび登場す人物の話だから、決して、この逸話が「悪いもの」として紹介されているわけではないのかもしれない。
つまり、かなり親友のひいき目であることを割り引いても、この話から、「正義感の強さ」を嗅ぐことはできなかった。
むしろ、率直なところ、まるで、血の気の多い鉄砲玉そのものじゃないか、とさえも思えてしまった。
さらに言えば、〇五年の、朝日新聞によるNHKへの編集介入騒動をめぐる晋三の、自ら丸腰で表舞台に弾け出てくるかのような無防備さの原型さえ感じてしまう。
なぜなら、やはり同じ週刊誌には、さらに晋三の〝武勇伝〟が、いくつか「評価」の文脈で紹介されているのだけれど、そのどれもが、なんだか似ているような気がした。
これは、下関で後援会関係者からやはり聞いたことのある話だった。
平成5年7月4日、第40回総選挙公示。晋三はこの日、政治家としての記念すべき第一歩を踏み出した。
2年前に父・晋太郎を亡くし、弔い合戦に臨んだ晋三は、どしゃぶりの雨の中で初めての出陣式を迎えたのだ。
下関市上田中の護国寺。安倍家では、この寺の本堂で、選挙の第1階個人演説会を開くのが、父・晋太郎時代から続く習わしになっている。
翌5日の夕方、その初めての演説会に駆けつけた150人ほどの支持者を前に、晋三がまさに演説を始めようとした時、最前列に陣取っていた4、5人の右翼が口々に、
「この若僧っ!」
「引っ込めっ!」
と叫び始めた。
一瞬、支持者たちが凍りつく。
その時、「あべ晋三」と大書きされた襷を肩からかけていた晋三が、突然、
「何を言うか!お前たちっ、出ていけっ!」
とマイクを持ったまま大音声を上げたのである。
それは右翼ばかりか、支持者たちをもたじろがせる迫力だった。しかし、右翼たちは、気を取り直してまた反撃のヤジを飛ばし始める。
「選対の運動員が、これはマズイと、忽ち彼らを取り囲んでつまみ出してしまいました。晋三さんは彼らをにらみつけていた。東京のお坊ちゃんとばかり思っていた晋三さんの、あの怒声にはびっくりしてしまいました。凄い迫力で、スタッフが〝今後、こういうことはいくらでもありますから、あまりムキにならないでください〟と諭したほどです。晋三さんはただの若僧じゃない、これはどえらい政治家になる、とその時、確信しました」(支持者の一人)
安倍晋三は、こうして支持者の度肝を抜いて政治家への道をスタートさせるのである。
(週刊新潮 平成一五年一〇月九日号)
晋三が二九歳のときであった。
記事が伝える通り、政治家として第一歩を踏み出したまさにその瞬間が、怒声であったとは、これはやっぱり晋太郎の息子は、「ケンカタロウ」なのではないか、と少々、寒気がしてしまう。
路上で暴走族に絡む話もそうだし、右翼のヤジに正面から向っていく話も、それが確かに彼の一面しかあらわしていないとしても、でも、なぜか周囲がまともに記憶している話はそんなのばっかりだから。
だって、いつもの辛辣な論調からは珍しく、安倍晋三を決して罵ってはいない、この週刊新潮の記事でさえ、やんわりと、こう書いている。
頼もしく見えるその一途な姿勢も、周囲をハラハラさせるほどの危うさを同時に孕んでいるということらしい。」「それは時に、周囲にはエキセントリックに映るほどである。」と。
それは、後援会関係者や政治記者からさらにこんな話を引き出しているからだった。
政治部記者によると、
「昨年5月、サンデー毎日が、晋三氏が早稲田大学でおこなった非公開の特別講座で〝憲法上、小型であれば原爆だって(保有に)問題ない〟と発言したことをスッパ抜きました。そして民主党が、これを国会で取り上げたんです。晋3氏は非公開の講義内容が報道されたことを〝学問の自由を侵す看過できない問題だ〟と、早口で逆に批判しました。しかし、その怒り方は尋常ではなかった。〝過激派が録ったテープをもとに、マスコミは報道するのか〟と、事務所の中では、凄い剣幕だったのです。また、今年元旦の朝日新聞の社説で北朝鮮拉致問題を〝不健康なナショナリズムが目につく〟と批判されたことに、晋三氏は〝朝日は(北朝鮮から死亡したと伝えられた)8人を忘れてしまえと言うのか〟と噛みつきました。周囲から、いちいちマスコミと対立するのはよくない、とアドバイスされて矛を収めましたが、その怒り方は、表面的なソフトイメージとは、まるで違うものです」
(週刊新潮 平成一五年一〇月一六日号)
晋三が人前で露骨に激昂した例には、まるで「枚挙にいとまがない」という表現がピッタリ、とさえ思えるほどだ。さらに……
野中広務が幹事長代理をしていた平成8年夏、山口県知事選の推薦問題をめぐって山口県選出の国会議員が、党中央と対立したことがありました。野中氏と親しい吹田幌・元自治大臣が知事選出馬を表明したため、地元の国会議員たちが推す二井関成・元自治官僚に党の推薦が出なくなってしまったのです。吹田氏は一度、新進党に移った人物でしたから、二井氏に出る方が筋が通っている。この時、まだ1回当選の新人議員だった安倍氏は、ほかの議員と共に党本部に乗り込み、野中氏に向かって、〝なぜ(二井氏に)推薦を出さないんだ!〟と激しく食ってかかったのです
この武勇伝は地元では有名で、野中幹事長は思わず、「親父さんは優しい穏やかな人だったのに、息子は手厳しいな」と周囲に漏らしたほどだったという。
(週刊新潮 平成一五年一〇月一六日号)
関係者の間ではあまねく知られ、さらにあまた残されているこうした〝武勇伝〟は、当然、ウメが知らないはずはなかった。
決して、我が子同然に育てた晋三を悪くいうことのないウメにとって、こうした、刺々しいまでに角の張った気性をまるくまるく含めた末の言葉が、きっとかつて聞かされた言葉だったのだろう。
「だからね、北朝鮮の拉致問題でもね、自分がこうだと思って始めたらね、最後まで絶対やるわよ。拉致被害者の家族が仮に『もう結構です』って言ったってやっちゃうわよ」
ここまでこんな激しい逸話を並べたあとでは、さすがに我ながら、ウメの「『もう結構です』って言ったってやっちゃうわよ」という言葉が、なんともいえない現実感をもって迫ってくる思いがする。
ただ、こうした「激しさ」が他面では、堅牢なほどに頑固なだけでなく、芯の強さにもなるだろうし、または素朴な人柄を貫くことにもなるのだろう。
あえて厳しい目で見て、こうした「気性の激しさ」が、それこそウメの話にあったように、幼少期から二〇代、三〇代を貫いて今日まで来ているとすれば、やっぱりそこに「熟す」ことが欠如した場合の、考え方と行動のしかたへの一抹の不安は残る。
でも、それ以上に不安なのは、何よりも、これだけ生々しい逸話が数を揃えてなお、そこに晋三の「政治家としての適性」をどのようにして見出すことがでるのか、という一国民、一有権者としての素朴な疑問が大きく膨らんでくることだった。
正直、頑固、一途、根気、そして素朴さ……。
人間の性格を理解するための言葉はたくさんある。
だけれども、人柄を言い表す言葉や逸話のすべてが決して、政治家としての適性を指し示すものと同じではないだろう。
ウメがいう、晋三の「芯の強さ」も「素朴さ」も、あるいは友人たちも胸を張る、その「正義感の強さ」も、それは政治家である以前に人間としてごく当たり前に備わっていて欲しいものだと思う。
もちろん、当然のことが当然にできないからこそ、世の傑物はときに驚くほど自身にとっては地味で堅実な営為に「生きているだけ」のことがあるのも確かだ。
だからこそ、当たり前のことが備わっていることが、「政治家と他の職業とを隔てる、特筆すべき〝適性〟」ともいえないのではないだろうか。
ウメが挙げ、友人が挙げ、後援会関係者が挙げる、晋三の性格のどこからも、やっぱり「政治家としての適性」とでも言うべき「核」を見出せないでいた。
むろん、晋三自身が語ったものを紐解けば、そこには祖父である岸信介からの強い「思想の影響と継受」を意識していることは伝わってくる。
それは、やはり晋三自らが旗に掲げているわけだから、その〝岸イズム〟の捉え方と継承が当たっているか、間違っているかを外から問うことは野暮だと思うのだった。
晋三本人が「こう」と信じているものには、それこそ妻であれ母であれ、なんぴとたりともその善悪の判定をくだすことはできない、と信じている。
だから、晋三の生き方を決して否定するのではなく、仮にすべてを肯定したうえで、やっぱり、彼の生き様はこういえるのではないだろうかと思う。
少し、気取った言い方かもしれない。
それは、「擬装された原風景」ではないのか、と。
祖父・岸信介の安保改定の意義を誰よりも強く理解しようと欲して〝保守革命宣言〟し、あるいは父・晋太郎の外務大臣秘書官としての経験から、外交は譲歩だけではだめで、「喧嘩して初めて理解し合える関係もある」としてブラフをも辞さない外交意識を現実のなかに持ち込もうとする晋三。
きっと晋三のこれまでの「原風景」は、それこそ強烈なものであったはずだ。
たまたま現世に縁あって、何代も続く政治家の次男坊として生まれ、それも戦後日本という時代状況を大きく運命付けた「二人の傑物」を同時に自らの遺伝子の遡上に抱えるという〝宿命〟をまとっていることを自覚したとき、晋三はきっと、自らの「原風景」にどれほど鮮明な彩を与えることができるのかという大きな、そして避けることのできない挑戦の宿阿を感じたに違いない。
それは、間違いなく大きな不安をもたらしたはずだし、同時に負担にもなったかもしれない。
「昭和の妖怪」岸信介も、「悲運の政治家」安倍晋太郎も、決して色褪せることなく、何十年もの時間を経た今でもさらに強く発色せんばかりの状況は、晋三にとってはあまりに残酷にすぎるかも知れなかった。
すでに結果が定着しているそんな過去の亡霊に立ち向かおうとするとき、自らの原風景を素直に育くんだところで、勝ち目はないし、勝負にもならない。
でも、晋三が先代二人と同様に政治家という職業を択んだときから、それは歴史の土俵に乗ったことを意味するのだ。
幼少の頃から、「パパの跡を継ぐ」といって憚らなかったその言葉が、青年期に至りその意味を理解できる現実感を伴った段階に達したとき、本来ならば成長とともに、能力と精神の身の丈にあった育みをみせるはずの原風景に強烈なゆがみが生じたのではないだろうか―。
原風景は、「原体験」とは、実は異なるものだと思う。
こうもいえるだろう。
それは、原風景と原体験が、字面の違い以上に、決定的にその次元を違えるものだとも。
晋三はもしかして、岸や晋太郎の「原体験」を必死に、みずからの原風景に取り込もうとしてきたのか……。
晋三の著書に記された、執拗なまでの安保や外交への記述を傍らに、いずれの政策論評も、妙なほどに現実感を伴っていないように感じてしまう。
晋三が、自らの「保守革命宣言」を語るときの原体験としての基盤は、あくまでも祖父・岸信介の安保改定が叩き台だし、あるいは父・晋太郎が外務大臣時代に勤めた秘書体験が底にある。
その結果、「タカ派」「強硬派」とさえ呼ばれるほどの〝評価〟を受ける晋三の原風景は、かなり今日の社会情勢に照らせば強烈で、峻烈にさえ映ることになった。
晋三の発言や行動を喚起する激しいまでの「原風景」がそれこそ、岸や晋太郎の原体験を織り込んだうえに成り立っているとすれば、軌跡に残されてきた武勇伝の数々を理解できる。
ただ、巣鴨刑務所での三年三ヵ月におよぶ「生か死かの淵を彷徨った」岸の原体験や、学生時代に海軍に出向き、特攻に志願して「死への情景」をみた晋太郎の原体験を、晋三が持っていないとしてもそれは非難すべきことではなかった。
いずれの人間も、抗えない時間と状況のなかで体験を受け容れるわけだから。
でも、きっとひとついえるのは、はたから見た物事の大小ではなくて、原体験とは、受け容れる本人の「見識と許容性」によって決定的にもなりうるし、絶対的にもなりうるということだろう。
だからこそ、原風景はときに追体験をともなわなくても成立するし、他人の原体験を貪欲に織り込んでいった末に、「擬態された原風景」を醸成させることがあるのかもしれない。
でもそれは、原体験を欠如させた原風景だから、紛れもなく現実感の薄いものになってしまう。
もし、そんな原風景の特質からこんな言葉が出てきたとするのならば、初めて自らを納得させることができた。
「総理、もし北朝鮮が拉致を認めて謝罪しないならば、席を立って帰りましょう」
案外、マスコミを通じて日本全体にあまねく知られるに至ったこの言葉は、人々の口端にのぼるたびに疲弊して軽くなっていく「政治家の言葉」としては異例なほど対照的に、晋三の原風景のそれこそ「芯」にまで繋がっている、かなりしっかりと根の張ったものなのかもしれない。
もちろん、その言葉を発するに至った情熱そのものについては、また別に評価の対象となりうるものだと思う。
岸から数えれば、三世目にあたる政治家としての晋三は、「擬装された原風景」を育んだ、さまざまな意味で〝新しい政治家〟なのだろうか。
行き着く先の結果はみえないけれど、でも、この新しいタイプの政治家は、必ずある種の「確信」をもって進んでいくことが予想できた。
追体験することのできない「過去」の原風景を抱えるということは、そこに「失敗」の追体験も喪失することを意味するからである。
祖父と父の追体験から「成功」そのものも、「失敗」した部分をも想念として受け継いだ、いわば非現実的な原風景には、みずからの体験としての挫折が刻まれていることはないだろう。
しかも晋三は、小泉政権の登場という思わぬ展開によって一軍の、それも四番打者に据えられた「いまだ打たざる巨砲」である。いや、「いまだバットを振らざる巨砲」といったほうが正確かもしれない。
晋三がこだわりをみせた外交も、翻って日本国内の内政でも、晋三がこれまでにこれといった特筆すべき結果を示していないことに注目したい。
もちろん、結果はあとからついてくるものだし、それこそ晋三を引き立てた小泉純一郎にだって総理就任はおろか、任期中に郵政民営化への端緒をつけることに成功するとは、まさに先の見えない「結果」であったのは間違いない。
でも、「いまだ振らざる四番打者」であり、失政、失策がない政治家だからこそ、「ポスト小泉」をめぐる国民の人気レースではつねにトップの支持率を獲得できたのだと思っている。
もし、国民と向き合う安倍陣営が、あえて「振らない」戦略を採っているのだとすれば、それは当たりだ。
自民党の総裁候補者に名前が浮上しているに過ぎない段階ではそれで済むだろう。でも、現実に総裁に選出され、日本国総理大臣に就任したとき、「いよいよ打ってみろ」という声に対してどう応じるのかが見ものだった。
でもその期に及んでも、ホームランを打たなくても、なお総理の座は務まるものかもしれない。
歴代の総理大臣のなかでも、小泉純一郎のように、ポール際ギリギリの打球をホームランにしてしまったケースなど、数えるほどしかいないだろう。
「経済に弱い」「経験が足りない」「内政手腕が未知数だ」という、晋三を論じるさまざまな評判は、有力候補から総理に就任するときが来れば、それこそおさまりがつかないくらい沸騰するはずだ。
そのなかで、支持率を保つには、それはそれでいろんなやり方はある。
もし私が晋三の立場であったら、自らの存在理由を維持させる方法のひとつは、やっぱり決して「バットを振らない」ことだと思う。
手腕を見せろ、という声に応えるならば、きっと、バントを構える。
バントであれば、仮に政策課題というランナーを次塁に進めることに成功したとしても、そして失敗したときでも、決して決定的な〝傷〟にはならないからだ。
さらに、うまく来た球がグラウンドに転がりさえすれば、「妙打」がゆえに、「妙案」という手腕の評価にさえつながりうる。
それに、どんな場面でどんな球を転がすにしろ、ウメのいう、「現代女性のヤワ好き」が、表舞台に立ってからの晋三の人気を支えているし、これからも支えていくことは間違いないだろう。
晋三が幹事長に就任した直後、〇三年の秋に『サンデープロジェクト』というテレビ番組で『新潮45』という月刊誌の女性編集長がコメントしていた「イケ面ですから」は、端的にウメの観方を象徴してもいた。
「イケ面」「プリンス」―
でも、この特殊な原風景を抱えた政治家を、そのイメージだけで受け容れるわけにもいかないように思う。
晋三が自民党総裁選で総裁となり、国会で首班指名を受けて総理大臣となったのちにも、この「擬装された原風景」から紡ぎだされる思考と政策は慎重に注視していかなくてはいけない。
いずれにしても、晋三が新しいタイプの政治家であることは間違いないのであって、それは国民にとって未経験のものであるから。
もしかしたら、小泉純一郎以上に、その本質を捉えようと努力し、理解するのには時間と困難を伴うことになるかもしれない。
特殊な原風景を抱えた人間は、ポストによって大きくその人と成りを変化させる可能性がある。
そして、変化の結果がどう転び、どう展開するのかは、それこそ未知数なのだ。
背景に潜む頼もしさと怖さと
以前、岸信介が、記者から尋ねられた瞬間、当意即妙に答えたとき、伊藤整はそこに切れ味鋭く含蓄と意志と、それに深謀遠慮があることを見抜いたが、この岸のDNAを引き継ぐ晋三はどうか、と意地悪なことを考えてしまう。
炊きつけるような言動で、考える躊躇なく相手の〝思わぬ〟言葉を引き出してしまう現代のインタビュアーといえば、やっぱり田原総一朗だろう。
捜してみると、田原と晋三との「憂国対談」なる記事が見つかった。
週刊朝日に記事が掲載されたのは、〇三年一月の号だから、晋三がまだ幹事長になる前、官房副長官として拉致問題で一躍脚光を浴びていたその最中のことである。
果たして、いかなる「当意即妙」な丁々発止が展開されているのか―。
田原 さて、これまで日本の北朝鮮外交は、たいへん弱腰だったと言われます。最大の理由として、朝鮮半島を植民地にしていた時代の反省や心の負担があると思います。戦後派の安倍さんはどう考えますか。
安倍 日韓基本条約を結ぶときの両国のやりとりを見ていますと、日本側は相当強く主張をしているんです。当時、朝鮮半島を併合していた時代のことを知っている人たちがたくさん役所にいたわけですが、歯を食いしばって国益のために頑張った。そういう姿を忘れてしまったのでは、と感じます。
田原 なるほど。
安倍 個人の情緒は断ち切らなければいけないと思うんです。世界中、国と国との関係ではいろんなことがあります。どっかで終止符を打たなければ次の一歩は踏み出せないのに、これまでは、変に自分の情緒的な良心を満足させようとしているかのごとき坑道もあったと思います。アジア外交全体に言えるのですが、いちばん大きな問題点は〝抑制された外交〟なんです。
田原 どういうことですか。
安倍 自らの主張を抑制するんですね。抑制しながらなんとなく円満に解決する。それは国益をちゃんと主張していないということなんです。なのに何か実績を残したかのような錯覚に陥っている。『北朝鮮が暴発するかも』と言いながら抑制するのは同じ文脈で、向こうは暴発をカードとして……。
田原 脅しに使いますね。そこを聞きたい。なんで外務省は抑制しながらの外交にこだわったんですか。
安倍 弱腰に見せることがあっても、抑制するときがあってもいいと思うんですが、ずっと抑制しっぱなしですからね。『暴発するかもしれない』と言うなら、ほんとに暴発するのかどうかを詰めて考えたことがあるのか。そういう情報を取ろうとしたことがあるのか。暴発に備えて努力をしたことがあるのか。それを問いたい。
これは、四ページにわたる記事のごく一部だけれど、このインタビュー記事を読んで、やっぱり会話のなかにこそ、用意されていないひとの思想は色濃く滲み出るものなのだな、とため息がこぼれた。
二人の議論は、もちろん聞き手と話し手という立場上、晋三の語りは非常に饒舌で、田原の審問を丸め込んでいるように見えるけれど、この議論はまったく噛み合っていないようにしか読めなかった。
つまり、「政策」を訊きだそうとする田原の絶妙なアプローチに対して、晋三の回答は、ともすれば「信念」の陳述に終始しているようにみえる。
これが、伊藤が取り上げた岸の言質とどこが違うのかと考えれば、岸の発言は、相手の意図と言動を取り込んだ上で、そこに自らの立脚点を築くのに対して、晋三のそれは、相手の質問の、いわば射程を見定めることなく自らの「思うところ」を堂々と表明するところにある。
安倍晋三という政治家を好きでも嫌いでもなく、むしろまったく興味を持っていない「無党派」として彼のことを書いているわけだけれど、本音をばらしてしまえば、こういう書き物だから、いささか辛辣なトーンで捉えているきらいは多分にある。
だから、あえて、晋三の言動を受ける一般国民のひとりとしては、晋三が「信念語って政策語らず」だともいうわけだけれど、それは裏を返せば、もちろん晋三という政治家の評価すべき部分にも転じるのは確かなはずだ。
信念さえはっきりと明示できない政治家が数多い昨今の状況のなかで、みずからの外交にかける熱意をこれほどまでに全面に展開している晋三が、稀有な存在であることは疑いがない。
それにしても、である。
安倍晋三という政治家がとりわけ頻繁にメディアに取り上げられるようになったきっかけは紛れもなく、小泉訪朝以後だけれど、これほど「国益」と「外交」というふたつのキーワードが惜しげもなく流布された状況を、ほかには知らない。
つまり、それは晋三が官房副長官から自民党幹事長に大抜擢され、その後、内閣官房長官に就任するまでのわずか数年の間に彼が応じたインタビューなどを見れば、まず例外なく、そのふたつの言葉が語られないことはないほどだといっていい。
国益と外交が大切だということは改めて認識させられたけれど、同時に多用されすぎているためか、それらの言葉があまりに空疎にも見えてきてしまう。
晋三はよく、「対話と圧力」という言葉を好んで使う。
手元に積みあげた、彼の著作から雑誌記事までを渉猟したとき、はたと気がついた。
そして、いよいよもって、やっぱりか、とも思うのだった
彼の外交姿勢というのは、もしかすると、第二次大戦後の東西冷戦時代にずいぶんと流行った「ゲーム理論」そのものじゃないか、と。
ゲーム理論といっても、さまざまに枝分かれしてそれほど単純ではないけれど、あっちの国がこう出てきたら、こっちはどう出るか、という、敵と味方に別れたシミュレーションで定式化して、さらにその蓄積を、実際の外交過程にどう持ち込むかといろいろと試行錯誤していた時代は確かにあった。
おそらく、それがもっとも遅れていたのは長らく米国の庇護下にあった日本だし、ゲーム理論の発祥国だった米国からそれを日本に持ち込んだ第一人者のひとりが、第三次小泉内閣で、初当選にして入閣を果たした猪口邦子元上智大教授の夫、東洋文化研究所教授の猪口孝だったと知れば、なにやら妙に因縁めいても聞こえよう。
でも、わざわざ「理論」うんぬんを持ち出さなくても、相手がどうでたらこっちはどうでるか、というだけの話だといえば、それまでだ。
けれど、ただひとつ気になるのは、いわゆる「ゲーム理論」が華やかに興隆して、有効だと信じられていたころは、米国とソビエトを軸に、文字通り東西が二極化していた時代だった。
東西の冷戦崩壊後に、敵―味方の軸がより多面で多層になってしまった今、「対話と圧力」という発想が、対北朝鮮という一点突破外交を超えて、世界全体での多層外交の場面においてどれだけ有効なのかは、不安が募る。
米国、北朝鮮、国益、外交と、晋三が繰り出すキーワードが、「乏しい」ものに見えてしまうのも、もしかすれば、そればかりを杓子定規に求めすぎるメディアの短絡さが大きな原因であることは確かだ。
でも同時に、やっぱり晋三が、いざ語りつくさんとばかりに饒舌であることも事実だと思う。
軸が多極化して、国際政治上のプレイヤーの国益が多層的に絡み合う外交状況が現実だとすれば、「対話と圧力」という単純すぎる理論軸がどこまで有効なのかは、もちろん素人にはわからない。
ただ、そんな明快すぎる武器は国民には分かりやすく、ともすれば耳障りよく響くから、その「国益と外交」「対話と圧力」というキャッチフレーズだけで取捨と淘汰の政治を実行されたら、たまらない。
ウメが施設に入ったことでもわかるように、人間には病気もあれば、老いもくる。
社会福祉の政策についても、語って欲しい、というのが国民としての本音でもある。
でも、晋三が社会福祉について語った記事を探すのはかなり困難を極めた。
ほとんど見つからないのだ。
だから、次の文章を見つけたとき、なんだか救われた気さえしてしまった。
聞き手はやっぱり、田原総一朗だった。
〇四年のインタビュー当時、晋三は幹事長を辞任し、雌伏のときを過ごしていた。
その記事には、刺激的な見出しがつけられていた。
「安倍晋三 総理になれば日本をこう変える」
田原 年金についてはどうですか。日本で年金制度が整ったのは1973年、福祉元年といわれていますが、このときには制度の前提がふたつあった。ひとつは経済が発展する。もうひとつは、人口が増え続ける。今まさに、この前提がふたつとも崩れたわけです。だから、福祉を軽くし、税金を重くする『低福祉、高負担』にならざるを得なくなった。さらにもうひとつ大問題がある。国と地方の借金がついに700兆円になってしまった。安倍さんがリーダーになったら、必ずこの問題を真っ正面から迫ってきます。さあ、これをどうしますか。
安倍 80兆円の国の予算に対して、税収は40兆~50兆円しかない。このままでは国がもたない。小泉政権はそこに手を着けようと舵を切ったわけです。2003年度は、十数年ぶりに補正予算を組みませんでした。2010年代の初頭までにプライマリーバランスを黒字にするという目標に向かって努力はしていますが、まだなかなか上手くいっていない。ではどうするか。ひとつはとにかく景気をよくして税収を増やす。もうひとつは、増税です。
田原 消費税の引き上げですね。
安倍 しかし、いままでは消費税を上げるときには所得税を引き下げてバランスをとってきましたが、今度はそれができません。非常に政治的に厳しい問題です。
田原 小泉さんは自分の在任中は消費税を上げないといっています。彼はわかっているんですね、ここで消費税を上げると、せっかく行政のムダを省こうとしているのが水の泡にされてしまうことをね。だけど、小泉さんの次の世代では消費税を上げざるを得ないですよ。
安倍 そのときには、目的を明確に提示すべきです。社会保障のため、年金、医療、介護のために消費税を使いますと。かつて1970年代に社会保障に使うお金は3・5兆円に過ぎなかったのが、今ではおよそ84兆円~86兆円にのぼります。これは一人あたりの給付がずっと増えてきたのが原因です。しかし2025年には152兆円にのぼる見込みです。これは、一人あたりの給付が増えるからではなく、給付の対象者が増えてくるからなんですね。給付があれば、負担もある。したがって、人口が減っていくなかで、税収を増やさざるを得ない。そのためには集めた税金は社会保障に振り向けますよ、ということをきちんと国民に説明していくことが大事だと思います。そして、そのときにはキメの細かい消費税にしなければいけない。ですから、10%を超えるのであれば、食料品などの非課税項目も設けないといけないでしょうね。
(『月刊現代』二〇〇四年十一月号)
このインタビューを前にして、安倍は参院選での敗北を受けて、幹事長からいったん、幹事長代理へと〝降格〟している。
もちろん、〇四年の参院選を、当の小泉純一郎は決して「敗北」とみずから呼ぶことはなかったけれど、幹事長が降格したという事実は、自民党内部での選挙結果に対する認識の、妥当ともいえる現実の体感温度を示していた。
活字になっているものを紐解く限りでは、晋三が幹事長に就任した〇三年以降から今までで、外交や憲法、靖国といった「信念論」のほかに、「政策」らしきものを語った詳細なものでは、これが唯一に近いもののようにみえる。
長年、政治家を相手に切り込み論客の先頭を走ってきた田原が、晋三につきつけたあいくちは、さすがに鋭い。
晋三が幹事長になった〇三年の時点で、彼が将来の総理大臣候補として浮上したのは確かだったけれど、〇四年の幹事長代理にいったん退いた時点で、いったいどれほどのひとが、〈小泉の次が安倍〉であるという目でこの男を見ていたのかは、疑問である。
〈いずれは、若手のホープとしてリーダーになるかもしれない〉
……そんなところではなかっただろうか。
まさしく晋三本人がそう考えていたからこその妙味が、このインタビュー記事に顕れているように感じてしまう。
さもなければ、よほど口が〝滑る〟のか……。
先にあげた、伊藤整が岸信介を論じた記事の、その真似事だけでもしてみれば、この記事から、晋三の人間性は、次のように分析できるのかもしれない。
田原は、将来の社会保障政策を推進するうえでは、もはや財源不足が否めない、と相手が否定できない論理を土俵としてサッと敷き、そのうえで、「安倍さんがリーダーになったら、必ずこの問題を真っ正面から迫ってきます。さあ、これをどうしますか」と呼び込む。
これに対して、晋三は「ひとつはとにかく景気をよくして税収を増やす。もうひとつは、増税です」と、イヨーッとばかりに、いともたやすく田原の土俵に上がっていく。
そして、上がっただけでなく、おそらく田原がもっとも引き出すことを狙っていたであろう、「増税」について自ら言及するのである。
増税を語れば選挙に負ける、というのが戦後日本の鉄則ともいえることを考えれば、果たしてこのインタビューは、将来に向けて避けえない増税論をやんわりとサブリミナルのように徐々に国民の間に浸透させることをねらった台本のあるデキレースなのか、とさえ勘ぐらせる。
だけど、そうは思わない。
なぜなら、田原が続いて、「だけど、小泉さんの次の世代では消費税を上げざるを得ないですよ」と、次の総理にとってこの増税が政策課題になることを迫って、そこに晋三を重ねようとしたとき、晋三はこう応えている。
「人口が減っていくなかで、税収を増やさざるを得ない。そのためには集めた税金は社会保障に振り向けますよ、ということをきちんと国民に説明していくことが大事だと思います」
おそらく、田原が言外に匂わせているのは、あなたが総理になったら増税はやるのか、やらないのか、という趣旨であろう。
もし、政治家として普通の感覚を持っているのであれば、そこは自らの言質をとられることを嫌い、田原の突きを、スッと脇へ逸らすのがまっとうだということにもなろう。
ところが、晋三のこの言葉は、「自分が総理になったら」という言葉さえないものの、田原の「増税やりますね」という一種、無謀なひと突きを素手で受け止めているようなものにさえ映る。
こういう場面で、ここまでの率直さに驚かされるのは、得てしてインタビュアーのほうである。
こちらが誘導する問いに乗ってきて、予想以上の言葉を繰り出す相手に対して抱く印象はたいがい、ふたつだと思う。
それは、「よほどの確信犯」か、「よほど脇の甘い人物」か、ということである。
晋三がそのどちらであるのかは、分からないけれど、伊藤が指摘した岸の発言と照らし合わせるならば、その言動の質の違いは、多少なりとも浮き彫りになる。
岸が、発言相手の真意と、そのねらいの広がりがどこにあるのかを考え、その問い口を受けてみせるその一方で、そこで一ひねりも二ひねりも、ヒラヒラと身をひるがえらせて再び正面に立ってみせるという〝芸〟を持っているのに対し、晋三は、相手が直球を投げればそれを正面に構えてがっちりと受け、そしてまた愚直なまでに球を遊ばせることなく、ピッチャーにその球を投げ返すという、いわば〝芸なき芸〟をみせるのだ。
乳母のウメが言った、「晋ちゃんはね、こうと決めたら、なんといおうとやっちゃうわよ」というその直球勝負の性格は、インタビュー記事を通じても、よくよく見て取れるような気がするのだった。
米国の政治家が好んで使う言葉に、「Read My Lips」というものがある。
直訳すると、「オレの唇を読め」になるけれど、日本語のニュアンスに一番近いのは、「行間を読む」になる。
晋三はいわば、こうした「行間を読む」必要のない政治家であるのかもしれない。
もとより、彼の言動には行間がないともとれるのだから、周囲の人間は、そもそも行間を読む余地がない……。
もちろん、そうした分かりやすい言動がこれまでの日本の政治家にはなかったのは確かだから、そこに政治不信の一旦があるといえば、晋三のそうした性質は決して非難されるはずはない。
北朝鮮の拉致被害者家族から厚い信頼を得たのもその言行一致の姿勢が好まれたのは確かだろうし、〇三年の幹事長就任後に一貫してメディアの世論調査で個人的に高い支持率を得てきた背景のひとつには、そうした「見えやすい発言」と「わかりやすい行動」が、代議士新世代を強く印象付けてきたから、という理由もあるのだろう。
そして、そのあたりは、晋三はまさしくみずからへの後継指名を下した小泉純一郎という男に通じるものがあるような気がする。
単純さはときに揺ぎ無い強さと力であり、そして、あるときは単純さは、歯止めの効かない怖さにも転じよう。
現実政治における有効な力とは、伊藤整がいうように、いかにも「アンビギュアス」なものなのかもしれない。
晋三のもつ単純さが、どちらに展開するのか、それは彼が総理大臣という権力を実際に握ってみるまでは想像もつかなかった。
そこが、安倍晋三という人間の頼もしさであり、怖さかもしれない……。
「次」を狙う政治家が恐れるのは身内の話に他ならない。確かに、それは常にもっとも生々しく、強烈であるはずだ。
悲しいかな、だからこそ、語り部は安倍家の外にいてはいけなかったのだ。
ウメは、そんな周囲の思惑など想像だにせず、週に一度、晋太郎の墓に参り続けていたのだった。ウメという女にとっての帰郷はきっと、政治の季節を貫いた愛の軌跡を固めようとする、最後の儀式であったのかもしれない。
晋太郎の墓所にしまわれた、墓参者の記帳ノートをめくれば、「危篤で面会謝絶」なはずの一月二二日に、確かに、久保ウメの名前があった。
〈偶然だろうか〉…それは、晋三の安倍家一行が墓参したのと同じ日だった。
そしてその三日後、ウメは〝封印〟された。
親子の別れから自殺未遂、企業家との交流までを孕んだ、安倍家の修羅と慟哭の様々を…何者かが封印した。
第5章
祖父を超える野心
北朝鮮から改憲へ
見事なる〝封印〟
何度目かに油谷を訪れたときだった。
山陰本線・人丸駅の前に数台停まっているタクシーは、そのときもせわしなくピストン輸送を繰り返していた。
でも、それもわずかの時間のことだった。
眺めていれば、一時間に一本ていどの列車から降りるのは、多くても十人がいいところだった。
それも、長門から下関に向うくだり列車から降りる人影はさらにまばらだから、おそらくのぼりとくだりが同時に駅に着いたとしても、ピーク時で二十人にも満たないだろう。
その光景は、間違いなく、過疎の村と呼ぶにふさわしかった。
おりる客を数えていても、そのほとんどは紛れもないお年寄りで占められている。
そんなお年寄りが小屋のような駅舎をくぐると、顔なじみのタクシーは阿吽の呼吸を計ったように、ひとかげにそっと近付いてくる。
それは優しい眺めだった。
「今日はどこへいってきたね?」
「下関に買い物にね」
客は行き先を告げない。
運転手も行き先を訊かない。
それでも、クルマは山のほうへ、湾のほうへ、岬のほうへと、人通りなどまったくない村のなかへ滑っていくのである。
懐かしいけれど、でも、それは間違いなく、初めてみる光景だったと思う。
この過疎の村のお年寄りのアシを支えているわずか数台のタクシーが村のなかを走れば、「ああ、あそこのばっちゃんが帰ってきたな」
「じっちゃんがどこかへ出かけるのかな」
と、およそひとの動きが手にとるようにわかるのだ。
それは素敵なことだった。
仕事で、地方の、それこそ「さびれた」という言い方が決して大げさじゃない場所を訪れることは数多くあった。
けれど、北海道の湖畔でも、滋賀の田園のなかでも、沖縄の離島でも、運転手が客の顔を見ただけで自宅まで連れ帰ってくれるなどという光景はなかなかみられたもんじゃなかった。
小さな村が名目だけではなく残っているから可能になる、そんなひととひとの結びつきがある、それが油谷なのだろう。
同時に、客を乗せる運転手のほうの、平和で安心しきった表情を見れば、そこにはほとんど見知らぬ客など訪れることがない様子もみてとれた。
大阪や東京のような大都会でノルマ達成に凌ぎを削り、かといって客まかせの営業ゆえに、プレッシャーから精神だけをすり減らして目だけ血走った様は、そこにはない。
油谷にあるのは、客をみた瞬間に、「あそこまで」「ここまで」と瞬時に、行き先を了解する、頼もしさと、そして、自負までもがのぞいていた。
だから、油谷を取材で訪れるたびに、まずタクシーの運転手に行き先の名前を告げると、驚くべきことに、訊ねた人物が今日は家にいるとか、いないとか、そこまで分かってしまうのだ。
それがお年寄りであれば、ほぼ百発百中で当たっているから、怖いぐらいでもある。
たしかに、駅に送るも、駅から送るも、ほぼタクシーがそのすべてのアシの需要を担っているわけだから、それは当然だった。
日本海の小さな小さな村の、その小さな掟といえば、それは、この村から生まれた安倍家という政治家の名誉を汚さないこと、ぐらいなのかもしれなかった。
そして、ウメが〝封印〟されてしまったのも、もしかしたらそのあたりの村の掟と文化に小さな因を持つのかもしれない。
政治家の秘書に、その政治家の出身地の人間が多いのはよくあることだと聞いていた。
多分に漏れず、晋三の父、晋太郎の秘書も、この油谷周辺の人間が多かった。
ウメもそうだし、それに永田町でどっぷりと生々しい政の前線に立ってきた、松原隆や奥田斉といった、まさしく安倍家の旧家臣団は、ここ油谷の出身者で占められていた。
男も女も、油谷の村を出たものが安倍家を支えてきたのだ。
そのなかに、ウメと同年齢の、もうひとりの女性がいたという。
その女性を捜していた。
ウメと同様、やはりその女性もいつの頃からかはわからないけれど、岸信介のそばに仕えていたという。
もちろん、愛人だとか妾だとか、そんな下世話な話の主人公として捜していたわけではなかった。
長く、岸信介の寵愛を受け、永田町の表にも裏にも通暁した老練の人物が、こんなことを言っていた。
「そうそう、岸さんのところに行くと、久保ウメさんがいてね。それで、もうひとりアマノさんというひともいたんだ。久保さんとアマノさんが岸さんの身の回りの世話をしていてね、一度、二人への手土産に帯どめを届けたことがあったかな。ああ、あの時は、娘の洋子さんにも手土産を持っていったんだ。アマノさんはどうしてるかなー」
アマノさん!
ウメの口からその名前を聞いたことはなかったけれど、やっぱり、ウメが入った施設のある長門古市駅前のタクシーの運転手から、その名前を聞いたことがあったのだ。
「ウメさんと一緒に、ずっと岸さんのところにいたアマノさんというひとが岬におるんと違うかな」
だから、村のタクシーのピストン輸送がひとしきり終わり、その数台すべてが駅前の営業所に戻ってきたのを見計らって、駅舎の脇のコンクリートの石段に座っていた腰をやおら上げた。
「運転手さん、岬のアマノさん、ご存知ですか?」
もちろんだった。
クルマは数分後には、岬へむかう山道を飛ばしていた。
対向車はまったくこない。ひとが通ったときだけ、この村の空気はわずかに振動を伝えるのだろう。
前から感じていた、この村の「牧歌的」な印象を変えなくてはいけないな、と思った。
ここは、やっぱり「孤立した」村なのかもしれない。
でも、いまや過疎と若年人口の減少で、油谷湾の水面同様に静かな雰囲気をたたえるこの村も、決して現在のみかけのような安寧をむさぼってきたわけではないのだろう。
この場所は、こう記されていた。
毛利氏は最大勢力時、安芸、周防、長門、備後、石見、出雲、隠岐の七ヵ国に加え、備中、伯耆の一部を支配し、石高百十二万石の大大名だった。だが、慶長五(一六〇〇)年の関ヶ原の戦で西軍についたため、徳川幕府によって、周防、長門の防長二国に削封されてしまった。それらの負担は直接防長二国の百姓への重税となってはね返ってきた。
(『大往生の島』佐野眞一)
のちに百姓たちの一部は、農兵を組織し、そしてそれが有名な高杉晋作の奇兵隊に吸収されたこともあったのだろ。
そして近代、長州はまさしく尊皇攘夷運動の中心となっていく。
農兵とはいっても、今となってはその姿を想像はしにくいが、戦後に生まれた世代にしてみれば、その姿は八〇年代に流行った、ハリウッド映画のベトナム戦争ものにその姿を重ねることができる。
農兵とはつまり、一般農民が武装して戦うわけで、それは今風にいえば、聞こえはよくないけれど、一種の「ゲリラ」ではなかったか。
もちろん、そこには戦うべき目的があったわけで、農民をして武器を持たせるに至った状況が、もとより平和な時代であったわけはない。
そして、かつての時代、奇兵隊を率いた高杉晋作から一字をとって名付けられたといわれる安倍晋三という代議士がこの地の血をひく者であることに今一度思いを馳せれば、なんだか、晋三の放つ積極性が、よくいえば「意欲的」、裏を返せば「戦闘的」とも受け取れた。
晋三はかつて、こうした自らの名前にも絡んだ幕末の志士たちについて、司馬遼太郎の作品に絡め、こう語っている。
もはや聴くほうも話すほうも、「北朝鮮問題」「外交」ばかりが溢れる晋三のインタビュー記事のなかでは、この歴史上の人物を語ったものは異例中の異例ともいえる。
なにしろ、晋三の歴史認識を鋭く示すものといえば、それは「安保」と「北朝鮮」しか、国民にはともすれば見えてこないようにも思うわけだから。
私は山口県出身の長州人ですから、高杉晋作の生涯を生きいきと描いた『世に棲む日日』がもっとも好きですね。短命の人生でしたが、その生き方には親近感を覚えます。その次は、戦国時代、大阪城の攻防をめぐって命をかけた激しい戦いが展開されていく『城塞』です。それぞれの登場人物が人間味豊かに描かれていて、ぐいぐい引き込まれてしまう。それと蘭学者であり、明治陸軍を設計した大村益次郎の生涯を描いた『花神』、そして項羽と劉邦の戦いを描いた『項羽と劉邦』でしょうか。
司馬作品のなかで人物として面白いという意味で共感するのは、やはり高杉晋作です。時代に求められてさっそうと登場し、時代が動くとともに退場していく。ある種の潔さやふてぶてしさがいい。藩政府から追われている時に、愛用の折り畳みの三味線と芸者を連れて、〝三千世界のカラスを殺し、ぬしと朝寝をしてみたい〟という都々逸を歌う余裕を持ちながら、時代をリードしていった。彼の時代の先を読む力や、決断したら断固として実行するという精神面を司馬さんは、まるで今、高杉晋作が生きているように描いています。『竜馬がゆく』も読みましたが、坂本竜馬はアウトサイダーで理想主義者。新しい日本をつくるという構想力に優れていた。高杉晋作は大陸浪人的な性格を持ちながらも忠義を大切な価値観とし、藩の組織を動かす力も気構えもあった。今の日本の状況を見ると、この高杉晋作や神格的な力で人を動かし、明晰な頭脳で物事を組み立て実行していった西郷隆盛のような人物が必要でしょうね。
(「国民作家 司馬遼太郎の謎」)
「時代に求められてさっそうと登場し、時代が動くとともに退場していく」という言葉は、なんとも示唆に富んでいる。
この晋三自身の言葉はまるで呼び水のように、自らの今立つ場所を予言していたとは言えないだろうか。
まさしく、この二つの予言は当たったのだと、思う。
小泉政権下、「時代に求められて」晋三は脚光を浴びて登場した。
そして、総理を目指し、そのイスに座ろうとも、いずれは「時代が動くとともに退場していく」。
政治の世界に限らない、この普遍の摂理ともいえる人間社会の人生の機微を、晋三が高杉晋作の人生と重ね合わせて「了」とするならば、いよいよこれは、晋三が政権を握ったらすごいことになるな、と確信してしまう。
それは、激しいことになるな、という意味だけど。
「短命の生き方でしたが、その生き方には親近感を覚えます」
そういう晋三の言葉を、政権という生命に置き換えれば、「短命」「退場」という二つの隠喩を知る晋三が、なりふり構わない政権運営を執ってもおかしくないと思うのだ。
ウメも言っていたではないか。
「一度、こうと決めたら、絶対やっちゃうわよ」と。
「拉致の家族のひとたちがもう結構ですって決めたって、やっちゃうわよ」って。
だから、怖い……。
自らの運命に対する決意と覚悟のある人間を止めることは、きっと難しい。
郵政民営化の是非にすべてをかけた小泉純一郎を誰も止めることができなかったように、安倍晋三という政治家が総理大臣になって、みずからが賭けるべきすべてを定めたときにこそ、この政治家は強さを増すに違いない。
でも、もちろんそれは、政治家としてはまっとうすぎるほどの、求められる道であるというのも確かだ。
総理のイスをまるで、自治会の回覧板のように廻してきたのが、これまでの自民党政治だったわけだから、それと決別した小泉政治の「政権」が、次の〝禅譲〟への単なる形骸化した過程ではなくて、政策の実現を柱に据えた本来の機能を取り戻したのも一面では間違いない。
一般国民が知りえる政治の裏面史が、いつも、総理のイスを誰に〝譲るか〟の禅譲裏史になってしまって、掘り起こされるのが総裁選の舞台裏の話であるというのも、いかに日本の政治文化が貧しいか、を示しているようなものだった。
晋三の係累で、岸信介の実弟にあたる佐藤栄作がまだ首相だった頃の話―。
次期総裁選に関し、総理から重大な話があった。総理「君のところへ、福田君から票読みの表が来ているそうだが、これは秘密にしておいて下さい。この問題については、竹下(官房長官)も大津(秘書官)も信用できないから」とのこと。
角福戦争は熾烈なものになっているが、佐藤派の大勢は、総理の意向に反して田中支持。幕引きを託した竹下官房長官も、総理側近の大津正氏も、総理の意向にそむく形になっている。佐藤政権の樹立、その長期化に中心的役割を果たしたこれらの人びとも、次期政権については、独自の考えを持っている。総理の寂しい心中を垣間見る思いだった。
午後、一〇〇二号室で、千田君と引退声明を仕上げる。
夜、読売の渡辺恒雄、常盤恭一両君と「松山」でてんぷら。
(『楠田實日記』一九七二年六月六日(火))
こんな描写を、生々しい、政の華とさえとる人々もいるのだろうけれど、きっと世代の違いといってしまえばそうなのかもしれない。
この手の裏話に象徴される茶室政治を見せられると、いかにも鼻白んでしまう気持ちしか起きない。
それこそ、晋三が繰り返し咆哮する「国益」の一端など、この茶室談話のどこからも感じることができないのだ。
晋三が、長州の農兵をまとめた気性激しい高杉晋作に精神の流れを遡らせて、「いざ国益を」と手に槍もちて立ち上がるのならば、頼もしくも見えてくる。
それに、こうした茶室政治の反動としての小泉政権であり、その延長での安倍政権であるならば、そこに「五十五年体制への反動」としてのひとつの脈は感じられた。
どんなに、ミヤビでツヤヤカな情景も、いずれは色褪せ、風雪とともに瓦解していく。
今は、まさにそんな時代の過渡期なのかもしれなかった。
住所もいわずに告げた「岬のアマノさん」の自宅の前にクルマが停まったとき、それを決定的に思い知らされた。
「あれっ、おかしいですね。このーあたりで間違いないんですけどね、あれっ、表札もないなっ」
岬の先のその集落は、多少なりとも駅前らしく整備された人丸駅前とはまったく風景が異なっていた。
わずか十分たらずクルマを走らせただけで、さらに時間の流れが遅い世界へと到着してしまったのだ。
昼間なのに、まるで村人が蒸発してしまったかのような人気さえ感じられない、そこはまるで、置き去りにされた漁村だった。
岬といっても、陸に上がればすぐに斜面へと連なるその集落は、細い道が傾斜を這うように登り、そこには、低い石段が短く、長く、刻まれていた。
運転手は、やおら携帯電話を取り出し、仲間に連絡して、場所を確認し始めた。
クルマを降り、朽ちた土塀の向こう、森のように生い茂った雑草のただなかに、まさに崩れ落ちんとするばかりの土蔵と家屋を見つけ、「いや、これは間違いないな」と、納得していた。
ひとのいい運転手は、かいがいしく動き、近所にひとを見つけて尋ねようとするが、もちろん人気のない集落でそれは叶うはずもなかった。
でも、半ば崩れた土蔵の姿を見れば、その家は地元でも〝有力〟だったに違いなかった。
そもそも「蔵を建てる」とは事業に成功したことの喩えであり、土蔵があるだけで資産があることを意味していた。日本ではある時期まで、土蔵があるだけで、ある程度の富と権勢を示していたのだ。
〝森〟の裏手にまわると、雑貨屋らしき店が見つかった。運転手と一緒に、店の引き戸を開けて声をかけると、電気もついていない店の奥から、ひとりの老婆が顔を出した。
訊ねれば、やはり見込んだとおりの場所が「岸さんに仕えていたアマノさんのお宅」であるということだった。
「でもね、もう亡くなってね。五、六年前になりますかね。たしか、娘さんがいたんですけど、その娘さんも津和野のほうに出て行ってしまいましてね……それっきりですからね」
ウメと同じように油谷から岸信介のもとへ出向いた「アマノさん」も、物故して久しかった。
アマノさんに会えれば、ウメの若い頃の仕事ぶりや生活なども聞けるだろうと、ほのかに抱いていた期待は、ここで潰えた。
でも、崩れ落ちようとする屋敷と土塀を前にして、満足してもいた。
この現実が、時間の流れにほかならなかった。
晋太郎が、黒いすすを吐き出す木炭車で選挙のたびに道中を通ったこの場所も、もうひとが消え、土塀は朽ち果てようとしていた。
ウメが言っていた言葉が思い出された。
「結局ね、(一票ほしさの)一票乞食から卒業できなかったのね……」
その一票乞食でさえ、今となっては成り立たなくなっていくに違いない。
この過疎の村では、きっと毎年、目に見えてその「一票」さえ、清らかに浄土へと召されていくのだろう。
ひとが世を去り、堅牢だった屋敷も塀も朽ちていく。
ひとがこしらえたものが、まさに重力に引き込まれるように土に還っていく、自然に抗わないさまこそ、美しい風景なのかもしれない。
岸信介も去り、アマノさんも去り、そして今、ウメも消えた。
時間の流れをつなぐものが、ひとの記憶だけだとするならば、その記憶もいずれは途絶えていく。
きっとそんな現世の掟に多少なりとも棹差す行為が、「語り」なのかもしれない。
わずかながらの、ウメの「語り」を多少でもいいから、遺しておかなくてはいけないと、運転手と二人で土塀の前に立ち、決意を新たにしたのだった。
そして、時間に抗うもうひとつの掟がある。
それは、野望という、「ひとの願い」にほかならない。
岸信介、安倍晋太郎、そして晋三と続く政治家三代を貫く、〝野望〟が今、ウメの記憶の封印とともに、成就しようとしている。
ノンフィクション作家の佐野眞一がもしこの岬を訪れたならば、きっとこんな風にいうのだろうか。
〈村を包んでいる奇妙なまでの生活感の乏しさは、国道整備と鉄路の電化という近代日本の発展図式から置き去りにされた、うらぶれた過疎の集落をみごとなまでに象徴し、そしてその素朴な静寂さの向こうに、ウメが生きた時代がたしかに終わりつつある時代の区切りという時間の淵をのぞく思いだった〉
そんな妄想で自分を慰めてみようとしたけれど、いやいや、ウメが語った少ない言葉の端々からうかがえた現実は、そんなきれいなものではなかったのだ。
〝岸王朝〟三代の夢と野心
〇五年暮れ、クリスマスムード一色の喧騒増す東京・六本木で、安倍洋子を尾けていた写真週刊誌の記者は、奇妙な場面に遭遇した。
安倍晋三の母・洋子のそばに寄り添っていたのは、数年前に辞めた、元秘書と思しき女性だった。
この女性は長く、安倍事務所の出納を預かってきた、金庫番としては永田町界隈では知られた人物である。
やはり安倍家の故郷である山口・油谷出身のこの元秘書は、女だてらに晋太郎の代から政のカネを仕切ってきた。
だとすれば、洋子と連れ添って歩いている姿はなにも不思議ではない。
しかし、二人の姿が奇異に映ったのは、この元秘書の女性もまた、洋子の強烈な個性に翻弄されたひとりとして周囲は見ていたからだった。
岸―安倍という政治家の暖簾を守る洋子と、家庭を預かり、長男・寛信と次男・晋三の養育を任されたウメ、そして事務所の経理を任されていたのがこの女性だった。
「安倍」という政治一家はこの三人の女が要諦を押さえていた。
ところが、この女性はその退職金の安さに不平を洩らしていた。しかも退職金の額は微々たるものなのに、「(その)税金ぐらいは自分で払いなさいよ」という洋子の言葉を最後に、安倍家との接触を絶ち、港区内のマンションで蟄居した余生を送っているはずだった。
晋三の後援者の間でも、「彼女も洋子さんには愛想を尽かしたようだ」という話が、密やかに囁かれていた。
件の女性が洋子と連れ立っていたとすれば、下衆の勘繰りにも花が咲く。
〈いよいよ、晋三の自民党総裁選出馬が現実味を帯びてきて、過去の話が掘り返されないように、接触して釘を刺しているのではないか〉
〈マスコミに嗅ぎ回られて、臭い話がでないように、念のために根回ししているのだろう〉
この女性と洋子が六本木で目撃されたころ、一方の永田町ではこんな話が流れていた。
「安倍さんのところに長くいた久保ウメさんが、危篤で面会謝絶のようだ。入っている病院は洋子さんしか知らない極秘らしい」
ウメが脳卒中で倒れたのは確かなようだった。だが、「危篤」「面会謝絶」「極秘」という、果たして流言飛語か現実かさえわからぬ話は、洋子の六本木での目撃情報とも重なり、ひとつの邪推を呼び起こした。
〈晋三を総理にするために、洋子が動き始めたな――〉
だからこそ、〇六年九月の総裁選は、晋三の戦いではないはずだ。それは、洋子の、王朝を三代に渡って生き延びた「女帝」としての、それこそ「ファミリー・プライド」を賭けた戦いになるに違いなかった。
七八歳を数える洋子にとっても、それこそ「最後のいくさ」ともなるだろう。
……国政にたずさわる者を送り出すためには自分の身を捨てても無我夢中でやる、ということに生き甲斐を感じておりましたが、それは、わたくしにも政治家の血が流れているからなのでしょうか。
(『わたしの安倍晋太郎』安倍洋子)
晋三に総理のイスが巡ってこようとする〇六年九月に向けて、洋子がかつて記したこの決意は、沸点に達しようとしているのではないだろうか。
今年は岸の生誕一一〇年目に当たる。
岸王朝のすべての歯車が、一世紀以上ものときを経て雪辱の〝総理奪還〟に収れんしていくように運命づけられていたとするならば、王朝の存亡は、九月の総裁選でその将来が占われることになる。
ほかでもない、女帝・洋子こそがそれを識っている―。姿を消したウメの残影に、私はそんな怨讐の誓いを感じた。
王朝といえば、小泉家を仕切っているといわれる小泉純一郎の姉、信子もまたときに王朝の女帝としても例えられるけれど、この信子がメディアの取材に一切応じず、みずからの書き物としてでさえ目に付くところには残さない「寡黙」ぶりなのに対し、安倍家の女帝は、いかにも饒舌だった。
しかるべき筋を通じた場合には、洋子はメディアのインタビューにもたびたび応じているようだった。私にはこの「しかるべき筋」というのがないものだから、公表された書物から洋子の言葉を拾うしかなかった。
ともかくも、女帝・洋子にしては、いささか人並みの不安感さえ覗かせているけれど、川奈に「おじいちゃまとの思い出」と言われれば、熱海会談のことを思い浮かべた。
毀誉褒貶の激しい岸の政治家としての人格で、こっぴどく岸を嫌う人々がまず間違いなく一致してあげものといえば、熱海会談だろう。
ところが、まさしくこの情景を、やはり児玉という虚実ないまぜの人物が語ることに示されているように、この熱海会談の内容の真偽については、これまた定かなものがなかった。
もし、日本に権謀術数史というものがあれば、紛れもなくそこに刻印を記すであろうこの熱海会談について、孫の晋三が、岸に直接尋ねたことがあった。
例えば、安保を成立させるために大野伴睦さんを説得した。その中で、大野さんに次の政権を渡すという念書を書き、大野さんを騙したと世間的にはいわれていました。そこで、その念書の件は本当なんですかということを、ある時、私と祖父と私の伯父とで昼飯を食べている時に、伯父が聞いたんです。
おそらく、「伯父」とは、岸の長男である岸信和であろう。
「あれは、確か書いたなあ」と祖父はいいました。伯父も私もその回答にはショックを受け、伯父はさらに「本当にそう思っていたんですか」と核心にふれる質問をしました。祖父は食べながらちょっと考えていた。そして、「あれを書かなければ、安保はどうなっただろうか」と一言いったんです。
生真面目で正義感の強い伯父は「政治家というのは悪いなあ」と言いながら私を見ました。私はなんとなく伯父に同意したように記憶していますが、私の気持は整理できていませんでした。一般の道徳からいえば、総理大臣が念書まで書いて大野さんを騙したわけですから、これはとんでもないことでしょう。しかし、ではそれをやらなかったらどうなったのか、ということです。
ここから急転、晋三は祖父・岸信介の語った歴史の真実を目の当たりにして、みずからの政治信条に引きつけてこう結論する。
例えば、当時の大野派の協力が得られない。党内もうまく行かない。よって安保条約も成立しない。とすると、人間の普通の社会での道徳は完うできるけれども、政治家としての本来の使命は完うできないでしょう。だとすれば、日本の運命はどうなるのか。だから、政治家は「結果責任」をより厳しく問われなければならないのではないか、とその時私は漠然と感じたわけです。
(『「保守革命」宣言』)
孫が、この祖父の語りから自身の政治信条を導き、あるいは補強していく姿には、ある種の慈しみさえ表れているように思ってしまう。
それは、晋三自身が記しているように、かつて京都大学の学生時代、全共闘の学生運動に身を投じていた岸信和が、親父の口から語られたこの歴史的な〝非難〟の場面を聞き、純朴に「政治家というのは悪いなあ」と感じ入ったのとは対象的に、晋三は一方でその場面がみずからのなかでは否定には至らず、むしろそこに、結果責任を優先すべきであるという、「目的のためにはあらゆる手段を尽くして見せる政治家の業」ともいうべきものを観たという風景にほからならいのだ。
この岸と晋三とをつなぐ流れを見たとき、やはり晋三は、来るべき総裁選に「勝ちにくる」のは当然だし、もしかしたら勝つかもしれないな、と予感した。
晋太郎に欠けていたのは、まさにこの「勝つためにはときに手段を選ばない」執念であったのかもしれない。
そして、それは、常人の道徳観に照らせば、「卑怯な器」であるのだろう。
この卑怯さこそ、実は、「政治的体質」とでも呼びうるもののようにも感じた。
そして、そうであれば、まさしく岸も一役買ったその「五五年体制」の哲学と伝統によって、安倍晋太郎は総理候補となり、そして総理のイスを逃したのだった。
九〇年四月、現職総理の小渕恵三が脳卒中で再起不能となったとき、有力政治家数人が角突合せ、赤坂のホテルの一室で次の総理を決定し、その結果「森総理」が誕生した。
そのとき、その前近代的な野蛮さを弾劾せんばかりに、世論は沸きに沸く。
でも、その〝野蛮〟こそが、岸を始祖とする王朝としての始まりを決定づけた安保改定の実現という「伝説」を生んだわけだった。
ならば、やはり晋太郎は、王朝の本流として、王朝の哲学である「禅譲政治」だからこそ敗れた、「体制のあだ花」であったのかもしれない。
そして、ついに既存体制の破壊を掲げて現れた小泉純一郎という異質の統治者がいた。
自民党政治の骨髄ともいえた派閥政治を全否定するその小泉が、自らの政権の四番バッターに抜擢したのが晋三だから、祖父により近い信条の親和性を感じ取り、育んだ自らの存在意義が、自らが引き継ぐ王朝の存立哲学の「逆説」としてあるとすれば、何よりもそこに政の非業さが見てとれるようだった。
けれど、ともすれば吐き気さえ催させかねないほどの生々しい臭気さえ伝わってくるこの会話のなかで、ある分かりやすい原則が貫かれているのはよくわかる。
それは、総理のイスををめぐって、次は誰に「譲る」とか、「渡す」とか、「頼む」とか、あまりに話が小さくまとまっていることなのだ。
ここまでの生々しさを突きつけられてしまうと、結局、総理のイスとは、政策や人柄とはまったく無縁の、「譲る」「渡す」「頼む」世界の、半径の小さいムラの人間関係でときに、めぐり、ときにめぐらずのものなのかもしれない、と、改めて愕然としてしまった。
こんな小さなムラの掟によって、国民が生きる大きな世界が規定されてしまうことを、岸王朝というひとつの歴史を多少なりとも垣間見た気になったところで、初めて実感したのだ。
なんと、不条理な―。
そして、安倍晋三という若い政治家が自著のなかで繰り返し説いた「政治家とは結果責任」という、その本来の意味は次のような文脈こそが本来のものではないのだろうか、と気付かされるのだった。
一本調子の直線的な政治は、実は政治としては最も無駄の多い、また脆い政治であろう。知慮ある政治家はけっして人々をして最短距離をいつもがむしゃらに進ませるような千篇一律なまねはしない。極端な場合には、目標地点の方角から廻れ右して後ろ向きに歩かせてさえもちゃんとそこへ人々をたどりつかせて見せる。強行軍はけっして強行軍だとは思わせない。それにひきかえ、人々をして択りに拓って荒涼たる砂礫地帯を歩かせ、わざわざ風光明媚の地帯は目に毒だなどと言って避けて通らせている指揮者などがもしあったなら、それこそ沙汰の限りと言うべきだ。
(『歴史の暮方』林達夫)
少なくとも、日本という国に生きてきてこのかた、ここに記されたような美しい政治の技術に長けていたと思える政治家に出会ってはいない。そこには、経験が圧倒的に足りないという事情もあるのだろう。
でもやっぱり、五五年体制の核を構成していた、「禅譲政治」と表裏一体の「派閥政治」の心理が、政治家個々が治者の技を磨くことに目を向けさせなかった一因であるようにも思う。
……『権威』による支配と、権威への無条件的追随。親分の前では自らを価値ひくきものとして意識するところの子分の卑屈な感情と、これに対する親分の『権威』及至『親心』。親分の権威への追随ということが、子分の行動の絶対的基準である。人は、主義主張を同じくすることのゆえに他の人と行動を同じくするのでなく、親分がある行動をとりあるいはとることを命ずるゆえに、そのような行動を無条件的にとるのである。しかも、人は、自らの内面的自主的な精神にもとづく主義主張というようなものによつてよりも、むしろ、出身地が同じであるとか酒や碁がすきであるとかいうような、人の精神にとつて外面的偶然的な事情によつて、自らの全行動全精神を拘束するところの親分子分乃至兄弟分関係を結ぶのである。
(『日本社会の家族的構成』川島武宜)
そして、ウメはまさにこの小さなムラの掟と、人間模様の綾をその内側からつぶさに覗いた半生を送ってきたのだった。
八〇年間、甘い結婚生活を一度も経験することなかったウメにとって、王朝宮である安倍家は家族そのものとなった。
ウメが不在となったことで東京の安倍の家は寂しくなったのではないかと、ウメに訊ねたことがあった。
「そう。間が抜けちゃうのよ。それまであったのが急になくなっちゃうと、間が持たなくなるでしょ」
ウメはそれを否定することなく、むしろ「間が持たなくなる」のではないかと言った。自らを安倍家の「間」と言い表すウメに、私は深くうなずいた。それは、ウメという女がおよそ半世紀にわたって育んだ「誇り」であり、「矜持」ともいえるように思えた。
「間」がその場の空気や局面をときに決定的に支配すると考えれば、ウメのその言葉は、〈自らがいかに安倍家のすべてであったか〉を表していた。
本来が楽観的な晋三には〝吉本(新喜劇)〟のスタイルでいくこと勧めているとも言った。それまでの話を覆して、実はこうだったというのが「吉本流」で、それを勧めているというのだ。
結婚する前の晋三が出勤するとき、毎朝その背を追いかけは今一度前髪が整っているかどうかを確認し、整っていなければ手櫛でもかまわないから梳くよう注意したものだと回想する。
油谷に戻ったウメは、ずいぶんと人目につかない場所に蟄居していた。
廃墟と空き地のすぐ間にある、人ひとりが通るのがやっとの細い路地を奥へと進むと、山の斜面が広がる。その、表からは見えない処にウメは隠れた。
そこは、住宅地図にさえ載っていない場所だった。私は、だれよりも洋子の「悲願」を理解していたウメらしい、終の棲家だ、と思っていた。
しかし、その棲家からも離れ、訪問客に会うことさえかなわない状況に置かれたウメの処遇を知ったとき、女帝・洋子の想像を絶する執念の激しさと、そしてその意思を支える者たちの決意の固さとを、剥き出しの刃のごとく胸に突きつけられた思いだった。
「ウメの話が本になったら困るわ」
王朝に仕える者たちを動かすには、その一言で十分だった……。
葬られゆくウメの思い
下関から気動車と呼ばれるディーゼル車でゴトゴトと二時間ほどかけ、病院にウメを訪れた〇六年二月上旬のその日、結局、ウメに会うことは叶わなかった。そして再び、来たときと同じ、長門古市駅に立っていた。
次の電車が来るまでにはまだ一時間以上もあった。
大阪や東京みたいに、駅前に同じ配色の看板がかかった見慣れた喫茶店もないから、仕方なく、一台だけ停まっていた地元のタクシーに乗りこんで、「どこかへ」連れて行ってくれるように頼んだ。
ウメに会うという最大の目標を失った今、どこへ行くかは問題ではなかった。
次の列車が来るまで、無人の駅の待合室でジッとしているのだけは耐えがたかったのだ。
とにかく、目の前の光景を変化させて、落ち込みそうになる自分の気持ちに余裕を与えたくなかった。
もし、駅の待合室で腰を下ろしたら、次の瞬間には沸点に達しかけている気持ちが爆発して、もう一度ウメのいる病院に向けて走り出してしまったかもしれない。
直情径行の激しい気性という点では、会ったことはないけれど、記事や関係者から仄聞する晋三の「荒さ」にもまた劣らないはずだった。
大きな狙いをもったときだけ、気性を治めることができるし、そのためには小さなことも犠牲にすることができる。
でも、ウメに会うという願いを封じられた今、久方ぶりに滾る血の動乱を持て余していた。
すぐにでも病院に立ち戻って、そしてこらえにこらえ、あくまでも穏便に辞去してきたあの慇懃な職員たちにこう叫んでしまいそうだった。
「おい、院長を出せ!」
面会はおろか、差し入れの湯飲み茶碗さえ受け取らないこの病院が、まるで免罪符であり、万能の〝イージスの楯〟のごとくに連発した、「患者のプライバシーが」とか「精神保健福祉法が」とか、仮に百歩譲って「医療の観点から面会はできない」としても、桜の模様の入った湯呑み茶碗の差し入れを、ウメ本人にさえ尋ねさえせずに受け取りを拒否することと、いったい何の関係があるのだろうか、と腹のなかでは思っていた。
こんな田舎芝居と茶番のために、立法者たちも精神保健福祉法をつくったのでもなければ、ましてや個人情報保護法をつくったわけでもないだろう。
これじゃあ、ウメに限らず、加齢人口が爆発的に増えるこれから、まるで「合法的な幽閉」がまかり通ることになってしまう。
やたらと自分自身の不甲斐なさが悔しくて悔しくて、目頭が熱くなっては、いかんいかん、と手動式のハンドルを廻しては、顔に外の風を当てた。
そして、白髪を短く五分に刈り込んだ運転手の、「じゃあ、千畳敷でも見てみますか?行って帰ってきても、そこなら次の電車には間に合いますから」という声に任せて、ずいぶんと痛んだビニールシートに揺られながら、田んぼのなかを走り、山の斜面を駆け上がっていった。
そこからは、運転手と客との、〝おなじみ〟の会話が始まった。
顔に馴染みのない客を乗せた運転手に、「仕事か、観光か」と訊ねられると、返答に困った末、「わたくしごとかな…」とつぶやいた。
そのときはもう、ウメに会うことができなかった悲しさと、そしてどこへぶつけていいのかさえ分からない、まるで〝幽閉〟さながらのウメの境遇に対する怒りとで、小洒落た合いの手を返す余裕もなかった。
まだ寒いから、春の景色にはほど遠かったけれど、いつだっただろう、ここを前に訪れたのは、と考えていた。
川を渡ったあたりで、ふと思い出した。
ああ、あれは、晋三の実弟、岸信夫の立候補した参院選のときだったな。
そんな反芻をしているうちに、タクシーはほどなく目的地に着いた。風力発電の巨大なプロペラがまわる千畳敷のうえに立ち、日本海を見下ろながら、そばに立ってあちらこちらを指さしていたタクシーの運転手に、ため息混じりに、「ウメさんという女性がいましてね…」と言ってみた。
すると、運転手は意外な反応を見せたのだった。
「あれっ、久保ウメさん?面会謝絶って……」
ツーッとつばを飲み、そしてこう言った。
「いや、おかしいな。去年の秋だったかなー、ウメさんを乗っけたんですよ。駅から、その病院までね。なんでも、友達が入っているとかでね。面会にいくとかでね。ウメさんって、岸さんのところにいたあのおばあちゃんですよね。知ってますけど。あれっ、おっかしいですねー。それに、あそこの病院はそんな面会ができないほどの重症のひとはいないはずなんですよ。去年の秋には元気そうだったけどな……そうですか、ウメさん、あそこにいるんですか」
ウメの入っている病院には、老人ホームが併設され、グループホームになっている一方で、神経内科もあるために、隔離病棟もあるのだった。
日本海から冷たく湿った風が斜面を駆け上がり、そして千畳敷の峰を越えてウメのいる病院へと吹き降ろして行くその抗えない流れのなかで、運転手は独り言のようにこう言った。
「こういっちゃ、あれですけどね、ウメさんがそんなだったとしたら、少しアタマのほうにきちゃって、それであんまり余計なことを喋られたらまずいから、あそこにいれちゃったのかもしれねーなー」
その傍らでは、かつて中国電力がモデル事業として建てたものの、雷に弱いという理由で本格的な実用には至らなかったという風力発電の巨大な羽が音もたてずに、ただ風を受けて回っていた。
どこからか、かつて佐渡島の賽の河原で見た、海岸一面を埋め尽くした水子供養の風車のように、寂しく風を切る、はかなげで切ない音が聞こえてくるような気がした。
カラ カラ カラ カラ カラ
と、そんな幻聴に乗って、ウメがかつて語ってくれたあの一言が、また甦ってくる。
「いつかは、私の人生を残してみたいわね」
でも、その前にウメは〝封印〟されてしまった。
心のどこかできっと、予感していたのかもしれない。
ウメに出会った三年前に、いつかこの日が来ることを。
それは、ウメが再びいなくなってしまうのではないか、という残酷な予感だったから、もしかしたらもっと早く、ウメと長い時間を過ごせるように油谷を頻繁に訪れることもできたのに、それを避けていたのかもしれない。
ウメは戦中をどうやって過ごしたのだろう。
長門の女学校に通っていたウメは、どんな学生だったのか。
岸信介とその妻、良子に仕え、そののちに安倍晋太郎・洋子と生き、晋三を背負ったあなたの姿を、もっともっと、しっかりと記録しておけばよかった。
手遅れになる前に。
だから、晋三が自民党の幹事長になったとき、大きなミスを犯してしまったのだ。
晋三が早晩、次の総理候補となることは衆目一致していたんだから、小泉純一郎の任期切れが訪れる〇六年九月までに、ウメの口から、ウメの人生を語ってもらうべきだった。
そもそも、ウメを〝発見〟した〇三年の時点で、肝心なときにウメが再び封印されてしまう可能性を、誰よりも分かっているはずだった。
妹の郁子と暮らす、隠居していた家を訪れていたときも、ウメは座を外すことがあった。
東京から電話が入ったからだった。
それは洋子からの電話だったではないか。
その時、横にいたノンフィクション作家の門田隆将と顔を見合わせたのを覚えている。
まるで、取材に訪れているのを察したかのような、〈ずいぶんとタイミングの良すぎる電話だな〉、と。
洋子はウメをこう呼んでいた。
「戦友」
安倍家のすべてを知るまでに心許した戦友だからこそ、総裁選という戦争状態のただなかでは逆に疎んじられることになってしまったのかもしれない。
三年前、駅からタクシーには乗らず、わざわざ集落のなかを歩いて安倍晋太郎が育った家に向った。
それは、大きな川の向こうがわにあって、渡場と呼ばれる場所にあった。
昔は造り酒屋でもあったというその家の敷地は確かに古かったけれど、その場所に到着したときにはもう、古い建物は壊されていて、定年を迎えて実家に戻ってきたという主によって建てられたばかりの真新しい今風の家屋がそこにはあった。
そこの主はずいぶんと親切だった。
晋三が幹事長になった直後ということもあって、東京からも多くのマスコミが連日、電話を含めて取材に問い合わせてくるのだといった。
主に勧められた応接セットの外には、すぐ窓の際まで懸淵川の水がきていて、窓を開けて飛び込めば、すぐにでも水浴遊びができそうに思えた。
主はいった。
「晋太郎さんが子供の頃は、この川で泳いだり、釣りをしたりしたそうですよ。ウナギなんかも釣れるんです」
渡場のその家から一キロといかずに油谷湾に注いでいることを考えれば、おそらく満潮のときにはこのあたりの川は海水と混じった汽水になるのだろうな、と想像した。
今、渡場には大きな橋が架かっている。
大きいといっても、川のはるか頭上を頑固な鉄の脚をむき出しにしてかかるアーチ状のものではなくて、むしろあまりみかけることの少ない、川の表面ギリギリに沿って渡したような、遠くからみれば四万十川の沈下橋にみえないこともないものだった。
渡場にかかる橋は、まるで静かな川面の上に、真っ白い反ものをサーッと向こう岸まで転がしたかのようだった。
晋太郎が育ったこの家は、しかし、今は安倍家のものではなかった。
安倍家と遠縁にあたる新しい主のものだった。
渡場の主は、安倍家からその土地を取得した経緯についてはあまり触れられたくないようだった。
晋太郎の父、安倍寛がかつて東京で商売に失敗し、女房との離婚に至ったとき、生まれてわずかの晋太郎は、この渡場の家に預けられてきた。
晋太郎はそこで、大叔母と呼ばれる女性に育てられたけれど、その大叔母は、〇三年にはすでに体調を崩していたそうで、会うことは叶わなかった。
今、油谷にある安倍家の自宅といえば、この反もののような美しい橋を渡り、渡場を抜けてまっすぐに山を上がったところにある。
長く、誰も住んでいないのだろう。
「あべ晋三」の選挙用の立て看板らしきものが立っているのが、唯一、そこが安倍家であることを知らせるだけで、敷地のなかに建っている平屋建ての家屋は、雨戸がピッタリと閉じられて、その雨戸のほこりを眺めれば、そこにもう長く人の手が入っていないことがうかがい知れた。
地元の人々に尋ねても、晋太郎の思い出ならばそれは尽きることなく湧いてきたけれど、晋三については、ほとんど具体的なことは記憶になかった。
そのワケは、晋三が山口県を選挙地盤にしているだけで、むろん、晋三は東京生まれの東京育ちであったことが大きいのだろう。
それでも、安倍家という政治一家を輩出したという多少の自負と誇りが、必死に村びとたちの口を開かせようとするのだろうか、訊ねた人々はみな一様に、晋三との美しい物語を記憶のどこかで探そうとするのだけれど、その姿が逆に哀れを誘った。
安倍家はたしかに油谷の出身ではある。
でも、東京生まれの東京育ちで、子供のころ、油谷の町に遊びに来ていた晋三兄弟の姿を伝聞したものは多くとも、すでに晋三は油谷の人びとにとっても遠い存在以外ではなかったのだ。
渡場の主もまた、晋三との思い出となれば、一応、考え込みはするけれど、「しっかりしていて」とか、いっぺんとおりのことしか出てこなかった。
日本全国を見渡せば、決してそれが責められることでも、珍しいことでもなかったけれど、もはや油谷の人びとにとって代議士「あべ晋三」をかつぐ理由は、いまだ思い出あざやかな安倍晋太郎の子であるに過ぎないように思うのだった。
「末は博士か大臣か」の戦後の立身出世の時代に、郷里の期待を背負って、まさに大臣となった安倍晋太郎に対しては、言葉では言い表せないほどの思慕を、あるときは支援者のひとりは目頭を潤ませて表現してみせたし、駅前、木村病院の人間たちも、幻の総理応接室に私を通して、その前で懐かしそうに当時を回顧してみせた。
これはもちろん、晋三が油谷の人びとにとって馴染んでいないというわけでもないし、油谷の人びとが晋三のことを支持していないわけでもないのだ。
ただ、ある政治家を支持する具体的な理由が見つからないのに、晋太郎の息子だから、という理由で御輿をかつぐ、日本の古い習慣ともいうべき文化が、村の老いたかつぎ手の表情を見ればみるほど、不条理で、やっぱりそこに違和感を感じてしまうのだった。
人柄も、表情もそれほど身近でない代議士に、一票を投じるとすれば、いったいその投票行為に、ひとびとはどれだけの意味と意義を見出しているのだろうか。
油谷の人びとにとってのそれは、間違いなく、亡くしてなお濃い、あまりに大きな「晋太郎」の影なのだった。
晋三の選挙地盤には、もはや過疎の村ともいえるこの油谷だけではなく、大きな人口を抱える下関も含まれている。
その下関では、多くの地元企業の関係者との縁も深く、そんな付き合いを巡っては、ゴシップ雑誌にあまたというほどではないにしろ、いくつかのスキャンダルが掲載されたことがあった。
でも、政治家とカネとの問題は、不見識だけれど、まったくといっていいほど関心はなかった。
皮肉にも、ものの本には、いわゆる戦後政治のなかで、田中角栄に連なる金権政治の土壌を一番さいしょにつくったのは、晋三の祖父である岸信介だという、そんな辛辣な記述もあった。
きっとそれは本当なのかもしれない。
でも、力のあるところにより、カネが流れこむのが政界の道理だとするならば、それほどの力を揮った岸信介という〝妖怪〟の孫にしては、いまだ一向にその背中に深い傷跡を残すようなスキャンダルのひとつも噴出しないというのは、見方によっては、これまた残念なことでもある。
とりわけ、晋三の支援者たちこそがそれを感じているのではないだろうかと思うのだった。
そもそも、積極的に政治家の後援活動、とりわけ与党を支援するもののなかで、みずからの商売や既得権に対する〝下心〟がないもののほうが少ないであろう。
もちろん、その代議士が支援者にとって顔の見える距離にいた、まさしく「縁のある者」であれば、そんなよこしまな下心の前に、純粋に応援する気持が先に立つのだろうけれど、もはや都市化していく選挙活動のなかで、あえて政治家に個人献金や企業献金する人びとの心のどこかに一片の〝期待〟がないというほうが、ちょっと信じられない。
でも、それを否定する気にもなれないのだ。
晋太郎が育った渡場の主が、定年まで勤めた石油会社の名前を聞いたとき、瞬時に、いまだ日本のムラを覆っている、地縁の強固な結びつきを悟らされた。
その石油会社の名前に、聞き覚えがあった。
それは、岸信介の長男、信和が役員を務めていた会社だったからだ。
東京の大学を卒業していたこの渡場の主人にして、それこそ数限りなくあったであろう就職先候補のなかから、この石油会社を選んだのを、単なる運命のイタズラとは信じない。
生涯の生き方をも、地縁、血縁に拠っていくこの風土のなかに、晋三は支えられ、いや「安倍家」はいまなお生きながらえているのだろう。
でも、繰り返して、決してそれは非難されるべきことではないし、それこそ、奇跡的なまでの美しい地域社会の紐帯であるようにさえ感じるのだ。
そう考えれば、やはりもうひとつの不思議なことにも納得がいくように思えた。
これまでに七人もの首相を送り出してきた山口県が、長州藩の時代からの伝統をいまなお強く意識し、誇りに思うのは当然だとしても、なぜこうも、山口県出身者がこぞって安倍晋三のことを本に書きとめているのだろうかというのは、大きな関心を呼んだ。
郷里の人間だから、より強い関心を惹かれるのは当然だから、といえば、それはそうかもしれない。
でも、晋三が幹事長になってから出版されたものを含め、それ以前のものも、やはり山口県出身者の手によるものが多く遺されていた。
石川県ではこうはいかないだろうな、と考えていた。
現に、森喜郎が総理になったからといって、石川県出身者がこぞって本を著すということはあまりに記憶にないし、別段、それが森を持ち上げたものでなくとも、逆に森を蹴落とさんばかりに酷評したものでさえも、お目にかかったことはなかった。
石川県と山口県では、ともに日本海に面しているとはいえ、もちろん、気候も風土も、気脈も異なるから、それは当然かもしれなかった。
でも、どちらかといえば、「沈黙する」石川県がもっていない山口県人の資質に目を向ければ、こうもいえるのではないだろうか。
「大いに語る」のが長州人、だと。
語る、という行為は、時と場合によっては主張する、という行為に通じてこよう。
それこそ、晋三がライフワークとしている感すらある「外交」をめぐっても、その日本の近代外交史上、重要な位置づけを占める大事件の舞台となったのも、その山口・下関だった。
文久三年、一八六三年のことである。
長州藩は、五月十日、下関海峡通航の合衆国汽船ぺムブローク号を田ノ浦で砲撃、二十三日、豊浦沖でフランス通報艦キンシャン号を砲撃、二十六日、オランダ軍艦メジュサ号を通峡の途次で砲撃、米・佛軍艦の逆襲で軍船を喪失し、主要台場を破壊されたが、憤激した高杉晋作の奇兵隊編成となり、砲台の修築となり、海峡通航の遮断となり、かくて、瀬戸内海の通航問題は列国のあひだに議せられるにいたった。
(『近代日本外交史』信夫清三郎)
黙することなく、堂々と異議を唱え、それが叶わないときには武力にさえ訴えるその心意気は間違いなく、「長州の血」であるのかもしれない。
ウメも言っていた。「長州の男性というのは、ある一つのことをしゃべらせたら、それなりにみんな、一通りに自分の筋論立てて。それで最後にやっぱり傾くときは情で傾くのね」と。
晋三という名の一字がその晋作に由来しているのは、その気性に照らして奇遇だとしても、伝統が血のつながりではなく、さらに深くは血が象徴する意識の連なりであることを考えれば、高杉晋作の激しさと、安倍晋三の烈しさが似通っていることは、必然のようにも見える。
懸淵川に遊び、渡場の船に乗り、油谷の山々を駆けていた晋三の祖父も、父も、もういない。
安倍晋三という政治家に会ったことはないけれど、なんだか、政治家・安倍家を生んだこの油谷という村も、風景も、とっても好きになった。
風景は決して捜しに行くものじゃない。
きっとそれは出会うもの。
そこに旅は新鮮さを与えるし、楽しさを感じさせるし、また旅へとひとをとりこにさせる。
ウメの目の前を走馬灯のように駆け巡った政治の風景もまた、ウメにとっては偶然の縁が紡いだ多くの出会いに他ならなかったのだろう。
〇六年二月三日夕方、人丸駅から下関に向おうとプラットフォームに立ったとき、空から乾いた小雪が散ってきた。
遠くの稜線の上には風力発電の羽が回っているのが見えた。その車内で、ウメから届いた手紙を開いた。
昭和十一年、先代安倍初出馬から毎々、多少の場所も、各々の人も、条件の異なるたびごとではございましたが、周囲一般の動きも併せて、心身とも、計り難き経験を覚えましたことは、まことに愚考の思ひも及ばない時間の経過でございました。
これから、日と刻をたのみに自分の保養を第一に努め、もっぱら妹と共に遊びました故郷の空を、水を、緑の山々とともに自分らしい精進に努めてゆきます。
秋らしい天候のつづくなか、小社の秋祭りらしい太鼓の音に、素直な明け暮れ……
油谷の木村病院の「幻の総理応接室」には、横二メートルはあろうかという、大きな書が架かっている。総理の座を逃した晋太郎が、「ぜひ」と贈ったものだった。そこには、こう書かれていた。
「一家千年之春 晋太郎」――。
乳母の口を封じてまで勝負に賭けた安倍家に、待ち遠しかった総理就任という「春」は結局、二度訪れた。
そしてその春の先に、晋三は自らの政治的信念を賭けた戦いを問い続けている。
ウメはこの手紙から数年後、ひっそりと生涯を終えた。
小さく営まれた葬儀には、「晋ちゃん」の姿はなかった…。
安倍晋三は二〇二二年、凶弾に倒れ、帰らぬ人となった。
ウメが悲劇の瞬間にこの世にいなかったのは、「晋ちゃん」を慈しんだウメにとってはむしろ、不幸ではなかったのかもしれない。 (敬称略)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
