
ツイッター運用の教科書
どうも、ケッキング山田です。
今回は企画第四弾ということで、全5章の構成でツイッター運用の教科書を作成した。
いつも通りモニター生を囲って、フィードバックをもらいながら、作成したので、そこそこいいものにはなっていると思う。
今回は13人のモニター生に協力して貰った。毎回メンバーは変わるね。今回は30分も立たずに募集終了したので、次回からのモニター生希望の方は通知オンで待機しておいてください。10人くらい集まった段階で募集終了するので。
ということで、本編の前に今回の企画で協力してくれたモニター生を紹介しようと思う。
ヒロさん(https://twitter.com/yoshitan221)
前回の企画の時に繋がった無課金でいかに女性を攻略するかを考えている人。笑おもしろキャッチコピーで活動しているが、フィードバックは丁寧に長文で毎回くれたし、見かけによらず真面目そうな方だ。
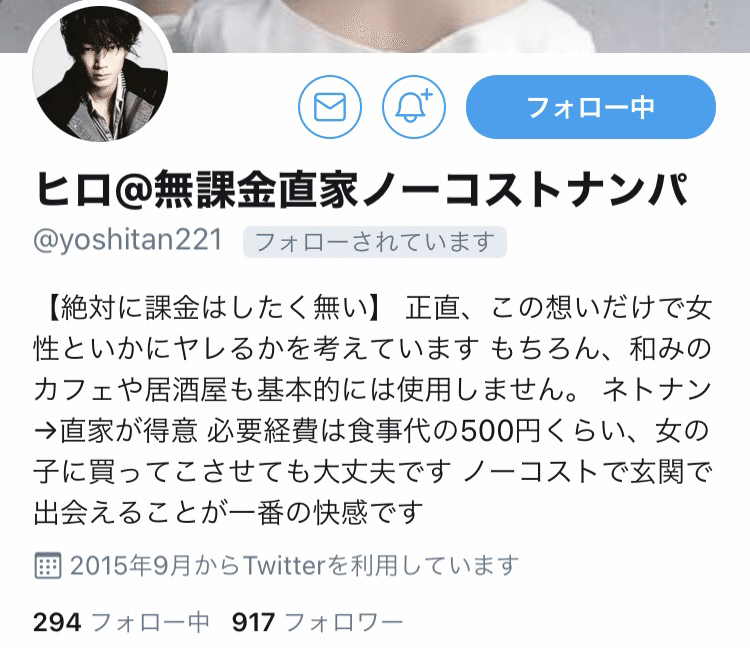
界無さん(https://twitter.com/CaymX666)
最近繋がった方で1日20時間ツイッターをして1ヶ月で爆伸びしている変人。今回の企画では一番長文でフィードバックをくれて、フィードバックをnoteの記事にして送ってくれたので、非常に助かった。今回の企画MVP。

しゅうさん(https://twitter.com/shu_kenyaku)
しゅうさんも最近繋がった方で、ぼくの記事を毎回音読してからフィードバックをくれるほど信頼してくれている。しかも、フィードバックの速度がとにかく速いし、長文だから助かっている。これからの活躍に期待だ。

かまどさん(https://twitter.com/Kamad1105)
かもどさんも割と最近繋がった方で、フィードバックが長文でかつ早い。普段のぼくのツイートにも結構反応してくれている。これから伸びそうだなという印象。鬼柱っていうネーミングがおもしろいね。笑

志鬼さん(https://twitter.com/kokorozashi_oni)
志鬼さんは前回は別のアカウントで参加されていたが、最近マーケティング用のアカウントを作ったらしく、今回はこっちで参加。これからどんどんアウトプットしていくみたいなので、頑張って欲しい。

くわさん(https://twitter.com/QwA_fredog)
くわさんも前回の企画にも参加していたかな。デザインをしている方で、ぼくとは活動の類似点があまりないが、熱心に毎回フィードバックをくれる。非常に感謝している。生きてるだけで全肯定らしい。笑

あかりさん(https://twitter.com/STUjya)
あかりさんは皆勤賞だね。第一回からの企画参加者。ぼくの文章の癖を指摘してくるレベルでぼくの文章を読んでいる。最近、フォロワーが伸び出したようだ。こっから爆伸びして、考えるOLみたいになるらしい。

るあちゃん(https://twitter.com/rua_iq)
るあちゃんも前回同様継続の参加者。毎回長文でかつ早いフィードバックをくれるのは安定。1日も遅れることがないから安定感抜群のモニター生。こういう子が1人でもいると非常に企画は作りやすいから感謝している。
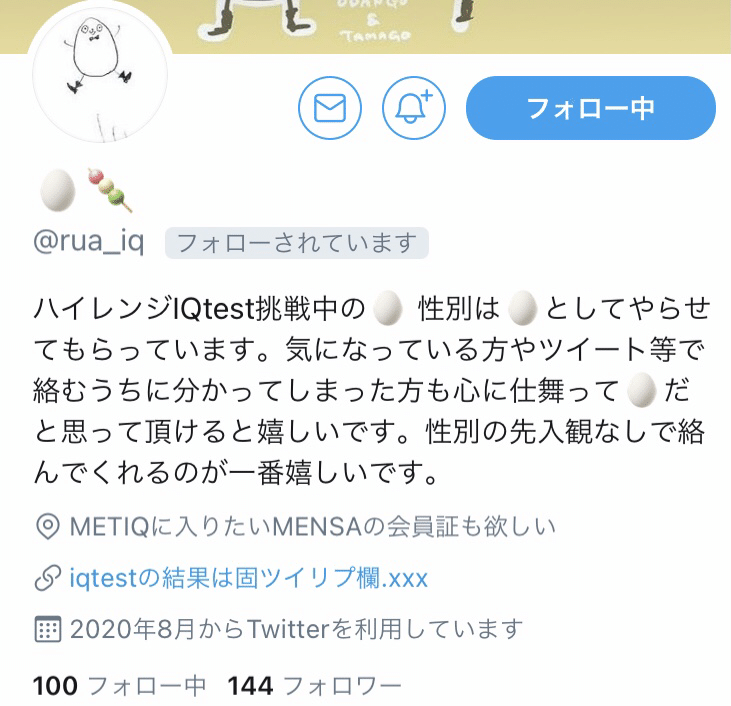
ゆーーさん(https://twitter.com/100dayguitar)
ゆーーさんも前回から継続参加者。割と早い段階からぼくのこと見てくれていて、最近になって本格的に文章力の強化に励んでいる。活動のメインはオフラインなので、オンラインでのスキルを今は磨いているという感じ。
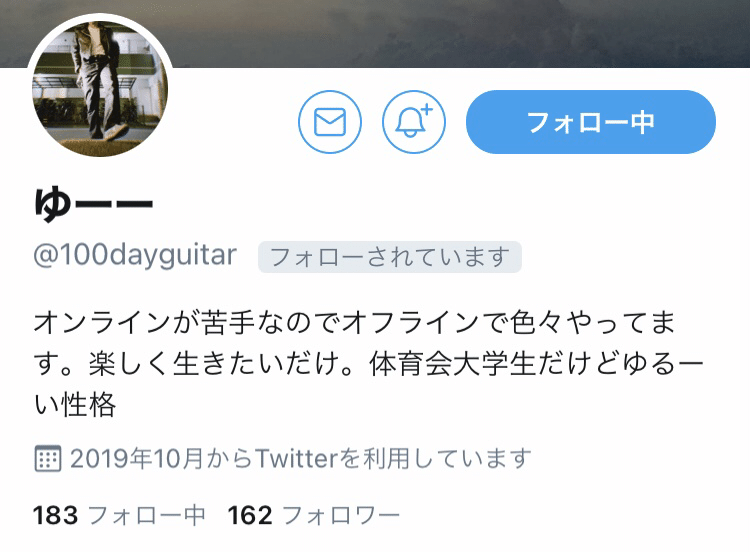
みやくん(https://twitter.com/zzzmnm)
みやくんもあかりさんと同時期くらいに出会った、古参ユーザー。彼も安定してフィードバック早いし、ぼくが書いたほぼ全ての文章を読んでくれているね。最近はnoteも結構更新しているので、興味がある方はぜひ。

サラちゃん(https://twitter.com/sarasalist)
サラちゃんは結構前に出会ったが、モニター生の参加としては初。ツイキャスの参加が皆勤賞な気がする。笑最近、80人規模のコミュニティを作って、じぶんなりの活動を始めているから、今後の活躍に期待。ポエム中心。

リタさん(https://twitter.com/RitaDreamGrant)
リタさんは最近繋がった方で手紙に関する情報発信をしている人だ。打ち出す世界観が独特なので、差別化としては非常にうまいなと。固定ファンがいる感じなので、これから広がっていきそうな印象だ。

5階くん(https://twitter.com/nemunemu_neet)
彼も古参ユーザーだね。最近のツイートではビックになるが口癖。これから成り上がるみたいなので、今のうちにフォローしておくと古参ぶれそうだ。しょうもないツイートの中にたまに意識高いツイートをしている変態。
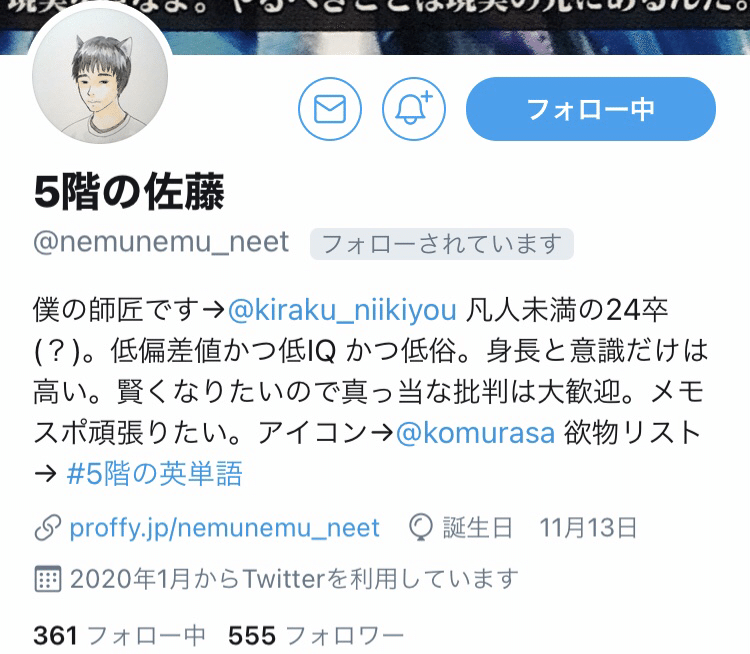
上記の13名が協力してくれたので、非常に感謝している。毎日更新で記事を出したのに、丁寧に早くフィードバックくれてありがとう。
また、次も企画やるんでその時はぜひ。
ということでさっそく本編へ。
この記事を読めば、正しいツイッター運用の方法、アイディアの出し方、差別化の方法、2種類の読書について、継続の攻略法などがわかると思うので、得られるものは大きいかなと。
1話:良い文章と悪い文章について
さて、今日から第五話にかけてツイッター運用の教科書を作っていこうと思う。
なぜ今回、このようなテーマで企画をしようかと思ったのかというと、ツイッター上でマーケッターと名乗る人々のほとんどが間違ったやり方でツイッターを運用しているからだ。ツイッターでフォロワーを集めたければいいねをたくさん押したり、リプ周りをしたりみたいなのが常識になっている。
もちろん数字だけのフォロワーを集めたければ全然おもしろくない発信を永遠と続けて、毎日おはよう戦隊をしていればいいのだが、おもしろいツイッタラーが果たしてそんな不毛な作業ゲーをしているだろうか?100%していないはずだ。
何をやるにしても本質を抑えなければ、そこから派生させ相乗効果を生み出すことはできない。
ツイッターの本質は情報発信の質だ。つまり、ツイートのクオリティ。ここが低いままだと、相互でつなげる以外でフォロワーを増やすことはできなくなる。
芸能人を除いて、匿名アカウントで伸ばそうと思ったら、文章一本勝負だ。
つまり、発信がおもしろくなかったら、どこかのタイミングで頭打ちになる。
フォロワーの多いビジネス系インフルエンサーがたくさんリプしろ!などということを言っているから、それを真に受けた情弱がアホみたいにインフルエンサーに大量リプを送る。(結局、得をするのはエンゲージメントが稼げるインフルエンサーなのだが)
ほんの少し考えれば、リプすることに何の意味があるのか?と疑問に思うはずだが、彼らはそうは思わないらしい。
ぼくは不思議でしょうがない。
彼らがやっているのは友達を作るために、その辺に歩いている人達に片っ端から声かけまくっているみたいなことだ。迷惑もいいとこだし、そんな奴は普通にうざいだろう。笑
じぶんを知ってもらわないと何も始まらない!などと彼らは言ってスパム行為を肯定しているが、そもそもじぶんの無能さをさらけ出すくらいなら知られない方がいい。
迷惑系YouTuberへずまりゅうは知名度こそ獲得したが、悪評が出回りすぎて今後の活動もやりづらくなっている。
このように大量リプみたいなスパム行為で自分を認知してもらおうとすると、コイツはこんな小賢しいことしかできないんだというような印象を見た人に与えてしまう。
というか、このやり方で集めた人達のレベルはすこぶる低いので、この属性の人達をいくら集めてもコミュニティは形成されない。(集まってきた人のほとんどがビジネス目的だからね)
数字上のフォロワーは増えても、それ以上の人々に不快感をもたれるから、
頭悪そうな行動はなるべくしない方がいい。それにぼくみたいな人に後々こうやってネタとして書かれ、小馬鹿にされたりもするからね。笑
このnoteを見ているほとんどの人はツイッターを活用して影響力を持ちたいとか、ツイッターからマネタイズしたいみたいに考えていると思うのだが、
バカ丸出しの人には誰もついていかないから発信力を鍛えてじぶんが作り出す場で他者を引き寄せるイメージを持っていないと長期的には絶対にうまくいかない。
あなたがこのnoteを見ているのはぼくの発信がなんかおもしろそうと思ってくれたからではないか?ぼくがたくさんリプをした結果、人が集まってきているわけではない。おもしろい発信をしていれば、口コミで自然と広がっていくのだ。
多くの人は発信力が低すぎる。
だから、じぶんから営業をかけないとフォローしてもらえないのだ。
ツイッターは文字のフィールドだから、基本的に140文字以内の文章だけで勝負することになる。文章力が低いとそもそも土俵にすら上がれないのは一目瞭然だ。
芸能人でもあるまいし、とにかくおもしろくないと話にならない。
だから、どうやって文章だけで勝負していくのかという疑問を答えるために
まずは「良い文章」「悪い文章」について解説していく。
具体的にこういうのを書いたらいいということを書くとコピー人間が量産され、さらに自体の悪化を促進することになるから抽象的に書くので各自、具体的に落として勝手に持ち帰ってほしい。
ぼくはこれまでネットの世界では「何を言うか」よりも「誰が言うか」の方が大事だということは何度も言ってきた。
だが最初はみんな当然0からのスタートなんだから、「何を言うか」のステージから始まる。おもしろい発言を継続していくことで段々と「誰が言うか」のステージに移行していく感じだ。
そもそもどんなときに人はおもしろいと感じるのか?ここが重要だ。
差別化を図ろうとしたとき、多くの人は難しいことを言おうとする。難しくて誰もが知らないであろうことをつぶやいている人。もしくは当たり前のことをつぶやき、毎日永遠に継続だー!みたいな意識で積み上げている人。
この両極端を攻めてはダメなのだ。専門用語や漢字を使いすぎて、いかにも難しい雰囲気が漂っていたら、そもそもツイートが誰にも見られない。逆に簡単なことばかり言いすぎていたらコイツは低レベルな奴だなというイメージが定着して決して見た人はファンにはならないだろう。
つまり、良い文章とは難しいことを簡単な言葉で説明しているものを指す。
難しい内容はほとんどの人がそのままは理解出来ないが、それを別の世界の簡単な言葉で言い換えるだけですんなりと頭に入るようになる。
これはどれだけ相手のことを思いやれるかの気持ちの問題だ。
大学受験のような初めて習う内容は難しくて、よくわからないという人が大部分を占める。だから、人はわかりやすく丁寧に解説してくれている参考書を求めるのだ。
結果的に複雑な概念をわかりやすく解説してくれる一部の良書がバカ売れするということになるのだが。それくらい、わかりやすいということは需要がある。
書いてある内容自体は難しいんだけど、簡単な言葉で説明されていると人は未知の概念もすんなりと頭に入るのだ。
価値とは読み手の世界を広げること。つまり、どうにかして難しいものを簡単に表現しなければならない。
九九の覚え方みたいなのをツイートしても価値にはならない。なぜなら、九九はみんな知っているから。
だが、量子力学を誰でもわかる言葉で解説したらそれは価値になる。量子力学という概念をほとんどの人が知らないから、未知の世界と既知の世界をつなげてあげることに価値が生まれ、そこに人は惹かれるからだ。
難しいことをドヤ顔でツイートしてもそれが別世界のものと捉えられては何の意味も無い。内容は深いんだけど、誰が見てもある程度は理解出来る、そんな文章が理想だ。
そういうツイートができるようになれば、自然と人は集まってくるから時間の問題でフォロワーは増え、徐々にコミュニティの輪は広がっていく。ツイッターは小さなコミュニティを作れたらほぼ勝ちだ。これはぼくが証明しているし、現にどんどん新しい人が集まってきている。モニター生の顔ぶれも毎回入れ替わるから、コンテンツを作っているぼくとしても新鮮な感じだ。
もちろん、ツイートの質が一番大事ではあるんだけど、ある程度の人数は相互でつなげないと、そもそも誰にも見てすらもらえないという現象が起こるから、地盤を整えるという意味でも1000人くらいまでは相互でつなげてもいいと思う。(ぼくも最初は相互でつなげた)
最終的には発信のクオリティで人を集めることができるようにならないと、
ビジネスにつなげることは不可能だ。
特に文字だけの勝負だと、どう伝えるかがかなり大事だから、何か伝えたいことがあるときは参考書を作るような気持ちでとにかくわかりやすさを重視すること。
テクニックとしてはひらがな比率をあげるといい。漢字ばかりが羅列されていると、瞬時に脳はこの人の文章は疲れると判断して、シャットアウトしてしまうから、読みやすい文章ってのがピンとこない人は難しい漢字は全部ひらがなに変換を意識してツイートを作ると、自然と読まれやすい文章になる。
大前提として、ユーザーの目に止まってもらわないと話にならないから、
まずはとにかく読みやすい文章を書くこと。
これが最優先事項。
あとは抽象的なことを簡単な言葉で説明もしくは表現することさえ意識していけば、あなたのツイートは自然と伸びてくる。
表現方法が個々のオリジナルの部分であり、おもしろさでもあるからだ。
後は脳死の行動に逃げないで考察することだ。考えれば考えるほど知性というのは洗練されていくので、頭は使った方がいい。バカでも稼げるみたいなキャッチコピーで売り出そうとしている人もいるが、あれは「こんなバカでもできるんだぞ」という弱者に希望を与えるための情弱狩りコンセプトだ。
全うなビジネスではバカは這い上がれない。読み手の世界を広げることがビジネスなのだから、バカはじぶんより狭い世界を生きている大バカものしか相手にできないのだ。
だから、顧客範囲がものすごく狭まるので、「考える」という訓練は常日頃からやった方がいい。普段から考えておかないと、ツイートも思い即かないし、思い即いたとしてもそれをユニークな形で表現できないからね。
すぐにはできるようにならないかもだけど、結局発信の質で決まる世界だから、知性を強化することからは逃れられないのだ。
最終的には情報発信の質に回帰するということは覚えておいた方がいい。
では!
適当にフィードバックよろしく!
2話:フォロワー1000人までの土台の作り方とマネタイズについて
さて、第二回目だ。
前回は割と全体像というかツイッター運用とはこういうものなんだぞというものを大まかに書いた。
昨日のフィードバックで多かったのが、フォロワー1000人までの土台の作り方を教えて欲しいというもの。それら、もろもろを含めて、今回は具体的にツイッター戦略的なのを書いていこうと思う。
何周回ってもツイッターにおいて大事なのはツイートの質であるということは昨日言った通りだ。返報性の原理を狙った大量リプやいいね周り以外の方法で自然にフォロワーが増えていくような仕組みを整えることができなければ、マネタイズはできない。(短期的な利益は見込めるかもだが、長期的には無理)
リプやいいねをたくさんする人のファンには誰もならないからだ。これは前回の復習であり、大前提のこと。
では、それらなしでどうやって、フォロワー1000人までの良質な土台を作るか?ということだ。
決して、これはプロフィールに相互100と書いてあるアカウントを1000人フォローすればいいわけではない。それらのアカウントはただの数字であり、繋がったところで何のメリットもない。これらのアカウントといくら繋がろうが僕らの発信は全く広がっていかないので、相互でつなげるとは言え、つなげる属性もまた重要になる。
そこから逆算したときに、じぶんのツイートに共感して貰えそうなユーザーはじぶんと似たような発信をしているインフルエンサーのツイートに反応している人達だ。
ぼくは最初の方はマナブとか赤髪社長とか竹花とか砂鉄とかプロ奢のツイートにRT、いいねしている人達を片っ端からフォローしまくった。
フォローは1日400人までだから、それを超えないように調整しつつ、
とにかくフォローしてフォロバこなかったら解除してを繰り返して2週間くらいで1000人くらいの土台は作れた。
実はこのとき、ぼくはほとんどツイートしていない。1日5ツイートくらい。
どうせ、フォロワー少ない状態では外に広がっていかないし、それならツイートをストックして、ある程度の土台が出来てから、どんどん打っていこうと思ったのだ。
このやり方でちょこちょこフォロワーを増やしつつ、ぼくのツイートに共感してくれた人が少しずつファンになっていった。
毎日コンスタントに140文字スレスレでじぶんの考え方や学習方法、価値観みたいなのを発信していたら、いつもツイート楽しみにしていますみたいなコメントがちらほらきて、その人達とコミュニケーションを取っていき、小さなコミュニティのようなものを作った。
ぼくの周りの仲の良い人達はそうやって形成されていき、最初は数人でリプのやりとりをするくらいだったが、そこにいろんな人が巻き込まれてきて、
だんだんとぼくの周辺の人達も固まっていった。
そういう人達にぼくの作ったコンテンツを配布することでみんなが感想を言ってくれて、おもしろそうな場が出来たのだ。あの時はケッキング山田の出すレポートを読むことが習慣になっていた人もいるだろう。
これからのツイッター運用ではこういうじぶんを囲う場を生み出す事が非常に重要である。これは大量リプでつながった浅い人達でなく、ぼくの考え方や価値観に共感して集まってきてくれた人達なので、質としてもかなり高いし、長期的な仲間になりやすい。
書く内容としては別にビジネスを教えるとか稼げる情報とかではなく、日記に近いような内容や考察系の記事だ。
記事の内容は何でもいい。面白くて、次も読みたいと思ってくれるような内容であれば。むしろ、みんなと違う方がいいから、一概にこういうのを書いた方がいいみたいなのは言えない。
現にぼくも適当にネタを拾って書いているだけだ。薄らと、こんな感じのことを書こうかなみたいなのを決めて、それをどうにか見ている人がタメになったと思ってもらえるような内容に組み立てていくのだ。
こういうじぶんのファンに向けたコンテンツ作成をぼくのことを見てくれる人数が少ないときから、ぼくはずっとやっていたのだ。
良質なコンテンツを出していけば、自然と認知されていって、新しい人達がどんどん巻き込まれていき、じぶんのファンもどんどん増えていく。
だから、まずはさっき言ったようにじぶんと似た属性の人達のツイートに
反応している人達をフォローする。
マナブや赤髪などはただの例なので、このnoteを見た全員が同じ人達を
ターゲットにしてフォロワーをかっさらおうとすると競争が巻き起こるので、じぶんでいろんな人を観察して、フォロワーを奪うターゲットは各自決めて欲しい。
フォロワー多いツイッタラーなんて無数にいるから、あんまり考えすぎず、わからなければ最悪適当でもいい。
あくまでじぶんの発信を広げるための土台であり、最終的にじぶんのファンにならなかった人は切れば良いだけの話なのだから。
ぼくも最初からフォロー解除する前提でフォローしてた。初期から継続して今も残っている人はほぼいない。
土台を生け贄にして、今のぼくの周りに集まってきてくれるコアユーザーがいるから彼ら土台の役目はもう終わったのだ。
そして、ある程度ファンができれば口コミでどんどん広がっていくから
時間の問題で濃いフォロワーは自動で増えるようになる。
しかも、ぼくの場合は過去に出したコンテンツも会員サイトに載せてアーカイブとして残しているので、新規でぼくのことを知った人も後追いでぼくが成り上がっていくストーリーを消費できるような仕組みを整えている。
これにより、フォロワー1人1人の満足度をかなり高めることができるのだ。
どうしてもツイートだけに共感したファンだとツイートが面白くなくなった途端に離れていくから、コンテンツのバリエーションを増やして、飽きさせない工夫は大事だ。
ぼくはツイート、ブログ、note企画、ツイキャスみたいにいろんなことをやって、様々な角度からフォロワーを楽しませる工夫をしている。
特にこのnote企画のようなフォロワーからフィードバックをもらってコンテンツを作成する手法は個人的には最強だと思う。
フォロワーからお題をもらってそれに答えるわけだから、何か伝えたいというアイディアも自然と降ってくるし、記事を書くことに対する負荷を減らすことができる。
後はフォロワーも記事を読んでフィードバックを出すわけだから、アウトプットも出来て成長する。しかも、じぶんの意見が反映された記事というのは嬉しいものだ。
参加型にすることで一緒にコンテンツを作るというストーリーが生まれ、
そのストーリーに価値が宿るのだ。
学校の文化祭や体育祭の本当の価値というのはクラス全員で一緒に頑張ってきたという過程だ。このストーリーがなければ、楽しさは半減するだろうし、クラスメイト間の仲間意識も生まれない。
そう、これからのコンテンツの価値は情報ではなく、ストーリーに宿る。
ストーリーを消費したいからぼくの企画のモニター生はわざわざめんどくさいフィードバックをしてまでぼくのコンテンツを見てくれる。
情報だけが欲しかったら、モニター生になる必要はない。
ぼくはコンテンツ作りに参加して貰うという場に価値を見いだしているから、なんかおもしろそうと思ってくれた一部の人がモニター生になってくれるのだ。
オンラインサロンとかも全部そう。あれは本質的には場から生まれるストーリーを消費したくて、人々は参加している。このように楽しくて成長できる環境を構築することが情報発信ビジネスのあるべき姿だ。
最初の方は無料で全部やらないとそもそも人が集まらないので、一定数人数が集まるまでは全部無料でやって、数百人、数千人と集まってきた段階で初めて有料にするだけでマネタイズは楽勝だ。
役に立つ情報ではなく、楽しく成長できる場を作るという意識はかなり大事。人間は根源的に成長欲求があるから、このコミュニティに所属したら人生よくなるって思ってもらえたら、その場に価値が宿る。
このような意識でツイッターは運営していくのだ。
ツイートしたり、コンテンツを出していったりするんだけど、それはじぶんの作り出す場でフォロワーに成長してもらい、楽しくストーリーを消費してもらうためだ。
情報を売るのではない。ストーリーを売るのだ。この感覚を覚えて欲しい。
まぁ早くマネタイズしたければ、コアなファンが固まった状態でこれを買ったら人生がよくなりそうと思わせるようなタイトルのものを売ればいい。思い即かなければ、売れているnoteをリサーチすればこういうのが需要有るんだということがわかるから、それらを観察しよう。
後はとりあえず、万垢になってそこからスポンサーを募集して、プロフにスポンサーのリンク載せているだけで稼ぐという方法もある。ただの広告ビジネスだけど。
これが一番簡単かな。
どの道、コアなファンを作るかフォロワー数を多く囲うかのどちらかは必要になるね。この両方を攻めることが長きに渡り繁栄をもたらす条件だから、マネタイズよりも場を作ることが大事。
コアなファンを作り、ある程度のフォロワー数を囲うとマネタイズとかいちいち考える必要はなくなる。どれかを有料にすればいいだけだから。
そういうツイッター運用を意識してやってほしいかな。
ということで、今回は終わり。
適当にフィードバックよろしく!
3話:2種類の読書法とその使い分けについて
さて、第三回目だね。
今日は読書をテーマに書いていく。多くの人の発信内容がつまらなく、情報発信で他者を引き寄せることができないのはおそらく根本的に勉強法に問題がある。つまり、頭が良くならないような勉強をしてしまっているのだ。
そこで多くの人がやっている勉強でかつ情報収集に使うのが読書だ。今回は読書の正しいやり方を伝授しようと思う。
と言ってもぼくは普段本はあまり読まないが、何も発信するネタが思い即かないとか頭を良くしたいみたいに考えている人は読書を活用するのも良いだろう。
最近、ぼくも読書を取り入れようかと考えているので、アウトプットがてら書いていく。読書にもやり方が二種類あり、目的によって使い分けた方がいい。
スポーツでも同じだろう。サッカー選手はボールだけ蹴っていればいいってもんじゃない。筋トレしたり、走り込みしたりというように時期によって、練習メニューを使い分ける。
試合直前は試合を意識したボールを使う練習がメインだが、十分に時間があるときはボールは使わず、体力作りのための走り込みメニューがメインだったりする。このように読書も目的によって読み方を変えることで、効率よく成長することができる。
まず1つめの読書法から。これは頭を良くするための読書法でじっくり一冊の本を熟読するといったやり方だ。選ぶ本としては哲学書みたいなすぐには読み終わらないような本がいい。
こういった今のじぶんのステージでは理解不能な本を読むことで頭は良くなる。内容としても抽象度の高いことばかりが書かれているから、すぐには理解出来ないはずだ。
多くの人は理解不能な本なんて読んでも何も意味が無いという発想になるのだが逆だ。
理解不能な本を理解していく過程で頭は良くなるので、今のじぶんのステージでスラスラ読めてしまう程度の本では人生は変わらない。読書で人生を変えようと思ったら、一冊の本を熟読するといった訓練は必要だ。
そして、哲学書などに書かれていることは知識を覚えるという意識では読まなくていい。とにかく、考えるのだ。抽象的なことをじぶんの中の具体的な情報と結びつけて、この人の言っていることをどうにかわかりやすく自分の言葉で説明できないかをひたすら思考する。
知識は全部忘れても良いので、頭を働かせて考えながら読むのだ。
ぼくも時間的に余裕があり、頭をよくしたいなと思ったときには哲学書や古典を熟読して、じぶんの脳内にインストールする。ダウンロードと違い、インストールにはそれなりの時間がかかるので、長い時間考えたり、反復して読み直したりみたいな多少の根気は必要だ。
抽象的なことをじぶんの頭でどのように分解して具体化するか考えている時に頭はよくなり、そうやって時間をかけて思考したものしか、突発的にパッとは出てこない。文章が書けないとか話すネタがないみたいなことを言っている人は極論、考えていないのだ。だから、引き出しにストックされているものがなく、瞬間的に何も出てこない。
脳内の引き出しとして機能するのは暗記して貯蔵された知識ではなく、思考した結果、じぶんの中で自由自在に抽象と具体が行き来できるよう体系化された概念だけだ。
多くの人は読書をしているのに、なぜ話せないし、書けないのか?それは読書の最中に瞬間的に知識を暗記したが故に頭が良くなった気がして気持ちよくなっているだけだからだ。
だから、その場しのぎのアウトプットしかできず、一年後も生きた知識として活用することができない。感覚的に気持ちよくなっている時というのは頭はよくなっていないので、ここは気をつけた方がいい。脳内で葛藤しているときが成長している時なので、わからない問いに対して必死に考え、答えが出ずに、頭が気持ち悪い状態の時に脳は進化している。
読書して毎日気持ちよくなっている人は一年後も全く頭はよくなっていないので、注意が必要だ。いやいや、頭よくなっていますよ!みたいな反論がたくさんきそうだが、それは知識量が増えたからそのように錯覚するだけで、単純に新しいポケモン100種類覚えました!と自慢しているのと同じだ。
覚えたとことで頭自体は良くなっていないだろう。その100種類のポケモンを人生でどのように使うの?って言われた時に説明できなければ、何の意味も無い。
これらは残念ながら死んだ知識として墓場に埋葬される。学生時代に点数取るためだけに一夜漬けで暗記した数式や古典単語は全部忘れたでしょ?
このように思考して脳内の情報と結びつけた知識でないと、引き出しとしてストックされないので、詰め込み式の暗記は長い目でみたら無駄だ。
だから、読書が趣味な人はこういう読み方を1日30分でもいいからやってみてほしい。1年後には見える世界が変わってくるからね。
この辺で次のもう一つの読書法に移る。
この読書法はすぐさまツイートやブログ記事としてアウトプットする情報が欲しいという場合に使える。即効性があるので、いわば1つ目の読書法が受験勉強のための勉強で2つめの読書法が定期試験のための勉強みたいなイメージ。
もちろん、定期試験のための勉強だけをすると全て取りこぼすので、長い目でみたら無駄になるんだが、受験勉強のための勉強を取り入れることで即効性の情報も取りこぼさずに済むのだ。
今のぼくは平均的な人よりは土台が固まっているので、最近はこっちの読書法ばかりやっている。この読書法とは事実が列挙された本を広く浅く読むというやり方。つまり、いろんな人と話すときに「あー、それ知ってる!」という状態を作るためだ。
またはつなげる情報のバリエーションを増やすために、知識を浅く広く取るのだ。ある程度知っていることであれば、すでにじぶんが持っている情報と結びつけて即興でストーリーを組み立てることができるようになるから、浅くて良いからいろんなことを知ることもまた大事。
ぼくがキーワードさえあれば、そこから派生させられるのも、割と幅広く物事を知っていて、それらをつなげているから。
知らないものはどう頑張っても繋がらないので、「あー、それ知ってる!つまり、それはこういうことだよね?(じぶんの持っている情報で言い換える)」をやると、話をいろんな方面へ展開できるようになる。
でも、これが知識が皆無で何も知らない話だと「え、それ全然知らないんだけど。。。。。。。」というように広がっていかない。
ぼくも流石にロシア語についての考察とかはできないよ。笑だって、そもそもロシア語なんて知らないから、じぶんの持っている情報とつなげようがないから。
どんな物事でも詳しくはないけど、ある程度知っているという状態を作ることで情報同士を結びつけることさえできれば、まるで何でも知っているかのように振る舞うことができる。この状態を作るために、幅広くいろんな知識を知っておこうねって話。
多くの読書家の人達は二つ目の読書は熱心にやっているように思う。つまり、知識量が多く、知っていることの範囲は広い。メンタリストなんちゃらさんとかがそのような感じ。
でも、一つの目の読書法でしっかり一冊の本を熟読して頭を良くするという作業も普段からしておかないと、具体と抽象の行き来ができないからつなげるという作業ができない。
だから、覚えた知識をそのまま言うことしかできなくなるのだ。メンタリストなんちゃらさんの話はタメにはなるけど、面白くはないでしょ?でも、ぼくの記事はおもしろいし、タメになるでしょ?笑
こういう違いが出てくるんだよね。
まぁ、メンタリストさんは知識をぶん回したビジネスで成功しているから彼は賢いんだけど、知識をぶん回してビジネスをやるという結論に行き着いたのは彼の思考力のおかげだから、彼に感化されて知識だけを吸い取っている人はせいぜい物知り止まりかな。
それ知ってる!と言えるだけで、その知識を用いておもしろいストーリーを組み立てることはできない。知識ももちろん大事だけど、それらをじぶんの情報と結びつけて、展開する力がなければ、オリジナルのものにはならないから、意味がないんだよね。
読書も深める読書と浅く広げる読書の両方をすることで世界は広がり、人生は変わっていく。というか、段々おもしろい人間になっていくね。
勉強法間違えると、つまんない人間、もしくは浅いことしか言えない人間になるので、読書をメインの勉強にする人は今日の記事を参考に戦略を組み立ててみてね。
ということで終わり。
では!
4話:ケッキング山田流無敵の継続術
さて、4回目だ。
今日は継続について書いていく。
前回は読書についてとそれに関する学習について書いたが、今回のテーマはいかにして継続していくか。
継続さえすれば、大体のことはうまくいくのだが、ほとんどの人がこのシンプルでかつ本質的なことができない。振り返ってみれば、文章に関してはぼくもただ継続しただけだ。ほんとうに全くの0からスタートしたので、継続以外に思いたる要因がない。才能がどうのうこうの言えたらかっこいいかもだが、ぼくには才能は備わっていなかったからそれはない。
実際に、3年前は全く文章書けなかったし、今も別に書けるようになったとは思っていない。ちょっとマシになった程度。まだまだそんなレベル。
いろいろ文章に関して質問は来る。どうすればおもしろい文章を書けるようになるか?おもしろいアイディアを生み出す方法みたいなのこともよく聞かれるし、こういう企画でもテーマとして扱うこともあるが、結局コアにあるのは継続だ。
ぼくは最も大事なことは継続であると思ったから、そのために結果を捨てた。何かを得るには何かを捨てなければならない。その代償に、いずれトップを取るために、ぼくは目先の利益を全て捨てた。
多くの人は何ヶ月以内に結果を出しました!みたいないかにじぶんが早く結果を出したかでマウントを取るが、ぼくはそれを捨てた。時間はどれだけかかってもいい。とにかく毎日文章を書き、あきらめることをあきらめる。
つまり、退路を絶ったのだ。
目標設定をするからそれを達成できなかったときに苦しくなるわけであって、ダラダラ継続して、とにかく挫折しないことを優先順位の一番上にもってくれば、ライバル達が勝手に消えていく。
ぼくは3年以上前から文章を書き続けてきて、最近になってようやく何十人かはおもしろいと言ってくれて、毎日ぼくの文章を読んでくれる固定読者がついたが、最初の2年くらいは誰にも読まれない中、ひたすら書いたり、勉強みたいなのを繰り返した。
普通の感覚ではここで損切りしたり挫折したりすると思うのだが、ぼくは最初から長い目で物事を見ていたし、ぼくの目標はお金を稼ぐ事ではなく、継続すること。
お金はあくまで付録。おもしろい文章を書いて、そこに人が集まっていれば、価値を生めているということだから、マネタイズなんて人が集まってからすればいいと思っていた。
ぼくは文章の可能性を感じたときに、文章というのはこれから一生書き続けるものだから、たかが最初の数年焦ってもしょうがないなと思い、とにかく書くことを習慣化したのだ。
まぁ、毎日書いていれば、自然とうまくなるだろくらいのノリ。今もそのスタンスは変わっていない。別に結果が出なくても、フォロワーが増えなくても関係ない。続けていたら、消去法でライバルは確実に消える。
そしたら、最後に立っているのはぼくだけになり、必然的にぼくが上に行ける。それくらのノリだから、モチベーションも全く落ちない。だって、結果を出そうとしていないんだから、そもそも落ち込むという発想がない。
落ち込むのはじぶんへの期待値が高いからであって、「これだけ頑張ったのだから結果が出るだろう」という思い込みが裏切られたときに人は落ち込む。
つまり、落ち込まないためにはじぶんへの期待値を下げればいい。「頑張るけど結果は出なくてもいい」「毎日続けることを楽しむ」こういう意識に切り替えられたら、継続に関しては全く苦しくなくなる。
ぼくが今こうして、ほとんど毎日文章を書いているのはぼくが書いた文章を見てくれている人にじぶんの考えを伝えたいからだ。
コミュニティというのも継続の負荷を減らすために作っている。じぶんの書いた文章を喜んで読んでくれる人が一人でもいたら人は頑張れる。読者がいれば何か書きたくなるから、ぼくがコンテンツを作るときはフォロワーを巻き込んで必ず参加型にする。
そうすれば、自然と書けるということがわかっているから。
自転車を下り坂からスタートさせれば、じぶんのエネルギーを使わずとも自然と自転車は坂を下っているだろう。またがっているだけで自然とこぎたくなる。文章でもそれを表現すればいい。
環境を作るだけで、自然とアイディアが降ってくるから書けるのだ。どうやって、アイディアを生み出すのですか?みたいな質問はよくくるが、ぼくの感覚としては脳内からひねり出しているというよりはコミュニティから召喚している感じ。
コミュニティとは下り坂である。下り坂を設置すれば自転車は勝手に動き出すように、コミュニティを設置すれば手は自然と動きだし、3000字程度なら自動で生産できる。フォロワーと密にやりとりをすることで「次にこういうの書いたら喜ぶだろうな」というのが感覚としてわかってくるからだ。
そういう漠然と空間にあるアイディアの塊みたいなのから一部を引っ張って
ぼくが文字に起こして召喚しているだけ。
この企画のモニター生も長文でフィードバックくれる人も何人かいるし、
文章を書くことが苦手なのに、フィードバックならスラスラ書けました!
と言ってくれた人も何人かいる。
それはぼくがモニター生に下り坂を提供したからだ。自分1人で無の空間からアイディアをひねり出そうとしたら、莫大なエネルギーを必要とするので、何かきっけを与えるのだ。
ぼくが何か記事を書き、その記事を元にフィードバックを送ってもらうやり方だとそこまで負荷がかかることなく、文章を書けるから、モニター生も成長できるのだ。これは決してポジショントークで言っているわけではなく、ぼく自身もそうやって文章の練習をしてきたからだ。
考えても考えてもアイディアなんて降ってこないから、ぼくは発信がおもしろい人のメルマガを読んで、それに毎回返信して文章を磨いていった。
これをすることにより、自然とインプットとアウトプットの両方ができて、しかもそれを毎日楽しんでやっていたら勝手に文章力が上がっていたという感じだ。
結果を捨てて、成長に全フリしたのだ。
そして、「じぶんでももうコミュニティを作れるな」とある時悟ったから、
行動に移して今があるという感じ。
つまり、車を動かす時にもエンジンをかけるという作業さえすれば後はアクセル踏んでいるだけで勝手に動くように意図的に文章を書く時のトリガーさえ作れれば、継続することも難しくはない。
ぼくにとってのそのトリガーはコミュニティの存在であり、フィードバックをもらうということだ。そして、企画のモニター生には彼らが文章を書くというトリガーはぼくが与えている。
だから、返信率はめちゃめちゃ高いし、それだけで文章を書く練習になると思う。じぶんで何か考えて下さいと漠然としたことを言われたら、かなり返信しにくいと思うのだが、ぼくがきっかけを与えることにより脳にかかる負荷を下げ、返信のハードルをグンと下げることができるのだ。
継続とはこのように目先に結果を捨て、成長に全フリする意識とじぶんの活動に他者を巻き込むことで楽勝になる。結果とは意識して出そうとするのではなく、継続していたら勝手に結果に繋がっていたという感じが理想。
ぼくはコンテンツを日々積み上げるという意識で文章を書いていない。
毎日送られてくるフィードバックを読みながら、何か読者に学びを還元したいという思いの元、楽しくコンテンツを作っていたら、結果的に積み重なっていたという感じ。
このようにぼくは毎朝、今日の積み上げハッシュタグをつけて気合い入れなくても楽しく負荷もなく継続出来るので、長期戦ではかなり強い。
結果を出そうとしていないが故に、焦りが生まれないからだ。継続することしか考えていないから、来年はもっと進化するし、再来年はさらに進化する。これが毎年続くし、書いた文章はアーカイブとして残るから、使いようによっては資産化できる。
これがぼくが考える最強継続戦略。周りがモチベーションの低下と共に勝手に失速していくのを待つ。その間、じぶんは楽しく成長するのだ。
文章で勝負しようと思ったら、毎日コンテンツを出し続けることはできて当たり前なので、「継続」の攻略は必須になる。
だから、上記に書いた方法を参考にして、ぜひあなたも「継続」という概念を攻略して欲しい。
そういえば、日本一のYouTuberのはじめしゃちょーも言っていた。
「目標がお金だと続かない」ってさ。
疲れたんで、終わり。
では!
5話:アイディアとユニーク性、クソツイッタラーについて
さて、今日は最終回だ。
最終回はアイディアを無限に生み出す方法をテーマにしていこうと思う。
このテーマではこれまでも何度も書いてきたのだが、結局これができないことにはコンテンツビジネスをすることは不可能なので、いろんな角度からこれからも何度も伝えていこうと思う。
これができるようになれば、唯一無二の存在になれるし、出すコンテンツが全部おもしろくなるから自然と人が集まってくるような状態が作れる。
つまり、継続なんて意識しなくても楽しく文章を書いているだけで、集客ができてしまうのだ。この記事を読んで「なるほど、そういうことね」で納得するだけではできるようにならないから、感覚をつかめたら、失敗してもいいからどんどん実践していってほしい。
では、書いていく。
まず、アイディアとは何なのか?多くの人が考えるアイディアは無の空間から突発的にひらめくものみたいな認識だと思うのだが、これは違う。もちろん、突発的にひらめく時もあるが、それを毎日100発100中で狙ってやるのなんて不可能に近い。
アイディアとは既存のもの同士の組み合わせによって生まれる。
第四章の記事を例に取ると、下り坂=コミュニティと定義しただろう。一見、これだけを見ると意味がわからないが、意味不明な者同士の組み合わせでうまくロジックを合わせられないか?ということを考えることがおもしろいコンテンツの作り方だ。
意味不明なもの同士がつながり、そこに電気が通ったとき、人はおもしろいと感じる。コミュニティの話は有名インフルエンサーもしているし、最近はコミュニティの時代だ!なんてことも言われていて、コミュニティのことをぼくがそのまま話しても何もおもしろくない。
どのような工夫を施せば、コミュニティというありきたりな話題をおもしろく料理できるのかと言うと、一見繋がりそうにない意味不明なものを持ち出して、無理矢理ロジックを合わせるのだ。
ぼくはそれを下り坂と自転車の例を出してコミュニティの話とつなげたから、読者はそんな風につながるのかぁと感銘を受け、おもしろいという判断を下すのだ。(もちろん、全員ではないけど)
そう、良い意味で読者の期待を裏切るのだ。つなげるものは離れていれば離れているほどいい。
ありきたりな比喩や少し考えれば誰でも繋がりそうなものだと読者は驚かないし、そのようなものにおもしろいとは思わない。
とにかく、ほとんどの人が持っていない視点を提供するつもりでコンテンツを作る。じぶんに持っていない視点を提供されるから、読者はおもしろいと思うのだ。
自己啓発本が長きにわたり売れ続けるのは大衆はぶっ飛んだ人のストーリーを消費したいからだ。大衆が見たら、「え、なんでそんな行動を取るの?」「リスク高すぎじゃん」みたいなことを平気でするんだけど、それが結果に繋がったとき、「こんな風にストーリーが繋がるんだ」と人々は驚き、人はそのストーリーに夢中になる。
これが自己啓発の正体であり、「そう繋がるの!?」みたいなとこを売っているのだ。どん底に落ちて、挽回までの道筋が見えない状況から這い上がってくるからおもしろい。
漫画とかもそう。どんな漫画も大体主人公が絶望的な状況に一回は落ちる。
だけど、そこから奇跡的な事が連発して復活を成し遂げていくだろう。そういう大衆が予想できないつながりを演出することで人々はおもしろいと感じる。
これがうまいなと思ったのがレペゼン地球だ。
彼らは借金を数億円抱えているのにも関わらず、YouTubeに広告収益をつけない。それどころか赤字を膨らませてまで、ドーム公演をやろうとする。
普通に考えたら、YouTubeに広告つけて借金を返済していったらいいじゃんと誰もが思うのだが、彼らはそれをやらないから人々は「え、なんで?」
となり、彼らについていろいろ考えている内に結果的にハマってしまうという。狂ってるから彼らはおもしろいのだ。
普通じゃない。裏の意図が見えないからこそ人々は夢中になる。
今の時代は合理的なものはつまらない。
ネットビジネスではこうすれば成功出来ます!みたいなノウハウはありふれていて、みんなが同じ情報を手にして、同じことを実践する。が、それは結局競争の世界で作業的要素が強いので、結果は出るかもしれないが、そんなものに人々は熱狂しない。
ツイッターであいさつ周りやってフォロワー増やしました!みたいなこと言われても、「ふーん、結果出て良かったね」というくらいにしかぼくは思わない。どう頑張っても熱狂はできないのだ。
それは単純につまらないから。
戦略は何でもいいから、とにかく夢中にさせるのだ。むしろ、ぼくはぼくに予測がつかない戦略で人生を切り開いていっている人を見るのがものすごく楽しい。ありきたりな方法でお金稼いでウェーイ!みたいなのは反応としては「すごいね!」で終わり。すごいけど、熱狂はしない。
狂ってるのに、そこにつじつまが合うからこそおもしろいのだ。
ぼくも文章ではそれを意識している。いかに意味不明な組み合わせを演出して展開できるか。それをひたすら考える。
もちろん、ほんとうに意味がわからなかったらダメだが、納得できるように説明して繋がったとき、それはおもしろいコンテンツとなる。主張自体はありきたりでいいから、いかにして別世界のものとつなげて、ロジックを合わせられるか。これが全て。
インプットしたことをそのままアウトプットするだけではダメ。これはみんなやるから差別化できない。あなたの知性により、異世界からオリジナルのものを引っ張り出して、主張に盛り込むのだ。
そうやって、オリジナルコンテンツというのはできる。これは究極の差別化方法だし、練習さえすれば誰でもできるので、とにかく意味不明な組み合わせにつじつまを合わせるということを意識して日々の発信に取り入れて欲しい。
ためになることは言わなくていい。狂っているあなたの主張を正しいと思わせればいいのだ。だれかが言っていることの引用ほどつまらないものはないから。
これがおもしろさの正体。
なんか、いろいろ書いたけど、このnoteがツイッター運用の教科書ってこと
すっかり忘れてたので、最終回らしく最後はツイッターの本質的なことを書いてしめようと思う。
時代が進めば進むほど、より本質的なものが求められるようになる。
つまり、面白い人は浮上してくるし、つまらない人はオワコン化する。
これはYouTuberを見ていても思う。
面白い人や才能ある人がどんどん出てきて人気になっているのに対して、昔人気だった人でも面白くなければ、落ち目になっている。
ツイッターでもこの流れは変わらない。リプ周りなどの小賢しいテクニックでもフォロワーを増やすことは確かにできる。だが、大事なのは質だ。
この人の発信が面白いから見たいという風に思われないとダメ。
毎日、面白いコンテンツを出し続ける。それが自然と口コミで広がっていく。この流れが理想。
フォロワーの質を分析してみても、じぶんからフォローしてフォロワーになった人達の質はものすごく低いが、引用RTなどの口コミを見て、ぼくのフォロワーになってくれた人達の質はかなり高い。
前者はただ繋がっているだけでぼく自身に興味はない。ツイートに脳死でいいね押されているくらい感覚的にわかる。
だから、口コミをうまく利用するのだ。この人は面白いからみんなに見て欲しい。そう思われるような魅力的な人になれれば、何をやってもうまくいく。
多くの人はじぶんを売り込もうとしすぎている。そういう思想はバレバレなので、ずるいことは考えずにどうしたらフォロワーにおもしろい存在として認知してもらえるだろうかというのをひたすら考え、ツイッター運用に取り込んで欲しい。
ぼくは多くの人がノウハウをnoteで販売している中、コンテンツを企画にしてフォロワーと共に作るというポジション取りをして、まだ認知度は少ないがユニークな存在にはなれたと思う。それは単純にやっている人がいないというのもあって、おもしろそうというのが一番の要因だろう。
しかも、これは形を真似たところで同じことは再現できないから真似したいとも思わないはずだ。
毎回、即興でストーリーを作る力が試されるし、思考の蓄積がものを言う勝負なので、このポジションはなかなか奪われないと思う。
まぁ、仮に形だけを真似されていろんな人がやり出しても大丈夫だ。
なぜなら、この企画というのはケッキング山田が記事を書くから価値が宿るのであって、おもしろくない人がやっても価値を生めないので、まさに「誰がやるのか」の勝負だ。
誰でもできることはやらなくていい。
あなたがやらないとダメだとフォロワーに思われるものをどんどんやっていこう。それがユニーク性だからだ。空いたポジションはまだまだたくさんあるし、ツイッターには量産型くそつまらんツイッタラーだらけなので、毎日思考訓練を重ね、あなただけのオリジナルコンテンツを召喚できるようになったとき、勝手に有名になっていくから、本物の力を手にできるよう、時間はどれだけかかってもいいから頑張って欲しい。
では、ここまで長い文章を読んで下さりありがとうございました!
これで第四弾の企画は完結です!
=================
メルマガ限定の濃い情報と登録特典のプレゼントは下記リンクから受け取れます。https://cyan376886.studio.site
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
