
人を虜にする文章術伝授企画
どうも、ツイッター上で「文章だけで世界を創る」をコンセプトに活動中のケッキング山田です。自己紹介的なのはだるいんで、全部カット。ぼくはそういうタイプじゃないし、実力で示すんで、さっそく本題へ。
企画第二弾スタート。
前回の企画第一弾は合計で900RTくらい、いったからそれなりに反響はあったように思う。(画像のは3日でbanされたときのやつ)
企画第一弾は会員サイトに載せてるので、ツイッターのプロフからメルマガ登録すると見れるから、このnoteがおもしろかったら第一弾もぜひ、のぞいてみてね。
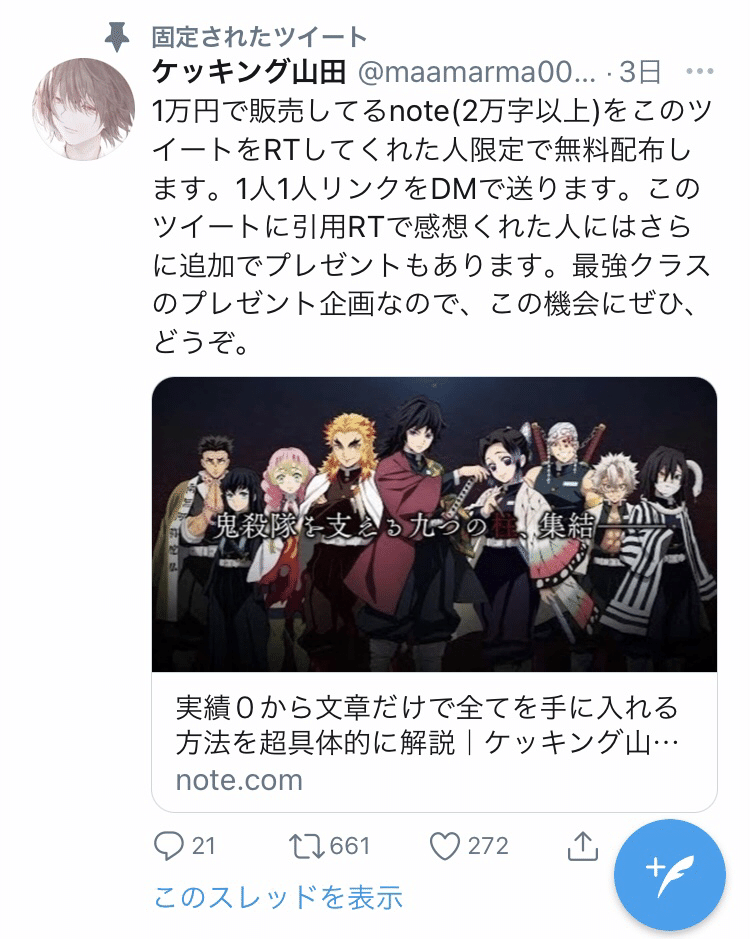
今回の企画はそれの続編だ。
人に読んでもらうような文章をいかにして作るのか。そのための思考法や具体的にどのような訓練をしていけばいいのか?また、それをどうやって実践していけばいいのか?という部分を深く切り込んでいった。
今回も前回同様15人くらいのモニター生を囲って、フィードバックをもらいながら作成したから、かなりよいものとなっているはずだ。単純に読みものとしてもおもしろいので、ぜひ読んで頂きたい。
前回も数え切れないくらいの感想メールが届いたけど、それを使って、いちいち宣伝しなくてもぼくの書く文章がおもしろいということは上記の600RTの画像だけでも十分に伝わると思う。
だから、前書きではじぶんのnoteがいかにおもしろいかという宣伝はしない。その代わり、このnote作成に大きく協力してくれたモニター生を紹介しようと思う。彼らの協力なしではこのnoteは生まれなかった。
るあちゃん(https://twitter.com/rua_iq)
高IQ界隈の子かな。この子が毎回一番長いフィードバックを最速でくれたし、アドバイスもたくさんくれた。ありがとう。

ひろさん(https://twitter.com/suraimu602)
ぼくの第一弾のnoteを写経してくれるレベルで絶賛してくれる、褒め上手な方。彼もまた毎回熱心にフィードバックをくれた。ありがとう。
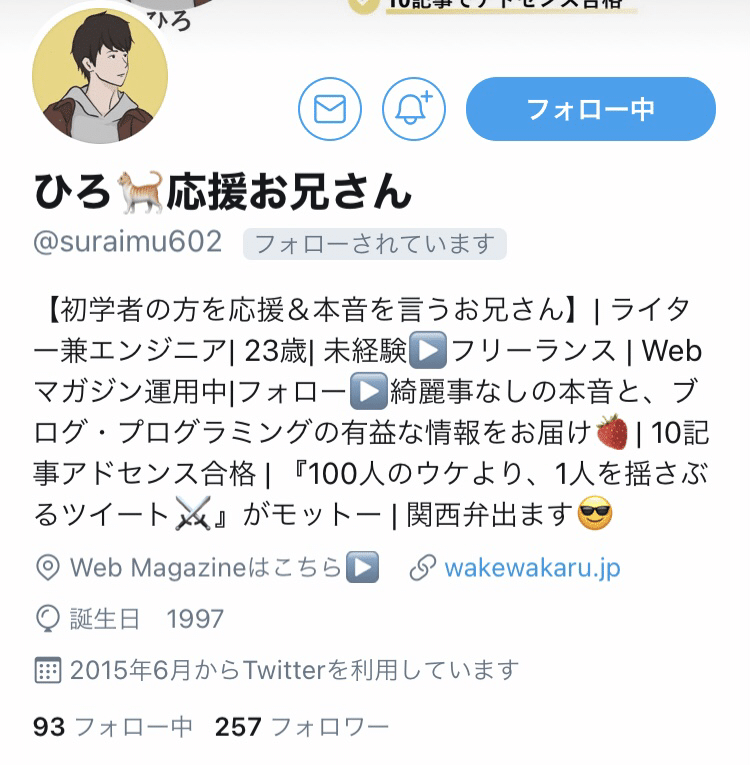
みやくん(https://twitter.com/miy_zw)
ぼくがフォロワー1000人くらいの時から見てくれてる超古参ユーザー。読者数人の時の第一回レポートも読んでるレアキャラ。ぼくの出すほぼ全てのコンテンツにフィードバックくれてありがとう。

あかりさん(https://twitter.com/STUjya)
この子もみやくん同様超古参ユーザー。ぼくの第一回レポートの頃からの購読者。前回の第一回noteではぼくの秘書を務め、支離滅裂なところの訂正とフィードバックを熱心にくれた。ありがとう。

アキさん(https://twitter.com/aki_hackman)
前回の一回目のnoteでも紹介したぼくと同じ属性のインフルエンサー。彼も毎回ぼくのnoteにフィードバックをくれる優秀なツイッタラーだ。彼とはよくツイキャスもする仲なので、暇な時はぜひ見に来て欲しい。熱心にフィードバックいつも、ありがとう。
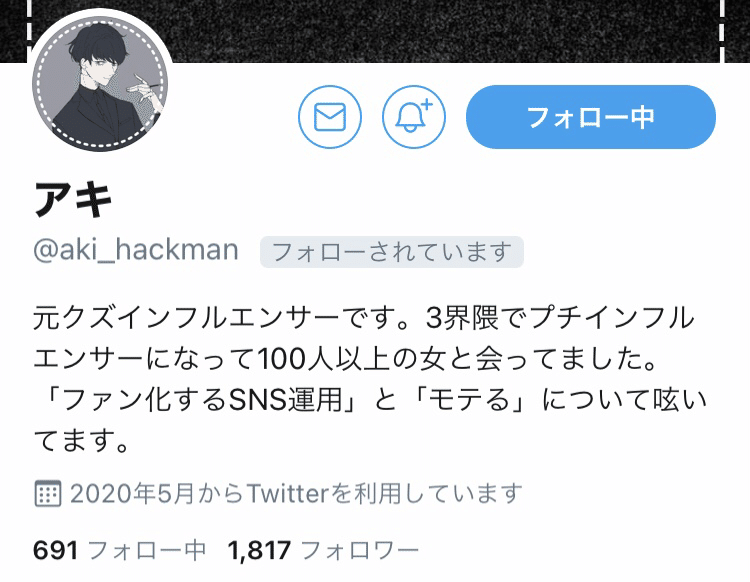
まそらくん(https://twitter.com/__masora__)
上記のアキさんとのキャスで出会ったプログラミングとマーケティングの二刀流の高校生。これからの成長が楽しみな高校生だ。最近仲良い。フィードバックくれてありがとう。

dragonさん(https://twitter.com/dC3eEaWfd0z4Ug5)
第一回目のnoteの企画でぼくの読者になってくれた割と新しめのメンバー。
彼もかなりの速さでフィードバックをくれて、いつも参考にさせて貰って非常に助かっている。いつも、ありがとう。

たなぼたさん(https://twitter.com/tanabota8739)
たなぼたさんも初期メンバーだね。第二回目のレポートからずっと見てくれているし、ぼくの出すコンテンツを毎回楽しみに待ってくれ、感想メールもよくくれる。いつも、ありがとう。

いっちさん(https://twitter.com/IfThenMaker)
いっちさんも最近知り合った。第一回目のnote企画がきっかけかな。しっかりぼくのダメなところは指摘してくれ、正直な辛口フィードバックをくれる信頼性のあるツイッタラー。いっちさんのアドバイスで実際にコンテンツの何カ所かは修正した。非常に感謝している。ありがとう。
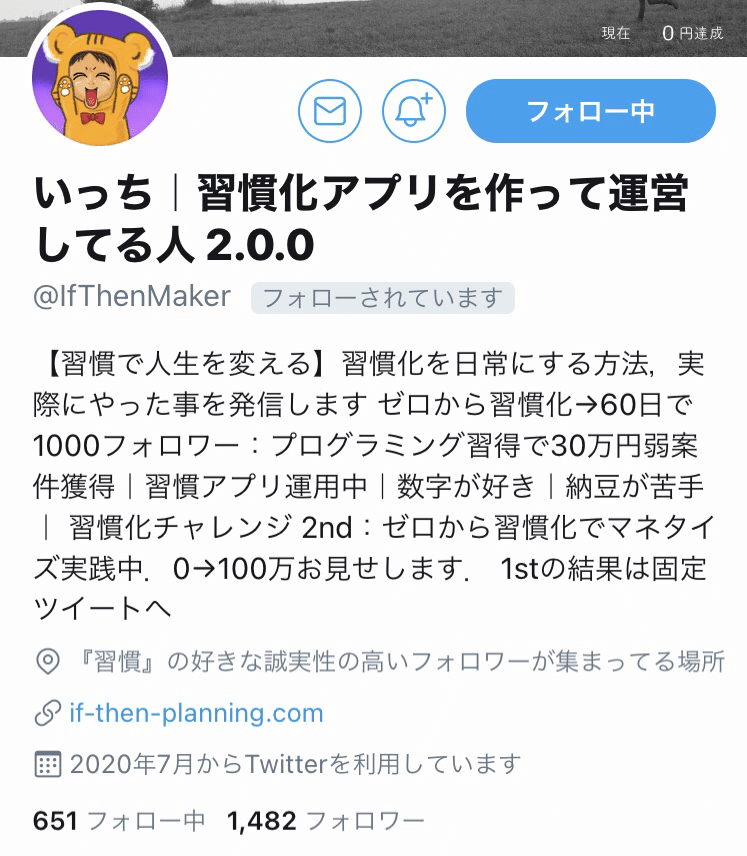
ふあさん(https://twitter.com/fua2020make)
彼も最近知り合ったメンバーだね。第一回目のnoteの企画から。DMでも気軽に相談してくれて親しみやすい方だ。準備中とのことなので、これからの活躍に期待だ。いつもフィードバックありがとう。

らくさん(https://twitter.com/rakuraku_18)
彼も一ヶ月くらい前につながった割と新しめのユーザー。まそらくん同様、高校生マーケッターだ。可能性に満ちあふれた。期待大の高校生。フィードバックありがとう。
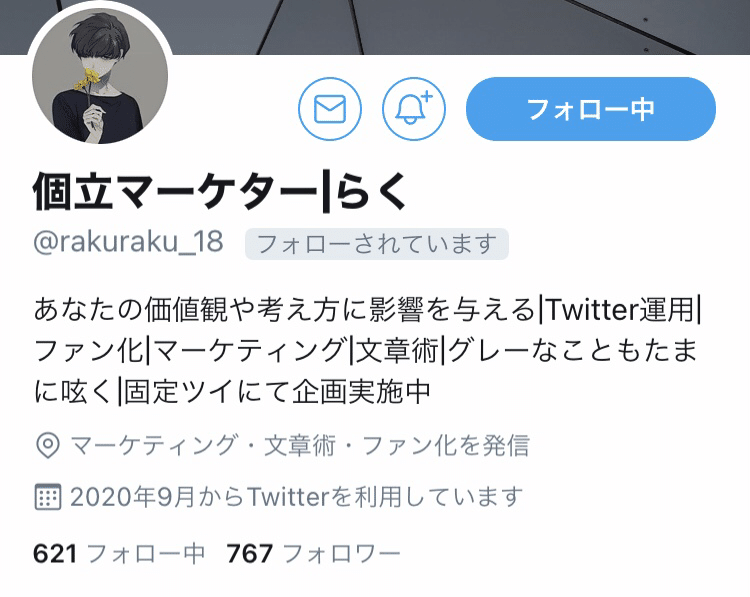
5階の佐藤(https://twitter.com/nemunemu_neet)
最古参ユーザー。ぼくが第一回レポートを出す前からなぜかぼくのことを見ていたらしい変態。クソみたいなフィードバックしかくれないが、ぼくの周りの強キャラにかわいがられている謎の人物。彼の今後の活動に注目。
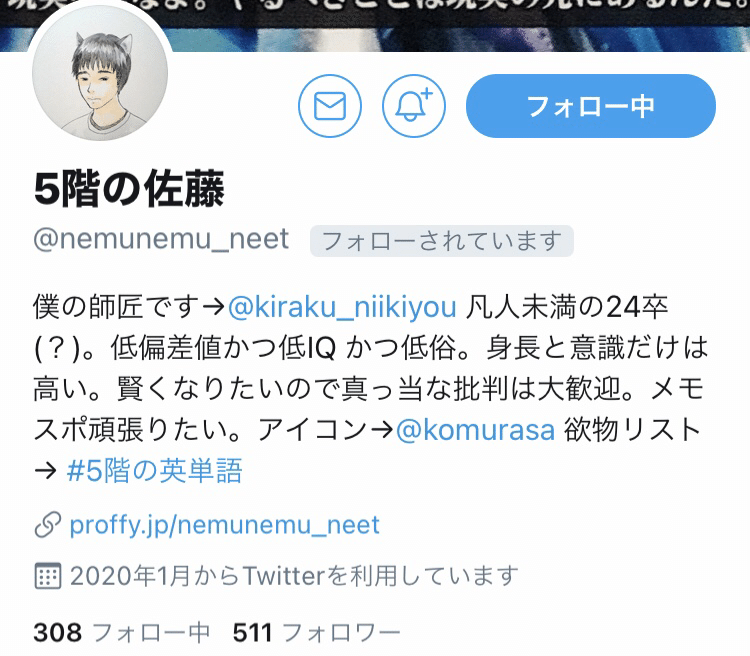
上記に挙げた人達がフィードバックをくれて作成されたので、いいものになっているはずだ。
ぼくが書きたいことを書いたわけではなく、こういうことを書いて欲しいという需要を潰しながら書いていったからね。
頭が良くなる思考法や人にスラスラ読んでもらえるような文章術はこのnoteを読めばわかるはずだ。
では、前置きはこれくらいにして、ここから先は興味のある人だけ進んで欲しい。では。
一話・無料コンテンツのカラクリと0→1より重要なこと
さて、第二回目の企画スタートだ。
と言っても、内容は今の段階では全く考えていない。モニター生が素晴らしいフィードバックをくれたので、それを元に全五回にまとめて作り込んでいこうと思う。
前回の続きとか考え出すと、ごちゃごちゃするので、一端頭を真っ白にして
また0からスタートする。(じぶんの書いたレポートを読み直すのはめんどい)前回のnoteでは視座の高いツイートでフォロワーを集める。そして、集めたフォロワーでコミュニティを作って、何か企画でもやれば、何でも売れるよという話だった。
実際にぼくが体現しているから机上の空論ではない。
このnote作成もミニ企画みたいなものだ。15人くらいのモニター生を囲って、彼らからフィードバックをもらうことでコミュニティという場からコンテンツは生み出される。
コミュニティから生み出されるコンテンツというのは他者からのエネルギーを利用してるから、情報に莫大なエネルギーが詰まっており、人々の心に突き刺さる文章に自然となるのだ。パズルのピースをフォロワーからもらって、ぼくがそれをはめ込んでいく。そして、完成品がコンテンツとなる。
まぁ、フォロワーにパズルのピースを与えてでも、この人の文章が読みたい
と思ってもらえるような存在にはならないといけないが、そのために視座の高いツイートをして、なんかおもしろいなと思ってもらえるような存在になろうということだったね。
もちろん、コミュニティから召喚されたコンテンツを無料にするか有料にするかはその人の気分次第だが、最初の方は売ることよりもじぶんのコンテンツをより多くの人に消費してもらい、ケッキング山田の書く文章はおもしろいんだぞ!ということをアピールした方がいい。
売る前にそもそも知ってすらもらえてなかったら土俵にすら立てないからだ。だから、まずは稼ぐとか考えずにじぶんの遺伝子をネット上にばらまくことだけを考えればいいのだ。
米津玄師が売れて、ライブにたくさんのファンを集めることができたのも無料でYouTubeでハイクオリティの曲を公開したからだ。
lemonが最初から有料だったら、何億回も再生されることはなかっただろう。ビジネスでも同様にじぶんの持っているコンテンツの99%以上は無料で出すのだ。
成功するかはどれだけサービス精神が旺盛かにかかっている。
飲食店でもそう。売れているお店は無料のもののクオリティが高い。
グラスや水、トイレの綺麗さこれらへのこだわりが強いのだ。
逆に売れない店というのは「どうせ、無料なんだし適当でいいだろ」
といった姿勢でビジネスをやっている。
だから、うまくいかない。コミュニティとしての価値が下がっているのだから、誰もその価値の低い場でお金を消費したいと思わないからだ。無料のコンテンツと有料のコンテンツは別物ではなく、つながっていると考えた方が良い。無料のコンテンツのクオリティが高ければ、自然と有料のコンテンツも高いと思ってもらえるし、当然逆もしかりだ。
無料がゴミなら有料もゴミだと思われる。
イメージとしては無料のコンテンツで貯めた信頼を有料コンテンツに還元する感じだ。だから、そもそも無料のコンテンツで信頼を貯めることができなければ、有料のコンテンツに還元されない。
YouTubeは莫大な動画を無料で提供することで信頼を得てるから、一部の人々が「広告を外す」というパズルのピースを埋めるために課金してくれるのだ。
ほとんどの人はパズルの全体像の半分以上を隠している。30%は無料で出すけど、70%は有料で!みたいなことをやっている。70%も隠れていたら、そもそも続きが気にならないので、課金されにくいのは当たり前だ。
残りも絶対に知りたいと思わせるまで出すことが大事なのだ。ぼくの場合は無料で99%を出し、ケッキング山田の出すコンテンツは全部消費したいと思ってくれる一部のファンがお金を落としてくれるといった構造だ。
うまくいっているビジネスモデルというのは最後のパズルのピースにだけ課金させるのだ。
ここで重要なのが課金しなくても十分に楽しめるものを提供するということだ。お金を払わないと実態がわからないものに関しては出してはダメだ。一部だけ見せて、結局お金を払わないと中身がわからないみたいなことをすると、読者のフラストレーションが溜まるだけでじぶんにとっても損だ。
試食品でもしっかり本物を食べさせてあげる。そして、もっと食べたいと思ってくれた人に対してセールスをかける。この順番が正しい。
お金を取るということは先の話で大事なのはじぶんの生み出す「場」を
楽しんでもらうことだ。
課金というのは楽しんでもらった先にある。あくまで価値提供が先だ。
経営がうまい遊園地などは入場料では高額なお金はとらない。ひたすら楽しい「場」を提供し、遊園地内で課金させるのだ。
この場合は同じだけお金を払ったとしても、体感的に奪われたのか、もしくは喜んでお金を払ったのかという違いが出るから、顧客には後者のように感じてもらわなければならない。
入場料で高額なお金を取った場合は人々は奪われたと思うが、遊園地の中でいろいろ課金してもらうと、人々はお金を払っているのに満足している。
そう、いちいち売り込む技術みたいなのを駆使しなくても良質なコンテンツをそっと置いておけば、人は喜んでお金を払うのだ。
ぼくもそれは意識している。今のところ、一つの企画以外ではキャッシュポイントを作っていないし、ほぼ全部無料で出している。この企画も一応値段はつけるけど、ほとんどの人は無料で受取ることになるだろう。
読んでもらうことが目的だから、それは全然いいんだけどね。無料のコミュニティでも十分楽しいと思ってもらえればそれでいいのだ。
と、ここまでは無料のもののクオリティがとにかく大事だということを書いた。では、どんなコンテンツを出していけばいいの?という疑問がおそらく、浮かび上がってくるはずだ。
出すコンテンツがないから多くの人は「稼げる情報」という抽象度の低い
誰でも取り扱えるようなものに手を伸ばす。
実際、抽象的なものより、具体的なものの方が大衆の食いつきはいい。
だが、難しく考える必要はない。有益な情報とか稼げる情報とかビジネス的な情報とかそんなものをいちいち考えなくてもとりあえず、文章がおもしろければ何かしらの形で収益化はできるのだから。
鬼滅の刃やONE PIECEが売れているのって、有益な情報を届けているというよりかは単におもしろいから消費されているだけだろう。
小説とかも同じ。別に読んだところで人生は変わらない。だけど、おもしろいから消費される。
ぼくもこの記事ではパズルのピースと遊園地の話がほとんどを占めているし、マーケティング用語とか稼げる何かとかそんなことは何も言っていない。
有益な情報を発信するみたいなことを考える前にまずは読みものとして
おもしろくなければダメだ。いくら、役に立つ内容でもおもしろくなければ、読んではもらえないからだ。
あなたも読めば絶対に役に立つとわかっていても、広辞苑や六法全書なんかには手を出さないだろう。これらを読むくらいなら鬼滅の刃を読むはずだ。このように大前提として、「おもしろい」というのがなくてはならない。
ここが欠けているから、いくらブログを積み上げても誰にも読まれないし、
「どれだけ継続したか」を語るマインド論しかネタが思い即かないのだ。
単純におもしろい文章さえ書けていれば、人々が一定数集まった段階で、
一部有料にするだけでもお金は生み出せてしまう。
0→1を生み出すという前の段階はおもしろい文章を書けるようになり、
あなたが書く文章を読みたいです!と言ってもらえるようなファンを
1人でもいいから作ることだ。
収益化を考える前に、まずはおもしろくて読んでもらえる文章が書けるようになるのが先だ。そうすれば、自然と人は集まってくるし、有料化なんて適当でいいんだから。
多くの人は収益化ばかり考えるが、その前の段階でほとんどの人が躓いている。ぼくの場合だと別に収益化なんて考えなくても、人が集まったら何を売っても売れると思っているから、実は収益化に関してはそこまで意識していない。
人を集めることすらもできないのに、収益化なんて考えても無駄だろう。
黙って、まずはおもしろ文章を書けるようになり、無料で全部提供する。
そして、人を集める。
ここまでできて、さてどうやって、収益化しようか考え始めるくらいでちょうどいい。お金を先に考えるから、コンテンツからお金のニオイが漂い、
つまらなくどこか打算的な雰囲気が醸し出されるのだ。
最初は誰かを喜ばせるために文章を書く。
それだけで十分なのだ。
二話・おもしろい文章を書く方法とアップルの戦略
さて、今日は第二話だ。
前回の内容のフィードバックから面白い文章の書き方、またトレーニング方法についてが多いかったからこの辺を書いていく。
今日の話が理解出来れば、あなたも文章だけで人生の可能性を広げることができるから、ぜひ、脳みそにインストールして欲しい。
具体と抽象の行き来の重要性とその訓練法についても書いた。
まず、文章のおもしろさというのはクスッと笑えるようなものではなく、早く続きが読みたい。スラスラ読めてしまうけど、勉強になる。そういう文章のことをおもしろい文章とぼくは定義している。
どんなにすごいことを書いていようが、それが読みにくかったらよい文章とは言えない。すごいことが書いてある文章が読みたければ、アリストテレスの書籍でも読んだ方がいい。
ぼくらがインターネットというフィールドにおいて文章で勝負しようと思ったら、どうしてもスラスラ読ませる工夫は必要だし、なおかつ読者を飽きさせてはいけない。そして、自分自身のオリジナリティを光らせなければならないのだ。
これができない限りはあなたが売れることはない。まぁ、一時的に売れたとしても誰かと同じだということがバレると落ち目になる。それなら、最初からオリジナリティを光らせるようなやり方でトレーニングすべきだ。鬼滅の刃が売れたからと言って、同じような世界観を表現してはダメだ。爆発的にヒットした作品の二番煎じなどじぶんからデジタルタトゥーを掘りにいっているようなものだ。
ビジネスは真似が大事などと言われるから多くの人はそれを鵜呑みにして丸ぱくりをしている。だが、これは全くダメだ。正しいぱくり方というのは大枠のみを真似て、中身はじぶんで考えるというやり方だ。
売れている映画や漫画も大枠は同じだ。大枠は変わらないし、これから生まれる作品も過去の作品の大枠を真似て作られるはずだ。
人々が感情移入しやすいストーリーの型というのは昔の人が研究し尽くしているし、大体決まっているので、そこは真似た方が早い。中身を変えることでオリジナルのものになるのだから。
服を作るときもいちいちじぶんで一から手で編んだりしないだろう。そんなものは工場に一瞬で作れる仕組みがあるのだから、大人しくそこは過去の人達の努力の恩恵を受取ればいいのだ。
服でもデザインという発想力の部分でオリジナルを光らせる。
多くの人は完全オリジナルのものを作ろうとして失敗する。だが、完全オリジナルのものなんて無理だ。ぼくらが思い即く程度のことなんて、数千年の人類史の中で必ず誰かが思い即いている。数え切れないほどの天才が今も昔にも、うじゃうじゃいるのに彼ら全員が見過ごして、ぼくらがそこを拾えるなどと思わない方がいい。そんなことは不可能だからだ。
過去の天才達が素材を残してくれているんだから、ぼくらはそれらの素材を組み合わせて、オリジナルのものを生み出せばいいのだ。
組み合わせなら無限にあるから、これなら飽和しようがないし、いくらでも作れる。そこに個人の表現や感情が混ざれば、完全なオリジナルのものと言えるだろう。
というか、ぼくがやっているのは全部これだ。主張自体は誰かが言ってそうなありきたりなことだ。さっきの言葉で言うと大枠は同じということだ。
上記の例でわかりやすく説明しよう。
上にいろいろ書いたが、結局主張だけを切り抜くと、「ビジネスでは真似が大事だと言われるけど、丸ぱくりはよくないよね」ということだ。
この主張だけなら、ツイッターにいるビジネスマンは誰でも言っているし、本の目次にもなってそうなくらい、すごくありきたりな言葉だ。
もちろん、これだけを聞いて人々は驚くことはないし、そんなことを教えられたからといって、ファンになるなんてことはない。
だって、みんな言っているから。
この主張をどうにかしてオリジナルのものに変えることができないだろうか?ということをぼくは考えた。
そうして、思い即いたのが「映画や漫画も大枠は真似しているけど、中身はオリジナルだよねぇ~」「服も大枠の作り方は同じだけど、デザインの部分がオリジナルだよねぇ」というように比喩を持ち出した。
これこそが組み合わせの力であり、主張自体はありきたりだけど、そこに鬼滅の刃と服のデザインの話をミックスすることで、この記事はケッキング山田のオリジナルコンテンツに化けるのだ。素材自体はその辺に転がっている。「鬼滅の刃」「服のデザイン」みたいな言葉はみんな知っているだろう。
だけど、これらがどういう風につながるかまでは多くの人々は見えないのだ。だから、つなげてあげるとそこに価値が生まれる。
別の世界のもの同士が抽象度を上げることによりつながった時、人々はおもしろいと感じ、脳内でパラダイムシフトが起こるのだ。抽象度の上げ下げが自由自在にできるようになれば、実はこの世にあるもののほとんどをつなげることができるから、ネタなんて無限に生み出せるのだ。
数学と英語も一見、別々のものだろう。だが、受験科目という一段抽象度を上げることにより、数学も英語も受験科目だし、同じだよね!というようになり両者はつながるのだ。
別の例を出すと、トイプードルとブルドックも抽象度を上げて、犬という単語を持ち出すと、種類は違うけど、両者犬なので同じだよね!となるわけだ。上記に挙げた最初の主張も抽象度の視点で解説すると、鬼滅の刃と服のデザインの両者の抽象度を上げることで、「大枠は同じだけど、中身でオリジナルを演出する」という部分でつながったのだ。
抽象度の上げ下げを自由自在にコントロールできると、「丸ぱくりはよくないよね」という誰でも言ってそうなありきたりな主張からここまで派生させることができる。
これがオリジナルの知性であり、ぼくの武器である。これは訓練次第で誰でもできるようなるし、あなたにもオリジナルの武器を身につけて欲しい。
この戦略自体も実はぼくのオリジナルではない。ぼくはこれをアップルの戦略を取り入れて、それを文章に落としこんだのだ。
アップルは携帯とパソコンというすでにあるもの同士をつなげることにより、携帯電話を再発明して、スマートフォンという新しい概念を生み出した。
ぼくは文章でもこれと同じことをすれば余裕で差別化できるし、オリジナルのものを生み出せるぞということに気付いたわけだ。多くのビジネスマンが「継続が大事です」「今日の積み上げ」「おはよう戦隊」みたいなことを言っている間にぼくは様々な事象をつなげて、オリジナルコンテンツを生み出す。
結局、みんなと違うユニークなものを出し続けられる人が生き残るし、ユニークなものというのは広がりやすいから、見つかるのも時間の問題なのだ。だから、小手先のテクニックなんかよりもオリジナリティを強化した方が絶対にいい。
新しい世界を見せてあげたとき、人はその人の書く文章をおもしろいとおもうのだ。ぼくはすでにある事象をつなげることで読者の世界を広げているだろう。もちろん、新しい世界を見せてあげるというのは別につなげるということをせずとも、オリジナルの体験をしてさえいればできる。
「夏祭りで暴走族と喧嘩して警察に捕まり、少年院に行った話」みたいなタイトルの記事だったら、いちいち比喩でつなげたりしなくてもそれ自体がオリジナルの体験コンテンツだから、事実を列挙するだけで読み手の世界を広げる役割を果たす。
大体、みんなこのように実際に希有な体験をすることで差別化を図ろうとする。
まぁ、この方法は差別化の方法としては簡単ではあるのだけど、このやり方はネタ探しにコストがかかるから、インスタグラマーのように写真を撮るためだけにナイトプールや高級飲食店などの秘境の地を巡る作業をしなくてはならなくなる。
文章は0円でコンテンツを生み出せるところが魅力なのに、ネタを拾うのに、お金がかかっていれば、本末転倒だ。
ぼくは家に引きこもってても無限にコンテンツを生み出したいので、とにかく様々な事象をつなげる力を磨くことをおすすめする。
そして、ここからはそのための訓練法について書いていく。
訓練法は日頃から出会う情報をどれだけ他のものとつなげる意識をして
生活しているかにかかっている。
本を読んだときに多くの人はとにかく読み切ることだけを目標にするから、
結局何も身につかず文章も書けるようにならないし、話せるようにもならないのだ。
そのやり方は達成感はあるだろうが、実際は何も身になっていない。
インプットした情報の中から「なるほどな~」と感銘を受ける言葉は何個かはあるだろう。そのように感情が動いたフレーズというのは心に残りやすいから、点と点を線でつなげておくのだ。その時に、主張に対して「例えば~だよね!」という風に例えばを口癖にする。
そうすることによって、抽象的な主張に対してもその都度具体化するから、
段々それがくせになって、ふとした瞬間にも話せるようになるし、自然と文字にも書き起こせるようにもなる。
点と点が繋がった線の数が脳内の引き出しの数だ。
これが多ければ多いほど、会話でもバンバンユニークな言葉で出てくるし、
「その発想はなかったわー」というようなオリジナルのトークスキルへと変化するのだ。
お笑い芸人やトーク力があると言われている人はこの能力がすごい。多くの人には見えない線が彼らの脳内にはあるから、その線を見せたときに人々は意表を突かれ、「この人はおもしろい!」と錯覚するのだ。
これが視聴者の世界を広げてあげるということであり、ファン化のための必須スキルと言える。これは努力次第で誰でもできるようになるから、ぜひ、練習してじぶんの武器にして欲しい。
ぼくも段々できるようになっていったし、まだまだ成長途中だ。この力は際限なく、どこまでも進化する。ぼくはそういうものだと思っている。
では!
三話・スラスラ読みやすい文章術の正体とコンテンツ無限生産装置について
さて、三回目だ。
今日はスラスラと読みやすい文章を書くにはどうしたらいいのか?という悩みに答えていく。
この章を読めば、それらは理解出来るので、あなたの文章活動にもぜひ生かして欲しい。
じぶんでいうのもなんだが、ぼくの文章は読みやすい方だとは思う。大体1記事3500~4000文字くらいの分量があるが、じぶんで読み直していてもスラスラと読めて、感覚的には2000文字くらいに思える。
昨日も書いたけど、ネット上で文章のみで勝負しようと思ったら、スラスラ読める文章術というのは必須になってくる。そもそも、SNSでガッツリ勉強しようと思っている人なんていないんだから、最初の数行を読んで、なんか読みにくそう、つまんなそうといった印象を読み手に与えてしまった時点で
もう終わりだ。
後半に、どれだけ有益なことをびっしり書いても読まれることはない。
SNSというのは娯楽施設なのだ。じぶんの商品を買ってもらうためのカモがその辺をぶらぶらしているわけではない。
文章でおもしろくてためになるという価値をまずは提供しなくてはならないのだ。SNSを使ってビジネスをしたければ、まずは「おもしろくてためになる」という価値を提供し、その後、読者に能動的に何か有料商品を買いたいと思ってもらえるのが正しい手順だ。
何か有料商品を買わないと申し訳ないと思ってもらえるくらい、無料で提供するくらいがぼくはちょうどいいと思っている。ここでも逆張りだ。みんな先に貰おうとするから、先に与えることで一人勝ちできるのだ。
結局、コミュニティを作ることに導線が繋がっているわけだから、仲間であるコミュニティメンバーには無料であろうと成長してもらう方がじぶんにとっても得なのだ。
読者が全員枯れたら、どの道終わりなので、読者を成長させることが最優先事項だ。
おはよう戦隊とか大量リプみたいなスパム行為をしている場合ではない。
これがわかっていないのに、いくら積み上げても無駄なので、まずはスラスラと頭に入ってきやすい文章というのについて理解を深めてもらおうと思う。
というか、ビジネス系の人達は謎のライティングスキルみたいなのをたくさん勉強しているみたいだけど、そんなの勉強しなくても面白くて、ためになる文章さえ書ければ、勝手に人は集まってくる。
そうやって、人が集まった後、何か売ればいいだけだから、ビジネスをそんなに難しく考える必要はないのだ。
人を集めて、何かを売る。ただこれだけ。人を集めるにはどうしたらいいか考える→おもしろい文章を書ければいい→じゃあ、次は何を売るか?→今までのじぶんのストーリーを売ればいい。
ストーリーというのは誰でも売ることのできる最強のオリジナルコンテンツだ。
いま書いているこのnoteですらストーリーの一部だ。こういう企画をやったらフォロワー集まりましたー!ということが後から言えるだろう。実践したことは後からネタになるのだ。
このnoteを書いている現時点で、ぼくはフォロワーが2500人くらいだが、3000人になったタイミングで3000人までの軌跡みたいなのを売れば、十分価値になるし、価格にもよるけど、いくつかは売れるだろう。
まぁ、小銭なんていらないので、ぼくの場合は出すとしても無料で投げるけど、じぶんでお金を生み出すという体験価値が欲しい場合は、値段をつけて売ればいい。
少しでもじぶんでお金を稼げると、自信に繋がるから、一度もお金を生み出した経験がない人はほんの少しでも良いから収益化してみるのもありだと思う。
相互でつなげた3000人だと売れないが、能動的にフォローしてくれた人が3000人いる場合は必ずいくつかは売れるから、商品なんてなくていいし、最初に考えるべきことではない。
3000人はぼくの例なので、適当だ。フォロワーの濃度が濃い場合は1000人でも十分だ。
濃さの判定はじぶんがフォロー解除したときに相手が残ってくれるかということが大事になる。残ってくれない場合はただ繋がっているだけなので、あなたに惹かれてフォローしているわけではない。大事なのはあなたに興味を持ってフォローしてくれてる能動的なフォロワーだ。この人数が1000人を超えれば、何を売っても少しは売れる。
成り上がったストーリーを売ることなら誰でもできるから、どうやったら、ツイッターというフィールドでじぶんにスポットライトが当たるかをひたすら考えるといい。
と、なんだかんだ、収益化までの道筋が全く見えないみたいな人も多い感じがしたので、前にも似たようなこと書いたが、今回もざっと復習がてら書いた。
結局、ビジネスにおいて大事なのはじぶんでもいけるんだという自信なんだよね。これさえ、あれば文章で成り上がるとかツイッターでフォロワー増やす程度のことは何も難しくはない。
多くの人はビジネスを勝手に難しいと捉えて、自爆しているだけ。
だって、ぼくは難解な知識を披露しているわけではないでしょ?誰でもわかるような簡単な言葉しか使っていない。
だって、ぼくは座学的な勉強ってほとんどしていないし、伝えたいことがあるから、ひたすらタイピングしているだけ。だから、スラスラ読める文章術の正体は友達と会話する感覚で書くということなんだよね。
あなたも友達と会話するために何か本を読んでインプットしたりしないでしょ?それと同じ。ぼくも文章を書くためにいちいちインプットしたりしない。
会話はリズムに乗せて、相手が投げてきたボールに対して柔軟に対応する。
ぼくもこの企画ではモニター生からフィードバックというボールをもらう。
それらを眺めていると、こういうことを伝えたいなぁというアイディアが自然と脳内に降りてくるから、それを文字に起こししているだけだ。
このnoteはあなたと会話する感覚でぼくは書いている。だから、読みやすいし、心に刺さる感情的な文章になるのだ。これは意識の問題であり、知識を書いているわけではないから、誰でもできるはずだ。
でも、多くの人は何か特別なことを言わないといけないと思い込んでて、インプットに莫大な時間を投下する。だから、いつまで経っても書けるようにならないし、仮に書けるようになったとしても知識ベースの記事だから、独り言のような文章になり、読み手の心には響かないという悲しい結末になる。
ぼくは会話の練習をしているのだけど、多くの人がしているのは街頭演説の練習。
文章めちゃめちゃ書けますみたいなこと言っているブロガーはただ、街頭演説がうまくなっただけ。話せるけど、誰も聞いていないみたいな感じだ。
その辺のブロガーが書いている記事を見てみて欲しい。数行読んだだけで、読む気が失せるはずだ。
それは彼らの文章が読み手を全く想像していなく、こういうことを書いたら、アクセスが集まって、お金に結びつくぞ!という打算が含まれているからだ。当然、そのような意識の元、書かれた文章はつまらないものになる。
お金のことしか考えていない政治家と同じだね。思っているより人はお金のニオイに敏感だから、文章の節々にそういうのって出てしまうんだよね。
言語化はできないけど、なんかこの人胡散臭いなとか、なんか好きになれないなという文章からにじみ出るオーラを人は感じるのだ。
じぶんの記事を上位表示させるキーワード選定とか、そういうのはどうでもいいとぼくは思っている。だって、ビジネスって結局は人対人だし、そこに血が通ってなかったら、文章で相手の心を動かしているというよりは洗脳に近いニュアンスになる。
じぶんのブログやサイトを上位表示させるような打算的な文章を書き続けても、一時的には稼げるかもしれないが、これだとコミュニティは形成されないので、長い目で見たら損だし、これはぼくのやり方ではない。ぼくはキーワードを全く意識していないから、読みやすい文章になるのかもね。
というか記事とかいくらでも書けるからこのnoteがbanされても別にいいと思っている。実際、第一回目の企画noteは速攻でbanされたし。笑
フォロワーからフィードバックをもらうことで企画も無限にできる。どれだけ、記事を書いても人々の悩みが消えるなんてことはありえないから、ケッキング山田の需要もなくならないのだ。
同じテーマでも視点をずらせば、別物のコンテンツとしても召喚できる。
このようにコミュニティを形成し、会話のキャッチボールを意図的に文章で作り出すと、無限にコンテンツなんて作れるようになるのだ。
そして、ぼくのコミュニティメンバーもぼくにボールを投げているわけだから、少しは成長している。
最初はぼくから投げられたボールをキャッチして、投げ返しているだけかもしれないが、どこかのタイミングでじぶんからボールを投げられるようになる時がくるのだ。
この状態に入れば、コミュニティというのはコンテンツ無限生産装置に化けるので、ほんとうに無敵な仕組みだなと思っている。
みんなお金お金というけれど、コンテンツを自由自在に生み出せないレベルではまだまだだし、そもそも何かを売るステージには立ててないので、まずは「いくらでも料理を出せますよ!」というレベルを目指した方がいい。
いくらでも料理を作れるようになってから、それらを多くの人に食べて貰う。その後、よい評判をもらえるようになって初めて、「じゃあそろそろ値段をつけるか」くらいで全然遅くはない。
初めて、作った試作品に値段をつけようとする大バカものばかりがネット上にはウヨウヨしているから、彼らのようにはならないでほしい。まずはいくらでもコンテンツは作れますよという状態に入ることが目標だね。
ということで、ちょうどいい文字数になってきたので、では!
四話・ひらめきの正体と飽きない文章術
さて、今日は第四回目だ。早いね。
明日で最終回か。
モニター生からもらったフィードバックで多かったのが、点と点が線で繋がる話をもっと深掘りしてほしいのと、ぼくが文章を生み出す中で苦労したことやぶち当たった壁みたいな内容が多かったのでこの辺を採用して、どうにかして、おもしろいような記事にしていこうと思う。
昨日書いた記事の実践編みたいな感じだね。とにかく、おもしろくて役に立てばなんでもいいと書いたからね。
この章を読めば、点と点が線となってつながる話がより深く理解できるようになるだろう。それと脳内の引き出しとひらめきのメカニズムがわかる。
まず、ぼくがツイートや文章を作成するに当たって、何も無の空間から全てを生み出しているわけではない。
中にはケッキング山田は天才だみたいに思う人もいるかもしれない。もちろん、そんな風に言って貰えること自体はうれしいのだけど、マジックのタネさえ、わかればあなたも訓練次第でできるようになるから、決してぼくがやっていることを特別なことだとは思わないで欲しい。
このnoteもモニター生がいるから書けている。モニター生がいるから、ぼくの脳内の引き出しがバンバン開いて、それを言語化していったら、勝手にコンテンツとなっているようなイメージだ。
ぼくはパソコンに座って、タイピングを始めるまではどんな内容の記事を書こうかなんてことは全く考えていない。モニター生からもらったフィードバックを眺めながら、大体こんな内容のことを書くかぁみたいに大まかな方向性を決める。そして、その後はもう流れに身を任せるといった感じだ。
とりあえず、船を作る(モニター生からのフィードバック)→目的地に着くまでは流れに身を任せるといったイメージだ。
ぼくはこの考え方を島田紳助から取り入れた。
彼は司会者として、脳内に無限の引き出しがあるかのようなトークスキルをテレビで披露していたが、彼も本番直前まで何を話すかは全く決めていないらしい。
リハーサルもしない。全部アドリブだそうだ。というか、彼はアドリブでないとできないのだ。本番前に台本なんて読んでも何も思い即かないと言っていた。台本という血の通っていない機械的なものでは脳内の引き出しが開かないからだ。
この感覚はぼくも非常によくわかる。書きたいことなんてネタを自ら仕入れようとしない限りない。会話のキャッチボールが始まり、相手からネタを投げかけられて初めて脳内の引き出しが開くのだ。
ぼくもその辺のブロガーと同じようなやり方で記事を書こうとしたら、当然つまらないような内容になるし、そもそも書く事が思い即かない。何度も言うが文章が書けない理由は知識不足なのではなく、意識の仕方が間違っているからだ。
もっと言うと、脳内の引き出しが開くような場を作ることができていないのだ。その場がコミュニティである。ぼくの文章はぼくが書いているように見えて、実はコミュニティから召喚されているコンテンツだ。
コミュニティの代表としてぼくが書いているだけであって、みんなの意見がないと、このnoteも完成しないし、コンテンツというのは場から生み出される感覚を持っておいて欲しい。
話を戻すと、おもしろい話ができるかどうかに知識量は関係無い。偏差値30のおもしろい小学生もいれば、偏差値90のおもしろくない東大生もいるのだ。
多くの人は文章が書けない理由を読書不足だから~とかインプットが足りないから~みたいに決めつけているが、単純にアウトプット不足なだけだ。
インプットで引き出しの数を増やすことができるが、引き出しがスムーズに開くようになるかはアウトプット量で決まる。
それに会話ができるのに文章は書けないなんてことはありえない。単にそれは慣れていないだけ。文字数を稼ごうとしたら書けなくなる。これを伝えたいんだという一つの主張を決めるだけで、どんどんネタは降ってくるようになる。
あなたも好きな人にラブレターを書くときは何か本を読んだりして知識をインプットしたりはしないでしょ?じぶんの好きだという思いを文章にのせるはずだ。
何を書こうかなんてことは書き始めてみないとわからない。
だが、好きという想いを伝えると決めた途端に、好きな人の好きな部分が
どんどん記憶の中から呼び覚まされるような感覚に陥る。これが一つの主張から引き出しが開く感覚であり、あなたも一度は体験した事があるだろう。
別の例で言うと、受験数学も同じ。
難関大学の数学は問題を見た段階では正直、何もわからない。これはどんな天才でも同じだ。(異次元クラスの天才なら一瞬で答えまでの道が見えるのかも)
ほとんどの人はちょっとずつ細分化していくことで、段々と答えまでの距離が縮まっていくといった感じだ。一つの公式を展開していくと、見えてくるものがあり、さらに別の引き出しが開いていく。これがひらめきというものだ。
この繰り返しで数学の問題は解けるようになっている。
ラブレターの例と同じだね。
具体と抽象の話は使えそうなので、ここで使ってみよっか。
ラブレター、数学の問題、ケッキング山田の文章、抽象度を上げることで
これら3つは「引き出しを開けていく作業」というので繋がる。
引き出しを開けていく作業こそがひらめきの正体だ。ひらめきの力は引き出しをスムーズに開けるような訓練をすることで、伸ばすことができる。決して才能ではない。
現にぼくも全くできなかったが、少しずつできるようになっている実感があるし、1年後にはもっとこの力は伸びているという確信がある。才能で片付けるのにはもったいない。脳は進化するのだ。
ぼくは理系だったし、数学にかなりの時間をかけたから、ひらめき=引き出しが開くというのは感覚的にわかっていて、数学的な思考が無意識のうちに
ぼくの文章に反映されているのかもしれない。
と、ここまでの話も結局は「引き出しを開ける話」だ。たった一つの主張だね。
それを具体例を出して展開しただけ。このように抽象的な主張に対して、具体例を交えるだけで、いろんな世界がつながるから、おもしろくて役に立って、なおかつ飽きないような文章構成になる。
多くの人はいろんな世界がつながらず、同じ世界の話ばかりするから途中で読者に飽きられるのだ。
そりゃ、どんなに焼き肉が好きです!と言っているお客さんにも永遠と肉ばかり提供したら、さすがに飽きてもう食べたくないというようになるだろう。
肉のおいしさとは野菜の存在があって初めて、際立つのだ。野菜は肉を飽きさせないためにある。
毎日同じメニューの食事を食べ続けて、飽きないなんて人はいない。人間は飽きる生き物だし、バリエーションを変え続けないと、絶対にダメだ。飽きられないようにアップルは毎年新作iPhoneを出しているとも言える。大して機能は変わらないけど、新作を出すというだけで人々の飽きの寿命を伸ばすことができるのだ。
これはセブンイレブンでも同じだね。季節限定、新作商品などちょっと変えただけのものをあたかも新しいものとして、売り出しているだろう。
それくらい人々は新作に弱い。飽きるからすぐに新しいものを追い求める。ビジネス書や自己啓発本も同じだね。
内容はほとんど同じなのに、パッケージと著者が変わっただけで、最新作コンテンツに化ける。
特にぼくらがこれから書いていく文章でも飽きさせない工夫は必須になる。
仮にさっきの脳内の引き出しの話でぼくが脳科学的な知識を書き出したら、
途端におもしろくなくなるだろう。脳内でニューロネットワークが構築されて、電気が流れることにより初めて記憶として定着するんです!みたいなことをドヤ顔で言っても、なんかつまらないし、読むのやーめたってなるのは目に見えている。
そんな専門知識が聞きたいなら、茂木健一郎の話を聞くよ!という意識に人々はなるのだ。
茂木健一郎ではなく、ケッキング山田を選んで貰うにはわかりやすさを重視し、ぼくの知性から召喚されるオリジナルの比喩で勝負して、独自のものを
絡めなければならない。
逆にこれさえできれば、どんなものでもオリジナルのものに変えることができるのだ。
具体と抽象を織り交ぜることによって、読者は飽きにくくなるから、ここさえ、意識すれば、オリジナルに変えることはそんなに難しいことではない。
文章でもジェットコースターのように緩急が大事だ。緩やかな傾斜の部分があるから、急に落下する部分のスリルを最大化させることができる。
野球でもストレートがあるからカーブが生きるだろう。カーブしか投げなかったら、いずれ目が慣れて、打たれるに決まっているのだ。
大学教授の授業がつまらないのは彼らが抽象的な話しかできないから、話の中に緩急が生まれず、生徒が授業に引き込まれないからだ。
文章とは緩急が命だ。抽象的な主張に対して、具体例で補強していき、読者の世界を広げ続けるのだ。そうすることにより、よほどつまらない文章でない限りは最後まで読んで貰えるようになる。
あと、なんか書こうかなと思ったけど、
文字数的にもちょうどいいので、この辺で!
五話・0からのコミュニティ形成と具体的な行動指針
さて、今日は最終回だ。
どんな感じで締めようかなといま、考えている。
文章術や具体と抽象の行き来みたいな思考法は4回まででダラダラ書いてきたから、最終回はそれをどのように実践していくのかという部分に切り込んでいこうと思う。
結局、あなたが行動しなければ、4回までせっかく読んだ内容が無駄になるから、4回までの内容を具体的にどう生かしていくかということを書いて最終回にする。
4回目までに書いた文章術や思考法をマスターしてもらえれば、ぼくがやっていることくらいならあなたにも再現できるようになる。
だって、ぼくが実践していることしか書いていないのだから。
かなり具体的に手順を示すと、まずは相互フォローでも良いから、ツイッター上でじぶんと似た属性の人達をフォローしつつ、第一回目のnoteにも書いた「一段高い視点のツイート」で練習する。
抽象的なことに対して、比喩を織り交ぜてツイートしていけば、よほど例えが下手くそでない限り、しっかりとツイートは伸びていくし、この人なんかおもしろいなとフォロワーに思ってもらえる。
そして、人は共感でRT、いいねする。「みんなが潜在的に思っているけど、言語化しにくいもの」を言語化してあげると、この人はじぶんに見えていない世界が見えててすごいという認識になるから、共感できてかつみんなが思い即かないようなツイートを考えるのだ。
これは4回目までの内容を踏まえて、トレーニングを積んでいけば、できるようになるから、そこまで難しく考える必要はない。
ビジネスマンの多くのはしょうもない根性論や精神論しか言わないが、これだとバリーションも少なすぎるし、読者に飽きられるに決まっている。
一貫性なんて出す必要ないのだ。
ぼくも全くそんなことは考えていない。
ただ、みんなが思い即かないような組み合わせで言葉を紡いでいるだけだ。
人と違う事が価値になるのだから、当然あなたもぼくの真似をしてはいけない。
別に真似をしてもいいが、ぼくの真似をするとあなたはぼくと競争することになり、たぶんぼくには勝てないから、あなたはあなたにしかない武器を光らせた方がいい。
だから、頭を使うことは必須になるかな。
どれだけ思考したかが個性に還元されるから。毎日、刀を研ぎ、知の剣の矛先を尖らせていく。
考える事ができない人はみんなと同じ作業ゲーしかできないということだから、インターネットという、いかにして個性を光らせるかのゲームには向いていないので、あきらめた方がいい。
伸びているツイッタラーを観察してみよう。必ず、独自の個性、世界観があるから。
サンプルがぼく1人だと、どうしてもぼくに影響されると思うので、いろんな人を見てみるといい。
2章に書いたかな。正しいぱくり方みたいなの。別に真似することはいいんだけど、1人だけだとその人の劣化コピーになるから、いろんな人を組み合わせて、さらにあなたの知性をブレンドすることにより、オリジナルコンテンツというのは容易に作れる。
このnoteを見ている人の中にはぼくを参考にする人もいるだろう。だから、ぼくを一つの素材としてあなたのオリジナルに消化させたい場合は「ケッキング山田+A+B+C=あなたのオリジナル」というような形にした方がいい。
最低3人くらいを混ぜると、完全オリジナルのものになるし、A、B、Cの別のサンプルはじぶんで探すのだ。
ぼくも業界の垣根を越えて、いろんな人を参考にしている。だから、それらの組み合わせにより、ぼくの存在はオリジナルのものになるのだ。
参考にしている人が1人だけだったら、その人の劣化コピーということが
すぐにバレてしまう。
4章でコミュニティという場からコンテンツは生まれるということを書いたが、これはいきなりだと難しいかもしれないので、自分自身がオリジナルの存在になるためにも、まずはいろんな人を組み合わせて、じぶんというオリジナルを確立していこう。
オリジナルの存在になれば、オリジナルの場ができて、そこに自然と人は集まってくる。ケッキング山田というなんか他とは違う面白い奴がいるなと思ってくれた人がぼくが作り出す場に引き寄せられるのだ。
その場に引き寄せられた人達の集団がコミュニティとなる。
だから、まずはフォロワーを増やしつつ、オリジナルのツイートをしていく。そうしたら、段々とツイートのエンゲージメントも高まってくるから、
数人じぶんのファンができてきたなと思った段階で、自分の思想や考え方を
ブログにでも書いて、1人ずつDMで配布しよう。
このとき、大事なのはあなたのために書きましたという演出をすることだから、できればブログではなくPDFの方がいい。
もちろん、PDFのやり方がわからなければブログのリンクをDMで送信すればいいのだけど。
ぼくも最初の方は読者が数人しかいなかったから、このやり方で一人一人しっかりコアなファンを作っていった。一人ずつDMでコンテンツを配布すれば、かなりの確率で感想メールをくれるから、その感想メールを元に次のコンテンツも作れて、3章か4章に書いた会話するように文章を書くという状況は作り出せる。
文章でキャッチボールをするという状況さえ作ることができれば、この人を喜ばせたいなという想いから、自然とアイディアは降ってくるから、そこまで心配する必要は無い。
あなたも話し相手が目の前にいる時に、何も話すことがないなんてことにはならないだろう。どんなコミュ障でも何か世間話程度はするはずだ。最初は気まずいかもしれないが、話し出すと流れに身を任せて、テンポよく会話できるようになる。
会話というのはいちいち頭で考えなくても反射的に言葉が出てくるだろう。
文章でも同様にフィードバックをもらえるようになったら、なら次はこれを書こうというアイディアは自然と思い即くのだ。
他者とじぶんでエネルギーを循環させることにより、そこで生まれたエネルギーはアイディアに変わる。
そう、たった一人を見つけるだけでも全然違うし、最初の一人を見つけるまでが勝負だとも言える。一人を見つけたら、後は人数を広げるだけだし、いまのぼくもその繰り返しでできている。
誰でも最初は一人から始まるのだ。
カルピスの原液さえ作ることに成功したら、広げるのは簡単なのだ。あとは同じ事をすればいいし、感覚がわかれば、人数が増えてきた段階で自動化すればいいのだから。
ぼくも今は会員サイトを作って、ある程度は自動化してるが、8月と9月は全部手動でコンテンツをフォロワーに配布していたし、何十人からもフィードバックをもらってコンテンツを作っていた。そうやって、作られたコンテンツをアーカイブとして残し、自動化しただけだ。
何も最初から自動化していたわけではない。手動の先に自動化というのはあるから、順序を間違えると失敗するので、そこは気をつけた方が良いかな。
(多くの人はいきなり自動化に走って失敗する。)
このnoteも同じ原理で作られている。
モニター生15人くらいを囲って1話ごとに毎回フィードバックをもらって、そのフィードバックを元にコンテンツを作成した。
これはカルピスの原液を作っている作業と言えるだろう。こうやって、5話まで原液を作り、コンテンツの情報密度を最高に高めた状態でツイッター上で発散するのだ。
ツイッターで拡散するのは最高に濃くなった原液を薄める作業だ。
人々の心に刺さる文章を書くには、このようにコミュニティを作成し、フィードバックをもらい、じぶんの書く文章はちゃんと響いているのかを確かめながらやった方がいい。
いわば、コミュニティとはろ過の装置だ。コミュニティを利用することで、コンテンツの情報密度を最高レベルに高めることができるので、「こういうのが知りたかった」と思ってもらえるような情報を読者に届けることができる。
一人で書きたいことをひたすら書きなぐると、いざ公開したときに読者の反応が「そんなのいらねーよ!」となりかねないので、そういう状態を回避するためにコミュニティは存在するのだ。
まぁ、人によってはコンテンツを作るためにそこまでするのはめんどくさいと思うかもしれないが、文章というのは人に読んでもらって初めて価値になるので、フィードバックはしつこいくらい貰った方がいい。
人との会話は実際に会話することでしか上達しないように、人に読んでもらえる文章を書けるようになるには実際に読んで貰って、フィードバックを貰った方がいい。
ある程度、文章でのキャッチボールを繰り返すと、フィードバックを貰わずとも、こういうのを書いたら読者は喜ぶだろうなというのが感覚的にわかるようになる。
その時、初めてじぶんの感覚だけで書きまくればいい。
毎回補助輪をつけて、自転車をこいでいたら、ある瞬間から「もうなくてもいける!」と悟る時がくるのと同じだ。
ぼくの場合、ブログはいちいちフィードバックをもらったりせずに、質問箱から適当にネタ拾って、こういうのを書いたら喜ぶだろうなというのを考えて書いている。
まぁ、このnoteのように企画コンテンツの場合は多くの人に読んでもらい、満足してもらうような内容にするために毎回フィードバックはもらうけどね。
二万字くらい書いて、それが不発に終わったら嫌だからね。笑
ということで、こんな感じでいいかな。
まずは一人を見つけて、そこからコミュニティを作り、展開していけば、コンテンツのネタには困らなくなるということだね。
もちろん、コミュニティメンバーに価値を提供するということが前提になるけどね。
しょうもない記事しか書けなかったら、おそらくフィードバックはもらえないので、そこは何度もアウトプットを繰り返してあなたが読者に必要とされるような価値ある存在になれるよう頑張るしかない。
ネタが無限になってかつ、書くコンテンツを多くの人が見てくれるようになったら、コンテンツビジネスは勝ったも同然なので、収益化の前にまずはコミュニティ作成を抑えよう。
ということで、今回の企画はこれにておしまい。
また、定期的に企画やるんで、次も見たい方はぜひツイッターフォローしてね。今回は引用RTで追加プレゼントとかはないけど、感想くれたら喜びます。
では、ここまで長い文章を読んで下さりありがとうございました!
=================
メルマガ限定の濃い情報と登録特典のプレゼントは下記リンクから受け取れます。https://cyan376886.studio.site
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
