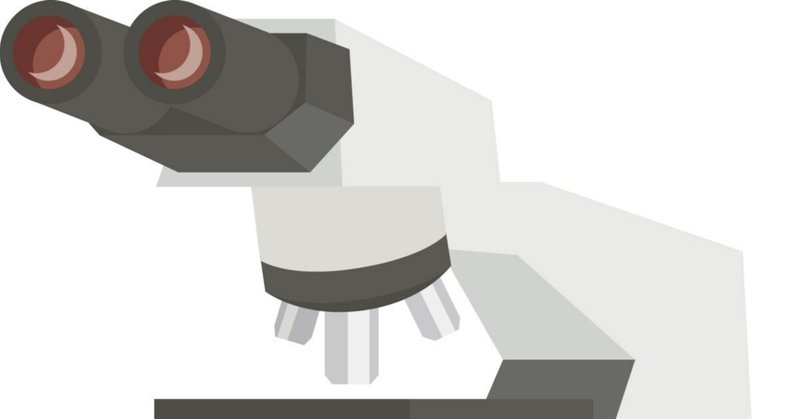
炭酸塩岩の分類法と記載
炭酸塩岩の主な構成物は、細粒の炭酸塩泥の基質 (mud/ ミクライト)、炭酸塩粒子 (grain/ 生物遺骸や一度固化した炭酸塩岩が破砕された炭酸塩岩粒子、ペロイドと呼ばれるミクライトからなる粒子、核とそれを取り巻く同心円状の構造を持つウーイドと呼ばれる粒子など)、孔隙を埋めるセメントなどです。
炭酸塩岩の分類方法はいくつも提唱されていますが、石油開発業界ではDunham (1962) の分類を基礎にした分類法が主流となっています。
たとえば、「Webサイト紹介・リンク集」の中でも紹介させていただいている「SEPM STRATA SEPM Stratigraphy Web」の中では C. G. St. C. Kendall, 2005 (after Dunham, 1962, AAPG Memoir 1) として以下のような図が掲載されています。これも Dunham (1962) をもととした炭酸塩岩分類法の一例です。

この分類法の特徴は、岩石の枠組み (framework) と、基質 (mud) と粒子 (grain) の量比や支持関係を重視していることです。他の分類法に比べると比較的簡便な分類法であり、現場での肉眼、ルーペなどでの記載が比較的容易に行えること、堆積環境もある程度反映していること、貯留岩としての性状 (孔隙率や浸透率など) もある程度反映していることなどから、石油開発業界では主流の分類法となっています。
もちろんそうはいっても、実際に炭酸塩岩を見てみると、ミクライト質の粒子が基質の mud と区別がつきにくかったり、mud-supported なのか grain-supported なのか区別がつかなかったり、粒子の種類を区別しないと必ずしも堆積環境や海水のエネルギーレベルを十分に判別できないなどの難しさや課題もあります。
炭酸塩岩の記載は、その目的や油層の特徴などによって、記載項目をカスタマイズしながら行うべきだと考えています。一度の記載で終わることなく、必要に応じて項目を追加したり、記載を定量化したりする工夫などをしながら、何度も見直す必要があります。石油開発の分野では貯留岩特性とその原因となる主たる地質学的要因に着目して、最終的には貯留岩特性の分布の推定に役立つ記載を目指すことが必要だと考えています。
一般的な記載事項としては、Dunham (1962)の分類法を基本としながら、薄片・顕微鏡レベルでは粒子の種類や形、サイズ、粒子サイズの揃い具合 (ソーティング)、セメントの種類や量、目に見える孔隙の量や種類などのほかに、コアサンプルサイズでの堆積構造やフラクチャーと呼ばれる破断面、スタイロライトと呼ばれる圧力溶解による縫合線状面などの記載も行われます。また、上方細粒化、上方粗粒化などの変化や単層の厚みの変化なども堆積環境やその変化などを掴むうえで重要となります。
記載の方針と記載用紙をどうするか、これは意外に重要な要素です。そして複数の人で分担して記載を行う場合は、なるべく同じものを見たら同じような記載になるように目合わせが絶対に必要です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
