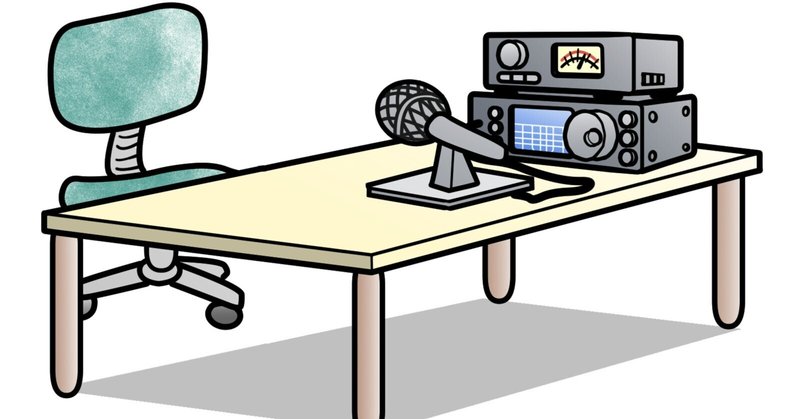
私のもう一つの免許、アマチュア無線
子供の頃に見た模型や工作雑誌にはたいていどこかに「アマチュア無線の免許をとろう!」みたいな記事や広告が出ていたものです。
少年時代、一時期海外短波放送を聞くことにはまりましたが、当然、アマチュア無線にも興味があって、小学生の時に当時の電話級アマチュア無線技士の試験を受けましたがあえなく敗退して、それ以降は挑戦をあきらめ、そのうち興味も薄らいでしまいました。
会社員になって、しばらくして、軽い登山やハイキングなどを楽しむ社内同好会の代表となった時 (まだ携帯電話など普及していない時代) に、なんとなく「無線がつかえるといいよね」という話になり、「じゃあアマチュア無線の免許を取ろうよ」ということになって、「第四級アマチュア無線技士」と名前の変わったかつての電話級の試験を受けることにしました。
小学生の時は何冊もの教科書を読んで勉強してもちんぷんかんぷんだった問題も、大人になって「第4級ハム国試 要点マスター」みたいな小さな本を読んで、過去問を解けばほぼ一夜漬けでも何とかなりました。頭の容量は減っても要領は良くなったということでしょうか。無線工学と法規に関する問題が出ます。
残念なことに、その時会社の同僚で本気で試験会場まで足を運んで免許を取りに行ったのは同好会会長の私だけでした。
その後、無線機を買い、コールサインの入った無線免許状を取得して、アマチュア無線局を開局しました。当時住んでいた三鷹のアパートからでも、コンディションが良ければ国内各地、近隣の海外局とも交信できました。
アマチュア無線機では、当時世の中で活躍していた国際通信社のテレックス通信や船舶向け海洋気象情報や新聞社の無線ファックスなども受信でき、それをパソコンに表示させるなどして、インターネットが流行る前のひととき、無線交信以外でもいろいろと楽しめました。
第三級アマチュア無線技士以上の資格になると「モールス通信」ができるようになります。ピンクレディーの「S・O・S」という曲のイントロで流れる「トトト・ツーツーツー・トトト」というやつですね。
結婚してしばらくアマチュア無線から遠ざかっていたのですが、ある時ふとモールス通信に興味を持ち、第三級アマチュア無線技士の試験を受けました。第三級の試験ではモールス通信は実技はなく、英数字のモールス符号を筆記で答えるだけなので簡単です。ほかの問題は第四級のレベルとほとんど変わらないので、いきなり第三級の試験を受けても良いと思えるぐらいお得感がありました。第三級になると第四級よりも電波の送信出力を上げることができ、移動するアマチュア無線局が出せる送信出力限度いっぱいまで出せるようになります。
モールス符号を覚えるだけなら、YouTubeでモールス符号を音楽に合わせたリズムで覚える動画などもあります。
2011年3月11日に発生した東日本大震災では多数のアマチュア局が、地方自治体に協力するなどして、被害情報の収集や安否情報の伝達等、人命の救助や災害の救援等のための非常通信を実施し、社会的に大きな貢献をしたとのことです。
総務省はアマチュア局による非常通信の考え方として以下のように述べています。
無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて運用してはならないことになっていますが、電波法(昭和25年法律第131号)第52条第4号の規定に基づく非常通信(地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいいます。)等を行う場合は、免許状の目的等にかかわらず運用することができます。
その運用において、非常の事態が発生し又は発生するおそれがあるかどうか、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるかどうか、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のためかどうかの判断は、アマチュア局の免許人が判断するものであり、非常通信は状況に応じて柔軟に行えるものとしています。その際、アマチュア局の免許人は、あくまでもボランティアという性格で非常通信を行うことになります。
そんなことが起きないに越したことはないのですが、「災害の時などに役立つかもよ」と家族には言ってみましたが、少なくとも趣味としての無線には全く興味はないようですし、無線と聞いて心に響くものはないようです。。。
最近はPCでインターネットと無線機を繋げて、海外のアマチュア局とも比較的簡単に無線?交信ができるシステムも構築されています (「EchoLink」など)。「無線局–中継局–PC–インターネット–PC–中継局–無線局」 みたいな接続だけでなく、そのシステムでは、「無線局–中継局–PC–インターネット–PC」というような交信や、「PC–インターネット–PC」という、もはや無線の要素がどこにもない交信? もできるのですが、ある時はサウジアラビアの無線局 (PC) からこのシステムで呼ばれ、PC同士でお話したりしてそれはそれで面白かったです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
