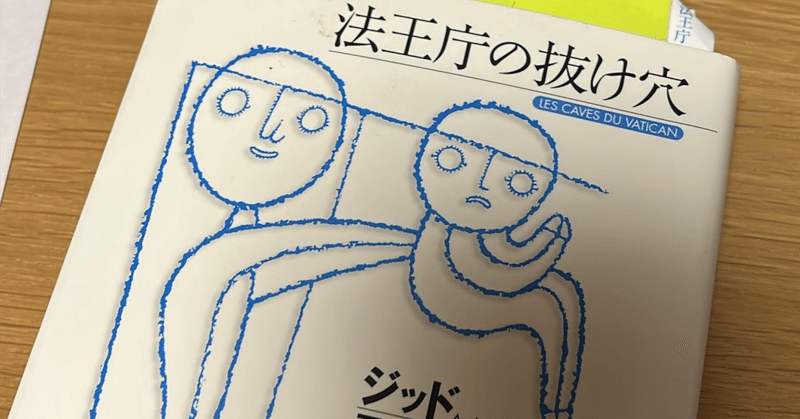
アンドレ・ジッド『法王庁の抜け穴』:聖女の降臨
趣味の読書ではなくて、講座用の読書です。舞台は第三共和政の頃、すなわち、教会と政治が乖離していた頃のお話です。一言で言うと、法王庁にいるべき「神の代理人」、すなわちローマ法王(今は「教皇」に統一されているけれど、タイトルに合わせてあえて法王と呼ばせていただく)がどこかに幽閉され、「今法王庁にいるのは偽者だ!」という説がまことしやかに流れ、「法王を救い出すためにお金を集めよう!」と大規模な詐欺がなされた、というものです。
いろんなストーリーがうまく噛み合って、とても面白いのですが、ここでは一つだけエピソードをピックアップして紹介します。聖女降臨のシーンです。
無神論者だったフリーメーソン会員アンティムは、リュウマチの治療のためにローマにやってきます。妻の妹夫婦が遊びにきて、皆で祈りをささげるところにイラつき、妻が聖女像の両脇に灯している蝋燭が気に喰わず、松葉杖を投げつけます。その杖は聖女像にあたり、像の腕が壊れて金棒が露出してしまいました。
その夜、アンティムは夢を見ます。柔らかい空気に包まれたかと思うと聖女が現れ、「私の腕を壊したのはおまえね」と言われたと思ったら、腕の跡の金棒が脇腹に突き刺さり、アンティムは激痛に襲われます。しかし、目が覚めるとリュウマチが治って、アンティムは杖なしで歩けるようになっていました。これを機に科学者は回心するのですが、この事実は自身の属するフリーメーソンにも知られてしまいます。生活の支援をフリーメーソンから得ていたアンティムは、回心したことで後ろ盾をなくして困窮する羽目になってしまいます。
何が言いたいかというと、神様が出てくるシーンの描写がやけにリアルで、ジッドってもしかしてこの手の経験をしたことがあるのか?という気にさせられた、ということです。
ちなみにフランスにもスピリチュアルなネタは結構あり、例えばジャン・コクトーとレイモン・ラディゲは降霊会を開いて死神を呼び出します。すると、その年の年末にラディゲは腸チフスで世を去ることになってしまいました。死の直前、ラディゲはコクトーに向かって「三日後にぼくは神の兵隊に銃殺される」と言い残し、実際にその三日後に死去することになります。また、土地が悪い、という話も結構あって、ゾラの小説では日当たりの悪いじめじめした土地に引っ越したテレーズの一家は、テレーズが浮気し、愛人とともに夫を殺し、最愛の息子を失った姑は発作を起こして目しか動かせなくなる、という悲劇に見舞われます。そして人殺しをした心の呵責から、テレーズと愛人は次第に相手を憎むようになり、互いを殺す準備を始めます。さらに、姑はふとしたことからこの二人が息子を殺したことを知ってしまい、「この二人の破滅を見届けなくては死ねない!」と思い続けます。やがて互いを殺そうとしていることに気づいたテレーズと愛人は、二人で毒杯をあおって死に、姑はそれを見つめる、というシーンで小説は終わります。悪い土地に住むと身体も精神も病む、ということを暗示しているとも言えます。
こういうスピリチュアルなシーンを集めてフランス文学を読み解く、というのも、もしかしたら面白いかもしれません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
