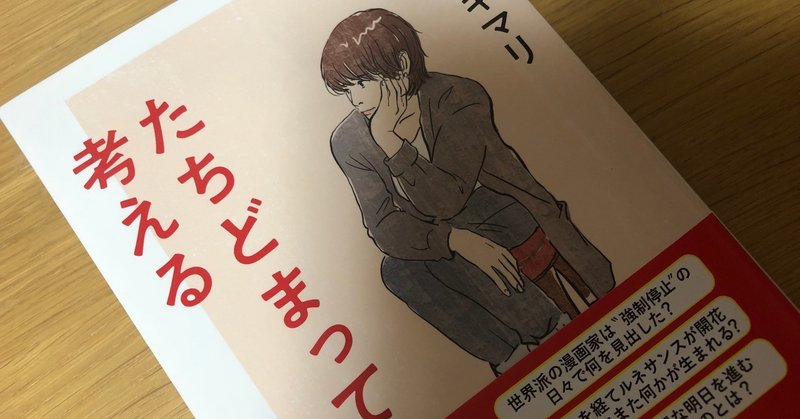
『たちどまって考える』(ヤマザキマリ)
テーブルに、9月10日に刊行されたばかりのこの本が置かれていたので、思わず読んだ。コロナ禍で家族と離れて日本にいるヤマザキマリさんの最新エッセイである。面白い点はいくつもあったが、ここで紹介しておきたいのは以下の点である。
1)ヨーロッパにおけるリーダーには、弁証力が求められ、イタリアの人たちは幼少期からこれを学ぶ。
2)民主主義とは参加することである。
3)日本人の失敗したくない病。
以下、これについてヤマザキさんの意見を要約する。
1)弁証力
これはさまざまな知識を動員して、自分の考えを自分の言葉で話す能力である。イタリアでは小学校の頃から、ノートを見ずに考えを述べる訓練をするという。これをヤマザキさんは「誰もが一端の専門家のように話す」として「自分の中に知識を取り入れて、咀嚼し、人前で話すという訓練の賜物」だと結論づけている。人の書いた文を読むだけでは、メッセージを発信することはできないのだ。
2)民主主義
検察庁法案改正をめぐって、ツイッターで芸能人が発信したとき、「わかっていないくせに口を出すな」という反応が少なくなかった。こういう反応は、民主主義の仕組みを理解していれば出てくるはずがない。芸能人である前に、民主主義でに参加する一般市民であるのは当然で、思想を熟成させていくための批判は欠かせない。ヤマザキさんは、日本には実は民主主義は根づいていないのではないか、と言うが、これは確かにそうかもしれない。リーダーについていく方を日本人は好むのかもしれない。
3)日本人は失敗したくない
サッカーでゴールを決めるときに選手たちが譲り合う、とか、間違いを恐れてなかなか言葉を発しない外国語学習などがこの例だ。しかし、江戸時代にまで戻るとこれは一変するそうだ。この時代は人の失敗を皆で笑うことで自分の生き方のヒントにする、ということが、ごく自然になされていた。
これを読んだとき、中野信子さんの『努力不要論』を思い出した。中野さんは、江戸時代まで、努力は無粋だった、と紹介している。列強に肩を並べようと躍起になるにつれ、遊びは脳の栄養、という大切なことが軽視されるようになっていったとのことで、これには深く納得してしまう。
また、ヤマザキさんは「失敗したくない」ことを世間体と結びつけているが、これも的を射た指摘だ。評価軸が中にあるか外にあるか、というのは結構重大なポイントだと思うのだが、世間を機にする限り、評価軸は外になり、そうなれば当然失敗が怖くなる。これを変えない限り、息苦しさは続くだろう。
鴻上尚史は『空気を読んでも従わない』の中で「社会」と「世間」を分け、社会は知らない人の集まり、世間を知り合いの集まりと定義している。日本人は世間を気にするため、知っている人には親切にするのだが、その反面、知らない人にはいくらでも刃のようになれる、という。そして欧米には、この二つの区別がない、というのだ。これはとても面白かったのだが、ヤマザキさんの話はこの指摘ともつながっているようだ。
全く関係のない話だが、私には「世間」を気にする思考回路がない。これは生きていく中で非常に楽なことなので、是非おすすめしたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
