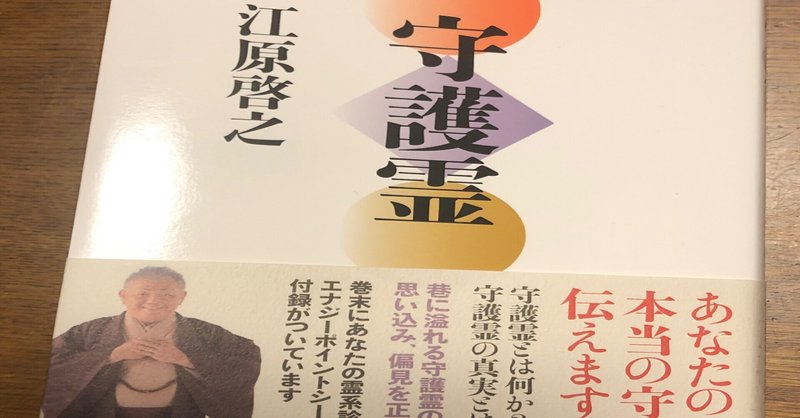
江原啓之『守護霊』を読む
なぜこの本を買ったかという話から始めよう。少しまで、私には「人生逃げ切り」を目論んでいた節があった。定年まで元気に働き、老後は本を読んだりちょっと旅行したりして呑気に過ごし、寄付もして人のために何かしよう、くらいのものである。しかし、ふとしたことから江原さんの「肉体は死んでも魂は永遠、この世はいろんなことを学んで魂を磨くために滞在する場」という意味の言葉を読み、考え方がガラリと変わった。死んで卒業、ではなく、この世がプロセスの一つに過ぎないのなら、できるだけのことをした方がいいではないか、と思ったのである。そう考えると、何かにチャレンジするなら、冷静に考えて段取りを作り、ベストを尽くせばいいし、もし望む結果が出なかったとしても、それは失敗ではなく、学びの一つに過ぎない(よって恐るるものは何もない)、という「大きい気持ち」になるというものだ。
そんなわけで、見た目は以前と変わらないながら、心の中だけはえらく戦闘的に日々を過ごしているのだが、そこで、もう少し「大いなる自分」とつながるよう、意識してみてはどうだろう、と思って読んだのがこの本である。近視眼的に目の前の「いいこと」だけを追いかけるのではなく、もう少し俯瞰した眼差しを持っていろいろ考えたいし、その「俯瞰した眼差し」は、いわゆる「守護霊」が持っているものなのではないか、と思ったのである。
読んでみると、やはりこの本はとても面白かった。守護霊のあり方というのは、例えば「その人が右に行くか左に行くか迷っている、右の方がいいことは俯瞰して見ればわかるが、その人が左に行こうとしても「痛い目に合わなくてはわからないでしょう」と見守る(しかしメッセージは送る)」という感じだそうだ。(これは江原さんの言葉そのものではなく、私が要約している。)もちろんこの本には、こんな言葉では片付けられないいろんなことが書かれていて、ことあるごとに読み返したいのだが、今日の時点で私が摑んだ要点は「惜しまず努力して進む」である。
私は若い頃、痛い目というか結構な困難に直面してきたので、どうしても守りに入る傾向があった。そのせいか、娘や息子にも「つつがない人生を送ってほしい」と思いがちである。しかし「つつがない人生」を送るだけ、というのもいささか物足りないような気もする。少なくとも私自身に関しては、あの困難は自分磨きに最適な軽石であったと理解して、これからも閃いたことはチャレンジする、という人生を歩むことにする。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
