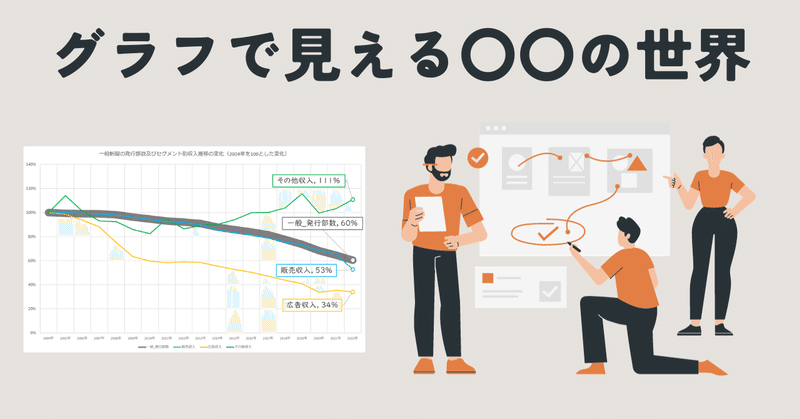
グラフで見える〇〇の世界 新聞業界編
ここでは、数字やデータが苦手な人向けに、グラフで見える〇〇の世界と題して、世の中に落ちているデータをちょっとだけ加工すると、新しい発見ができる!をTipsも交えてお届けします。なお、数字やデータを扱う際は、数学ではなく、”算数”を使っていますので、ご安心を。
1.新聞っていまどうなの?
今回は、以下の日本新聞協会の公開データを眺めることで、新聞ビジネスの現在とその原因を見つけてみたいと思います。また、新聞ビジネスを参考に、旧4マスメディアの最後の砦として、テレビ業界が参考にできることに触れていきたいと思います。


今回は、シンプルに、発行部数と関連する収入を時系列に並べてみました。
掲載されている一番古い2004年を100として、2022年までの推移見てみましょう。墨色の太い折れ線が全国の一般新聞の発行部数、青色が販売収入、黄色が広告収入、緑色がその他の収入。

出典:日本新聞協会
基準値をつくることで、4つの指標の変化に注目してみることができます。すると、見えてくることは、
1.発行部数と販売部数は、ほぼ一致した減少傾向。
2.広告収入だけ、上記2つの指標よりも激しく減少している。
3.その他収益は、2012年から上昇傾向。
新聞のビジネスモデル上、直販のサブスクリプションモデルは、単価のコントロールで一程度収入をコントロールできるが、母集団が減少すると売上自体をあげることが困難なことが分かります。また、発行部数の減少は、マスメディアという地位を相対的に押し下げ、広告価値に兌換する力も奪っていきます。
このように従来のビジネスモデルが崩れる場合、新たな収益源を模索するのが普通ですが、新聞業界はそのテコ入れに時間を要してしまったのがグラフからも分かります。それは、その他収入の変遷をよく見てください。2004年の売上を超えるのは2015年を除くと、11年後の2016年まで事業規模を拡大することができていなことが分かります。その間企業として何もしていなかったわけでなく、主戦場を、販売部数や広告収入に集中して暗中模索をしていたの事がうかがえます。
2.直近10年の状況は?
では、もう少し最近に絞ってみることで、我が事化してみましょう。過去10年間の推移から、近未来をイメージすることが容易になるでしょう。読者の皆さんも、自分居る業界や会社のトレンドでも同じことができるので、是非やってみてください。さて、新聞業界は、2004年からのトレンドと変わらず2013年からの10年間で、発行部数も販売収入も広告輸入も3~4割もダウンサイズしています。一方、頼みの綱ともいえる、その他収入は、25%前後の規模でここ数年伸び悩んでいます。伸びが創れない一方、毎年4%のサイズ縮小していくこのトレンドは、今後10年後の景色も見えてくる気がします。

出典:日本新聞協会
3.非日常がつづくとそれは日常
ここまでは、各分析項目の変化を比較するために、インデックス(指数)化したデータに注目してきましたが、最後に、ビジネスの実態、つまり収入を見てみましょう。新聞業界において、一般新聞の収入は、約2.5兆円近くありました。それが、2022年度には1.3兆円にまで縮小しています。減少していることは、前述の部分でも触れているので改めて指摘する部分ではないのですが、よく眺めてみると、販売収入も、広告収入も、その他収入も一貫して規模縮小しているのがわかるかと思います。厳密には、その他収入は一定規模を維持してはいますが、全体の底上げをする動きにはなっていません。この20年近くづづくダウントレンドは、客観的にみると旧来のビジネスモデルによる収益が立ちいかなくなっているのは一目瞭然です。しかし、なぜ、その他収入などによるテコ入れが成功しないのでしょうか?具体的な問題は様々あるのでここでは触れませんが、この長期データでいえること、そして、2023年現在の日本でビジネスをしている人の多くの参考になることが分かります。
それは、
異常もつづくと、それは日常
ではないでしょうか?でなければ、昭和平成の時代において憧れの職業として様々に優秀な人材が入っていった新聞業界の人々が、この長期間、テコ入れが全くできない理由が見つかりません。つまり、俯瞰で見ると異常な状態に向かっている新聞業界という”大きな船”も、ちょっと傾いた甲板でダンスを続けているようなものなのでしょう。個々人がそのちょっとした傾きが気になりながらも、みんなで楽しくダンスを踊りつつければ、その傾きの中で踊りをつづけてしまい、そのうち傾き自体を感じなくなってしまうのでしょう。これは、新聞業界について話しているようですが、現在の”日本丸”も同じ状態なのは、いうまでもありません。
もう少し数字的な話に戻しましょう、日本企業の多くがビジネスの計画を立てる中で、実は見ているようで見えていなかった現象の一つに、人口縮小と市場縮小の関係があります。人口統計数字は、中長期的に大きな変動があまりない、信頼性の高い統計数字の一つです。その統計において、日本の人口動態は、2008年をピークにダウントレンドに入ることがかなり昔からわかっていましたし、今現在もそのダウントレンドの延長に人口が推移していることも分かっています。しかし、四半期の決算は年度の数字、競合他社とのシェア争いを意識しすぎてか、自分たちが戦う”生け簀”の変化への対応を怠ってしまったのではないでしょうか。確かに、サラリーマン社長とて3年前後で切り替わる昨今、10年先の種まきをするほど余裕がないのかもしれません。
しかし、2000年代から続く長期低迷は、短期的な施策でどうこうすることができないのは、この新聞業界のデータでもはっきりしています。中長期な取り組みによってこそ改善されることがあるのですが、日本のサラリーマン社長にとっては、難しいのかもしれません。

出典:日本新聞協会
本記事、お読みいただきありがとうございます。
無料記事にしては、情報量や質が”あったな”と思ってくれた方は、
以下にて「応援課金」よろしくお願いします。以後の執筆の励みにさせていただきます。
ここから先は
¥ 100
是非、サポートお願いします。データやメディア、そして、普段のビジネスで気になること、活用できることを発信して、少しでもみなさんの役に立つコンテンツになりたいと思います。
