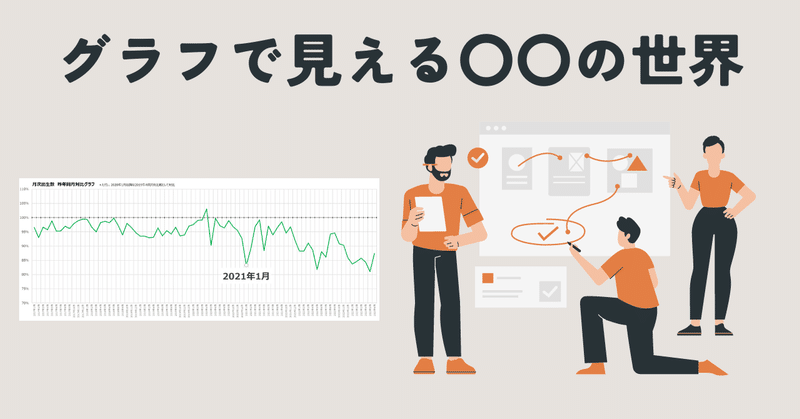
グラフで見える〇〇の世界 コロナと出生数編
ここでは、数字やデータが苦手な人向けに、グラフで見える〇〇の世界と題して、世の中に落ちているデータをちょっとだけ加工すると、新しい発見ができる!をTipsも交えてお届けします。なお、数字やデータを扱う際は、数学ではなく、”算数”を使っていますので、ご安心を。
コロナ渦が与える少子化の波(現在進行形)
コロナ渦の影響で、ますます少子化が進んでいる、
2016年に年間100万人を切った出生数は、
あと5年もすると年間50万人まで減る!
と言われたらどうでしょう?そもそも少子化という記事が踊らない日は無いぐらい、日本における大きな課題・問題の一つですが、肌感覚以上に深刻になっているかもしれないというのが、本日のテーマです。今回は、厚生労働省のデータから、人口動態統計速報から出生数などの月次数字を使って、実態をグラフにしてみました。
ご存じの通り日本の出生率は年々下がっているのですが、コロナのような大きな事件事故の影響を見るために、月次でその推移を見てみようとと思います。なお、出生数は、7~10月が多く、2月が一番少ないので、経年の変化を見るために、各月の12カ月前数字と比べた昨年対比を並べてグラフにしています。なお、2020年1月以降はコロナ期間となり、通常期との比較ができなくなるので、その期間は2019年の同月と比較して出しています。
では、以下のグラフ1を見ていきましょう。年々出生数は下がっているので100%(黒線)を下回ますが、2020年までの下がり方と、2021年以降の下がり方に大きな違いがあるのがわかると思います。2021年1月を境に、ダウントレンドがより顕著になっています。(グラフが小さいのでクリックして大きくして見てくださいね)
このダウントレドの切っ掛けは、もちろん2020年3月ごろから本格化したコロナ規制です。この時期の社会不安が、適齢期の人々に与えた影響が、出産期間である”十月十日”後に表れてきました。

*ただし、2020年1月以降は2019年の同月を比較として対比
ただ今回の違いは、一時的なダウントレンドではなく、今も続いているのが特徴。比較として、同規模の社会的な不安や緊張が起きた2011年3月の東日本大震災を見てみましょう。以下のグラフ2は東日本大震災の前後期間を同じ指標で見たものです。なお、このグラフは、前出のグラフと違い、震災期間を含めて全月次を12カ月前数字と比較して昨年対比で表現しています。これを見るとわかるのですが、コロナ渦と違い、震災の”十月十日”(2012年1月)以降に、継続したダウントレンドは見られません。

同じような社会的なインパクトのあった東日本大震災と比べても、今回のコロナ渦は社会に与えている影響が大きいことが分かります。その大きさは、ダウントレンドの持続性に顕著に表れています。改めて前述のグラフ1を見てください、コロナ以前は減少はすれど振れ幅は小さく減っていた出生率は、コロナ渦後、2022年12月から最新データの2023年06月までで、実に7カ月連続で2019年対比で90%を切っています。仮に80万人の出生数が、毎年10%減少していくと、5年後には47万人と50万人すら割ってくるのです。コロナは、生活様式の変化だけでなく、大きな潮目を我々にもたらしているのではないでしょうか。
おまけ1:実は、死亡数も急上昇

*ただし、2020年1月以降は2019年の同月を比較として対比
出生数が下がるのと同じようなトレンドになっているのが死亡数。これもコロナ渦による社会的な緊張感や先行き不安が影響してなのか、はたまた団塊の世代が死亡数に多く含まれるようになったのか、仮説を検証するには、本記事長くなるので、今回は、数字のみにとどめます。にしても、我々が思っている以上にコロナ後の世界は大きく変わり始めていますね。
おまけ2:月によって結構変る出生数と死亡数

*2008年01月~2023年06月平均
実は知っているようで知らない月によって生まれてくる赤ちゃんも、死亡する人も結構違うという事実。出生数は、7月~10月がピークで、冬になると下がって2月がボトムとなります。つまり、子作りは冬場が多い。また、死亡率はもっと顕著で、梅雨の6月を底辺に、寒くなる1月をピークに大きく変動します。人間、暑さよりも寒さに弱いのですね。
Tips:季節(特殊)要因に気をつけろ!
上記、出生数も死亡数も季節要因が大きいときは、単なる前月比較をならべると、経年の傾向は見えなくなります。ということで、今回のように経年の変化を可視化したい場合は、その季節(特殊)事由を打ち消すために、昨年対比で月次差分を打ち消して指標化していくのが工夫の一つです。
独り言:
今回もそうですが、お役所のデータは、いまも元号中心で処理されていますが、データベースには、西暦も併記してくれないかな~と独り言ちてみる。ということで、今回は加工したExcelデータも置いておきますので、興味ある人は眺めてください。
本記事、お読みいただきありがとうございます。
無料記事にしては、情報量や質が”あったな”と思ってくれた方は、
以下にて「応援課金」よろしくお願いします。以後の執筆の励みにさせていただきます。
ここから先は
¥ 100
是非、サポートお願いします。データやメディア、そして、普段のビジネスで気になること、活用できることを発信して、少しでもみなさんの役に立つコンテンツになりたいと思います。
