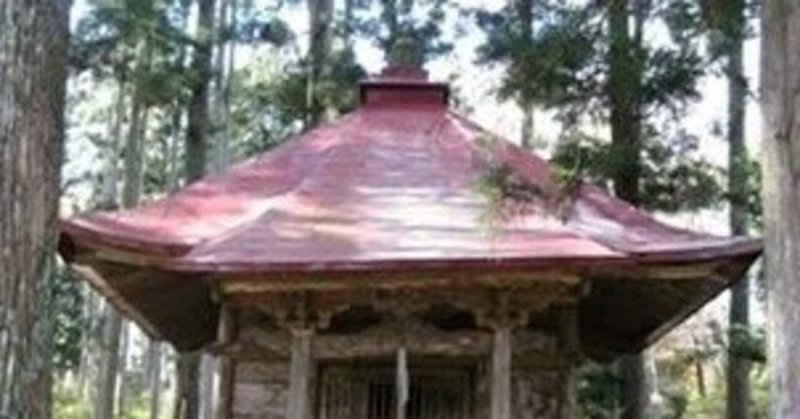
【神社】閖上の観音伝説 変わる観音像の姿
閖上の観音伝説をまとめておきます。
広浦の観音伝説(現:閖上)
「広浦の漁師である治兵衛が漁に出ていたが、
この日だけは一匹の魚もとれなかった。
彼が漁をやめて帰ろうとすると、
海底で光輝く物があるので、
直ちに網をおろして引き揚げると異様な御体神を得た。
彼はそれを大切に家に持ち帰り、安置して日夜拝んでいた。
こうしているうちに、浜の人々が、毎晩、不思議な光が西の方に飛んで行って高い山にとどまるのが見えると言いはじめた。
それを聞いた治兵衛は、光のとどまる場所が高舘山山頂である
ことを確かめると、御神体をそこに移し奉って高舘山羽黒権現と
称することにした。
養老三年(719年)6月15日のことである。
その後、保安四年(1123年)、名取の老女が紀州熊野三社
の那智宮の御分霊を合祀して、熊野那智山大権現と号することになったという。」

熊野那智神の御神体(藤塚碑の記より)
「元正天皇(715年~725年)の時、国郡に巡使を遣わし蝦夷を討たんとして諸国に疫病を祭祀した。
その際、陸奥の国に熊野那智の神を分霊して御船に遷幸し陸奥国へ出帆下向の途、海上風に遭い遂に難破した。
時に養老元年(718年)六月十日、
名取里浜の橋浦茂右衛門が海辺にて波間に光明輝くと
心づき磯辺を尋ねてみると、藤蔓揺り揚がり藤の後に神体が出現された。
茂衛門は心霊を守護して里浜の明神堂に安置した。
その官令があって名取の高舘山に遷祀(移し祀ること)
して那智権現を祀り、藤蔓は中島浜に塚を築いた。
それより里浜を揺上浜(ゆりあげ浜)とし、中島浜を藤塚と改称したという。」※1
※御浜下りの祭では、高舘山から神輿を閖上新町の橋浦家で
休むのが恒例となっています。
本地仏のこと
本地仏とは
仏が人々を救済するために神の姿をかりて現れるという、
本地垂迹説にもとづくもの
名取熊野の本地仏
阿弥陀如来→熊野本宮社
薬師如来→熊野神社(新宮)
観音菩薩→熊野那智神社
※聖観音→羽黒山
千手観音→紀州熊野那智神社
ということで、名取熊野那智神社は、紀州に合わせると千手観音に。
しかし、閖上からゆりあがった観音様は、
奥州札所三十三観音一番札所ですが、十一面観音です。
高舘山で発見された懸仏は、146体中、140体は聖観音。
他、阿弥陀如来は4体、十一面観音と千手観音が1体ずつ。

高舘山にある観音像はこちらのサイトに書いてあります。
閖上天正院の話し
他、閖上には修験者による十一面観音像があります。
閖上天正院(行屋:修行僧・修験者などが行をする家)があり月山(阿弥陀仏)、羽黒山(観世音菩薩)、湯殿山(大日如来)、 蔵王権現を祀っていたそうです。
地元の伝承より、
『明治22年閖上中町に住んでいた漁師が、
なげ網に出かけ漂流中に、一体の仏像を発見した。
それを拾いあげきれいに洗って保存していたところ、一家全員が腸チフスになった。仏罰を恐れたその家では、早速、仏師に頼み、
修復させ行屋におさめたという。
安置されたのは、奈良県吉野金峯山の金剛蔵王権現の分霊とされる。』
閖上湊神社の由縁によれば、
「不動明王像を除く四体の明王像は閖上の羽黒山修験行堂天正院に、
十一面観音像は同じく閖上の淘上山観音寺
(真言宗智山派)の仏として安置されました。
後に天正院は当社の所有となり、
四明王様をお祀りしておりましたが、
東日本大震災の津波により流失してしまいました。
なお、不動明王像については閖上外の寺に安置されるも
火災により焼失したと伝えられています。」
現在は、新しく湊神社が再建されています。

<御祭神>
健御賀豆智命、伊波比主命、天之児屋命、比売神
<末社> 富主姫神社(竹生島弁財天)
竹駒神社遥拝社

福島県桑折町の大聖寺の鐘に記された(「名取旭女者~」)
があり、生誕地説もあるのですが、
こちらも聖観音像が納められています。
羽黒講の修行者による由来が主であるなか、
十一面観音像である理由は、詳しくわかりません。
補陀楽渡海と室根神社
熊野には、「補陀楽渡海」があります。
那智の滝に対する信仰は、
熊野灘を行き交う船舶が、この滝を目指したという
海上安全の信仰が根底にあります。
地震、津波の影響を受けていた地なので、どこからか流れ着いた仏像や、火災から守るためだったのか、沼や池に見つかる仏像の伝説は数多くあります。
その多くが十一面観音の長谷からくる水脈=水の観音(長谷観音)説があり、東北地方に広く分布していたと言います。
「いったいどのくらいの数の長谷寺が全国にあったのであろうか。
その分布はどうなっていたか。わが東北は、どうなっていたか。それは、実に大変な数になっていたのである。わたくしは、大正十三年刊『豊山小史』により、『豊山玉石集』というのに、その諸国分布を示していることを知った」※高橋富雄「大和長谷寺と東北長谷寺」より
おすずひめ伝説が伝わる岩沼には「長谷」の地名があります。

石巻や気仙沼の県北に多い長谷観音堂を考えると、東北地方では、長谷観音が広まっていたと考えられます。
また、
病気治癒のために奈良時代は、十一面観音像が多かったそうです。
後に、救済の観音像に人気となり、聖観音になった説があります。
しかし、橋浦家の伝説を読むと、
十一面観音像が、陸奥開拓によってもたらされた観音であるとも受けとれるのですが、
蝦夷征伐と陸奥への開拓のために船で訪れた
大野東人の室根神社が繋がっているかもしれません。

大野東人:737年『日本書記』
色麻の名前が登場する。
初めて色麻柵を設けたのが大野東人と言われる。
一関市「室根神社マツリバ行事」より
「本宮は養老2(718)年、鎮守府将軍大野東人が、
当時霊威天下第一とされていた紀州婁郡本宮村
(現在の和歌山県田辺市本宮町)の熊野神をこの地に勧請。
蝦夷との戦いで苦戦したことから、
神の加護を頼ろうとしたものです。
熊野神の分霊は、和歌山県から船で5カ月間もかかって
現在の宮城県気仙沼市唐桑町に到着。
東人は白馬17騎の諸郷主を招集して神輿を迎えました。」
※本宮の金と新宮の銀(金銀の鈴)が伝承されています。

名取の那智神社と室根神社の創建年代が
同じになっている事も、関係がありそうです。

名取川の源流は「神室山(かむろ)」です。水に対する観音信仰は、
海と川にあると考えられます。
その海に繋がる「室」は修験の中でも洞窟に籠るものとして伝わり、
東北地方には神室山、室根山など、室と着く名前の山があります。
栗原にある栗駒山にも奥の院は御室です。
一関の室根山は、牟婁峯(むろね)山と変えています。
昔は室根山は、「鬼首山」と呼んでいました。
別説では、穂積臣がこの山に熊野神をたて、
紀州熊野から勧請してから室根に名前をかえたとも。
名取のゆりあがった観音様は、古くは、物響寺からきた羽黒の観音様であったが、後の陸奥開拓による熊野神のご加護により薬師(大野東人に関係)の疫病退散により治めたことを伝承しているでしょう。
東北地方における熊野の歴史は、海と山が交差しています。
日本海→山路(出羽三山信仰)→太平洋へ伝播へ。
太平洋→山路(熊野信仰)→日本海へ伝播。
双方の海と山を結ぶ修験(出羽と熊野)が、
名取熊野三社で融合していることは、
非常に興味深いことです。

※1 『閖上の歴史の一端をひもとく』大脇兵七著
あわせてこちらも。
薬師信仰については、こちらを。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
