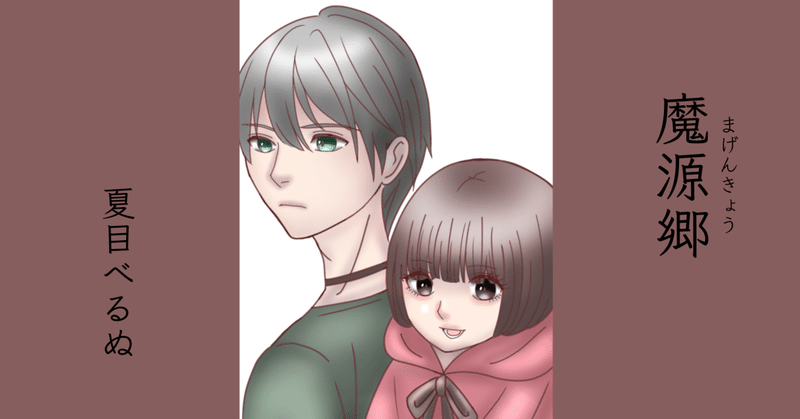
魔源郷 第20話「魔物の村」
街道を越え、山道を歩いているフィンとマリー。
「大丈夫かしら…。そこへ行ったら、私たちは魔物に襲われるんじゃないの?」
マリーは不安を口にした。
「それを分かってて来たんじゃないのか?」
「分かっててって…。やっぱり大丈夫じゃないのね…。」
マリーは恨めし気にフィンを見た。
「確かに私は魔物について知りたくて来たけど、戦う気はなかったから…。」
「奴らだってそんな感じなんじゃないかな。自分から襲いたくて襲ってるわけじゃないんだから。あくまでも身を守るためなんだ。まあ、中にはどうしようもない衝動に駆り立てられて暴れる奴もいるが…。」
「そう考えてみれば少しは気分がラクだけど…。でもやっぱり心配…。いつもと違うから。いつもは、戦う気で魔物と向き合ってたから。今は、例え武器を持ってても丸腰でいるみたいな感じ。そうだわ、こんなもの持ってたら、余計危ないんじゃないかしら?」
マリーは腰に装備している銀の剣に手を当てた。
「そんなに心配なら、捨てれば。」
「捨てるなんて!それは出来ないわ。大事な剣なんだから。」
「じゃ、使わなければいいだけのことだ。」
「…どうしてそんなに落ち着いていられるの?自分の命がかかってるのよ。」
マリーは呆れたように言った。マリーには、あまりにもフィンには緊張感がない様子に見えた。
「あなたは信用出来ると思ったのに…。」
疑惑の目でマリーはフィンを見た。
フィンは気にしたふうもなく、地面から引っこ抜いた雑草をばりばりと食べながら歩いていた。
「あんたが決めたことだ。魔物に会いたくないなら引き返せばいい。」
「いいえ、引き返さないわ。一度決めたことは必ずやり遂げると誓ってるの。ここで引き返したら一生後悔すると思う。…本当に魔物がいるんでしょうね?」
マリーはフィンを睨み付けた。
「俺の頭がおかしくなければ、この先に奴らはいる。そして一つ言っておくけど…。」
と、フィンは立ち止まって、マリーを正面から見据えた。
「俺はあんたを信用しているから、この先に行くんだ。俺は奴らを仕留めるためにこの先に行くわけじゃないし、彼らを危険な目に遭わせようとしているのでもない。あんたがそういう輩ではないと判断したから、このまま先に行く。もしそういう輩だったら、この先へは行かないよ。」
そしてまた歩き出した。
「ごめんなさい…、疑って。せっかく案内してもらっているのに…。」
マリーは項垂れた。
「別に謝ることはないって。まあ、普通に考えて正気じゃないよな、自ら魔物の巣に向かうなんて。それを怪しむのは当然のことだ。」
「…そうね。私も何かおかしくなってるみたい。今まで敵と思ってたのに、変…。」
マリーは笑って言った。
しばらく歩き続けた。
静けさの中で、マリーは緊張する心だけを感じていた。
そして人里のようなものが見えたとき、気持ちが少しだけ緩んだ。
「あれって…?」
「崖になってるぞ。気を付けて降りろ。」
フィンが注意した。足元を見ると、ほとんど崖のようになった急な坂になっていた。その下をずっと行くと、遠くに見えている里に辿り着く。
深い谷の底にある里。
「あそこに、魔物がいるの?どう見ても人が住んでるようにしか見えないけど。」
「魔物が住んでいるのは、何も洞窟の中とは限らないだろう。」
「それはそうだけど…。」
マリーの想像とは違っていた。
谷の底に到着して、里に近付くにつれ、その思いは強まっていった。
石で造られた簡素な家が立ち並んでいる。
「何者だ!」
里の入り口に人が立っていた。
一見すると人間のように見えるが、マリーはその者が魔物であると分かった。
「ただの旅人だ。ちょっと、ここに立ち寄りたいだけなんだけど、通してもらえるかな。」
フィンが言った。
「駄目だ。通すわけにはいかない。その格好、猟師だろう。」
魔物の男は、警戒した態度でフィンたちを探るように睨んでいた。
「確かに猟師だが、別に何もしない。疲れてるんだ。休みたい。」
「あ…あの…、私は戦いに来たのではないわ。つまり…、あなたたち魔物のことを知りたくて。」
マリーは緊張しつつも、まっすぐに魔物を見つめて言った。
「知ってどうするんだ。この場所のことを他の奴に知らせるつもりか。」
「いいえ。そんなことはしないわ。疑うのも無理ないけど、今は信じてとしか言えない。私もあなたたちを信じるから。」
「おかしな人間だな…。」
「とにかく通してほしいね。歩き続けで、ぐったりなんだ。まあ、駄目なら仕方ないけど。」
マリーはフィンの方を訝しげにちらと見た。フィンは本当に疲れたような顔をしていた。
「お願い。」
マリーは頭を下げた。
「駄目だ、駄目だ。俺はここを守らなければならない。お前たちのような怪しい者をここに入れるわけにはいかない。」
「そうよね。あなたの立場だったら私もそうすると思う。」
マリーはそう言って、銀の剣を手にした。
「何をする気だ!」
魔物が身構えた。
次の瞬間、マリーは剣を自分の太腿に突き刺した。
「お、おい!」
フィンが驚いて叫んだ。
魔物も驚いてマリーを見つめた。
「何やってんだ!?」
「ここまで来て、引き返せない…。」
マリーの脚が血で赤く染まっていく。
「お願い。」
マリーは魔物をじっと見た。
「無茶なことを!何考えてんだ。おい、まさかこんなことまでしてる奴を見捨てたりしないよな。」
フィンは魔物を見た。
「ち!分かった、分かった!」
魔物は仕方なく、二人を里の中に入れた。
「本当にびっくりしたというか何と言うか…呆れたね。」
フィンがマリーを見て言った。
「どうすればいいか、これしか思いつかなかったの。賭けよ。」
入り口を守っていた魔物に連れて来られた所は、小さな医院のような所だった。
「もし助けてくれなかったら、私は疑問を持ったまま帰ることになったわ。でも信じた通り、助けてくれた。」
「自分が死ぬかもってことは考えなかったんだな…。」
「私は死なないわ。加減したし。意志を見せたかっただけだから。」
マリーは魔物に手当てされて、脚に包帯を巻かれた。
門番は一人の魔物を連れて来ると、また里の入り口に戻っていった。
その魔物は、人間に似ているがやっぱり明らかに魔物で、先のとがった奇妙な耳と細長い尾があった。顔を見ると、人間の老人のような髭が生えており、深い皺が刻まれていた。
「聞きましたよ。困った人ですね。ここへ入るためにそこまでするなんて。」
老人はマリーを見て言った。
「しかしそれで、汚らしい気持ちでここへ来たわけではないと分かりました。」
「私は猟師ですが、魔物について知りたくて来たんです。」
「よくここが分かりましたね。」
「いや、ここにこんな村があるとは知らなかったんです。俺は魔物の気配が分かるので、それで見つけたというわけで。」
「魔物の気配を?」
老人はフィンをじっと見つめた。
「君たちは…信頼出来そうな人間ですね。そんな人間を見たのは、久しぶりです。ここには、我々以外何者も寄り付かない。寄せ付けもしない。この村は我々だけの秘密の村ですから。我々は、ただひっそりと静かに暮らしたいだけなのです。分かってもらえますね。」
「はい。」
マリーは頷いた。
「傷が癒えるまで、ここに滞在するといいでしょう。魔物について知りたい、と仰ってたそうですが。あなたたちのことは私が皆に話しておきますから、ご心配なく。申し遅れましたが、私はこの村の村長のモートルと申します。」
「私はマリーです。」
「フィンです。」
「マリーさんとフィンさんですね。私は結構長生きしてましてね、百何歳なのです。百と…少し。細かい数字はもう忘れましたが。」
老人は笑った。
「私はこの通り、猟師です。正直に言いますが、今まで魔物…魔獣を何匹も殺してきました。それが当たり前のことだと思ってしていたのです。」
マリーは老人の目を見て話し出した。
「そうですね。猟師とはそういうものでしょう。人間が魔物から身を守るためならば、仕方がない。」
「…私は幼い頃、魔物に家族を殺されて、ずっと憎んできました。人間が善で、魔物は悪だと思っていたんです。でも…、人間同士の争いを見て、そうじゃないことが分かった…。それで私は分からなくなったんです。本当に魔物は悪で、それを殺すことは正しいことなのか。だから魔物のことを理解したいと思ったんです。ここに来て驚きました。このように、人間と変わらない暮らしをしているなんて…。暴れて人間を苦しめる魔物しか知らなかったから…。」
「猟師の人たちは、魔物のことを他の人間よりよく知っている、らしい、と聞いていたのですが…。」
「知っているのは、魔物の種類とか、弱点とか、そういう表面的なことです。戦うための。中身のことなんて全然考えもしてませんでした。何を考えているのかなんて。」
「では話しましょうか。魔物の起源を。魔物とは、人間から造られた生き物だということです。」
「え!?人間から?」
「そうです。人間と獣を融合して造られたもの。それが魔物です。何故造られたのかは謎ですが。我々のように、穏やかに生きている魔物もいれば、暴れている魔物もいる。人間もそうではありませんか?つまり、たいして変わらないのです。人間も魔物も。ただ魔物は、魔獣に変身すると脅威的な力を持ちますから、それが人間を苦しめることになります。だから猟師という職業が生まれた。魔物から人間を守るために必要な力ですね。」
「に…人間と獣から…。知らなかった…。」
マリーはしばらく言葉を失っていた。
「我々魔物を造り出したのは、他でもない、あなた方人間です。」
「それじゃ…人間は…人間自ら造り出したもののために…。」
「そういうことです。」
「ばかみたい…。なんてこと…。何故そんなことしたのかしら…?」
「それは分かりません。」
「私たち人間は知らなさすぎる…。もしそれを皆が知ったらどうなるかしら。」
「どうにもならないね。」
フィンが言った。
「今更、何も変わらないよ。魔物は人間の敵。人間は魔物の敵。それはもう確定しているんだ。今更、魔物の起源を知った所でどうにもならない。猟師もなくならない。それとも、あんたはそれを聞いて憎しみが消えたとでも言うのか?」
「いいえ。今でも恨んでるわ。私の家族を奪った魔物のことは。」
マリーは唇を噛んだ。
「複雑なのよ…。原因をたどって、考えていくと。私の家族を殺したのは魔物。それを造ったのは人間。一体、何を憎めばいいの?一体、何に復讐すればいいの?…虚しいわ。」
「あなたが自分の家族を魔物に殺されて、魔物を恨むのは当然のことです。それと同じように、我々の中でも、人間を恨む者もいる。それは心がある者なら当然のことなのです。我々は心のある生き物です。その点では変わりない。しかし、あなたが虚しく感じるのは、憎しみによってお互いに殺し合っても、何もならないことが分かったからでしょう。死んだ者が帰ってくるわけでもない。仇をとったとしても、心が癒されるでしょうか。」
「でも…私は誓ったのよ!猟師になって、魔物を退治するって。そうすることが、私の使命だって思って今まで生きてきたのに!これじゃ私は何のために…。」
「一つ言えるのは…、あなたは魔物に憎まれる存在、猟師であるということです。猟師として生きていく限り、あなたは魔物に憎まれ続けるでしょう。」
「…モートルさんはとても親切な方ですね。私は猟師なのに…。」
「年をとると、何事にも寛容になってくるのですよ。」
「猟師ではなく一人の人間として扱ってくれるのですね。…私、動けるようになったら村を見て回りたいんですが。」
「自由になさって結構ですが、一つ忠告しておきます。猟師の格好で外に出るのはやめた方がいいですよ。村長として、無用な争いはしてほしくない。あなた方のことは村の者に話しておきますが、決して、皆を怖がらせるようなことはしないで頂きたい。」
「ええ。分かっています。」
マリーは杖をついて村を歩き回った。
剣は持たずに。泊めてもらっている村長に預けていた。
村の魔物たちは、マリーの姿を見ると、用心深く遠くからじっと観察したり、すばやく家の中に逃げ込んだりした。話しかけてくる者など誰もいなかった。
フィンは背中に剣を背負ったまま、マリーの様子を遠くから見守っていた。
「何しに来たんだ!」
魔物の子供が、マリーに向かって叫んだ。そして、マリーに向かって石を投げた。マリーは無意識で石をよけた。
「人間め!」
マリーはその子供を見て微笑んだ。
子供はマリーの笑顔を見て、戸惑ったような顔をした。
「何笑ってんだ!僕は許さないんだからな!お前たちのせいで、僕たちはこんな所に追いやられて暮らさなきゃいけないんだ!いつかここを出て仕返ししてやるからな!」
子供はそう言って、走り去っていった。
その後ろ姿をマリーはじっと見つめていた。
マリーの姿を、村人たちは遠巻きにして見ていた。
村人たちの視線が、マリーには冷たく感じた。
「皆さん!」
突然、マリーは叫んだ。
その声に村人たちは驚き、立ち止まってマリーを凝視した。
「聞いて!いえ、聞かなくてもいいわ。これは私の独り言。でも出来れば聞いていてほしい。…私は、魔物を憎んでいた。今も。あなたたちも、私を、人間を憎んでる。人間が魔物狩りをしているから。でも私だって、魔物に家族を殺されたわ。それで憎んでる。だけど、この憎しみが、一体何を解決してくれるっていうの?お互いに憎み合って、殺し合って。泥沼に入ってくだけだわ。この争いがいつまで続けば、本当の平和がやってくるの?人間同士でさえ、争っているっていうのに。お互いに譲り合わなければ、永遠に、平和はやって来ないのよ…。」
村人たちは、しばらく呆然としてマリーを見つめていたが、それ以上、マリーに近付こうとする者もなく、それぞれの場所に戻っていった。
ただ、先程マリーに石を投げた子供だけが、遠くから、マリーをじっと見続けていた。
マリーの傷も癒え、特に変わったこともなく日々が過ぎた。
そして、この村を去るときが来た。
「ありがとうございました。」
マリーは村長に向かって頭を下げた。
「いえいえ。こちらこそ、久々に良い機会を与えてもらいましたよ。村の者も、人間を珍しがっていましたから。とりあえず、何事もなくてほっとしました。」
「そうですね。」
マリーはにっこりと笑った。
そこへ、一人の子供が走ってきた。この間、マリーに石を投げた子供だった。
「あの子…。」
マリーは子供を優しい目で見つめた。
子供は、少し離れた所で立ち止まり、マリーの顔をちらと見て、顔を背けた。
「…ごめん。」
子供は、それだけを言って、再び走り去っていった。その後ろ姿を、マリーは、穏やかに微笑みながら見送っていた。
マリーとフィンは村を出た。
「ありがとう、フィンさん。私の心が決まったわ。」
「どうするんだ?」
「猟師を続けるわ。だって、一度決めた道だから。私は猟師として生きる。」
「そうか。」
「でも、前とは違う。魔物がどういうものか、猟師がどういうものか、少しは分かった。私の選んだ道がどれだけ重いものか分かった。それでも、私は猟師を続ける。私は人間だから、人間を守らなければならない。…そう思うの。」
マリーはそう言って、下を向いた。
「魔物を造ったのは、私と同じ人間でしょ。だから、私にも責任がある。人間のしたことだもの。自分たちのことは自分たちでどうにかしなきゃって思ったの。私はそういう気持ちで猟師を続けるわ。他の猟師は関係ない。私の信念よ。そのために魔物に憎まれようと、それでもいい。私の憎しみだって消えない。でも仕返しとか敵討ちのためにやるんじゃない。これが私の使命だから。」
「そんなに堅苦しく考えてると、いつか頭の中が爆発するんじゃないか?」
フィンが笑って言った。
「私は真剣に言ってるのよ。笑わないで。」
マリーは膨れた。
「でも、あなたなら分かってくれると思う。私は人間だから、人間を助ける立場にある。それは変えられない。猟師をやめることは、今までの自分を捨てることと同じ。一度踏み入れた道を引き返すことは出来ない。それはもう変えられない。」
「まあ、自分が正しいと思ったらそれでいいんじゃないのか。」
「ええ。」
マリーは強く頷いた。
街道の方まで歩いてきて、道が二手に分かれた所へ出た。
「フィンさん、ありがとう。あなたのお陰で、私は決心出来た。前よりも、猟師として生きる覚悟が出来たわ。フィンさんはこれからどうするの?」
「どうするって、魔物の気配を探して進むだけだよ。」
「そうだったわね。魔物の気配が分かるのよね。便利な力だけど、私には必要ない力。フィンさんは魔物を浄化出来るけど、私は魔物を殺すことしか出来ないから。それでどっちへ進むの?私はその逆を行くことにするわ。」
フィンは進む方向を無言で指し示した。
「…思ったんだが…、あんたは優しすぎる。その心を捨てないと、猟師を続けられないぞ。」
「心配してくれるの?でももう大丈夫だから。」
マリーは微笑んだ。
「あんたはもう、魔物を同じ生き物としか認識出来なくなった。その状態で、猟師として、魔物を殺し続けるのは辛いだろう。」
「そうね。でも、それが重要だと思うわ。罪悪感を感じること。何も感じなくなったら、終わりだと思う。人間としてね。…フィンさんは、猟師をやめさせるために私を魔物に会わせたの?」
「そういうわけではないが…。猟師を続けるなら、余計な感情は一切捨てることだ。」
「フィンさんは、感情を捨てたって言うの?」
「とうの昔にな。」
「じゃあ、どうして私を連れて来たの?魔物の気配が分かるなんて言って。そう言わなければ、ここへ来ることはなかったわ。」
「あんたが困っていたから。」
「それは、思いやりね。ほら、フィンさんだって、猟師なのに感情を捨ててないじゃない。」
「感情とは違う。思いやりでもない。やるべきことだからそうしているまでだ。」
「私には、そうは思えないけど。今だって、心配してそう言ってくれてるんでしょ。」
「どう思っても勝手だが、これは忠告なんだ。」
「フィンさんは、何かに縛り付けられているように見えるわ。自由じゃないみたい。」
フィンの表情が微かに変わった。
「美しい景色や生き物を見て、美しいと思うのは、人間として当たり前の感情だわ。もしそれがなくなったら、終わりって気がする。美しいものを美しいと感じられなくなったら、人間じゃない。それと同じよ。罪悪感も。それがある限り、私は人間なのよ。猟師である前に、私は一人の人間。分かってて魔物を殺すの。異常かしら。でもそういう宿命だと思ってるから。やらなければならないのよ。例え罪悪感にさいなまれても。」
マリーはそう言って、穏やかに微笑んだ。
フィンは黙ってマリーを見つめていた。
二人はそれぞれの道に戻って行った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
