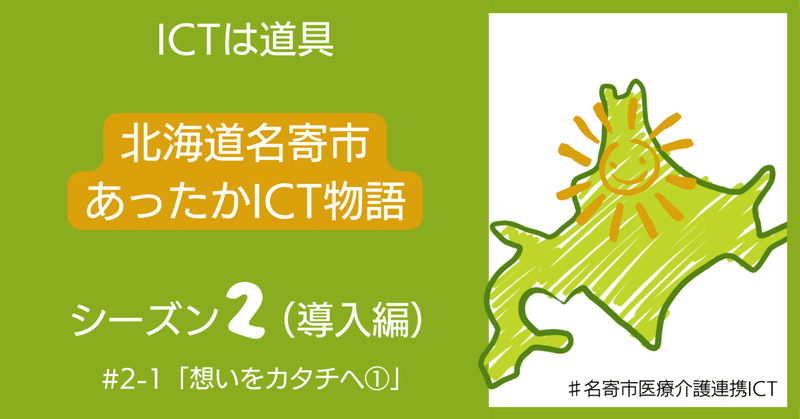
#2-1 北海道名寄市あったかICT物語【シーズン2(導入編)】
エピソード1「想いをカタチへ①」
執筆・インタビューを担当するのは・・・
こんにちは!
(社)地域包括ケア研究所の大曽根 衛(おおそね まもる)です。

シーズン1に引き続き、2020-21年度(令和2-3年度)に「名寄市医療介護連携ICT導入・運用アドバイザー」として、関わらせていただいた立場から
、「ICTにまつわる物語」を記していきたいと思います。
★名寄のICTはあったかい
シーズン1の冒頭でも触れましたが、名寄市の医療介護連携におけるICTの取り組み、とにかくあったかいんです。
導入に至る背景も、導入方法も、導入後の活かし方も。
「あったかさ」はなかなか言葉では伝わりにくいですが、さまざまな形でできる限りお伝えしていきたいと思います。
★シーズン2のスポットライト・・・
シーズン2では、ICT導入編として、
キーパーソンなど「ひと」にスポットライトを当てながら、実際にICTのシステム導入に着手する2020年(令和2年)4月からを見ていきます。
お一人目は、2020年4月から名寄市行政職員に参与として着任され、ITの専門家としてICT導入を具体的にカタチにしていかれた守屋潔さん(名寄市健康福祉部参与 地域包括ケア ICT システム担当)。
続けて、導入プロセスを共創してくれたケアマネージャの井上正義さん(名寄社協指定居宅介護支援事業所)と江口英樹さん(居宅介護支援事業所SUN)。
さいごに、シーズン1でもお名前が出ていた本プロジェクトのリーダーの酒井博司先生(名寄市立総合病院 副院長・患者総合支援センター センター長・名寄市医療介護連携ICT協議会 会長)にスポットライトを当てていきます。
同じICTをそれぞれの視点から見ていくと、より立体的に感じられるとともに、各自の想いがICTに体温として伝わっていく様子がわかっていただけると思います。
それでは、守屋潔さん(名寄市健康福祉部参与 地域包括ケア ICT システム担当)にお話をうかがっていきます。

★名寄着任直後に見た景色
大曽根
それでは守屋さん、よろしくお願いします。
守屋
はい、よろしくお願いします。
大曽根
守屋さんは、東北大で通信工学を専攻され、民間企業で経験を積まれた後、2008年より旭川医科大学に転職されました。当時急務だった道内の遠隔医療ネットワーク構築に多数携わられ、ポラリスネットワーク1.0の立ち上げにも参画されました。
そんな守屋さんが、シーズン1の主人公でもある橋本さんの救世主として名寄に着任されることになったのが、2020年4月ですね。
守屋
はい、いろんなご縁が重なって約2年前に名寄に着任しました。
大曽根
着任当時、どのような景色を守屋さんは見られていたのですか?
守屋
名寄に着任して最初に、包括が中心になってヒアリングしてきたケアマネさんの声を集めた資料を受け取りました。
EXCEL で 480 行になる膨大なものでした。
順不同で重複もありましたが、生々しい現場からの肉声がそのまま記録されていて臨場感がありました。
医療に対する困っていること、不満、要望が書き連ねてありましたが、別に病院から介護側に対する要望のリストもありました。
これは大きかったです。

ー大曽根
その情報があるかないかで全く動きが変わったのですね。
ー守屋
橋本さんたちが集めてくれたこの具体的な声を手がかりにすればシステムを作るのは簡単だって感じました。
改めてヒアリングをしないといけないとなると、それだけで1年は後ろ倒しになっていたでしょうね。もしくは、声を聞かずに作るか。。
2020年度(令和2年度)には導入のための概算予算をあげていたので、この情報があるかないかは天地の差です。
入り口として、システムのたたき案を作るために、まず素材があったというところがひとつポイントでした。
ー大曽根
橋本さんにとってカオスの状況の中で、ちゃんと握ってたバトンがあったというわけですね。
—守屋
これはもう餅は餅屋ですよ。
やっぱり専門の人間であれば大したことはないことでも、そうでないと大変なことってありますよね。
橋本カオス時代に、よくあの成果物を作ってくれていたなっ!て思います。
橋本さんはすごく回り道をした、ぐるぐるぐるぐる回り道したって言いますけど、とんでもない。
ゴールに向かって素晴らしい、理想的な道を歩んできてくれたなあと思って。
とはいえ、もちろん大変だっただろうなって思いますね。
ー大曽根
そのリストをどのように活用していかれたのですか?
ー守屋
このExcelの480行をプリントアウトして、毎日カバンに入れて色んなところに持ち歩いて何回も読み込んだんですよね。
さらに4月、5月の2カ月間に全介護施設を挨拶も兼ねてまわりました。
いろいろな立場の人から話を聞いたり、あるいはアンケートで言っていることがこれが本当かどうかっていうこと確認したりしてました。
この2カ月間、ケアマネの業務を教えてもらいながらフロー図にまとめてみたりもしました。

図にしていくと、どの部分の情報を集めてくればいいのか、どこで連携できるかとか、だんだん見えてくるんです。
どのような情報がお互いで共有できればよいか整理していく作業を行い、最終的に 25 項目に絞りこみました。
この 25の情報を医療介護現場から収集して共有できる仕組みを作ればよいと考え、システムの仕様を作り上げました。
25項目中の23項目はシステム化できるなぁという風に踏んだんですよね。
全体でいうと要望事項の90%はシステムで応えていて、しかもとても安価に構築できるようにした。
そもそも一般的に100点満点のシステムを構築するというのはコストや実現性を考えても現実的でなく、運用でのカバーや工夫とセットで構築していくことが大事だと思っています。

そういうことも含めて、私としては上出来だったと思っていて、6 月からケアマネ向け、介護施設向け、調剤薬局向けなど職種ごとに説明会を開催しました。
でも、、
「あれ?」って感じで、みなさんの反応がなかったんです。
ー大曽根
要望に応えている自信もあったのに、反応がなかった。
ー守屋
そうなんです。
自分としては自信を持ってプレゼンしましたが、しかし参加者からは質問もなく手応えを感じられませんでした。
その後も何回か説明の機会を持ちましたが積極的な支持を得ることはできなかったばかりか、「こういうものを望んでいたわけではない」との批判も少し受けました。
現場から言われたとおりに必要な情報を参照できるようにしたのに、なぜ理解してもらえないのだろうかとの失望感は隠せませんでしたが、しかしシステムの仕様としてはこれしかないだろうと考え、粛々と準備作業を進めていきました。
さらに、困ったことは運営協議会の委員になってくれるケアマネジャーの候補がなかなか見つからなかったことでした。
そんなとき一人のケアマネジャーが立候補してくれました。
それが、井上正義さんです。
井上さんは「ICTに可能性を感じる!」と発言してくれました。
暗闇の中に一筋の光が差し込んだ瞬間でした。
ー大曽根
守屋さんもある意味でプチカオスに入っていたんですね。
知らなかったです。
★強烈な反省と手触り感のあるプロセスづくり
ー守屋
当時は、橋本さんと私が少し孤立していた感じだったかもしれません。
それにも関連しますが、ICT立ち上げにはシステム構築だけでなく、運用を検討する話し合いの場が必要ということを経験的に知っていたので、システム構築費用を賄う補助金制度と同時に、外部からアドバイザーを招聘する費用を補助してくれる制度のほうにも応募していました。
北海道庁がICT導入アドバイザー事業制度をつくってくれていたこともとてもありがたかったわけです。
ただし私の中では、アドバイザーには有識者に指導してもらうというよりも、みんなが話し合える場作りをしていく、ファシリテーターの存在をイメージしていました。
2020年9月、予算内示を受けてICT導入検討会議を立ち上げ外部アドバイザーとして大曽根さんに加わってもらうことになりました。
大曽根さんは、これ以前からも名寄市の取り組みには関わってもらっていましたが、この補助金制度で正式に依頼することができましたね。
さっそく大曽根さんから「介護の現場の方にとっては ICTの肌触り感がないのだろう」と指摘され、運用のイメージをつかんでもらうためワークショップを開催していくプロセスを用意していくことにしました。
ー大曽根
そうでしたね。
システムを自分たちのものとして使っていただくには、導入前のプロセスにいかに関わってもらい、自身の業務や患者さん・利用者さんの医療やケアに具体的にどのようにプラスになるのかが、イメージできることが大事だと思ったんです。
みんなで一緒に対話して、考えて、そして自分たちに合った形や使い方ができあがっていく。
企画メンバーとしては<手触り感のあるプロセス>として、
***
①事例検討を通じて連携のあり方をアップデートする:2020.9-2021.1
②ICT先行トライアル:2021.2-2021.5
③トライアルのふりかえりと磨き上げ:2021.3-2021.6
④ICT本格稼働:2021.7-
⑤輪を徐々に拡げる:2021.11-
***
というイメージを創りましたね。

①の事例検討会も、5つの具体的ケースに関係する多職種が毎回違ったメンバーで集まって話し合ったわけですが、別にICTじゃなくても患者さんや利用者さんにプラスになるが事あったらみんなで出し合おうという感じでおこないました。
実際、あの時期どんなことを守屋さんはお感じになっていましたか?
ー守屋
事例検討会やってすぐにみんなが盛り上がったかっていうと、必ずしもそうではなかったと思うんです。ちょっとずつちょっとずつっていう感じ。
でもちょっと可能性は感じるなとかね。だけど自分がやるのは・・・と、最初はおっかなびっくりだったと思います。
そして、私はケアマネたちから具体的な利用者さんの支援の様子を聞いてものすごく反省の思いがこみあげてきました。
それまで「情報(データ)」を中心としてシステム設計をしていましたが、そこに「人」が住んでいなかった。
一人の利用者を中心に関わる多くの人たちの動き方をイメージできていなかったので、何度ICTの機能について説明をしても共感を得られなかったのだなと。
自身の介護への共感の欠如を悟りました。
事例検討会やワークショップでの話し合いを重ねることで参加メンバーの中にもICTへの期待、可能性を感じてもらえるようになったように思えます。

ー大曽根
守屋さんは、よくICTはあくまでも道具だからとおっしゃっていましたね。
ですので、事例検討会でもICT云々関係なく、まずこのケースにおいてどういう連携が望ましいのかをみんなで考えるところから始めました。
その中に少しICTの可能性も入れていこうねっていう流れをつくりました。
多職種が集まって「連携」を感じれるって事がまさに手触り感があり、あたたかい感じだったのかと思います。
★手ごたえを感じた先行トライアル
ー守屋
その流れがあったうえで、システム設置の準備が整い、2021年2月からの先行トライアル期間がうまくいったことが大事だったと改めて思います。
先行トライアルのメンバーのドクターが主治医をされている 4 名の患者を対象として、関わっているケアマネ、包括、訪看、薬剤師、通所介護、訪問介護、そして病院の患者総合支援センター(看護師、MSW)がトライアル運用メンバーとなり、ICTを使ってみて運用方法を検討するという試みです。
先行トライアル・キックオフミーティングでは「もし ICTがあったら」との想定の元に皆が意見を出し合うことで大いに盛り上がったことを覚えています
ただ、介護の方の中には、いざ始まるにあたってもまだ不安でやめようかと迷っていた方もいたんです。
たとえば、デイサービスと訪問介護事業所が一番情報を発信する量が多いんですよね。
今までデイサービスとか訪問介護の人たちは自分達は情報は出すばっかり。
出さなきゃいけないんで出すんだけど、他事業所からの情報は返って来ない。
自分たちは情報を出すけども全体の動きがどうなっているかは分からないなどの感情もあったのかと思います。
ー大曽根
それが先行トライアルが始まってみて・・・
ー守屋
はい、それが返ってくるようになったわけですよね。
全体の動きが見えるようになったと。
そこに一つ可能性を感じてくれたのかなあと思うんですよね。
いざトライアルやってみて実際デイサービスや訪問介護の人たちが一生懸命投稿してくれたんですよね。
それこそデイサービスで利用者さんがこんな事を話してたとか、食事美味しいと言ってくれたとか、そういうさりげない事も書いてくれるようになったんですよね。
最初のスタート段階は何を書いていいか分からないというところだったと思うんですけど、トライアルの終わり頃はそんな感じで、ときには長い文章も書いてくれたりしてくれたんですよね。
ー大曽根
利用者さんの全体が見える、って介護の方々にとってはとても大事なことですよね。
ー守屋
介護職の人にとっては、最初はワークショップもおっかなびっくりだったように思います。
ICTというよく分からない物に対する抵抗感もあるし、医師や病院スタッフと話すのも。
でも、ICTをちょっと脇に置きながら多職種で同じ場でフラットに話し合って、お互いを理解し合う期間があったり、先行トライアルというちょっと安全な場があったりで、少しずつ不安が取れていったように思います。
―大曽根
そうでしたね。
守屋さんにとって、先行トライアルがうまくいったというのはどのような部分を指すのですか?
ー守屋
うまくいったというのはあくまでも事務局の視点であって、実際当事者はその時どう思ってたかのかは気になっていました。

一人の利用者さんを中心として途切れる事なく次々に多職種の投稿が続いたんですよね。一つの投稿に対してコメントがついて。
時にはドクターがコメント入れてくれたりとかね。
酒井先生から慢性心不全という病気が重症化する兆候として「体重の変化」が大事なんだよってことをみんなに伝えてくれたんでみんなこまめに体重を測定するようになって。
看護師さんだけでなく、デイサービス、ヘルパー、ケアマネも訪問した時に測ってくれて、さらには薬剤師さんも測ってくれてたんですよ。
一体感というか、みんなが協力しあってくれていた状態。
やっぱりみんな利用者さんに良くなって欲しいと思ってますから。
ー大曽根
ケアマネをハブにしたコミュニケーションから、利用者さんを中心にした輪のようなイメージですね。
ー守屋
酒井先生が、医師という立場を強く出し過ぎずに、輪の一部としてフラットに降りてきてくれたのは大事なことだったと思いますね。
「これまで入退院を繰り返してきた患者たちであったがその後一回も増悪での入院はない。やはり地域で見守ってくれると診療においても有用」との感想をいただけました。
★歩み寄りと連携のアップデート
さらに、名寄市立総合病院もまた介護現場からの声に向き合ってくれました。
利用者さんの「次回病院受診日」の情報は、今回ICTで自動では取得できないものでしたが、病院側で手動で登録してくれることになりました。この情報は介護現場ではあると本当に助かる。
市役所も、各種介護手続きの簡素化や文書のペーパーレス化などに取り組み始めました。
市役所に対する不満って言うのも多かったのですが、市役所の方も変わろうということで、介護事業所さんたちの業務負荷を減らせるようにってことで色々市役所の方も一歩踏み込んで手間をかけてくれたんですよね。
例えば介護認定の決定までのプロセスや介護予防計画書など、ケアマネは何回も市役所に来ないといけないんですよね。書類不備があればもちろんですが、申請や決定通知書の受け取りなどなんども。
市とケアマネでの介護認定情報の開示請求から公開まで、介護予防計画書の作成は全部オンラインで出来るようにした。
それぞれが歩み寄りながら、運用でカバーし合う。
よりよい連携のあり方を試行し始めてくれ、このあたりから歯車が噛み合ってきたと思います。
ー大曽根
歩み寄り、大事ですし、あたたかいですね。
先行トライアル期間の途中と終了時に関係者で振り返りと、より良い運用方法を検討する機会を何度か作ったり、先行トライアルに参加していない方々にも進捗の共有や説明会を繰り返し、運用マニュアルの整備などを経て、いよいよ2021年7月から本格稼働になりました。
まだ1年経たないですが、守屋さんとしては当初期待していたものと比べると現在いかがでしょうか。
★本格稼働から1年弱、「今」と「これから」
ー守屋
現在まで市内ほぼ全介護施設が参加し、1000名を超える利用者(参考:介護認定者 1700名)からの同意をいただき、毎日フル稼働しています。
現場の人たちの日常動作の中に組み込まれているようです。3月にアンケートをしましたが、ほとんどの人が一日複数回見る、最低でも一日一回は見ているとの回答でした。
訪問看護ステーションの方が仰ってたのが、朝職場に着いたらまず一回立ち上げてチェックし、今日の動きを確認し、お昼に帰ってきてまたチェックすると。そういう感じでルーティーンワークの中に組み込まれてるって形ですね。
一度システムが動かなくなった日がありましたがすぐに訪問看護師から
「これがなかったら仕事にならないじゃないの」とのクレームが入りました。そのとき、怒られながらもなんだか嬉しいなという感覚もありました。
大曽根
うれしいですね。
これからについてはどのようにお考えですか?
ー守屋
医療とのより踏み込んだ連携が必要だと思います。
現在は、あくまでも患者総合支援センター(連携スタッフ)との連携がうまくいっている段階です。
病院においてもこれをどう活用していけばいいのかは、環境整備も含めて今取り組んでいるところです。
また、働き方改革の観点でいくと、使用者にとって仕事のプロセスが変わるってとこまでいかないとICTの本当の成果じゃありません。
医療介護の世界は法律に縛られてるので、なかなか簡単ではないのですがそれでも不要なプロセスを省くなど可能なことがあると思います。
「今までこうだったけど、今度からこういう風にしませんか?」というような現場からの創意工夫が増えるといいなと思います。
お互いの仕事のプロセスを見直して改善して、お互いの業務負荷を減らしていくイメージです。
システム構築は終わったけども、この運用検討のディスカッションは終わらせずに、続けていくことが大事だと思っています。
ー大曽根
本格稼働の第1フェーズが終わり、これから第2フェーズということですね。
ー守屋
はい。
1年目の段階で、外部識者から客観的に取り組みをご評価いただいていることは大変心強いです。
HIT(一般社団法人 北海道総合研究調査会)さんが昨年度行った道内のICT導入地域の大規模調査とシステム構築の考察に関する研究があるのですが、高くご評価いただきました。
ポイントは、SNSなどを活用した病診連携や多職種コミュニケーションツールの導入にとどまらず、名寄市は「地域包括ケアシステム」を構築するためのツールとしてICTが活用されている点です。
それほど前例は多くないようです。
行政が旗振り役になることが必要なので、そのあたりも評価はしてくださっています。
ー大曽根
これからもさらに連携や地域包括ケアシステムを磨き上げていくことが重要ですね。
外からのフィードバックも励みになりますね!
HITさんの報告資料では、システム導入から改善・効果確認まで、異なる役割を担う外部の専門的人材の招聘が特徴的とも書いてありました。
医療現場およびICTに詳しい人材と地域包括ケアシステム構築の専門家(ファシリテーター)の2名だと。
まだプロジェクトは途上ですが、守屋さんや名寄市の素晴らしいみなさんと一緒にこうして進められてきて本当に光栄に思います。
引き続きよろしくお願いいたします。
それでは、守屋さんありがとうございました。
後半では、守屋さんがここまでシステムに魂を込めることを大切にされている背景についてもお聞きしてみたいと思います。
ー守屋
ありがとうございました。

シーズン2エピソード1はICT導入の流れを中心に守屋さんの視点からひも解いてきました。
続いて、エピソード2はICTに魂を込める守屋さんの個人的な想いの背景についても触れていきます。
※内容はインタビュー実施時点(2022年4月5日)のものになります。
★★名寄市あったかICT物語の構成★★
【シーズン1(導入前夜編)】
【シーズン2(導入編)】
· エピソード6:「医師としての紆余曲折の全てが今につながる」
【シーズン3(運用編)】
· エピソード4「前編:薬剤師だから創り出せる、在宅でのあたたかい連携のカタチ」
· エピソード5「中編:薬剤師だから創り出せる、在宅でのあたたかい連携のカタチ」
· エピソード6「後編:薬剤師だから創り出せる、在宅でのあたたかい連携のカタチ」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
