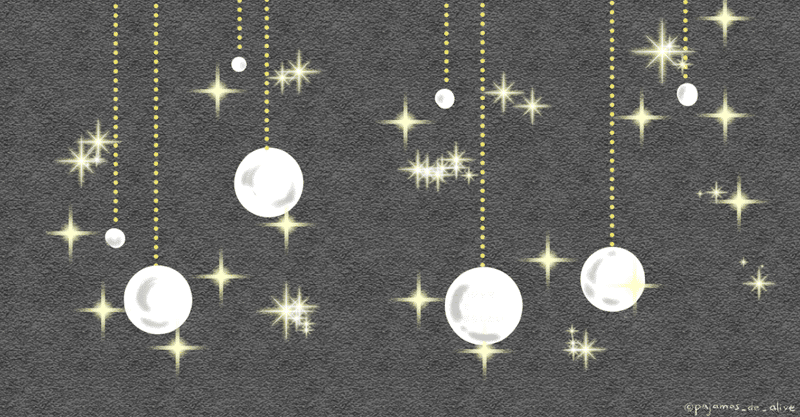
【短編小説】魔法をかけてみろ
「まるで魔法みたい。シュワシュワして綺麗だね、マサコちゃん」
姪の小春はテーブルの上に頬をのせ、グラスに入った琥珀色のビールをうっとりと眺めている。炭酸がだいぶ抜けたビールは、小さな泡をグラスの底から静かに立ち昇らせていた。
井の頭公園を見下ろす高台にあるこの古いマンションを小春は気に入っていた。「ちょっと昔っぽいところがいい」と小学四年生になったばかりのくせに言うのだった。
彼女の母親・羽根子はわたしの四つ下の妹だった。料理研究家の仕事をしながら、シングルマザーとして小春を育てている。仕事で羽根子が北海道に一泊することになり、明日の昼まで預かることになっていた。
繊細なグラスにそそぐと、ビールはこんなに美しく見えるのだ。普段は缶のプルトップを開け、そのまま口をつけていたので気が付かなかった。十年前に他界した父は、毎晩ビ瓶ビールを麒麟のグラスにそそいで満面の笑みを浮かべていた。小さい頃から食いしん坊だった羽根子は、普段の食卓には上がらないイカの塩辛やチーズをのせて焼いた揚げなどのおこぼれもらうのを、横で待っていたっけ。
「わたしも飲んでみたい」
小春がそう言うので、冷蔵庫からジンジャーエールを取り出し、もうひとつのグラスにそそいだ。ふたりでしばらく眺めていたが、いつまでも泡は勢いを失わず、グラスの底から次々に生まれていった。「なんか違う」と小春は不満を漏らしたが、小春のジンジャーエールも、花びらが散った後に桜の若葉が伸びるさまに似ていて、わたしは悦に浸った。
小春の華奢な身体にふとんをかけ、蛍光灯を消すと、「マサコちゃん、一生のお願いがある」と彼女は声を絞り出した。
「わたし、一度でいいから、朝マックしてみたい。お母さんはいつも、オーガニックの野菜を美味しくおしゃれなご飯にしてくれる。お母さんの作るご飯が大好きだし、料理のお仕事もかっこいいと思う。でもね、ときどき自分で選んだものを食べたり、行きたいところに行ってみたいの。どうしてだが、お母さんには言い出しにくいの。お母さんがしょんぼりしそうで」
わたしは「いいよ」と悪い魔女になったつもりで約束した。
翌朝、吉祥寺駅前のマクドナルドで購入した朝食を、井の頭公園の池のベンチに座り、ふたりで食べた。小春は何度もうなずきながら甘みと塩味が後を引くハンバーガを頬張った。
「人生にはちょっとした魔法が必要だ」
はかなく輝く泡や、親に内緒で頬張るジャンクフードや、夜明け空の奇跡みたいなグラデーション、迎えにくる羽根子が小春をぎゅっと抱きしめるときの親密さ、そんなもの達が、日常の隙をついて襲ってくる寂寥感や無力感から抜け出すための小さな魔法になる。
「魔法をかけてみろ」
まだ見たことのない神様にそう言われた気がして、わたしは目を細めた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
