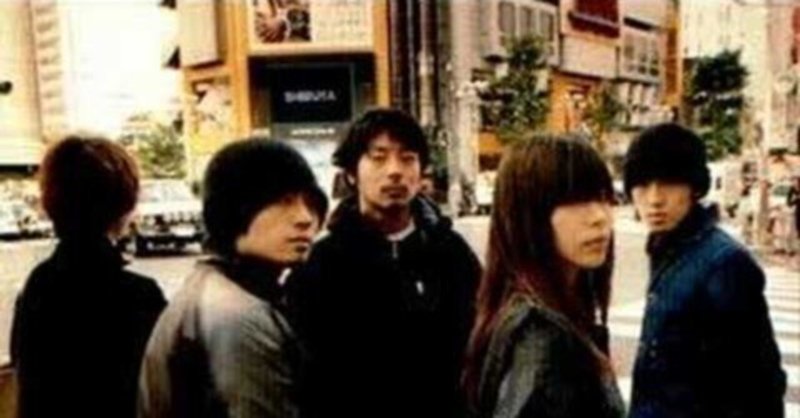
至高のバンド「SUPERCAR」Vol.7:まとめ
この記事をご覧いただきましてありがとうございます。
さて、以前の投稿より、自分の好きなことを楽しく書いてみようということで、趣味の音楽について【短期集中連載】を開始しております。
テーマはズバリ、
”至高のバンド「SUPERCAR」"
SUPERCARは、90年代後半から2000年代にかけて日本の音楽シーンで活躍したバンドであり、数多のアーティストの中でも私がトップクラスで好きなバンドであります。
なお、SUPERCARの説明や魅力については、Vol.1でたっぷりと紹介していますで、ぜひご覧ください👇👇
Vol.2〜6は、SUPERCARが発表したオリジナルアルバムについて1枚ずつ、私なりに魅力を深掘りしています。
ニッチなテーマですが、少しだけお付き合いいただけると幸いです。
”SUPERCAR”とは
本記事からご覧になる方もいらっしゃると思うので、改めて簡単に説明します。
SUPERCARは、90年代後半から2000年代にかけて日本の音楽シーンで活躍した4人組のロックバンドですが、残念ながらすでに解散しています。
活動の中で音楽性を柔軟かつ大胆に変化させ、オルタナティブロック→エレクトロニックサウンド→テクノサウンド→サイケデリックロックという変化をわずか8年間で、しかも全てを完成度の高い次元で成立させています。
解散からかなり時間が経過していることや、メジャーシーンから少し離れた活動であったことから、今現在の世間的な認知度はかなり低いですが、2018年にデビュー20周年を記念したベストアルバムがリリースされたり、25周年の2022年に公式YouTubeチャンネル開設と全MVが公開されたりなど、解散してもなお影響力と存在感があるバンドです。
詳細が気になる方は、ぜひ上記のVol.1をご覧ください。
*
さて、これまでの記事でSUPERCARのオリジナルアルバムを1枚ずつ紹介・解説をしていきましたが、改めてすごいバンドだなと。
発表したオリジナルアルバムは全部で5枚と、他の長く活動しているアーティストに比べたら決して多くはありませんが、1枚毎のセンスとクオリティが非常に高く、それぞれが全く違う景色を見せてくれます。
一方で、1997年のデビューから2005年の解散まで、活動期間は約8年。その間にオリジナルアルバム5枚と企画盤2枚をリリースしたことになります。
そうやってみると、活動期間中はほぼ休みなくノンストップで制作活動を続けてきたのでしょうか。
フルミキさん曰く、ナカコーさんは自宅とスタジオを往復する日々だったと話していますし、レコーディングやライブ以外でメンバーと会うことはほとんどなかったらしいです。
地元の幼馴染で結成されたバンドではありますが、デビューしてからは完全にプロの生活ですね。
だからこそ、短いスパンの中でアルバム毎に異なるコンセプトと高いクオリティをみせることができ、まさにSUPERCARの如く活動期間を全速力で駆け抜けたのかなと。
解散時でもメンバー全員がまだ20代であり、もしかしたら活動自体が「スリーアウトチェンジ」で感じるような気だるくもキラキラした青春だったのでしょうか。
決して多くを語らない少し不器用なバンドのように見えますが、だからこそ演奏の中で心を通わせ合うことで”バンドマジック”が生まれたのだと思います。
そんなこんなで、私もこれまで連載を続けてみて、改めて色々と気づくことがありました。いくつか書いてみたいと思いますので、しばしお付き合いください。
バンドであり”表現者”
前回Vol.6でも書きましたが、一連のサウンドの変化を見ていくと、単なるロックバンドという括りでは納まりきらないような気がしています。
もちろんデビュー時の初期は純粋なバンドサウンドが鳴っていましたが、作品を追う毎に音源やライブでも多種多様なサウンドが鳴り響くようになりました。
特に「HIGHVISION」期のライブ映像などを見てみると、ナカコーさんは基本シンセサイザーを演奏し、いしわたりさんやフルミキさんの前にもシンセが置いてあります。
また、音源では打ち込みが多用されていたり、ドラムのコーダイさんがDJやサンプリングに参加していたりなど、グループにおける活動や演奏の幅が広いです。
サウンドに限らず、クオリティの高い作品の世界観やジャケットアートワークなどからも強いこだわりを感じるところがあり、ただ音楽を鳴らすだけのグループではないようにも感じます。
なので、私自身もSUPERCARのことをロックバンドとはっきり言うのには少し抵抗がありますが、かと言ってうまく当てはまる言葉も見当たりません。一番近しいのは”表現者”でしょうか。
バンド解散後のメンバーそれぞれの活動を見ていくと、ナカコーさんとフルミキさんは既存の音楽にとどまらず型にハマらない自由な表現活動をされていて、いしわたりさんは作詞家・音楽プロデューサーとしての確固たる地位を築き、コーダイさんは別名義でプロデュースやプログラミングなどをしながら細々と活動されています。
メンバー全員が音楽に関わりつつも(コーダイさんは地元で一般職についているそうですが)それぞれが異なる方向に進んでいます。
SUPERCARという枠組みの中で全員20代という若いうちに様々な経験をしたうえで、メンバーそれぞれが進むべくして進んだ道のりが今日の状況なのでしょう。
*
余談ですが、SUPERCARの映像をYouTubeで観ていると、コメント欄に外国人のコメントが非常に多いんですよね。
当然、海外では日本語詞は理解できないでしょうから(日本人でもSUPERCARの歌詞は理解できません笑)恐らく、サウンドのノリやリズム感がいいと思ってくれているのでしょう。
初期の純粋なバンドサウンドよりも、後期の多種多様な音を鳴らす”表現者”としてのSUPERCARのサウンドは、確かに海外ウケしそうです。
いずれフィッシュマンズみたいに、時空を超えて海外で評価を得るようなことがあったら非常に嬉しいな〜なんて妄想を膨らませています。
サウンドを”量産して削る”
オリジナルアルバムを発売順に追ってみて気づいたのが、SUPERCARはサウンドを「量産して、削る」作業を繰り返していたことです。
アルバム毎のボリュームで見ていくと⇩⇩
スリーアウトチェンジ:19曲、78分11秒
JUMP UP:11曲、51分34秒
Futurama:16曲、75分16秒
HIGHVISION:10曲、48分13秒
ANSWER:14曲、59分55秒
というように、大ボリュームとコンパクトを繰り返しています。
サウンドだけでざっくりとジャンル分けすると、「スリーアウトチェンジ」〜「JUMP UP」がバンドサウンド期、「Futurama」〜「HIGHVISION」がエレクトロサウンド期、「ANSWER」が第2バンドサウンド期になります。
デビュー作「スリーアウトチェンジ」で一発録りの荒々しい轟音ギターサウンドをこれでもかと詰め込んだ一方、次作「JUMP UP」では丁寧にサウンドが鳴り、J-POP寄りの非常に聴きやすいアルバムになりました。
続いて「Futurama」では、新しい境地を拓くことになるエレクトロをベースにしたサウンドを、「スリーアウトチェンジ」同様これでもかと詰め込みます。フルミキさんの「新しいサウンドの融合を、稚出でも構わずに作ってみたい」という発言の通り、実験要素も含まれた大ボリュームの傑作が生まれました。これも一方、次作「HIGHVISION」では、「Futurama」で構築したエレクトロサウンドが極限まで研ぎ澄まされ、約50分10曲の中に未知の世界が広がる究極の芸術作品が誕生しました。
「ANSWER」で再びバンドサウンドに回帰するも、初期とは異なるダークでサイケデリックな世界観が広がります。このアルバムに関しては既に完成されたような雰囲気があり、バンド自体もその後活動を終え、解散します。
アルバム制作や活動の背景は不明確な部分が多いですが、理想のサウンドをまず作ってみてアルバムに詰め込んでみるという潔さと、それを踏まえて削って整えて上手にまとめるという技術。完全に職人です。
バンドの音楽性が徐々に変化したり、コンセプトアルバムや影響を受けた音楽を意識した作品を制作するのはよくあることですが、SUPERCARほど音楽性の変化が分かりやすく、聴いていて面白いアーティストはいないと思っています。
おすすめの”聴きかた”
何度も書いているように、SUPERCARは月日を追う毎、オリジナルアルバム毎に全く異なる雰囲気や世界観があります。
SUPERCARの音楽遍歴を追ってみたい場合、まずはシングル集「A」を聴くことをおすすめします。

「A」はSUPERCARが解散した直後に発売されたアルバムで、それまでに発表したシングル曲が発売順に収録されています。
このアルバムを収録順に聴くだけでも、SUPERCARの音楽性の変化や魅力、面白さを十分に感じることができます。
このアルバムで興味を持ったら、オリジナルアルバムを初期から順番に聴いてみたり、気になった時期のアルバムを聴いてみるのもいいかもしれません。
ちなみに、2018年にデビュー20周年を記念したベストアルバムが発売されています。

このアルバムはシングル曲+人気や認知度のある曲を収録した2枚組なのですが、収録曲順がとっ散らかっています。正直、SUPERCAR初心者にはあまりおすすめできません。
大ボリュームのブックレットや全MVが収録されているブルーレイが付録されていたりして、どちらかというと古参ファン向けの作品であるように感じました。
*
続いて、完全に自己満のテーマですが、私が思う、SUPERCARのオリジナルアルバムを聴きたい時間帯を以下の通りまとめました。
朝 :Futurama
午前:スリーアウトチェンジ
午後:HIGHVISION
夕方:ANSWER
夜 :JUMP UP
朝「Futurama」は、1曲目”Changes”から何かが始まるような目覚めを感じさせ、曲を追う毎に徐々に光が射して盛り上がっていきます。荒々しくもどこか腑抜けたようなエレクトロサウンドも、まだ起き抜けの体と頭に心地よく響きます。また、#7”SHIBUYA Morning”という曲もあったりして、朝といっても早朝5時くらいのイメージがあります。
午前「スリーアウトチェンジ」は、何よりまず青空がよく似合います。轟音ギターサウンドが終始鳴り響き、エネルギッシュで活動的な午前中の風景に非常にマッチします。ドライブなんかで流しても盛り上がりそうですね。自動車なら僕の白いので許してよ♪
午後「HIGHVISION」は、なんでしょう、午後が一番納まりがいいです(笑)午後といっても15時過ぎくらいの、夕方に向かうあたりの気怠い感じにアルバムの雰囲気が合うような気がしています。それは、アルバムジャケットのぼやけた斜光具合からもそう思わせられます。
なお、午前「スリーアウトチェンジ」と午後「HIGHVISION」は、場合によっては逆でもいいかななんて思ったりして。
夕方「ANSWER」は、日が暮れて夜に向かっていく過程のダークな世界観を感じます。最初はとっつきづらい印象がありますが、決して暗いだけのアルバムではなく要所でポップな楽曲もあり、時間をかけて体に馴染んでくる作品だと思っています。#7”HARMONY”や#9”GOLDEN MASTER KEY”などは夕暮れの雰囲気に非常にマッチしていて、個人的にも好きな曲です。
夜「JUMP UP」は、もはや夜しか似合わないような気がしています。アルバムジャケットや歌詞カードのコンセプト、サウンドのメロウで落ち着いた雰囲気など、全ての要素からそう感じさせます。雨が降っていたら、なお最高ですね。
*
また、時間帯によらずとも、その時々の気分や場面で聴き分けても面白いかもしれません。
私的には⇩⇩
エネルギッシュなギターサウンドが聴きたいなら「スリーアウトチェンジ」
J-POP寄りの聴きやすさを求めるならば「JUMP UP」
好奇心旺盛なエレクトロサウンドを聴くなら「Futurama」
神秘的で芸術的なサウンドに浸りたいときは「HIGHVISION」
アダルトでジャジーなサウンドに酔いたいなら「ANSWER」
これらは完全に私の感覚なので、強要は一切しません。好きな時に好きな音楽を聴いてください😅
解散について思うこと
余計なお世話かもしれませんが、SUPERCARの解散について少しだけ触れさせていただきます。
SUPERCARについて調べたり深掘りしていくと、必ずといっていいほど解散時の泥沼劇が浮上します。
特に、解散理由はナカコーさんといしわたりさんの不仲説であるとか、ナカコーさんがバンドを見捨てたといった声が多くみられます。
私自身も2005年発売の”ROCKIN'ON JAPAN”に掲載されている解散時のメンバー全員のインタビューを拝見しましたが、上記のように解釈されてもおかしくないような内容が書かれていました。
それくらい、メンバーそれぞれの当時の心境が赤裸々に綴られていて、いちファンとしては見ていて辛くなるような内容でした。

活動期間中も、とあるメンバーが脱退希望を申し出たり、メンバー間のコミュニケーションが次第に減ってきたりと、ギリギリの状態が続いた末の解散だったようです。インタビューでメンバー全員が方向性の違う発言をしていたのも、それが影響しているかもしれません。
でも、人間関係なんて所詮そんなもんじゃないのでしょうか。私からしたら、円満に解散するグループのほうが不思議です。
バンドの解散も見方を変えれば、気が合う男女がカップルになって次第にすれ違い別れてしまうのと同じだと思っています。ただ、SUPERCARはその背景が明るみになって世間に広まってしまった結果、解散を良くないニュアンスで解釈されてしまっています。
それらのことから、どうもナカコーさんに批判の矢が向かれがちなように感じますが、私は決してそうは思えません。
Vol.6でも触れましたが、ナカコーさんは最後までSUPERCARというバンドの可能性を模索していたのではないかと感じています。
作曲家として様々な音楽のエッセンスを吸収し、驚異的なスピードで成長し、ソロとして十分活動できる中でも「ANSWER」でバンドサウンドに回帰したところには、ナカコーさんなりのバンドへの愛を感じずにはいられません(個人の見解です)。
また、フルミキさん曰く、事務所や出版社には解散に至る背景を公表しない約束をしたのに裏切られてしまったようであり、インタビュー内容も果たしてどこまでが真実なのか疑ってしまいます。
デビュー時には衝撃的な新人として業界から猛プッシュされたようですが、解散時までこういった形で公にさらされると、なんだか最後まで業界に振り回されたように見えて、少し可哀想に感じます。
それでも、ナカコーさんはTwitterでSUPERCARについて肯定的な発言をしていますし、フルミキさんもSNSで度々SUPERCARについて触れていますし、メディア露出が多いいしわたりさんもSUPERCARのことを語る場面があるなど、当時は何があったか分かりませんが、大人になった現在では、メンバーそれぞれがSUPERCARをいい思い出や経験として捉えているのではないでしょうか。
*
とはいえ、結局のところSUPERCARは作品が良すぎるので、解散のことなんてどうでもいいんですよね。
何年経っても決して色褪せないエバーグリーンで魅力的な音楽とバンドが放つ”バンドマジック”に私自身もずっと虜になっていますし、音楽業界で現在まで影響を与え続けているところをみても、SUPERCARというバンドはやはり唯一無二の素晴らしいバンドです。
ほんと、リアルタイムで追ってみたかったです。再結成してくれたら本当に嬉しいことですけど、難しいかな?😅
最後に
本記事を含め全8回(番外編含む)の短期集中連載、かなり疲れました(笑)
好きな音楽の、そして大好きなアーティストであるSUPERCARについて書き続けてきたことは非常に楽しく、持ち合わせている知識と溢れる思いでタイピングがスラスラと進みましたが、それが裏目に出て1記事の作成にかなりの時間と労力を使ってしまいました。
中途半端な記事は作りたくないという変な完璧主義と、間違ったことや変な憶測は書けないという謎の真面目さも相まって、当初は1記事3000文字程度を予想していたのに、ほとんどの記事が倍の6000文字越えになりました(Vol.4に至っては約10000文字でした😭)
純粋な音楽レビューは初めてで勝手が分かりませんでしたが、様々なサイトや文献を参考にしながら何とか形にできました。おかげさまで全記事ともそれなりに納得のいく内容に仕上げることができ、自身のライタースキルも少し上がったような気がしています(もし記事作成に関してアドバイスがあれば、ぜひコメントなどでお願いします!)。
とりあえず、これを毎週続けてこれた自分を褒めてあげたいです。
*
自分のことはさておき、20歳の頃に初めて聴いて衝撃を受けたSUPERCAR。すでに解散しているバンドなのに、こうして30歳手前になるまで好きで居続けているとは思いませんでした。
それだけ、私のみならず音楽業界や音楽ファンに響くようなエバーグリーンで永遠の輝きを放てる様々な魅力を持ち合わせています。
解散後もSUPERCARに影響を受けたアーティストはたくさんいるようですが、似たようなアーティストには未だに巡り会えていません。それだけ、SUPERCARは唯一無二の存在なのです。
全8回の記事でその魅力を惜しみなく紹介したつもりですが、後になってまだまだ出てくるかもしれませんね。これからもSUPERCARを飽きずに聴き続けますし、また気が向いたら記事にしたいと思います。
お付き合いいただき、ありがとうございました!
それでは
乱筆にて
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
