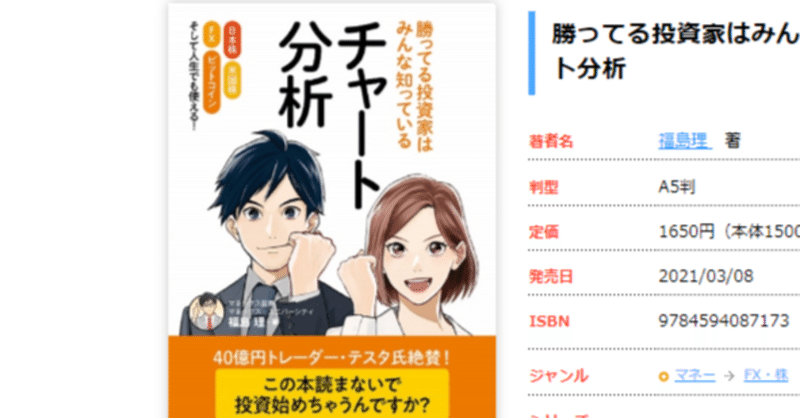
『勝ってる投資家はみんな知っている チャート分析』福島理著, 扶桑社, 2021
Part 1 過去の高値と安値
◆過去の高値を超えると、上昇の勢いが増して上値をつけやすくなる。

◆過去の最高値や年初来高値は多くの投資家が注目している節目なので普段から気にかける。

◆主なテクニカル指標一覧

Part 2 ローソク足
ローソク足基本9種

・小陽線 Small White Candle ~売り買い拮抗しつつも少し値上がりした状態。連続出現で大陽線につながる期待がある。
・小陰線 Small Black Candle ~ 売り買い拮抗しつつも少し値下がりした状態。連続出現で大陰線につながる可能性もある。
・大陽線 Big White Candle ~ ローソク足の実体がほかに比べて明らかに長く(普通の値幅の5倍以上ともされる)、買い方の勢いが強く、その後も買いの勢いが続くことを示唆。
・大陰線 Big Black Candle ~ ローソク足の実体がほかに比べて明らかに長く(普通の値幅の5倍以上ともされる)、売り方の勢いが強く、その後も売りの勢いが続くことを示唆。
・上影陽線 ~ 上ヒゲの長い陽線を持つローソク足。買い方の勝利で陽線ではあるものの、売り方の抵抗が強く、伸びきれなかったと解釈可能。高値圏で出現すると下落転換の示唆、安値圏では下落継続を暗示。
・上影陰線 ~ 上ヒゲの長い陰線を持つローソク足。高値圏で出現すると下落転換の示唆、安値圏では下落継続を暗示。
・下影陽線 ~ 下ヒゲの長い陽線を持つローソク足。安値圏で出現すると上昇転換の示唆、高値圏では上昇継続を暗示。
・下影陰線 ~ 下ヒゲの長い陰線を持つローソク足。売り方の勝利で陰線ではあるものの、買い方の抵抗が強く、下がりきれなかったと解釈可能。高値圏で出現すると下落転換の示唆、安値圏では安値からの反発を示唆。
・十字線(寄引同時線) ~ ローソク足の実体部分が横線で、始値と終値が同値の場合。買い方と売り方の勢いが拮抗している状態。高値圏では買い方の勢いを売り方が止めたと理解でき下落転換を示唆。安値圏では売り方の勢いを買い方が止めたと理解でき上昇転換を示唆。また、十字線でも上ヒゲが長い場合は上値が重く、下ヒゲが長い場合は下値抵抗が強いとみることができる。
示唆する意味別による区別
ローソク足が示唆する意味は大きく分けて以下の3つ。
①上昇示唆
②下落示唆
③気迷い/転換示唆

・陽線坊主(陽の丸坊主) ~ 上下のヒゲがなく比較的大きな実体を持つ陽線。その後も買い方の勢いが続くことが期待される。
・陰線坊主(陰の丸坊主) ~ 上下のヒゲがなく比較的大きな実体を持つ陰線。その後も売り方の勢いが続くことが暗示される。
・陽の寄り付き坊主 ~ 寄り付き後に一直線で高値形成するも大引けで少し下げて終値を形成する、比較的大きな陽線に上ヒゲを付けたローソク足。
・陰の寄り付き坊主 ~ 寄り付き後に一直線で安値形成するも大引けで少し上げて終値を形成する、比較的大きな陰線に下ヒゲを付けたローソク足。
・陽の極線 ~ ローソクの実体も上下のヒゲも短く、相場の転換点や株価変動の加速時に出現。迷いながらも上昇への期待を内包。
・陰の極線 ~ ローソクの実体も上下のヒゲも短く、相場の転換点や株価変動の加速時に出現。失望感の中での迷いを表しているが、まだ弱気が先行する状態。
・一本線(四値同時線) ~ 寄り付き後、上にも下にも行けず、取引も少なく、勢いが全くない状態。
Part 3 トレンドライン
トレンドは以下の3つに分類できる。
①上昇トレンド ~ 下値支持線(サポートライン)に注目
②下降トレンド ~ 上値抵抗線(レジスタンスライン)に注目
③横ばいトレンド(ボックス相場・レンジ相場・保ち合い相場)
③’の亜種として三角保ち合いがある。
Part 4 チャートパターン
1. ダブルボトム

ここでのポイントは二番底をつけて反転上昇した時点では上昇トレンドに入ったかどうかは不明という点。実際の買いのエントリーはネックライン(一番底を形成した後の高値・中間高値)を超えたときに上昇トレンドに入ったと判断する。当面の利確目標(エグジット)は二番底からネックラインの値幅をそのままネックラインの価格に上乗せしたところ。
2. ダブルトップ

ここでのポイントは二番天井をつけて反転下落した時点では下降トレンドに入ったかどうかは不明という点。実際の売りのエントリーはネックライン(一番天井を形成した後の安値・中間安値)を下回ったときに下降トレンドに入ったと判断する。当面の利確目標(エグジット)は二番天井からネックラインの値幅をそのままネックラインの価格から下回ったところ。
3. ヘッドアンドショルダーズトップ(三尊)

左ショルダーの高値を形成後、その高値を更新しヘッドの新高値を形成。この時点では上昇トレンドと見えるが、ヘッドをつけてからの戻り安値(右)が前回の戻り安値(左)とほぼ同値あるいはそれ以下に下落すると売り圧力が強くなってくる。その後反発するも前回つけた新高値のヘッドを更新することなく左戻り安値と右戻り安値を結んで引いたネックラインを下抜けることで上昇トレンドの終焉サインとなり、売りシグナルが発生。利確目標値(エグジット)は売りシグナルポイントからヘッドとネックラインの値幅分を下にずらした価格となる。
4. ヘッドアンドショルダーズボトム(逆三尊)

左ショルダーの安値を形成後、いったん反発。そこから前回の安値(左ショルダー)を更新しヘッドの新安値を形成。この時点では下降トレンドと見えるが、ヘッドをつけてからの戻り高値(右)が前回の戻り高値(左)とほぼ同値あるいはそれ以上に上昇すると買い圧力が強くなってくる。その後反落するも前回つけた新安値のヘッドを更新することなく左戻り高値と右戻り高値を結んで引いたネックラインを上抜けることで下降トレンドの終焉サインとなり、買いシグナルが発生。利確目標値(エグジット)は買いシグナルポイントからヘッドとネックラインの値幅分を上にずらした価格となる。
5. 三角保ち合いの3パターン

①強気の三角保ち合い ~ 株価が上昇と下落を繰り返すなか、投資家が前回安値まで株価下落を待てずに買いを入れてくるため、安値が切り上がってくる形。投資が強気になっているため、頂点を付けた後に上昇する確率が高くなる。
②弱気の三角保ち合い ~ 株価が上昇と下落を繰り返すなか、投資家が前回高値まで株価上昇を待てずに売りを入れてくるため、高値が切り下がってくる形。下値は一定で底堅く推移しているものの、上に戻る力が弱いため、前回高値まで上昇しないとみる投資家が増え弱気になっているため、三角形の頂点から下に均衡が破られたときに、投資家は一斉に損失を確定させる損切り決済(ロスカット)を行ったり、新規売の参加者も増加。下落する確率が高くなる。
③均衡している三角保ち合い ~ 高値が徐々に切り下がると同時に安値も徐々に切り上がってくることで振幅が小さくなる形。つまり、これからの株価について先高感を持った投資家と先安感を持った投資家が均衡しているので、頂点が形成されるまで上下どちらに動くかはわからない。上放れや下放れを確認してからエントリーすることになる。
・三角保ち合いは相場がパワーをためている証拠で、保ち合いから放たれると大きく動き出すサインでもある。
Part 5 移動平均線(Moving Average)

1. 移動平均線(MA)の種類
・単純移動平均線(SMA:Simple Moving Average) ~ 終値の平均値をシンプルにつなぎ合わせた平均線。
・指数平滑移動平均線(EMA:Exponential Moving Average) ~ 直近の価格に比重を置いて算出。個別の価格データへの加重を過去の価格ほど指数関数的に減少させて平均値を算出。加重移動平均線(WMA)と比較した場合、直近の価格に対する比重は指数平滑移動平均線(EMA)の方が大きい。
また単純移動平均線(SMA)と比較した場合、より値動きに敏感に反応するため売買シグナルが早く出現しやすい。
・加重移動平均線(WMA:Weighted Moving Average) ~ 過去は低く直近ほど高く評価して算出。期間10日の場合、直近の価格データを10倍、その前日を9倍、10日前のデータを1倍して計算。欧米でよく利用される。指数平滑移動平均線(EMA)と比較した場合、直近の価格に対する比重は加重移動平均線(WMA)の方が小さい。また単純移動平均線(SMA)と比較した場合、より値動きに敏感に反応するため売買シグナルが早く出現しやすい。
・三角移動平均線(TMA:Triangular Moving Average) ~ 期間の中央の日に大きなウェイトを掛けて算出。
・正弦加重移動平均線(SWMA:Sine Weighted Moving Average) ~ 加重移動平均の一種で、三角移動平均に類似。
2. 移動平均線の期間設定

・日足 ~ 5日、25日、75日、100日、200日
・週足 ~ 9週、13週、26週、52週
・月足 ~ 6ヵ月、12ヵ月、24ヵ月、60ヵ月
3. 移動平均線の活用法 ①移動平均線の向き、ローソク足との位置関係
・移動平均線の向き
1. 上向き ~ 基調は上昇トレンド
2. 横ばい ~ 基調は保ち合い、気迷い局面
3. 下向き ~ 基調は下降トレンド
a.ローソク足が移動平均線より上 ~ 強い相場
b.ローソク足が移動平均線より下 ~ 弱い相場

・移動平均線の上にローソク足があり、移動平均線が上昇過程にある場合は、この移動平均線がローソク足の下値支持線として働くケースがしばしば見かけられる。
・移動平均線の下にローソク足があり、移動平均線が下落過程にある場合は、この移動平均線がローソク足の上値抵抗線として働くケースがしばしば見かけられる。
4. 移動平均線の活用法 ②ゴールデンクロスとデッドクロス
・ゴールデンクロス(GC) ~ 短期移動平均線(5日線・13週線)が中期・長期移動平均線(25日線、26週線)を下から上に突き抜けた場合を指し、一般的には買いシグナル、相場トレンドの上昇局面入りを示唆する。
・デッドクロス(DC) ~ 短期移動平均線(5日線・13週線)が中期・長期移動平均線(25日線、26週線)を上から下に突き抜けた場合を指し、一般的には売りシグナル、相場トレンドの下落局面入りを示唆する。

5. グランビルの法則

・グランビルの法則で利用する移動平均線の期間や時間足は、一般的に200日移動平均線と日足が基本ではあるが、トレードスタンスによって、5日、25日などを使い分ける。
Part 6 MACD
1. MACDの定義と計算方法
・MACD は、Moving Average Convergence Divergence の略で、日本語に訳すと移動平均収束拡散法。
・計算方法
MACD線 = 短期EMA(指数平滑移動平均)ー 長期EMA
MACDシグナル線 = MACD自体のEMA

2. MACDの一般的パラメータ
・日足チャートで一般的に多く使われるパラメータ(括弧内は TradingView 内でデフォルトで入っている MACD の設定画面の中の呼び方)
短期EMA(ファスト期間)= 12日
長期EMA(スロー期間)= 26日
MACDシグナル線(Signal Smoothing)= 9日
3. MACDの売買シグナル
・買いシグナル ~ ゼロ地点より下で、MACD線がMACDシグナル線を下から上に抜けるゴールデンクロス出現時。クロスの角度が大きければ大きいほどより強いトレンド転換のサインとみることができる。
・売りシグナル ~ ゼロ地点より上で、MACD線がMACDシグナル線を上から下に抜けるデッドクロス出現時。クロスの角度が大きければ大きいほどより強いトレンド転換のサインとみることができる。
4. MACDのヒストグラムの意味

・MACDのヒストグラムの計算方法
MACDのヒストグラム = MACD線 - MACDシグナル線
意味するところは、MACD線とMACDシグナル線の乖離幅。
・ヒストグラムゼロ地点は必ずゴールデンクロスかデッドクロスの出現時である。
・ゼロ地点(0地点)の下でゴールデンクロス発生時(必然的にヒストグラムゼロ地点)に最初の買いシグナル。その後、MACD線がゼロ地点(0地点)を超えたらその上昇トレンドを本物と判断し、ここが追随買いシグナルの発生ポイントとなる。
・ゼロ地点(0地点)の上でデッドクロス発生時(必然的にヒストグラムゼロ地点)に最初の売りシグナル。その後、MACD線がゼロ地点(0地点)を下回ったらその下降トレンドを本物と判断し、ここが追随売りシグナルの発生ポイントとなる。
・ヒストグラムのボトムアウト(大底)、つまりヒストグラムのグラフが下降から上昇に転じる点は、MACDのゴールデンクロスより早く形成されるため、買いシグナルとしては最も早く出現するが、転換シグナルとしては弱いため、MACD上のゴールデンクロス出現の予兆程度に捉えておく方がよい。
・ヒストグラムのピークアウト(天井)、つまりヒストグラムのグラフが上昇から下降に転じる点は、MACDのデッドクロスより早く形成されるため、売りシグナルとしては最も早く出現するが、転換シグナルとしては弱いため、MACD上のデッドクロス出現の予兆程度に捉えておく方がよい。
5. MACDのダイバージェンス

・株価は上がっているのにMACDの2本のラインは下がっている、いわゆるダイバージェンスが発生しているときは、足元の株価自体は上がっているが、上昇トレンド自体は終わりに近づいていると判断でき、株価反転のシグナルととらえ、売りのチャンスが近づいていると考えられる。
・株価は下がっているのにMACDの2本のラインは上がっている、いわゆるダイバージェンスが発生しているときは、足元の株価自体は下がっているが、下降トレンド自体は終わりに近づいていると判断でき、株価反転のシグナルととらえ、買いのチャンスが近づいていると考えられる。
Part 7 ボリンジャーバンド
1. ボリンジャーバンドの主な特徴
ローソク足チャート上に通常5本のラインが描かれる。上から順に①プラス2σ、②プラス1σ、③移動平均線、④マイナス1σ、⑤マイナス2σ。
株価がボリンジャーバンドの ①±1σ の範囲に収まる確率は約68.3%、②±2σ の範囲内に収まる確率は約95.4%、③±3σ の範囲内に収まる確率は約99.7%とされている。
2. ボリンジャーバンドの計算式

3. ボラティリティ・ブレウクアウト(ボリンジャーバンド順張り型①)

・株価の保ち合いが続き、バンド幅が狭くなった場合という条件の下で、±2σ をブレイクアウトしたときに順張りでの買い/売りと判断する。その後は相場に勢いがつきバンド幅は広がっていくことが想定される。決裁のタイミングは、株価が+2σ を終値で下回ったところか、またはバンド幅が収束しはじめたとき。
4. バンドウォーク(ボリンジャーバンド順張り型②)

・トレンドが発生継続している場合、株価は①移動平均線と±2σラインの間、あるいは②±1σラインと±2σラインの間で上下動を繰り返しながらトレンド方向に動いていく。このとき、±2σのラインに沿ってローソク足が並ぶ状態をバンドウォークと呼ぶ。
・このバンドウォーク発生中かつ上昇トレンド継続中に、株価が一時的に下がり、中心線である移動平均線にタッチする場合、押し目買いポイントになりうる。
5. ボリンジャーバンド逆張り型

・株価の保ち合いが続くレンジ相場という条件の下で、±2σにタッチしたら逆張りでエントリーし、買いで入った場合は上値抵抗線として機能している+2σ、売りで入った場合は下値抵抗線として機能している-2σにタッチしたところが当面の決済ポイントと判断する。確率約99.7%の±3σ到達で逆張りすれば、さらに確度は高まる。
・なお発案者のジョン・A・ボリンジャー氏は「逆張りでは使うべきではない」と主張している。
Part 8 一目均衡表
1. 一目均衡表の背景にある3大理論
①時間論
基本数値に関する考え方。一目均衡表における基本数値は9、17、26の3つとされている。
②波動論
価格変動によって起きる波の基本3パターンのこと。
・I波動 ~ 上昇だけ、下落だけといった一方通行的なライン
・V波動 ~ 上昇して下落(反落)、または下落して上昇(反発)をそれぞれワンセットとしてみたパターン
・N波動 ~ 上昇→下落→再上昇、または下落→上昇→再下落をそれぞれワンセットとしてみたパターン

・N波動は、I波動とV波動の連続性から形成され、いずれN波動が完成しないと上昇局面も下落局面も到来しにくいと考える。すべての波動はN波動に集約され、相場はN字で動くと考えられる。
③値幅観測論(水準論)

値幅観測論(水準論)とは、株価の目標値を予想するときに使う。最もポピュラーなのはV計算値。V計算値は最初に上昇した最高到達点(左高値)から下げて底値を打つ(中央安値)までの下落幅の倍の上昇を反発局面での目標値とする計算値。よくいう倍返し。
2. 一目均衡表の分析道具

・一目均衡表の分析には以下の分析道具を用意する。
①基準線
・計算式 =(当日を含めた過去26日間の最高値+最安値)÷ 2
相場の中期的な方向性を表す。
②転換線
・計算式 =(当日を含めた過去9日間の最高値+最安値)÷ 2
相場の短期的な方向性を表す。
③先行スパン1
・計算式 =(転換値+基準値)÷ 2 を26日先行させて表示
④先行スパン2
・計算式 =(当日を含めた過去52日間の最高値+最安値)÷ 2 を26日先行させて表示
⑤遅行スパン
・計算式 = 当日の終値を26日遅行させて表示
⑥雲
・雲 = 先行スパン1 と先行スパン2 の2本に囲まれた領域
雲は抵抗帯、支持帯になるので、株価も抵抗帯の雲を上抜けると動きが軽くなる傾向があるので、雲を上抜けたときに買い、下抜けたときに売りと判断できる。

3. 一目均衡表の基本的活用法
①基準線と転換線を使った活用法
・基準線が上向きなら上昇トレンド、下向きなら下降トレンド
・ローソク足が基準線より上ならば強い相場、下ならば弱い相場
・基準線が上向き(上昇トレンド)で転換線が基準線を下から上に抜けるゴールデンクロスを「好転」といい、買いシグナルとなる。
・基準線が下向き(下降トレンド)で転換線が基準線を上から下に抜けるデッドクロスを「逆転」といい、売りシグナルとなる。
②先行スパン1と2を使った活用法
・ローソク足が雲の上方にあれば強い相場、下方にあれば弱い相場
・ローソク足よりも上にある雲は上値抵抗帯、ローソク足よりも下にある雲は下値支持帯として機能
・ローソク足が雲を下から上に突破した場合は上昇サインとなり「好転」と判断、逆にローソク足が雲を上から下に割り込んだ場合は下落サインとなり「逆転」と判断
・先行スパン1と2が交差した地点を「雲のねじれ」と呼び、相場の転換点(トレンドの転換、もしくは加速局面)となる「変化日」の可能性が高い
・ローソク足が雲の中にある場合は相場の方向性はあいまいな状態にあるといえる
③遅行スパンの活用法
・遅行スパンがローソク足を下から上に上抜けると「好転」強気相場となり、買いのシグナル
・遅行スパンがローソク足を上から下に突き抜けると「逆転」弱気相場に転じて、売りのシグナル
・遅行スパンがローソク足と絡む動きが継続する場合は保ち合い相場(レンジ相場)と判断可能
④三役好転と三役逆転
・三役好転の3条件で非常に強い買いシグナル

・三役逆転(三役暗転)の3条件で非常に強い売りシグナル

Part 9 RSI
1. RSIの定義
・RSIとは、Relative Strength Index の略で相対力指数のこと。ある一定期間内の相場の動きが、相対的に買われすぎなのか、売られすぎなのかを判断するオシレーター系テクニカル指標の代表格。
2. RSIの計算式と最適パラメータ
①計算式
RS =(n日間の終値の上昇幅の平均)÷(n日間の終値の下落幅の平均)
RSI =100 - {100 ÷ (RS+1)}
②最適パラメータ
上記のnの値は、日足ベースの場合は14日、週足だと9週か13週。
3. RSIの活用法
・RSI は0%から100%の間で推移し、0%に近づくほど相場は弱く、100%に近づくほど相場が強いと判断可能。
・典型的な逆張り指標。基本的には、RSI が70%を超えると買われすぎ(過熱状態)と判断し、売りシグナル。逆に、30%を下回ると売られすぎ(冷却状態)と判断し、買いシグナル。
・ただし、ストップ高やストップ安が連続するような相場が急変している場合は80%、20%をパラメータにする場合もある。また、この指標はダマシも多い。
・RSI 上のダイバージェンス現象

上記の図のようなRSI 上のダイバージェンス現象発生後は下落に転じる可能性が高いため、売りと判断。
ダイバージェンス出現はそれまでのトレンドが転換する有力なシグナルになる。
4. RSIの弱点と対策
①RSIの弱点
・値動きが横ばいだったり、レンジ内で推移している場合のRSIの的中率は高い一方、上下に強いトレンドが発生するとRSIの的中率は下がる。
②RSIとMACDの併用による対策
・理由はRSIがボックス相場に強く、急激なトレンド発生時に弱いのに対して、MACDはトレンド発生時の分析に優れ、ボックス相場では有効度が下がる指標だから。
・また、まれにオシレーター系のRSIとトレンド系のMACDの両方でほぼ同時に同じシグナルを出す場合があるが、その場合的中率は上がると判断してもよい。
・明確なシグナルが出現していないときは無理にトレードしない。休むも相場。
5. ストキャスティックス
①ストキャスティックスの定義
・ストキャスティックスはRSIと同じくオシレーター系テクニカル指標で、買われすぎ、売られすぎを判断する指標。ストキャスと略して呼ばれることもある。
・ファストストキャスティックス = %K と %D
相場の動きに敏感に反応し、売買シグナルが頻繁に出るがダマシも多い。
・スローストキャスティックス = Slow%K と Slow%D
これらはファストストキャスティックスの移動平均線を利用するため、その分、売買シグナル出現頻度は減る。ダマシも減る。
②ストキャスティックスの利用方法
・スローストキャスティックスの2本のラインが80%以上であれば買われすぎ、20%以下なら売られすぎと判断。
・Slow%K が Slow%D のラインを下から上抜けるゴールデンクロス時は買いポイント、Slow%K が Slow%D のラインを上から下抜けるデッドクロス時は売りポイント。
6. その他のテクニカル指標

Part 10 フィボナッチ
1. フィボナッチ・リトレースメント活用法
・株価の戻りの目安の判断にしたり、価格帯の中での下値支持線や上値抵抗線として利用する。
・利用するパラメータは23.6%、38.2%、50%、61.8%、補足的に76.4%。

・使い方具体例
終点を0%として、意識する戻りのメドを23.6%、38.2%、50%、61.8%ラインに置き、最後に全戻しである100%ラインを意識する。
サポートよろしくお願いします。サポートしていただいた分は書籍の購入などクリエイターとしての活動費に使い、有益な情報発信につなげていきたいと考えています。
